死亡事故で弁護士への相談は必要?メリット・費用・選び方を専門家が徹底解説
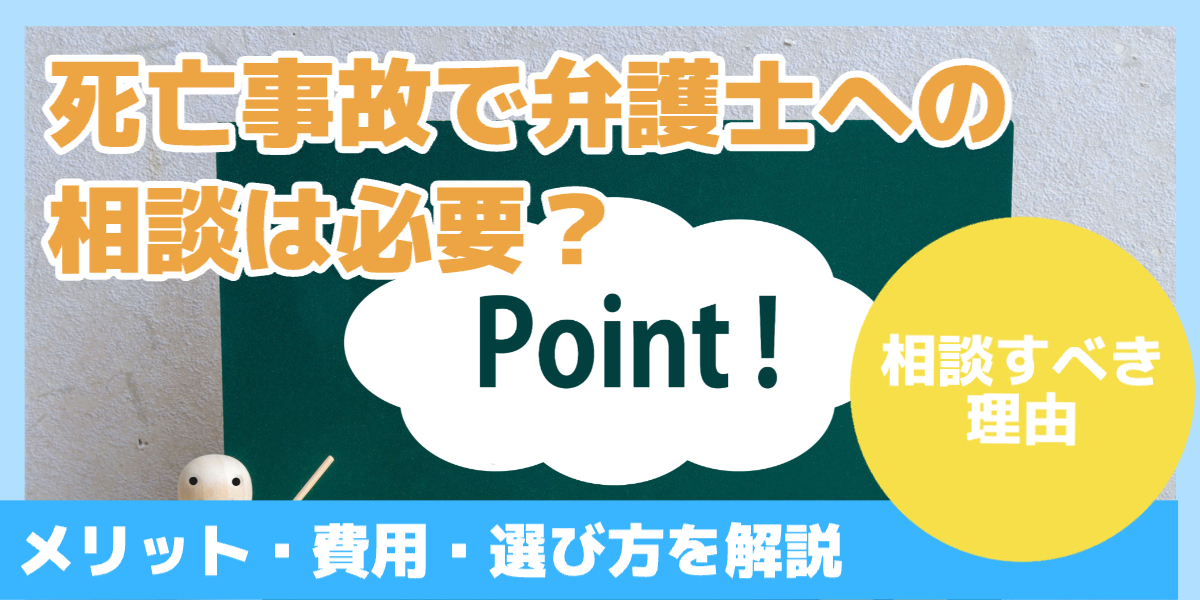
「突然の事故で家族を失い、何から手をつけていいかわからない…」
「保険会社から賠償金の提示があったけれど、この金額が妥当なのか判断できない…」
かけがえのないご家族を不慮の事故で亡くされ、今は悲しみと混乱の中にいらっしゃることと存じます。このような状況で、複雑な法的手続きや加害者側との交渉に直面することは、精神的に大きな負担になるはずです。
本記事は、故人の尊厳と残されたご家族の未来を守るために、弁護士に相談すべき理由や費用の仕組み、選び方まで徹底的に解説します。
交通死亡事故の手続きや賠償問題でお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にぜひ一度ご相談ください。
ご遺族の心に寄り添い、数多くの事案を解決に導いてきた経験から、進むべき道を具体的に示します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずは気軽に相談してみてください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
死亡事故の被害者になった際に弁護士に相談すべき理由
交通死亡事故において、弁護士への相談は単なる選択肢の一つではありません。ご遺族が正当な権利を守り、故人の無念を晴らすために、極めて重要かつ戦略的な一手です。
ここでは、なぜ弁護士の介入が不可欠なのか、その5つの本質的な理由を解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
賠償金が「弁護士基準」で計算され大幅に増額する可能性が高い
交通事故による損害賠償金、特に慰謝料の算出には、主に以下の3つの異なる基準が存在します。これらの基準は、それぞれ異なる目的と算定方法を持ち、結果として賠償額に大きな差が生じることがあります。
| 基準 | 特徴 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、法律によって加入が義務付けられている保険です。 交通事故被害者の最低限の救済を目的としています。 そのため、自賠責基準で算定される慰謝料額は、他の基準に比べると低額になりやすいです。 |
| 任意保険基準 | 任意保険会社が独自に定めている算定基準です。 各保険会社によって基準は異なりますが、一般的には自賠責基準よりは高額です。 ただ、後述する弁護士基準よりは低額に設定されています。 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 「弁護士基準」は、過去の交通事故に関する裁判例の積み重ねによって形成された基準です。 裁判所が実際に判決を下す際に用いられる基準であるため、「裁判基準」とも呼ばれます。 |
弁護士が交通事故の示談交渉に介入するメリットは、「弁護士基準」を適用して交渉を進められる点です。
弁護士が交渉することで、保険会社は弁護士基準を無視して示談を進めることが難しくなり、結果として賠償額の大幅な増額が期待できます。
特に死亡事故における死亡慰謝料や、後遺障害が残った場合の慰謝料、逸失利益などでは、弁護士が介入することで賠償金が2倍、3倍に増額するケースも決して珍しくありません。
これは、弁護士が法的な専門知識と過去の判例に基づき、適正な賠償額を主張し、交渉を行うためです。
専門的な知識や交渉力により、保険会社の提示額を鵜呑みにし、本来受け取れるはずの適正な賠償額が得られなくなるリスクを防げるでしょう。
関連記事:【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説
加害者・保険会社との複雑な交渉を一任できる
弁護士に依頼すると、加害者・保険会社との複雑な交渉を一任できる点も魅力です。
ご家族を失った悲しみの中で、加害者本人や、交渉のプロである保険会社の担当者と直接対峙することは、想像を絶する精神的負担を伴います。弁護士は、法律の専門家であると同時に、ご遺族を守る「盾」としての役割を果たします。
依頼を受けた瞬間から、弁護士はご遺族の代理人としての連絡窓口となり、煩雑な手続きや厳しい交渉をすべて引き受けてもらうことが可能です。
これにより、ご遺族は保険会社からの直接の連絡や、自身で交渉をしなければならない負担から解放され、心理的な安全を確保できるようになるでしょう。
関連記事:交通事故で相手の保険会社の対応が悪いときの対処法と弁護士に相談するメリット
精神的な負担が軽減されて故人を偲ぶ時間に専念できる
弁護士に依頼すると、精神的な負担が軽減されて故人を偲ぶ時間に専念できる点もメリットです。
死亡事故後の手続きは、賠償交渉だけではありません。葬儀の手配や相続手続きなど、やるべきことは数多く存在します。また、加害者が起訴されたら、刑事裁判の対応が必要となる場合もあります。
これら全ての手続きが終わるには、1年以上の期間を要することも珍しくありません。
弁護士に法的手続きを委任することで、ご遺族はこれらの付随的な負担から解放されます。
法的な問題は専門家に任せ、ご自身の心のケアや、残されたご家族との時間に専念することが可能です。
遺族に不利な「過失割合」を覆して適正な割合を主張できる
死亡事故では、被害者本人が事故状況を証言できないため、加害者の一方的な主張が通る可能性がある問題を抱えています。
結果的に、保険会社から提示される「過失割合」が、故人に不当に高く設定されているケースは珍しくありません。過失割合が1割でも不利になれば、賠償金総額は何百万円、時には何千万円も減額されてしまいます。
弁護士に依頼すると、刑事事件の捜査記録である「実況見分調書」などを取り寄せて徹底的に分析してくれます。また、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像といった客観的証拠を収集できることがあります。
その後、事故現場の状況を科学的・法的に再構築し、故人に過失がなかったこと、あるいは極めて小さかったことを論理的に主張してくれます。適正な割合を主張するためにも、弁護士は大切な存在です。
関連記事:交通事故の過失割合納得いかない!適正化を弁護士に任せるべき理由
刑事裁判で想いを伝える「被害者参加制度」をサポートしてもらえる
ご遺族が弁護士に依頼するメリットの一つに、「被害者参加制度」をサポートしてくれる点も挙げられます。
被害者参加制度とは、ご遺族が刑事裁判に出席し、被告人(加害者)に直接質問したり、裁判官に心情を述べたりすることを可能にする制度のことです。
弁護士は、申し立て手続きを代行するだけでなく、被害者の心情や被害状況を正確に反映した意見陳述書の作成を支援してくれます。
これにより、裁判官や裁判員に、事件の重大性やご遺族の苦しみを深く理解してもらうことが可能になるでしょう。
また、公判廷での質問事項の準備においても、弁護士の専門知識は不可欠です。
加害者に適切に質問することで、正確な事実関係を確認できます。また、加害者の反省の度合いや再発防止への意識を問うことで、裁判所の心証形成に大きな影響を与えることも可能です。
交通死亡事故の手続きや賠償問題でお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にぜひ一度ご相談ください。
ご遺族の心に寄り添い、数多くの事案を解決に導いてきた経験から、進むべき道を具体的に示します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずは気軽に相談してみてください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
弁護士への依頼で増額が期待できる賠償金の内訳
交通事故で大切なご家族を失った悲しみは、決して金銭で癒されるものではありません。その喪失感は計り知れず、いかなる賠償金も故人の代わりにはなり得ないでしょう。
しかし、加害者が引き起こした結果に対して法的に正当な償いを求めることは、残されたご遺族の当然の権利です。
そして、その償いを適切な形で受け取ることは、今後の生活の経済的基盤を再構築し、一つの区切りをつけて前に進むために重要なプロセスといえます。
ここでは、弁護士に依頼することで増額が見込める具体的な賠償金の内訳を解説します。
- 死亡慰謝料(故人本人と遺族の精神的苦痛に対する補償)
- 死亡逸失利益(故人が生きていれば得られたはずの収入)
- 葬儀関係費用(葬儀代・墓石建立費など)
- 治療費・入通院慰謝料(事故発生から死亡までの期間分)
死亡慰謝料(故人本人と遺族の精神的苦痛に対する補償)
死亡慰謝料は、事故によって命を奪われた故人本人の精神的苦痛と、近しいご家族(父母、配偶者、子)が受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。
金額は、故人が家庭内でどのような役割を担っていたか(一家の支柱、母親・配偶者など)によって大きく変動します。
前述しましたが、この慰謝料の算定には以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判基準)
中でも、弁護士基準は最も高額になる基準です。保険会社は自社の基準で低く提示してきますが、弁護士であれば裁判例に基づいた高額な基準で交渉できます。
さらに、ひき逃げや飲酒運転、著しく悪質な運転態度など、加害者側に重い過失がある場合には、これらの基準額に上乗せした慰謝料を請求することも可能です。
関連記事:交通事故で死亡した場合の慰謝料は? 子どもや高齢者の死亡事故とその慰謝料相場について
死亡逸失利益(故人が生きていれば得られたはずの収入)
死亡逸失利益は、もし事故がなければ故人が生涯にわたって得られたであろう収入の補償です。賠償項目の中で最も高額になることが多い要素といえます。
計算式は、以下のとおりです。
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数
基礎収入額は、給与所得者の場合は事故前年の年収が基準となります。専業主婦(主夫)の場合は性別別労働者の平均賃金、学生や子供の場合は学歴に応じた平均賃金を用いるなど、立場によって算定方法が異なります。
生活費控除率は、故人が生きていればかかったであろう生活費を差し引くための割合のことです。性別・扶養家族の有無などにより30〜50%の間で変動します。
関連記事:後遺障害の逸失利益とは?等級別の相場や計算方法を弁護士が解説
葬儀関係費用(葬儀代・墓石建立費など)
通夜・告別式・火葬・墓石の建立などにかかった費用も賠償の対象となります。
自賠責保険では上限が100万円と定められていますが、弁護士基準(裁判基準)では原則として150万円が上限の目安とされています。
香典返しや過度に高額な墓石費用などは対象外となる場合がありますが、社会通念上、妥当な範囲の実費は請求可能です。
故人の社会的地位などにより葬儀が大規模になったといった特段の事情がある場合には、150万円を超える費用が認められる可能性もあります。
治療費・入通院慰謝料(事故発生から死亡までの期間分)
交通事故の発生から入通院治療を受けていた場合、その治療にかかった費用と、その期間の精神的苦痛に対する慰謝料も請求できます。
ご遺族が死亡慰謝料に意識を向けるあまり、この死亡までの期間の損害を見過ごしてしまうことは珍しくありません。
弁護士であれば、故人が亡くなる直前まで受けた苦痛に対する補償も見逃すことなく請求してくれる可能性が高まります。
慰謝料の算定基準については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:【交通事故損害賠償額算定基準】交通事故の損害賠償額が変わる3つの算定基準を詳しく解説
関連記事:交通事故の損害賠償額の決め方とは?交通事故の慰謝料の計算方法を弁護士が解説
死亡事故における弁護士への相談は、早期に行うことが重要
交通死亡事故が発生した直後は、ご遺族は深い悲しみと混乱の中にあり、法的な対応まで考えが及ばないのが当然です。しかし、事故直後の時期こそが、将来の正当な賠償獲得のために重要な期間となります。
その理由の一つが、証拠の保全です。事故の客観的な状況を示すドライブレコーダーや現場周辺の防犯カメラの映像は、時間の経過とともに上書きされて失われる可能性があります。
弁護士に早期に依頼することで重要な証拠を迅速に確保し、散逸を防ぐことが大切です。
また、早い段階で弁護士が介入することで、ご遺族が不利な発言をしたり、不当に低い金額で示談に応じたりするリスクを未然に防げます。
加えて、加害者の刑事手続きが進行する中で、被害者参加制度の活用など民事の賠償交渉を有利に進めるための戦略的な手を打つことも可能です。
初動の速さが最終的な結果を大きく左右することを、ぜひ心に留めておいてください。
交通死亡事故の手続きや賠償問題でお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にぜひ一度ご相談ください。
ご遺族の心に寄り添い、数多くの事案を解決に導いてきた経験から、進むべき道を具体的に示します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずは気軽に相談してみてください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
弁護士に相談するタイミングについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:交通事故問題を弁護士に相談するタイミングはいつがいいか?
関連記事:後遺障害の悩みは弁護士に相談・依頼すべき?メリットや費用・タイミングを徹底解説
死亡事故の損害賠償を弁護士に依頼する場合の費用相場
弁護士に依頼するにあたり、多くの方が懸念されるのが費用面でしょう。特に、ご家族の収入の柱を失ったご遺族にとっては切実な問題です。
しかし、費用の仕組みを正しく理解し、後述する費用を抑える方法を活用すれば、過度に心配する必要はありません。
ここでは、弁護士費用の内訳と相場について解説します。
弁護士費用の内訳
弁護士費用は、主に以下の4つの項目で構成されています。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
- その他
それぞれ具体的に解説します。
相談料
弁護士に法律相談をする際に支払う費用です。最近では、交通事故の初回相談を無料としている法律事務所もあります。
着手金
弁護士に正式に事件を依頼する(委任契約を結ぶ)際に、最初に支払う費用です。事件の結果にかかわらず返還されないのが原則ですが、この着手金も無料(完全成功報酬制)としている事務所も一定数存在します。
報酬金
事件が解決した際に、その成功の度合いに応じて支払う費用です。一般的には、「獲得した賠償金の〇%」といった形で計算される成功報酬制が採用されていることが多いですが、最低成功報酬額を定めている事もあります。
その他
上記3つの他にも、日当や実費などが別でかかる場合もあります。
日当とは、弁護士が裁判所への出廷などで遠方に出張した場合に発生する費用です。半日や1日単位で金額が定められています。
一方で実費とは、事件処理のために実際にかかった費用のことです。収入印紙代・郵便切手代・交通費・カルテなどの取り寄せ費用などが含まれます。
弁護士費用の相場
2004年に弁護士報酬が自由化されたため、現在では各法律事務所が独自に料金体系を定めています。
しかし、その妥当性を判断する上で、今なお重要な指標となるのが「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準(旧基準)」です。今でも旧基準を参考に、料金を設定していることもあります。
以下に、旧基準に基づいた民事訴訟事件の着手金と報酬金を計算するとどうなるか記載しました。あくまで目安のため、事案に応じて金額は変動します。
例:4000万円で訴訟提起して、実際に3000万円の賠償が得られた場合
- 着手金:4000万円×3%+69万円=189万円(税別)
- 報酬金:3000万円×10%+18万円=318万円(税別)
出典:交通事故の弁護士費用はいくらかかる?弁護士費用特約や費用倒れしないコツも紹介【弁護士監修】
交通死亡事故の手続きや賠償問題でお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にぜひ一度ご相談ください。
ご遺族の心に寄り添い、数多くの事案を解決に導いてきた経験から、進むべき道を具体的に示します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずは気軽に相談してみてください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通死亡事故の際の弁護士の選び方
弁護士に依頼するといっても、誰に頼んでも同じ結果になるわけではありません。特に交通死亡事故は、医学的知見や複雑な損害計算、刑事手続きとの連携など、極めて高度な専門性が要求される分野です。
適切な弁護士を選ぶことが、結果を大きく左右します。ここでは、後悔しないための「交通死亡事故の際の弁護士」を見極める4つのチェックポイントを解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
関連記事:交通事故に強い弁護士の選び方!後悔しないポイントや相談の流れを現役弁護士が解説
交通死亡事故の解決実績は豊富かをチェックする
弁護士を選ぶ上で重要な基準は、その分野における実績です。単に交通事故を扱っているだけでなく、交通死亡事故の解決実績が豊富かを確認する必要があります。
法律事務所のウェブサイトを見る際には、相談件数だけでなく、具体的な「解決事例」が掲載されているかを確認しましょう。
医学的知識や専門家との連携はあるかを調べる
弁護士を選ぶ際は、医学的知識や専門家との連携はあるかを調べることも大切です。
死亡事故では、事故と死亡との因果関係が争点になることがあります。特に、事故からしばらく経ってからお亡くなりになった場合、その証明には高度な医学的知識が不可欠です。
弁護士自身が一定の医学的知識を有しているか、必要に応じて協力してくれる医師や専門家との連携体制が整っているかを確認しましょう。
遺族の気持ちに親身に寄り添ってくれるかを確認する
技術的な専門性と同様に、弁護士の人間性も大切です。
ご遺族は深い悲しみの中にあり、精神的に非常にデリケートな状態にあります。高圧的に接するような弁護士を選ぶと、かえって心の傷を深めてしまうことになりかねません。
初回の法律相談は、弁護士の専門性を見極める場であると同時に、人としての相性を確認する機会でもあります。
「話を親身になって聞いてくれるか」「心痛に寄り添う姿勢があるか」など、信頼関係を築ける相手かどうかを感じ取ることが重要です。
料金体系が明確で分かりやすく説明してくれるかを確かめる
弁護士を選ぶ際は、料金体系が明確で分かりやすく説明してくれるかを確かめることも重要です。
信頼できる弁護士は、費用についても誠実です。最初の相談の段階で、どのような費用が、いつどのくらい発生するのかを明確に説明してくれます。
成功報酬の計算方法や、実費の内訳など、少しでも疑問に思うことがあれば遠慮なく質問してみましょう。
もし、費用に関する説明が曖昧であったり、質問に対してはぐらかすような態度が見られたりした場合は注意が必要です。後々、予期せぬ請求をされてトラブルになる可能性があります。
安心して依頼するためにも、契約書にサインする前に費用に関するすべての点をクリアにしておくことが大切です。
交通死亡事故で弁護士に相談して賠償金を受け取るまでの流れ
突然の悲劇に見舞われ、何から手をつけてよいか分からないご遺族のために、弁護士に相談してから最終的に賠償金を受け取るまでの標準的な流れを、6つのステップに分けて具体的に解説します。
ステップ1:無料法律相談の予約・実施
まずは、法律事務所を探し、無料法律相談を予約することから始めましょう。
相談当日は、弁護士が事故の状況やご遺族のお話を詳しくヒアリングします。
この時点で、交通事故証明書や保険会社からの書類、故人の収入がわかる資料があれば、より具体的なアドバイスを受けることが可能です。
ステップ2:契約・委任状の作成
法律相談の内容に納得して弁護士に依頼することを決めたら、委任契約書を作成し、契約を締結します。
契約が成立すると、弁護士は直ちに加害者側の保険会社に対して「受任通知」という書面を送付します。
この通知が相手方に届いた時点から、保険会社からの連絡はすべて弁護士が窓口となり、ご遺族に直接連絡が来ることはありません。
ステップ3:証拠収集・損害額の調査と計算
次に弁護士は、正式な代理人として、賠償請求に必要な証拠の収集と調査を開始します。
具体的には、警察が作成した事故の捜査記録(実況見分調書など)や、故人が治療を受けた病院のカルテ、診療報酬明細書などを取り寄せます。
その後、客観的な証拠を基に、死亡慰謝料や逸失利益、葬儀費用など、請求できる損害項目を、「弁護士基準」で精密に計算し直します。
ステップ4:加害者側の保険会社との示談交渉
損害額の計算が完了すると、弁護士はそれを基に損害賠償請求書を作成し、加害者側の保険会社に送付して、本格的な示談交渉を開始します。
法的な根拠と過去の裁判例を示しながら、粘り強く増額を求めて交渉を続けるのが特徴です。
多くのケースでは、この交渉段階で双方が合意に至り、示談が成立します。
ステップ5:【交渉不成立の場合】民事裁判(訴訟)への移行
示談交渉の結果、保険会社が提示する条件が受け入れられない可能性もゼロではありません。
このような交渉決裂のケースでは、弁護士はご遺族と協議の上、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。
裁判では、法廷でお互いの主張と証拠を提出し合います。裁判の途中で裁判官から話し合いで解決できないか模索されることもあり、訴訟の途中でも話し合いで解決をすることもあります。
話し合いで解決ができなければ、最終的には裁判官が判決を下します。
ステップ6:賠償金の受け取り・解決
示談交渉で賠償金の金額が確定すると、その内容を記した「示談書」または「免責証書」を作成します。
裁判の話し合いであれば、「和解調書」を作成し、判決の場合には、裁判所から「判決文」が届きます。
示談交渉や裁判の話し合いで解決した場合、定められた期日までに指定口座に賠償金が一括で振り込まれます。
判決の場合は、判決が確定してから、同様に指定された口座に賠償金が一括で振り込まれることが多いでしょう。
交通死亡事故の弁護士に関するよくあるご質問(FAQ)
交通死亡事故に関して弁護士への相談を検討される際、ご遺族から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
自分の保険に弁護士費用特約がついているかを確認する方法は?
自分の保険に弁護士費用特約がついているかを確認したいなら、ご自身やご家族が加入している自動車保険の「保険証券」を確認しましょう。
特約が付帯している場合、「弁護士費用補償特約」や「自動車弁護士費用等補償特約」といった記載があります。
保険証券が見当たらない場合や、記載内容がよく分からない場合は、契約している保険会社に直接電話で問い合わせることも効果的です。
自動車保険だけでなく火災保険などに付帯しているケースもあるため、念のため確認してみるとよいでしょう。
相手方が任意保険に入っていない(無保険の)場合の対処法は?
相手方が任意保険に未加入の場合でも、賠償請求を諦める必要はありません。
まず、加害車両が加入している自賠責保険に対して、法律で定められた上限額(死亡事故の場合は最大3,000万円)まで賠償金を請求します。
ひき逃げで加害者が不明である場合や、加害者が自賠責保険に加入していない場合、自賠責保険での保障を受けられません。この場合でも「政府保障事業」による損害のてん補を受けられます。
ご自身やご家族の自動車保険に「無保険車傷害保険」や「人身傷害補償保険」が付帯していれば、それを利用して補償を受けることも可能です。
これらの手続きは複雑なため、弁護士に依頼し、どの制度からどのような順番で請求するのがよいか戦略を立ててもらうことが大切です。
出典:日本損害保険協会|自賠責保険
出典:国税庁|政府保障事業
刑事裁判が終わってから相談しても間に合う?
刑事裁判が終わってから弁護士に相談しても間に合います。
交通事故による人の生命・身体への損害に関する損害賠償請求権の時効は、「損害及び加害者を知った時から5年」です(民法第724条の2)。刑事裁判が終わった時点で5年の期間内であれば、弁護士に相談して民事の賠償請求手続きを開始することは可能です。
ただし、弁護士が刑事裁判の段階から関与することで、民事の賠償交渉を有利に進めるための証拠を確保できるメリットがあります。時効の観点からは間に合いますが、最善の結果を得るためには、できる限り早い段階で相談することが大切です。
出典:e-Gov法令検索|民法
地方在住でも都市部の弁護士に依頼できる?
地方在住でも都市部の弁護士に依頼できます。
近年は電話・メール・ウェブ会議システムなどが普及しており、物理的な距離は弁護活動の障壁にはなりません。弁護士選びで重要なのは事務所の場所ではなく、交通死亡事故における専門性と実績です。
地方の弁護士よりも、都市部に集中している専門性の高い弁護士に依頼する方が、より良い結果を得られる可能性は十分にあります。まずは地域にとらわれず、専門家を探す視点を持つことが大切です。
まとめ|死亡事故が発生したら、適切な賠償と心の平穏のために弁護士に相談しよう
本記事では、交通死亡事故に直面されたご遺族が弁護士に相談すべき理由と具体的な方法を多角的に解説しました。
弁護士が介入し「弁護士基準」で交渉することで、保険会社の当初提示額より高い賠償金を得られます。また、加害者側との複雑で精神的負担の大きい交渉をすべて一任できるため、ご遺族は故人を偲ぶ時間に専念することが可能です。
突然の悲劇により家族を失い、何から手をつけていいかわからないと悩む人は少なくありません。故人の尊厳を守り、残されたご家族の未来を守るためにも、まずは専門家への相談という形で踏み出してみましょう。
交通死亡事故の手続きや賠償問題でお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にぜひ一度ご相談ください。
ご遺族の心に寄り添い、数多くの事案を解決に導いてきた経験から、進むべき道を具体的に示します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずは気軽に相談してみてください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応




