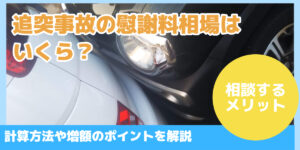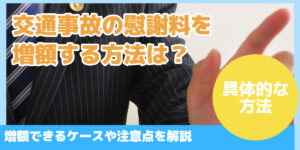交通事故で骨折した場合の慰謝料はいくら?相場や計算方法・手続き方法を弁護士が解説

「交通事故で骨折した場合、慰謝料はいくらもらえる?」
「保険会社から提示された金額が妥当かが分からない」
突然の事故で心身ともに大きな負担を強いられている中、将来への不安を感じる人はいるのではないでしょうか。
慰謝料は、適切な知識を身につけて戦略的に行動しなければ、適正な金額を受け取れない可能性があります。相場や手続きの方法などを理解しておくことが大切です。
この記事では、交通事故による骨折で請求できる慰謝料の種類や金額の相場を解説します。また、適正な金額を受け取るための具体的な計算方法と手続きの流れも解説します。
交通事故による骨折の慰謝料に不安を感じている人は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
取扱件数1,200件以上の経験と医学的知識までカバーした専門性により、適切なアドバイスを提供します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故で骨折したときにもらえる慰謝料の種類
交通事故で骨折という大きな怪我を負った場合、加害者側に対して請求できる慰謝料は、精神的苦痛を補償するタイミングによって2つの種類に分けられます。
自身の権利を正しく把握するためには、2つの慰謝料の概念を理解することが大切です。以下、それぞれ具体的に解説します。
入通院慰謝料
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故の発生日から治療を終える(完治または症状固定)までの期間に受けた精神的・肉体的苦痛に対して支払われる補償です。
たとえば、足を骨折して1か月入院し、その後3か月通院してリハビリを行った場合、痛みや治療の苦しさ、通院にかかる負担、入院生活による日常生活の制限などが慰謝料として評価されます。
骨折の痛みや手術・リハビリの辛さ、入院生活による自由の制限、通院にかかる時間や労力などを金銭的に評価した結果、これらが大きければ慰謝料額が高額になります。
ただ、このような事項を個別の事案で毎回すべて評価していくことは現実的ではないので、慰謝料の金額は一応の目安として、主に入院期間や通院期間の長さに応じて算定されるのが慣例となっていて、治療が長期にわたるほど高額になる傾向があります。
弁護士基準(裁判基準)では、骨折で通院3か月程度のケースでは70万円~80万円程度となることが一般的です。
※骨折などのない軽症の場合には通院3か月で50万円前後になります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、症状固定の診断を受けた後も、完治せずに後遺障害が残ってしまった場合に請求できる、入通院慰謝料とは別の補償です。
この慰謝料は、後遺障害とともに将来にわたって生きていかなければならないという精神的苦痛に対して支払われます。
後遺障害慰謝料は、残った後遺障害が自賠責保険の基準に基づく「後遺障害等級」として正式に認定されると請求が認められやすくなります。
なお、この後遺障害等級に認定されなくても、事実として後遺障害が残ったのであれば後遺障害慰謝料の支払いが認められる可能性はありますが、ハードルは高くなります。
等級は症状の重さに応じて第1級(最も重い)から第14級(最も軽い)までの14段階に分類されており、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料の目安の金額が決まります。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫慰謝料の金額は、自賠責保険の「後遺障害等級認定」に基づき、たとえば14級では約32万円(自賠責基準)、1級では最大で2,800万円以上(裁判基準)となる場合もあります。
後遺障害等級認定については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:後遺障害等級認定とは?手続きの流れ・適切な等級獲得のポイントを弁護士が解説
交通事故で骨折した場合の慰謝料はいくら?
骨折による慰謝料の金額は、事故の状況や被害者のケガの程度によって大きく異なります。慰謝料は、民法第709条に基づく「不法行為による損害賠償」の一部として請求されるもので、被害者の精神的苦痛に対する金銭的補償として位置づけられています。
交通事故の慰謝料額は、1つの決まった金額が設定されているわけではありません。慰謝料を算出するための「基準」が3つ存在し、どの基準を用いるかによって、最終的に受け取れる金額が数倍も変わることがあります。
この構造を知らないまま保険会社と交渉を進めてしまうと、本来得られるはずだった正当な補償を受け取れない可能性があるため注意が必要です。
関連記事:交通事故の慰謝料はどうやって計算する?弁護士基準の相場と通院期間ごとの早見表【弁護士監修】
慰謝料を計算する3つの基準
慰謝料の計算基準には、以下の3つがあります。
それぞれの基準について、詳しく解説します。
自賠責基準
自賠責基準は、自動車の運転者に加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償保障法第5条)で用いられる計算基準です。
交通事故被害者に対して、法律で定められた最低限の補償を提供することを目的としているため、3つの基準の中では最も金額が低く設定されています。
入通院慰謝料は、原則として1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故)を基礎とし、「治療期間」と「実治療日数×2」のいずれか短い方の日数を乗じて計算されます。
また、治療費や休業損害などを含めた傷害部分の賠償額全体で120万円という上限が定められている点も特徴です。
出典:e-Gov 法令検索|自動車損害賠償保障法
出典:国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
任意保険基準
任意保険基準は、加害者が任意で加入している自動車保険会社が、内部的に独自で設定している支払基準です。この基準は保険会社ごとに異なり、公表されていません。
一般的には、自賠責基準とほぼ同じか多少上乗せした程度の金額であることが多いですが、次に説明する弁護士基準と比較すると大幅に低い水準です。
交通事故の被害者が、加害者側の保険会社から最初に提示される示談金は、多くの場合がこの任意保険基準に基づいて計算されています。
弁護士基準
弁護士基準(裁判基準とも呼ばれます)は、過去の裁判例の積み重ねによって形成された、法的に最も正当とされる賠償額の基準です。
弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いるもので、被害者が受けた精神的苦痛を適正に評価した金額といえます。
3つの基準の中で最も高額になるのが特徴で、自賠責基準や任意保険基準の2倍以上になることも珍しくありません。
しかし、弁護士基準を用いて保険会社と交渉し、適正な賠償額を獲得するためには、弁護士の介入が事実上不可欠となる点には注意が必要です。
交通事故慰謝料の算定基準については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:【交通事故損害賠償額算定基準】交通事故の損害賠償額が変わる3つの算定基準を詳しく解説
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料が、用いる基準によってどれほど違うのかを具体的に見てみましょう。
骨折の場合、弁護士基準では原則として「重傷扱い(別表I)」として計算されます。
| 通院期間 | 自賠責基準(※) | 弁護士基準(重傷の場合) |
|---|---|---|
| 1か月 | 129,000円 | 280,000円 |
| 3か月 | 387,000円 | 730,000円 |
| 6か月 | 774,000円 | 1,160,000円 |
表から明らかなように、通院6か月の場合、自賠責基準と弁護士基準では約39万円もの差が生じます。
入院が加われば、差はさらに大きくなります。保険会社の提示額を鵜呑みにせず、弁護士基準での請求を検討することがいかに重要かが分かるでしょう。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害が残った場合に請求できる後遺障害慰謝料も、自賠責基準か弁護士基準かによって金額が大きく異なります。後遺障害等級は第1級から第14級まであり、等級が重くなるほど慰謝料も高額になります。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準(円) | 弁護士基準(円) |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万 | 2,800万 |
| 第2級 | 998万 | 2,370万 |
| 第3級 | 861万 | 1,990万 |
| 第4級 | 737万 | 1,670万 |
| 第5級 | 618万 | 1,400万 |
| 第6級 | 512万 | 1,180万 |
| 第7級 | 419万 | 1,000万 |
| 第8級 | 331万 | 830万 |
| 第9級 | 249万 | 690万 |
| 第10級 | 190万 | 550万 |
| 第11級 | 136万 | 420万 |
| 第12級 | 94万 | 290万 |
| 第13級 | 57万 | 180万 |
| 第14級 | 32万 | 110万 |
出典:国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
例えば、比較的認定されやすい第14級でも、自賠責基準の32万円に対して弁護士基準では110万円と、約3.4倍の差があります。



適切な等級認定を受けること、そして弁護士基準で請求することの重要性は計り知れません。
関連記事:交通事故の損害賠償額の決め方とは?交通事故の慰謝料の計算方法を弁護士が解説
交通事故による骨折の慰謝料に不安を感じている人は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
取扱件数1,200件以上の経験と医学的知識までカバーした専門性により、適切なアドバイスを提供します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
骨折の部位ごとの後遺障害等級と慰謝料相場
交通事故による骨折で後遺障害が残った場合、その慰謝料額は、どの部位を骨折し、どのような後遺障害が残ったかによって認定される「後遺障害等級」によって大きく変動します。
ここでは、骨折部位ごとに認定されうる主な後遺障害等級と、弁護士基準による慰謝料相場を解説します。
頭蓋骨の骨折
頭蓋骨骨折は、脳に損傷が及ぶ可能性があります。高次脳機能障害や麻痺、嗅覚・味覚障害など、深刻な後遺障害につながることも珍しくありません。
頭蓋骨の骨折で認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第1級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2,800万円 |
| 第2級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 2,370万円 |
| 第5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服せないもの | 1,400万円 |
| 第9級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服せる労務が相当な程度に制限されるもの | 690万円 |
| 第12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 |
| 第14級 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 |
頸椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折
背骨(脊柱)の圧迫骨折は、背骨が変形してしまったり、可動域が制限されたり、痛みが残ったりする可能性があります。
背骨(脊柱)の圧迫骨折によって認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第6級 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 1,180万円 |
| 第8級 | 脊柱に運動障害を残すもの、または中程度の変形を残すもの | 830万円 |
| 第11級 | 脊柱に変形を残すもの | 420万円 |
鎖骨の骨折
鎖骨を骨折すると、骨が変形して癒合したり、肩関節の動きに制限が出たりすることがあります。
鎖骨の骨折によって認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第12級5号 | 鎖骨に著しい変形を残すもの | 290万円 |
| 第12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
肋骨の骨折
肋骨の骨折では、骨の変形や、治癒後も痛みが続く神経症状が後遺障害として認定される可能性があります。
肋骨の骨折によって認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第12級 | 肋骨に著しい変形を残すもの/局部に頑固な神経症状を残すもの | 290万円 |
| 第14級 | 局部に神経症状を残すもの | 110万円 |
上腕骨の骨折
肩から肘までの腕の骨である上腕骨の骨折は、肩関節や肘関節の機能障害、偽関節(骨が正常に癒合しない状態)などの後遺障害が考えられます。
上腕骨の骨折によって認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第8級 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの/一上肢に偽関節を残すもの | 830万円 |
| 第10級 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
| 第12級 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの/長管骨に変形を残すもの | 290万円 |
前腕の骨折
肘から手首までの2本の骨(橈骨・尺骨)の骨折は、手首や肘の動きに影響を与え、機能障害が残ることがあります。
前腕の骨折によって認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第8級 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 830万円 |
| 第10級 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
| 第12級 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
手指の骨折
手指の骨折は、指が動かなくなる機能障害や、指を失ってしまう欠損障害につながる可能性があります。
手指の骨折によって認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第7級 | 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの | 1,000万円 |
| 第9級 | 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指の用を廃したもの | 690万円 |
| 第12級 | 一手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの | 290万円 |
| 第14級 | 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの | 110万円 |
骨盤の骨折
体の中心を支える骨盤の骨折は、股関節の機能障害や、脚の長さに差が出てしまう短縮障害、神経症状などが残ることがあります。
骨盤の骨折で認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第10級 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの | 550万円 |
| 第12級 | 骨盤骨に著しい変形を残すもの/一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
| 第13級 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | 180万円 |
大腿骨の骨折
脚の付け根から膝までの太い骨である大腿骨の骨折は、股関節や膝関節の機能障害、脚の短縮障害などが後遺障害として考えられます。
大腿骨の骨折で認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第8級 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの/一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 830万円 |
| 第10級 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの/一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
| 第12級 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの/長管骨に変形を残すもの | 290万円 |
下腿の骨折
膝から足首までの骨(脛骨・腓骨)の骨折では、膝関節や足関節の機能障害、偽関節、脚の短縮などが後遺障害として残る可能性があります。
下腿の骨折で認定される主な後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の主な内容 | 弁護士基準による慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 第8級 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 830万円 |
| 第10級 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
| 第12級 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
なお、後遺障害が残った場合には、上記の慰謝料以外にも将来の収入を一定割合で喪失したものとして「逸失利益」も補償してもらえます。逸失利益について詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
関連記事:後遺障害の逸失利益とは?等級別の相場や計算方法を弁護士が解説
過去の判例から見る骨折事故の慰謝料金額の傾向
過去の地裁判決では、被害者の具体的な障害の程度や日常生活への影響、将来の労働能力の喪失などを踏まえ、慰謝料の金額が個別に評価される傾向が見られます。
以下、代表的な判例を見ていきましょう。
仙台地方裁判所 平成22年(ワ)第1382号
平成18年12月10日、51歳の女性の教諭の信号待ち後に発進した原告車に後続の被告車が追突した事故です。
被害者は、第3腰椎圧迫骨折が発生し、脊柱の変形が残ったことにより、後遺障害等級11級7号に認定されています。
この事故で怪我を負った女性が、運転者とその使用者に対して損害賠償を求めました。結果、後遺障害慰謝料として500万円、総額1959万5410円の賠償が確定しています。
秋田地方裁判所 平成21(ワ)354号事件
交通事故の被害者である夫婦が、加害者と車両の保有者に対して損害賠償を求めた判例です。
被害にあった夫(原告A)は、右足の骨折(脛骨・腓骨)や右肘と左膝の挫創など、治療に11か月を要する傷害を負いました。症状が固定した後も、右足の関節痛、額の中央と右腕に醜状障害が残り、併合12級の障害等級が認定されています。
妻(原告B)は、右腕の骨折や肺の挫傷など、治療に15か月以上を要する傷害を負いました。症状が固定した後も右足に神経症状が残り、14級9号の障害等級が認定されています。
裁判所は、被害者夫婦が負った傷害や後遺障害、休業損害、慰謝料などを詳細に検討し、加害者側に対して、夫(原告A)に後遺障害慰謝料として360万円、総額約2209万円、妻(原告B)に約661万円の支払いを命じました。
交通事故の骨折で慰謝料を請求する流れと必要な手続き
交通事故で骨折した場合の慰謝料請求は、事故発生から解決まで、決められた手順に沿って進みます。流れを理解しておくことは、適切な時期に適切な行動をとるために重要です。
ここでは、慰謝料を受け取るまでの具体的なステップを解説します。
事故が発生したら、まずは負傷者の救護と安全確保を行い、速やかに警察に連絡します。
警察への届出は法律上の義務(道路交通法第72条)であり、これを怠ると、保険金の請求に必要不可欠な「交通事故証明書」が発行されません。また、事故の状況がわかる実況見分調書も作成されません。
同時に、ご自身が加入している保険会社にも事故の発生を報告しましょう。加害者の氏名、連絡先、加入している保険会社などの情報も確認することが大切です。
もし、加害者に対して慰謝料の請求を考えているなら、弁護士にも相談・依頼しておきましょう。適切な慰謝料を受け取るために必要な手続きについて、具体的なアドバイスをもらえます。
交通事故による骨折の慰謝料に不安を感じている人は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
取扱件数1,200件以上の経験と医学的知識までカバーした専門性により、適切なアドバイスを提供します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
事故後は、痛みの程度にかかわらず、必ず医療機関を受診しましょう。事故直後は興奮していて痛みを感じにくくても、後から症状が現れることは少なくありません。
事故から受診までの期間が空いてしまうと、保険会社から事故と怪我との因果関係を疑われ、治療費や慰謝料の支払いを拒否される原因になり得ます。
医師の指示に従い、適切な治療を開始することが重要です。
治療を継続し、怪我が完全に治ることを「完治」といいます。一方、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと医師が判断した状態を「症状固定」と呼びます。
この症状固定の診断は、慰謝料請求の手続きにおいて重要な節目です。入通院慰謝料の計算期間がここで終了し、もし後遺障害が残っていれば、後遺障害に関する手続きへと移行します。
医師の判断のもと、適切に対処しましょう。
症状固定後も痛みや可動域制限などの症状が残ってしまった場合、その症状を「後遺障害」として正式に認定してもらうための手続きを行いましょう。
医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、必要な検査資料とともに損害保険料率算出機構に提出し、審査を受けます。
審査の結果、症状が何級の後遺障害に該当するかが決定され、後遺障害慰謝料の請求が可能になります。
治療が終了(完治または症状固定)し、後遺障害等級認定の結果が出た後、損害額の全体像が確定します。
このタイミングで、加害者側の保険会社との間で、慰謝料を含む損害賠償金全体の金額を決めるための「示談交渉」が本格的に始まります。
保険会社から示談金の提示がありますが、金額が適正かどうかを慎重に検討し、必要であれば増額を求めて交渉しましょう。
示談交渉で双方が合意に達すると、「示談書」が作成されます。示談書に署名・捺印をすると、法的な拘束力が生じ、原則として後から追加の請求は一切できなくなります。
そのため、内容を十分に確認し、納得した上で署名することが重要です。示談成立後、通常1週間から3週間程度で、指定した口座に慰謝料を含む示談金が振り込まれます。
交通事故による骨折で適切な慰謝料を受け取るために重要なこと
交通事故で骨折という大きな被害に遭った際、受け取る慰謝料の額は、事故後の行動によって大きく左右されます。
保険会社との交渉を有利に進め、正当な補償を得るためには、単に治療を受けるだけでなく、将来の請求を見据えた戦略的な対応が重要です。
ここでは、被害者の方が自身の権利を守るために、絶対に押さえておくべき4つの重要なポイントを解説します。
医師の診断書・検査結果をしっかり残す
検査結果は、慰謝料請求において強力な武器となる客観的な証拠です。
特に、後遺障害の認定を目指す場合、レントゲンやMRI、CTなどの画像検査の結果は、症状の存在を医学的に証明するための決定的な証拠となります。
医師に作成してもらう診断書や後遺障害診断書も同様に重要です。事故直後から症状固定に至るまでにどのような症状があり、どのような治療を受け、どのような経過を辿ったのかを示せます。
詳細かつ正確な医療記録を残しておくことで、後の交渉結果に大きく影響します。慎重に書類を作成してもらいましょう。
医師の指示通りに治療を継続する
治療の継続性は、怪我の重さや治療の必要性を証明する上で非常に重要です。
「痛みが軽い」「仕事が忙しい」などの理由で通院を中断したり、通院頻度が不規則になったりすると、保険会社から「治療の必要性は低い」と判断されかねません。
結果、治療費の支払いを早期に打ち切られたり、入通院慰謝料を減額されたりするリスクが高まります。
必ず医師の指示に従い、症状が改善するまで、あるいは症状固定の診断が下されるまで、粘り強く治療を継続してください。
慰謝料以外の損害賠償項目も漏れなく請求する
交通事故で請求できるのは、慰謝料だけではありません。
病院に支払った「治療費」や通院にかかった「交通費」、仕事を休んだことによる減収分を補う「休業損害」など多種多様な損害賠償項目が存在します。
場合によっては、後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する「逸失利益」も受けることが可能です。
これらの項目を一つひとつ正確に計算して漏れなく請求することが、最終的な受取額の増加につながります。
示談書にサインする前に必ず弁護士に相談する
保険会社から提示された示談書に一度署名をしてしまうと、示談は成立し、そこに記載された金額以上の請求は、原則として一切できなくなります。
後から「実は後遺障害が悪化した」「もっと高額な慰謝料がもらえるはずだった」と気づいても、請求できません。
保険会社が提示する金額は、法的に正当な弁護士基準よりも低いことがほとんどです。
示談書に署名する前に、金額が本当に妥当なものなのかを必ず確認しましょう。



適切な金額か判断できるか不安な人は、交通事故に詳しい弁護士に相談し、専門的な視点からチェックを受けることが大切です。
弁護士の選び方について気になる人は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:交通事故に強い弁護士の選び方!後悔しないポイントや相談の流れを現役弁護士が解説
交通事故による骨折の慰謝料に不安を感じている人は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
取扱件数1,200件以上の経験と医学的知識までカバーした専門性により、適切なアドバイスを提供します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の骨折による慰謝料の悩みを弁護士に相談するメリット
交通事故で骨折を負い、慰謝料請求に直面したとき、多くの方が「弁護士に相談すべきか」と悩まれます。
弁護士への相談は、被害者が正当な権利を実現するために有効な手段です。主に、以下のようなメリットがあります。
以下、それぞれ詳細に解説します。
弁護士基準の適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
弁護士に依頼するメリットの一つに、慰謝料の増額が期待できることがあげられます。
前述の通り、慰謝料の算定には3つの基準があり、弁護士が用いる「弁護士基準」が最も高額です。
保険会社は通常、自社の「任意保険基準」や最低限の「自賠責基準」で計算した低い金額を提示してきます。
弁護士が代理人として交渉することで、法的な根拠に基づき最も高い弁護士基準での支払いを強く主張することが可能です。
結果的に、当初の提示額から数十万円、場合によっては数百万円単位での増額が実現するケースも少なくありません。
保険会社とのやり取り・示談交渉を一任できる
怪我の治療を続けながら、保険会社の担当者と頻繁に連絡を取り、専門用語が飛び交う交渉を行うことは、被害者にとって大きな精神的・時間的負担となります。
時には、高圧的な態度で治療費の打ち切りを迫られるなど、ストレスを感じる場面もあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、こうした保険会社との全てのやり取りを窓口として一任できます。
被害者の方は煩わしい交渉から解放され、安心して治療に専念することが可能です。
後遺障害等級認定や休業損害の主張・証明をサポートしてくれる
後遺障害が残った場合、適切な「後遺障害等級」の認定を受けられるかどうかは、将来受け取る賠償額に絶大な影響を与えます。
弁護士であれば、適正な等級認定を得るために、医学的知見と法律的観点から的確なアドバイスを提供してくれます。どのような検査が必要か、後遺障害診断書にどのような記載をしてもらうべきかなどを詳細に教えてくれるでしょう。



また、休業損害や逸失利益といった複雑な計算が必要な損害項目についても、被害者の状況に合わせて正確に算出し、正当性を法的に主張・立証してくれます。
交通事故による骨折の慰謝料に不安を感じている人は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
取扱件数1,200件以上の経験と医学的知識までカバーした専門性により、適切なアドバイスを提供します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故による骨折の慰謝料に関するよくある質問(FAQ)
交通事故による骨折の慰謝料に関して、被害者の方から多く寄せられる質問にお答えします。
骨折で手術した場合、慰謝料は増える?
原則として、手術をしたという事実だけで、慰謝料の計算式が変わり、自動的に増額されるわけではありません。入通院慰謝料は、あくまで治療期間に基づいて算定されます。
ただし、以下のように被害者が受けた精神的苦痛が通常よりも著しく大きいと客観的に認められるケースでは、慰謝料が増額される可能性があります。
- 麻酔なしで行われた手術
- 命の危険が伴う大手術
- 同じ部位に何度も手術を繰り返した場合
自分のケースが上記に該当するかわからない場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
自転車事故の骨折でも慰謝料は請求できる?
自転車事故の骨折でも、慰謝料は請求可能です。加害者の過失によって損害を被った場合、被害者は交通手段に関係なく加害者に対して損害賠償(慰謝料を含む)を請求する権利があります。
慰謝料の計算方法や請求の考え方は、自動車事故の場合と基本的に同じです。
ただし、加害者が自転車の場合、自動車のように自賠責保険や任意保険に加入していないケースも珍しくありません。
賠償金の支払能力が問題となることがあるため、手続きが複雑になる場合は弁護士に相談しましょう。
加害者側の過失割合が大きい場合、慰謝料は増額される?
慰謝料は、加害者の過失が大きいからといって増額されるものではありません。
むしろ、自身の「過失割合」が大きい場合、受け取るべき損害賠償金全体(慰謝料を含む)が割合に応じて「減額」される仕組みになっています。
これを「過失相殺」と呼びます。
民法 第722条2項
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
加害者側の保険会社は、加害者を守るために被害者の過失割合を多く見積もる場合があります。適切な過失割合を提示するためにも、弁護士に相談することが大切です。
まとめ|交通事故の骨折による慰謝料は早めの対応と専門家への相談が重要
この記事では、交通事故で骨折した場合の慰謝料について、種類や計算基準、請求手続き、そして適正額を獲得するためのポイントを網羅的に解説しました。
慰謝料の計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。この中では、弁護士基準が最も高額で正当な基準です。
弁護士基準で慰謝料をもらうためには、弁護士の依頼が欠かせません。



交通事故による骨折で慰謝料の請求を考えている場合は、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。
交通事故による骨折の慰謝料に不安を感じている人は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
取扱件数1,200件以上の経験と医学的知識までカバーした専門性により、適切なアドバイスを提供します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応