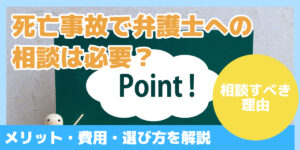交通事故の逸失利益とは?計算方法や認められない・減額される原因を解説

「逸失利益の計算方法がわからない」
「保険会社から提示された逸失利益が低くておかしい」
交通事故による逸失利益(いっしつりえき)は、被害者が受け取るべき正当な補償の一つです。しかし、その計算方法は複雑で、専門的な知識がなければ提示額が妥当か判断できません。
この記事では、交通事故の逸失利益の概要や、計算方法を詳しく解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫実際の示談金には、上記に加えて治療費や休業損害などが別途加算されます。
職業別の基礎収入の考え方や逸失利益が減額される原因と対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故の逸失利益で悩んでいる場合は、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が、適切な逸失利益の受け取りに向けてサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の「逸失利益」とは?基礎知識を解説
交通事故の損害賠償にはさまざまな項目があります。なかでも「逸失利益」は、被害者の将来に関わる重要な補償です。
慰謝料や休業損害との違いを理解し、基礎知識を正確に押さえておきましょう。
逸失利益とは|事故がなければ将来得られたはずの収入
逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られるはずの収入や利益のことを指します。
本来であれば、被害者は事故後も健康を維持し、働き続けることで一定の収入を得ていたはずです。しかし、交通事故によって後遺障害が残ったり、最悪の場合には命を落としたりすることで、将来得られるはずだった収入の一部または全部を失うことになります。
この「本来得られるはずだった将来の収入の喪失分」を金銭的に評価し、加害者側に損害賠償として請求するのが逸失利益です。
逸失利益は、被害者本人にとってだけでなく、その収入をもとに生活していた家族にとっても非常に重要な補償です。家計を支えていた方が事故により働けなくなった場合、その影響は配偶者や子どもの生活にも及びます。



「生活の基盤となる収入の損失」を補う意味でも、逸失利益の算定は損害賠償の中核的な要素といえるでしょう。
逸失利益と慰謝料の違い
逸失利益と慰謝料は、どちらも交通事故で請求できる損害賠償ですが、その性質が全く異なります。
逸失利益は、先述したとおり、将来失われる「財産的損害」に対する補償です。
一方、慰謝料は、交通事故によって被害者が受けた「精神的苦痛」に対する補償です。以下のように、金銭では直接的に計れない心の損害を金額で評価したものを指します。
- 身体の痛みや入通院による苦しみ
- 後遺障害による不自由な生活
- 家族を失った悲しみ など
このように、逸失利益は経済的損害、慰謝料は精神的損害という明確な違いがあり、両者は別々に計算されます。最終的な損害賠償額は、これらを合算して請求するのが一般的です。
| 項目 | 補償の対象 | 性質 |
|---|---|---|
| 逸失利益 | 将来失われる収入・利益 | 財産的損害 |
| 慰謝料 | 精神的な苦痛 | 精神的損害 |
逸失利益と休業損害の違い
逸失利益と休業損害は、どちらも「失われた収入」に対する補償である点は共通しています。
主な違いは、対象となる期間です。
休業損害は、事故発生から症状固定(治療を続けても改善が見込めない状態)までの間に、仕事を休んだことで失われた収入を補償します。
対して逸失利益は、症状固定後(後遺障害)または死亡後から、将来にわたって失われる収入を補償するものです。
| 項目 | 対象期間 | 性質 |
|---|---|---|
| 逸失利益 | 症状固定後 または 死亡後 | 将来の減収補償 |
| 休業損害 | 事故発生 ~ 症状固定まで | 事故後の現実の減収補償 |
逸失利益を請求できる2つのケース
逸失利益は、大きく以下の2つに大別されます。
以下、それぞれどのようなケースで請求できるかについて詳しく解説します。
後遺障害逸失利益
交通事故による怪我が完治せず、後遺障害が残った場合に請求できる逸失利益です。
後遺障害によって以前のように働けなくなると(労働能力の喪失)将来の収入が減少すると考えられるため、その減収分を補償として請求します。
後遺障害逸失利益を請求するには、自賠責保険の基準に基づく「後遺障害等級認定」を受けることが原則として必要です。



この等級によって、労働能力がどれだけ失われたかが判断されます。
後遺障害等級については、以下の記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。
関連記事:後遺障害等級とは?等級一覧表から申請方法、慰謝料の相場まで弁護士が徹底解説
死亡逸失利益
交通事故によって被害者が死亡した場合に、相続人が請求できる逸失利益です。
被害者は本来、仕事を続けて賃金や報酬を得て、その収入の一部を家族の生活費や教育費などに充てることができたはずです。しかし事故によりそれが不可能となったため、遺族の生活を支える部分が補償されます。
将来得られたはずの収入から、被害者自身が生前に消費したであろう生活費を控除した残額を遺族が受け取る仕組みです。
死亡逸失利益は、単なる経済的損失の補填にとどまらず、残された家族の将来の生活を支えるための重要な補償といえます。
逸失利益の計算で重要な3つの要素
逸失利益を計算するためには、大きく分けて3つの重要な要素を確定させる必要があります。
この3つの要素をどう設定するかによって受け取れる金額が大きく変わってくるため、適切な理解が必要です。
以下、それぞれ具体的に解説します。
基礎収入
基礎収入とは、逸失利益(事故によって将来得られなくなった収入)を計算する際の出発点となる金額です。
つまり、「事故がなければ得られていたはずの収入の水準」を示すもので、被害者の経済的損失を適正に評価する上で重要な要素の一つとなっています。
基礎収入は、原則として事故前年の現実の収入額(年収)を用いる点が特徴です。裁判所や保険会社が損害額を算定する際の方法や、考慮すべき資料は、職業や年齢、雇用形態によって異なります。
| 会社員 | 源泉徴収票に記載された税金控除前の総支給額 |
|---|---|
| 自営業者 | 確定申告書の申告所得額(実態と異なる場合は修正) |
| 主婦(主夫) | 賃金センサスの労働者・全年齢平均賃金 |
また、学生や若年者の場合は、将来就労して得られると見込まれる収入を「賃金センサス」などから推定します。若年者とは反対に、高齢者や退職後の被害者の場合は、就労継続の見込みや年金収入などを考慮して基礎収入を算出します。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力がどれだけ失われたかを割合で示したものです。この要素は、後遺障害逸失利益の計算でのみ使用されます。
原則として、認定された後遺障害等級に応じて、以下のような基準値が定められています。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1級 | 100 % |
| 2級 | 100 % |
| 3級 | 100 % |
| 4級 | 92 % |
| 5級 | 79 % |
| 6級 | 67 % |
| 7級 | 56 % |
| 8級 | 45 % |
| 9級 | 35 % |
| 10級 | 27 % |
| 11級 | 20 % |
| 12級 | 14 % |
| 13級 | 9 % |
| 14級 | 5 % |
ただし、上記はあくまで基準です。被害者の職業や受傷内容によっては、基準と異なる喪失率が認められる場合もあります。
労働能力喪失期間とライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、労働能力が失われた(収入が減少する)と想定される期間のことです。主に、以下のように考えられます。
- 後遺障害の場合:原則として症状固定日から67歳までの期間
- 死亡の場合:死亡日から67歳までの期間
ただし、将来の収入を「一時金」として一括で受け取るため、将来発生するはずの利息分(中間利息)を差し引く必要があります。
このとき、将来の収入を現在の価値に割り引くための係数として用いられるのが、「ライプニッツ係数」です。



労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて、現在の価値に割り引きます。これを中間利息控除といいます。
なお、2020年4月1日以降に発生した交通事故では、民法改正により法定利率が年3%に変更されました。そのため、ライプニッツ係数も旧法の年5%ではなく、年3%を前提とした新しい係数表が用いられています。
これによって、以前よりも高額の逸失利益が認められやすくなったことは交通事故被害者にとって良いニュースです。
しかし、ライプニッツ係数による中間利息控除の考え方は一般的の方にはわかりにくいことも事実です。正しい後遺障害逸失利益を計算するためには、弁護士に相談することが極めて大切です。
交通事故の逸失利益で悩んでいる場合は、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が、適切な逸失利益の受け取りに向けてサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
逸失利益の計算方法|後遺障害・死亡別に計算式を解説
逸失利益は、どのように計算されるのでしょうか。ここでは、弁護士基準(裁判基準)に基づいた逸失利益の計算式を解説します。
※弁護士基準(裁判基準)とは、過去の裁判例の蓄積をもとにした賠償金の算定基準です。自賠責基準・任意保険基準の2つに比べて、賠償金が最も高額になるのが特徴です。
後遺障害逸失利益の計算式
後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。
基礎収入(年収) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
たとえば、基礎収入500万円で後遺障害12級(喪失率14%)、喪失期間20年(ライプニッツ係数14.8775)の場合は、以下のとおりです。
500万円 × 14% × 14.8775 = 10414,250円
ただし、症状固定時に67歳が近い場合や、後遺障害の状況(むちうち等)によっては、喪失期間が制限されるケースもあります。
関連記事:後遺障害の逸失利益とは?等級別の相場や計算方法を弁護士が解説
死亡逸失利益の計算式
死亡逸失利益は、将来の収入から本人の「生活費」を差し引いて計算します。
計算式は、次のとおりです。
基礎収入(年収) × (1 – 生活費控除率) × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「生活費控除率」とは、被害者が生存していれば自身の生活のために必要だった費用の割合を意味します。被害者の家族構成や立場によって、以下のように定められています。
| 被害者の立場 | 生活費控除率の目安 |
|---|---|
| 一家の支柱(被扶養者1人) | 40% |
| 一家の支柱(被扶養者2人以上) | 30% |
| 女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30%(※40%程度の場合もある) |
| 男性(独身、幼児等含む) | 50% |
ここからわかるように、死亡逸失利益とは、単に「収入の何年分」といった単純な計算ではありません。被害者の収入状況・家庭状況・将来の就労可能性など多くの要素を総合的に考慮して算定されます。



自身のケースで正確な金額を知りたい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
関連記事:死亡事故で弁護士への相談は必要?メリット・費用・選び方を専門家が徹底解説
【職業・立場別】逸失利益の「基礎収入」の計算方法
逸失利益の計算で争点になりやすいのが「基礎収入」です。基礎収入は、職業や立場によって、収入の証明方法や計算の考え方が異なります。
適切な基礎収入で逸失利益を受け取るためにも、計算方法を知っておくことが重要です。
ここからは、基礎収入の計算方法を職業・立場別に紹介します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
会社員(給与所得者)の場合
会社員(公務員含む)の場合、事故前年の源泉徴収票に記載された「総支給額(税金や社会保険料が引かれる前の金額)」を基礎収入とします。
被害者が実際に労働の対価として得ていた収入水準を正確に反映する要素と考えられているためです。収入の証拠としては、源泉徴収票、課税証明書、給与明細書などが用いられます。
ただし、事故前年の収入が一時的な事情(育児休業・病気・会社の業績悪化など)で低下していた場合は、過去数年分の平均収入を採用することもあります。



若年労働者で将来の昇給が確実視できる場合、賃金センサス(全年齢平均)を基礎収入とすることもあります。
自営業者(個人事業主)・会社役員の場合
自営業者(個人事業主)の場合、逸失利益を算定する際の基礎収入は、原則として「事故前年の確定申告書に記載された申告所得額」が基準となります。確定申告書の控えや納税証明書などが、その裏付けとなる代表的な証拠資料です。
ただし、実際の事業者の中には節税目的で経費を多めに計上し、実際よりも所得を低く申告しているケースも少なくありません。
このように過少申告が疑われる場合には、帳簿・請求書・領収書・通帳記帳などの客観的資料を提出し、実際の収入水準を立証することが求められます。
会社役員の場合は、基本的に「役員報酬額」が基礎収入として採用されます。ただし、会社の利益配当や株式配当といった「労務の対価ではない収入」は、逸失利益の対象外とされる点に注意が必要です。
家事従事者(主夫・主婦など)の場合
主婦や主夫など、現実に金銭収入を得ていない家事従事者も逸失利益を請求することが可能です。
家事労働は金銭的に評価できるとされており、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の全年齢平均賃金を基礎収入とします。
パート収入がある場合は、原則としてパート収入額と上記の平均賃金額を比較し、高い方を基礎収入として計算します。
学生・未成年者・幼児の場合
学生や幼児など、事故当時に収入がない場合でも逸失利益は認められる場合があります。将来働いて収入を得る蓋然性が高いと判断されるためです。
この際の基礎収入には、「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」における全労働者・全年齢平均賃金(男女計)が用いられます。
一方で、進学が確実視されている大学生や高専生などの場合は、「大学卒業者の平均賃金」を基礎収入とするケースも少なくありません。将来的により高い収入を得ることが見込まれるためです。
とはいえ、若年者であれなんでも平均賃金が認められるわけではなく、当該収入を得られる蓋然性がある程度あることの立証は必要です。
就労可能年数(働ける期間)については、一般的に18歳(大学進学予定なら22歳)から67歳までの期間を基準とします。
無職者・失業者の場合
事故当時に無職・失業者であった場合、逸失利益の請求は難しくなる傾向があります。
ただし、以下の場合は請求が認められる可能性が高いです。
- 労働能力と労働意欲がある
- 就職先が内定していた
- 一時的な失業
具体的な就職活動をしていた証拠(面接履歴など)があれば、再就職で得られたであろう収入を基礎とします。また、就職先が決まっていた場合は、内定先の給与額を基礎収入として計算することが可能です。
けがの治療中など、一時的な失業であったと認められれば、前職の収入などを参考に基礎収入が算定されます。
ここでも、収入を得ることができる蓋然性の立証が重要です。
【モデルケース別】逸失利益の計算シミュレーション
具体的なモデルケースを用いて、逸失利益がどのように計算されるかシミュレーションします。どれくらいの金額になるかを判断する参考にしてみてください。
※計算はすべて2020年4月1日以降の事故(ライプニッツ係数年3%)を前提とします。
ケース1:会社員(40歳・年収600万円・後遺障害12級)の場合
40歳で年収が600万円だった会社員が交通事故に遭い、後遺障害12級と認定された場合、計算式は以下のとおりです。
【条件】
- 基礎収入: 600万円
- 後遺障害等級: 12級(労働能力喪失率 14%)
- 労働能力喪失期間: 67歳 – 40歳 = 27年間
- ライプニッツ係数(27年): 18.327
【計算式】
600万円 × 14% × 18.327 = 15,394,680円
このケースの逸失利益は、約1,539万円となります。
ケース2:家事従事者(35歳・女性・後遺障害14級)の場合
35歳の家事従事者が交通事故に遭い、後遺障害14級と認定された場合、逸失利益の金額は以下のとおりです。
【条件】
- 基礎収入: 399万6,500円(2023年女性・全年齢平均賃金)
- 後遺障害等級: 14級(労働能力喪失率 5%)
- 労働能力喪失期間: 67歳 – 35歳 = 32年間
- ライプニッツ係数(32年): 20.388
【計算式】
3,996,500 × 0.05 × 20.388 = 4,074,032円
このケースの逸失利益は、約407万円となります。
※ただし、14級(特にむちうち)の場合、喪失期間が5年程度に制限されることも多く、その場合の逸失利益は約96万円(407万4,032円 × 5% × 4.580)まで減額されます。
ケース3:学生(20歳・死亡事故)の場合
20歳の学生が交通事故で死亡した場合、逸失利益の金額は以下のように計算されます。
【条件】
- 基礎収入: 526万9,900円(仮に賃金センサス男女計・全年齢平均とする)
- 立場: 男性(独身)
- 生活費控除率: 50%
- 労働能力喪失期間: 67歳 – 20歳 = 47年間
- ライプニッツ係数(47年): 25.0247
【計算式】
5,269,900 ×(1-0.5)× 25.0247= 5,269,900 × 0.5 × 25.0247= 65,880,258円
このケースの逸失利益は、約6,588万円となります。
交通事故で逸失利益が認められない・減額される主な原因
保険会社から提示された逸失利益が「0円」であったり、想定より著しく低かったりする場合があります。
主な原因は、以下の5つです。
以下、それぞれ具体的に解説します。
原因1:後遺障害等級が認定されていない
後遺障害逸失利益は、原則として自賠責保険の後遺障害等級が認定されていることが前提です。「非該当」と判断された場合、保険会社は「労働能力の喪失はない」として逸失利益を0円と主張してきます。
しかし、実際には等級が非該当であっても、医学的な証拠や症状の一貫性が認められる場合には、裁判で逸失利益が認められるケースもあります。
神経症状や慢性的な痛みが残っており、労働能力に明確な支障があると医師の診断書や勤務記録などで立証できる場合などです。
後遺障害等級が認定されていないことは逸失利益請求の大きなハードルとなりますが、諦める前に異議申立てや裁判での主張立証を検討することが重要です。
関連記事:むちうち後遺症認定は難しい?後遺障害になるポイントは?等級認定を弁護士に依頼すべき理由
原因2:事故後も収入が減っていない
事故後、職場復帰して事故前と同じ収入を得ている場合、保険会社は「現実の減収がない」として逸失利益を否定することがあります。
しかし、収入が減っていないからといって、必ずしも労働能力が維持されているとは限りません。以下のようなケースでは、逸失利益が認められる場合もあります。
- 痛みや後遺症を抱えながらも無理をして働いている
- 同僚のサポートや配置転換により何とか業務を続けている
- 会社側の温情的な配慮によって給与が維持されている
このような場合は、収入が維持されている理由が「本人の特別な努力」や「職場の温情的な配慮」によるものであることを客観的に立証することが重要です。
また、事故によって昇進・昇給の機会が失われた場合や、将来的な転職やキャリア形成に支障が出た影響も、逸失利益の範囲に含まれる可能性があります。



「収入が減っていないから請求できない」と早合点せず、事故後の働き方や職場の実情を丁寧に整理して主張することが大切です。
弊所で実際に取り扱った案件の中にも、保険会社から減収がないことを指摘されながらも保険会社に逸失利益を認めさせた事例は多数あります。
原因3:労働能力喪失期間が短く計算されている
保険会社は、労働能力喪失期間を短く見積もることで逸失利益を減額しようとします。とくに注意が必要なのが、むちうち(14級9号、12級13号)の場合です。
外見上の変化が乏しく、完治・不完治の判断が曖昧になりやすいことから、「長期にわたる労働能力喪失はない」と判断される恐れがあります。



喪失期間が「5年〜10年程度」と短く主張されるケースも珍しくありません。
確かに、特殊事情のないむち打ち事例では労働能力喪失期間が制限されることも珍しくありません。
しかし、例えばスポーツ選手や運転職などの特殊なケースでは、事故後何年経っても慢性的な痛み・しびれなどが続き、仕事の効率が下がったり、職種変更を余儀なくされたりする場合もあります。
こうした実情を反映するためには、職業による特殊性、医師の診断書や通院記録、勤務成績・出勤状況などの客観的資料で立証することが重要です。
原因4:事故前からの病気や加齢変化が影響している
交通事故による後遺症の評価では、被害者が事故前から持っていた病気(既往症)や、年齢による身体の変化(加齢変性)が問題となることもあります。
保険会社はこれらの要素を理由に、賠償額を減らそうとすることも珍しくありません。このように、被害者側の身体的な素因を理由に損害賠償額を減らすことを「素因減額」と呼びます。
しかし、素因減額が常に適用されるわけではありません。もともと病気があったとしても、事故が引き金となって症状が顕在化した場合には、事故との因果関係が認められます。



以下の要素を客観的な資料で立証できれば、事故が主因であることを裏付けることが可能です。
- 事故前には症状がなかった、または軽度であったこと
- 事故後に症状が急激に悪化したこと
- 医師の診断書などで事故との因果関係が明示されていること
弁護士に相談すれば、過去の裁判例や医証を踏まえて、どの程度まで減額が妥当か、あるいは全く減額すべきでないかを的確に判断してもらえるでしょう。
原因5:被害者にも過失がある
被害者側にも事故発生の原因(過失)がある場合、その割合に応じて賠償金全体が減額されます。これを「過失相殺」と呼びます(民法第722条2項)。
過失相殺は、損害賠償全体に影響する重要な要素です。
たとえば、被害者の過失が2割の場合、逸失利益を含む損害賠償総額が2割減額されます。つまり、本来1000万円の賠償を受けられるはずだったとしても、過失相殺により実際の支払額は800万円となるわけです。
保険会社が提示する過失割合をそのまま受け入れるのではなく、過失割合が妥当かどうかを一度弁護士に精査してもらうことが重要です。
交通事故の過失割合について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:交通事故の過失割合を徹底解説|ケース別の相場と納得できない時の対処法
交通事故の逸失利益を請求するときに必要な証拠・書類
逸失利益を請求するには、被害者の「収入の実態」や「後遺障害の程度」を客観的に示す証拠が不可欠です。適切な書類をそろえることで、保険会社や裁判所に損害額の正当性を裏付けられます。
主な書類は以下のとおりです。
| 区分 | 書類の例 |
|---|---|
| 収入関係 | ・源泉徴収票 ・確定申告書 ・給与明細 ・課税証明書 |
| 医療関係 | ・診断書 ・後遺障害診断書 ・通院記録 |
| 勤務・就労関係 | ・勤務成績表 ・出勤簿 ・会社からの証明書 |
| 生活実態 | ・家族構成や扶養関係がわかる住民票・戸籍謄本 |
ただし、事故の状況や職業形態(自営業・会社員・主婦など)によって、必要となる資料や証明方法は異なります。
適切な証拠を漏れなく準備するためにも、早い段階で交通事故に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
交通事故の逸失利益で悩んでいる場合は、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が、適切な逸失利益の受け取りに向けてサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の逸失利益が「おかしい」「低い」と感じる場合の対処法
保険会社から提示された逸失利益の金額に納得できない場合、すぐには示談(合意)してはいけません。一度示談が成立すると、後になって覆すことは原則として難しくなります。
以下のステップを参考に、冷静に対処しましょう。
ステップ1:提示された金額の計算の根拠を確認する
まずは、保険会社の担当者に連絡を取り、提示された逸失利益の計算書(損害計算書)を必ず取り寄せましょう。ここに記載されている数字が、どのような根拠で算出されたかを確認することが重要です。
逸失利益の金額は、以下の3つの要素によって大きく変わります。
- 基礎収入はいくらで計算されているか
- 労働能力喪失率は何%か
- 労働能力喪失期間は何年で計算されているか
どれか一つでも過小に設定されていると、最終的な賠償額が大幅に低くなってしまうため、入念に確認が必要です。
ステップ2:損害計算書を弁護士・交通事故専門家にチェックしてもらう
損害計算書を入手したら、交通事故に精通した弁護士にチェックしてもらうことが重要です。
弁護士は、主に以下の3点を確認してくれます。
- 保険会社の計算が「任意保険基準」や「自賠責基準」で行われていないか
- 基礎収入の算定は妥当か
- 労働能力喪失期間は不当に短縮されていないか
弁護士であれば、保険会社の提示額が妥当か、増額の余地がどれくらいあるかを即座に判断することが可能です。不明点がある場合は、必ず弁護士に相談しましょう。
ステップ3:必要に応じて異議申立て・示談拒否・訴訟提起を検討する
弁護士に相談した結果、逸失利益の増額が見込まれる場合は、保険会社との交渉に移ります。
弁護士が、過去の裁判例や被害者の職業・年齢・後遺障害等級をもとに適正な賠償額を算定し、主張を組み立ててくれるでしょう。
後遺障害等級が低すぎる、または非該当とされたときは、「異議申立て」を行うことが可能です。異議申立てによって等級が上がれば、逸失利益も大きく変わる可能性があります。
適切な後遺障害等級の認定を受けた場合でも交渉がまとまらない場合は、交通事故紛争処理センターでのあっせん・和解の申立てや、裁判所への訴訟提起も視野に入れましょう。



弁護士が代理人として手続きを進めることで、主張に法的根拠が加わり、最終的に裁判基準での解決が期待できるでしょう。
交通事故の逸失利益に関するよくある質問
ここからは、逸失利益に関して、被害者の方から多く寄せられる質問に回答します。後のトラブルを防ぐためにも、ぜひ参考にしてみてください。
逸失利益の請求に時効はある?
逸失利益の請求には、時効があります。主な時効は、以下のとおりです。
- 後遺障害逸失利益:症状固定日の翌日から5年間
- 死亡逸失利益:死亡日の翌日から5年間
※加害者が不明な場合(ひき逃げ等)は、事故日の翌日から20年間です。ただ、途中で加害者が判明した場合は、判明日を起算日として5年の時効が適用されます。
時効を過ぎると請求権が消滅するため、早めに対応する必要があります。
出典:e-Gov法令検索|民法
逸失利益はいつからもらえる?
逸失利益は、原則として加害者側(保険会社)との示談が成立した後に、他の賠償金(慰謝料、治療費など)と一括で支払われます。
示談交渉は、後遺障害の場合は「症状固定後」、死亡の場合は「四十九日法要後」あたりから本格化します。交渉がまとまれば、示談成立から約2週間程度で振り込まれるのが一般的です。
年金受給者でも逸失利益は請求できる?
年金受給者の場合、年金の種類によって判断が分かれます。
判例は,老齢・退職年金、障害年金など、保険料負担のある家族のための生活保障的な性質を持つ年金について逸失利益性を認めます。
また年金を受給しながら働いていた場合には、労働に対する収入部分についての逸失利益も、原則として認められることになります。
事故により、将来受け取るはずだった障害年金が減額された場合などは、別途損害として認められる可能性があります。
まとめ|適切に逸失利益を受け取るためにも、金額が妥当か弁護士に相談しよう
交通事故の逸失利益は、被害者とご家族の将来の生活を守るための非常に重要な補償です。しかし、その計算は複雑なうえ、保険会社は自社の基準で金額を低く提示してくることも珍しくありません。
保険会社から提示された金額を見て「低い」「おかしい」と感じたら、絶対にその場で示談しないようにしましょう。また、交通事故に強い弁護士に損害計算書をチェックしてもらうことも大切です。
弁護士が介入して裁判基準で交渉・請求することで、提示額が増額されるケースも少なくありません。逸失利益の金額に不安を感じた場合は、まず信頼できる弁護士に相談しましょう。
交通事故の逸失利益で悩んでいる場合は、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が、適切な逸失利益の受け取りに向けてサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応