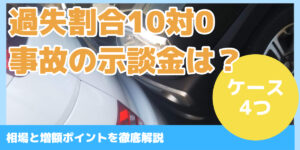事故で過失割合9対1に納得いかない場合の対処法は?応じるリスクや注意点を解説
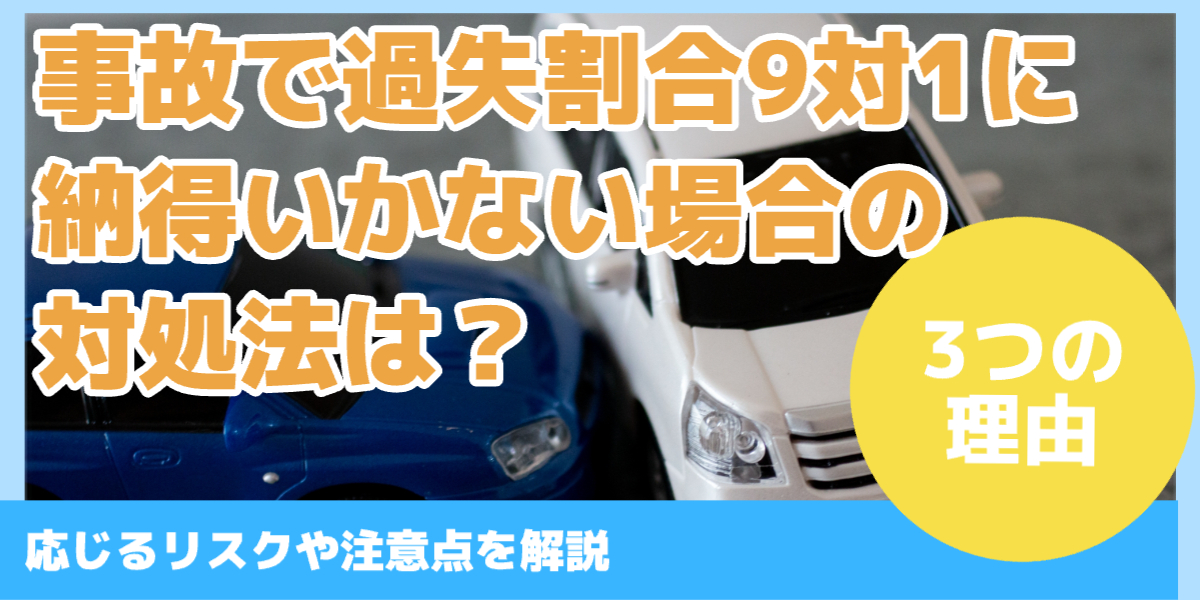
「加害者側の保険会社から9対1と提示された理由が知りたい」
「過失割合を9対1から10対1にする方法はある?」
事故の被害に遭い、過失割合が9対1であることに納得がいかない方も多いでしょう。しかし、その提示に感情的に反論しても、過失割合が覆ることはありません。
この記事では、交通事故の過失割合が9対1になる理由や、その割合で示談するリスクを解説します。さらに、納得いかない場合の具体的な対処法や、交渉を有利に進めるための証拠についても詳しく説明します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫納得のいく過失割合にするためにも、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故の過失割合にお悩みの場合は、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故に精通した弁護士が、個々のケースに併せて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
なぜ過失割合が9対1?完全被害者扱いにならない理由
交通事故において、加害者側の保険会社が、被害者側にも1割の過失が認められる「9対1」という過失割合を主張することがあります。ただ、「自分は悪くないのに」と不満が残る被害者も多いのではないでしょうか。
ここからは、なぜ10対0の「完全被害者」扱いにならないのかについて、3つの理由を解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
被害者にも「注意義務違反」があると判断されるため
道路交通法では、運転者には常に周囲の安全を確認し、危険を回避する義務があります(道路交通法第70条)。
そのため、以下のような状況では、たとえ被害者であっても「注意義務違反があった」と見なされることも珍しくありません。
- 危険を予測できたにもかかわらず、回避行動が遅れた
- 相手の明らかな交通違反(例:信号無視)を予見できた
- 軽微な前方不注意があった
過失割合は、事故当事者双方の「注意義務違反」の程度によって決まります。
そのため、被害者側にも「わずかな不注意」があったと判断されると、1割の過失が認定される可能性があるでしょう。
基本の過失割合が「9対1」の事故類型であるため
保険会社が提示する過失割合は、担当者の主観ではなく過去の膨大な裁判例(判例)を基に作成された基準を用いて決められています。
過去の裁判例などの蓄積である『別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』という書籍が実務では参考にされます。これらの基準では、類似した事故態様ごとに基本となる過失割合がパターン化されているのが特徴です。
中には、被害者側にも注意義務違反を認め、基本類型が「9対1」として設定されている事故も一定数存在します。
保険会社は、この実務上の基準に則って過失割合を参考にするため、9対1として提示している可能性が考えられるでしょう。
10対0は「回避不能かつ明白な違反があったとき」に認められるため
被害者の過失の基本類型が10対0となる交通事故は、極めて限定的なケースです。
一般的に、被害者側にとって「事故の発生を予見できず、回避が不可能だった」と客観的に証明できる場合に、10対0とされる傾向があります。10対0が適用される典型的な例は以下のとおりです。
- 停車中に追突された(玉突き事故など)
- センターラインオーバーの車と正面衝突した
- 相手が赤信号を完全に無視して交差点に進入してきた
上記以外の事故では、被害者側にも「何らかの回避行動(クラクションを鳴らす・ブレーキを踏むなど)が可能だったのではないか」と判断され、過失が問われやすいのが実情です。
過失割合が10対0になるケースについては、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:右直事故の過失割合10対0は可能?被害者が有利な場合が認められるケースを紹介
過失割合が9対1になる可能性があるケース
では、具体的にどのような事故で過失割合が9対1(被害者1割)となる可能性があるのでしょうか。
ここでは、保険実務や判例で9対1が基本割合とされる可能性があるケースを紹介します。
自身の事故がこれらに当てはまるか確認してみてください。
優先道路を走行する車と非優先道路から進入した車の事故
信号機のない交差点で、優先道路を走行する車(被害者)と、非優先道路から進入してきた車(加害者)が衝突した場合、基本は9対1となります。
優先道路とは、以下のような場所を指します。
優先道路
- 優先道路の標識がある道路
- センターラインが交差道路を横切って引かれている道路
優先道路に準じて考えてよい道路
- 他方の道路と比べて明らかに道幅が広い道路
優先道路側にも交差道路からの進入車に注意する義務があると考えられています。



その結果、被害者側にも1割の過失があると認定されるのが基本です。
追突事故(灯火義務を怠った場合)
追突事故は、原則として追突した側(加害者)が10対0で過失を負います。しかし、前方車(被害者)が「灯火義務を怠った」ことが原因で追突された場合は例外です(道路交通法第52条)。
主に、以下のようなランプを適切に灯火させなかった場合が挙げられます。
- ヘッドライト(前照灯)
- スモールライト(車幅灯)
- テールランプ(尾灯)
- ハザードランプ など
この場合、被害者側にも事故を誘発した原因があるとして、1〜2割程度の過失が認められる可能性が高いです。
車線変更中の事故
同一方向に走行中、車線変更した車(加害者)と後続の直進車(被害者)が衝突したケースも、9対1になる可能性がある事例です。
基本は7対3となりますが、以下のような状況では9対1になる可能性もあります。
- 車線変更が禁止されている場所(黄色の車線)での事故
- 変更車の合図がなかった場合の事故



状況によって判断が変わりやすいため、一度弁護士に相談することが大切です。
交通事故の過失割合にお悩みの場合は、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故に精通した弁護士が、個々のケースに併せて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
関連記事:交通事故の過失割合納得いかない!適正化を弁護士に任せるべき理由
9対1の過失割合を覆せる可能性が高いケース
9対1の過失割合でも、状況次第では見直しが認められる可能性があります。主なケースは、以下のとおりです。
- 加害者が一時停止・信号無視など明確な交通違反をしていた
- ドライブレコーダー映像で被害者に注意義務違反がないことが証明できる
- 現場実況見分調書の記載が事実と異なる
- 目撃者証言が新たに得られた
加害者が一時停止や信号無視などの明確な交通違反をしていた場合、被害者側の過失が再評価されることがあります。また、ドライブレコーダーの映像で被害者に注意義務違反がなかったことを証明できれば、過失割合の修正が期待できます。
さらに、現場実況見分調書の内容が実際の状況と異なる場合や、新たに目撃者の証言が得られた場合も有力な再交渉の材料です。
これらの条件がそろう場合、示談前であれば弁護士を通じて再交渉やADR(裁判外紛争解決手続)を申し立て、過失割合の見直しを求めることが可能です。



条件に当てはまる場合は、過失割合を覆せないか弁護士に相談してみましょう。
関連記事:過失割合のゴネ得はどう防ぐ?応じる危険性や対処法・効果的な証拠を弁護士が解説
過失割合9対1で示談することで生じるデメリット
保険会社から提示された9対1の過失割合に納得がいかないまま「交渉が面倒だから」と示談に応じてしまうと、被害者にとって大きな不利益が生じる可能性があります。
主なデメリットは、以下のとおりです。
以下、それぞれ詳細に解説します。
「過失相殺」によって受け取れる示談金が1割減額される
被害者側に1割でも過失があると、過失相殺が適用されます(民法第722条2項)。被害者の損害額全体から、自身の過失割合分(この場合は1割)が差し引かれる仕組みです。
被害者の損害額(治療費・慰謝料・休業損害など)の総額が500万円の場合を例にすると、以下のように計算されます。
- 過失10対0の場合:500万円の全額を受け取れる
- 過失9対1の場合:500万円×1割(50万円)が減額され、450万円を受け取れる
このように、自身の過失が1割あるだけで、受け取れる示談金が数十万円単位で減ってしまうデメリットがあります。
加害者の損害額の1割を支払う義務が発生する
過失相殺は、相手方(加害者)にも適用されます。加害者は、自身の損害額の9割を自分で負担し、残りの1割を被害者側に請求可能です。
つまり、被害者は、加害者の損害額(車の修理費など)の1割を支払う義務を負うことになります。加害者の車の修理費が100万円の場合、被害者は100万円の1割、つまり10万円を加害者に支払わなければなりません。
実際には、被害者が受け取る示談金からこの10万円が差し引かれる(相殺される)形で処理されるのが一般的です。



いずれにせよ、被害者の金銭的負担が増えることに変わりはありません。
交通事故の過失割合に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。
関連記事:交通事故の過失割合を徹底解説|ケース別の相場と納得できない時の対処法
【ステップで解説】過失割合9対1に納得がいかない場合の対処法
提示された9対1の過失割合に納得できない場合、すぐ示談に応じるべきではありません。
適切な手順を踏んで交渉すれば、過失割合が10対0(または被害者の過失がより少ない割合)に変更される可能性は十分にあります。
以下の4つのステップで冷静に対処しましょう。
ステップ1:相手の主張を確認する
過失割合に納得がいかない場合、まずは相手方保険会社がなぜ9対1という割合を提示してきたのかを正確に把握することが重要です。
相手の主張内容を理解せずに反論しても、話がかみ合わず交渉が長期化してしまう恐れがあります。
保険会社に対しては、以下の3点を具体的に確認しましょう。
- どのような事故態様だと認定しているか
- どの判例や基準を参考にしているか
- 被害者のどのような行為を「1割の過失(注意義務違反)」と判断したのか
これらの確認は、可能な限り書面で回答してもらうようにしましょう。電話でのやり取りだと「言った・言わない」の水掛け論になりやすく、後から証拠として提示もできません。



感情的に反論する前に、まずは相手方保険会社の主張を理解するよう心がけましょう。
ステップ2:自己の主張を整理する
次に、自分の立場や主張を論理的に整理しましょう。「なぜ9対1では納得できないのか」「どの点で相手の主張と食い違っているのか」を明確にすることがポイントです。
たとえば以下のように事故状況を箇条書きで整理したり、あるいは時系列で整理したりして、自身の行動が適切だったことを示せるようにしておくとよいでしょう。
- 自分は徐行していた
- 相手が一時停止を無視した
- 信号が青だった
感情的な反論ではなく、事実に基づいた説明を準備することで、後の交渉や証拠収集がスムーズになります。
ステップ3:主張を基礎づける証拠を集める
保険会社の主張に対して、「納得いかない」と感情的に訴えても交渉は進みません。
相手の認定を覆すためには、被害者側には注意義務違反がなかったことや、加害者側にさらなる過失があったことを示す客観的な証拠が不可欠です。
以下のような、10対0を主張できる客観的な証拠を集めましょう。
- ドライブレコーダーの映像
- 事故現場や車両の損傷箇所の写真
- 警察が作成した実況見分調書
どのような証拠が有効かは、次の「過失割合を9対1から10対0に交渉する際に重要な証拠」で詳しく解説します。
ステップ4:弁護士に相談する
自分で交渉しても納得いく結果が得られない場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談しましょう。
弁護士は、過去の判例や類似事例をもとに、妥当な過失割合を判断し、保険会社との交渉を代行してくれます。
そのほか、弁護士に相談することで得られるメリットは以下のとおりです。
- 法的な観点で、適切な過失割合を再計算してもらえる
- 保険会社との交渉をすべて任せられる
- ADR(裁判外紛争処理機関)や訴訟への移行がスムーズになる
多くの法律事務所では初回相談を無料で行っています。また、弁護士費用特約に加入している場合、自己負担なしで相談・依頼することが可能です。



示談書にサインする前に、一度専門家の意見を聞いてみましょう。
関連記事:交通事故の示談交渉は自分でできる?考えられるリスクや注意点を徹底解説
交通事故の過失割合にお悩みの場合は、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故に精通した弁護士が、個々のケースに併せて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
関連記事:交通事故で弁護士に依頼するメリットは?デメリットや依頼の適切なタイミングも解説
過失割合を9対1から10対0に交渉する際に重要な証拠
過失割合を10対0に近づけるには、事故状況を客観的に示す「証拠」が欠かせません。
とくに以下の4つの証拠は、交渉を有利に進めるうえで重要です。
- ドライブレコーダーの映像
- 警察が作成する実況見分調書・供述調書
- 事故現場や車両の損傷状況を示す写真
- 事故時刻の信号サイクル表
証拠を適切に揃えることで、相手側の主張を崩し、過失割合を見直してもらえる可能性が高まるでしょう。
それぞれの特徴について、以下の表にまとめました。
| ドライブレコーダーの映像 | 事故の瞬間や双方の動き、信号の色、危険運転の有無を客観的に記録できます。 同乗者のスマホ映像や他車・店舗カメラ映像も有効です。 |
|---|---|
| 実況見分調書・供述調書 | 警察が事故現場を調査し、図面・状況・当事者説明などをまとめた公的資料です。 検察庁で閲覧・交付してもらえます。 |
| 事故現場や車両損傷の写真 | 車両の損傷箇所・停止位置・ブレーキ痕・道路状況などを撮影しましょう。 現場の全体像を押さえることが重要です。 |
| 信号サイクル表 | 事故時刻における赤・黄・青の点灯時間を記載した資料です。 警察署に申請することで、開示を受けられます。 |
実況見分調書の取り寄せや信号サイクル表の開示申請などは、法的知識や手続きへの理解が必要です。個人で収集・整理することが難しい場合もあるでしょう。
そのため、過失割合の見直しを本気で目指すなら、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。弁護士に相談すれば、必要な証拠の収集・整理をサポートしてくれます。



必要な書類を適切に収集・整理するためにも、弁護士への早期相談が大切です。
事故の過失割合9対1で納得いかない人からよくある質問
過失割合9対1の人身事故の慰謝料の相場は?
慰謝料の金額は、入通院期間や後遺障害の有無・等級によって決まります。
ただし、算出された慰謝料額から自身の過失割合が差し引かれる点に注意が必要です。
入通院慰謝料が100万円で、後遺障害慰謝料が200万円(合計300万円)の場合、300万円から1割(30万円)が過失相殺されます。この場合、実際に受け取れる慰謝料額は270万円です。
交通事故の慰謝料相場については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:交通事故の損害賠償額の決め方とは?交通事故の慰謝料の計算方法を弁護士が解説
関連記事:交通事故は「人身事故」扱いにすべき?人身事故にすべき理由や切り替え手続きを解説
自分が1割の過失でも、加害者の治療費を払う必要はある?
加害者の治療費を被害者が直接支払うケースは稀です。
人身事故の場合、被害者の治療費は、加害者が加入している「自賠責保険」や「対人補償」から支払われます。
一方で、過失割合が9対1の場合、被害者には加害者の損害(治療費を含む)の1割を負担する義務があります。
そのため、加害者の治療費の1割と、被害者が受け取る示談金が相殺されて処理される可能性もゼロではありません。



結果、被害者が受け取る示談金が減額される形で間接的に負担することになります。
9対1の事故で保険を使うと等級は変わる?
自身が加入している自動車保険を使った場合、等級は下がります。過失割合が9対1の場合、被害者側は以下の2つの支払い義務を負う可能性があるためです。
- 相手(加害者)の車両修理費などの1割
- 自身の車両の修理費
これらの支払いに自身の車両保険や対物賠償保険を使うと、翌年の自動車保険の等級は「3等級ダウン」となり、保険料が上がります。
修理費が少額の場合は、保険を使わずに自己負担(自腹)で支払った方がトータルの支出を抑えられるケースもあるでしょう。
まとめ|過失割合9対1に納得いかないなら、弁護士へ相談しよう
交通事故で保険会社から「過失割合9対1」と提示された場合でも、その判断は絶対ではありません。
安易に示談に応じてしまうと、受け取れる示談金が1割減額されるだけでなく、相手の損害の1割を負担するリスクを負うことになります。一度成立した示談は、原則として覆せません。
もし提示された割合に納得がいかないのであれば、まず保険会社に9対1の明確な根拠を確認しましょう。その後、ドライブレコーダーや実況見分調書など、10対0を主張できる客観的な証拠を集め、保険会社と再交渉することが大切です。
自身での交渉が難しい場合や、保険会社の対応に不満がある場合は、示談書にサインする前に、交通事故に強い弁護士に相談することも検討してみましょう。
交通事故の過失割合にお悩みの場合は、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故に精通した弁護士が、個々のケースに併せて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応