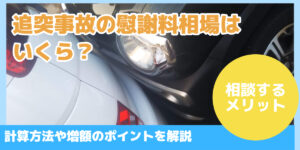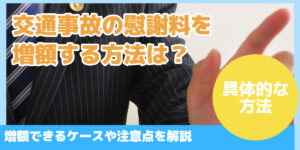交通事故の慰謝料はどうやって計算する?弁護士基準の相場と通院期間ごとの早見表【弁護士監修】

「交通事故の慰謝料って、一体いくらもらえるんだろう?」
「保険会社から提示された金額が妥当なのか、全くわからない…」
交通事故に遭い、心身ともに大変な状況の中、複雑な慰謝料計算について不安を感じるのは当然のことです。
この記事では、交通事故の慰謝料がどのように計算されるのか、その全体像を弁護士の視点から徹底的に解説します。
ご自身の権利を守り適正な慰謝料を得るには、正しい知識が欠かせません。正当な補償を得るために、ぜひ知っておきましょう。
交通事故の示談交渉や賠償金に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて親身にサポートいたします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故で請求できる慰謝料とは?
交通事故における慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛を金銭に換算して賠償するものです。
これは、治療費や休業による減収といった具体的な財産上の損害とは別に、目に見えない「心の痛み」に対して支払われます。
損害賠償の請求は個人の感情論によるものではなく、日本の民法によって明確に保障された権利です。(参照:民法|第709条)
交通事故の慰謝料は、以下3つの種類に分類されます。
まずはこの3種類を理解し、慰謝料の全体像をつかんでおきましょう。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)|ケガの治療で受け取る慰謝料
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故によるケガの治療を余儀なくされたこと自体に対する精神的苦痛を賠償するものです。
この慰謝料は、治療期間中に被害者が経験する以下のような精神的負担を包括的に評価します。
- ケガそのものの痛み
- 通院や入院に伴う時間的拘束
- 治療への不安
- 日常生活における不便さ など
計算の際は、通院の回数ではなく、主に治療にかかった期間(入院期間および通院期間)を基準にします。
同じケガであっても、治療が長引けばそれだけ精神的苦痛も大きくなると考えられるため、期間が長くなるほど慰謝料額は高くなる傾向にあります。
ただし、怪我の内容や、通院の期間に比べて通院の回数が少なすぎる場合には、通院の期間が長くても減額の要素になる場合があります。
この慰謝料は、被害者がケガの治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻すための助けとなる重要な賠償項目と言えるでしょう。
後遺障害慰謝料|後遺症が残った場合に受け取る慰謝料
後遺障害慰謝料は、身体や精神に永続的な機能障害や症状が残った場合の精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
これは、「将来にわたって後遺症と向き合い、生きていかなければならない」という計り知れない精神的負担を補償するものです。
この慰謝料の請求は、以下のステップで進めます。
- これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないという「症状固定」の診断を医師から受ける
- その残存した症状について、後遺障害等級の認定を受ける
この等級認定が、後遺障害慰謝料を請求するためのいわば「資格証明」となり、認定された等級に応じて慰謝料額が決定されます。
死亡慰謝料|被害者が亡くなった場合に遺族が受け取る慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が亡くなられた場合に、その無念と遺族の悲しみに対して支払われる賠償金です。この慰謝料は以下2つの性質を併せ持っています。
| 対象 | 概要 |
|---|---|
| 亡くなられた被害者本人 | 事故による恐怖や痛み、そして志半ばで人生を絶たれた無念さに対する慰謝料 |
| 遺族(配偶者、子、両親など) | 最愛の家族を突然失ったことによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
この2つの要素が一体となって、死亡慰謝料の総額が算定されるのが一般的です。
なお、被害者本人への死亡慰謝料の請求権は、相続人である遺族に引き継がれるため、遺族は被害者本人に対する慰謝料と、遺族への慰謝料の両方を受け取ることになります。
近親者慰謝料|近親者が亡くなったり重度の障害が残った場合に受け取る慰謝料
交通事故によって被害者が亡くなった場合や、植物状態(遷延性意識障害)のような極めて重い後遺障害が残るケースもゼロではありません。
この場合、被害者本人への慰謝料とは別に、そのご家族自身の精神的な苦痛に対しても「近親者慰謝料」が発生することがあります。
この権利は、主に被害者の父母、配偶者、子に認められており、大切な家族を失ったりその痛ましい姿を目のあたりにしたりすることで受けた、ご家族自身の深い悲しみや苦しみを補償するものです。(参照:民法|第711条)
ここで最も重要なポイントは、この近親者慰謝料は、あくまで、ご家族一人ひとりが持つ「固有の権利」として請求できる点です。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫亡くなった被害者本人の慰謝料を遺族が受け継ぐ(相続する)のとは、全く別のものであることは覚えておきましょう。
関連記事:交通事故の慰謝料とは?計算方法や慰謝料相場・注意点を弁護士が徹底解説
交通事故で請求できる慰謝料の計算基準は3種類
交通事故の慰謝料額を決定づける最も重要な要素は、どの「計算基準」を用いるかです。慰謝料の計算基準は、金額が低い順に以下の3種類があります。
加害者側の保険会社が最初に提示してくる金額は、被害者が本来受け取るべき正当な金額よりも低い基準で計算されていることがほとんどです。
それぞれの基準についてみていきましょう。
自賠責基準|国が定める最低限の補償
自賠責基準とは、「自動車損害賠償保障法」に基づき、国が定めた支払基準です。自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険で、その目的は交通事故被害者に対する最低限の救済を確保することにあります。
基本的なセーフティーネットとしての位置づけであるため、自賠責基準は3つの基準の中で最も賠償額が低く設定されています。特に重要な点は、傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料など全てを含む)の支払上限額が120万円と定められていることです。
重傷を負った場合や治療が長期化した場合には、この上限額をすぐに超えてしまいます。
任意保険基準|保険会社独自の非公開基準
任意保険基準とは、加害者が任意で加入している自動車保険会社が、示談交渉の際に用いる内部的な支払基準です。
この基準の最大の特徴は、保険会社各社が独自に設定しており、その具体的な計算方法や金額が一般に公開されていない点です。
任意保険基準での金額は、自賠責基準をわずかに上回るものの、弁護士基準よりは低くなります。
保険会社は営利企業であり、自社の支払額が多くなりすぎないように基準を設定しているためです。
被害者本人が直接交渉する場合、保険会社からは任意保険基準を基に示談金額を提示されるケースが多く、交通事故の被害者にとっては不利な交渉を強いられる一因となっています。
弁護士基準(裁判基準)|本来受け取るべき最も高額な基準
弁護士基準(裁判基準)は、これまでの交通事故に関する裁判の判例を基に作られた算定基準です。
実際に裁判所が損害賠償額を判断する際に用いるため、法的に最も正当性が高く、3つの基準の中では慰謝料額が最も高額です。
この基準の詳細は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という専門書籍(通称「赤い本」)にまとめられており、全国の弁護士や裁判官が適正な慰謝料を算出するために参照しています。
ただし、被害者ご本人が保険会社と直接交渉する際、この弁護士基準がスムーズに認められることはまずありません。



弁護士が被害者の代理人として交渉することで、保険会社が弁護士基準での支払いを検討する流れが一般的です。
交通事故の入通院慰謝料の計算方法と相場|通院日数と重症度で決まる
入通院慰謝料の金額は「治療期間(入院・通院した期間)」「実通院日数(実際に病院へ行った日数)」「ケガの程度(重傷か軽傷か)」という3つの要素によって決まります。
これらの要素を、どの計算基準に当てはめるかによって、最終的な金額が大きく変わってきます。
ここでは、自賠責基準と弁護士基準、それぞれの計算方法を見ていきましょう。
自賠責基準による計算の場合
自賠責基準における入通院慰謝料は、明確な計算式に基づいて算出されます。まず、日額は4,300円と定められています(2020年4月1日以降発生の事故に適用)。
この日額に、慰謝料の対象となる「対象日数」を掛けて総額を計算します。(参照:国土交通省自賠責保険・共済ポータルサイト|限度額と補償内容)
「対象日数」は、以下の2つのうち、いずれか少ない方の日数が採用されるのが特徴です。
- 治療期間(治療開始日から治療終了日までの総日数)
- 実通院日数×2
この「×2」のルールは、治療期間が長期にわたるものの、実際の通院頻度が極端に低いといったケースで、慰謝料が不当に低額になるのを防ぐための調整措置です。
例えば、治療期間が90日間、その間の実通院日数が40日だった場合の計算例は以下のとおりです。
- 治療期間:90日
- 実通院日数×2:40日×2=80日
この場合、少ない方の80日が「対象日数」として採用され、慰謝料は4,300円×80日=34万4,000円となります。
弁護士基準による計算の場合
弁護士基準では、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」に治療期間を当てはめて、金額を算出します。
この計算方法では、ケガが重いほど精神的な苦痛も大きいという考え方に基づき、ケガの重症度によって2種類の表が使い分けられます。
| 表の種類 | 解説 | 通院6ヶ月の慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 重いケガ用の表 (「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」別表Ⅰ) | 骨折や内臓損傷など、検査結果で客観的な異常が認められる重傷の場合に用いる | 116万円 |
| 軽いケガ用の表 (「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」別表Ⅱ) | むちうちや軽い打撲など、レントゲンでは異常が見つかりにくい比較的軽傷の場合に用いる | 89万円 |



通院6ヶ月どちらの表を使うかによって慰謝料の金額は大きく異なるため、どちらを適用するかは保険会社との交渉における重要な争点です。
交通事故の後遺障害慰謝料の計算方法と相場|後遺障害等級に応じて決まる
後遺障害慰謝料は、症状固定後も残ってしまった後遺症の精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。その金額は、認定された後遺障害等級(1級~14級)によって決まります。
この後遺障害慰謝料は、どの計算基準を用いるかで金額に大きな差が生じることもあります。実際に自賠責基準と弁護士基準でどの程度の差があるかを見ていきましょう。
自賠責基準による計算の場合
自賠責基準では、後遺障害等級ごとに慰謝料の金額が法律で一律に定められています。これは後遺障害によって生じる精神的苦痛に対する、あくまで国が定める最低限の補償です。
具体的な金額は以下の通りです。
| 後遺障害等級 | 慰謝料額(要介護の等級は省略) |
|---|---|
| 第1級 | 1,150万 |
| 第2級 | 998万円 |
| 第3級 | 861万円 |
| 第4級 | 737万円 |
| 第5級 | 618万円 |
| 第6級 | 512万円 |
| 第7級 | 419万円 |
| 第8級 | 331万円 |
| 第9級 | 249万円 |
| 第10級 | 190万円 |
| 第11級 | 136万円 |
| 第12級 | 94万円 |
| 第13級 | 57万円 |
| 第14級 | 32万円 |
自賠責保険には後遺障害部分全体での支払上限額も設定されており、逸失利益など他の損害項目と合算して上限を超える場合、全額が支払われない可能性もあります。
弁護士基準による計算の場合
弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例を基にした、被害者の苦痛の実態に即した基準であり、自賠責基準よりも高額に設定されています。
後遺障害等級が認定された場合、弁護士に依頼し、以下の表に示すような金額を基準に交渉を進めていきましょう。
| 後遺障害等級 | 弁護士基準(裁判基準) |
|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 |
| 第2級 | 2,370万円 |
| 第3級 | 1,990万円 |
| 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
表からも分かるとおり、弁護士基準では、受け取れる慰謝料額は自賠責基準の2倍から3倍以上になることもあります。



この差額は、被害者が本来受け取るべき正当な賠償額であるにもかかわらず、適切な知識を持って請求しなければ失ってしまう可能性がありますから、賠償の提案があった際にはどの基準で賠償提案をされているのか、よく注意しなくてはなりません。
後遺障害等級については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:後遺障害等級とは?等級一覧表から申請方法、慰謝料の相場まで弁護士が徹底解説
交通事故の死亡慰謝料の計算方法と相場|被害者の家庭での立場で変わる
交通事故で被害者が亡くなった場合、慰謝料の額は、被害者がご家庭の中でどのような立場にあったかによって大きく変動します。
例えば、一家の経済的な大黒柱を失うのと、まだ幼い子どもを失うのとでは、遺族が受ける精神的な打撃の性質や大きさが異なると考えられているためです。
ただし、この「立場の違い」をどのように金額へ反映させるかは、用いる計算基準ごとに異なります。その違いを見ていきましょう。
自賠責基準による計算の場合
自賠責基準では、被害者の「一家の支柱であったか」といった家庭での立場は、慰謝料額の計算において直接的には考慮されず、以下3つの要素を機械的に合算します。
| 慰謝料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 1.亡くなった本人への慰謝料 | 400万円 |
| 2.遺族への慰謝料(父母、配偶者、子) | 1名の場合:550万円 2名の場合:650万円 3名以上の場合:750万円 |
| 3.被扶養者がいる場合の加算 | 上記金額にさらに200万円を加算 |
例えば、被害者に妻と扶養していた子ども1人(遺族2名)がいた場合、慰謝料は以下のように計算されます。
400万円+650万円+200万円=1,250万円
このように自賠責基準はあくまで最低限の補償であり、遺族それぞれの深い悲しみといった実態が十分に反映されているとは言い難いのが実情です。
弁護士基準による計算の場合
弁護士基準では、被害者が家庭で果たしていた役割という実質的な側面を最も重視して慰謝料を算定します。遺族が受ける精神的苦痛の大きさを、より実態に即して金額に反映させるためです。
| 立場 | 金額 | 理由 |
|---|---|---|
| 一家の支柱(家族の生計を主に支えていた方) | 2,800万円 | 精神的な支えと経済的な大黒柱を同時に失った遺族の苦痛が最も大きいと考えられるため、最高額となる |
| 母親、配偶者 | 2,500万円 | 家庭生活において中心的な役割を担っていた方を失った、計り知れない精神的苦痛を考慮した金額 |
| その他(独身者、子ども、高齢者など) | 2,000万円~2,500万円 | 被害者の立場に関わらず、かけがえのない命が失われたこと自体の重大さを評価した金額 |
仮に、先ほど自賠責基準で挙げた「被害者に妻と扶養していた子ども1人(遺族2名)がいるケース」の場合、弁護士基準での慰謝料は2,800万円となり、自賠責基準の2倍以上となります。
また、被害者の属性や家族の状況によっては、この慰謝料がさらに高額に修正されることもあります。



このように、弁護士基準は被害者の家庭における地位や状況を金額に反映しており、自賠責基準をはるかに上回る高水準の補償を目指すものなのです。
【ケース別】交通事故の慰謝料計算シミュレーション|いくらもらった?
今まで解説したように、どの程度の慰謝料を見込めるかは、自賠責基準と弁護士基準のどちらを適用するかによって大きく異なります。
ここでは、比較的多い以下のケースにおける慰謝料を、自賠責基準と弁護士基準の両方で計算していきます。
本章を参考に、ご自身のケースと照らし合わせてみましょう。
関連記事:追突事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や増額のポイントを弁護士が解説
交通事故によるむちうちで6ヶ月(半年)通院した場合の慰謝料
交通事故によるむちうちで6ヶ月間(180日)にわたって通院したケースを考えてみましょう。このうち、実際に病院へ通った日数は50日とします。
今回、算出の計算に使うのは、日数の少なくなる「実通院日数×2=100日」です。この100日に1日あたりの慰謝料4,300円をかけて、慰謝料を計算しましょう。
一方、弁護士基準では、この場合、弁護士は過去の裁判例を基にした「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の「別表Ⅱ」という表を用いて慰謝料を算出します。
自賠責基準と弁護士基準の金額は、以下のとおりです。
| 慰謝料 | 算出方法 | |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 43万円 | 4,300円×100日=43万円 |
| 弁護士基準 | 89万円 | 通院6ヶ月の相場 |
| 差額 | 弁護士基準の方が46万円高い | 89万円-43万円=46万円 |
弁護士基準を適用することで、被害者が受けた精神的苦痛がより適切に評価され、自賠責基準よりも46万円以上高い金額を請求できる可能性があるのです。
関連記事:交通事故のむちうちで慰謝料はいくらもらえる?相場や計算例を弁護士が解説
交通事故による骨折で6ヶ月(半年)通院した場合の慰謝料
同じ6ヶ月の入通院慰謝料でも、骨折などの重傷を負った場合で計算してみましょう。
自賠責基準の場合、治療期間と通院日数が同じであれば、ケガの種類や重症度に関わらず、通院慰謝料の金額は変わりません。そのため、むちうちと同じく、実通院日数×2=160日に1日あたりの慰謝料4,300円をかけて、通院慰謝料を計算します。
一方、弁護士基準(裁判基準)は、被害者が受けた精神的苦痛の大きさに応じて、適正な賠償を支払うべきという考え方に基づいています。今回は重傷であるため被害者の精神的苦痛はさらに大きいと判断され、軽傷の場合と異なる「別表Ⅰ」という基準を用いて、慰謝料の算定額はより高額です。
それぞれの基準ごとの慰謝料金額とその差額は、以下のとおりです。
| 慰謝料 | 算出方法 | |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 43万円 | 4,300円×100日=43万円 |
| 弁護士基準 | 116万円 | 通院6ヶ月の相場 |
| 差額 | 弁護士基準の方が73万円高い | 116万円-43万=73万円 |
表より、弁護士基準と自賠責基準の差が73万円となり、重症度が高い骨折では、軽症のむちうちの場合より両基準の金額差が大きいと分かります。
適用される基準が変わるだけで、慰謝料額に差が生まれることは少なくありません。適正な賠償を受けるためには、ご自身のケガに合った基準で請求することが重要です。
骨折した場合の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:交通事故で骨折した場合の慰謝料はいくら?相場や計算方法・手続き方法を弁護士が解説
後遺障害で12級が認定された場合の慰謝料
もし治療を続けてもケガが完治せず、「後遺障害」として12級の認定を受けた場合、通院に対する慰謝料とは別に、「後遺障害が残ったことへの慰謝料」を請求できます。
この後遺障害慰謝料は、以下のように自賠責基準と弁護士基準で特に大きな差が生まれます。
| 基準 | 慰謝料 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 94万円 |
| 弁護士基準 | 290万円 |
| 差額 | 弁護士基準の方が196万円多い |
このケースでは、弁護士基準で請求すれば、慰謝料だけで3倍以上の金額になる可能性があります
また、後遺障害が残ると、将来の仕事や収入に影響が出ることへの補償、いわゆる「逸失利益」も請求できます。
この逸失利益も弁護士基準で計算することで大幅に増額されるケースがほとんどです。



そのため、最終的に受け取れる賠償金の総額は、慰謝料の差額である196万円をはるかに上回る可能性があるでしょう。
慰謝料計算に必要な証拠・資料
慰謝料を適正に計算して保険会社に請求するには、損害を客観的に証明する資料が欠かせません。
特に怪我が事故によるものであるとを証明する診断書は、慰謝料請求の基礎となる非常に重要な書類です。人身事故として扱われるには、警察へ診断書を提出する必要があります。診断書を提出できないと治療費や慰謝料の請求が困難になる可能性があるため、事故後は速やかに受診しましょう。
慰謝料計算に必要となる主な証拠・資料の例は、以下の通りです。
| 書類の種類 | 主な役割と重要性 |
|---|---|
| 診断書・診療報酬明細書 | ・怪我の事実と治療内容、費用の証明 ・入通院慰謝料算定の基礎となる |
| 後遺障害診断書 | ・治療後も後遺症が残った場合に等級認定を受けるための最重要書類 ・後遺障害慰謝料や逸失利益の金額に大きく影響する |
| 交通事故証明書 | ・警察に届け出ることで発行され、事故の発生を公的に証明する書類 |
| 休業損害証明書・源泉徴収票など | ・事故による休業での減収を証明し、休業損害を請求するために必要な書類 |
| 各種領収書 | ・通院交通費や診断書の作成費用など、実際にかかった費用を証明する ・保管がなければ請求できない可能性がある |



これらの書類を事故直後から意識して揃えておくことが、慰謝料を含む損害賠償金全体の適正な算定につながり、不当な減額を防ぐための重要な準備となるでしょう。
交通事故の慰謝料以外に請求できる「損害賠償金」とは?
交通事故の被害者が請求できるのは、精神的苦痛に対する「慰謝料」だけではありません。被害者は事故によって生じたあらゆる損害を合計した「損害賠償金」全体を請求する権利があります。
請求漏れを防ぎ、正当な賠償を確保するために、全体像を把握しておきましょう。
積極損害|治療費や交通費などの実費
積極損害とは「交通事故がなければ支出する必要のなかった、実際にかかった費用」を指します。具体的には以下のような項目があげられます。
| 費用 | 概要 |
|---|---|
| 治療関係費 | ・ケガの治療のために必要となった費用全般 |
| 通院交通費 | ・病院への通院にかかった交通費 |
| 入院雑費 | ・入院中に必要となる日用品や通信費などの購入費用 |
| 付添看護費 | ・入院や通院の際に、家族などの付き添いが必要になった場合に認められる費用 |
| その他の費用 | ・診断書などの文書作成費用 ・器具・装具の購入費 ・後遺障害によって必要になった家屋 ・自動車の改造費 など |
これらの費用が賠償として認められるには、すべて「必要かつ相当」な範囲内であると判断される必要があります。よって、請求の際は原則として領収書をはじめとする証拠書類が必要です。
また、保険会社から「過剰診療」や「高額診療」と見なされると、一部が支払われないケースもあるため、医師と相談しながら適切な治療を受けるようにしましょう。
消極損害|休業損害(休業補填)や逸失利益
消極損害とは、交通事故がなければ得られたはずなのに、得られなくなってしまった経済的利益(収入)のことです。
具体的には「休業損害(休業補填)」「逸失利益」があげられます。
休業損害(休業補填)|交通事故で仕事を休んだ分の補償
休業損害は、交通事故によるケガが原因で仕事を休み、その結果発生した減収分に対する補償です。
これは治療期間中に限定される損害で、原則として以下のように計算されます。
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
基礎収入を証明する資料は、以下のように職業によって異なります。
| 職業 | 収入を証明する資料 |
|---|---|
| 会社員 | ・源泉徴収票 ・給与明細 |
| 自営業者 | ・確定申告書 |
また、家事労働は経済的に評価されるべきとの考えから、収入のない専業主婦(主夫)であっても、休業損害は請求可能です。
その場合、国の統計である「賃金センサス」の女性全年齢平均賃金などを基に基礎収入を算出し、休業損害を請求します。
逸失利益|後遺障害や死亡で失われた将来の収入
逸失利益は、後遺障害が残った、あるいは死亡したことによって、将来にわたって得られたはずの収入が得られなくなったことへの補償です。
逸失利益には後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があり、計算式は以下のとおりです。
後遺障害逸失利益=基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
死亡逸失利益=基礎収入×(1–生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
計算に使用する用語について、以下にまとめました。
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 労働能力喪失率 | 後遺障害等級に応じて定められた、労働能力がどの程度失われたかを示す割合 例:12級は14%、14級は5% |
| ライプニッツ係数 | 将来にわたって受け取るはずだった収入を賠償金として一時金で受け取る際、将来発生するはずの利息分をあらかじめ差し引く(中間利息控除)ための係数 |
| 生活費控除率 | 亡くなった本人が生きていれば自分の生活のために使ったはずのお金の割合を差し引くための係数 |
専門的な要素が多く、一般の方が逸失利益を正確に計算するのは難しいケースは少なくありません。



後遺障害や死亡などのケースは、弁護士に相談し正確な慰謝料を計算することをおすすめします。
交通事故の示談交渉や賠償金に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて親身にサポートいたします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
なお、交通事故の損害賠償額については、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:交通事故の損害賠償額の決め方とは?交通事故の慰謝料の計算方法を弁護士が解説
交通事故の慰謝料計算に影響するケース
これまでお伝えしてきた慰謝料の相場は、あくまで基本的なモデルケースの金額です。
実際は事故ごとの個別の状況によって、本来受け取れるはずの慰謝料が基準額よりも増えたり、反対に減ってしまったりすることがあります。
ここでは、どのような場合に慰謝料の金額が変動するのか、「増額されるケース」と「減額されるケース」に分けて具体的に見ていきましょう。
交通事故の慰謝料が増額される可能性があるケース
以下のような「特別な事情」があった場合、被害者の方が受けた精神的な苦痛は、通常の事故よりも大きいと判断されます。
その結果、弁護士が用いる裁判基準の相場額から、さらに慰謝料が増額される可能性があります。
加害者に飲酒運転・ひき逃げ・無免許などの悪質な行為があった
加害者の運転が単なる不注意ではなく、極めて悪質・危険なものであったケースでは、慰謝料が大幅に増額される可能性があります。
具体的には、以下のような行為が当てはまります。
- 飲酒運転、薬物使用運転
- ひき逃げ(救護せずに現場から走り去る行為)
- 無免許運転
- 時速30km以上の大幅なスピード違反
- 赤信号を意図的に無視する行為
判断基準のポイントは、危険性を認識しながらあえて危険な行為を行った、当然認識すべき危険を無視したなど、加害者の行為が単なる不注意の範囲を大きく超えているかどうかです。
事故後の加害者の態度が極めて不誠実だった
交通事故後の加害者の心ない対応で被害者がさらに精神的なダメージを負ったと判断された場合、慰謝料が増額される可能性があります。
例えば、以下のような態度は、被害者の苦痛を増大させる不誠実な対応と見なされます。
- 被害者に対して暴言を吐いたり、脅したりする
- 警察の取り調べに嘘の証言をする
- ドライブレコーダーの映像を消去するなど、証拠を隠そうとする
- 一度も謝罪に来ない、反省の色が全く見えない
相手の不誠実な言動は、可能な限り録音や書面で記録しておきましょう。また、警察や保険会社への虚偽説明を指摘することも、悪質な態度を立証する上で有効です。
生死の境をさまようなど、被害者が甚大な精神的苦痛を受けた
事故の状況が特に悲惨であったり、ケガが極めて重かったりした場合も、慰謝料が増額される可能性があります。
以下のような状況が例としてあげられます。
- 事故によって長期間、意識不明の状態に陥った
- 麻酔なしでの処置など、耐え難い痛みを伴う治療を受けた
- 何度も命に関わるような大手術を繰り返した
- 事故が原因で胎児を流産した
- 家族が目の前で事故の瞬間を目撃してしまった
この主張を裏付けるには、客観的な証拠が不可欠です。主に、カルテや医師の意見書、本人や家族による状況の記録などが用いられます。
裁判所もこうした事情を重く見て、基準額以上の慰謝料を認めることがあります。
後遺障害により生活への重大な影響が出た
後遺障害が残ったことによる影響が、仕事上のハンデ(労働能力の低下)だけに留まらない場合も、増額が考慮されます。
被害者の方の「人生そのもの」を大きく変えてしまうような、深刻な影響が出た場合です。
- 将来を期待されていたスポーツ選手や音楽家としての道を断たれた
- 事故が原因で、結婚の約束が破談になってしまった
- 顔に大きな傷跡が残り、人と会うのが辛くなってしまった
- 手足の麻痺により、長年続けてきた趣味を諦めざるを得なくなった
このような特別な事情は、賠償額を決定する上で十分に考慮されるべき大切な要素となります。主張を証明するには、治療の過酷さを示すカルテや医師の意見書、本人や家族が状況を記録した日記や陳述書などが有効です。
慰謝料が増額されるケースについては、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説
交通事故の慰謝料が減額される可能性があるケース
一方で、被害者側の事情が考慮され、慰謝料を含む賠償金全体が減額されてしまうことがあります。
これは「事故によって生じた損害は、関わった双方の責任に応じて、公平に分担すべき」という法律の基本的な考え方に基づくものです。どのような場合に減額の対象となるのか、代表的な2つのケースを見ていきましょう。
被害者に過失がある場合
交通事故が起きた原因について、被害者側にも「不注意(過失)があった」と判断される場合、その不注意の度合いに応じて賠償金が減額されます。
このルールを「過失相殺(かしつそうさい)」と呼びます。
例えば、加害者が赤信号を無視し、被害者は青信号で横断していたとしても、被害者の「左右の安全確認が不十分だった」といった不注意が認定されるケースがあります。
仮に賠償金の総額が1,000万円、被害者の過失割合が20%(2割)とされた場合、計算は以下のようになります。
- 賠償金の総額:1,000万円
- 被害者の過失割合:20%
- 減額される金額:1,000万円×20%=200万円
- 実際に受け取れる金額:1,000万円-200万円=800万円
たとえ被害者であっても、自身の不注意が事故の一因となった場合は、その分だけ受け取れる金額が減ってしまうのです。
過失割合については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:交通事故の過失割合を徹底解説|ケース別の相場と納得できない時の対処法
被害者側の持病などが影響する場合(素因減額)
被害者の方が「事故に遭う前から持っていた病気や体質が今回のケガの悪化や治療の長期化につながった」と判断されるケースでも、慰謝料が減ることがあります。
この場合、事故とは直接関係のない「個人の要因(素因)」が損害を大きくした部分は「素因減額(そいんげんがく)」と呼ばれ、賠償額から差し引かれることがあるのです。
具体的には、以下のような状況が考えられます。
| 例 | 減額に関係する部分 |
|---|---|
| 骨粗しょう症を患っていた方の場合 | 健康な人であれば軽いヒビで済んだかもしれない骨折が、骨の脆さによって悪化してしまった、と考えられる部分 |
| もともと椎間板ヘルニアがあった方の場合 | 事故による首や腰の痛みが、ヘルニアの影響で通常よりも長引いてしまった、と考えられる部分 |
とはいえ、すべての病気が減額対象になるわけではありません。「年齢を重ねることで骨が少し脆くなっていた」といったごく一般的な身体の変化であれば、基本的には減額の対象にはならないとされています。



保険会社から素因減額を主張されても、それが法的に妥当とは限らないケースもあるため、まずは一度弁護士にご相談ください。
交通事故の慰謝料計算を弁護士に相談|依頼する3つのメリットと理由
交通事故の慰謝料請求において、弁護士に相談・依頼することは、適正な賠償金を得るための最も有効な手段です。
保険会社との交渉には専門的な知識が必要であり、被害者個人で対応するには限界があるため、早めに弁護士への相談を検討しましょう。
ここでは、弁護士に依頼する具体的なメリットを3つに絞って解説します。
慰謝料が最も高額な「弁護士基準」で請求できる
弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料を最も高額な「弁護士基準」で請求できる点にあります。
弁護士基準は他の基準に比べて高額ですが、被害者ご本人が直接交渉しても、保険会社がこの基準に応じることはまずありません。
しかし、法律と交渉のプロである弁護士が代理人として立つことで、状況は一変します。
保険会社に対し法的な根拠をもって交渉することで、本来受け取るべき金額への大幅な増額を目指せるでしょう。
保険会社との複雑でストレスのかかる交渉をすべて任せられる
事故でケガを負い、心身ともに辛い時期に、慣れない保険会社の担当者と何度も示談交渉を重ねるのは、想像以上に大きなストレスになりかねません。
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、心身ともに負担のかかる手続きを代行してもらえます。依頼後は、保険会社からの連絡窓口が原則弁護士になるため、相手方と直接やりとりが不要になります。不当に治療の打ち切りを迫られたり、低い金額で示談を急がされたりする心配もなくなるでしょう。
これにより、煩わしい交渉から解放され、安心して治療と生活の回復に専念できるのです。
示談交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:交通事故の示談交渉は自分でできる?考えられるリスクや注意点を徹底解説
後遺障害等級認定の獲得を有利に進められる
もし体に後遺症が発生してしまった場合、その後の人生を支える補償を得るために、「後遺障害等級」の認定は非常に重要です。
この等級は、提出する書類の内容に大きく左右される、とても専門的な手続きです。弁護士は、専門知識を駆使して以下のようなサポートを行い、適正な等級認定の獲得を後押しします。
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 「後遺障害診断書」のチェックと助言 | 等級認定の要となる医師の診断書に、認定に必要な情報が法的な観点で正しく記載されているかを確認し、より有利な内容になるよう働きかける |
| 「異議申立て」による逆転の可能性 | 逆転の可能性 認定された等級が不当に低い、または認定されなかった場合でも、専門知識を基に「異議申立て」を行い、より適切な等級の獲得を目指す |



専門家のサポートがあるかないかで、将来受け取れる金額が大きく変わることもあるため、非常に大切な手続きと言えるでしょう。
関連記事:弁護士に依頼すると交通事故の解決までの期間は早くなる?期間の目安・早くなる理由を解説
交通事故の慰謝料計算に関するよくある質問
交通事故の慰謝料は自賠責と任意保険の両方からもらえますか?
慰謝料を二重に受け取ることはできません。
慰謝料は事故で受けた精神的苦痛という「一つの損害」に対する補償であり、一つの損害に対して複数の場所から補償を受けることはできないためです。
通常、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社が自賠責保険の分もまとめて、賠償金全額を被害者に支払います(一括払い制度)。
交通事故の通院日数はどうやって数えればいいですか?
通院日数の考え方は、慰謝料を計算する「基準」によって大きく異なります。
主な2つの基準の違いを、以下の表で比べてみましょう。
| 項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 計算の基礎 | 日数 | 期間 |
| 具体的な計算方法 | 「治療期間」と「実通院日数×2」を比べ、少ない方の日数を基に計算する | 治療期間(例:6ヶ月)を、過去の裁判例に基づいた算定表に当てはめて計算する |
| 通院頻度の影響 | 通院日数がそのまま計算に直結する | 期間がベースだが、通院頻度が極端に少ない(月1回など)と減額される可能性がある |
自賠責基準では単純な日数が機械的に計算されるのに対し、弁護士基準では治療期間に加えて「通院の密度(頻度)」も考慮されるという違いがあります。
交通事故で接骨院に通った場合慰謝料の計算方法は変わりますか?
接骨院に通っていても、慰謝料の計算方法は病院(整形外科)に通った場合と基本的には変わりません。
ただし、接骨院での施術費や通院を慰謝料の対象として保険会社に認めてもらうには、原則として医師の許可や指示が必要である点は注意が必要です。
接骨院に通いたい場合は、必ず主治医に相談し、許可や指示を得てからにするようにしましょう。
まとめ|交通事故の慰謝料の計算に悩んだら弁護士に相談しよう
交通事故の慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対する正当な賠償であり、民法で保障された権利です。
慰謝料の計算には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、弁護士基準が最も高額かつ法的に正当な基準です。
加害者側の保険会社が最初に提示する金額は、本来受け取るべき弁護士基準の金額よりも大幅に低いケースが多いため、弁護士に依頼して正当な「弁護士基準」での慰謝料を請求することをおすすめします。
交通事故の示談交渉や賠償金に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて親身にサポートいたします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応