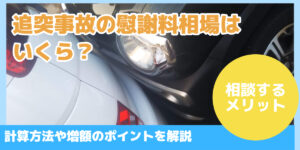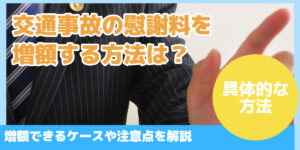もらい事故で慰謝料はいくらもらえる? 相場や計算方法、請求の流れを解説【弁護士監修】

「もらい事故で慰謝料はもらえるの?」
「もらい事故の慰謝料はいくらぐらい請求できるのか知りたい」
交通事故に巻き込まれ、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
もらい事故とは、信号待ち中の追突やセンターラインオーバーによる衝突など、被害者に過失がない交通事故を指します。過失割合が10対0となるため、本来は被害者に落ち度はありません。
しかし、慰謝料の請求には条件や注意点があり、手続きを誤ると適正な金額を受け取れないおそれがあるのです。
本記事では、もらい事故の慰謝料について、請求できる条件・種類と計算基準・相場・請求の流れや時効・弁護士に依頼するメリットを弁護士監修のもとで解説します。
もらい事故で泣き寝入りしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。
もらい事故での慰謝料請求をお考えの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
これまで扱った交通事故に関する相談実績は1,200件以上で、後遺障害認定のサポートも可能です。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
\ 相談実績1,200件以上/
【無料相談受付中】365日対応
もらい事故とは?「過失割合が10対0」となる交通事故
もらい事故とは、被害者に一切の落ち度がない交通事故を指します。法律上は「過失割合が10対0」と整理されるケースであり、典型例はいくつか存在します。
また、もらい事故には被害者側の保険会社が示談交渉を代行できないといった特徴もあり、一般的な事故とは対応の仕方が異なります。
詳しく見ていきましょう。
過失割合が10対0になる事故の例
もらい事故に該当するのは、被害者側に一切の過失がないケースです。もらい事故の典型的には次のようなものが挙げられます。
- 赤信号で停車中に後方から追突された
- センターラインをオーバーした対向車と正面衝突した
- 駐車場に停めていた車に相手の車がぶつかってきた
これらはいずれも、被害者に一切の過失がなく、10対0と認められやすい事故です。事故の状況や証拠の有無によっては、過失割合の修正を巡って争いになることがあります。
実際には、もらい事故と考えられるケースでも、保険会社が「被害者にもわずかな過失がある」と主張してくることがあるのです。
たとえば、停車中でもブレーキランプが点灯していなかった場合や、道路上の位置取りによっては過失割合が修正される可能性があります。
そのため「必ず10対0になる」とは限らず、事故状況や証拠の有無によって判断が分かれる点には注意が必要です。
関連記事:右直事故の過失割合10対0は可能?被害者が有利な場合が認められるケースを紹介
関連記事:過失割合10対0事故の示談金相場と増額交渉の注意点を解説
【注意点】もらい事故の被害者側は保険会社に示談交渉を代行してもらえない
通常の交通事故であれば、自分が加入している自動車保険に示談代行サービスが付いていることが多く、被害者側の保険会社が加害者側と交渉を進めてくれます。
しかし、もらい事故の場合は事情が異なります。被害者に過失がないため、被害者側の保険会社は賠償金を支払う義務がありません。そのため、弁護士法第72条の規定により、被害者側の保険会社が示談交渉を代行することはできないのです。
結果として、被害者本人が加害者側の保険会社と直接交渉しなければなりません。しかし、相手方保険会社の担当者は交渉経験も知識も豊富であるため、個人で対等にやり取りするのは極めて困難です。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫適切な準備や弁護士のサポートなしに交渉を進めると、不利な条件で示談をまとめられてしまう危険性があります。
もらい事故に遭ったら慰謝料は請求できる?
もらい事故でも、必ず慰謝料が認められるわけではありません。
請求できるケースとできないケースがあり、その判断は事故の内容や被害の状況によって変わります。
具体的な条件やケースごとの違いを確認していきましょう。
関連記事:交通事故の慰謝料とは?計算方法や慰謝料相場・注意点を弁護士が徹底解説
慰謝料を請求できる条件
もらい事故でも、慰謝料の対象になるのは人身被害がある場合が原則です。
慰謝料は、傷害や後遺症・死亡に伴う精神的苦痛への補償として認められます。物損事故のみである場合であっても自宅が破損した場合や、ペットが怪我をして死亡した場合など特殊な状況でなければ慰謝料請求はできません。
車の修理費や代車費用などの物損は別途賠償の対象になりますが、それだけでは慰謝料を受け取ることはできません。慰謝料を請求するには、怪我をしていること、そしてその事実を証明する診断書や人身事故の届出が必要です。
交通事故の現場では「たいしたことはない」と思える軽い痛みでも、後から症状が悪化することがあります。少しでも不調を感じたら必ず受診しておきましょう。
なお、整骨院や接骨院のみの通院では、保険会社から「医学的根拠が不十分」とされ、慰謝料が大きく減額されることがあります。
慰謝料を適正に受け取るためには、必ず一度は整形外科などの医師に診断を受けて診断書を取得し、事故を「人身事故」として警察に届け出ておくことが大切です。
もらい事故で請求できる慰謝料の種類
慰謝料とひと口にいっても、その内容は被害の状況によって異なります。もらい事故で請求できる慰謝料は、以下の3種類に分けられます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故によってケガを負い、治療や通院・入院を余儀なくされたことによる精神的苦痛を補うための慰謝料です。
事故によって日常生活や仕事に支障が出たり、治療のために時間や労力を割かざるを得なくなったりすること自体が負担であり、その損害を金銭で補うものです。
かすり傷や打撲といった比較的軽いケガでも、通院すれば対象となります。「症状の重さ」ではなく、治療を受けなければならない状況そのものが精神的苦痛とみなされるのがポイントです。
また、慰謝料の算定においては「通院期間」に加え、「通院の頻度」も影響します。たとえば、弁護士基準では治療期間をベースに算定されますが、実際の通院回数が極端に少ない場合には「治療の必要性が低かった」と判断され、減額される可能性があります。
そのため、症状がある限りは医師の指示に従って通院を続け、診療記録を積み重ねておくことが重要です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、治療を続けても完治せず、事故による後遺症が起こったことに対する精神的苦痛を補うための慰謝料です。後遺症があることで、生活の質が低下したり、仕事や趣味に制限が生じたりするなど、長期的な不利益を負うことになります。
そこで法的には、後遺症の内容や程度を後遺障害として評価し、その重篤度に応じた等級を設定して、等級に応じた慰謝料を支払う仕組みが設けられています。これは、被害者が事故前と同じ生活を送れなくなったことへの補償の意味合いが強い慰謝料です。
関連記事:後遺障害等級認定とは?手続きの流れ・適切な等級獲得のポイントを弁護士が解説
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が命を奪われた場合に、遺族が被った精神的苦痛を補うための慰謝料です。突然の事故により大切な家族を失った悲しみや喪失感は計り知れず、その苦痛に対して金銭で償うという考え方に基づいています。
この慰謝料は、被害者本人の痛みや苦しみではなく、遺族が受けた精神的損害に対する賠償である点が特徴です。遺族が請求権者となり、被害者の立場や家族関係によって慰謝料の扱いが変わる仕組みが採用されています。
怪我なし(物損のみ)で慰謝料は請求できる?
交通事故でケガをしていない場合は、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは基本的に認められません。
この場合に補償されるのは、以下のような「物的損害」に限られます。
- 車やバイクの修理費
- 評価損(事故歴による車両価値の下落)
- 代車費用 など
「お詫び金」や「迷惑料」といった名目で慰謝料を請求することは、判例上も認められていません。物損事故のみの場合、精神的苦痛に対する慰謝料は原則として認められていないのです。
もっとも、交通事故でペットが死んでしまった場合には、家族同然であることも考えると精神的苦痛は発生しえます。また、自宅が破損した場合、程度によっては損壊したまま居住しなければならず、同様に精神的苦痛は発生するでしょう。
このように特別な事情がある場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、事故直後は怪我をした自覚がなくても、後になって体に痛みやしびれなどが現れることがあります。その場合は、速やかに病院で診察を受けて診断書を取得し、事故を「人身事故」として警察に切り替えて届け出なければなりません。
これを怠ると、後から慰謝料請求する際に「事故との因果関係が不明」とされ、適切な補償が受けられないおそれがあります。



慰謝料の可否は「人身被害があるかどうか」で変わります。自己判断せず、まずは受診と診断書の取得を徹底しておくことが適切な補償につながります。
もらい事故の慰謝料を計算する3つの基準
もらい事故で慰謝料を計算するときには、以下の3種類の基準が使われます。
どの基準を採用するかによって、最終的に受け取れる金額には差が生じます。
ここからは、それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
関連記事:交通事故の慰謝料はどうやって計算する?弁護士基準の相場と通院期間ごとの早見表【弁護士監修】
自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づき国が定めた最低限の補償基準です。
全国で一律に適用されているため、どの保険会社でも算定方法は同じになっています。これは、計算方法を単純化し、被害者を迅速に救済することを目的としているためです。
自賠責基準はあくまで「最低限の補償」を目的とした基準です。
そのため、重傷事故や死亡事故では、実際の損害や精神的苦痛を十分にカバーできないケースが多く、実務上は自賠責基準を出発点とし、任意保険基準や弁護士基準での上積みが検討されます。
任意保険基準
任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している慰謝料算定基準です。詳細は非公開なものの、一般的には自賠責基準をわずかに上回る程度の金額にとどまります。
実際に被害者が加害者側の保険会社から最初に提示される金額は、この任意保険基準をもとに計算されたものです。したがって、提示額をそのまま受け入れると、弁護士基準と比べて大幅に低額で示談が成立してしまうおそれがあります。
保険会社側は自社の支払額を抑える立場にあるため、被害者が適正な補償を受けるためには慎重な判断が必要です。
弁護士基準
弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例を集積した「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」などを根拠とした、裁判所が用いる算定基準です。3つの基準のなかで最も高額であり、かつ法的な正当性も高い基準とされています。
弁護士基準は、被害者自身が保険会社と交渉するだけでは認められず、弁護士が交渉や訴訟に介入することによって初めて主張可能となります。
実務上も、自賠責基準と比べて2倍から3倍以上の金額となるケースが多く、被害者が適正な補償を得るために弁護士基準での請求を行う意義は大きいといえます。



基準によって慰謝料の金額は数倍の差が出ます。提示額を鵜呑みにせず、「どの基準で計算されているのか」を意識するだけでも、交渉の見え方が変わってきます。
関連記事:【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説
【ケース別】もらい事故の慰謝料相場
もらい事故の慰謝料は、ケガの内容や事故後の状況によって変わります。同じ事故でも、軽傷か重傷か、後遺障害が残るかどうかによって請求できる慰謝料は全く異なるのです。
ここでは、以下のケースごとに金額の目安を整理していきましょう。
関連記事:追突事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や増額のポイントを弁護士が解説
むちうち・軽傷の慰謝料相場
交通事故でもっとも多いのが、いわゆる「むちうち」や軽傷のケースです。
通院期間は数週間から3か月程度となることが多く、慰謝料の目安は数十万円規模にとどまります。ただし、どの基準で計算するかによって金額が変わるため注意が必要です。
各基準の慰謝料相場は以下のとおりです。(月10回程度通院を3か月・むちうちの場合の目安)
| 基準 | 慰謝料の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 25.8万円 | 最低限の補償にとどまり、実際の負担感と比べて不足しやすい |
| 弁護士基準 | 53万円 | 裁判所の基準に基づき、最も高額。 交渉次第で倍以上になるケースも多い |
※自賠責基準は日額4,300円×通院日数×2より算出
※金額はあくまでも目安であり、実際には通院日数や治療内容によって変動します。
慰謝料額に影響を与えるポイントは、通院日数とその必要性です。医師の指示に従って定期的に通院していれば、相場に沿った金額が認められやすくなります。
一方、受診間隔が空くと「治療の必要性が低い」と判断され、減額されるおそれもあります。
関連記事:交通事故のむちうちで慰謝料はいくらもらえる?相場や計算例を弁護士が解説
関連記事:追突事故でむちうちになったら?事故後の対応や慰謝料請求で損しない方法を弁護士が解説
骨折・重傷の慰謝料相場
骨折や重度の外傷を伴う事故では、入院や長期の通院を余儀なくされることも多く、慰謝料の金額は数百万円規模に達することもあります。手術を受けた場合や後遺症が残る場合には、さらに増額される傾向にあります。
各基準の慰謝料相場を以下にまとめました。(入院1か月+月10回程度の通院を3か月・骨折場合の目安)
| 基準 | 慰謝料の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 51.6万円 | 最低限の補償にとどまり、入院・手術費用を十分にカバーできないケースが多い |
| 弁護士基準 | 115万円 | 裁判例に基づき、実際の通院・入院日数を反映した適正額に近づく |
※自賠責基準は日額4,300円×(入院日数+通院日数)×2より算出
※相場は一例であり、実際には治療期間・症状の程度・労働への影響などにより変動します。
重傷事案では、慰謝料額が生活再建に直結するため、どの基準で計算されるかが重要です。適正額を得るには、弁護士基準を用いた交渉が不可欠といえるでしょう。
関連記事:交通事故で骨折した場合の慰謝料はいくら?相場や計算方法・手続き方法を弁護士が解説
後遺障害慰謝料の相場
交通事故でケガが治りきらず、後遺症が残ってしまった場合には「後遺障害慰謝料」を請求できます。この金額は、後遺障害等級(1級〜14級)によって厳格に区分されており、相場に幅があります。
後遺障害慰謝料の目安は以下のとおりです。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | 代表的な状態の例 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1,150万 (要介護の場合は1,650万) | 2,800万円 | 両目が失明したりや両腕をひじ関節以上で失った場合など |
| 3級 | 861万 | 1,990万円 | 咀嚼又は話すことができなくなった・両手の手指を |
| 7級 | 419万 | 1,000万円 | 外貌に著しい醜状を遺す |
| 14級 | 32万 | 110万円 | しびれ神経症状が残る場合など |
※あくまでも目安です。弁護士基準の詳細は「損害賠償額算定基準」に基づき、症状・立証資料に応じて調整されます。
後遺障害慰謝料は、等級認定の有無で賠償総額に差が出るのが特徴です。診断書や検査データの提出が不十分だと等級が認定されないこともあるため、医師の協力を得ながら的確に証拠を残すことが重要です。
なお、認定が見送られた場合でも、その結果に納得できなければ「異議申立て」によって再審査を求められます。
追加の資料や医師の意見書を添えることで、再度の認定につながるケースもあるため、あきらめずに対応するようにしましょう。
関連記事:後遺障害等級とは?等級一覧表から申請方法、慰謝料の相場まで弁護士が徹底解説
死亡慰謝料の相場
交通事故で被害者が死亡した場合、遺族は死亡慰謝料を請求できます。死亡慰謝料は自賠責基準と弁護士基準で考え方や金額が異なるのが特徴です。
自賠責基準は全国一律で最低限の補償を目的としており、加算方式で金額が決まります。
一方で弁護士基準は、被害者の立場や家庭内での役割を重視して金額を算定します。
また、死亡慰謝料の請求権は被害者本人に発生するものですが、その権利は相続人に承継されます。
したがって、死亡慰謝料を請求できるのは遺族のうち法定相続人にあたる人であり、複数の相続人がいる場合は、その相続分に応じて分配される仕組みです。
自賠責基準では、以下の要素を合算して金額を算出します。
| 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 本人分 | 400万円 | 被害者本人の精神的苦痛に対する補償 (遺族が相続して請求) |
| 遺族分 | 1人=550万円 2人=650万円 3人以上=750万円 | 請求権者の人数によって加算 |
| 被扶養者加算 | +200万円 | 被扶養者がいた場合に加算される |
一方、弁護士基準では、被害者の立場によって金額が変わります。
| 被害者の立場 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 約2,800万円 |
| 配偶者・子 | 約2,500万円 |
| その他(独身者・高齢者など) | 約2,000万円前後 |
自賠責基準と比べると、弁護士基準では2倍以上の差が出ることも珍しくありません。
死亡慰謝料は、遺族の生活再建や精神的救済に直結する重要な賠償項目です。適正な金額を受け取るためには、弁護士基準での算定を前提に交渉を進めることをおすすめします。
慰謝料は「症状の程度」と「どの基準を使うか」で相場が決まります。表に示される金額はあくまで目安であり、個別事情に応じて増減がある点には注意が必要です。
関連記事:交通事故で死亡した場合の慰謝料は? 子どもや高齢者の死亡事故とその慰謝料相場について
通院日数・通院頻度が慰謝料に与える影響
慰謝料の算定においては、どのくらいの頻度で通院したかも重要な判断材料となります。
一般的には、慰謝料額は「実際に通院した日数」と「治療期間(日数)」の双方を基に計算されます。とくに自賠責基準では、実通院日数×2という計算方式が採用されるため、通院の回数が少ないと金額が減額される可能性があります。
また、通院の間隔が長く空いてしまうと「治療の必要性が低い」と判断され、保険会社から減額交渉を受けやすくなります。



事故後は「痛みが軽くなったから」と自己判断で通院を中断するのではなく、医師の指示どおりに通院を続け、診療記録を残すことが重要です。
もらい事故の慰謝料以外にも請求できる損害賠償
もらい事故で受け取れるお金は、慰謝料だけではありません。治療にかかった金額や休業による減収、壊れた車の修理費など、さまざまな損害が賠償の対象となります。
ここでは、慰謝料以外に請求できる代表的な損害項目を整理し、どのような費用が補償されるのかを解説します。
【ケガに関する損害】治療費・休業損害・逸失利益など
交通事故の被害者は、慰謝料だけでなく実際に支払った医療費や事故による減収分なども損害として請求できます。代表的な項目は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 治療関係費 | ケガの治療に必要となった費用 | 診察費、手術費、投薬費、入院費、通院交通費など |
| 休業損害 | 事故によって仕事を休んだことで失った収入 | 会社員の減収、自営業・フリーランスの売上減、専業主婦(主夫)の家事労働の喪失など |
| 逸失利益 | 後遺障害や死亡によって将来得られるはずだった収入 | 労働能力の低下や喪失による生涯収入の減少分 |
補償を受けるためには、治療関係費であれば領収書を残すこと、休業損害であれば勤務先の証明や収入資料を提出することが欠かせません。
さらに、逸失利益は後遺障害等級の認定に依存するため、診断書や検査データを整えておくことが重要です。
【物に関する損害】修理費・代車費用・評価損など
もらい事故ではケガに関する補償だけでなく、壊れた車やバイクといった「物的損害」についても賠償を請求できます。代表的な項目は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 車両修理費 | 壊れた自動車やバイク、自転車などの修理に要する費用 | バンパー修理、ドア交換、部品代など |
| 買替差額 | 修理不能(全損)の場合に必要となる買い替え費用 | 廃車になった車の買い替え費用など |
| 代車使用料 | 修理や買い替えの期間中に代車を利用した場合の費用 | レンタカー代など |
| 評価損(格落ち損害) | 修理後も事故歴がついたことによる車両価値の下落 | 中古車市場での査定額低下など |
特に評価損は、事故車扱いになることで市場価値が下がる点が特徴です。
将来的な資産価値を守るためにも、評価損は重要な請求対象といえます。
また、物的損害を請求する際には、修理見積書や領収書、査定書などの客観的資料が必要です。これらを揃えておくと、保険会社との交渉もスムーズに進めやすくなるでしょう。



評価損や代車費用は、相手の保険会社と意見が対立しやすい項目です。金額に納得できないときは、弁護士へ相談すると良いでしょう。
もらい事故の慰謝料を請求するまでの流れ【4ステップ】
もらい事故で慰謝料を請求するには、事故直後から解決に至るまで、一定の手順を踏むことが大切です。
初期対応を怠ったり、交渉の流れを誤ったりすると、本来受け取れるはずの慰謝料が減額される、あるいは請求自体が認められないおそれがあります。
ここでは、慰謝料請求の一般的な流れを4つのステップに分けて解説します。
もらい事故の直後に警察へ通報し、証拠を確保する
もらい事故に遭った場合、最初にすべきことは警察への通報です。
交通事故は警察に届け出る義務があり、慰謝料を請求するためには人身事故として扱ってもらう必要があります。
物損事故のままでは精神的苦痛に対する賠償を求められなくなるおそれがあるためです。
あわせて、事故現場での証拠収集も欠かせません。ドライブレコーダーの映像とともに、スマートフォンで事故直後の現場写真を撮影し、車両の破損状況や道路環境を記録しておきましょう。
さらに、第三者の目撃証言は後の交渉で強い裏付けになるため、事故の目撃者がいれば連絡先を控えておくことをおすすめします。
こうした証拠は、加害者側や保険会社と交渉する際に発生しがちな「言った・言わない」の争いを防ぎ、適正な慰謝料を獲得するための武器となります。
通院して診察記録を残す
事故後は自覚症状が軽くても、できるだけ早く病院を受診することが大切です。
交通事故直後は興奮状態で痛みに気づきにくく、数日経ってからむちうちや頭痛、しびれなどを自覚するケースも少なくありません。
軽い違和感でも医師に診てもらえば、診察記録が残り、人身事故として扱ってもらいやすくなります。診断書は慰謝料請求の根拠となる重要な資料となるでしょう。
その後も定期的に通院を続けることが必要です。治療を途中でやめたり、通院間隔が長く空いたりすると「症状が軽かった」と判断され、慰謝料の減額につながるおそれがあります。医師の指導を受けながら記録を積み重ねていくことが、適正な慰謝料額の取得につながるのです。
加害者側の保険会社と示談交渉をする
治療が一段落し、症状固定または通院が終了したら、加害者側の保険会社との示談交渉に進みます。
ここで提示される金額は、多くの場合任意保険基準に基づいたものであり、実際には適正額よりも低く算定されているケースがほとんどです。
そのため、加害者側に言われるままを受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料よりも大幅に少ない金額で合意してしまう可能性があります。
納得できない場合は、提示内容を精査し、症状や通院実績と照らし合わせて判断することが必要です。ただし、被害者本人だけで交渉を進めるのは難しく、経験豊富な保険会社の担当者に押し切られてしまうリスクもあります。
交渉がまとまらない場合には調停や訴訟に進む
示談で合意に至らない場合は、裁判所での解決手続きを利用します。
選択肢としては民事調停と訴訟がありますが、まずは費用や時間の負担が軽い調停を申し立てるのが一般的です。調停委員が間に入ることで冷静に意見を整理しやすく、支払い方法や条件面も含めて合意を目指せるでしょう。
調停でも合意が得られない場合には、訴訟に進みます。
訴訟は、請求額に応じて簡易裁判所(140万円以下)または地方裁判所(140万円超)が管轄し、過去の裁判例に基づく弁護士基準を用いて慰謝料額を算定するものです。(参照:裁判所|裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A|調停が成立しなかった場合のその後の手続はどうすればいいですか?)
訴訟に至ると、示談よりも高額な賠償が認められる可能性が高くなります。
時効請求の基本ルール
交通事故の慰謝料請求には消滅時効があり、一定期間を過ぎると慰謝料を請求する権利が消えてしまいます。
時効の考え方には以下の2つあり、どちらか早い方で権利が消滅します。
- 損害や加害者を知った日から数える期間(知った時からのカウント)
- 事故そのものが起きた日から数える期間(事故日からのカウント)
時効は、被害者に早期の請求を促しつつ、長期間いつまでも紛争が続かないようにするために設けられている仕組みです。
交通事故での請求時効を下表にまとめました。
| 請求の対象 | 損害や加害者を知った時から数える期間 | 事故が起きた日から数える期間 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 身体にケガがある場合(民法724条の2) | 5年 | 20年 | 後遺障害がある場合は「症状固定」からカウントされることが多い |
| 物損のみの場合 (民法724条) | 3年 | 20年 | 車や物の修理費などが対象 |
とくに身体のケガに関する請求は、通院の有無や後遺障害の認定などによって「いつからカウントが始まるのか」が変わる点に注意が必要です。
時効が迫っている場合でも、内容証明郵便で請求の意思を相手に伝えたり、訴訟や調停を起こしたりすることで、時効を完成猶予することができます。
「あと数日で時効かもしれない」と不安に思ったら、まずは弁護士に相談すると、権利を失わずに済むかもしれません。



事故直後からの対応が、その後の請求額を左右します。ステップごとに確実に進めることが、適正な賠償を受ける近道です。
もらい事故で慰謝料を請求するときの注意点
慰謝料を請求する際には、相手の言い分に飲まれず、権利を守る意識を持つことが大切です。
ここからは、もらい事故で慰謝料を請求する際にとくに注意すべきポイントを解説します。
保険会社提示額をそのまま受け入れない
もらい事故の場合、被害者には過失がないため「提示額は正しいはず」と思い込んでしまいがちです。しかし、保険会社は自社に有利な基準で算定するため、最低限の金額しか提示してこないことが多いのが実情です。
特に慰謝料や休業補償は、弁護士基準と比べると2倍以上の差が出るケースも珍しくありません。一度示談に応じてしまうと、後から症状が悪化しても追加請求は原則できません。
金額が適正かどうかは専門的な判断が必要なため、提示額を鵜呑みにせず、必ず算定根拠や使用基準を確認し、不明点があれば弁護士に相談することが重要です。
診断書・通院記録など証拠を必ず残す
もらい事故では被害者に過失がない分、保険会社は「本当に事故によるケガかどうか」を厳しく確認します。特にむちうちは画像検査で異常が出にくいため、診断書の記載内容や通院頻度、治療の一貫性が補償の根拠となります。
領収書、通院日ごとの診療明細、交通費のICカード履歴、自家用車なら走行距離やガソリン代の記録など、細かな資料もケガがあった証拠です。これらが揃っていないと、後に「申告されている症状は事故との因果関係が薄い」と判断され、治療費や慰謝料を否認されかねません。
特に後遺障害等級を申請する場合には、初診からの一貫した通院記録が重要です。
示談書に署名する前に専門家に確認する
示談は「一度署名すると原則、追加請求や撤回のできない契約」であり、将来の補償まで含めて最終的に確定するものです。示談書に署名する前には、専門家に文言や条件の確認を依頼すると良いでしょう。
とくに慰謝料の金額や休業損害の計算方法、将来の後遺症に備えた補償が含まれているかどうかは、専門的な知識がないと判断が難しい部分です。弁護士に確認してもらえば、不利な条件や見落としを回避できるだけでなく、必要があれば相手方に修正交渉をしてもらうことも可能でしょう。
自分では気づけない法的リスクを事前に排除できるのは大きなメリットです。安心して署名するためにも、示談書は弁護士の確認後に署名することをおすすめします。
もらい事故の慰謝料請求は、証拠の有無や示談条件次第で結果は大きく変わります。



安易に署名せず、弁護士のチェックを受けることで、適正な補償を確実に守れるでしょう。
もらい事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
もらい事故では、加害者側の保険会社と直接交渉しなければならず、提示額も低く抑えられがちです。こうした場面では、弁護士に依頼することで、適正な基準での請求や手続きのサポートを受けられます。
ここでは、その具体的なメリットを見ていきましょう。
関連記事:交通事故に強い弁護士の選び方!後悔しないポイントや相談の流れを現役弁護士が解説
弁護士基準で慰謝料を増額できる
弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料の算定に弁護士基準が使える点です。保険会社が提示する任意保険基準は、自賠責基準に少し上乗せした程度の水準であることが多く、被害者が本来受け取れる金額よりも低く抑えられています。
これに対し、弁護士基準は裁判例に基づいた客観的で正当な基準であり、金額が自賠責基準の2倍以上に増額されるケースも珍しくありません。とくに長期通院や後遺障害が残った場合には、数百万円~数千万単位で差が出ることもあります。
弁護士が交渉に入ることで、被害者に不利な条件を改められるため、適正額での示談成立につながる可能性が高まります。なお、こうしたサポートを受けるには示談が成立する前に相談することが不可欠です。早めに動くほど適正な慰謝料の獲得につながりやすいため、事故直後の段階から相談しても、問題ありません。
後遺障害等級認定のサポートを受けられる
後遺障害等級の認定は、慰謝料や逸失利益の金額に直結する重要な手続きです。しかし、診断書の内容や医師の所見が不十分だと、適切な等級が認定されず、賠償額が下がってしまうおそれがあります。
弁護士は、必要に応じて医師へ追加の意見書を依頼したり、症状の具体的な影響を立証する資料を整えたりと、申請の準備を全面的にサポートします。
適正な等級を獲得できれば、慰謝料や逸失利益が大幅に増額される可能性があるのです。複雑で専門的な後遺障害等級の認定手続きを弁護士が伴走してくれる点は、被害者にとって大きな安心材料となります。
保険会社や加害者との交渉を任せられる
もらい事故では、自分の保険会社が示談交渉を代行できないため、被害者自身が加害者や保険会社と直接交渉する必要があります。
しかし、保険会社の担当者は交渉のプロであり、専門的な知識も経験も豊富です。被害者が個人で対等に渡り合うのは難しく、強いストレスや心理的負担を感じてしまうかもしれません。
弁護士に依頼すれば、加害者側とのやり取りや資料提出などの煩雑な手続きをすべて任せられるため、被害者は治療や日常生活の回復に専念できます。
また、弁護士があなたの代わりに交渉に必要な専門知識を駆使することで、示談を有利に進められるようになるでしょう。



もらい事故では、過失がないにもかかわらず被害者が不利な立場に置かれることが少なくありません。納得のいく解決のためには、早い段階から専門家に相談することが大切です。
もらい事故での慰謝料請求に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせたサポートをご提案いたします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
\ 相談実績1,200件以上/
【無料相談受付中】365日対応
弁護士費用特約を使えば費用負担なしで弁護士に依頼できる
もらい事故の被害者からは、「過失がないのに弁護士費用まで負担するのはおかしい」という声が聞かれることもあります。そのような不公平感を解消できるのが、保険に付帯している弁護士費用特約です。
弁護士費用特約を利用すれば、原則として自己負担なく弁護士に依頼が可能です。
ここからは、弁護士費用特約の仕組みや補償範囲について見ていきましょう。
費用負担なしで弁護士依頼ができる仕組み
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士への相談料・着手金・報酬金を保険会社が負担するため、原則として自己負担はありません。
これは、「もらい事故なのに、弁護士費用まで被害者が負担するのは不合理だ」という声に応える制度でもあります。費用の心配がなくなれば、保険会社との交渉や後遺障害等級認定のサポートといった専門的な業務を弁護士に任せられるでしょう。
弁護士費用特約を利用した結果、補償額が数十万〜数百万円規模で変わることも珍しくありません。
金銭面の不安が大幅に軽減されることで精神的にも余裕を持てるため、治療や生活再建に集中できるのが大きな利点です。
自動車保険や家族の契約に付帯している場合もある
弁護士費用特約は、自動車保険に付帯していることが多い補償です。
多くの場合、補償範囲は契約者だけに限らず、同居している家族の契約や、別居している未婚の子どもの契約に付帯している特約でも利用できる場合があります。
事故後は慌ただしくなるため、弁護士費用特約の有無を誤りやすいものです。早めに保険証券をチェックし、どの契約で特約を利用できるのかを把握しておくと、適正な補償の請求ができるようになるでしょう。
一般的な補償上限は300万円前後
弁護士費用特約の補償上限は、一般的に300万円程度に設定されています。
この金額は多くの交通事故案件をカバーするのに十分であり、弁護士が示談交渉から裁判対応まで担ってもほとんどのケースで上限を超えずに対応可能です。
さらに、特約を利用しても翌年以降の保険料が上がったり、等級が下がったりといった不利益が被害者に及ぶことは基本的にありません。
実際、特約を利用して弁護士に依頼することで、保険会社提示額の数倍の賠償金を得られた例も数多く存在します。
補償を最大限に受けるためには、特約の有無を確認し、積極的に活用することをおすすめします。



弁護士費用特約に加入しているかどうかは保険証券で簡単に確認できるので、事故に備えてチェックしておくと良いでしょう。
関連記事:交通事故の弁護士費用はいくらかかる?弁護士費用特約や費用倒れしないコツも紹介【弁護士監修】
もらい事故の慰謝料に関するよくある質問
もらい事故で「慰謝料」と「示談金」はどう違うのですか?
「慰謝料」と「示談金」は混同されやすい用語ですが、意味が異なります。主な違いは以下のとおりです。
| 慰謝料 | 交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金 |
|---|---|
| 示談金 | 慰謝料に加えて治療費・通院交通費・休業損害・物損など、事故によって発生した損害をすべて含めた和解金の総額 |
つまり、慰謝料は示談金の一部という位置づけです。
両者の違いを混同していると、交渉の場で金額の内訳を誤解してしまうおそれがあります。
あらかじめ区別を理解しておけば、示談金の内容を正しく判断でき、納得感を持って交渉を進められるでしょう。
もらい事故でも慰謝料がもらえないケースはありますか?
もらい事故だとしても、すべてのケースで慰謝料が受け取れるわけではありません。
以下のような場合には、慰謝料が認められない可能性があります。
- ケガがない場合:物損事故のみでは慰謝料の対象外
- 診断書がない場合:医師の診断がなく、ケガを証明できない
- 因果関係が不明確な場合:事故と症状の関係を裏付ける証拠が不足している
慰謝料を請求するには、少なくとも医師の診察を受けて診断書を取得し、事故によるケガであることを明確にしておく必要があります。
精神的苦痛だけで慰謝料請求はできますか?
もらい事故に遭って「ショックでつらい」「精神的に落ち込んだ」という理由だけでは、慰謝料が認められるのは難しいのが実情です。
慰謝料請求には医師の診断書や通院記録といった客観的な証拠が必要であり、裏付けがなければ認められません。
ただし、交通事故によってPTSDやうつ症状などの精神的疾患を発症した場合には、医師の診断を受けることで慰謝料請求の対象となる場合があります。
精神的苦痛だけを理由にするのではなく、必ず医療機関を受診し、事故と精神的苦痛の因果関係を示す証拠を残すことが大切です。
慰謝料請求の通知はいつ届きますか?
慰謝料の支払いに関する通知は早ければ事故から数週間で届きますが、数か月後になることもあります。
これは、治療が続いている間は損害額が確定せず、示談交渉を始められないことによります。治療が続いている間は慰謝料も確定しません。
通常は、治療が終了して損害額が算定できた段階で通知が送られてきます。
ただし、弁護士が代理人として入っている場合には、交渉準備の整ったタイミングで早めに通知が届くこともあるでしょう。
通知が来ないからといって放置すると、時効が進んで権利を失ったり、交渉の主導権を相手に握られたりするおそれがあります。



必要に応じて自分から状況を確認し、早めに行動することが大切です。
まとめ|もらい事故の慰謝料請求は早めの行動と弁護士相談がカギ
もらい事故の慰謝料は、怪我を負った場合に請求できるのが原則です。金額は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準といった算定方法の違いによって変わります。
さらに、請求を適切に進めるためには、事故直後から証拠を確保し、医師の診断を受けて記録を残すことが不可欠です。示談交渉や調停・訴訟に発展する可能性もあるため、請求の流れを把握しておくことが重要になります。
もらい事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すると、弁護士基準による適正な慰謝料を得やすくなり、交渉のストレスや不利な和解を避けられるでしょう。



早めの行動と弁護士相談こそが、もらい事故で泣き寝入りしないための最大のポイントです。
もらい事故での慰謝料請求に不安を感じる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
これまで扱った交通事故に関する相談実績は1,200件以上で、後遺障害認定のサポートも可能です。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
\ 相談実績1,200件以上/
【無料相談受付中】365日対応