交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払い時期や流れ・早く受け取る方法を弁護士が解説
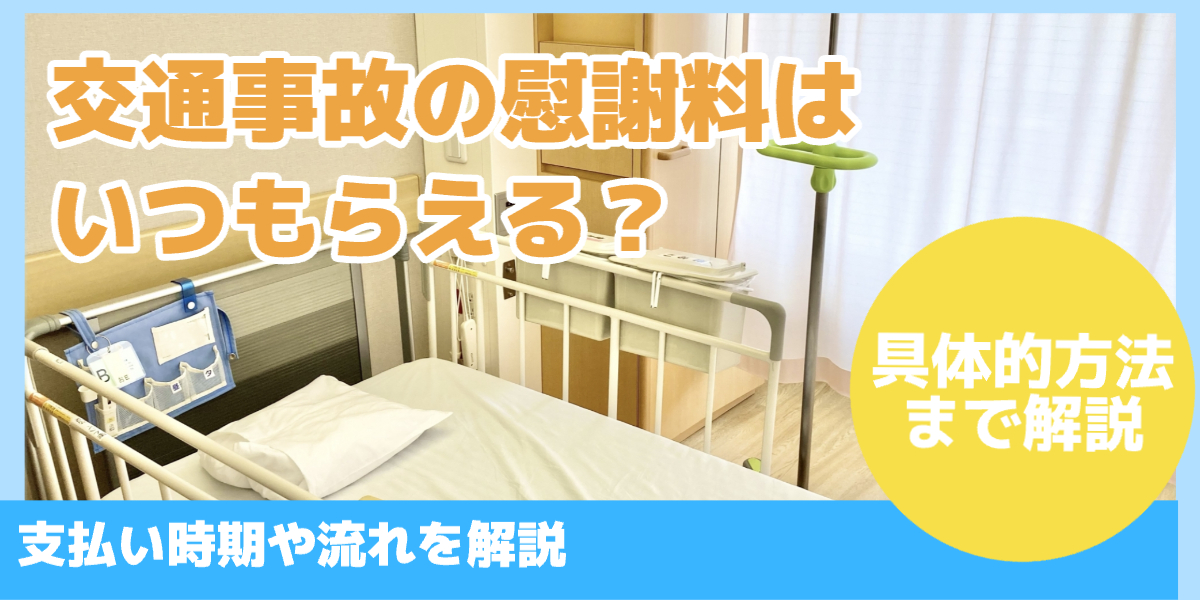
「事故の慰謝料はいつになったらもらえる?」
「保険会社とのやり取りが始まったけど、どれくらい時間がかかる?」
事故後の手続きは複雑です。特に「慰謝料がいつ支払われるのか」という点は、気になる人もいるのではないでしょうか。
本記事では、交通事故の慰謝料が支払われるまでの具体的な時期、事故発生から受け取りまでの全体的な流れを解説します。
また、支払いが遅れるケースへの対処法から、示談成立前に資金を受け取るための具体的な方法まで、専門家の視点から徹底的に解説します。
交通事故の慰謝料で不安を感じる方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が個々のケースに寄り添い、適切な解決方法をアドバイスします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の慰謝料はいつもらえる?
交通事故の慰謝料は、原則として加害者側の保険会社との「示談」が成立した後に支払われます。
「示談」とは、事故の損害賠償について加害者側と話し合い、合意に達する手続きのことです。書面で交わす「示談書」は、合意内容を正式に記録する重要な書類です。
加害者側の保険会社と賠償金額について合意して示談が成立すれば、示談書に署名・捺印して返送してから、1〜3週間程度で指定の銀行口座に振り込まれるのが一般的です。
示談成立から振込までの流れは、以下のようになります。
- 示談内容の合意
電話などで加害者側の保険会社担当者と賠償金額について最終的な合意をします - 示談書の送付
保険会社が示談書を作成し、被害者のもとへ郵送します(約3日) - 示談書への署名・捺印と返送
届いた示談書の内容を最終確認し、問題がなければ署名・捺印して保険会社へ返送します(約3日) - 保険会社での手続きと振込
示談書が保険会社に到着後、社内での支払い手続きを経て、指定口座へ慰謝料が振り込まれます(約3〜7日)
ただ、示談がいつ成立するかによって、慰謝料を受け取れる時期が大きく変わるのが特徴です。
慰謝料の支払い時期は、事故による被害の状況によって主に3つのケースに分かれます。
それぞれのケースで、事故発生から慰謝料受け取りまでの期間の目安は異なります。次の項目から、各ケースの具体的な支払い時期について詳しく見ていきましょう。
関連記事:交通事故の示談期間はどれくらい?ケース別の目安期間や長引く原因・短縮方法を解説
【完治した場合】治療終了から支払いまでの期間
交通事故による怪我が完治した場合、示談交渉はすべての治療が終了した時点から開始されます。治療費や入通院慰謝料などの損害の総額は、治療を終えなければ確定しないためです。
事故発生から慰謝料支払いまでの期間の内訳は、以下のようになります。
- 治療期間
怪我の程度によりますが、「むちうち」であれば3〜6か月程度が目安です - 示談交渉期間
治療終了後、損害額を算出し交渉を開始してから示談成立まで、通常2〜3か月程度かかります - 支払い期間
示談成立後、1〜3週間で振り込まれます
たとえば、むちうちで3か月間通院治療を行った場合、「治療期間3か月+示談交渉期間2〜3か月+支払い期間約2週間」となります。
ただし、骨折や手術が必要な重傷の場合は、治療期間が長くなるため、さらに慰謝料受け取りまでに時間がかかることがあります。
関連記事:交通事故のむちうちで慰謝料はいくらもらえる?相場や計算例を弁護士が解説
【後遺障害が残った場合】症状固定から支払いまでの期間
治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。
症状固定後も体に痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、その後遺症について「後遺障害等級認定」の手続きを行うのが一般的です。
後遺障害等級が認定されて初めて、後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入)などの損害額が確定し、示談交渉を開始できます。
事故発生から支払いまでの流れと期間は、より長くなります。
- 治療〜症状固定までの期間
怪我の内容によりますが、骨折などで半年〜1年、高次脳機能障害など重篤な場合は1〜2年かかることもあります - 後遺障害等級認定の期間
申請の準備に約1か月、審査機関での審査に1〜2か月程度かかります - 示談交渉期間
等級認定後、交渉開始から成立まで2〜3か月程度が目安です - 支払い期間
示談成立後、1〜3週間で振り込まれます
たとえば、骨折から治療6か月で症状固定となった場合、「治療期間6か月+等級認定期間3か月+示談交渉期間3か月+支払い期間約2週間」の合計1年程度となります。
関連記事:交通事故で骨折した場合の慰謝料はいくら?相場や計算方法・手続き方法を弁護士が解説
【死亡事故の場合】遺族が慰謝料を受け取るまでの期間
遺族が慰謝料を受け取る死亡事故の場合、示談交渉は葬儀などが一段落し、遺族の気持ちが少し落ち着いた頃に開始されるのが一般的です。具体的には、四十九日の法要が終わった後から交渉を始めるケースが多く見られます。
事故発生から支払いまでの期間の内訳は以下の通りです。
- 交渉開始までの期間
事故発生から四十九日法要後まで、約2か月 - 相続人の確定
戸籍謄本などを取り寄せて法的な相続人を確定させるのに1〜2か月かかる場合があります - 示談交渉期間
損害賠償額が高額になりやすく、遺族の被害感情も強くなる傾向があるため、交渉は慎重に進められ、3か月以上かかることも珍しくありません - 支払い期間
示談成立後、1〜3週間で振り込まれます
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫これらの期間を合計すると、死亡事故の場合は事故発生から慰謝料の支払いまで、半年から1年程度かかることが一つの目安となります。
死亡事故の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:交通事故で死亡した場合の慰謝料は? 子どもや高齢者の死亡事故とその慰謝料相場について
交通事故の慰謝料で不安を感じる方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が個々のケースに寄り添い、適切な解決方法をアドバイスします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故発生から慰謝料が支払われるまでの流れ
慰謝料が支払われるまでは、単に待つだけでなくいくつかの重要なステップを踏む必要があります。事故直後の対応から示談成立まで、被害者の方が主体的に関わるべき場面も少なくありません。
ここでは、その流れを5つのステップに分けて具体的に解説します。
STEP1:事故発生・警察への届出・病院での受診
まず、交通事故にあった場合には、必ず警察に届け出なければなりません(道路交通法第72条)。
これは法律上の義務であると同時に、後の保険請求に不可欠な「交通事故証明書」を発行してもらうために必要な手続きです。
次に、怪我の自覚症状が軽くても、事故後速やかに病院で診察を受けましょう。
「大したことはない」と自己判断してしまうのは危険です。事故直後は興奮していて痛みを感じにくいこともあり、後から症状が悪化するケースは少なくありません。
受診が遅れると、事故と怪我との因果関係が認められず、正当な治療費や慰謝料が支払われなくなるリスクがあります。
STEP2:治療・通院の開始
医師の指示に従い、治療に専念し、定期的に通院することが極めて重要です。通院の期間や頻度は、治療費はもちろんのこと、精神的苦痛に対する「入通院慰謝料」の金額を算定する際の重要な基礎となります。
この段階で注意すべきは、加害者側の保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診される可能性があることです。保険会社は自社の支出を抑えるために早期の治療終了を促すことがありますが、治療の必要性を最終的に判断するのは医師です。
医師がまだ治療が必要だと判断している限り、安易に治療を中断してはいけません。
STEP3:症状固定・後遺障害等級認定の手続き
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」と呼びます。症状固定の診断は、治療の終了を意味すると同時に、後遺障害が残った場合に損害賠償請求をするスタート地点となります。
症状が残存した場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、「後遺障害等級認定」の申請を行います。
申請方法には、手続きを加害者側の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自身や代理人の弁護士が直接書類を収集・提出する「被害者請求」の2種類があります。
「被害者請求」であれば被害者が主体的に手続きを進められるため、納得のいく等級認定を受けやすい点が魅力です。手続きが複雑なため、「被害者請求」の手続きをしたい場合は、弁護士に相談しましょう。
交通事故の慰謝料で不安を感じる方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が個々のケースに寄り添い、適切な解決方法をアドバイスします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
STEP4:損害額の算出・加害者側の保険会社との示談交渉
治療が完了した時点や、後遺障害等級が確定した時点で、事故による損害額を算出することが可能です。ここから、加害者側の保険会社との本格的な「示談交渉」が始まります。
交渉の対象となる損害には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害が残った場合は逸失利益など、多岐にわたる項目が含まれます。
保険会社は営利企業であるため、自社の内部基準(任意保険基準)に基づいて法的に正当な金額よりも低い賠償額を提示してくることがほとんどです。
この提示額を鵜呑みにせず、内容を慎重に検討する必要があります。
STEP5:示談成立・示談書への署名・慰謝料の振込み
双方が賠償金の金額や支払条件について合意に達すると、「示談成立」となります。その後、保険会社から送られてくる示談書に署名・捺印をして返送します。
ここで重要なのは、一度示談書に署名をすると、原則としてその内容を覆すことは難しいという点です。後から新たな後遺症が発見されたとしても、追加の賠償請求は極めて困難になります。
したがって、示談内容に少しでも疑問や不満がある場合は、決して安易に署名してはいけません。
示談書が保険会社に受理された後、1〜3週間で慰謝料を含む示談金全額が指定の口座に振り込まれ、一連の手続きは完了となります。
慰謝料の支払い方法(振込・一括/分割)
交通事故の慰謝料の支払い方法は、主に振込による一括払いと分割払いがあり、また「誰から支払われるのか」という点も状況によって異なります。
ここでは、慰謝料の支払い主体と、一括払い・分割払いの違いについて詳しく解説します。
誰が支払うのか(加害者or保険会社)
交通事故の慰謝料の支払い主体は、「加害者本人」か「加害者が加入する保険会社」のどちらかです。
実際には、多くのケースで加害者が自動車保険(任意保険)に加入しており、示談交渉から支払いまで保険会社が代行するのが一般的です。
ただし、任意保険に未加入の場合や、保険の補償限度額を超える部分については、加害者本人が自らの資力で負担するケースもあります。
そのため、誰が実際に支払うのかは、加害者の保険加入状況や事故内容によって異なる点を理解しておくことが大切です。
一括と分割の違い
慰謝料の支払い方法は、大きく一括払いと分割払いに分けられます。
一括払いは、示談成立後に決定金額をまとめて指定口座へ振り込む方法です。一方で、分割払いとは、慰謝料の総額を事前に取り決めた支払回数・金額に分けて支払う方法のことを指します。
一般的には、示談成立後にまとまった金額を銀行振込によって一括で支払うケースが多く、迅速に被害者の経済的負担を軽減できるのが特徴です。
ただ、加害者が任意保険に加入していない場合や、個人で支払う資力に乏しい場合には、分割払いが選択されることもあります。分割払いは総支払額の回収が長期化するほか、途中で支払いが滞るリスクもある点に注意が必要です。



交渉の際には、できる限り一括払いを目指すのが望ましいですが、状況に応じて柔軟に対応するよう心がけましょう。
交通事故の慰謝料の支払いが遅くなるケースと対処法
慰謝料の受け取りまでの道のりは、必ずしもスムーズに進むとは限りません。示談交渉の難航や手続きの遅延など、さまざまな要因で支払いが想定より遅れてしまうことがあります。
ここでは、支払いが遅くなる典型的な5つのケースと、それぞれの状況で被害者が取るべき戦略的な対処法を解説します。
示談交渉が難航している場合
示談交渉が長引く一般的な原因は、賠償金額、特に「過失割合」についての意見の対立です。
過失割合とは、事故の発生に対する当事者の責任の割合のことで、被害者側の過失割合が大きくなるほど、受け取れる賠償金は減額(過失相殺)されます。
保険会社は支払額を抑えるため、被害者側に有利でない過失割合を主張してくることが多く、交渉が平行線になることがあります。
示談交渉が難航している場合は、客観的な証拠を集めることが重要です。ドライブレコーダーの映像や警察が作成した実況見分調書、目撃者の証言などが有効な武器となります。
これらの証拠を基に、弁護士を通じて過去の裁判例に照らして法的に適切な過失割合を主張することで、交渉を有利に進めることが可能です。
当事者同士での解決が難しい場合は、裁判外紛争処理機関(ADR)である「交通事故紛争処理センター」などを利用するのも一つです。
後遺障害等級認定に時間がかかっている場合
後遺障害が残った場合、その等級が確定するまで示談交渉は開始できません。
また、等級認定手続き自体に時間がかかることもあります。特に、高次脳機能障害のように判断が難しい症状の場合や、提出した医療資料が不十分な場合は審査が長引きやすいのが特徴です。
さらに、認定された等級に不服がある場合、「異議申し立て」を行えますが、この手続きには新たな医学的証拠の収集が必要となります。結果が出るまでに、さらに2〜4か月、場合によってはそれ以上の期間を要します。
遅延を防ぐためには、最初の申請段階で必要な検査をすべて受け、後遺障害診断書に症状を具体的かつ正確に記載してもらうなど、万全の準備をすることが大切です。
異議申し立てを行う際は、なぜ初回で認められなかったのかを分析し、それを覆すための新たな医学的証拠を的確に提出する必要があります。



専門的な知識を要するため、交通事故に精通した弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。
交通事故の慰謝料で不安を感じる方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が個々のケースに寄り添い、適切な解決方法をアドバイスします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
加害者が任意保険に加入しておらず支払い能力に問題がある場合
加害者が任意保険に未加入(無保険)の場合、被害者は加害者本人と直接交渉しなければなりません。しかし、個人には保険会社のような支払い能力がないことが多く、交渉がまとまっても支払いが滞ったり、分割払いを求められたりするケースが少なくありません。
まずは、加害者が加入している自賠責保険に対して「被害者請求」を行い、最低限の補償(傷害の場合上限120万円)を確保します。
もし加害者が自賠責保険にすら加入していない場合は、国の「政府保障事業」に請求することで同等の補償を受けることが可能です。
それでも不足する分については、加害者本人に請求します。支払いを拒否された場合は、内容証明郵便で請求の意思を明確にした上で訴訟を提起し、判決を得て給与や預金を差し押さえる(強制執行)といった法的手段を検討する必要があります。
また、ご自身が加入している自動車保険の「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」が利用できないかも確認しましょう。
保険会社の対応が遅れている場合
保険会社の担当者が多忙で連絡が滞る、あるいは意図的に対応を遅らせるケースも存在します。
まずは担当者に連絡し、対応を促すことが大切です。それでも改善されない場合は、担当者の上司や、保険会社の「お客様相談センター(カスタマーサービスセンター)」に連絡し、担当者の変更を求めるなどの対応を要求しましょう。
それでも状況が変わらない場合は、中立的な第三者機関である「そんぽADRセンター」に苦情を申し立てることで、問題解決のサポートを得られます。
出典:日本損害保険協会|相談対応、苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター)
示談がまとまらず裁判(訴訟)に発展した場合
示談交渉が完全に決裂した場合の最終手段が、裁判所を通じた解決(訴訟)です。裁判になれば、最終的には裁判官が法に基づいた判決を下してくれるため、白黒がはっきりつきます。
裁判は専門的な手続きのため、多大な時間と労力を要します。
裁判所の統計によれば、交通事故の損害賠償請求訴訟の平均審理期間は13.3か月にも及びます。
つまり、提訴から解決まで1年以上かかることを覚悟しなければなりません。裁判にまで発展した場合は、個人で対応することは現実的ではなく、弁護士への依頼が不可欠となります。
弁護士に依頼することで、法的な主張や証拠の提出を適切に行い、有利な判決を得る可能性を高められます。
出典:裁判所|地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情
慰謝料が支払われない場合
交通事故の慰謝料の支払いが遅くなるケースの中には、そもそも慰謝料が支払われない場合も存在します。
交通事故の慰謝料が支払われない大きな要因の一つは、加害者が任意保険に加入していないことです。この場合、保険会社による対応が行われないため、被害者は直接加害者本人に請求しなければならず、支払いが遅延または不履行となりやすい状況に陥ります。
また、加害者に十分な資力がなく、慰謝料を支払う能力を欠いている場合も支払いが滞りがちです。給与差押えなどの法的手続きを経ても、回収が難しいケースも少なくありません。
上記のようなケースの場合、被害者は自賠責保険の「被害者請求制度」を活用することで、一定額まで慰謝料や治療費の補填を受けられます。



さらに、弁護士に相談して法的措置による回収を検討することも大切です。
交通事故の慰謝料で不安を感じる方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が個々のケースに寄り添い、適切な解決方法をアドバイスします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の慰謝料を早くもらう方法
治療が長引いたり、仕事を休まざるを得なくなったりすると、示談成立を待つ間の生活費や治療費の負担は深刻な問題です。
ただ、最終的な示談金が支払われる前に、当面の資金を受け取るための制度がいくつか用意されています。これらの制度を戦略的に活用することで経済的な不安を軽減し、安心して治療や交渉に臨むことが可能です。
ここでは、慰謝料などを早く受け取るための3つの具体的な方法を解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
自賠責保険の「仮渡金制度」を利用する
「仮渡金(かりわたしきん)制度」は、交通事故の被害者が当座の費用に困ることがないよう、法律で定められた迅速な支払い制度です。加害者が加入する自賠責保険に対し、損害額が確定する前に一定額の前払いを請求できます。
この制度のメリットは、受け取りまでのスピードの早さです。必要書類に不備がなければ、請求から約1〜2週間と短期間で支払いを受けられます。
受け取れる金額は、怪我の程度に応じてあらかじめ決まっています(自動車損害賠償保障法施行令第5条)。
ただし、請求は1回の事故につき一度しかできず、受け取った金額は最終的な示談金から差し引かれます。
自賠責保険への「被害者請求」で直接請求する
「被害者請求」とは、被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を直接請求する手続きです。
通常、賠償金は加害者側の任意保険会社が自賠責保険分もまとめて支払います(一括対応)。ただ、この制度を使えば、任意保険会社との示談成立を待たずに自賠責保険の補償限度額(傷害の場合120万円)までの金額を先に受け取ることが可能です。
示談交渉が長引いている場合や、加害者が任意保険に未加入の場合に特に有効な手段です。
支払われるまでの期間は仮渡金よりは長く、申請から1か月程度が目安ですが、仮渡金よりもまとまった金額を受け取れる可能性があります。
ただし、診断書や診療報酬明細書など、必要な書類をすべて自分で収集・作成して提出する必要があり、手続きが煩雑な点がデメリットです。
加害者の任意保険会社に治療費などの「内払い」を交渉する
「内払い(うちばらい)」とは、加害者側の任意保険会社が、損害賠償金の一部を示談成立前に支払う対応のことです。これは法律で定められた制度ではなく、あくまで保険会社のサービスの一環として行われます。
治療費については保険会社が病院に直接支払う「一括対応」が一般的ですが、それ以外の休業損害や通院交通費などについて、内払いを交渉できる場合があります。
内払いに応じてもらえるかどうか、また、いくら支払われるかは、保険会社の方針や交渉次第です。



法的な権利ではないため必ずしも支払われるとは限りませんが、当面の生活費に困っている事情などを具体的に説明し、交渉してみる価値はあります。
交通事故の慰謝料の請求で弁護士に相談するメリット
交通事故の被害に遭われた方が正当な権利を実現し、適正な賠償金を受け取るためには、弁護士に相談することが大切です。
弁護士への依頼は、単に手続きを代行してもらうだけでなく、交渉の力関係を対等にし、最終的に受け取る金額を大きく左右する可能性を秘めています。
ここでは、弁護士に相談する3つの具体的なメリットを解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
保険会社との交渉をすべて一任でき、治療に専念できる
交通事故後、被害者は心身ともに大きなダメージを負っています。
そのような状況で、示談交渉のプロである保険会社の担当者と対等に渡り合うのは、精神的にも時間的にも大変な負担です。専門用語を多用されたり、高圧的な態度によって治療の打ち切りを迫られたりするケースもあります。
弁護士に依頼すれば、こうした煩わしい交渉の窓口をすべて任せられます。保険会社からの連絡はすべて弁護士が受け、法的な観点から適切に対応します。
これにより、被害者の方は交渉のストレスから解放され、自身の体の回復と心の平穏を取り戻すことに専念することが可能です。
一般的に最も高額となる「弁護士基準」で慰謝料の請求が可能になる
一般的に最も高額となる「弁護士基準」で慰謝料の請求が可能になる点も、弁護士に依頼するメリットです。
交通事故の慰謝料算定には、3つの異なる基準が存在します。
| 自賠責基準 | 法律で定められた、被害者救済のための最低限の補償基準です。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定している内部基準です。自賠責基準よりは多少高いものの、公表されておらず、法的な拘束力はありません。 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例の蓄積から形成された基準で、裁判所が賠償額を判断する際に用いられます。3つの基準の中で最も高額かつ法的に正当な基準です。 |
通常、保険会社が被害者本人に提示する示談金は「任意保険基準」で、本来受け取るべき「弁護士基準」の金額よりも大幅に低いことがほとんどです。被害者本人が弁護士基準での支払いを要求しても、保険会社が応じることはまずありません。
しかし、弁護士が代理人として交渉に臨むと状況は一変します。弁護士には「裁判」の選択肢が存在するため、保険会社も裁判になった場合に見込まれる「弁護士基準」を前提とした交渉に応じざるを得なくなります。
適切な後遺障害等級認定の獲得をサポートしてもらえる
弁護士は、適正な等級認定を得るために、医学的知見と法律的知識の両面から被害者をサポートします。
後遺障害が残った場合、最終的な賠償金額を決定づける重要な要素が「後遺障害等級」です。何級に認定されるかによって、慰謝料や逸失利益の金額が数百万円、場合によっては数千万円単位で変わってきます。
弁護士に依頼すると、以下のようなサポートを受けられます。
| 治療段階でのアドバイス | 等級認定で有利になるために、どのような検査(MRI・神経学的検査など)を受けておくべきか、医師に症状をどう伝えるべきかなどを具体的に助言します。 |
|---|---|
| 後遺障害診断書のチェック | 医師が作成した診断書の内容を専門家の視点で精査し、認定に必要な情報が漏れなく、かつ的確に記載されているかを確認・修正を依頼します。 |
| 異議申し立てのサポート | もし結果に不服がある場合でも、認定機関がなぜその判断を下したのかを分析し、それを覆すための新たな証拠を収集して、説得力のある異議申立書を作成します。 |



このように、適正な賠償金を得るための土台作りから最終的な交渉まで、すべての段階で被害者の権利を守るサポートを受けることが可能です。
交通事故で弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:交通事故で弁護士に依頼するメリットは?デメリットや依頼の適切なタイミングも解説
関連記事:弁護士に依頼すると交通事故の解決までの期間は早くなる?期間の目安・早くなる理由を解説
交通事故の慰謝料で不安を感じる方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が個々のケースに寄り添い、適切な解決方法をアドバイスします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の慰謝料がいつもらえるかに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、交通事故の慰謝料の支払い時期に関して、よく寄せられる質問にお答えします。
示談書に署名してから何日くらいで振り込まれる?
示談書に署名・捺印し、加害者側の保険会社に返送した後、通常は1〜3週間程度で指定した銀行口座に示談金が振り込まれます。
保険会社側で書類の最終確認と社内での支払い手続きが必要なため、署名後すぐに入金されるわけではありません。
もし3週間を過ぎても入金がない場合は、保険会社の担当者に進捗状況を確認してみましょう。
通院中でも慰謝料の一部をもらうことはできる?
通院中でも慰謝料の一部をもらうことは可能です。
最終的な慰謝料額が確定する示談成立前であっても、当面の治療費や生活費を補うために、賠償金の一部を先に受け取る方法がいくつかあります。
具体的には、以下の制度を利用することが考えられます。
- 加害者の自賠責保険に請求する「仮渡金制度」や「被害者請求」
- 加害者の任意保険会社と交渉して支払ってもらう「内払い」
- ご自身が加入している「人身傷害保険」
どの方法がご自身の状況に最適か、検討してみるとよいでしょう。
示談金・慰謝料の振込口座は家族のものでも指定できる?
原則として、慰謝料は被害者本人名義の銀行口座に振り込まれます。これは、賠償金が被害者自身の損害を填補するものであるためです。
ただし、被害者が未成年者である場合には親権者の口座を指定できるなど、特別な事情がある場合は保険会社との合意の上で家族名義の口座への振込が認められることもあります。
また、弁護士に依頼している場合は、一度弁護士事務所の口座に振り込まれ、弁護士費用を差し引いた金額が被害者の口座に送金されるのが一般的です。
示談金が分割払いになることはある?
加害者が任意保険に加入している場合、示談金は一括で支払われるのが一般的です。
しかし、加害者が任意保険に未加入で、本人に十分な資力がない場合には、加害者との直接交渉の末、やむを得ず分割での支払いに合意することがあります。
この場合、途中で支払いが滞る「踏み倒し」のリスクが常に伴います。このリスクを少しでも軽減するためには、示談の合意内容を、強制執行認諾文言付きの「公正証書」として作成しておくことが重要です。
これにより、支払いが滞った際に裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能になります。
まとめ|交通事故の慰謝料は受け取り時期の見通しを立てることが重要
この記事では、交通事故の慰謝料がいつ支払われるのか悩む方に向けて、具体的な時期の目安から全体的な流れ、支払いを早める方法までを多角的に解説しました。
慰謝料は原則として示談成立後1〜3週間で支払われます。示談成立までの期間は、怪我が完治したか、後遺障害が残ったか、死亡事故かによって大きく異なります。場合によっては、数か月から1年以上かかることも珍しくありません。
まずは、ご自身の状況を確認し、慰謝料受け取りまでの大まかな見通しを立ててみましょう。



もし保険会社の対応や提示額に少しでも疑問を感じたり、手続きの複雑さに負担を感じたりした場合は、専門家である弁護士に相談することが大切です。
交通事故の慰謝料で不安を感じる方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が個々のケースに寄り添い、適切な解決方法をアドバイスします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応










