過失割合10対0事故の示談金相場と増額交渉の注意点を解説
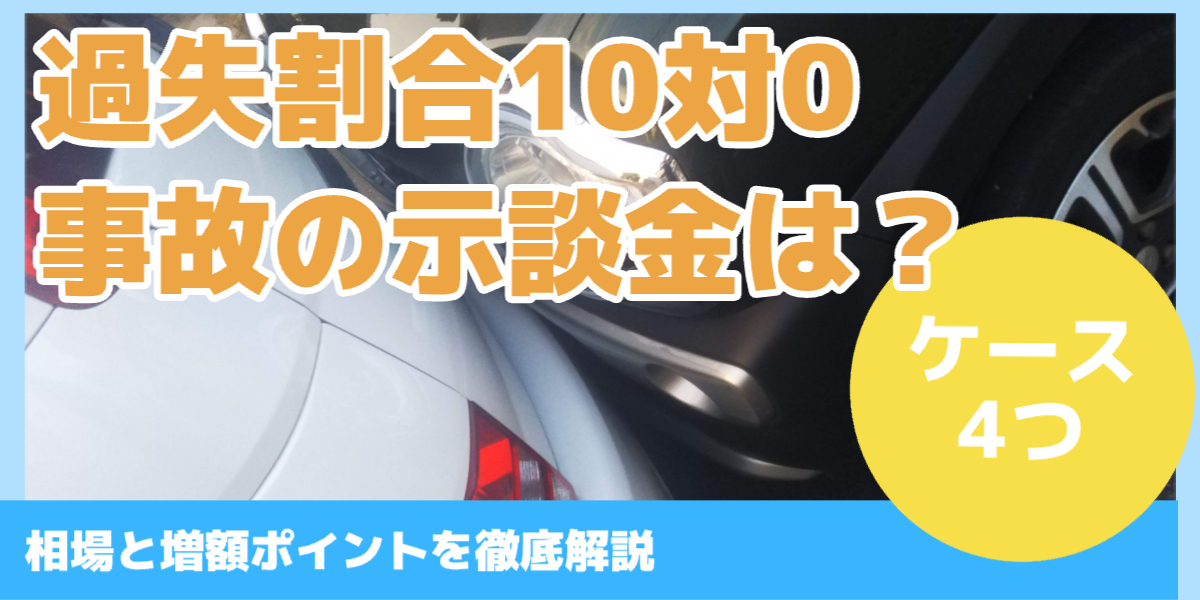
「過失割合10対0の事故なのに、保険会社が提示した示談金が低すぎる…」
「保険会社が提示した示談金が適切かわからず不安…」
あなたに一切の非がない「もらい事故」にもかかわらず、相手の保険会社から提示された示談金額に疑問や不満を感じていませんか。
実は、保険会社が最初に提示する金額は、法的に正当な基準よりも低く抑えられている可能性があります。
この記事では、過失割合10対0の事故における示談金の適切な相場や、正当な金額を受け取るための交渉の注意点について詳しく解説します。
交通事故の示談金で悩みを抱えているなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故のトラブル解決実績の豊富な弁護士が、個々の状況に合わせて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
【状況別】過失割合が10対0の事故における示談金の相場
示談金の相場は、事故による被害の状況によって大きく変動します。
ここでは、被害状況を4つのケースに分けて、それぞれの示談金相場を解説します。
自身の状況と照らし合わせ、適切な相場のイメージを掴みましょう。
関連記事:追突事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や増額のポイントを弁護士が解説
関連記事:交通事故の過失割合を徹底解説|ケース別の相場と納得できない時の対処法
関連記事:交通事故の慰謝料とは?計算方法や慰謝料相場・注意点を弁護士が徹底解説
むちうち・軽症(通院1か月〜6か月)の場合の慰謝料相場
交通事故で最も多い「むちうち」などの軽症の場合、慰謝料の相場は通院期間によって決まります。
慰謝料の計算には複数の基準がありますが、最も高額な弁護士基準(裁判基準)で計算した場合の相場は以下のとおりです。
| 通院期間 | 慰謝料相場(弁護士基準) |
|---|---|
| 1か月 | 19万円 |
| 2か月 | 36万円 |
| 3か月 | 53万円 |
| 4か月 | 67万円 |
| 5か月 | 79万円 |
| 6か月 | 89万円 |
※書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』から引用
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫実際の示談金には、上記に加えて治療費や休業損害などが別途加算されます。
むちうちの慰謝料については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:交通事故のむちうちで慰謝料はいくらもらえる?相場や計算例を弁護士が解説
関連記事:追突事故でむちうちになったら?事故後の対応や慰謝料請求で損しない方法を弁護士が解説
後遺障害が残った場合の慰謝料・逸失利益の相場
治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまった場合は「後遺障害」として認定を受ける可能性があります。
後遺障害が認定されると、通常の入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することが可能です。
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への補償
- 逸失利益:後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少したことへの補償
後遺障害は症状の重さに応じて1級から14級までの等級に分けられ、等級ごとに慰謝料の相場が決まっています。主な例は、以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
|---|---|
| 第14級 | 110万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第1級 | 2,800万円 |
なお逸失利益は、被害者の年齢、収入、後遺障害等級などに基づいて個別に計算されるため、非常に高額になりやすい点が特徴です。
関連記事:交通事故の逸失利益とは?計算方法や認められない・減額される原因を解説
死亡事故の場合の慰謝料相場
交通事故によって被害者の方が亡くなった場合、遺族は加害者側に対して死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料の相場(弁護士基準)は、被害者の家庭内での立場によって以下のように変動する点が特徴です。
| 被害者の立場 | 慰謝料相場(弁護士基準) |
|---|---|
| 一家の支柱 | 約2,800万円 |
| 両親・配偶者 | 2,500万円 |
| その他(独身者、子どもなど) | 約2,000万円~2,500万円 |
※書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』から引用
実際の示談金では、これに加えて葬儀費用・逸失利益などの損害も加算されるため、総額はさらに高額となる場合があります。
関連記事:交通事故で死亡した場合の慰謝料は? 子どもや高齢者の死亡事故とその慰謝料相場について
怪我なし・物損のみの場合の示談金相場
怪我がなく、車や所持品の損壊のみで済んだ場合は「物損事故」として扱われます。
物損事故で請求できる示談金(損害賠償金)は、原則として修理にかかった費用が上限です。
主に、以下のような費用を請求できます。
| 修理費用 | 事故で壊れた物の修理にかかる費用 |
|---|---|
| 買替差額 | 修理が不可能な場合や、修理費が時価額を上回る場合に認められる費用 |
| 代車費用 | 修理期間中に代車を利用した場合の費用 |
| 評価損 | 事故によって車両の市場価値が下がったことによる損害 |
| 休車損 | 営業車などが使用できなくなったことによる営業上の損害 |
物損事故では、原則として慰謝料は請求できません。ただし、ペットが死傷した場合など、例外的に慰謝料が認められるケースも存在します。
自身のケースで慰謝料をどれだけ請求できるか悩んでいる場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
関連記事:もらい事故で慰謝料はいくらもらえる? 相場や計算方法、請求の流れを解説【弁護士監修】
関連記事:交通事故の示談金とは?計算方法や相場・手続きの流れを弁護士が解説
交通事故の示談金で悩みを抱えているなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故のトラブル解決実績の豊富な弁護士が、個々の状況に合わせて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
過失割合10対0の事故で請求できる費用の内訳
示談金は、さまざまな損害項目の合計額で構成されています。
請求漏れがないように、どのような費用を請求できるのかを正確に把握しておくことが重要です。
ここでは、過失割合10対0の事故で請求できる主な費用の内訳を解説します。
治療関係費
交通事故による怪我の治療にかかった実費は、「治療関係費」として加害者側に請求できます。
これは、被害者が事故によって負った身体的損害を回復するために、必要かつ相当な範囲で支出した費用を指します。
治療関係費の主な項目は、次のとおりです。
- 診察費、手術費、入院費
- 投薬料、検査料
- 接骨院・整骨院での施術費(医師の許可がある場合)
- 通院交通費(公共交通機関、タクシー、自家用車のガソリン代など)
- 将来の介護費用(重度の後遺障害が残った場合)
- 器具・装具の購入費(車椅子、義足など)
治療関係費は、単なる医療費だけでなく、被害者の身体的・生活的な回復を目的とする費用全般が対象となる点を覚えておきましょう。
請求の際は、領収書や医師の診断書・指示書などの証拠資料をしっかり保存しておくことが重要です。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、交通事故によって怪我を負い、入院や通院を余儀なくされたことに対する「精神的苦痛」を金銭で補償するものです。
慰謝料の算定は、入院・通院の期間や実際に通った日数を基準に行われます。治療期間が3か月であっても、実際に通院した日数が少ない場合は慰謝料が低くなることがあります。
一方で、入院を伴うケースでは、身体的・精神的な負担が大きいと判断されるため、通院のみの場合よりも高額になる傾向があります。
休業損害
事故の治療のために仕事を休んだことで減少した収入に対する補償です。被害者が事故に遭わなければ本来得られたはずの収入を、加害者側(またはその保険会社)に請求できます。
正社員だけでなく、以下のように働き方の形態を問わず認められます。
- パート
- アルバイト
- 派遣社員
- 契約社員
- 自営業者など
収入のない専業主婦(主夫)や学生でも、家事労働や学業への支障を根拠に請求が認められる場合があります。
計算方法は、以下のとおりです。
基礎収入 × 休業日数
給与所得者であれば事故前3か月の平均給与をもとに日額を算出し、自営業者やフリーランスは確定申告書などで実際の所得を証明する形になります。
専業主婦(主夫)については、賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の一般労働者平均賃金を基礎収入として用いるのが実務上一般的です。
後遺障害慰謝料
治療を尽くしても身体的または精神的な後遺症が残り、「後遺障害」として等級認定された場合に請求できる慰謝料です。
後遺障害等級は1級から14級まであり、等級が重くなるほど慰謝料の金額は高くなります。
また、後遺障害慰謝料は入通院期間に応じて支払われる「入通院慰謝料」とは別に請求できます。
治療中の精神的苦痛と、治療後に残った後遺症による苦痛をそれぞれ分けて補償してもらうことが可能です。
関連記事:後遺障害等級認定とは?手続きの流れ・適切な等級獲得のポイントを弁護士が解説
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残った、または死亡したことによって、将来得られるはずだった収入が得られなくなったことに対する補償のことを指します。
損害賠償の中でもとくに金額が大きくなりやすい項目で、被害者の人生設計や生活基盤に大きく関わる重要な要素です。
逸失利益の金額は、主に以下の3つの要素を基に算出されます。
- 基礎収入:事故前の年収
- 労働能力喪失率:後遺障害等級に応じて定められた割合
- 労働能力喪失期間:原則として67歳までの年数
これらの要素をもとに、以下の計算式で金額を算出する点が特徴です。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(ライプニッツ係数で割引)
逸失利益は、将来の生活を支えるための補償であるため、示談交渉の際には最も争点になりやすい項目でもあります。
関連記事:後遺障害の逸失利益とは?等級別の相場や計算方法を弁護士が解説
物損に関する損害(修理費、代車費用など)
10対0の事故であっても、人身事故と同時に「物損」に関する損害が発生している場合は、その賠償を別途請求可能です。
物損とは、車両そのものの損壊だけでなく、事故によって壊れた携行品や周辺費用など、人の身体以外に生じた損害を指します。
具体的には、以下のような項目が対象です。
- 車両の修理費用
- レッカー代
- 代車使用料
- 事故で壊れた衣服やスマートフォンなどの携行品損害



これらの損害は、人身に関する損害とは別に計算され、合計額が示談金となります。
妥当性を証明するためにも、修理見積書や領収書、購入時のレシートなどの客観的な証拠を揃えておくことが重要です。
示談金の額は計算基準で大きく変わる!3つの計算基準を解説
交通事故の慰謝料を含む示談金の計算には、3つの異なる基準が存在します。
どの基準を用いるかによって、示談金の金額が数倍変わることも珍しくありません。
それぞれの基準の特徴を理解し、相手の保険会社がどの基準で提示してきているかを見極めることが重要です。
関連記事:交通事故の慰謝料はどうやって計算する?弁護士基準の相場と通院期間ごとの早見表【弁護士監修】
自賠責基準:国が定める最低限の補償
自賠責保険は、すべての自動車・バイク所有者に加入が義務付けられている「強制保険」です(自動車損害賠償保障法第5条)。交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるよう、国の制度として設けられています。
ただし、自賠責保険はあくまで「人身事故に対する最低限の補償」が目的であり、物損(車や物の修理費など)は対象外です。
また、補償額にも上限があり、以下のように限度額が定められています。
| 死亡事故 | 最大3,000万円 |
|---|---|
| 傷害事故 | 最大120万円 |
| 後遺障害 | 後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円※ |
※上記以外の後遺障害は3,000万円(第1級)~75万円(第14級)



3つの基準の中では、最も支払額が低く設定されている点が特徴です。
被害の程度が大きい場合や、実際の損害額が自賠責の限度額を超えるときには、任意保険や弁護士を通じて、より高い基準での補償を求めましょう。
任意保険基準:保険会社独自の非公開基準
任意保険会社が、示談交渉の際に用いる内部的な支払基準です。
相手の保険会社が最初に提示してくる金額は、通常この任意保険基準で計算されている場合が多いでしょう。
この基準は各社が独自に設定しており、公にはされていません。
一般的には、自賠責基準よりは少し高いものの、次に解説する弁護士基準よりは大幅に低い金額となります。
弁護士基準(裁判基準):過去の判例に基づく最も高額な基準
弁護士基準(裁判基準)は、過去の交通事故の裁判例を基に算出される基準で、「裁判基準」とも呼ばれます。
自賠責基準や任意保険基準よりも高額になりやすく、被害者にとって最も有利な賠償水準といえます。2倍近く差ができることも珍しくありません。
以下の章では、弁護士基準(裁判基準)を示談金の算定基準にするために大切なことを詳しく解説します。
示談金を弁護士基準(裁判基準)にするには弁護士への依頼がほぼ必須
相手の保険会社は、営利企業であるため、支払う保険金をできるだけ抑えようとします。
そのため、被害者本人が「弁護士基準で支払ってほしい」と交渉しても、ほとんどの場合応じてくれません。



「これが弊社の基準ですので」と、任意保険基準での支払いを主張されるのが通常です。
しかし、弁護士が代理人として交渉に立つと、保険会社は裁判に発展する可能性を考慮せざるを得なくなります。
裁判になれば、最終的に弁護士基準での支払いを命じられる可能性が高いため、交渉段階で弁護士基準に近い金額での示談に応じてくれやすくなるでしょう。
したがって、正当な賠償額である弁護士基準での示談金を受け取るためには、弁護士への依頼が事実上必須となります。
まずは弁護士に相談し、適切な示談金を受け取れるかどうかを確認してみましょう。
交通事故の示談金で悩みを抱えているなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故のトラブル解決実績の豊富な弁護士が、個々の状況に合わせて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
以下の記事では、交通事故の慰謝料を増額する方法について解説しています。併せて参考にしてみてください。
関連記事:【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説
関連記事:交通事故の弁護士費用はいくらかかる?弁護士費用特約や費用倒れしないコツも紹介【弁護士監修】
弁護士費用特約の使い方|10対0でも等級ダウンなし
交通事故で過失割合が10対0となるケースでは、相手側の保険会社が対応してくれず、自分で交渉を進めなければなりません。その際、強い味方となるのが「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約とは、示談交渉や訴訟にかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度で、使っても等級(保険のランク)は下がりません。
弁護士費用特約の補償上限は、一般的に300万円(相談費用は10万円程度)までとされています。対象となるのは、主に以下の費用です。
- 弁護士への相談料
- 示談交渉を依頼する際の着手金
- 結果に応じて支払う報酬金
- 必要に応じた訴訟費用
弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、同居の家族や別居中の未婚の子が事故に遭った場合にも利用できるのが一般的です。また、自分の車ではなく他人の車に同乗していた場合でも、条件を満たせば補償対象になるケースがあります。
もし弁護士費用特約が付いていない、あるいは利用条件を満たさない場合でも、「法テラス(日本司法支援センター)」を通じて無料または低額で弁護士に相談することが可能です。



自治体によっては交通事故相談窓口を設けているところもあるため、早めに情報を確認しておくとよいでしょう。
過失割合10対0の事故で示談交渉を開始するタイミングは?
適切なタイミングで示談交渉を始めることは、正当な賠償金を受け取るうえで重要です。
焦って示談を開始してしまうと、本来請求できるはずの損害が請求できなくなる恐れがあります。
怪我の状況によって、交渉を開始すべきタイミングは異なるため、自身の状況に合わせて適切なタイミングを理解しましょう。
関連記事:交通事故の示談交渉の流れは?押さえておきたい重要ポイントや注意点を解説
後遺障害がない場合:怪我の治療が完了(症状固定)してから
後遺障害が残らなかった場合は、怪我の治療がすべて完了してから示談交渉を開始します。
治療の完了は、医師が「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と判断した状態を指し、これを症状固定と言います。
症状固定を迎える前に示談を成立させてしまうと、その後に治療が必要になったとしても、追加の治療費や慰謝料を請求することは原則できません。



必ず医師の判断を仰ぎ、治療が完了したことを確認してから交渉を始めましょう。
後遺障害がある場合:「等級認定」の結果が出てから
症状固定後も後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定の手続きを行います。
示談交渉は、この等級認定の結果が出てから開始するのが正しいタイミングです。
なぜなら、認定された等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わるためです。
先に示談してしまうと、後から後遺障害に関する賠償を請求できなくなってしまいます。



必ず等級が確定してから、すべての損害額を算出して交渉に臨みましょう。
過失割合10対0の事故で示談交渉をする際の注意点
過失割合が10対0の事故は、被害者側に一切の落ち度がないため、有利に交渉を進められるように思えます。
しかし、実は10対0の事故だからこその注意点が存在します。
これらの点を理解しておかないと思わぬ不利益を被る可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
自分の保険会社は示談交渉を代行してくれない
通常、自動車保険に加入していれば、自分の保険会社が相手方との示談交渉を代行してくれます。
しかし、サポートが受けられるのは、自分にも一定の過失(責任)がある場合に限られます。
過失割合が10対0の事故では、被害者は相手方に賠償金を支払う義務がありません。つまり、自分の保険会社は金銭的な利害関係を持たない「第三者」となり、示談交渉に介入できなくなります。
そのため、「完全な被害者」であるにもかかわらず、自分で相手方(または相手方の保険会社)と直接交渉を進めなければなりません。
被害者が一人で交渉に臨むと、不利な条件で話をまとめられてしまうリスクが高いため、弁護士に相談して示談交渉を任せることが大切です。
関連記事:交通事故の示談交渉は自分でできる?考えられるリスクや注意点を徹底解説
相手の保険会社の提示額は「弁護士基準」より大幅に低い
前述の通り、相手の保険会社が提示する示談金額は、自社の任意保険基準で計算されています。
これは、法的に正当な弁護士基準と比較すると、著しく低い金額です。
特に慰謝料の項目で大きな差が出ます。
- 入通院慰謝料:弁護士基準の半分以下になることも多い
- 後遺障害慰謝料:等級によっては数倍の差が出ることもある
相手の提示額を鵜呑みにせず、「これは最低ラインの金額だ」と認識しておくことが重要です。
一度サインすると示談のやり直しは原則できない
示談書は、法的な効力を持つ契約書です。
一度サインをして示談が成立すると、その内容は原則として覆すことができません。
後から「やっぱり慰謝料が低すぎる」と感じたり、新たな後遺症が発覚したりしても、追加の賠償請求は極めて困難になります。
示談のやり直しが認められるのは、詐欺・強迫・重要な錯誤があった場合など、民法上の限られた事情に該当するときや、予想外の後遺障害が後日発覚したといった極めて例外的な場合のみです。



示談書にサインする前には、提示された金額がすべての損害を適切に補償しているか、慎重に確認しましょう。
関連記事:右直事故の過失割合10対0は可能?被害者が有利な場合が認められるケースを紹介
関連記事:過失割合のゴネ得はどう防ぐ?応じる危険性や対処法・効果的な証拠を弁護士が解説
保険会社から示談金額の提示が来たら?サインする前に確認すべきこと
相手の保険会社から示談金の提示があったら、すぐにサインをしてはいけません。
以下の2つのポイントを必ず確認し、内容に納得できるかを慎重に判断してください。
以下、それぞれ具体的に解説します。
慰謝料が納得のいく基準で計算されているか
示談交渉では、提示された金額の内訳をしっかり確認することが重要です。
とくに、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料といった精神的苦痛に対する補償額が妥当な基準で算出されているかを丁寧にチェックしましょう。
保険会社が初回に提示してくる示談金は、ほとんどの場合「任意保険基準(保険会社独自の社内基準)」で計算されています。
法律上の根拠がないうえ、「弁護士基準(裁判基準)」と比べて大幅に低い点が特徴です。



提示額と弁護士基準の相場を比較し、あまりにも金額が低い場合は、増額交渉をしましょう。
休業損害や通院交通費など請求項目に漏れがないか
示談金の内訳書を細かく確認し、請求できるはずの項目が漏れていないかをチェックすることも重要です。
主に、見落としやすい以下の項目を確認しておきましょう。
- 休業損害は正しく計算されているか
- 通院交通費は全期間分が計上されているか
- 物損の代車費用や評価損は含まれているか



とくに休業損害では、基礎収入の計算方法を巡って争いになることがあります。
源泉徴収票や確定申告書などの客観的な資料を基に、正しい金額が算定されているかを確認しましょう。
計算方法がわからない場合や、確認が漏れていないか不安な場合は、弁護士に相談することも大切です。
交通事故の示談金で悩みを抱えているなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故のトラブル解決実績の豊富な弁護士が、個々の状況に合わせて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
過失割合10対0の事故の示談金相場に関するよくある質問
ここからは、過失割合10対0の事故の示談金相場を把握したいと悩む人によくある質問に回答します。後でトラブルにならないためにも、現段階で確認しておきましょう。
専業主婦(主夫)や学生でも休業損害は請求できる?
専業主婦(主夫)や学生でも、休業補償を請求することが可能です。
専業主婦(主夫)の家事労働は経済的に評価されるため、事故によって家事ができなかった期間については休業損害が認められます。この場合、賃金センサスの「産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者平均賃金」を基準として休業損害を計算します。
学生の場合も、アルバイトを休んだ分の収入減はもちろん、事故によって卒業が遅れたり、就職が内定していたのに取り消されたりした損害を請求できる可能性があります。
相手が保険に入っていなかった場合の対処法は?
相手が無保険(自賠責保険にも任意保険にも未加入)の場合、加害者本人に直接損害賠償を請求することになります。
しかし、個人に支払い能力がないケースも多く、回収は困難を極めることも珍しくありません。



このような場合は、まず自身が加入している保険の利用を検討してみましょう。
- 人身傷害保険:自分の過失に関係なく、保険会社が損害額を支払ってくれる
- 搭乗者傷害保険:契約車両に乗車中の人が死傷した場合に定額が支払われる
- 無保険車傷害保険:相手が無保険の場合に、自分の保険会社が補償してくれる
さらに、相手が自賠責保険にも加入していないケースでは、「政府の自動車損害賠償保障事業」を利用できる可能性があります。
これは、無保険車による人身事故や、ひき逃げなどの被害に遭った被害者を救済するための公的制度で、政府が自賠責保険と同等の基準で補償を行うものです。
ただし、請求手続きには事故証明書や診断書などの書類が必要で、一定の時間と手間を要します。こうした複雑なケースでは、弁護士に相談して適切な解決策のアドバイスを受けることも非常に重要です。
提示された示談金額が妥当かを確認する方法は?
提示された示談金額が妥当かを確認する確実な方法は、交通事故に詳しい弁護士に相談することです。
弁護士であれば、提示された金額が弁護士基準と比較して妥当な水準にあるかを即座に判断できます。
多くの法律事務所では無料相談を実施しているため、示談書にサインする前に一度相談してみましょう。
また、弁護士に依頼すれば、その後の増額交渉もすべて任せられます。適切に増額交渉をするためにも、弁護士に相談することが大切です。
まとめ|過失割合10対0の事故の示談金相場を理解して、適切な示談金を受け取ろう
過失割合10対0の交通事故では、被害者であるあなたに一切の責任はありません。受けた損害に見合う正当な賠償金を受け取る権利があります。
しかし、相手の保険会社の提示額は、低額な任意保険基準であることが多いです。また、10対0の事故では自分の保険会社は交渉してくれないため、自身で交渉をする必要があります。
相手の保険会社から提示された金額に少しでも疑問を感じたら、安易にサインをしてはいけません。本記事で解説した内容を参考に、請求できる費用の内訳や慰謝料の計算基準を確認してみましょう。
自身での交渉に不安を感じる場合や、提示額に納得がいかない場合は、迷わず弁護士などの専門家に相談することが大切です。
交通事故の示談金で悩みを抱えているなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
交通事故のトラブル解決実績の豊富な弁護士が、個々の状況に合わせて適切な解決策を提案します。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応







