交通事故の示談交渉の流れは?押さえておきたい重要ポイントや注意点を解説
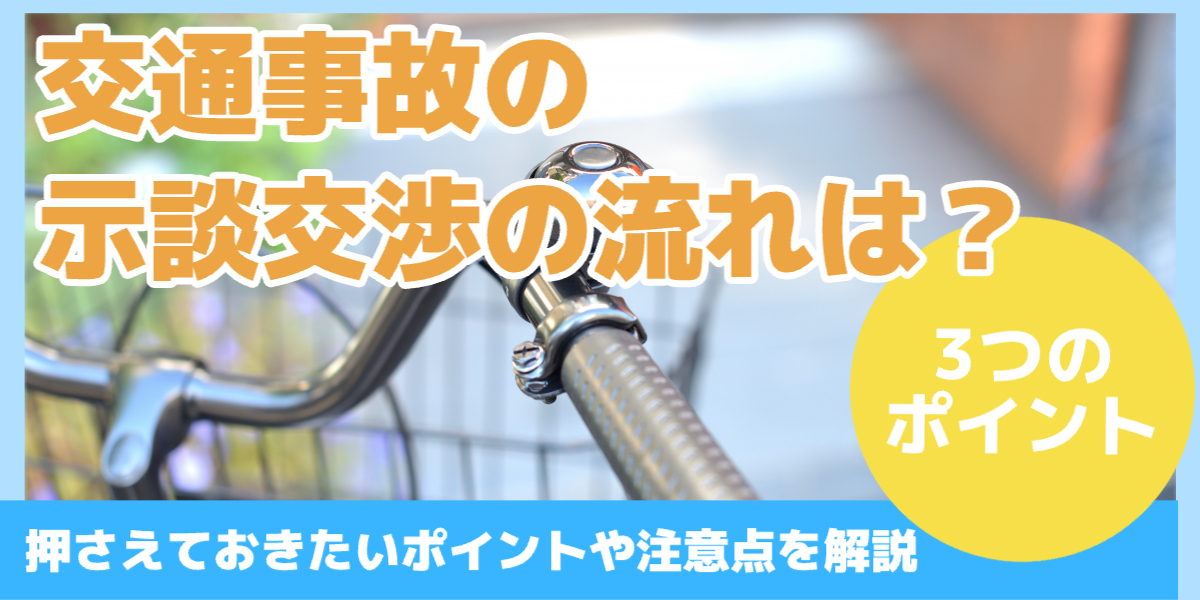
「保険会社から示談の連絡が来たけど、どう対応すればいいんだろう?」
「提示された示談金の額が、本当に妥当なのか不安…」
突然の交通事故に遭い、心身ともに大変な状況のなかで、専門的な知識が必要な示談交渉までご自身で進めるのは、大きな不安が伴いますよね。
交通事故の示談交渉は、事故後の人生を左右する重要な手続きです。しかし、その流れや注意点を正しく理解していないと、本来受け取れるはずの賠償金よりも低い金額で合意してしまう可能性があります。
この記事では、交通事故の示談交渉の基本的な流れから、交渉を有利に進めるための重要なポイントまでを解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫示談金の計算基準や弁護士に依頼するメリットも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の示談交渉とは
交通事故における示談交渉とは、事故の当事者双方が裁判手続きを経ずに、話し合いによって損害賠償の問題を解決する手続きのことです。
具体的には、加害者側(多くは加害者が加入する保険会社の担当者)と被害者が、治療費や慰謝料、休業損害などを含む「示談金」の金額や支払い方法について合意を目指します。
一度示談が成立すると、原則としてその内容を覆すことは困難です。
そのため、安易に合意するのではなく、ご自身の損害に見合った適切な賠償を受けられるよう、慎重に交渉を進める必要があります。
ただし例外として、相手が重大な事実を隠していた場合や、詐欺・脅迫など不当な手段で合意させられた場合には、示談を取り消せる余地があります。しかし、例外は非常に限定的で立証も難しいため、合意前に慎重な確認が必要です。
関連記事:交通事故の損害賠償額の決め方とは?交通事故の慰謝料の計算方法を弁護士が解説
関連記事:追突事故の示談とは?手続きの流れや注意点・受け取れる示談金の内訳・相場を解説
【ステップで解説】交通事故発生から示談交渉成立までの流れ
交通事故の発生から示談が成立するまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。全体の流れを把握しておくことで、今どの段階にいるのか、次に何をすべきかが明確になります。
ここでは、一般的な示談交渉の流れを6つのステップに分けて解説します。
ステップ1:事故発生後すぐに警察・保険会社に連絡する
交通事故に遭ったら、まずは警察に連絡して「交通事故証明書」の発行に必要な届け出を行う必要があります。警察に連絡しなければ道路交通法違反になるため、必ず連絡しましょう(道路交通法第72条)。
次に、ご自身が加入している自動車保険の保険会社にも速やかに連絡します。たとえご自身に過失がない「もらい事故」であっても、今後の対応について相談したり、利用できる保険(弁護士費用特約など)がないかを確認したりすることが重要です。
事故直後は動揺しているため、冷静な判断が難しいかもしれませんが、この初期対応が後の交渉をスムーズに進めるための第一歩となります。
また、この段階で弁護士にも相談すると、後々の治療や後遺障害認定、示談交渉などを円滑に進めることが可能です。
ステップ2:治療に専念し、完治または症状固定を目指す
事故で怪我をした場合は、何よりも治療に専念することが大切です。示談交渉は、すべての治療が終了してから本格的に始まります。
治療の終了には、怪我が完全に治る「完治」と、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態である「症状固定」の2つのケースがあります。
とくに重要なのが「症状固定」のタイミングです。相手方の保険会社から治療費の打ち切りを打診されることもありますが、自己判断で治療をやめてはいけません。医師の専門的な判断に従いましょう。
ステップ3:後遺障害が残った場合は「後遺障害等級認定」を受ける
医師から「症状固定」の診断を受けたにも関わらず、身体に痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合は、「後遺障害」として認定を受けるための手続きに進みます。
後遺障害等級認定とは、残った症状がどの程度の後遺障害に該当するのかを、専門機関が1級から14級までの等級で認定する制度です。
この等級が認定されると、通常の傷害部分の賠償とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害の影響により得られなくなった利益)を請求できます。
適切な等級の認定を受けられるかどうかは、最終的な示談金の額に影響を与えるため、重要な手続きです。
なお、以下の記事では、後遺障害等級認定について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
ステップ4:保険会社から示談案(賠償額)が提示される
治療が終了し、損害額全体が確定した段階で、加害者側の保険会社から示談金の金額を記載した「示談案(損害賠償額計算書)」が送付されます。
この書類には、以下のような項目ごとに金額が記載されています。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
ここで注意すべきなのは、提示された金額はあくまで「保険会社の基準」で計算されたものであり、法的に正当な金額よりも低い場合がほとんどであるという点です。
この提示額は交渉の出発点の一つと捉え、内容を鵜呑みにせず、専門家へ相談するなど慎重に検討することが求められます。
ステップ5:提示内容を検討し、示談交渉を開始する
保険会社から示談案が届いたら、いよいよ本格的な示談交渉の開始です。提示された各項目の金額が、自身の受けた損害に対して妥当なものか、計算の根拠は何かを精査します。
もし提示額に納得できない場合は、その旨を保険会社に伝え、希望する金額とその根拠を示して交渉を進めていくことになります。
この交渉段階では、専門的な知識や交渉力が必要となるため、円滑に進めたい場合は弁護士などの専門家に依頼するとよいでしょう。



少しでも不安を感じるなら、一度弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
ステップ6:示談が成立したら、示談書に署名・捺印をする
双方の主張がまとまり、賠償額について合意に至ると、示談成立となります。
その後、保険会社から合意内容を記した「示談書(免責証書)」が送られてきますので、内容に間違いがないかを最終確認した上で、署名・捺印をして返送します。
示談書が保険会社に渡ると、通常1〜2週間程度で指定した口座に示談金が振り込まれます。
前述のとおり、一度示談書にサインをすると、後から「追加で損害が見つかった」などの理由でやり直すことは困難です。そのため、署名・捺印はすべての内容に納得した上で、慎重に行うようにしましょう。
交通事故の示談交渉に必要な書類と準備すべき資料
交通事故の示談交渉を適切に進め、ご自身の正当な権利を守るためには、客観的な証拠となる書類を正確に、そして漏れなく準備することが不可欠です。
ここでは、交通事故の示談交渉で必要になる書類を、「すべての事故で共通」「物損事故」「人身事故」の3つのケースに分けて、それぞれ詳しく解説します。
すべての事故で共通して必要な書類
まず、事故の種類にかかわらず、示談交渉の基本となる書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 内容 | 主な入手先 |
|---|---|---|
| 交通事故証明書 | 事故が発生した日時、場所、当事者の氏名などが記載された公的な証明書 | 自動車安全運転センター |
| 当事者の情報 | 氏名・住所・連絡先・運転免許証・車検証・加入している自賠責保険・任意保険の会社名や証明書番号など | 事故現場で相手方と交換 |
物損事故(物が壊れた事故)の場合に必要な書類
物損事故では、壊れた物の損害額を証明する書類が中心となります。
| 書類名 | 内容 | 主な入手先 |
|---|---|---|
| 修理費用の見積書・領収書 | 破損した車両や物の修理にかかる費用の見積書や、実際に支払った際の領収書 | 修理工場、ディーラー |
| 代車費用の見積書・領収書 | 修理期間中に代車を利用した場合、その費用を証明する書類 | レンタカー会社 |
| 事故車両などの写真 | 車両の損傷箇所や事故現場の状況がわかる写真 | ご自身で撮影 |
人身事故(怪我をした事故)の場合に必要な書類
人身事故では、治療関係の書類や、怪我によって生じた損害を証明する書類など多岐にわたります。
治療に関する書類は、以下のとおりです。
| 書類名 | 内容 | 主な入手先 |
|---|---|---|
| 診断書 | 医師が作成する、傷病名や治療期間などが記載された書類。警察に人身事故として届け出る際に必要です。 | 病院 |
| 診療報酬明細書 | 治療内容や投薬、検査などの詳細な医療情報が記載された書類。治療の必要性や妥当性を判断する資料になります。 | 病院 |
| 通院交通費の領収書・メモ | 通院にかかった電車代、バス代、タクシー代、ガソリン代などを証明するものです。領収書がない場合は、日時や区間を記録したメモでも代用できることがあります。 | ご自身で保管・記録 |
休業損害に関する書類は、以下のとおりです。
| 書類名 | 内容 | 主な入手先 |
|---|---|---|
| 休業損害証明書 | 会社員など給与所得者の方が、事故による怪我で仕事を休み、収入が減少したことを証明する書類です。 | 勤務先 |
| 確定申告書の控え | 自営業者や個人事業主の方が、事故による休業での損害額を証明するために使用します。基本的に事故前年の分があれば足りますが、過去数年分を用意する必要がある場合もあります。 | ご自身で保管(税務署) |
後遺障害が残った場合は、追加で以下の書類が必要になります。
| 書類名 | 内容 | 主な入手先 |
|---|---|---|
| 後遺障害診断書 | 症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)と診断された後、残った後遺症の内容を医師に作成してもらう専門の診断書です。 | 病院 |
| 後遺障害等級認定通知書 | 提出された後遺障害診断書などをもとに、専門機関が後遺障害の等級を認定した結果を通知する書類です。 | 損害保険料率算出機構 |
また、上記の必須書類に加え、以下のような資料があると、自身の主張の客観的な裏付けとなり、交渉を有利に進められる可能性があります。
- ドライブレコーダーの映像
- 実況見分調書、供述調書などの刑事記録(警察から取り寄せ)
示談交渉は、基本的に提出された書類に基づいて行われます。必要な書類が一つでも欠けていると、請求できるはずの損害が認められなかったり、交渉が長引いてしまったりする可能性があるため注意が必要です。
もし、書類の準備や内容の確認に少しでも不安を感じる場合は、一人で悩まず、交通事故問題に精通した弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の示談交渉で押さえておきたい3つのポイント
示談交渉を有利に進め、正当な権利を守るためには、事故発生当初から押さえておくべき重要なポイントがいくつかあります。知識がないまま対応してしまうと、後で不利益が生じる可能性があります。
ここでは、とくに重要な3つのポイントに絞って解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
警察に「人身事故」として届け出る
交通事故には、物が壊れただけの「物損事故」と、人が怪我をした「人身事故」の2種類があります。怪我をしているにも関わらず、警察への届け出を物損事故として処理してしまうと、後の示談交渉で不利になる可能性があります。
事故直後は興奮していて痛みに気づかなくても、後から症状が出てくるケースは少なくありません。少しでも身体に違和感がある場合は、医師の診断書を警察に提出し、「人身事故」として扱ってもらうようにしましょう。
関連記事:交通事故は「人身事故」扱いにすべき?人身事故にすべき理由や切り替え手続きを解説
医師が「治癒」「症状固定」と判断するまで治療を続ける
怪我の治療期間は、入通院慰謝料の金額を算定する上で重要な要素となります。
しかし、治療が長引いてくると、相手方の保険会社から「そろそろ治療を終わりにしませんか」と、治療費の打ち切りを打診されることがあります。
保険会社の提案に安易に応じて治療を中断してしまうと、まだ症状が残っているにも関わらず、その後の治療費は自己負担となり、慰謝料も本来より低い金額で計算されてしまいます。
「治癒」「症状固定」の判断は、保険会社ではなく、あくまで治療を担当している医師と被害者が相談のうえで行うものです。保険会社から打ち切りを打診されても、治療による症状の改善の見込があるのであれば、治療を継続しても問題ありません。
保険会社が治療の打ち切りを連絡してきたときの対処法については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた!治療費打ち切りが通達されたときの対応方法
事故直後にその場で安易に示談しない
事故現場では、加害者から「ここで示談してほしい」といった申し出を受けることがあります。しかし、事故直後の混乱した状態で、その場で示談に応じることは避けましょう。
事故直後には、怪我の程度や車の修理費用の全容はわかりません。口頭であっても一度示談が成立したとみなされると、後から新たな損害が発覚しても追加の請求が認められないリスクがあります。
交通事故の現場で少額の賠償金を提示されて、「なかったことにしてほしい」などと依頼された場合でも、その場では「保険会社を通して対応します」と伝え、警察とご自身の保険会社に連絡するようにしてください。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の示談金で重要な3つの計算基準
交通事故の損害賠償額(示談金)を計算する際には、実は3つの異なる基準が存在します。どの基準を用いるかによって、最終的に受け取れる金額が大きく変わってきます。
それぞれの特徴を理解し、ご自身がどの基準で交渉すべきかを把握しておくことが重要です。
なお、交通事故の損害賠償額を決定する方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:交通事故の損害賠償額の決め方とは?交通事故の慰謝料の計算方法を弁護士が解説
関連記事:交通事故の示談金とは?計算方法や相場・手続きの流れを弁護士が解説
自賠責基準:国が定める最低限の補償基準
自賠責基準とは、自動車の所有者に加入が義務付けられている「自賠責保険」で用いられる計算基準です。
これは、交通事故被害者に対して最低限の補償を確保することを目的として国が定めたもので、3つの基準のなかでは最も賠償額が低くなります。
たとえば、入通院慰謝料は原則として日額4,300円で計算され、傷害部分の賠償額には上限が120万円と定められています。
加害者が任意保険に加入していない場合などを除き、この基準がそのまま示談交渉で使われることは少ないですが、自賠責基準は賠償額の最低ラインであることを覚えておきましょう。
任意保険基準:保険会社独自の非公開な基準
任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険会社が、示談交渉の際に社内的に用いる独自の計算基準です。この基準は公にされておらず、各保険会社によって内容が異なります。
一般的に、自賠責基準よりは高い金額が設定されていますが、次に説明する弁護士基準(裁判所基準)には及びません。
なお、被害者本人が交渉する場合、保険会社はほとんどの場合、この任意保険基準に基づいて計算された示談額を提示してきます。
弁護士基準(裁判所基準):過去の判例に基づく最も高額な基準
弁護士基準(裁判所基準)とは、過去の交通事故に関する裁判の判例を基に算出される賠償基準です。弁護士が被害者の代理人として示談交渉を行う際や、裁判になった場合に用いられるため、このように呼ばれています。
この基準は、法的に正当な賠償額を反映したものであり、3つの基準のなかで最も高額になります。保険会社が当初提示する任意保険基準の金額と比較して、2倍以上の差が出るケースも珍しくありません。
たとえば、むちうちで通院3か月の場合、自賠責基準では慰謝料の最高額は38.7万円程度ですが、弁護士基準では53万円程度となり、2倍近い差が生じます。このように、基準ごとに金額差が大きいため、どの基準を用いるかが非常に重要です。
しかし、被害者本人が「弁護士基準で支払ってほしい」と主張しても、保険会社が応じる可能性は低いでしょう。弁護士が介入して初めて、この基準での交渉が可能になるのが実情です。



弁護士基準での示談金を求めるなら、一度弁護士に相談することが大切です。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
【ケース別】交通事故の示談交渉でよくあるトラブルと対処法
示談交渉は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。相手方の対応によっては、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。ここでは、示談交渉で起こりがちな代表的なトラブルと、その対処法について解説します。
冷静に対応するためにも、事前に知識を身につけておきましょう。
相手方(加害者・保険会社)が示談交渉に応じない場合
加害者本人やその保険会社が、話し合いに全く応じなかったり、連絡が取れなくなったりするケースがあります。
このような場合、まずは内容証明郵便を送付して、交渉を求める意思を正式な形で伝えることが有効です。
内容証明郵便は、誰が、いつ、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるため、相手に心理的なプレッシャーを与えられます。
それでも相手が応じない場合は、裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を提起したりといった、法的な手続きを検討しましょう。
示談交渉が長引いて話がまとまらない場合
示談交渉において、過失割合や損害額の算定などを巡って双方の主張が対立し、交渉が長期化することがあります。
交渉が平行線をたどるだけで進展が見られない場合は、一度専門家である弁護士に相談することが大切です。
弁護士が介入することで、法的な根拠に基づいた客観的な主張を展開できるため、相手方の保険会社も態度を改め、交渉が進展しやすくなります。
また、ADR(裁判外紛争解決手続)機関を利用したり、最終的な手段として訴訟に移行したりすることも選択肢となります。
交通事故の過失割合については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:交通事故の過失割合を徹底解説|ケース別の相場と納得できない時の対処法
相手方が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない「無保険」の状態だった場合、交渉はより困難になります。この場合、まずは加害者の自賠責保険に対して、被害者が直接損害賠償を請求する「被害者請求」という手続きを行います。
しかし、自賠責保険には支払い上限額があるため、損害額が上限を超えてしまう部分については、加害者本人に直接請求しなければなりません。加害者に支払い能力がない場合、回収は難しくなります。
このような状況に備え、自身が加入している保険の「無保険車傷害保険」や「人身傷害補償保険」が利用できないか、確認してみることが重要です。
交通事故の示談交渉でトラブルが発生した場合は、一人で悩まず弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、個々の事例を客観的に把握し、適切なアドバイスをもらえる可能性が高まります。



無料相談を実施している弁護士事務所もあるため、まずは相談してみることが大切です。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
示談交渉が成立しない場合の主な解決手段
示談交渉が成立しない場合は、主に以下の3つの解決手段が挙げられます。
以下、それぞれ具体的に解説します。
ADR(裁判外紛争解決手続)
ADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判をせずに、中立・公正な第三者機関の仲介のもとで紛争の解決を図る手続きです。交通事故の分野では、「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などが代表的なADR機関として知られています。
これらの機関では、交通事故問題に精通した弁護士などが担当者となり、無料で法律相談や和解のあっせんを行ってくれます。ADRの大きなメリットは、手続きが非公開であること、裁判に比べて迅速な解決が期待できること、そして費用が原則無料である点です。
あっせん案に双方が合意すれば和解成立となりますが、合意に至らない場合でも、審査会に審査を申し立てることが可能です。多くのADR機関では、保険会社は審査会の示す裁定に拘束されるため、被害者にとっては有利な解決につながりやすい制度といえます。
ただし、ADRはあくまで話し合いを基本とするため、相手方が出席を拒否したり、複雑な争点があったりする場合には向いていません。
裁判所での民事調停
民事調停は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員で構成される「調停委員会」が、当事者の間に入って話し合いを進め、紛争の解決をサポートする裁判所の手続きです。
ADRと同様に手続きは非公開で進められ、当事者双方が合意に至れば「調停調書」が作成されます。この調停調書は、裁判の判決と同じ効力(債務名義)を持つのが大きな特徴です。つまり、相手方が調停で決まった内容を守らない場合、この調停調書に基づいて給与の差し押さえなどの強制執行を申し立てることが可能になります。
調停は訴訟に比べて申立ての費用が安く、手続きも比較的簡単です。しかし、相手方が出頭しない場合や、話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり、最終的に訴訟で解決を目指すことになります。
加害者が任意保険に加入しておらず、話し合いがこじれている場合など、法的な強制力を持った合意を得たい場合に有効な手段です。
訴訟(裁判)
訴訟(裁判)は、ADRや調停といった話し合いでの解決が困難な場合に、裁判官が法に基づいて最終的な判断(判決)を下すことで、紛争を強制的に解決する手続きです。
最大のメリットは、相手方の意向に関わらず、確定判決が出れば紛争に終止符を打てる点です。判決には法的な強制力があり、相手が支払いに応じない場合は強制執行ができます。また、裁判官が証拠に基づいて厳密に事実認定を行うため、主張が正当に認められれば、弁護士基準(裁判所基準)で満額の損害賠償を得られる可能性が高まります。
一方で、解決までに半年から1年以上、時には数年かかることもあり、時間と労力がかかる点がデメリットです。また、弁護士費用や裁判所に納める印紙代などの費用も高額になる傾向があります。
必ずしも勝訴できるとは限らず、主張が認められなければ、相手の言い分に近い内容で判決が下されるリスクも伴います。
関連記事:交通事故の裁判はすべき?メリットや費用・期間・必要な証拠を弁護士が解説
交通事故で示談交渉をする際の注意点
示談交渉に臨むにあたっては、ご自身の権利を守るために、いくつか重要な注意点があります。交通事故の示談交渉の注意点は、主に以下の4つです。
ここで挙げる注意点をしっかり意識して、交渉に臨みましょう。
提示された過失割合が妥当か必ず確認する
過失割合とは、発生した交通事故の責任が、当事者それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したものです。
たとえば、ご自身の過失割合が1割(10%)とされた場合、損害の総額から1割が減額されてしまいます。
保険会社が提示する過失割合は、必ずしも客観的で正しいとは限りません。
ドライブレコーダーの映像や事故現場の状況、過去の判例などに基づいて、提示された割合が妥当なものかしっかりと確認する必要があります。
安易に同意せず、納得できない場合はその根拠を明確に求めることが重要です。
関連記事:交通事故の過失割合納得いかない!適正化を弁護士に任せるべき理由
出典:e-Gov法令検索|民法
相手の提示額を鵜呑みにせず、増額の根拠を示す
前述のとおり、保険会社が最初に提示する示談金の額は、法的に正当な基準である「弁護士基準(裁判所基準)」よりも低く抑えられているのが通常です。
従って、提示された金額をそのまま受け入れる必要はありません。
なぜ増額が必要なのか、その具体的な根拠を提示して交渉することが大切です。客観的な証拠や法的な基準に基づいて主張することで、交渉を有利に進められるでしょう。
交渉の記録をすべて残しておく
保険会社の担当者とのやり取りは、後々のトラブルを防ぐためにも、その内容をすべて記録しておくことが重要です。
電話で話した場合は、「いつ、誰と、どのような内容を話したのか」を詳細にメモしておきましょう。可能であれば、重要なやり取りは書面(メールやFAXなど)で行うのが確実です。
口頭での約束は、後になって「言った」「言わない」という水掛け論になりがちです。交渉の過程で不利な言質を取られないため、万が一交渉が決裂して調停や裁判に進んだ場合の証拠とするためにも、交渉記録の保管は徹底しましょう。
示談交渉の時効(期間)を常に意識する
交通事故の損害賠償請求権には、「時効」という期限が定められています。この期間を過ぎてしまうと、たとえ損害があったとしても、加害者や保険会社に対して賠償を請求する権利が消滅してしまいます。
時効の期間は、物損事故の場合は被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、人身事故の場合は5年です(民法第724条、民法第724条の2)。
示談交渉が長引いている間に、気づいたら時効が目前に迫っていたという事態は避けなければなりません。
交渉が難航している場合は、常に時効の期限を意識しておくことが重要です。
時効期間が経過しそうになっている場合、一定の行為を行うと時効とならない制度があります(時効の完成猶予・更新)。代表的なものとして訴訟を提起することが挙げられます。



時効期間が迫っているような場合には示談交渉をするのではなく早めに裁判を定期することも検討しましょう。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
交通事故の示談交渉は、自身で行うことも不可能ではありません。
しかし、保険会社の担当者は、日々多くの事故処理を対応する交渉のプロです。知識や経験に乏しい個人が対等に渡り合うのは、決して容易ではありません。
示談交渉の際、専門家である弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得られます。
以下、それぞれ詳細に解説します。
慰謝料が「弁護士基準」となり、示談金の大幅な増額が期待できる
弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料の算定基準として高額な「弁護士基準(裁判所基準)」を用いて交渉できる点です。
前述のとおり、保険会社が提示する「任意保険基準」と「弁護士基準」とでは、賠償額に2倍以上の差がつくことも珍しくありません。
弁護士が代理人として交渉の場に立つことで、保険会社も法的に正当な基準で対応せざるを得なくなります。
結果として、被害者ご本人が交渉するよりも、最終的に受け取れる示談金が大幅に増額される可能性が高まります。
不利な過失割合を修正できる可能性がある
示談交渉における大きな争点の一つが「過失割合」です。保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合でも、個人でその主張を覆すのは困難なことが多いです。
その点、交通事故案件に精通した弁護士であれば、事故状況の客観的な証拠や過去の裁判例に基づき、法的な観点から相手方の主張の矛盾点を突き、より有利な過失割合へと修正できる可能性があります。
過失割合が1割変わるだけでも、最終的な受け取り額は大きく変動するため、このメリットは大きいといえるでしょう。
関連記事:事故で過失割合9対1に納得いかない場合の対処法は?応じるリスクや注意点を解説
保険会社との交渉や書類準備をすべて任せられる
交通事故の被害に遭われた方は、怪我の治療や仕事への復帰など、ただでさえ心身ともに大きな負担を強いられています。そのような状況で、専門用語が飛び交う保険会社との交渉や、煩雑な書類の準備まで行うのは、精神的に大きなストレスとなります。
弁護士に依頼すれば、こうした一連の手続きをすべて代行してもらえます。被害者の方は交渉の矢面に立つ必要がなくなり、治療や日常生活の回復に専念できます。



精神的な負担が軽減されることも、弁護士に依頼する重要なメリットです。
交通事故の際に弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてみてください。
関連記事:交通事故で弁護士に依頼するメリットは?デメリットや依頼の適切なタイミングも解説
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
交通事故の示談交渉に関するよくある質問
ここでは、交通事故の示談交渉に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。
示談交渉はいつから始めるべき?
示談交渉を始めるべきタイミングは、治療を終了した後からです。
上述の示談の流れでもあったように、治療が終わって治癒もしくは症状固定となると、損害額が確定します。そのため、その時点で示談交渉を開始するのがタイミングとしては適切です。
治療費や生活費などに困って示談をしたいと保険会社に持ちかけると足元を見られて極めて不利な条件で示談をさせられかねません。お金に困った場合には一定額の前払いを請求できることもあるので、まずは弁護士に相談してみてください。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
示談解決までにかかる平均的な期間はどのくらい?
示談で解決するまでにかかる期間は、事故の態様によって大きく異なります。物が壊れただけの物損事故であれば、2〜3か月程度で終わることが多いです。
一方、怪我を伴う人身事故で後遺障害が残らなかった場合は、治療期間にもよりますが、半年から8か月程度が目安となります。
なお、後遺障害が残って等級認定の手続きが必要なケースや、死亡事故のケースでは交渉が複雑化するため、結果的に1年以上かかるケースも珍しくありません。
交通事故の慰謝料がいつもらえるか気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払い時期や流れ・早く受け取る方法を弁護士が解説
関連記事:交通事故の示談期間はどれくらい?ケース別の目安期間や長引く原因・短縮方法を解説
弁護士なしで示談交渉はできる?
弁護士に依頼せず、自身で示談交渉を行うこと自体は可能です。
しかし、相手方の保険会社は、裁判になった場合に受け入れられない、任意保険基準を用いた損害額の算定や過失割合を主張して、自社に有利な条件で交渉を進めようとします。
このような主張に対して、法律や過去の判例に関する専門知識を駆使して反論して合意できなければ適切な損害賠償を得られません。
知識や経験で劣る個人が、交渉のプロである保険会社を相手に、法的に正当な賠償額を勝ち取るのは難しいのが現実です。
弁護士なしで交通事故の示談交渉をするリスクや注意点については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:交通事故の示談交渉は自分でできる?考えられるリスクや注意点を徹底解説
関連記事:弁護士に依頼すると交通事故の解決までの期間は早くなる?期間の目安・早くなる理由を解説



少しでも不安を感じるなら、一度弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
まとめ|適切に示談交渉をするためにも、一人で悩まず専門家に相談することが大切
この記事では、交通事故の示談交渉について、手続きの流れから重要なポイント、注意点までを解説しました。
交通事故の示談交渉は、今後の生活に影響を及ぼす重要な手続きです。相手方保険会社の提示する条件が、必ずしも適切なものとは限りません。むしろ、専門知識がなければ気づかないうちに、不利な条件で合意させられてしまうリスクも潜んでいます。
もし、保険会社の対応に疑問を感じたり、提示された示談金の額に納得がいかなかったりした場合は、決して一人で抱え込まず、交通事故問題の専門家である弁護士に相談しましょう。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにお任せください。
交通事故案件の経験豊富な弁護士が、適正な賠償額を獲得できるようサポートします。
初回60分の無料相談も実施しているので、お気軽にご相談ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応








