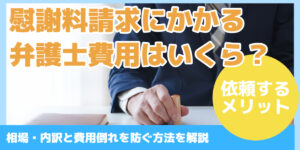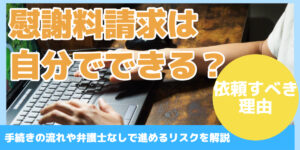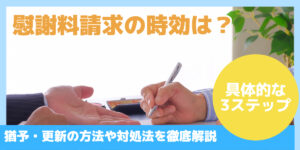離婚後でも慰謝料は請求できる!条件や時効・相場を弁護士が徹底解説

「離婚後に慰謝料の請求はできない?」
「離婚後の慰謝料請求が難しいケースはある?」
離婚当時は精神的に追い詰められていて考えが及ばなかったり、後になってから元配偶者の不貞行為といった許しがたい事実が発覚したりすることもあるでしょう。
その際、「もう手遅れだ」と諦めてしまう人は少なくありません。しかし、離婚後であっても、慰謝料を請求できる可能性があります。
この記事では、離婚後でも慰謝料請求ができる条件や、できないケースを解説します。また、離婚後の慰謝料請求のやり方や弁護士に依頼するメリットも解説します。
離婚後の慰謝料請求について悩んでいるなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
離婚問題に詳しい弁護士が状況を丁寧にヒアリングし、適切な解決策を一緒に考えます。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご連絡ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚後の慰謝料請求は可能|まずは3つの必須条件をチェック
離婚後の慰謝料請求は、決して不可能なことではありません。しかし、感情だけを根拠に請求が認められるわけではなく、法律上の要件をクリアする必要があります。
請求を具体的に検討する前に、まずは土台となる3つの必須条件を満たしているかの確認が不可欠です。
以下、それぞれ具体的に解説します。
条件1:慰謝料請求の「時効」が成立していないか
慰謝料請求権は、永久に存在する権利ではありません。法律で定められた「時効」という期間制限があり、この期間を過ぎると権利が消滅してしまいます。
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
まず、被害者が不法行為による損害と加害者を知った時から3年が経過すると、時効が成立します。離婚自体に対する慰謝料である場合、離婚成立時が「知った時」となり、離婚成立から3年間が時効期間です。
一方、離婚そのものではなく、離婚の原因である不法行為について慰謝料を請求する場合は、不法行為事実と加害者を知ったときから3年間が時効期間となります。
また、不貞行為の相手方(不倫相手)への慰謝料請求権には、独自の時効が存在します。「不倫の事実」と「不倫相手の氏名など個人を特定できた時」から3年間です。
元配偶者への請求権が時効になっても、不倫相手への請求は可能なケースもあると覚えておきましょう。
| 離婚自体に対する慰謝料 | 離婚そのものによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。時効は「離婚が成立した日」から3年間となります。 |
|---|---|
| 離婚の原因に対する慰謝料 | 離婚の原因となった個別の不法行為(不貞行為やDVなど)に対する慰謝料です。時効は、「不法行為の事実とその加害者を知った時」から3年間です。(人の生命又は身体を害する不法行為は、知った時から5年間) |
| 不貞行為の相手方(不倫相手)への慰謝料 | 元配偶者の不貞は知っていても相手が誰か分からなかった場合、相手を特定できた時点から新たに3年の時効が始まります。 |
なお、いずれの請求権も、不法行為の時から20年という長期の時効期間も設定されています。
関連記事:慰謝料請求の時効は?猶予・更新の方法や時効が過ぎた際の対処法を徹底解説
関連記事:不倫の時効は何年?起算点や時効完成を止める方法を弁護士が解説
条件2:離婚時に「慰謝料を請求しない」という合意をしていないか
離婚時に作成する離婚協議書や公正証書には、「清算条項」が盛り込まれるのが一般的です。
この条項に合意した場合、原則として、後から慰謝料を請求できません。当事者間の紛争を最終的に解決し、将来の蒸し返しを防ぐための重要な取り決めだからです。
ただ、合意の前提となる重要な事実が、一方の当事者によって意図的に隠されていた場合は例外です。
たとえば、夫が妻に不貞行為の事実を隠したまま離婚を促し、清算条項を含む離婚協議書にサインさせた場合、妻は清算条項を含む合意の無効を主張できる可能性があります。
ただし、「不倫を疑っていたけれど、追及せずに合意してしまった」というようなケースでは、錯誤の主張が認められるのは難しくなります。あくまで、合意の判断の基礎となる事実を知らず、相手に騙されて権利を放棄してしまったといえるような状況が必要です。
もっとも、離婚時の清算条項については夫婦間のもので、不倫相手にまで効力は及びません。そのため、不倫相手には請求が可能です。
条件3:相手の「不法行為」を証明できるか
慰謝料とは、相手の「不法行為」によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
慰謝料を請求するためには、相手に法律上「不法行為」と評価される行為があったことを、請求する側が証明しなければなりません。この立証責任は、全面的に請求者にあります。
慰謝料請求の根拠となる主な不法行為には、以下のようなものがあります。
| 不貞行為(浮気・不倫) | 配偶者以外の異性と肉体関係(性交渉またはそれに類する行為)を持つことを指します。 食事やデートをしていただけでは、原則として不貞行為として認められません。 |
|---|---|
| DV(ドメスティック・バイオレンス)・モラハラ | 殴る蹴るといった身体的暴力や、人格を否定するような暴言を繰り返し浴びせるなどの精神的虐待のことを指します。 |
| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく同居を拒否したり、生活費をまったく渡さなかったりと、夫婦の協力・扶助義務を意図的に放棄する行為を指します。 |
これらの行為があったという事実を客観的な証拠によって証明することが、慰謝料請求をするうえで重要です。
離婚後の慰謝料請求が難しい・できない4つのケース
離婚後の慰謝料請求ができないケースも存在します。希望的観測だけで行動を起こす前に、請求が困難または不可能となる典型的なケースを理解し、自身の状況を冷静に分析することが重要です。
主なケースは、以下のとおりです。
以下、それぞれ具体的に解説します。
ケース1:離婚原因が「性格の不一致」など一方に責任がない場合
離婚調停申立時の申立の動機として多く選択される「性格の不一致」は、法律上、どちらか一方に責任があるとはいえない「ノーフォルト(無責)」の離婚原因とされています。
慰謝料は、相手の有責な不法行為によって生じた精神的苦痛を賠償するもののため、そもそもどちらにも法的な責任がないのであれば、慰謝料請求権は発生しません。
ただし、調停申立書に記載された理由と、実際の離婚原因が異なる場合には注意が必要です。
相手の不貞行為が許せず離婚に至ったものの、事を荒立てたくないために「性格の不一致」として申し立てるケースは少なくありません。
このような場合、たとえ書類上は無責の離婚であっても、不貞行為があったことを後から証拠で立証できれば、慰謝料の請求は可能です。
ケース2:慰謝料請求の権利を放棄する「清算条項」に合意している場合
前述の通り、離婚時に清算条項を含む合意書に署名・押印した場合、原則としてその合意は有効であり、後からの請求はできなくなります。
たとえば、相手の不貞行為を離婚前から知っていたにもかかわらず、早期に離婚を成立させたいといった理由から、追及せずに清算条項に合意したとします。
この場合、不貞行為という事実を知りながら、それに対する慰謝料請求権を自らの意思で放棄したと判断される可能性が高くなります。
後になって「やはり慰謝料が欲しい」と考え直しても、一度有効に成立した合意を覆すことは、原則として不可能です。
ケース3:慰謝料請求の根拠となる「証拠」が一切ない場合
慰謝料請求は、請求者の主張だけでは成り立ちません。
相手方が「そんな事実はなかった」と否定した場合、請求者側が不法行為の存在を客観的な証拠によって証明する必要があります。
証拠が一切なければ、たとえそれが事実であっても、裁判所は不法行為の存在を認定できません。結果として、請求は棄却されてしまいます。
ケース4:すでに夫婦関係が破綻していた場合
不貞行為を理由に慰謝料を請求された側が、法的に反論する際の強力な主張の一つに、「不貞行為が始まる前に、すでに夫婦関係は破綻していた」というものがあげられます。
法律上、不貞行為が不法行為となるのは、「婚姻共同生活の平和の維持」という法的に保護されるべき利益を侵害することだからです。
不貞行為の時点で夫婦関係が修復不可能なほどに壊れており、「保護すべき婚姻共同生活の平和」が存在しなかったと判断されれば、その後の不貞行為は不法行為とはなりません。また、慰謝料請求権も発生しません。
ここで重要なのは、「破綻」が単なる感情的なすれ違いや夫婦喧嘩の多さではなく、客観的な事実によって判断される法的概念という点です。
たとえば、長期間に渡る別居期間があれば、破綻していたとされる可能性があります。一方で、生活費のやり取りがあったり、時折食事をしたりしていれば、破綻しているとは認められない可能性が高いです。
【原因別】離婚後の慰謝料の相場はどれくらい?
慰謝料を請求するうえで気になるのが「一体いくら受け取れるのか」という点です。慰謝料の金額は、法律で一律に定められているわけではなく、個別の事情を総合的に考慮して決定されます。
しかし、過去の裁判例から、離婚原因に応じた「相場」が存在します。この相場は、交渉や裁判を進める上での重要な指標となるでしょう。
不貞行為(浮気・不倫)が原因の場合
配偶者の不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、150〜300万円程度です。
一方、不貞行為はあったものの離婚には至らなかった場合の相場は50〜100万円程度と、離婚した場合に比べて低くなる傾向があります。
不貞行為による慰謝料は、状況によって異なります。慰謝料が高額になりやすいケースは、主に以下のとおりです。
- 婚姻期間が長い場合
- 不貞行為の期間が長く、回数も多い場合
- 不倫相手が妊娠・出産した場合
- 請求された側に十分な資力や高い社会的地位がある場合
- 不貞行為が原因で、うつ病などの精神疾患を患った場合
これらの要素は、請求者が受けた精神的苦痛の大きさを客観的に示す指標として、裁判所が金額を算定する際に重視します。
DV・モラハラが原因の場合
配偶者からのDV(身体的暴力)やモラハラ(精神的虐待)を理由に離婚する場合の慰謝料相場は、50〜100万円程度です。
DV・モラハラによる慰謝料も、状況によって変わります。入院・後遺障害が発生した場合は、150万円を超える可能性もあります。
慰謝料が高額になりやすいケースは、主に以下のとおりです。
- 暴力が頻繁に行われている場合・長期間にわたっている場合
- 凶器が使われた場合・生命の危険を感じるほどの暴力だった場合
- 骨折などの深刻な傷害を負った場合・後遺症が残った場合
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)など、重い精神疾患と診断された場合
- 子供の前で暴力や暴言が繰り返された場合
DV・モラハラの慰謝料請求で重要なのは、客観的な証拠の存在です。医師の診断書や怪我の写真、警察への相談記録などがある場合、請求者の主張の信憑性が格段に高まり、慰謝料額も高額になる傾向があります。
悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)が原因の場合
正当な理由なく生活費を渡さなかったり、一方的に家を出て同居を拒否したりといった「悪意の遺棄」が原因で離婚する場合の慰謝料相場は、50〜300万円程度です。
以下のような場合、悪意の遺棄による慰謝料が高額になりやすい傾向があります。
- 遺棄された期間が長い場合
- 遺棄された側に幼い子供がいて、生活が困窮した場合
- 遺棄された側に収入がなく、経済的に追い詰められる場合
- 悪意の遺棄に加えて不貞行為も行われていた場合(例:家を出て不倫相手と同棲していた)
とくに、悪意の遺棄と他の不法行為が同時に行われていた場合、それぞれの行為の悪質性が考慮され、慰謝料はより高額になる可能性があります。
離婚の慰謝料相場については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:離婚の慰謝料の相場はどのくらい?離婚の原因別の金額や請求手順を弁護士が解説
離婚後の慰謝料請求のやり方|証拠集めから支払いまでの4ステップ
離婚後に慰謝料を請求すると決意した場合、感情的に相手に連絡を取るのではなく、法的な手続きに沿って冷静かつ戦略的に進めることが成功の鍵となります。ここでは、証拠集めから始まり、最終的な支払いを受けるまでの標準的な4つのステップを解説します。
この流れを理解することで、今自分がどの段階にいて、次に何をすべきかを明確にすることが可能です。以下、それぞれ具体的に解説します。
ステップ1:慰謝料請求の証拠を集める
慰謝料請求をする際は、「証拠を確保する」ことから始めましょう。請求の意思を始めに伝えると、相手が警戒して証拠を隠滅したり、破棄したりする危険性が高いからです。
適切な慰謝料を獲得するためには、請求の根拠となる不法行為を客観的に証明できる証拠をできる限り多く入手することが大切です。証拠を隠蔽・破棄されないよう、相手に慰謝料請求の意思を伝える前に証拠を集めておきましょう。
どのような証拠が有効かについては、後の章で詳しく解説します。
ステップ2:相手方との話し合い(交渉)を行う
証拠がある程度集まったら、次は元配偶者との話し合い(交渉)を試みます。この段階で相手が事実を認め、支払いに応じる姿勢を見せれば、迅速かつ低コストで解決できる可能性があります。
もし話し合いで合意に至った場合は、その内容を「合意書」や「示談書」といった書面に残すことが大切です。口約束だけでは、後で「言った、言わない」のトラブルになりかねません。
特に、慰謝料が分割払いになる場合は、支払いが滞った際に強制執行ができるよう、合意書を「公正証書」の形で作成しておきましょう。
ステップ3:内容証明郵便で正式に慰謝料を請求する
直接の話し合いで相手が請求を無視したり、不誠実な対応に終始したりする場合は、次の手段として「内容証明郵便」を送付します。
内容証明郵便には、支払いを法的に強制する力はありません。しかし、時効が迫っている場合に「請求(催告)」を行った証拠となり、時効の完成が6ヶ月間猶予される効果があります(民法第150条)。
また、相手に「本気で請求してきている」「次は裁判になるかもしれない」と心理的なプレッシャーを与えることも可能です。
ステップ4:裁判所での調停・訴訟を申し立てる
内容証明郵便を送っても相手が支払いに応じなかったり、交渉が決裂したりした場合は、裁判によって解決しなければなりません。
手続きは通常、「調停」から始まります。裁判所に「慰謝料請求調停」を申し立てると、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら、話し合いによる合意形成を目指します。
もし調停でも合意に至らず「不成立」となった場合は、「訴訟」を提起しましょう。訴訟では、当事者双方の法的な主張と証拠をもとに裁判官が事実を認定し、慰謝料の支払い義務の有無や金額について「判決」という形で法的な判断を下します。
判決には強制力があるため、相手が支払わない場合は、預金や給与などの財産を差し押さえる強制執行が可能です。
離婚後の慰謝料請求について悩んでいるなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
離婚問題に詳しい弁護士が状況を丁寧にヒアリングし、適切な解決策を一緒に考えます。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご連絡ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚後の慰謝料請求で有効な証拠の種類
慰謝料請求は、不法行為の存在をどれだけ客観的に証明できるかが重要です。ここでは、代表的な不法行為の証明に有効な証拠の種類とそのポイントを解説します。
以下、それぞれ詳細に解説します。
録音・録画データ
音声や映像による記録は、強力な証拠の一つです。相手の言葉や行動そのものが記録されているため、言い逃れができません。
以下のような録音・録画データを残しておきましょう。
- 元配偶者が不貞行為の事実を認める会話の録音
- モラハラにあたる暴言や人格否定発言の録音
- DVの現場を撮影した動画
相手の同意なく録音・録画したデータも、民事裁判では証拠として認められるケースがほとんどです。
ただし、証拠を得るために住居侵入などの犯罪行為を行った場合は、その証拠の有効性が否定されるリスクがあります。
また、逆にこちらが刑事責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
メール・LINEなどのメッセージ
現代において、メール・LINEなどのメッセージの履歴は不法行為を裏付ける重要な証拠の一つです。
主な例として、以下のものがあげられます。
- 不倫相手と性交渉があったことを示すやり取り
- 二人で旅行や宿泊したことがわかるメッセージ
- DVやモラハラに該当する脅迫的なメッセージや罵倒の言葉
メッセージのやり取り全体を、日付や送受信者がわかるようにスクリーンショットなどで保存することが重要です。
断片的なメッセージよりも、前後の文脈がわかる方が証拠としての価値が高まります。
診断書や精神科・心療内科の通院履歴
診断書や精神科、心療内科の通院履歴は、DVやモラハラによって受けた心身のダメージを医学的に証明する客観的な証拠です。不法行為の存在だけでなく、それによって生じた損害の大きさを立証できます。
主な例は、以下のとおりです。
- DVによる怪我(打撲、骨折など)に関する医師の診断書
- 夫の不貞やモラハラが原因で発症した、うつ病・適応障害・PTSDなどに関する精神科医の診断書
診断書に、怪我や病気と不法行為の因果関係を記載してもらうことで、証拠価値はさらに高まります。
精神的な不調を感じたら、我慢せずに早期に専門医を受診することが重要です。
第三者の証言
当事者以外の人物による証言も、主張を補強する証拠となり得ます。
主な例は、以下のとおりです。
- 元配偶者と不倫相手がラブホテルに入るのを目撃した友人・知人の証言
- DVの現場を目撃した親族や隣人の証言
- 元配偶者本人から不倫の事実を打ち明けられた同僚の証言
第三者の証言は裁判では証言内容を書面にした「陳述書」として使用したり、証人尋問で法廷で証言してもらうことで証拠として利用します。
警察や公的支援機関への相談記録
DVや深刻なモラハラの場合、公的機関への相談記録は、被害の事実と経緯を裏付ける信頼性の高い証拠となります。
主な例は、以下のとおりです。
- DV被害で警察に通報した際の110番通報記録や、作成された被害届
- 配偶者暴力相談支援センターなどへの相談記録
これらの記録は、被害が一度きりのものではなく、継続的であったことを示す上でも有効です。
被害に遭った際には、一人で抱え込まずに公的機関に相談することが重要になります。
離婚後の慰謝料請求は弁護士に相談すべき?依頼するメリットを解説
離婚後の慰謝料請求は、法的な知識と戦略が求められます。一人で立ち向かうことも不可能ではありませんが、多くの困難が伴うでしょう。
ここからは、離婚後の慰謝料請求をする際に法律の専門家である弁護士に相談・依頼することの具体的なメリットを解説します。
以下、それぞれ詳しく解説します。
メリット1:時効の管理や法的に有効な証拠集めのアドバイスがもらえる
離婚後の慰謝料請求における障壁の一つが「時効」です。前述の通り、請求の種類によって時効の起算点や期間が異なり、管理は複雑です。
弁護士に相談すれば、正確な時効の期限を算出し、期限が迫っている場合には内容証明郵便の送付など、時効の進行を止めるための適切な手続きを迅速に行ってくれます。
また、「どのような証拠が、どの程度の証明力を持つか」を法的な観点から的確に判断し、より強力な証拠を確保する方法についてアドバイスも受けられます。
法廷で通用する質の高い証拠を効率的に集める手助けとなるでしょう。
メリット2:精神的負担が大きい相手との交渉をすべて任せられる
離婚の原因となった元配偶者と金銭が絡む交渉を直接行うことは、想像を絶する精神的負担を伴います。
特に相手が不誠実であったり、高圧的であったりする場合、冷静な話し合いは困難を極め、交渉のストレスから心身に不調をきたしてしまう方も少なくありません。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの「代理人」として、相手方とのすべての連絡や交渉の窓口となります。あなたは相手と直接顔を合わせたり、話したりする必要がなくなります。
法的な根拠に基づき、感情的にならずに淡々と交渉を進める弁護士が間に入ることで、相手も冷静にならざるを得なくなり、話し合いがスムーズに進展する可能性が高まります。
この精神的負担の軽減こそが、弁護士に依頼するメリットの一つといえるでしょう。
メリット3:調停や裁判で適切に対応でき、適正な慰謝料を獲得しやすくなる
調停では、調停委員を論理的に説得するための主張の組み立てが欠かせません。裁判になれば、法律のルールに則った書面(訴状、準備書面など)を作成して証拠を提出し、的確に法的な主張を行う必要があります。
これらの手続きを一般の方が一人で行うのは困難です。弁護士に依頼すれば、これらの複雑な手続きをすべて代行してもらえます。過去の裁判例や法理論に基づき、あなたのケースで有利な主張を構成し、適正な慰謝料額を算出して請求します。
法廷での尋問などにも適切に対応できるため、結果として、一人で進めるよりも正当な慰謝料を獲得できる可能性が格段に高まるでしょう。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:離婚の際は弁護士に依頼を―プロに依頼するべきその理由とは―
関連記事:離婚の弁護士費用はいくら?相場や内訳・払えない場合の対処法を弁護士が解説
離婚後の慰謝料請求について悩んでいるなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
離婚問題に詳しい弁護士が状況を丁寧にヒアリングし、適切な解決策を一緒に考えます。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご連絡ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚後の慰謝料に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、離婚後の慰謝料請求に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。
離婚後に請求できるお金は慰謝料以外にある?
慰謝料以外にも、離婚後に請求できる可能性のあるお金はいくつかあります。ただし、それぞれに慰謝料とは異なる請求期限(時効や除斥期間)が定められているため注意が必要です。
以下、慰謝料以外に請求できる可能性があるものと、その特徴・請求期限を表にまとめました。
| 財産分与 | 婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産(預貯金、不動産、保険など)を公平に分ける制度です。 離婚原因がどちらにあるかは関係なく請求できます。 請求期限は、離婚成立から2年です。 |
|---|---|
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金(または共済年金)の保険料納付記録を分割する制度です。 これにより、将来受け取る年金額を調整します。 請求期限は、原則として離婚成立から2年です。 |
| 養育費 | 未成年の子供がいる場合、子供が経済的に自立するまで(通常は成人もしくは大学を卒業するまで)親権者でない方の親が支払うべき子供の生活費や教育費です。 離婚時に取り決めをしていなくても、後から請求できます。 また、一度決めた後でも、双方の経済状況の変化などに応じて増額や減額を求めることも可能です。 |
証拠がなくても慰謝料は請求できる?
慰謝料を「請求する(求める)」こと自体は、証拠がなくても可能です。しかし、相手が不法行為の事実を否定し、支払いを拒否した場合、証拠がなければ法的に支払いを強制できません。
裁判になった場合、不法行為があったことを証明する責任は、請求する側にあります(立証責任)。もし相手が事実を認めて任意に支払いに応じるのであれば、証拠は不要です。
しかし現実は、支払いを免れるために事実を否定するケースがほとんどです。そのため、裁判で慰謝料を獲得するためには、客観的な証拠が不可欠といえるでしょう。
慰謝料にも税金はかかる?
原則として、離婚慰謝料に税金(所得税や贈与税)はかかりません。慰謝料は、不法行為によって受けた精神的損害を賠償するためのもので、新たな利益を得る「所得」や、無償で財産をもらう「贈与」とは性質が異なると考えられているためです。
ただし、例外的に課税対象となるケースがあります。
| 額が社会通念上、あまりにも高額な場合 | 慰謝料の相場を大幅に超える金額を受け取った場合、その超過分が実質的な贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。 |
|---|---|
| 不動産や有価証券などで支払われた場合 | 金銭ではなく不動産などの資産で慰謝料が支払われた場合、支払った(譲渡した)側に、その資産の取得時からの値上がり益に対して譲渡所得税が課されることがあります |
| 相続税や贈与税を免れるための偽装離婚とみなされた場合 | 慰謝料の支払いが、実質的には税金逃れのための財産移転と税務署に判断された場合は、課税対象となります。 |
上記のケースを理解して、適切に税金の処理を行いましょう。
不倫相手にも離婚後に慰謝料を請求できる?
元配偶者の不貞行為が原因で離婚した場合、その不倫相手に対しても離婚後に慰謝料請求が可能です。
法律上、共同で不法行為を行った者(この場合は元配偶者と不倫相手)は、「共同不法行為者」として、被害者が被った損害全額に対して連帯して賠償責任を負うとされています。
なお、元配偶者との間で交わした「清算条項」の効力は、原則として不倫相手には及びません。そのため、元配偶者に対しては慰謝料を請求しないと合意した場合でも、不倫相手には慰謝料の請求が可能です。
不倫相手に慰謝料を請求する方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
まとめ|離婚後の慰謝料請求は一人で悩まず、専門家に相談しよう
この記事では、請求が可能となる条件や具体的な手続きの流れなどを解説しました。
離婚後の慰謝料請求には、「時効」「過去の合意」「証拠」の3つの条件があります。3つの条件を満たしていれば、離婚後であっても慰謝料を請求することが可能です。
しかし、実際に行動に移し、複雑な交渉や法的手続きを乗り越えていくためには、専門的なサポートが欠かせません。一人で悩まず、まずは弁護士に相談することから始めましょう。
離婚後の慰謝料請求について悩んでいるなら、「弁護士法人アクロピース」にお任せください。
離婚問題に詳しい弁護士が状況を丁寧にヒアリングし、適切な解決策を一緒に考えます。
初回60分の無料相談も実施しているので、まずはお気軽にご連絡ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応