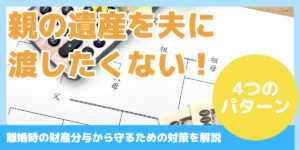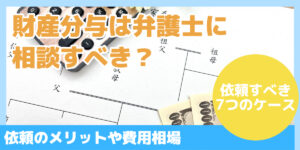財産分与の対象にならないものとは?相続遺産や親からの贈与を守る方法【弁護士監修】

「離婚するにあたって、親から相続した財産まで渡さなければならないのだろうか」
「結婚前から必死に貯めた自分のお金は、どこまで守れるのだろうか」
離婚の財産分与において、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
離婚時の財産分与において、自分自身が個人的に取得した財産(特有財産)は、相手方に渡す必要はありません。財産分与の対象となるのは、あくまでも夫婦の協力により築いた「共有財産」のみであるためです。
この記事では、財産分与の基本的な仕組みから、対象にならない財産(特有財産)の具体的な種類、そしてその大切な財産を守り抜くための具体的な方法まで、専門的な視点から解説します。
離婚にあたり、ご自身の大切な財産を守る参考にしてください。
離婚時の財産分与でお悩みの方は、離婚問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は、相談実績1000件以上の高い専門性を持っております。
一人で悩まず、まずは初回60分無料の電話相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
そもそも財産分与とは?共有財産と特有財産の違いも解説
離婚時の財産分与を正しく理解するには、法律上の重要な二つの概念「共有財産」と「特有財産」の違いの理解が欠かせません。
ここからは、財産分与制度の基本となる2種類の財産について、法的な背景とともに解説します。
関連記事:離婚時の財産分与はどうなる?家や貯金の分け方・手続きの流れを弁護士が解説
財産分与は婚姻中に協力して築いた財産を公平に分ける制度
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて離婚時に公平に分配する制度です。(参照:法務省|財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
引用:民法|768条
また、財産分与には、目的が異なる以下3つの要素が含まれます。
| 要素 | 概要 |
|---|---|
| 清算的財産分与 | 婚姻中に協力して築いた財産を清算する、財産分与の最も中心的な要素 |
| 扶養的財産分与 | 離婚によって一方の配偶者が経済的に困窮する場合に、その生活を支えるために補完的に行われるもの |
| 慰謝料的財産分与 | 一方の不貞行為などが原因で離婚に至った場合に、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の要素を含めて財産分与を行うもの |
この制度は、夫婦の一方のみに収入がある場合でも、他方の家事・育児により財産形成が可能になったという考えに基づいています
したがって、夫婦の収入に差がある、一方が専業主婦(主夫)であるなどのケースでも財産形成への貢献度は平等とみなされ、原則として財産を半分ずつ分ける「2分の1ルール」が適用されます。
夫婦で協力して築いた「共有財産」は財産分与の対象
財産分与の対象となるのは、「共有財産」と呼ばれるものです。共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して得たすべての財産を指します。
例えば、預貯金、不動産、自動車や株式だけでなく、退職金も対象となります。
ここで最も重要な点は、財産の名義が夫婦のどちらか一方になっていても、その原資が婚姻中の収入である限り、実質的には共有財産とみなされることです。(参照:裁判所|財産分与請求調停)
例えば、給与が振り込まれる一方の名義の預金口座も、その給与は配偶者による家事や育児に支えられて得られたものであるため、夫婦の共有財産となります。名義という形式ではなく、その財産が「夫婦の協力によって得られたか」という実質で判断されるのです。
共有財産が多く、トラブルになりやすい熟年離婚については以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:熟年離婚の財産分与はどうすべき?具体的な進め方や起こりやすいトラブルを解説【弁護士監修】
個人の努力や親族の協力で得た「特有財産」は対象にならない
共有財産とは対照的に、財産分与の対象にならない財産を「特有財産」と呼びます。これは、民法762条で定められており、夫婦の協力とは無関係に、一方の配偶者が個人的に取得した財産を指します。(参照:民法|762条)
例えば、独身時代の預貯金や、婚姻後に相続した財産などです。これらの財産は、配偶者の協力なくして得られたものであるため、財産分与の対象になりません。
特有財産を守るには「証拠」が欠かせません。
例えば、婚姻前の預金は婚姻前の通帳コピー、相続した財産は遺産分割協議書や遺言書、親からの贈与は振込明細や贈与契約書を残しておくことが大切です。証拠がなければ、実際には特有財産でも共有財産と推定されてしまうリスクがあります。(参照:民法|762条の2)
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫「これは結婚前から持っていたお金だ」と口で主張するだけでは、法的に不十分です。本来なら特有財産であるものも、証拠がなければ共有財産として扱われ、分与の対象となるリスクがあるのです。
【一覧】財産分与の対象にならないもの(特有財産)とは?
財産分与の対象にならない「特有財産」の例は、以下のとおりです。
しかし、いずれのケースにおいても「特有財産である」と法的に認められるには、客観的な証拠が必要です。財産の種類ごとに、それぞれの性質や注意点を知っておきましょう。
婚姻前から持っていた個人の財産
結婚する前に各自が所有していた以下のような財産は、典型的な特有財産です。
- 独身時代に貯めた預貯金
- 一人暮らしの際に購入した家具
- 結婚前に購入した不動産や自動車など
これらは夫婦の協力とは無関係に形成された資産であるため、財産分与の対象外となります。
ただし、婚姻前に取得した財産であっても、婚姻後にその価値が大きく増加し、その価値増加に配偶者の協力が寄与したと認められる場合には、増加分が財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、結婚前に購入した不動産のローンを婚姻中の家計から返済した場合や、夫婦で協力してリフォームを行った結果、資産価値が上昇したようなケースでは、一部が共有財産と判断される可能性は考えられるでしょう。
そのほかにも、婚姻期間が長期間に及んでいる場合や、婚姻前の預貯金についても共有財産と一体化しているような場合には、特有財産性が失われていると判断されることもあります。
結婚前からの個人資産の分与については、以下の記事でも解説しています。
関連記事:親に買ってもらった車は財産分与になる?離婚時の財産分与の相場とその対象
相続した遺産
婚姻中に、親などの親族から相続によって得た遺産(不動産、預貯金、有価証券など)は、特有財産とされます。相続は、被相続人との身分関係に基づいて発生するものであり、夫婦の協力によって得られたものではないからです。
相続財産であることを証明するためには、以下のような書類を保管しておきましょう。
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 被相続人の除籍謄本
なお、相続した遺産であっても、夫婦の共同口座へ入金すると、共有財産との判別が不可能になります。そのため、相続した遺産は個人の口座で管理し、婚姻と無関係に得た旨を証明できるようにすることが大切です。
親から贈与された財産
親や親族から個人に対して贈与された財産も、特有財産となります。例えば、以下のようなものが該当します。
- 住宅購入時に親から子へ頭金として援助された資金
- お小遣いとして個人的に受け取った金銭
これらは夫婦の生活を支えるための一般的な援助とは異なり、個人への贈り物と解釈されるためです。
例えば、夫婦共同で自宅を購入するにあたって親から贈与された資金を頭金に充てた場合、頭金の分は特有財産と判断されます。そのため、不動産の財産分与は2分の1よりも考慮されるでしょう。
同様に、贈与された資金で配偶者名義の資産(車や株式など)を購入した場合も、特有財産と主張できる可能性があります。
夫婦の協力とは無関係に得た財産
相続や贈与以外にも、夫婦の協力とは無関係に一方の個人的な事情によって得た財産は、特有財産とみなされることがあります。ただし、これらの財産は判断が分かれるケースも多く、注意が必要です。
以下に、主な例と特有財産とみなされる理由をまとめました。
| 例 | 特有財産とみなされる理由 |
|---|---|
| 交通事故の損害賠償金 | 事故に遭った個人の損害を填補するものであるため |
| 宝くじ・個人の趣味で得た賞金 | 取得の経緯が個人的な事情によるため |
ただし、交通事故の損害賠償金に給与の代替(共有財産)となる休業損害や逸失利益が含まれる、宝くじや個人の趣味の原資がお小遣い(共有財産)であるなどの場合は、判断が分かれるケースもあります。
状況によって判断が異なるため、判断に迷う場合は専門家のアドバイスを受けるのが確実です。
個人的な借金・負債
夫婦の一方が、ギャンブルや浪費、個人的な趣味など、夫婦の共同生活とは無関係な理由で作った借金は、その個人の負債であり、財産分与において考慮はされません。つまり、相手の個人的な借金を返済する義務はなく、共有財産からその負債分を差し引くこともないのです。
これに対し、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなど、夫婦の共同生活のために生じた負債は「マイナスの共有財産」として扱われ、プラスの財産と合わせて清算されます。
子ども名義の財産
子ども自身が受け取ったお年玉やお祝い金、あるいは子どもがアルバイトで稼いだお金などは、子どもの固有の財産です。これらは夫婦の財産ではないため、当然、財産分与の対象にはなりません。
ただし、夫婦の財産を税金対策などの目的で形式的に子ども名義の口座に入れている「名義預金」の場合は、実質的に夫婦の共有財産と判断され、分与の対象となります。名義預金については、次章で解説します。
婚前契約で対象外と合意した財産
結婚前に、夫婦となる二人の間で「この財産は将来離婚する際の財産分与の対象としない」といった内容の契約(婚前契約または夫婦財産契約)を結んでいた場合、その合意が優先されます。



婚前契約は、法律や公序良俗に反しない限り有効であり、将来の財産分与をめぐるトラブルを未然に防ぐための有効な手段となり得ます。
ただし、この契約は必ず婚姻届を提出する前に締結する必要があり、結婚後に内容を一方的に変更することは原則としてできません。(参照:民法|758条)
財産分与の対象になるもの
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、たとえ専業主婦(主夫)で直接的な収入がない側であっても、原則として受け取る権利があります。
「夫の給料だけで築いた財産なのに、専業主婦が受け取るのはおかしい」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、法律では、専業主婦(主夫)の家事や育児といった家庭への貢献も、財産形成への重要な「協力」とみなされます。一方が家庭を支えることで、もう一方が外で働き収入を得ることができた、と考えるためです。



そのため、財産形成への貢献度(寄与度)は夫婦で平等とされ、特別な事情がない限り、共有財産を2分の1ずつに分けるのが基本となります。
【ケースバイケース】財産分与の対象になるか判断が分かれるもの
財産の中には、以下のように「共有財産」と「特有財産」の両方の要素を含んでおり、単純に分けることが難しいものがあります。
これらの財産については、どの部分が分与の対象となるのかを、個別の事情に応じて按分計算するなど、慎重な判断が求められます。それぞれの財産について、順番にみていきましょう。
退職金
退職金は、給与の後払いとしての性質を持つため、財産分与の対象となります。長年の勤務に対する対価であり、その勤務期間中に配偶者の支えがあったと評価されるからです。
ただし、財産分与の対象となるのは、あくまで「婚姻期間に対応する部分」のみです。勤務期間全体のうち、結婚していた期間の割合に応じて按分計算を行います。
例えば、勤続40年のうち婚姻期間が30年であれば、退職金額の4分の3が共有財産とみなされます。
また、まだ支払われていない将来の退職金であっても、支給される確実性が高い場合は分与の対象です。
一般的に退職金の評価額は、離婚の基準時(通常は別居時)に自己都合退職したと仮定した場合に支給される額を基準に計算されるのが一般的です。
年金
年金は、以下のように財産分与の対象になる場合と「年金分割」という別の制度の対象になる場合があります。
| 対象となる制度 | 年金の例 |
|---|---|
| 財産分与 | ・企業年金 ・私的年金(iDeCo・個人年金保険など) |
| 年金分割 | ・厚生年金 ・共済年金 |
財産分与の対象になる種類の年金は、退職金と同様に婚姻期間に対応する部分を計算して分け合います。
一方、年金分割の対象になるものは、両者の合意のもとで婚姻期間中の保険料納付実績(標準報酬)を夫婦で分割し、将来それぞれの年金受給額に反映させる形をとります。
ただし、配偶者が3号被保険者であった場合は、平成20年4月以降に婚姻していた期間の分は配偶者の合意が無くても、申請すれば年金が分割されます。
退職金や年金の財産分与については、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:離婚時に退職金は財産分与の対象となるのか
生命保険の解約返戻金
貯蓄性のある生命保険や学資保険などを婚姻期間中に解約した場合に戻ってくるお金(解約返戻金)は、一般的には夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
これは、保険料が夫婦の共有財産である家計から支払われていたと考えられるためです。
ただし、独身時代から加入している保険を結婚後も継続している場合は、いつ支払った保険料であるかによって、財産分与での扱いが変化します。
| 保険料の支払時期 | 区分 |
|---|---|
| 独身時代 | 特有財産 |
| 婚姻後 | 共有財産 |
重要なのは、契約者が誰かということではなく、保険料を誰が(どの財産から)支払っていたかという点です。
この場合、別居時点での解約返戻金額に対して、全保険料支払期間に占める婚姻期間の割合を乗じるなどの按分計算を行います。
株式・投資信託
婚姻期間中に、夫婦の共有財産(給与など)を原資として購入した株式や投資信託は、共有財産として財産分与の対象となります。
評価額は、財産分与の基準時(別居時や離婚時)の時価で計算するのが一般的です。
一方で、結婚前から保有していた株式や、親から相続した株式は特有財産であり、原則として対象外です。
しかし、婚姻前に保有していた株式であっても、婚姻後に配偶者の協力(家事育児による生活の安定や、事業への直接的な貢献など)によってその価値が著しく増加したと認められれば、増加した分は財産分与の対象になる可能性があります。
タンス預金・へそくり
自宅に保管している現金(タンス預金)や、配偶者に内緒で貯めていたお金(へそくり)は、何を原資としているかによって扱いが異なります。
問題となるのは、そのへそくりが特有財産(結婚前の貯金や親からの贈与)を原資としていると証明できるかどうかです。
たとえ、贈与や独身時代の預貯金を原資としたへそくりであっても、資金の動きを証明できなければ共有財産から貯めたものと推定されます。
原資の種類と扱いについて、以下にまとめました。
| 原資 | 区分 |
|---|---|
| 夫婦の共有財産(お小遣い) | 共有財産 |
| 親や親族からの贈与や独身時代の預貯金 | 特有財産 |
つまり、原資が夫婦の共有財産(給与など)であれば、財産分与の対象となります。隠していたからといって、分与の義務を免れることはできません。
また、財産を意図的に隠す行為は「財産隠し」とみなされ、後の調停や裁判で著しく不利な立場に置かれる可能性もあります。
名義預金(配偶者や子ども名義の口座)
名義預金とは、口座の名義人と預金を実質的に所有・管理している人が異なる預金のことです。財産分与において、裁判所は口座の名義という形式ではなく、その預金の「実質的な所有者は誰か」という観点で判断します。
重視される点は、以下のとおりです。
- その預金の原資は誰の収入
- 通帳や印鑑は誰が管理しているか



例えば、税金対策や将来の教育費のために夫の給与の一部を子ども名義の口座に貯金をしていた場合、その通帳や印鑑を親が管理し、自由に出し入れできる状態なら、それは子どもの固有の財産ではなく、夫婦の共有財産と判断されます。
分与対象にならない財産を守るための3つのポイント
分与対象にならない財産を守るには、以下3つのポイントが大切です。
特有財産を、離婚時の財産分与から確実に守るためには、日頃からの準備と意識が欠かせません。順番に見ていきましょう。
共有財産と特有財産を適切に区別する
自身の財産を守るための基本的な原則は、特有財産と共有財産を明確に分けて管理することです。生活費の口座は婚姻後に新しく用意し、独身時代からの預貯金は、個人資産を管理するために口座を分けておきましょう。
一度でも共有財産と特有財産が混ざり合ってしまうと、その中から「ここまでが自分の特有財産だった」と法的に証明することは極めて困難です。
財産を明確に分けることは、離婚時の分与トラブルから個人資産を守る大きな助けとなるのです。
特有財産とみなせる客観的な証拠を確保する
財産分与の交渉や調停・裁判の場では、「これは私の特有財産だ」という口頭での主張だけではまったく通用しません。その主張を裏付ける客観的な証拠がなければ、法的には認めてもらえない可能性が非常に高いのです。
そのため、特有財産に関連する書類は、必ず大切に保管しておく必要があります。具体的には、以下のような書類が挙げられます。
| 財産の種類 | 書類の例 |
|---|---|
| 相続した財産 | ・遺産分割協議書 ・遺言書 |
| 贈与された財産 | ・贈与契約書 ・贈与の事実が分かる振込記録 |
| 婚姻前の財産 | ・婚姻日時点の残高が分かる預金通帳 ・不動産の売買契約書や登記簿謄本 |
これらの証拠が、あなたの正当な権利を主張するための生命線となります。古い通帳や振込記録が残っていないかを確認してみましょう。
合意内容は必ず書面に残す
夫婦間の話し合いによって財産分与の内容が決まった場合、その合意内容を口約束で済ませてはいけません。後からの「言った・言わない」というトラブルを防ぐため、合意内容は必ず書面に残しておきましょう。
この書面は「離婚協議書」として作成することが一般的です。さらに、その離婚協議書を公証役場で「公正証書」にしておくと、さらに有用性が高まります。
公正証書は、公証人が内容を確認して作成する公的な文書であり、高い証明力を持ちます。
特に、金銭の支払いに関する取り決め(分割払いなど)について「強制執行認諾文言」を付けておけば、万が一支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく相手の給与や預金を差し押さえる強制執行手続きが可能となります。



自分での証書作成が難しい場合は、専門家の助けを借りることをおすすめします。
離婚時の財産分与でお悩みの方は、離婚問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は、相談実績1000件以上の高い専門性を持っております。
一人で悩まず、まずは初回60分無料の電話相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
損をしない財産分与の進め方4ステップ
財産分与を円滑かつ公正に進めるには、念入りな準備と順序だてた手続きが欠かせません。
ここでは、話し合いから法的手続きに至るまでの標準的な4つのステップを解説します。
財産リストを作成し、共有財産と特有財産を仕分ける
最初に行うのは、夫婦双方の財産をすべて洗い出し、一覧化することです。預貯金、不動産、生命保険、有価証券、自動車などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産もすべてリストアップします。
次に、そのリストに基づいて、各財産が「共有財産」にあたるのか、それとも「特有財産」にあたるのかを仕分けします。
作成した財産目録が、財産分与における交渉の土台となります。
夫婦間で財産分与の話し合い(協議)を進める
財産の全体像が把握できたら、次はその分け方について夫婦間で直接話し合います(協議)。お互いが納得できる形で合意に至れば、それが最も円満かつ迅速な解決となるでしょう。
合意できた場合、合意内容は必ず「離婚協議書」などの書面にまとめ、署名・捺印をします。可能であれば法的な強制力を持つ「公正証書」として作成しておくと、将来のトラブル防止に有効です。
家庭裁判所での「財産分与請求調停」を行う
夫婦間の話し合いで合意に至らない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てます。
調停では、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が中立な第三者として間に入り、双方の主張を整理しながら、合意形成に向けた話し合いをサポートします。
ここで合意が成立すると、その内容は「調停調書」という法的な効力を持つ書面に記載され、確定判決と同様の強制力を持ちます。(参照:裁判所|財産分与請求調停)
調停不成立の場合は「審判」へ移行する
調停でも話し合いがまとまらなかった場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。
審判では、裁判官が当事者双方から提出された主張や証拠資料から、法的な観点として妥当な財産の分与方法を決定します。



裁判官によるこの決定(審判)は判決と同じ強制力を持つため、当事者はその内容に従わなければなりません。
なお、まだ離婚していない夫婦が財産分与を求める場合は、離婚調停の中で話し合いをすることも可能です。
この場合調停で合意ができない場合は、離婚裁判で財産分与も決定します。(参照:裁判所|財産分与調停(審判)を申し立てる方へ)
財産分与の対象にならないものを見極めるなら弁護士に依頼|相談する4つのメリット
ここからは、弁護士に依頼する以下4つのメリットを解説します。
財産分与のうち、特に特有財産の主張が絡むケースは、法的な知識と交渉力が結果を大きく左右します。より良い結果を得るために、ぜひ押さえておきましょう。
正確な財産の評価と適切な分与額を算出してくれる
婚姻前からかけていた保険やまだ支給されていない退職金など、特有財産と共有財産の部分が混在している財産もあります。
そのような財産については、専門知識がなければ適正な価値を評価することが難しいケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、複雑な財産法的な基準に基づいて正確に評価し、財産分与の対象とならない額を算出してもらえます。
法的根拠に基づき、特有財産であることの主張・立証を任せられる
「これは私の特有財産だ」と主張するには、主張する側が法的に有効な証拠を揃え、説得力のある主張を組み立てる必要があります。
しかし、専門知識がないとどのような証拠を集めたらよいか分からず、本来なら特有財産と認められる資産が共有資産となってしまうケースは少なくありません。
弁護士は、法律の専門家として、どのような証拠が有効かを的確にアドバイスし、法的な主張・立証活動を行います。相手方が不当な要求をしてきた場合も、法的根拠をもって状況に合わせた解決方法を提供できるのです。
感情的な対立を避け、冷静な交渉を代理してくれる
離婚の話し合いは、どうしても感情的な対立に陥りがちです。とくに金銭が絡む場合、スムーズに話し合いが進まないケースもよく見られます。
しかし、弁護士が代理人となることで、相手方と直接顔を合わせて交渉する必要がなくなり、精神的なストレスを大幅に軽減可能です。
交渉のプロである弁護士は、感情論に流されることなく、法的な争点に絞って冷静かつ論理的に交渉を進め、円滑な解決をサポートします。
書面作成等の煩雑な手続きを任せられる
訴訟になった場合には、特有財産であることを証明する必要があり、その理由等も書面に記載します。
また、訴訟や審判の期日に出廷する必要がありますが、弁護士に依頼することで、ご自身は出廷をしなくても大丈夫なこともあります。



専門家の手を借りることで、正確な手続きが可能になり、仕事や新生活の準備にも集中できるでしょう。
弁護士に特有財産の主張について相談をお考えの方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
関連記事:【弁護士監修】財産分与は弁護士に相談すべき?依頼のメリットや費用相場を解説
財産分与で対象にならないものに関するよくある質問
離婚前に預金を引き出す・隠すとどうなりますか?
離婚を予期して預金を引き出したり別の口座に移したりする行為は「財産隠し」とみなされ、不利な結果を招きます。
相手方が弁護士に依頼すれば、過去の口座取引履歴は調査できる場合もあるため、不自然な資金の動きはほぼ確実に発覚します。
悪質な場合は、預金の引き出し自体が不法行為とみなされ、別途慰謝料の支払いを命じられる可能性もあります。
財産分与を有利にする目的で離婚前に預金を引き出すのは、絶対に避けてください。
離婚時に財産分与の通帳開示はどこまで必要ですか?
財産分与の対象となる共有財産を確定させるため、基本的には「別居日(または離婚日)まで」の残高がわかる資料の開示が求められます。
ご自身の特有財産(婚姻前の預貯金など)を主張したい場合には、婚姻前からの財産であることを証明するために、婚姻から別居日までの履歴も必要となります。
また、相手が開示を拒否した場合でも、調停や裁判の手続きを通じて、法的な手段での開示請求は可能です。必要と判断される通帳は、すべて開示することになると考えておくとよいでしょう。
専業主婦に財産分与するのはおかしいといわれたらどうしたらいいですか?
専業主婦であっても、原則共有財産の2分の1を受け取る範囲は保証されています。そのため、その主張は完全な誤りです。
もし「専業主婦への財産分与はおかしい」と言われた場合、感情的に反論するのではなく法律で認められた権利であることを冷静に伝えましょう。
相手が応じない場合は速やかに弁護士に相談し、法的な対応を依頼するのが最善です。
財産分与自体を拒否することはできますか?
財産分与は民法で定められた法的な権利であるため、一方の都合で拒否することはできません。
相手が正当な理由なく財産分与を拒否し続ければ、最終的には訴訟や審判といった裁判所の手続きに移行し、裁判所が分与を命じることになります。
裁判所の決定に従わない場合は、給与や預金口座などの財産を差し押さえられる強制執行を受ける可能性があります。
まとめ|財産分与の対象にならないものを正しく見分けるなら弁護士に相談しよう
財産分与の対象にならないものは、婚姻前の財産・相続や贈与で得た財産・個人的な損害賠償金などの特有財産です。どこまでが対象になるのか判断が難しい場合もあるため、早めに専門家へ相談し、証拠を整えておくことが重要です。
財産分与は、離婚後の人生設計を左右する極めて重要な問題です。どの財産が対象になるのか判断に迷う場合や、相手方との話し合いが難航している場合には、決して一人で悩まず、できるだけ早い段階で法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
離婚時の財産分与でお悩みの方は、離婚問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は、相談実績1000件以上の高い専門性を持っております。
一人で悩まず、まずは初回60分無料の電話相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応