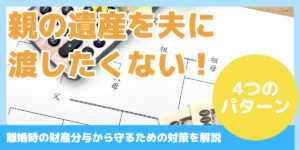【弁護士監修】財産分与は弁護士に相談すべき?依頼のメリットや費用相場を解説
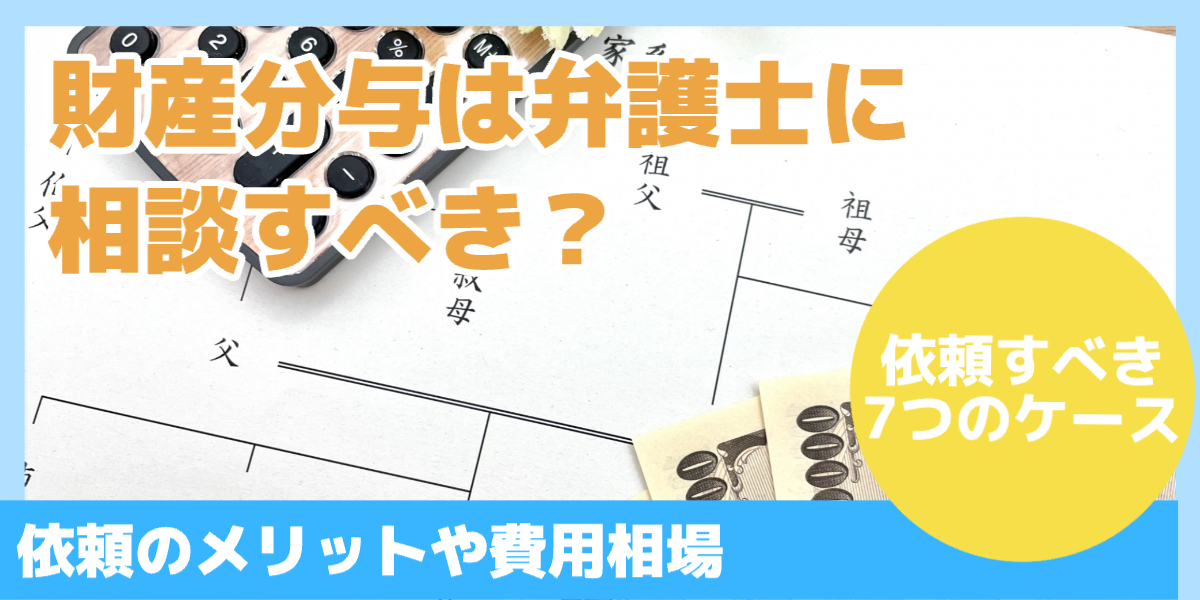
「離婚後の生活のために財産はきちんと分けたいけど、相手が協力してくれない…」
「相手の財産がどれだけあるか分からない。もしかしたら隠されているかもしれない…」
離婚という人生の大きな岐路において、上記のような不安や疑問を抱くのは当然のことです。とくに財産分与は、離婚後の生活基盤を左右する極めて重要な問題でありながら、手続きは複雑で精神的な負担も伴います。
この記事では、財産分与の本質や弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。財産分与に強い弁護士の選び方や費用相場も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
財産分与に関するお悩みや、相手方との交渉でお困りの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
離婚・財産分与問題に精通した弁護士があなたの状況を丁寧に分析し、最善の解決策をご提案します。
まずは、初回60分の無料相談をご活用ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
財産分与とは
財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を公平に分配する手続きのことです。民法第768条に定められた法的な権利であり、離婚後の経済的な安定を確保するための重要な制度となっています。
一般的に財産分与は、夫婦の財産を清算する側面が強いですが、それだけではありません。財産分与には、以下の3つの性質があります。
- 清算的財産分与
- 慰謝料的財産分与
- 扶養的財産分与
清算的財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に清算する要素です。離婚原因を作った側(有責配偶者)からでも請求が認められます。
慰謝料的財産分与は、不貞行為やDVなど、相手方の有責行為によって離婚に至った場合の損害賠償(慰謝料)を、財産分与に含めて支払う要素です。
本来、慰謝料と財産分与は別のものですが、実務上は一括して解決することがあります。
扶養的財産分与は、離婚によって一方の配偶者が経済的に困窮する場合、生活を補助する目的で財産を分与する要素です。長年専業主婦(主夫)であったため、すぐに安定した収入を得ることが難しいケースなどが該当します。
関連記事:離婚時の財産分与はどうなる?家や貯金の分け方・手続きの流れを弁護士が解説
関連記事:熟年離婚の財産分与はどうすべき?具体的な進め方や起こりやすいトラブルを解説【弁護士監修】
財産分与は「2分の1」が原則
財産分与における財産の分配割合は、原則として「2分の1」とされています。これを「2分の1ルール」と呼ぶことがあります。
婚姻期間中に築かれた財産は、夫婦が互いに協力し合った結果形成されたものであり、その貢献度は対等であるという考え方があるためです。
例えば、夫が会社員として外で働き収入を得て、妻が専業主婦として家事や育児を担っていた場合を考えます。この場合、夫が仕事に専念できたのは、妻が家庭を支えていたからこそです。
したがって、妻の家事労働という非金銭的な貢献も、夫の金銭的な貢献と同等の価値があると評価されます。
そのため、収入に差があったり、あるいは一方が専業主婦(主夫)で直接的な収入がなかったりしても、原則として財産の形成に対する貢献度は等しいと見なされ、共有財産を半分ずつ分ける権利が認められる可能性があります。
関連記事:財産分与の割合はどのくらい?例外ケースや注意点を弁護士が解説
2分の1ルールが修正される可能性のあるケース
原則は2分の1ですが、このルールを適用することが不公平と裁判所が判断した場合、修正されることがあります。裁判所が目指すのは単なる平等ではなく、個別の事情に応じた「公平」の実現だからです。
具体的なケースとしては、まず夫婦の一方が持つ特別な才能や資格によって高額な資産が形成された場合が挙げられます。
次に、夫婦の一方の特有財産(後述)が、共有財産の維持または増加に大きく貢献した場合も、割合が修正される可能性があります。例えば、妻が相続した遺産を元手に事業を始め、それが大きく成功したようなケースなどです。
逆に、夫婦の一方がギャンブルや浪費によって共有財産を著しく減少させた場合、その責任を負う形で分与割合が減らされることもあります。
ただ、「2分の1ルール」が修正されるのは、当事者間に合意がある場合に限られる点には注意が必要です。また、裁判となった場合も修正される可能性があります。
財産分与の対象となる「共有財産」と対象外の「特有財産」とは?
財産分与を正しく行うためには、まずどの財産が分与の対象となるのかを正確に区別する必要があります。
法律上、財産は以下の2種類に分けられるためです。
- 共有財産
- 特有財産
以下、それぞれ詳しく解説します。財産の区別は、分与額を大きく左右する要因となるため、必ず確認しておきましょう。
財産分与の対象となる「共有財産」とは
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して取得・維持してきた財産を指します。重要なのは、財産の名義が夫と妻のどちらになっているかではなく、その財産が夫婦の協力によって得られたものかどうかという「実質」で判断される点です。
例えば、夫の給料から積み立てた夫名義の預貯金はもちろん、妻がパートで得た収入を貯めた妻名義の預金も共有財産となります。夫婦の協力には、外で働いて収入を得ることだけでなく、家事や育児といった家庭内での貢献も含まれるためです。
具体的にどのようなものが共有財産にあたるのか、以下に代表的な例を挙げます。ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
| 財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 預貯金 | 夫婦それぞれの名義の預金・貯金(普通、定期、積立など) |
| 有価証券 | 株式、投資信託、国債など(婚姻中に購入したもの) |
| 保険 | 生命保険、学資保険などの解約返戻金(婚姻期間中の保険料支払部分に対応する額) |
| 不動産 | 土地、建物(戸建て、マンションなど) |
| 自動車 | 夫婦や家族が使用していた自動車 |
| 退職金・年金 | 婚姻期間に対応する部分の退職金、年金 |
| その他 | 家具、家電、貴金属、美術品、子ども名義の預金(原資が夫婦の収入である場合) |
財産分与の対象にならない「特有財産」とは
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても親からの相続や贈与によって得た財産など、夫婦の協力とは無関係に取得した財産を指します。これらは財産分与の対象にはなりません。
例えば、結婚前に貯めた預金、親が亡くなった際に相続した不動産や株式、親から住宅購入資金として贈与された金銭などが典型的な特有財産です。
財産が特有財産かどうかは主張する当事者が証明しなければなりません。
民法第762条第2項は「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」としているためです。
例えば、夫名義の口座にある預金について、夫が「結婚前から持っていた金だ」と主張しても、客観的な証拠(婚姻前の日付が入った通帳など)で証明できなければ、その預金は共有財産と推定されます。
「証明できなければ共有財産」という原則は、財産分与の交渉や裁判において非常に重要な要素です。
関連記事:財産分与の対象にならないものとは?相続遺産や親からの贈与を守る方法【弁護士監修】
【要注意】名義人と実際の権利者が異なる財産の扱い
財産分与で特に争いになりやすいのが、「名義預金」の扱いです。とくに「子ども名義の預金」は、争いやすい要素といえます。
口座の名義が子どもであっても、そのお金が財産分与の対象となるかは、名義ではなく実質で判断されます。裁判所が重視するのは、「その預金の原資は何か」「誰がその口座を管理していたか」という点です。
例えば、夫婦の給与から毎月一定額を子どもの将来の学費として積み立てていた場合、その原資は夫婦の共有財産であるため、口座の名義が子どもであっても共有財産と扱われる可能性が高いです。
一方で、祖父母などから子どもへのお年玉やお祝い金として贈られ、それをそのまま貯めていた預金は、子どもの固有の財産と判断され、財産分与の対象外となるのが一般的です。
財産分与に関するお悩みや、相手方との交渉でお困りの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
離婚・財産分与問題に精通した弁護士があなたの状況を丁寧に分析し、最善の解決策をご提案します。
まずは、初回60分の無料相談をご活用ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
財産分与で弁護士に相談・依頼すべき7つのケース
財産分与は当事者同士の話し合いで解決するのが理想ですが、状況によっては専門家である弁護士の介入が不可欠となるケースがあります。
以下の7つのケースに当てはまる場合は、早期に弁護士へ相談しましょう。
以下、それぞれ具体的に解説します。
1.夫婦の共有財産が高額または複雑な場合
夫婦の共有財産が高額な場合や複雑な場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
分与の対象となる財産の総額が高額になるほど、少しの計算ミスや見落としが大きな損失につながります。
また、複数の銀行口座・投資信託・海外資産などが絡む複雑な資産構成の場合、全体像を正確に把握し、法的に正しく評価・分配する作業は専門家でなければ困難です。
財産の価値が大きいほど、弁護士に依頼して確実な手続きを踏む必要性が高まります。
2.不動産(自宅・投資用マンション)や株式が財産に含まれる場合
不動産(自宅・投資用マンション)や株式が財産に含まれる場合も、弁護士に依頼するのが適切です。
預貯金と異なり、不動産や非上場株式には決まった価格がありません。そのため、「いくらと評価するか」が大きな争点となります。相手方が意図的に低い評価額を提示して、支払う分与額を減らそうと試みるケースは少なくありません。
弁護士に依頼すると、不動産鑑定士などの専門家と連携し、実勢価格に基づいた適正な評価額を算出してくれます。株式についても、上場株式か非上場株式かによって評価方法は全く異なり、専門的な知識が必須です。
適正な評価なくして、公正な財産分与はできないため、不動産(自宅・投資用マンション)や株式が財産に含まれる場合も弁護士に依頼するとよいでしょう。
3.相手の財産を正確に把握できていない・財産隠しが疑われる場合
「相手が全財産を開示してくれない」「給与に比して貯蓄が少なすぎる」といった問題がある場合も、弁護士に依頼するのが適切です。
個人で相手の財産を調査するには限界がありますが、弁護士は「弁護士会照会」などの法律上の制度を用いて、金融機関や保険会社に情報の開示を求められます。
財産隠しは、離婚の現場では頻繁に起こり得る事象です。隠された財産を見つけ出せるかどうかは、最終的に受け取れる金額に直結するため、弁護士に依頼するとよいでしょう。
4.財産分与の割合に納得がいかない場合
財産分与の割合に納得がいかない場合も弁護士に依頼することを推奨します。
特別な才能による高額資産の形成や、特有財産の大幅な貢献など、2分の1ルールが不公平となる事情がある場合、その割合を修正するよう主張できます。
しかし、この主張を法的に認めさせるには、過去の裁判例などを踏まえた説得力のある論理構成と、それを裏付ける客観的な証拠が必要です。感情的な訴えだけでは、裁判所を動かすことはできません。
専門的な法的議論を構築するためにも、弁護士に依頼するとよいでしょう。
5.相手が話し合いに応じない・感情的になっている場合
離婚の話し合いでは、当事者同士が感情的になり、冷静な対話が困難になることが多々あります。相手が話し合いを拒否したり、非協力的な態度を取ったりする場合、交渉は行き詰まってしまいます。
弁護士が代理人として間に入ることで、感情的な対立を避け、法的な論点に絞った冷静かつ合理的な交渉が可能です。弁護士の存在そのものが相手方へのプレッシャーとなり、交渉のテーブルに着かせる効果も期待できます。
6.相手がすでに弁護士を立てている場合
相手がすでに弁護士を立てている場合は、直ちに弁護士に相談しましょう。
相手方が法律の専門家を立てているにも関わらず、こちらが一人で立ち向かうのは、武器を持たないで戦場に出るようなものです。法律知識・交渉術・手続きのノウハウなど、あらゆる面で不利な状況に置かれる可能性があります。
相手が弁護士を立てたという事実を知った時点で、こちらも専門家を代理人に立て、対等な立場で交渉に臨むことが大切です。
7.経営者などで財産の評価が難しい場合
経営者などで財産の評価が難しい場合も、弁護士に依頼するとよいでしょう。
会社の株式(特に非上場株式)の価値評価、事業用資産と個人資産の切り分け、将来の退職金や役員報酬の扱いなど、会計や税務の知識も必要となる論点は多いです。
こういった特殊な財産の評価には、高度な専門性が求められます。弁護士が公認会計士などの他分野の専門家と協力して対応することが一般的です。
離婚時の財産分与を弁護士に依頼するメリット
財産分与で弁護士に依頼することは、手続きを代行してもらう以上の価値をもたらします。ここでは、弁護士に依頼することで得られる5つの具体的なメリットを解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
1.正確な財産調査で「隠れ財産」を見つけ出せる
弁護士に依頼するメリットの一つが、徹底した財産調査能力です。相手が財産を隠している場合や、正直に開示しない場合でも、弁護士は法的に認められた強力な調査手段を行使できます。
その代表格が「弁護士会照会(23条照会)」です。弁護士が所属する弁護士会を通じて、金融機関・保険会社・証券会社・勤務先などに、口座情報や契約内容、給与額などの情報開示を公式に要請できます。
個人からの問い合わせには応じない機関も、弁護士会からの正式な照会には回答してくれる可能性が高まるでしょう。
さらに、調停や裁判といった裁判所の手続きに進んだ場合には、「調査嘱託」というより強力な手段を使用できます。裁判所が直接、関係機関に調査を依頼するもので、弁護士会照会で開示されなかった情報も得られる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、これらの専門的な調査能力により、隠された財産を発見し、正当な分与の対象に含めることが可能です。
2.法的根拠に基づき有利な分与割合を主張できる
財産分与の割合は、必ずしも2分の1とは限りません。あなたの特別な貢献や相手の不当な行為など、分与割合を修正すべき事情がある場合、弁護士はその主張を法的に組み立ててくれます。
状況を詳細に分析し、関連する法律や過去の裁判例(判例)を根拠として、なぜ2分の1ルールがあなたのケースでは不公平であるかを論理的に主張します。
説得力のある交渉や裁判での主張が可能となるため、より有利な条件での解決を目指せるでしょう。
3.不動産や退職金など評価が難しい財産を適正に評価できる
財産分与では、不動産や株式、退職金などの評価額が争点になりがちです。例えば不動産には、実勢価格(時価)・固定資産税評価額・路線価など複数の評価基準があり、どの基準を用いるかで金額が大きく変わります。
相手方は、自分に有利な低い評価額を主張してくるかもしれません。弁護士であれば、財産分与において妥当とされる実勢価格での評価を主張し、必要であれば不動産鑑定士と連携して適正な価値を明らかにしてくれます。
また、将来受け取る予定の退職金についても、単に同居期間で按分するだけでなく、将来の受取額を現在の価値に割り引く「中間利息の控除」という専門的な計算が必要です。
こうした複雑な財産の評価を専門家の視点で行うことで、不当に低い金額で合意してしまうリスクを防げるでしょう。
4.相手との交渉や面倒な手続きをすべて一任できる
離婚協議は、精神的に大きなストレスを伴います。相手方とのやり取りや複雑な書類の作成、裁判所への出頭など、負担は計り知れません。
弁護士に依頼すれば、これらの交渉や法的手続きのすべてを代理人として任せられます。相手と直接顔を合わせることなく、法に基づいて冷静に交渉を進めることが可能です。
精神的な負担から解放され、新しい生活の準備に集中できるでしょう。
5.精神的な負担が軽減される
離婚という人生における大きな転機において、精神的な安定を保つことは重要です。「自分の味方になってくれる法律の専門家がいる」という事実は、計り知れないほどの精神的な支えとなります。
先行きが不透明な状況や、感情的になりがちな相手方との対立の中で、弁護士は客観的な視点から法的な見通しを明確に示し、冷静かつ的確なアドバイスを提供してくれるでしょう。
一人で全てを抱え込まずに済むという安心感は、金銭的なメリットと同じくらい価値のあるものといえます。弁護士に依頼することで、単に法的な問題解決に留まらず、依頼者が精神的な健康を保ち、将来への希望を見出せるようになるでしょう。
財産分与に関するお悩みや、相手方との交渉でお困りの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
離婚・財産分与問題に精通した弁護士があなたの状況を丁寧に分析し、最善の解決策をご提案します。
まずは、初回60分の無料相談をご活用ください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
離婚の際に弁護士に依頼するべき理由については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:離婚の際は弁護士に依頼を―プロに依頼するべきその理由とは―
後悔しないための財産分与に強い弁護士の選び方
弁護士に依頼すると決めても、「どの弁護士に頼めばよいのか」という新たな問題に直面します。
弁護士なら誰でも良いというわけではありません。財産分与を成功させるためには、この分野に精通した「強い」弁護士を選ぶことが不可欠です。
ここでは、後悔しない弁護士選びのための4つの重要なポイントを解説します。
1.離婚・財産分与問題の解決実績が豊富かをチェックする
弁護士にはそれぞれ得意な分野があります。医療過誤に強い弁護士もいれば、企業法務の専門家もいます。
財産分与を依頼するなら、当然「離婚・財産分与」を専門分野として掲げ、豊富な解決実績を持つ弁護士を選ぶべきです。
法律事務所のウェブサイトを確認し、「取扱分野」として離婚問題が明記されているか、具体的な解決事例やお客様の声が掲載されているかをチェックしましょう。特に、財産分与に関するコラムや解説記事が充実している事務所は、その分野への注力度が高いと判断できます。
相談時には、これまでに扱った財産分与事件の件数や、類似のケースでの経験を具体的に質問してみることも効果的です。
2.特殊な状況にも対応してくれるかどうかを確認する
状況が特殊であればあるほど、より高度な専門性が求められます。例えば、以下のような場合です。
- 会社経営者で非上場株式の評価が問題になる場合
- 不動産を多数所有している場合
- 海外に資産がある場合
このような複雑な状況では、単に離婚法務に詳しいだけでなく、関連する分野(会計・税務・不動産鑑定など)の知識や、他の専門家との連携経験がある弁護士が適しています。
初回相談の際に、自身の具体的な状況を伝え、「このようなケースを扱った経験はありますか?」と率直に確認しましょう。その問いに対して、明確で具体的な回答ができる弁護士は、信頼できる可能性が高いです。
3.料金体系が明確で分かりやすく説明してくれるかを確認する
弁護士費用は決して安いものではありません。だからこそ、費用に関する説明が明瞭であることは、信頼できる弁護士を見極めるための重要な指標です。
相談料・着手金・成功報酬・実費など、どのような費用が、どのタイミングでいくら発生するのかを、書面なども用いて具体的に説明してくれる弁護士を選びましょう。
特に成功報酬の計算方法は、「獲得した経済的利益の〇%」といった形で定められることが多いため確認が必要です。「経済的利益」が何を指すのか、計算方法はどうなるのかを事前にしっかり確認しておきましょう。
4.過去の利用者の口コミ・評判がよいかをチェックする
弁護士や法律事務所のウェブサイトに掲載されている情報に加えて、第三者からの客観的な評価も参考にすることが大切です。
インターネット上の口コミサイトやレビューは、実際にその弁護士に依頼した人の生の声を知る上で役立ちます。
とくに、弁護士の対応姿勢に関する以下のような具体的なコメントに注目しましょう。
- 連絡がスムーズだったか
- 説明が丁寧だったか
- 親身になって話を聞いてくれた
ただし、口コミは個人の主観に基づくものであるため、すべてを鵜呑みにするのは危険です。複数の口コミを比較検討し、全体的な傾向を掴みましょう。最終的には、無料相談などを利用してご自身で直接話し、相性を実際に確かめることが重要です。
財産分与を弁護士に依頼する際の費用相場
弁護士費用は事務所によって異なりますが、ある程度の相場は存在します。ここでは、費用の内訳と、旧日本弁護士連合会の基準を参考にした相場について解説します。
関連記事:離婚の弁護士費用はいくら?相場や内訳・払えない場合の対処法を弁護士が解説
弁護士費用の内訳
弁護士費用は、主に以下の4つの項目で構成されています。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- 実費
ここからは、それぞれの特徴について具体的に解説します。
相談料
相談料とは、弁護士に法律相談をする際に発生する費用のことです。
弁護士は、法律の専門家として依頼者の抱える問題に対し、的確なアドバイスや解決策を提示する役割を担っています。相談料は、弁護士の専門知識や経験に対する対価として位置づけられます。
近年では、より気軽に法律相談を受けられるようにとの配慮から、初回相談を無料としている事務所が多くなっています。
弁護士との相性や事務所の雰囲気を確認できる貴重な機会であり、費用を気にすることなく複数の弁護士から話を聞くことが可能です。
「弁護士法人アクロピース」では、初回相談60分を無料で実施しています。
離婚問題・財産分与に精通した弁護士が、一人ひとりの状況やご希望を丁寧にヒアリングし、適切な解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
着手金
着手金は、弁護士に事件を正式に依頼する際に発生する初期費用です。
依頼した事件の結果(勝訴・敗訴・和解など)に関わらず支払う必要があり、原則として依頼者に返還されることはありません。
着手金の金額は、事件の法的・事実的な難易度や対象となる財産の価額などによって大きく異なります。
例えば、財産分与のような事案では、対象となる財産の総額が大きければ大きいほど、それに比例して着手金も高くなる傾向があります。
また、事件の進行状況に応じて追加の着手金が発生するケースも珍しくありません。交渉段階で解決に至らず、調停や裁判へと手続きが移行する際は、それぞれの手続きごとに新たな着手金が必要となる場合があります。
弁護士との契約を締結する前には、着手金について十分に確認しておくことが極めて重要です。
初期の着手金だけでなく、事件が長期化した場合の追加着手金の発生条件や、その概算総額について確認しておきましょう。
成功報酬
成功報酬とは、事件が解決した際に、その成功の度合いに応じて支払う費用です。一般的に、取得した財産の額(経済的利益)の割合に応じて計算されます。
つまり、弁護士の働きによって得られた財産が多ければ多いほど、報酬額も大きくなるのが特徴です。着手金を低く設定し、成功報酬の割合を高くしている事務所など、料金体系はさまざまなので、依頼前に確認しておきましょう。
その他
弁護士報酬(着手金・報酬金など)とは別に、事件処理をするうえで実際にかかる費用も依頼者に請求されるのが一般的です。
具体的には、以下のような費用が含まれます。
- 印紙代
- 郵便切手代
- 裁判所への交通費
- 不動産鑑定費用
- 謄写費用
- 日当
弁護士との契約時には、弁護士報酬だけでなく、実費についてもどのような項目が、どのようなタイミングで発生する可能性があるのかを十分に確認し、不明な点は質問することが重要です。
財産分与の弁護士費用の相場
現在、弁護士費用は自由化されています。ただ、かつて日本弁護士連合会が定めていた「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」が今でも参考にしている弁護士法人・弁護士事務所は多いです。
以下に、訴訟(裁判)になった場合の着手金と報酬金の目安をまとめました。
| 費用の種類 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 30分5,000円~1万円程度 | 初回無料の事務所も多い |
| 着手金 | 20万円~30万円 | ・事件に着手する際に支払う費用 ・結果にかかわらず返金されないのが原則 |
| 報酬金(成功報酬) | 20万円~30万円+経済的利益の約10~30% | ・離婚成立時に基本報酬が発生 ・財産分与や慰謝料などを得た場合、その額に応じた報酬が加算される |
経済的利益とは、紛争解決によって得られる利益のことをいい、離婚調停の場合慰謝料・養育費・財産分与などで得られた金額をいいます。
上記はあくまで旧基準に基づく目安であり、実際の費用は各法律事務所の規定によります。必ず、依頼前に見積もりを確認するようにしましょう。
財産分与の弁護士費用は誰が払う?相手に請求できるケース
「弁護士費用は相手に払わせたい」と考えるのは自然な感情ですが、原則として弁護士費用は「依頼した本人が全額自己負担」となります。たとえ相手に離婚の原因があったとしても、ご自身が依頼した弁護士の費用を相手方に請求することは、基本的にはできません。
夫婦間の話し合い(協議)や調停で解決する場合は、相手が任意で支払いに応じない限り、弁護士費用を負担させることは困難といえるでしょう。
財産分与と弁護士に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、財産分与と弁護士に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
相手が財産を隠しているかを調べることは可能?
相手が財産を隠しているかを調べることは可能です。個人で調査するには限界がありますが、弁護士に依頼すれば法的な手段を用いて調査できます。
具体的には、弁護士会を通じて金融機関や保険会社などに情報開示を求める「弁護士会照会(23条照会)」があります。また、裁判所の手続きの中で裁判所から調査を依頼する「調査嘱託」も一つです。
これらの手続きにより、相手が隠している預貯金口座や生命保険契約などが見つかるケースは少なくありません。財産隠しが疑われる場合は、弁護士への相談が最も有効な手段です。
財産分与の請求に期限はある?
財産分与の期限に時効はあります。財産分与の請求権は、離婚が成立した時から2年で消滅します(民法768条2項)。
この2年という期間は「除斥期間」と呼ばれ、途中で進行を止めたり(中断・更新)、期間を延長したりできません。2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てるなどの法的な請求手続きを取らないと、権利そのものが失われてしまいます。
なお、法改正によりこの期間が5年に伸長される予定ですが、まだ施行されていません(2025年現在)。離婚後は速やかに行動を起こすことが極めて重要です。
弁護士に無料相談するだけでもメリットはある?
弁護士に無料相談するだけでも大きなメリットがあります。無料相談を利用することで、費用をかけずに専門家から客観的なアドバイスを得られるためです。
ご自身の状況でどのような財産分与が見込めるのか、法的な見通しはどうか、相手の主張に問題はないか、といった点を整理できます。また、弁護士の人柄や事務所の雰囲気を確認し、自分と相性の良い弁護士かどうかを見極める機会にもなるでしょう。
依頼するかどうかは別として、まずは専門家の意見を聞いてみること自体に価値があります。
住宅ローンが残っている家はどのように分与する?
住宅ローン付きの家は、その価値とローン残高の関係によって扱いが異なります。具体的には、家の時価がローン残高を上回る「アンダーローン」か、下回る「オーバーローン」かで判断します。
| アンダーローンの場合 | 家の価値からローン残高を差し引いたプラスの部分(純資産価値)が財産分与の対象となります。 |
|---|---|
| オーバーローンの場合 | ローン残高が家の価値を上回っているため、資産価値はゼロまたはマイナスと評価されます。 この場合、不動産自体は財産分与の対象とはならず、残ったローン(負債)をどう分担するかが問題となります。 |
いずれのケースも、不動産の適正な評価や金融機関との交渉など、複雑な問題が絡むため、専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
「弁護士法人アクロピース」では、初回相談60分を無料で実施しています。
離婚問題・財産分与に精通した弁護士が、一人ひとりの状況やご希望を丁寧にヒアリングし、適切な解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応
まとめ|適切に財産分与を実施するために弁護士に依頼しよう
この記事では、財産分与の基本的な考え方から、弁護士に依頼すべき具体的なケース、費用などを網羅的に解説しました。
財産分与は、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を公平に分ける手続きであり、原則として貢献度を等しいと見なす「2分の1ルール」が適用されます。
しかし、対象となる「共有財産」と対象外の「特有財産」の区別は複雑で、特に不動産や株式、相手の財産が不透明な場合など、専門的な判断が不可欠な場面は少なくありません。
また、財産隠しが疑われる場合の調査方法や、有利な分与割合を主張するための法的構成、複雑な資産の適正な評価など、多くの局面で専門家の力が必要になる可能性があります。
もし今、「相手との交渉に行き詰まっている」「財産の全体像が見えず不安である」と感じているのであれば、専門家に相談することが大切です。一人で悩み続けるのではなく弁護士に相談し、具体的な一歩を踏み出しましょう。
離婚・財産分与の問題に直面されている方は、相続・離婚問題に強みを持つ「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたの状況を丁寧に伺い、最善の解決策をご提案します。
初回60分の無料相談も実施しています。お気軽にお問い合わせください。
\ 相談実績7000件以上/
【無料相談受付中】365日対応