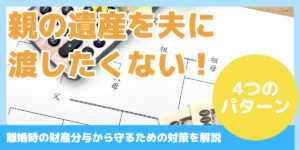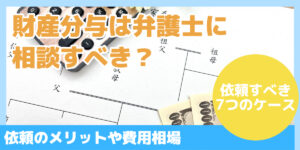財産分与の割合はどのくらい?例外ケースや注意点を弁護士が解説

「財産分与の割合はどう決まるの?」
「収入が高い方がより多く財産をもらえるのではないか?」
離婚を控え、このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける制度です。財産分与の割合は原則2分の1ですが、例外的に取り分が増減する場合もあります。
本記事では、自分の割合を正しく主張する方法と注意点を弁護士が解説します。
離婚に伴う財産分与であなたの取り分を正しく確保するためにも、ぜひ最後までご覧ください。
財産分与の割合にお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
経験豊富な弁護士が状況を正確に分析し、あなたにとって最善の解決策を提案します。
初回60分の無料相談に、まずはお気軽にお問い合わせください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
財産分与とは?知っておきたい基礎知識
財産分与は、離婚に際して夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分ける制度です。理解が不十分だと「何が対象になるのか」「どのくらい請求できるのか」で思わぬトラブルに発展することも少なくありません。
財産分与に関して特に押さえておくべき基礎知識は次の3つです。
財産分与の仕組みを正しく理解し、離婚後の生活基盤を守るための知識を整理しておきましょう。
財産分与の請求期限
現行法では、離婚成立から2年以内に財産分与を請求しなければなりません(民法768条2項)。
この期間は「除斥期間」と呼ばれ、過ぎてしまうと一切の請求が認められなくなります。
財産分与の請求期限は、2024年5月に成立した民法改正により、現行の2年から5年に延長される予定です(2026年5月までに施行予定)。
ただし、施行前に離婚が成立したケースには従来どおり2年の期限が適用されます。
たとえ期限が延びたとしても、請求手続きを遅らせるのは危険です。
時間が経つほど、相手が財産を費消・隠匿するリスクが高まり、話し合いに応じてくれる可能性も低くなるため、可能な限り離婚前に協議するようにし、離婚後になってしまった場合でもできるだけ早めに請求しましょう。
財産分与の対象になる財産・対象にならない財産
財産分与の対象は、婚姻中に夫婦の協力で築いた「共有財産」です。
一方、結婚前からの財産や相続・贈与による財産など、夫婦の協力と無関係に得たものは「特有財産」とされ、分与の対象外になります。
財産分与の対象となる共有財産と、分与の対象外である「特有財産」の具体例は以下のとおりです。
| 区分 | 種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 共有財産(財産分与の対象) | 預貯金・現金 | 給与振込口座、へそくりなど |
| 不動産 | 夫婦で購入した土地や建物 | |
| 動産 | 自動車、家具、家電 | |
| 有価証券 | 株式、投資信託など | |
| 保険 | 学資保険・生命保険の解約返戻金 | |
| 退職金・年金 | 婚姻期間に対応する部分 | |
| 特有財産(財産分与の対象外) | 婚姻前の財産 | 結婚前に貯めた預金、購入した不動産 |
| 相続・贈与財産 | 親から相続した現金や不動産、贈与による資産 |
このように、名義が夫か妻かを問わず、婚姻中に協力して築いた財産は共有財産とみなされます。給与や貯金、住宅など、夫婦生活を支える財産が中心です。
一方で、結婚前から保有していた財産や、親からの相続・贈与による資産は特有財産として扱われ、財産分与の対象から外れます。
実務では、この「共有財産」と「特有財産」の線引きがしばしば争点になります。
法律上、どちらに属するか不明な財産は原則として「共有財産」と推定されるため、特有財産だと主張する側は、通帳や契約書などで資金の出どころを証明しなければなりません。
関連記事:財産分与の対象にならないものとは?相続遺産や親からの贈与を守る方法【弁護士監修】
財産分与の3つの性質と目的
財産分与は、大きく3つの性質を持っています。代表的なのは次の3つです。
- 清算的財産分与:夫婦が協力して築いた財産を公平に分けるもの
- 扶養的財産分与:離婚後に経済的に不安を抱える側を援助するもの
- 慰謝料的財産分与:離婚原因による精神的苦痛を分与額に反映するもの
「清算的財産分与」は、最も基本的な性質です。収入だけでなく、家事や育児といった家庭内の貢献も同じように評価されます。離婚の原因を作った側であっても、財産形成への貢献があれば分与を受け取る権利が認められます。
「扶養的財産分与」は、病気や育児・介護、高齢等の事情で、離婚後に経済的に困窮する一方当事者を援助すべき場合に利用されるものです。ただしこれは例外的であり、基本は清算的財産分与が主となります。
「慰謝料的財産分与」は、不貞やDVによる精神的苦痛を、財産分与に上乗せして解決する考え方です。本来は慰謝料請求と別制度ですが、実務では、慰謝料という名前を避けて「解決金」名目にしたり、「財産分与」とまとめて処理する場合もあります。
関連記事:離婚時の財産分与はどうなる?家や貯金の分け方・手続きの流れを弁護士が解説
財産分与の割合を決めるまでの3ステップ
財産分与を円滑に進めるためには、計画的かつ段階的なアプローチが必要です。基本的には以下のステップで進行します。
この流れを理解しておくことで、感情的な対立を避けつつ、効率的に手続きを進められるでしょう。
分与対象になる共有財産を正確に把握する
財産分与の第一歩は、夫婦の共有財産を正確に洗い出すことです。預金通帳や不動産の登記事項証明書、などの財産を裏付ける資料を集めて「財産目録」を作成することです。
次に重要なのが「基準時」の統一です。裁判実務では、夫婦の協力関係が事実上終了したとされる「別居時」が基準とされるのが一般的です。したがって、別居時点での預金残高や不動産の評価額を正確に押さえておく必要があります。
また、相手が財産を隠すおそれもあるため、以下のような対策も講じましょう。
- 同居中に資料をコピーしておく
- スマホなどで撮影して保存しておく など
早い段階での証拠確保が、後の交渉を有利に進める助けとなるでしょう。
夫婦で話し合い(協議)を進める
財産の全体像を把握したら、次は夫婦での話し合い(協議)に進みます。当事者間で合意できれば、時間や費用の負担を最も少なく抑えられるため、最も望ましい解決が可能です。
合意した内容は、必ず書面に残しておきましょう。当事者間で作る「離婚協議書」よりも、公証役場で「公正証書」として作成しておくと安心です。
公正証書は、公証人が内容を確認して作成するた公的文書であり、裁判においても強力な証拠として認められます。養育費等、将来にわたっての金銭給付を約束するときは、特に公正証書として作成しておくことをおすすめします。
公正証書の場合、通常「強制執行認諾文言」が入りますので、公正証書は裁判の判決と同じ効力を持つ「債務名義」です。
これにより、相手が養育費等を支払わない場合でも、新たに訴訟を起こすことなく、給与や預金を差し押さえる強制執行が可能になるでしょう。
解決しなければ調停や審判・訴訟に進む
夫婦間の協議で合意に至らない場合や、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所での法的手続きに進みます。
財産分与のみが争点である場合には、まず調停で解決を試み、調停で合意できなければ審判によって解決します。
財産分与だけでなく離婚についても争点となっている場合には、離婚調停の中で解決を試み、調停で解決できなければ離婚訴訟で解決する流れです。
それぞれの特徴を以下にまとめました。
| 手続き | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 調停 (離婚調停・財産分与請求調停) | 裁判官と調停委員が仲介し、双方の主張を調整する | 話し合いベースで、合意が成立しなければ終結 |
| 審判 | 調停で合意できなかった場合に、裁判官が事情を考慮して分与方法・額を決定 | 非公開で進み、当事者の合意がなくても法的拘束力あり |
| 訴訟 (離婚訴訟の中で財産分与を争う場合) | 公開の法廷で主張・立証を行い、最終的に裁判官が判決を下す | 判決は法的拘束力が強く、強制執行も可能 |
調停は「中立的な第三者の仲介による話し合い」で、合意が前提となる一方、審判や訴訟では裁判所が強制的に判断を下すため、当事者の意向にかかわらず法的拘束力を持ちます。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫証拠収集や書面作成には専門知識が必要となるため、早めに弁護士へ相談しておくと安心です。
財産分与の割合は「原則2分の1」
財産分与の割合は、裁判実務で一貫して「夫婦が半分ずつ分けるのが原則」とされています。共働きか専業主婦(主夫)か、収入の多寡にかかわらず、夫婦の貢献は等しく評価されるという考え方です。
この章では次の3点を解説します。
共働き・専業主婦(主夫)・収入差にかかわらず折半が基本
財産分与の割合は、共働きか専業主婦(主夫)か、収入差が大きいかどうかにかかわらず、原則として2分の1ずつです。その背景には、婚姻生活を「役割分担による共同事業」とみなす考え方があります。
裁判所は、収入を得る活動と、家事・育児で家庭を支える活動とを同じくらい価値があると評価しています。
したがって「自分が稼いだ分は自分の財産」という主張は通らず、あくまでも「夫婦二人で築いた財産を折半することを理解しておきましょう。
財産分与の割合に影響しない要素
財産分与の割合は原則「2分の1」であり、「子どもの有無」や「離婚原因」は割合に影響しません。
未成年の子どもがいても、その生活費や教育費は「養育費」で別に扱われるため、財産分与の割合とは分けて考えます。
また、不貞やDVといった離婚原因があっても、有責配偶者の財産分与の権利は失われず、精神的苦痛の賠償は「慰謝料」として別途請求されるべきものです。
つまり、財産分与はあくまで「夫婦で築いた財産の清算」であり、慰謝料や養育費とは別に考える必要があります。
たとえば、「不倫をされたのだから、自分が多くもらうべきだ」という主張は認められませんが、「財産は折半しつつ、不倫の慰謝料を別途請求する」という形であれば正当な主張となります。
当事者の合意による割合変更は可能?
財産分与の割合は、裁判所が判断する場合には「原則2分の1」が基準となります。しかし、夫婦が話し合って合意する場合には、この割合を自由に変更が可能です。
たとえば、「子どもの進学費用を考慮して一方に多めに渡す」「離婚後の生活を安定させるために7対3で分ける」といった取り決めもできるでしょう。
ただし、合意する際には次の点に注意が必要です。
- 書面に残しておく:口約束では後々トラブルになりやすいため、決まったことは必ず書面に残しておきましょう。
- 不公平すぎる内容は無効のおそれがある:「10対0」など極端に不利な条件は、公序良俗違反として裁判所に否定される場合があります。
- 合意の経緯が重要:脅迫や強要のもとで結ばれた合意は無効になり得るため、双方が納得していることが前提です。
つまり、自由な合意は認められる一方で、「形式の整備」と「公正さの確保」が欠かせません。適切な書面を用意し、必要に応じて弁護士に確認してもらうことが、後のトラブル防止につながります。



特に口約束や簡単なメモだけでは、裁判で合意を証明できず無効になることがあります。
【例外】財産分与の割合が変更される5つのケース
中には財産分与を2分の1にすると、不公平に感じる場合もあるでしょう。その不満が裁判所に認められると、例外的に財産分与の割合が変更されることがあります。
ただし、この例外が認められるのは限られたケースにすぎません。主張する側には、客観的な証拠をもとに「なぜ折半では不公平なのか」を厳しく立証することが求められます。
財産分与の割合が変更されるのは、以下のようなケースです。
詳しく見ていきましょう。
特別な能力・資格・経営などで大きく財産形成した場合
夫婦の一方が特別な能力で莫大な資産を築いた場合、裁判所は財産分与の割合を変更することがあります。主に対象となるのは、高度に専門的な知見、芸術的才能など、本人固有の資質に依存したケースです。
実際に、上場企業の経営者が築いた220億円の資産については、妻への財産分与が5%(10億円)にとどまった判例もあります(東京地判平成15年9月26日)。
一方の特別な能力由来の資産が2分の1ルールの例外として認められるかどうかは非常に難しく、単に高収入であるだけでは足りません。
一般的な「内助の功」を超えていると立証できる場合に限られます。例外が認められるハードルは極めて高い点には注意が必要です。
一方の激しい浪費があった場合
ギャンブルや過度な遊興、不貞相手への高額な支出などによって共有財産を大きく減らした場合、浪費した側の取り分は不利に変更される可能性があります。
この場合、裁判所は「浪費がなかったもの」として財産を計算し、その分を浪費した側の持分から差し引く「持ち戻し計算」を行うことがあります。
たとえば夫婦の財産が800万円あり、そのうち夫が300万円をギャンブルで浪費した場合でも、共有財産の基準は800万円とみなされます。結果的に妻は400万円を受け取り、夫の取り分は浪費分を差し引いた100万円程度に減らされることになるのです。
浪費の主張が認められるためにはクレジットカード明細や借金契約書などの明確な資料が欠かせません。
家事や育児の著しい怠慢があった場合
家事や育児を放棄して、夫婦の共同生活にほとんど貢献していなかった場合も、財産分与の割合が変更される場合があります。
裁判所は、家事や育児といった家庭内での労働も財産形成への重要な貢献と評価しているため、その役割を長期間にわたり果たさなかったことが立証されれば、貢献度が低いと判断されるのです。
たとえば長期間にわたり家事や育児を一切担わず、生活費の負担もしなかったような場合には「家庭を放棄していた」と評価されることがあります。
ただし、「家事が苦手」や「子育てに消極的だった」といった主観的な不満では認められません。
こちらのケースも、証拠として生活実態を示す資料や第三者の証言が必要となります。日常の行動は数値や書面として残りにくいため、この主張が認められるのは非常に例外的です。
特有財産を投入して共有財産が形成された場合
結婚前の貯金や親からの相続財産などの特有財産を共有財産の購入に充てた場合、その分は分与割合に反映される可能性があります。
たとえば3,000万円のマンションを買う際、妻が親からの贈与500万円を頭金にし、残り2,500万円を夫婦の収入からローンで返済した場合です。
この場合、妻は頭金分(6分の1)を特有財産として確保した上で、残りを夫婦で折半することになります。マンションが2,400万円で評価されれば、妻は1,400万円、夫は1,000万円を取得できる計算です。
この扱いを認めてもらうには、頭金が特有財産であることを証明する契約書や送金記録といった客観的資料が欠かせません。
婚前契約(夫婦財産契約)がある場合
婚前契約(夫婦財産契約)を結んでいる場合には、その内容に基づいて財産分与の割合が変更されることがあります。
夫婦財産契約は、夫婦が婚姻前に財産の帰属や分与方法を取り決める制度であり、原則として契約の内容が優先されるのです。
契約の効力を確実にするためには、私的な合意書にとどめず、公証役場で「公正証書」として作成しておくと良いでしょう。公正証書は争いが生じた際にも有効な証拠として機能します。
ただし、婚前契約であっても内容が著しく不公平な場合には、多くが効力を認められません。
たとえば、「離婚原因を問わず、妻は財産分与を一切請求できない」といった条項は、公序良俗に反するとして裁判所で無効とされる可能性があります。



財産分与の割合が修正されるケースはごく限られており、主張を認めてもらうためには客観的な証拠と専門的な判断が不可欠です。
財産分与の割合を有利にするための準備
財産分与は「原則2分の1」ですが、証拠や準備次第で結果が大きく変わることがあります。話し合いを有利に進めるためには、事前の準備が重要です。
離婚を協議する前に、以下の準備を進めておくと、財産分与を有利に進められるでしょう。
財産資料を早めに確保する
財産分与で最も重要なのは「どんな財産があるのか」を正確に示すことです。
下記のような財産を裏付ける資料は、できるだけ同居中からコピーやデータの保存をしておきましょう。
- 通帳
- 不動産の登記事項証明書
- 保険証券
- 株式の取引明細 など
離婚を意識し始めてから資料を集めようとしても、相手が隠したり処分したりするケースが少なくありません。
特に、不動産の評価額や退職金の見込み額は後から把握が難しいため、証明資料の確保は早いほど有利です。
特有財産の出所を明確にする
「結婚前からの貯金」や「相続で得た現金」などは特有財産にあたり、分与の対象外です。ただし、主張するには明確な証拠が必要となります。
たとえば、以下のような証拠が有効です。
- 結婚前の預金通帳の残高証明
- 親からの相続を示す遺産分割協議書
- 贈与契約書など
これらを整理せず生活用口座に入金してしまうと、共有財産と混同され「特有」と認められなくなるおそれがあります。
将来の争いを避けるためには、特有財産は別口座で管理し、証拠を時系列で揃えておくことが重要です。
浪費の記録を残しておく
相手がギャンブルや不倫で浪費していた場合、立証できれば自分に有利な割合を主張できます。ただし、証拠がなければ単なる主張として割合の変更は認めてもらえません。
有効なのは、クレジットカードの利用明細、ローン契約書、相手名義の高額送金記録、不自然に高額な出費がわかる家計簿などです。
たとえば「給料日に50万円を引き出し、その直後にパチンコ店で大金を使った」とわかる記録があれば、裁判所も浪費と判断しやすくなります。



日常的にレシートや通帳コピーを残しておく習慣が、いざというときに自分の取り分を守る武器になります。
財産分与の割合にお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
経験豊富な弁護士が状況を正確に分析し、あなたにとって最善の解決策を提案します。
初回60分の無料相談に、まずはお気軽にお問い合わせください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
財産の評価額で揉めたときの解決策
財産分与では「財産をいくらと評価するか」で争いになることが少なくありません。特に不動産や退職金、株式などは評価額が変動しやすいため、解決策を知っておくことが大切です。
不動産の評価方法で揉めた場合
不動産は、評価の仕方によって大きく金額が変わります。主な評価基準は次の3つです。
- 固定資産税評価額:市区町村が課税のために算定する価格で、時価の7割程度になることが多い。
- 路線価:相続税・贈与税の算定に用いられるもので、時価の8割程度を目安とする。
- 時価(実勢価格):実際の売却相場で、最も高額になりやすい。
たとえば、同じ不動産でも固定資産税評価額は2,000万円、路線価は2,400万円、時価は3,000万円と評価が分かれることがあります。
売却予定がある場合は時価、そうでなければ路線価や固定資産税評価額を基準とするなど、ケースに応じた選択が必要です。
相手と評価額で合意できないときは、不動産鑑定士に鑑定を依頼し、専門家による客観的評価をもとに解決することも有効です。
退職金の評価額で揉めた場合
退職金は「すでに支給されたもの」か「将来支給が見込まれるもの」かによって評価方法が大きく異なります。特に、将来分の退職金は「支給がどの程度確実か」「婚姻期間に対応する割合をどう計算するか」が裁判で争点になる部分です。
たとえば、勤続20年以上で定年退職が近い場合には、将来の退職金も財産分与の対象とされやすいものです。
一方、勤続年数が短い場合には「退職金の支給が不確実」として対象外になる場合があります。
裁判所は勤務先の退職金規程や支給見込み額を示す資料を重視するため、労働契約書や就業規則、勤務先からの証明書を入手できるかどうかが結果を大きく左右します。
弁護士に依頼すれば、必要資料の収集方法や主張の整理をサポートしてもらえるでしょう。
株式や投資信託の評価額で揉めた場合
株式や投資信託などの金融商品は相場変動が大きいため、「別居時の価格を基準にするのか」「清算時の価格を基準にするのか」で意見が割れるケースが多くあります。
特に景気変動が激しい時期には評価額の差が数百万円単位になることもあり、当事者の主張が対立することも少なくありません。
たとえば、別居時に500万円だった株式が清算時には300万円に下落していた場合、夫婦のどちらに基準を合わせるかで取り分が大きく変わります。反対に、上昇して800万円になっていた場合も同様で、どちらの基準が「公平」かで揉めるのです。
実務では「別居時点を基準にする」のが原則ですが、清算時の価格を採用すべきと主張されるケースもあります。
いずれにせよ証券会社の取引履歴や基準日の評価額を示す書面を確保しておくことが、公正な解決のために不可欠といえるでしょう。



不動産や退職金など、評価が分かれやすい財産でも、専門的な知識をもとに冷静に整理すれば公平な結論へ導くことが可能です。
【種類別】財産分与の割合の考え方
財産分与の対象となる財産は、預貯金や不動産、保険、借金など多岐にわたります。種類ごとに評価方法や分割方法が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
ここでは、以下の財産における、分与の考え方を解説します。
預貯金
婚姻期間中に夫婦の収入から積み立てられた預貯金は、名義が誰であっても共有財産とされ、原則2分の1ずつに分けられます。
夫名義の口座はもちろん、妻や子ども名義の口座であっても、実質的に夫婦の収入から拠出されていれば財産分与の対象です。
さらに重要なのは「どの時点の残高を、共有財産の基準にするか」です。
裁判実務では、夫婦の協力関係が事実上終了した「別居時点」を基準にするのが一般的とされています。そのため、別居後に積み立てた預貯金は対象外と扱われるのです。
別居開始時点の残高を確認できる通帳や銀行の証明書があれば、財産分与で自分の取り分を正しく主張できるでしょう。
保険(学資保険・生命保険など)
下記のような貯蓄性のある保険は、解約返戻金があるため財産分与の対象になります。
- 学資保険
- 終身保険
- 個人年金保険 など
一方、掛け捨て型保険は解約返戻金がないため分与の対象外です。
財産分与の評価基準は「別居時または離婚時点の解約返戻金額」です。支払った保険料の合計ではなく、その時点で解約すれば戻ってくる金額を基準に計算します。
婚姻前から加入していた場合は、婚姻期間中に積み立てられた部分だけが共有財産とされます。たとえば、基準時の返戻金が300万円で、婚姻時点の返戻金が100万円なら、その差額200万円が分与の対象です。
実務では保険契約を現物で分けることは難しいため、一方が契約を続け、もう一方に解約返戻金の半額を代償金として支払う方法がよく用いられます。
借金・ローン
財産分与では、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや自動車ローンといったマイナスの財産(負債)も含めて清算します。
ただし、分与の対象となるのは住宅の購入資金、子どもの教育費、生活費の補填といった「夫婦の共同生活を維持するために負担した借金」に限られます。
一方で、ギャンブルや浪費、趣味のための借金など、夫婦の生活に関係のないものは共有の負債とはみなされず、個人が返済義務を負います。
財産分与の計算は、プラスの財産から共有の借金を引いた「純資産」を基準に行います。
もし、負債が資産を上回る「オーバーローン」の状態であれば、分与すべき財産が存在しないため、原則として財産分与は行われません。
不動産(マンション・土地など)
不動産は財産分与の中でも特に扱いが難しく、分割方法が争点になりやすい資産です。代表的な方法には、次の2つがあります。
- 換価分割
- 代償分割
換価分割は、不動産を売却して現金化し、諸費用やローン残債を差し引いた残額を夫婦で分ける方法です。最もシンプルで公平ですが、売却までに時間がかかったり、希望価格で売れなかったりといったリスクがあります。
代償分割は、一方が不動産を取得して住み続け、もう一方に代償金を支払う方法です。この場合、不動産の適正な評価と、代償金を支払えるだけの支払い能力が前提となります。
なお、「名義」は結論を左右しません。婚姻中に夫婦の協力で形成・取得された資産であるかどうかが判断の軸です。
財産分与における不動産の扱いは、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:共有名義ローンは夫・頭金は妻の離婚における財産分与の問題点を解説
子どもの名義資産
子どもの名義資産は「当然に子どものもの」と思われがちですが、資金の出どころによっては財産分与の対象になります。
夫婦の収入や児童手当を積み立てた口座や学資保険は、夫婦が築いた財産とみなされ、共有財産として分与の対象です。
一方で、下記のようなお金は「子どもの固有財産」として扱われ、財産分与の対象外となります。
- 祖父母からのお年玉や入学祝い
- 親戚からの贈与
- 子ども自身のアルバイト収入 など
ただし、夫婦の収入と祖父母からの贈与が同じ口座で混ざっていると、共有財産と判断される可能性があります。
資金の出所を証明するためにも、通帳の取引履歴や贈与契約書など客観的な証拠を残しておきましょう。
退職金・年金
退職金は給与の後払いと考えられるため、婚姻期間中に対応する部分が財産分与の対象です。
まだ支給されていなくても、支給が見込まれる場合には将来の退職金も対象に含まれることがあります。
なお、財産分与の話ではありませんが、年金については「年金分割」が設けられており、婚姻期間中に納めた厚生年金や共済年金の記録を夫婦で分け合うことが可能です。
国民年金(基礎年金)は対象外ですが、この制度を利用することで専業主婦(主夫)であった側も将来年金を受け取れるようになります。
なお、年金分割の請求期限は離婚後2年以内です。
これは民法に定める財産分与の請求期限とは別の制度に基づくものであり、たとえ民法の改正で財産分与の期限が延長されても、年金分割については従来どおり2年以内です。
ただし、国会では年金分割の請求期限についても、5年以内にする法案が提出されています。今後の動向が注目されます。(参照:厚生労働省|その他の制度改正事項について|1.離婚時の年金分割の請求期限の延長)
関連記事:熟年離婚の財産分与はどうすべき?具体的な進め方や起こりやすいトラブルを解説【弁護士監修】



財産の種類ごとに分与のルールや注意点は大きく異なるため、個別事情に応じた正しい判断が不可欠です。
財産分与の割合を決めるときに注意すべき2つのポイント
財産分与の交渉や手続きを進める上では、戦略的な視点が必要です。
特に、2分の1ルールの変更を求める場合や、相手の不誠実な対応が疑われる場合には、以下の2つのポイントを意識しましょう。
財産分与の割合変更を主張するときは証拠が必要
財産分与は「原則2分の1」が強固なルールですが、特別な事情を理由に割合変更を求める場合には、必ず客観的な証拠が求められます。単なる主張や感情的な言い分では裁判所に認められません。
証拠として有効なのは、次のような資料です。
- 財産形成の経緯を示す資料:預貯金通帳、不動産の登記簿、売買契約書など
- 浪費や怠慢を裏付ける資料:クレジットカードの利用明細、領収書、家計簿、生活実態を記録した資料など
- 特有財産の寄与を示す資料:遺産分割協議書、婚姻前からの通帳履歴、贈与契約書など
- 判例や統計の調査結果:過去の裁判例や司法統計を示し、自分の主張に合理性を持たせる
証拠を揃えることで、裁判所に対して「なぜ2分の1ルールを修正すべきか」を具体的に説明できるようになります。
ただし、これらの資料を網羅的に収集し整理する作業は非常に煩雑です。
弁護士に依頼すれば、必要な証拠を効率的に揃えられるだけでなく、法的に正しい整理を経て説得力のある主張につながるでしょう。
相手の財産隠しが疑われるなら早めに弁護士に相談する
財産隠しは、受け取れるはずの財産分与額を不当に減らされるおそれがあります。
相手が預金を開示しなかったり、不動産を過少申告したりするケースもあり、個人で全てを調べるのは困難です。財産隠しの疑いがある場合には、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士は、まず交渉で任意の財産開示を求め、それでも応じなければ弁護士会照会を通じて金融機関や勤務先から情報を収集します。
さらに調停や訴訟に進めば、裁判所を通じて資料を取り寄せる調査嘱託によって、より強力な調査が可能です。
もし相手が分与させないために財産を処分しようとしている場合には、仮差し押さえによって資産を一時的に凍結し、権利を守る手段も取れるでしょう。



これらの専門的な手続きは、状況に応じた適切なタイミングと方法で行う必要があり、専門家である弁護士の判断と実行力が不可欠です。
財産分与の割合で悩んだときに弁護士に相談するメリット
財産分与は、法的知識や証拠の収集、相手との交渉など、多くの労力を必要とします。
自分だけで進めようとすると、思わぬ不利益を被る可能性もあるでしょう。
ここでは、弁護士に相談することで得られる具体的なメリットを3つの観点から解説します。
財産調査・証拠収集で適正な財産分与の割合を主張できる
弁護士は、弁護士会照会や調査嘱託を通じて、当事者が把握しにくい財産まで調べることが可能です。
隠された預金口座や勤務先の退職金規程なども調査対象となり、公平な分与割合を導くための裏付けとなります。
たとえば、相手が証券口座の所持を開示していなかった場合でも、弁護士を通じて存在を確認できる場合があります。
こうした調査で財産の全体像を明らかにできれば、裁判所の信頼を得やすくなり、主張の説得力も高まるでしょう。
資料の収集や整理を弁護士に任せることで手間を大幅に減らせる点も大きなメリットです。結果として、証拠に基づいた適正な分与割合を確保しやすくなります。
裁判例や法律知識に基づき財産分与の割合の交渉を有利に進められる
弁護士は、過去の裁判例や実務の傾向を熟知しているため、裁判所がどのような判断を下す可能性があるかを見極めることが可能です。
たとえば、「自分のケースで2分の1ルールの例外が認められるか」といった点を、法的根拠に基づいて具体的に予測できます。
また、不動産の評価額についても、路線価・時価・鑑定額といった複数の評価方法の中から、どの基準が採用されやすいかを弁護士が判断してくれるでしょう。
こうした知見を踏まえて交渉に臨めば、相手に対して説得力を持って主張を展開でき、感情論に流されることなく戦略的に進められます。
結果として、交渉全体を有利に運びやすくなるのです。
財産分与の面倒な手続きを任せて精神的負担を軽減できる
離婚や財産分与の手続きは、感情的にも手続き的にも大きな負担を伴います。相手との直接交渉は口論に発展しやすく、調停や訴訟では膨大な書類作成や証拠提出が求められるためです。
弁護士に依頼すれば、以下のような交渉や手続きをすべて一任できるのがメリットです。
- 調停の期日呼び出しに合わせて書類を整える
- 裁判所に適切な証拠を提出する
- 相手とのやりとりをすべて代行する
その結果、依頼者は新しい生活の準備や仕事に集中でき、精神的な消耗を最小限に抑えられます。
さらに「専門家が自分を支えている」という安心感が、困難な時期を乗り越える大きな力になるでしょう。
関連記事:【弁護士監修】財産分与は弁護士に相談すべき?依頼のメリットや費用相場を解説



財産分与は将来の生活を左右する大切な手続きです。不安や迷いがあるときこそ、私たち弁護士が全力であなたの力になります。
財産分与の割合にお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
経験豊富な弁護士が状況を正確に分析し、あなたにとって最善の解決策を提案します。
初回60分の無料相談に、まずはお気軽にお問い合わせください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
財産分与の割合についてよくある質問
財産分与で「妻が多めにもらえる」「夫が多めにもらえる」ということはありますか?
性別によって自動的に取り分が変わることはありません。原則は常に「2分の1ルール」で、夫婦それぞれが平等に財産を分け合うのが基本です。
ただし、例外的に割合が修正されるケースがあります。
たとえば、一方が特殊な能力や経営手腕によって通常では考えられない規模の財産を築いた場合には、その貢献度を踏まえて割合が調整される場合です。
また、もう一方がギャンブルや不貞相手への浪費などで財産を大きく減らしたと証明できれば、その分が不利に計算されることも少なくありません。
このように「妻だから多くもらえる」「夫だから少なくなる」といった単純なルールは存在せず、あくまで夫婦それぞれの財産形成への貢献度に基づいて判断されます。
離婚時に貯金を隠すとどうなりますか?
財産隠しは非常にリスクの高い行為です。
たとえ一時的に隠し通せたとしても、弁護士による「弁護士会照会」や裁判所の「調査嘱託」といった法的手続きを通じて、口座や保険、証券などの存在が明らかにされる可能性は高いです。
隠していた財産が発覚した場合、裁判官からの信用を失い、調停や審判で不利な判断を受けやすくなるでしょう。
さらに、後から発覚すれば追加で分与を命じられるだけでなく、悪質と判断されれば損害賠償の対象になることも考えられます。
「隠した方が得をする」ということはなく、むしろ不利益が大きいのが実情です。財産は正直に開示し、公平な解決を目指すのが最善の対応といえるでしょう。
財産分与で持っていかれない、対象外のものはありますか?
財産分与の対象にならないものは「特有財産」と呼ばれます。これは夫婦の協力で築いた財産ではなく、一方が個人的に得た財産のことです。
特有財産の典型的な例としては、以下の2つです。
- 結婚前から所有していた預貯金や不動産
- 婚姻中であっても、親からの相続や贈与で取得した財産
これらは本人の固有の財産とされ、分与する必要はありません。
ただし、特有財産であることを証明できる資料(通帳、遺産分割協議書、贈与契約書など)がなければ、裁判では共有財産と推定されます。
また、共有口座に入金するなどして他の財産と混ざると、証明が難しくなり「共有財産」と判断される可能性もあるため注意が必要です。
子どもの貯金や学資保険は共有財産に含まれますか?
子ども名義の資産でも、原資が夫婦の収入や児童手当であれば共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。学資保険も同様で、夫婦の収入から保険料を払っていれば対象に含まれます。
一方で、祖父母からのお年玉や祝い金、子ども自身のアルバイト収入は「子どもの固有財産」とされ、財産分与の対象外です。
また、親が毎月お小遣いとして子どもの口座に入金していたケースでは、金額が少額で子どもが自由に使っていた場合には固有財産と認められることがあります。
ただし、金額が大きい場合には「夫婦の財産の移し替え」と判断され、共有財産扱いになる可能性が高いため注意が必要です。
財産分与をしなくてもいいケースはありますか?
財産分与が行われないケースも存在します。代表的なのは、婚姻期間中に共有財産が全く形成されていない場合です。
たとえば、結婚期間がごく短く、別居や離婚までに預貯金や不動産の取得がなかったケースが該当します。
また、夫婦双方が合意して「互いに財産分与請求をしない」と決めた場合にも、手続きは不要です。
ただし、このような合意は後から「言った、言わない」の争いになりやすいため、公正証書などの書面で明確に残しておくことが欠かせません。
「共有財産が存在しない場合」か「夫婦が合意して放棄する場合」に限って、財産分与を行わなくてもよいと考えておきましょう。
まとめ|財産分与の割合は「原則2分の1」!不安なときは弁護士に相談しよう
財産分与の割合は、夫婦の貢献を等しく評価する考え方から、原則「2分の1」に分けるのが基本です。収入差や働き方にかかわらず、このルールは一貫して適用されます。
夫婦の一方がギャンブルなどで財産を浪費した場合や特有財産の持ち込みがあった場合など、公平を保つために割合が修正される例外もあります。
ただし、こうした例外を認めてもらうには、浪費の明細や資金の出所を示す書類など、客観的な証拠が欠かせません。
不安や疑問があるときは、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。専門的な助言を受けることで、公正な分与を実現し、新しい生活に向けて確かな一歩を踏み出せるでしょう。
財産分与の割合にお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。
経験豊富な弁護士が状況を正確に分析し、あなたにとって最善の解決策を提案します。
初回60分の無料相談に、まずはお気軽にお問い合わせください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応