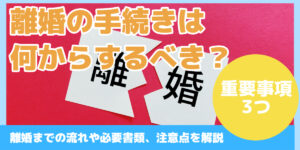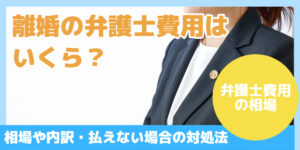離婚してくれない配偶者に疲れたらどうする?相手の心理や法的措置の内容を弁護士が解説
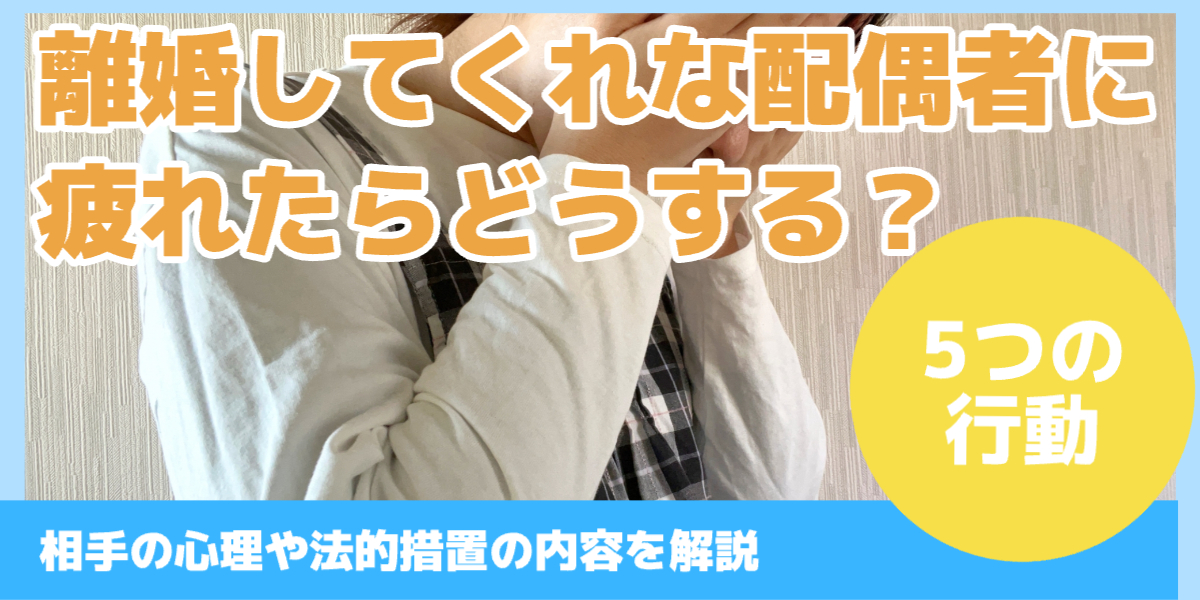
「離婚したいのに、相手が応じてくれないのはなぜだろう」
「何度話しても話し合いが進まず、精神的に限界を感じている」
配偶者が離婚に応じてくれない場合、このような不安や精神的な負担を抱えるのは当然のことです。
配偶者が離婚に応じない背景には、愛情の未練や世間体、経済的な不安など、さまざまな心理が関係しています。
本記事では、離婚を拒む配偶者の心理や話し合いで進展がないときの具体的な対処法、法的手続きを通じた解決方法までを詳しく解説します。
相手に離婚を拒まれて悩んでいる方は、正しい知識を身につけ、問題を解決するための一歩を踏み出しましょう。
配偶者が離婚してくれないとお悩みの方は、離婚問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは、初回60分の無料相談からお気軽にご相談ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚してくれない配偶者の心理とは?
配偶者が離婚を受け入れないのは、感情的な執着だけでなく、生活面や世間体に関する不安も影響しています。
離婚を拒む配偶者の心理で具体的に考えられるのは、以下のとおりです。
配偶者の心理を理解することで、離婚手続きをどう進めるべきか考えやすくなります。離婚を拒み続ける理由や背景を、6つの観点から見ていきましょう。
相手への愛情が残っている
離婚を拒む理由としてまず挙げられるのが、配偶者のなかにまだ愛情が残っているケースです。
「一方的に関係を終わらせたくない」「もう一度やり直せるかもしれない」という未練が、離婚届への署名をためらわせます。
とくに長年の結婚生活を共にしてきた場合、情や思い出が強く残りやすく、別れを現実として受け入れにくくなります。そのため、感情的に説得しても逆効果になる場合が多いのです。
配偶者への愛情がもう残っておらず、関係の修復が難しい場合、相手の心情を否定せずに話し合う姿勢が求められます。
夫婦関係の改善の余地があると思っている
配偶者が離婚を拒む背景には、「まだ関係を修復できる」と考えている心理がある場合もあります。
特に、夫婦間のすれ違いが原因で離婚の話しが出ている場合、以下のような期待をしているケースが考えられます。
- 相手が冷静になれば関係が戻る
- 時間をかければ気持ちが変わる
- 話し合えば解決できる
しかし、離婚を望む側にとっては、気持ちが既に離れている場合が多く、話し合いを続けても平行線をたどるケースが少なくありません。
関係修復が不可能だと感じている理由を説明し、誤解を残さない形で意思を示すことが大切です。
離婚した事実を周囲に知らされるのが恥ずかしい
配偶者が離婚を拒む理由の一つに、周囲の目(世間体)を気にするの心理がある場合も少なくありません。
とくに職場や親族、近所とのつながりが強い人ほど、離婚の事実が知られることに拒否反応を示す傾向があります。
- 離婚を「失敗」と捉えられることへの恐れ
- 離婚の理由が自分にあると思われたくないという気持ち
- 「結婚生活を失敗したと思われたくない」という見栄やプライド
こうした心理から、配偶者は話し合いを避けたり、感情的に反発したりする場合があるのです。
世間体を気にして離婚を拒む配偶者には、『離婚は失敗ではなく、新しい人生を始める選択』と伝えましょう。相手の離婚に対する拒否感を和らげ、現実を受け入れてくれる可能性があります。
離婚後の生活費に不安を感じている
離婚による経済的な不安から決断を避けている可能性もあります。
専業主婦(主夫)やパート勤務の配偶者は、離婚後に収入が減ることを想像して踏み出せなくなるケースも少なくありません。
現実問題として、離婚すれば収入源が分かれ、人によっては生活水準が下がる可能性があります。そのため「離婚したら生活できない」「子どもを養えない」と不安を感じ、離婚そのものを避けようとするのです。
このようなケースでは、以下の内容を具体的に説明し、不安を軽減させることが重要です。
- 経済的な支援制度
- 養育費
- 財産分与の仕組み など
生活再建の見通しを示すことで、相手が離婚を受け入れるきっかけにつながる場合があります。
離婚時の財産分与や離婚準備の詳細は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:離婚時の財産分与はどうなる?家や貯金の分け方・手続きの流れを弁護士が解説
関連記事:子連れ離婚の手続きの順番はどうなる?準備から離婚後までのステップと注意点を弁護士が解説
配偶者に財産を分けたくない
離婚時の財産分与で自身の資産が減ることを嫌がり、離婚を拒んでいる可能性があります。
共有財産と相手と分け合う事実に強い抵抗を示し、「自分が働いて築いた財産を取られるのは納得できない」と考えるケースです。
とくに高額な預貯金や不動産、退職金が関係する場合、財産の減少を避けたい心理が強くはたらき、離婚を引き延ばす傾向があります。
しかし、婚姻中に形成された財産は原則として共有財産であり、法律上は公平に分ける義務があります。
(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。引用:民法|第768条1項
財産分与をめぐる争いは長期化しやすいため、弁護士など専門家を交えて法的に整理するのが現実的です。法的根拠に基づき、冷静に対応しましょう。
財産分与に関する問題を弁護士に依頼するメリットは、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:【弁護士監修】財産分与は弁護士に相談すべき?依頼のメリットや費用相場を解説
子どもと離れたくないと思っている
「子どもと離れたくない」という強い思いから離婚に応じない人もいます。親権を失うことで一緒に暮らせなくなることを恐れ、離婚そのものを避けようとするケースです。
子どもへの愛情が深い親ほど、面会交流では満足できず「離婚すれば子どもとの関係が壊れる」と感じている傾向があります。
相手が子どもを理由に離婚を拒む場合、以下の点を伝えると良いでしょう。
- 離婚後も親子関係は続くこと
- 面会交流によって子どもと定期的に関われること
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫法律上、離婚後も親子関係は続くこと、面会交流という形で関わりを継続できることを具体的に示し、相手の不安を解消することが重要です。
離婚してくれない配偶者に疲れた場合にとるべき5つの行動
話し合いを重ねても離婚に応じてもらえない状態が続くと、心身ともに疲弊してしまいます。
しかし、感情のままに行動しても状況は好転しません。冷静に手順を踏めば、法的にも実質的にも前進できる可能性があります。
ここでは、離婚を拒む配偶者に疲れたときにとるべき5つの行動を紹介します。
ご自分を守りながら、無理なく離婚に向けて動き出すための方法を確認しましょう。
離婚の意思が固まっていることを主張し続ける
配偶者に離婚の意思が固まっていることを一貫して伝えましょう。
一度伝えただけでは、相手が「時間がたてば離婚したい気持ちはなくなるだろう」と誤解し、本気度が伝わらない可能性があります。
離婚の意思を繰り返し伝えることで、相手に本気で離婚を望んでいる姿勢を示すことが重要です。ただし、感情的に伝えるのではなく、なぜ離婚したいのかを具体的に示すことが大切です。
- 価値観の違い
- 信頼関係の崩れ
- 性格の不一致 など
離婚の意思を何度も伝えても拒み続ける場合、本項で紹介している後述の法的措置の実施を検討しましょう。
対立回避のために専門家である弁護士を交えて話し合う
離婚の話し合いが平行線をたどるときは、第三者を交えて話し合うと良いでしょう。
夫婦間だけで話し合いを続けると、感情的な対立に発展してトラブルが発生したり、打開策が見つからず前に進めなかったりする可能性があります。
第三者が間に入ることで、冷静かつ客観的な視点から話を整理でき、離婚の合意が取れる可能性があります。
ただし、親族や友人に依頼すると偏った意見や感情的な衝突を招く恐れがあるため、弁護士に相談するのが現実的です。
離婚の話し合いに弁護士が介入するメリットは以下のとおりです。
- お互いの立場や状況を踏まえて最適な離婚条件を組み立ててくれる
- 法的なルールに基づいた話し合いができる
- 相手の感情的な反発を抑えやすい
一人で悩んで心身ともに疲弊してしまう前に、法律のプロである弁護士へ相談することをおすすめします。
離婚問題を弁護士に相談する場合の費用は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:離婚の弁護士費用はいくら?相場や内訳・払えない場合の対処法を弁護士が解説
別居で物理的な距離を置く
離婚の話し合いが進まないときは、別居して物理的な距離を置くことを検討しましょう。
同居を続けながらの話し合いは、顔を合わせるたびに感情的になりやすく、冷静な判断ができなくなる可能性があるためです。
別居によって生活環境を分けることで、互いに冷静さを取り戻し、自分の気持ちを整理しやすくなります。
また、専業主婦・パート勤務等で、別居中の生活費に不安があるケースでは、婚姻費用の分担請求調停の申し立てを検討しましょう。
婚姻費用分担請求とは、収入の高い方に対し、別居中の生活費の一部を支払うよう求められる法的手続きです。(参照:裁判所|婚姻費用の分担請求調停)
民法第760条では、夫婦が別居していても互いに生活を支え合う義務があると定めています。そのため、別居中であっても配偶者に生活費の支払いを求めることが可能です。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する引用:民法|第760条
ただし、婚姻費用分担請求が必ず認められるわけではありません。
別居の原因が自分にある場合や、浪費・不貞行為などで婚姻関係を破綻させたとみなされる場合には、請求が認められない可能性があります。
離婚条件の一部を妥協する
離婚の合意が得られないときは、離婚条件の一部を妥協することで交渉が進む場合があります。
すべての希望を通そうとすると、相手の反発を招き、話し合いが長期化するケースも少なくありません。
まずは、配偶者がとくにこだわっている条件を整理しましょう。その上で、ご自分が「絶対に譲れない条件」と「譲歩できる条件」を明確にしておきます。
| 条件の優先順位 | 具体例 |
| 絶対に譲れない条件 | 養育費、親権 など |
|---|---|
| 譲歩を検討できる条件 | 財産分与の割合、慰謝料 など |
すべてを譲る必要はありませんが、上記のように優先順位を整理し、一部の条件を妥協することで合意に近づく場合があります。ただし、焦って不利な条件を受け入れるのは避けましょう。
判断が難しい場合は、弁護士に相談しながらご自分にとって最適なラインを見極めることをおすすめします。
法定離婚事由に該当していれば証拠を集める(DV・モラハラなど)
相手が離婚を拒否し続けても、不貞行為や悪意の遺棄などの法定離婚事由(民法第770条)に該当していれば、裁判で離婚が認められます。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判で離婚を認めてもらうには、主張を裏づける客観的な証拠が必要です。以下に、主な離婚理由と証拠の例をまとめました。
| 法定離婚事由 | 証拠例 |
|---|---|
| 不貞行為 | ラブホテルへの出入り写真 メール・クレジットカードの利用履歴 |
| 悪意の遺棄 | 生活費の不払い 正当な理由のない同居拒否の記録 |
| 3年以上の生死不明 | 捜索願の受理証明書 警察の捜査記録 |
| 強度の精神病 ※2024年の民法改正により削除予定 | 医師の診断書、治療の記録 |
| その他婚姻を継続し難い重大な事由 | DV(診断書・写真) モラハラ(日記・録音・メール) |
暴言や暴力の録音、浮気や不倫を示すLINEやメールのやり取りなどは有力な証拠になります。



証拠の収集には時間と労力がかかりますが、離婚問題に強い弁護士に相談すれば、どの証拠が有効かを見極めながら進められます。
離婚を拒む配偶者をどう説得すべきか悩んでいる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
離婚問題に詳しい弁護士が、話し合いの進め方や法的な手段について丁寧にご案内します。
まずは、初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
不倫で離婚を検討している場合の証拠集めに関しては、以下の記事をご覧ください。
離婚してくれない配偶者に疲れたときに検討すべき法的措置
話し合いを続けても離婚に応じてもらえない場合は、法的な手続きを検討する段階に入ります。この段階まで行くと、話し合いでは結論が出にくいため、弁護士や裁判所を介した手続きが必要です。
ここでは、離婚を拒む相手に対して実行できる2つの法的手段「離婚調停」と「裁判離婚」の概要を解説します。
それぞれの手続きの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選びましょう。
離婚調停
配偶者が離婚を拒否し続けた場合、次の段階として家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停とは、裁判官や調停委員が第三者として間に入り、夫婦双方の主張を整理しながら合意による解決を目指す手続きです。(参照:裁判所|夫婦関係調整調停(離婚))
離婚調停の主な特徴は以下のとおりです。
- 調停委員が間に入るため、感情的な対立を避け、冷静かつ公平に話し合える
- 夫婦が直接顔を合わせる時間は少なく、調停委員を介して交互に意見を伝える
- 申立ては、必要な書類と費用を準備し、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行う
なお、双方が合意している場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ではなく、話し合いで決定した家庭裁判所を利用しても問題ありません。
調停が不成立に終わった場合、裁判離婚に移行します。スムーズに解決へ進めるためには、早い段階で弁護士に依頼し、調停に備えた証拠や主張を整理しておくことが重要です。
離婚調停を有利に進めるポイントや全体の流れは、以下の記事をご覧ください。
関連記事:離婚調停の有利な進め方!流れと具体的な方法を解説
関連記事:離婚調停は弁護士に依頼すべき?費用相場や相談タイミングを専門家が徹底解説
裁判離婚(調停で合意できなかった場合に提起)
離婚調停を申し立てたものの、話し合いで合意に至らず「不成立」になった場合、最終的な手段として家庭裁判所に裁判離婚を提起します。(参照:裁判所|離婚)
裁判では、裁判官が法的な視点から離婚を認めるかどうかを判断します。
裁判で離婚が認められるには、民法第770条1項で定められた法定離婚事由のいずれかに該当し、それが客観的な証拠による立証が必要です。
裁判離婚は調停よりも時間と費用がかかりますが、法定離婚事由が認められれば、裁判所の判決によって強制的に離婚が成立します。
訴訟の流れや必要な書類、主張の立て方については、離婚問題に詳しい弁護士と連携しながら進めましょう。
- 書面作成や証拠提出を一任できる
- 法廷での主張を代理で行える
- 裁判手続きに伴う精神的負担を大きく減らせる



弁護士が代理人として対応すれば、書面作成や証拠提出、法廷での主張まで一任できるため、精神的負担を大きく減らせます。
裁判離婚の流れやかかる時間・費用は、以下の記事を参考にしてみてください。
離婚してくれない配偶者に疲れたときにやってはいけないNG行動
離婚してくれない配偶者に疲れた場合、以下の行動は避けるようにしましょう。
感情のままに動くと離婚がさらに難しくなったり、自分にとって不利な結果を招いたりする恐れがあります。
離婚の話し合いを少しでもスムーズに進められるよう、配偶者や家族、子どもなどにやってはいけないNG行動を確認しましょう。
感情のままに相手を責める
離婚を拒む相手に対して、怒りや不満をぶつけてしまうのは避けましょう。感情のままに責め立てると、相手の反発を強め、話し合いがますます難しくなります。
たとえば「こうなったのはすべてあなたのせい」などの否定的な言葉は、相手の防御反応を刺激し、以下のような悪影響を及ぼす可能性があります。
- 相手の離婚への拒否感をさらに強める
- 一時的に気持ちがすっきりしても、さらなる関係の悪化につながる
- 冷静な協議ができなくなる
離婚したい事実を受け入れてもらうには、感情的な言葉ではなく「今この状況をどう解決したいのか」を冷静に伝えるのがポイントです。
相手を責めたくなっても、まずは冷静になって現状をどう打開するかを検討しましょう。
子どもや無関係の友人を味方につけようとする
離婚してくれない状況をなんとかするために、子どもや友人を巻き込むのはやめましょう。味方を増やそうとする行為は、一時的な安心感を得られても、問題の本質的な解決にはつながりません。
特に、以下のようなNG行動は状況を悪化させる可能性があります。
- 子どもに離婚すべきかどうかを判断させる
- どちらの親に着いていくかを子どもに迫る
- 友人を介して配偶者の悪口を広める
子どもを巻き込む行為は、子どもに精神的な負担を与え、心に深い傷を残す可能性があります。また、友人を介して悪口を広めると、冷静に話し合うどころかトラブルを拡大させてしまう恐れがあります。
離婚は夫婦間の問題のため、子どもや無関係の友人を巻き込まず、弁護士や裁判所を通じて解決の道を探りましょう。
離婚届を無断で提出する
離婚届を配偶者に無断で提出するのもNG行動の一つです。
配偶者の署名や押印を偽造して離婚届を提出する行為は、法的なリスクが非常に高く、以下のような責任を問われる可能性があります。
| 法的リスク | 詳細 |
|---|---|
| 刑事責任 | 以下に該当する恐れがある。 ・有印私文書偽造罪 ・行使罪(刑法第159条) ・電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項) |
| 民事責任 | 不法行為として慰謝料請求の対象となる可能性がある。 |
| 手続上の無効 | 偽造された離婚届は無効となり、法律上の離婚は成立しない。 |
以上のように、刑事・民事上の責任を問われるだけでなく、離婚自体が成立しません。
不正な手段は後に取り返しのつかない結果を招くため、一方的な提出ではなく、正式な順序で離婚手続きを進めることが何よりも重要です。
DV・モラハラで配偶者を追い詰める
離婚を拒む相手に対して、暴力やモラハラで言うことを聞かせようとする行為はしてはいけません。
DVは身体的な暴力だけでなく、暴言や脅迫、人格否定、経済的支配なども含まれます。モラハラも同様に相手の尊厳を傷付け、精神的に追い詰める行為です。
こうした暴力や精神的な支配を行うと、以下のようなリスクが生じます。
- 刑事事件として立件される可能性がある
- 逆に相手から慰謝料や保護命令を求められる
- 加害行為として記録に残り、離婚時に不利な結果を招く
どんなに感情が高ぶっても、暴力やハラスメントに頼らず、弁護士に相談して法的な手段で解決を目指しましょう。
仕返しのつもりで不倫に走る(不貞行為)
離婚を拒む相手に仕返しをしようと不倫に走るのは避けましょう。
不倫は一時的な感情のはけ口になったとしても、法的には「不貞行為」と見なされ、ご自身の立場を著しく不利にする可能性があります。
具体的には、以下のようなリスクが考えられます。
- 離婚の意思を主張するどころか、反対に離婚の責任を問われる立場になる
- 有責配偶者に該当して、離婚請求が認められない可能性がある
- 配偶者から慰謝料を請求される
離婚を有利に進めるためには、感情的な行動ではなく、法的根拠に基づいた冷静な対応が重要です。



精神的に辛い状況でも、ご自分の立場を不利にしないよう、まずは弁護士に相談して今後の対応方法を検討しましょう。
不倫の慰謝料の基礎知識や相場は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:不倫で慰謝料はいくらもらえる?相場や請求しないほうがいいケースも解説【弁護士監修】
配偶者が離婚してくれない場合に弁護士に相談するタイミング・準備すべきこと
離婚の話し合いが長引いて精神的に疲れている場合は、弁護士に早めに相談するのが得策です。
とくにDV・モラハラ・経済的な支配などがある場合は、証拠収集や安全の確保を弁護士にサポートしてもらいましょう。
弁護士に相談する際は、以下の3点を事前に用意しておくと証拠確認がスムーズに進めやすくなります。
- 離婚の経緯を時系列で整理したメモ
- 財産・収入・支出に関する資料(通帳や給与明細など)
- 相手とのやり取りが分かる証拠類(LINEやメールのスクリーンショットなど)



これらを準備しておくことで、初回相談で弁護士が状況を把握でき、より具体的なアドバイスを受けやすくなるでしょう。
離婚してくれない配偶者に疲れたときによくある質問
別居してるのに離婚してくれない場合はどうしたら良いですか?
別居していても相手の合意がなければ協議離婚は成立しません。
ただし、別居期間が長期にわたり(目安5~10年)、夫婦の実態が失われている場合は民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」として法定離婚事由に該当し、裁判で離婚が認められる可能性があります。
また、DV等が原因であれば、より短期間でも認められる場合があります。
長期間の別居で離婚する場合は、弁護士に相談し、調停や裁判離婚への移行を検討しましょう。
相手が離婚を拒否し続けるとどうなりますか?
配偶者が離婚を拒否しても「一生離婚できない」訳ではありません。
以下のような、民法が定める法定離婚事由の一定条件を満たせば、裁判官の判決によって離婚が強制的に認められます。
- 暴力
- 不倫
- 長期の別居 など
ただし、調停や裁判は精神的負担が大きいため、早期解決を目指すなら弁護士に相談し、法的な手段を検討するのが賢明です。
まとめ|離婚してくれない配偶者に疲れたら早めに弁護士に相談しよう
離婚を拒む配偶者と向き合い続けるのは、心身に大きな負担がかかります。感情的にぶつかるよりも、相手の心理や立場を理解しながら、冷静に手続きを進めることが解決への近道です。
話し合いが進まないときは、弁護士を交えて客観的に整理し、別居や調停、裁判など法的な手段を検討しましょう。



一人で抱え込まず、信頼できる専門家のサポートを受けることで、現実的な選択肢を見つけやすくなります。
離婚問題に強い弁護士法人アクロピースでは、これまでに1,000件以上の相談実績があり、協議・調停・裁判などあらゆる段階であなたをサポートいたします。
離婚を拒む相手への対応に疲れた方は、弁護士法人アクロピースの初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応