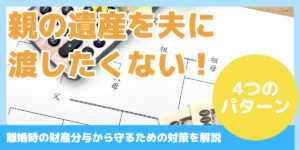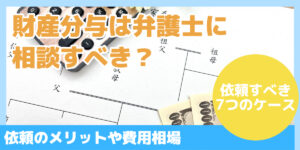離婚時の財産分与はどうなる?家や貯金の分け方・手続きの流れを弁護士が解説

「離婚するときの財産ってどうやって分けるの?」「家や預金はどうなるの?」と悩んでいませんか。
離婚時の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分け合う制度です。預貯金や不動産だけでなく、退職金や保険まで対象になる場合があります。
しかし、分け方にはルールがあり、協議で決まらない場合は調停や審判に進むケースもあります。税金や登記、名義変更など事務手続きにも注意が必要です。
本記事では、離婚における財産分与の対象や割合、手続きの流れ、よくあるトラブルへの対処法を解説します。
離婚時にどの財産がどう分けられるのか、不利にならないために何を準備すべきか参考にしてください。
離婚時の財産分与でお悩みの方は、離婚問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は、相談実績1000件以上の高い専門性を持っております。
一人で悩まず、まずは初回60分無料の電話相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚における財産分与とは?対象範囲と基本ルール
離婚に伴い、婚姻中に形成した財産を公平に分ける手続きが「財産分与」です。対象となる財産や基本ルールを正しく理解していないと、不公平な取り分になったり、請求できる権利を見落としたりする可能性があります。
以下では、財産分与の目的や範囲を詳しく解説します。対象となるもの、そうでないものを理解し、手続きをスムーズに進めましょう。
財産分与の意味・目的
財産分与とは、離婚時に夫婦が築いた共有財産を公平に分け合う制度です。
民法第七百六十八条
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
財産分与の主な目的は、婚姻中に築いた財産を公平に清算することです。
専業主婦やパート勤務の配偶者でも、家事・育児を通じて家庭に貢献していれば、収入を得ていた配偶者と同じく財産を分ける権利があります。収入の差があっても「夫婦の協力によって築いた財産」が対象だと判断されるため、2分の1ずつの分与が基本です。
ただし状況によっては、離婚後の経済的不安を軽減する生活保障や、離婚原因を作ったことへの損害賠償的な意味合い、貢献度が考慮されるケースもあります。
また、財産分与は、離婚日の翌日から起算して2年以内に請求が必要です。(民法768条2項ただし書き)。
離婚を検討している場合は、早めに財産の洗い出しと分与方法の確認を進めましょう。(参照:法務省|財産分与)
離婚時に財産分与の対象になるもの
財産分与の対象になるのは、結婚生活を通じて夫婦が共同で形成した財産です。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 車
- 有価証券・株
- 退職金
- 生命保険の解約返戻金
たとえば、預金通帳の名義がどちらか一方であっても、その口座に婚姻中に入金された共通収入があった場合、共有財産とみなされます。また、配偶者が将来受け取る退職金も、支給が確実な場合は分与できる可能性があります。
財産の性質や名義にとらわれず、実質的に夫婦で築いた財産かどうかが判断基準です。
分与対象を適切に把握するためにも、収入源・時期・購入経緯を明確にした上で、弁護士などの専門家に相談しましょう。
離婚時の財産分与の対象にならないもの
財産分与の対象外となるものの例は、以下の通りです。
- 婚姻前に貯めていた財産
- 親から贈与・相続した不動産
- 個人的に背負っている借金(ギャンブルなど)
これらの財産は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産ではないため、分与対象には含まれません。また、共有財産であっても「分与を行わない」と夫婦間で決めたものは対象外です。
分与対象にならない財産を明確に区別するには、購入日・取得経緯・名義人などの情報を整理し、通帳や契約書などの資料を用意しておくとよいでしょう。
関連記事:財産分与の対象にならないものとは?相続遺産や親からの贈与を守る方法【弁護士監修】
離婚時に何が分与対象になるのか判断に迷う際は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
法的知識が豊富な弁護士が、あなたの状況に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。
まずは、初回60分無料の電話相談をご活用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
名義が片方でも離婚時の財産分与の対象になるケース
財産の名義が夫または妻どちらか一方になっていても、その財産が夫婦共同で築かれたものであれば財産分与の対象です。
たとえば、夫名義で購入した住宅でも、それが婚姻中の収入で購入されていた場合には妻にもその財産の一部を請求する権利があります。
これは、共働きで収入を支え合っていた夫婦に限らず、妻が専業主婦として家事・育児で生活を支えていたケースでも同様です。
名義人でないからといって請求をあきらめず、婚姻中の収入状況や支出内容などの記録から分与の根拠を示しましょう。
関連記事:熟年離婚の財産分与はどうすべき?具体的な進め方や起こりやすいトラブルを解説【弁護士監修】
離婚における財産分与の種類
離婚における財産分与の種類は、以下の3つに分かれます。
離婚に至った経緯や双方の生活状況などによって、選ぶ分与方法は異なります。以下でそれぞれの特徴と判断基準を確認し、適切な請求を行いましょう。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分け合う制度です。
最も基本的かつ中心的な分与方法で、離婚時の多くは精算的財産分与が選ばれます。
具体的には、婚姻期間中に築いた財産を名義・貢献度にかかわらず共有財産と見なし、原則として2分の1ずつ分ける方法です。
たとえば、1,000万円の価値がある不動産を所有していた場合、500万円ずつ公平に分け合います。
妻が専業主婦で収入がない場合でも、家事・育児・扶助といった収入以外の貢献度を評価し、基本的には2分の1ずつ公平に分配します。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚に至る原因をつくった配偶者に対し、精神的・経済的損害の補填という側面を加味して行う分与です。
相手の不法行為(浮気・暴力・モラハラなど)が原因で離婚せざるを得なくなった場合、財産分与の額に慰謝料相当分を上乗せするよう求めることがあります。
財産分与と慰謝料請求は、法律上は別々の制度です。しかし手続き簡略化や金銭的な問題から、慰謝料を含んだかたちで財産分与額を調整する合意がなされることがあります。
慰謝料相当分を含めて分与しますので、その前提となる不法行為があったことの証拠や客観的な裏付けが必要です。
浮気による離婚で慰謝料請求を行う場合、不倫相手とのやりとりを示す証拠が不十分であれば、裁判で認められない可能性があります。
精神的損害への補償も含めた解決を望むなら、弁護士と連携して請求方法や方針を慎重に検討しましょう。
慰謝料請求については、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚後に生活が困難になる配偶者に対し、一定の生活支援を目的として行われる分与です。
主に、以下のような理由で経済的に自立が難しい場合に適用されます。
- 高齢
- 病気
- 無職 など
たとえば、長年専業主婦だった配偶者が定職に就けず経済的な負担が大きい場合、扶養的財産分与として一定額を継続的に受け取れる可能性があります。
ただし、あくまで扶養に準じた支援であり、永続的な援助ではありません。
扶養的財産分与を請求したい場合は、生活状況をできるだけ具体的に説明し、早めに弁護士などに相談して方針を立てましょう。
ご自分がどの分与方法に該当するのか判断しにくい場合は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
最大限有利な離婚な離婚を目指し、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。
まずは初回60分無料相談でお気軽にご相談ください!
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚における財産分与の割合
離婚における財産分与の割合は、婚姻期間の長さや貢献度などによって変更される場合があります。
以下で、基準となる割合と変動するケースの具体例を詳しく解説します。基本的なルールや例外を抑え、分与の割合をめぐったトラブルをできるだけ回避しましょう。
基本は「2分の1」が原則
財産分与は原則として、夫婦それぞれに2分の1ずつもらう権利があるとされています。
たとえ片方が家計を支え、もう片方が収入を得ていなくても、婚姻中の財産は夫婦が協力して築いた共有財産とみなされるためです。
前述のとおり、夫が外で働いて妻が専業主婦として家庭を支えていた場合でも、夫婦で築いた財産は平等に評価されます。家事・育児は収入が発生しませんが、これらは労働と同等の経済的価値があるとされています。
そのため、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつになるのが一般的です。(参照:法務省|財産分与)
関連記事:財産分与の割合はどのくらい?例外ケースや注意点を弁護士が解説
財産分与の割合が変わるケース
原則の割合は2分の1ですが、特別な事情がある場合は割合が調整されるケースがあります。
- 結婚期間がごく短く財産形成に片方しか関与していなかった場合:裁判所側で貢献度を考慮した割合に変更される
- 片方の配偶者がギャンブルや浪費などによって共有財産を減らした場合:その責任を反映して分与額が減らされる可能性がある など
また、共働きで財産形成に貢献した場合であっても、どちらか片方の貢献度が極めて高ければ、分与の割合変更が認められる可能性があります。
例えば、一方の配偶者が特別な資格を利用して、共有財産の大半が形成された場合のような時は、変更が認められる可能性があります。
基本的に2分の1ずつ分与しますが、こうしたケースでは割合が変更される場合もあると覚えておきましょう。
離婚時の財産分与のやり方
離婚時に共有財産をどのように分けるかは、対象となる財産の種類ごとに扱い方が異なります。
ここでは、以下の項目別に財産分与のやり方を解説します。
どの財産がどのように分与されるのか理解し、共有財産を公平に分配しましょう。
家(不動産)
不動産の分与方法は、以下の2パターンに分かれます。
- 不動産を売却して現金化し、その利益(売却額)を2分の1ずつ分け合う
- 一方がそのまま住み続け、もう一方に代償金(公平な分け前として支払うお金)を支払う
たとえば戸建て住宅を売却して分配する場合、利益(売却額)が3,000万円であれば、それぞれ1,500万円ずつ分配します。売却の場合、不動産会社と連携して買主を見つけるか、不動産買取業者に買い取ってもらわなければなりません。
一方が住み続ける場合には、住まない側へその不動産の時価評価を基に計算した代償金を支払うことで清算します。不動産会社に査定を依頼し、その住宅の価値を明確にする必要があります。
ただし、頭金を一方配偶者の婚姻前の預貯金から支払っているような場合には、単純に2分の1とならないこともありますので、専門家に相談するのが良いです。
ローンあり・オーバーローンの場合の注意点
住宅ローンが不動産の価値を下回っている(アンダーローン)場合、離婚時の取り扱いとしては主に次の2つの方法があります。
- 不動産を売却し、売却代金でローン全額を返済して、残額を夫婦で分け合う
- 不動産を売却せず、不動産の評価額からローン残高を差し引いた金額を夫婦で分け、ローンの残額は住み続ける側が単独で引き継いで返済する
不動産価値がローン残高より高い(オーバーローン)場合は、資産価値が実質的にマイナスとなるため、原則として財産分与の対象にはなりません。
ただし、住宅に住み続けるかどうか、ローンをどちらが引き継ぐかは大きな判断ポイントです。ローンが残っている住宅の名義変更には、金融機関の同意が必要な場合もあるため慎重に対応しましょう。
また、住宅ローンが残っている不動産の分与には法的な知識が必要です。必要に応じて、弁護士に相談しながらどう分与すべきか判断しましょう。
現金・預貯金
婚姻期間中に夫婦共同で貯めた預貯金は、名義に関係なく共有財産とみなされ、2分の1ずつに分けるのが原則です。
専業主婦(夫)であっても、家庭に貢献していれば分与の対象になります。以下のような現金、預貯金も2分の1つ分配します。
- へそくり
- タンス貯金
- 手元の現金
なお、口座が複数ある場合は、全ての口座の残高を合算して半分に分けるのが基本です。
分配の基準となるのは、通常「離婚時」または「別居時」の残高ですが、話し合いの内容や事情によっては、異なる時点が採用される場合もあります。
株式
株式は、離婚時の株価で評価され、その価値を2分の1ずつ分けるのが原則です。
たとえば、別居時の株価が20万円、離婚時が30万円だとした場合、離婚時の30万円で分与を行います。
ただし、株式は現金と異なり、価値が変動しやすく分割そのものが難しい傾向があります。とくに非上場株など換金が困難なものは評価が複雑になるため、税理士や専門家の助言が必要です。
退職金
退職金は、婚姻期間中に形成された部分のみが財産分与の対象になります。支給額の全体ではなく、婚姻期間に対応する割合だけを共有財産として評価するのが原則です。
たとえば、勤務年数が20年でうち10年間が婚姻期間だった場合、分与対象は10年分に相当する額になります。婚姻前や別居後の勤務分は対象外になるため、正確な期間の把握が重要です。
また、退職金がまだ支給されていなくても、支給の確実性が高い場合は期待財産として分与できる可能性があります。
財産分与における退職金の扱いは、以下の記事をご参考ください。
自動車
自動車も婚姻期間中に購入したものであれば、分与の対象です。
車両の価値は査定額を基に算出され、以下のいずれかで清算します。
- 売却によって現金化して分ける
- 一方が所有してもう一方に代償金を支払う
たとえば、売却の査定額が150万円であれば75万円ずつ分けるのが基本です。
ローンが残っている場合は、その残債を控除した上での評価になります。ローン契約者が誰かによって、負担の割合も検討する必要があります。車検証・ローン明細・査定書などの資料をそろえておき、話し合いを円滑に進めましょう。
車の財産分与については、以下の記事でも解説しています。併せて参考にしてみてください。
関連記事:親に買ってもらった車は財産分与になる?離婚時の財産分与の相場とその対象
保険
生命保険や学資保険なども、解約返戻金が発生する契約であれば、その金額相当が財産的価値を持つため分与の対象となります。
具体的には、婚姻期間中に支払った保険料で積み立てられた部分が、共有財産に該当します。
分け方としては、以下の2つの方法があります。
- 保険を解約して返戻金を分ける
- 契約を一方が引き継いで他方に解約返戻金額に相当する財産を贈与する
なお、掛け捨て型の保険や死亡保険金が対象のものなど、解約返戻金がない契約は分与対象外です。
対象になるかどうか判断するには、保険証券や契約書の確認が欠かせません。不明点がある場合は、保険会社やFPに相談して評価額を明確にしておくと良いでしょう。
離婚で財産分与したら税金はかかる?
離婚で財産分与を行う際に「税金はかからないのだろうか」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
結論としては、財産分与で税金がかかるケースも存在します。以下で、税金がかかるケースと確定申告の要否について解説します。
税金の知識は手続きを円滑に進めるために必要になるため、事前に確認しておきましょう。
財産分与で税金がかかるケース
結論からいえば、財産分与に税金がかかるのは例外的なケースです。
多くの場合は課税されませんが、以下の2つの条件に該当すると贈与税がかかる可能性があります。
- 分与された財産が明らかに多すぎる場合
- 離婚が税金逃れを目的とした形式的なものであると認められた場合
たとえば、高額な財産をを一方的に譲り受けたようなケースでは、その「多すぎる部分」が贈与税の課税対象となります。
これは国税庁の公式見解に基づくもので、財産分与の目的ある清算や生活保障を超えた利益と判断されるためです。
このケースで受け取った財産が不動産の場合、以下の税金が課されます。
| 課税対象となるケース | 税金の種類 |
|---|---|
| 不動産を財産分与で受け取った場合 | 不動産取得税・登録免許税 (参照:国税庁|No.7190 登録免許税のあらまし/総務省|不動産取得税) |
| 不動産を財産分与で片方に渡した場合 | 譲渡所得 (参照:国税庁|No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき) |
また、税金逃れを目的とした離婚の場合は、受け取った財産全てが課税対象となるため注意しましょう。
ただし、一定の条件を満たす場合には、特別控除が適用されることがあります。特別控除の適用を受けるには申告が必要なため、国税庁や自治体のホームページで事前に確認しましょう。
財産分与したら確定申告は必要?
離婚による財産分与を行った場合、確定申告は不要です。財産分与では一般的に税金は発生しないため、確定申告を行う必要はありません。
ただし、例外的に贈与税が課税される場合や、不動産の贈与などで課税対象になった場合は、確定申告が必要になるケースがあります。課税対象になるかどうか判断しにくいときは、税務署または税理士に相談してみましょう。
離婚における財産分与の手続きの流れ5ステップ
離婚における財産分与の手続きの流れは、以下の5ステップです。
トラブルなく分与を行うためにも、ステップごとでやるべきことを理解しましょう。
財産分与は、まず対象となる財産の洗い出しから始めましょう。
具体的には、財産目録(全ての財産を一覧にまとめた書類)を作成し、夫婦で築いた共有財産の種類と金額を明確にします。
スムーズに手続きを進めるには、預貯金通帳や不動産の登記簿、保険証券、株式の明細など裏付けとなる資料をそろえておくことが重要です。
特に不動産や保険・退職金の評価には根拠資料が求められるため、できるだけ客観的なものを用意しましょう。
財産の洗い出しと資料の収集の正確度は、財産分与の成否を左右します。早い段階から計画的に進めましょう。
ステップ2では、相手との協議で合意を目指します。
財産分与は、まずは夫婦で話し合って手続きを進めるのが原則です。協議が成立すれば、家庭裁判所を通さずに手続きを進められるため、費用や時間の面でも大きなメリットがあります。
合意内容は必ず書面で残し、財産分与協議書として保管しておきましょう。
万が一支払いが滞った場合に備え、裁判を経ずに強制執行できるように、要件を満たした公正証書で作成しましょう。
書類の作成には公的知識が必要なため、自分で作成するのが難しい場合は弁護士に依頼しましょう。
協議での合意は比較的円満かつ迅速に解決できる方法であるため、できる限りこの段階での解決を目指すのが望ましいです。
協議離婚の進め方は、以下の記事で解説しています。スムーズな手続きのためにも、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:協議離婚の進め方―流れや手続について―
協議での解決が難しい場合は、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てます。
調停では、第三者である調停委員が間に入り、両者の意見を聞きながら中立的な立場で調整を図ってくれます。柔軟な合意形成が期待できる点がメリットです。(参照:裁判所|財産分与請求調停)
相手との直接交渉が困難な場合でも、調停であれば第三者が間に入った話し合いの場が確保されるため、感情的な衝突を避けたい人にも適しています。
早期解決を目指すなら、無理に協議を続けるより調停を活用するのも選択肢の一つです。
なお、申し立てには財産目録や離婚時の夫婦の戸籍謄本、証拠書類などが必要となるため、事前準備をしっかり行いましょう。
調停の段階で弁護士に相談することをおすすめします。
調停でも合意に至らなかった場合は、裁判所による審判へ自動的に移行します。審判では、裁判官が当事者の主張や提出資料を基に判断し、財産分与の内容を決定します。
調停と異なり、話し合いではなく裁判所の判断に従うことになるため、希望通りの結果にならない可能性もあります。
また財産分与だけが争点であれば、家庭裁判所の審判で対応可能です。しかし、不貞行為に基づく慰謝料など損害賠償が主たる争点となる場合は、民事訴訟に発展し、地方裁判所で扱われるケースもあります。
審判や訴訟は、調停と比べて手続きが複雑で解決までに時間も費用もかかりやすいのが実情です。法的な主張や証拠の整理も求められるため、信頼できる弁護士に相談して念入りに準備を進めましょう。
離婚裁判の流れを知りたい方は、以下の記事をご参考ください。
財産分与が決まったら、財産分与が決まったら、実際に財産の名義を変更する手続きを行います。
不動産であれば所有権移転登記、預金は名義変更や口座移管、自動車は陸運局での名義変更などが必要です。
分与を受けた不動産については、不動産取得税や登録免許税が発生するため、登記と併せて納税の手続きも行う必要があります。(参照:国税庁|No.7190 登録免許税のあらまし/総務省|不動産取得税)
不動産の名義変更や登記手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。不備なく確実に手続きを進め、後のトラブルを防ぐためにも、登記は早めに司法書士へ相談・依頼しましょう。
離婚調停・裁判には、信頼できる弁護士との連携が欠かせません。
「どの弁護士に相談すれば良いかわからない」「何から始めるべき?」とお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は、相談実績1000件以上の高い専門性があり、豊富な経験と知識に基づいて最適な解決方法をご提案いたします。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚時の財産分与の協議が進まないときの対処法
離婚時の財産分与では、当事者間の話し合いだけでは解決が難航する場合があります。相手が非協力的だったり、条件で折り合わなかったりする場合には、無理に協議を続けず次のステップを検討しましょう。
ここでは、協議が進まないときに取るべき具体的な対処法を2つご紹介します。適切な対応策を理解し、冷静に次の一手を選びましょう。
調停を申し立てる
話し合いが進まない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるのが現実的な選択肢です。
前述のとおり、調停では中立の第三者(調停委員)が間に入り、冷静かつ公平な話し合いを進めてくれます。
離婚前と離婚後で、調停は以下の2種類に分かれます。
| 申し立てるタイミング | 内容 |
|---|---|
| 離婚前 | ・夫婦関係調整調停(離婚調停)で財産分与について話し合うことが可能 ・財産分与だけでなく、子どもの親権や養育費の支払い、慰謝料などに関する話し合いにも対応(参照:裁判所|夫婦関係調整調停(離婚)) |
| 離婚後 | ・財産分与請求調停として個別に申し立てることが可能 ・裁判よりも手続きが簡単で費用も抑えられるため、争いを避けたい方や感情的な対立を整理したい方に適している (参照:裁判所|財産分与請求調停) |
協議に限界を感じたら、無理をせず調停への切り替えを検討しましょう。
離婚調停の進め方や流れは、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
弁護士に相談する
弁護士は財産分与に関する法律や判例に精通しており、自分にとって不利な条件を避けるための交渉や書類作成を代行してくれます。
また、弁護士が代理人として関わることで相手も法的な立場を意識するようになり、話し合いが進みやすくなる場合があります。
特に以下のようなケースでは、弁護士にどうすべきか相談しましょう。
- 相手が財産を隠している
- 非現実的な要求をしてくる
- そもそも話し合いに応じない など
調停や審判に発展した際にも、弁護士は心強い味方になってくれるでしょう。
費用はかかりますが、不公平な分与や将来的なトラブルを防ぐための自己防衛と考えるべきです。一人で抱え込まず、早めに弁護士の力を借りましょう。
関連記事:【弁護士監修】財産分与は弁護士に相談すべき?依頼のメリットや費用相場を解説
離婚調停・裁判の実施をご検討の方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
プライバシー厳守の完全個室で丁寧にヒアリングし、離婚問題の解決までの道のりを全力でサポートいたします。
小さなお子様連れでの法律相談も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚時の財産分与前にやっておくべき準備・注意点
財産分与は、感情的な対立だけでなく、手続き上の不備でもトラブルに発展しやすい問題です。
分与の話し合いを行う前に、以下の準備を段階的に進めておくと手続きが円滑に進みやすくなります。
後から「言った・言わない」で揉めないように、準備と記録を確実に行いましょう。
財産目録・通帳・証拠書類を整理する
財産を正確に把握するためにも、財産目録や通帳、証拠書類を整理しておきましょう。
公平な財産分与を実現するには、夫婦で築いた財産の全体像を明確にすることが第一歩です。
そのためには、財産目録を作成し、預貯金の通帳や不動産の登記簿、株式の取引明細などの書類を収集する必要があります。
名義が夫または妻のいずれか一方であっても、婚姻期間中に得た財産であれば、原則として共有財産に該当します。見落としがないよう、保有する口座や契約内容を一つずつ確認し、資産と負債の両方を丁寧にリスト化しましょう。
また、浮気やモラハラなどによる離婚で財産分与を行う場合、それを裏付ける証拠(写真・LINEのやりとり・診断書など)も集める必要があります。
財産の全容や離婚原因の証明ができれば、有利な条件での財産分与交渉につながります。弁護士や司法書士に相談しながら適切に準備を進めましょう。
協議書・覚書・公正証書で書面化する
財産分与に関する合意は、協議書や覚書として文書にまとめておきましょう。口約束だけでは、後から「言った・言わない」をめぐって揉めることがあります。
離婚協議書に正式なフォーマットはありませんが、できる限り内容を具体的に記載することが重要です。
たとえば「財産分与として○円を支払う」「不動産の名義をどうするか」などを記載します。
離婚協議書は自分で作成することもできますが、トラブルや不備を回避するなら弁護士に依頼することをおすすめします。
また、相手がまた、相手が財産分与で決められた金銭の支払いに応じない時に備えて、公証役場で執行認諾文言付きの公正証書を作成するのも選択肢の一つです。
このような公正証書には、「支払が履行されない場合は、直ちに強制執行を受けても異議を述べない」といった文言(執行認諾)が含まれています。
相手が約束通りに支払わなかった場合でも、裁判を経ずに強制執行を申し立てることが可能です。(参照:日本公証人連合会|公証事務)
離婚時の財産分与についてよくある質問
離婚時に貯金を隠すとどうなりますか?
意図的に貯金を隠す行為は、不正行為とみなされる可能性があります。
財産分与では、夫婦で築いた財産を正確に把握する必要があります。後から発覚すれば、財産分与のやり直しや損害賠償を求められる場合があるため注意しましょう。
通帳や取引履歴を調べれば、不審な出金や資金移動などの問題は明らかになります。不利な立場に陥らないためにも、誠実に開示する姿勢が重要です。心配な場合は、弁護士に相談して進めましょう。
財産分与をしなくていいケースはありますか?
原則として、夫婦が婚姻中に築いた財産は共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。
ただし、婚姻期間が極端に短かった場合や財産の大半が一方の特有財産だった場合は、分与の必要がないと判断されない可能性があります。
また、協議で「分与しない」と夫婦間で合意すれば、分与を省略できます。分与の対象外になるかどうかは状況によって異なるため、専門家の判断を仰ぎましょう。
離婚するとどちらが家を出ていくべきですか?
法律上、離婚したからといって必ずしもどちらか一方が出ていかなければならない規定はありません。しかし、名義や今後の生活、子どもの養育環境を踏まえて、どちらが住み続けるかを協議で決めるのが一般的です。
感情的な対立に発展しそうな場合や判断に迷う場合は、法的な観点からアドバイスをくれる弁護士に相談しましょう。
離婚時の財産分与で会社株はどう扱われますか?
会社の株式も、婚姻期間中に取得したものであれば財産分与の対象になります。たとえ名義が一方にあっても、株の取得原資が共有財産であれば、分与の対象に含まれます。
ただし、未上場企業の株などは評価が難しく、専門的な算定が必要です。税理士や弁護士と連携し、慎重に手続きを進めましょう。
タンス預金や子供の貯金は財産分与の対象になりますか?
タンス預金は、婚姻期間中に形成された共有財産であれば分与対象となります。ただし、存在や金額を証明するのが難しいため、通帳履歴や現金管理の記録が重要です。
子ども名義の貯金でも、親が管理し実質的に家計から拠出していた場合は、名義に関わらず分与対象とされるケースがあります。判断しにくい場合は、弁護士などの専門家に確認しましょう。
まとめ|離婚の財産分与は専門家のサポートを受けながら適切に進めよう
離婚における財産分与は、単なる財産の分け合いではなく、今後の生活基盤を左右する重要なステップです。公平な分配を実現するためには、財産の全体像を正確に把握し、適切な手続きを踏むことが欠かせません。
また、税金の問題やトラブルを避けるためにも、専門家のサポートを受けながら進めるのが賢明です。離婚後の生活を安定させるためにも、早めに準備し、納得できる財産分与を目指しましょう。
弁護士法人アクロピースでは、離婚問題に強い弁護士が多数在籍しております。
1000件以上の相談実績があり、離婚問題に特化した探偵との連携体制も整っております。
一般的な離婚問題から慰謝料問題、親権問題まで幅広く対応しております。
まずは初回60分無料相談でお気軽にご相談ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応