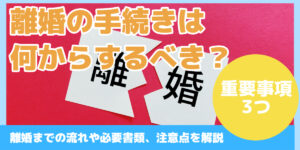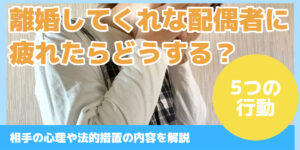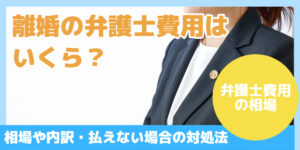熟年離婚したらどうなる?知っておきたい知識や後悔しないポイントを現役弁護士が解説

「熟年離婚を考えているけれど本当にすべき?」「離婚したいけれど老後の生活が不安…」と悩んでいませんか。
熟年離婚とは、婚姻20年以上の夫婦が離婚することを指し、人生後半の再スタートとして注目されつつあります。
しかし、年金や退職金の分割、老後資金の確保、子どもや家族との関係悪化など、若い世代の離婚とは異なる問題が山積みです。感情だけで判断すると、離婚後に後悔してしまうケースも少なくありません。
本記事では、熟年離婚をする上で知っておくべき知識や手続きの流れを詳しく解説します。離婚すべきかどうか迷っている方、手続きの流れがわからず一歩踏み出せていない方は、ぜひ参考にしてみてください。
熟年離婚によるトラブルにお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
離婚問題で有利に立つには、交渉力が必要です。当事務所は、これまで1000件以上の離婚問題の相談実績があります。
経験豊富な弁護士が、あなたにとって最善の道筋をご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
熟年離婚とは?
熟年離婚とは、長年連れ添った夫婦が人生の後半になってから離婚することです。現在、婚姻期間20年以上の離婚件数は増加傾向にあります。
熟年離婚のメリットやデメリット、手続きの流れを知る前に、まずは定義や件数の推移、離婚に至る主な原因を確認しましょう。
熟年離婚の定義と件数の推移
熟年離婚とは、長期間婚姻関係にあった夫婦や高齢になってから離婚することを指す、一般的な用語です。
50歳前後、あるいは婚姻期間20年以上の夫婦が離婚することを意味する言葉として使われるケースが多くあります。
婚姻20年以上の離婚件数は、近年増加傾向にあるのが実情です。
国土交通省の調査によると、1995年の熟年離婚件数は年間6,000件未満だったものの、2001年以降は1万件以上にまで達しています。(参照:国土交通省|1-4. 増加する一人暮らしの高齢者)
また、65歳以上女性の高齢単身世帯の数は、2000年には229万人だったものの、2025年には456万人にまで増加しています。(参照:国土交通省|③高齢単身世帯の推移)
離婚件数の増加だけが原因ではありませんが、高齢期の単身生活が一般化しつつあり、離婚が例外的な出来事ではなくなっているのです。
熟年離婚に多い原因
離婚に至る主な原因は、以下のようなものがあります。
- モラルハラスメント(モラハラ)で精神的な負担が大きい
- 夫婦間の会話がゼロに近い
- 定年退職後に夫婦関係が悪化した
たとえば、現役時代は夫が仕事、妻が家庭といった役割を担っていた家庭では、定年後に夫が自宅にいる時間が増えます。その結果、生活リズムが崩れ、お互いの存在がストレスになる可能性があります。
また、長年積み重ねてきた不満やすれ違いが、子どもの独立や夫の定年退職によって夫婦の時間が増えることで、一気に表面化する場合もあるでしょう。
「妻が夫に従うべき」といった考え方の夫の場合、専業主婦だった妻が「これ以上我慢できない」「夫との関係を終わりにしたい」と離婚を切り出す場合もあるのです。
熟年離婚のメリットとデメリット【後悔を防ぐために】
熟年離婚は新しい人生のスタートになる一方で、老後生活の不安要素にもなり得ます。
ここでは、公的な統計調査を基に熟年離婚のメリット・デメリットを解説します。メリットとデメリットの両面を正しく理解し、後悔のない選択につなげましょう。
熟年離婚のメリット
熟年離婚のメリットは、経済的・精神的な負担を軽減できる点です。とくに介護や夫婦間のストレスが長期化していた場合、離婚によって心身の安定を取り戻す人も少なくありません。
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」では、要介護者の主な介護者は同居している家族であるケースが多数を占めているのが実情です。60歳以上の介護者の割合は、男性で75%、女性で76.5%とされ、老老介護の深刻さが伺えます。
介護で精神的な負担がかかっているのであれば、離婚によってその重圧から解放されるメリットがあります。
また、離婚で家事や時間の配分を自分のペースで管理できるようになったり、好きなことに時間を使えたりする点もメリットです。長年家庭内の役割に縛られていた人にとっては、離婚を機にセルフケアの機会が広がり、日々の暮らしに前向きな変化をもたらす場合があります。
精神的に自立したいと考えている場合は、一人の時間を確保することが心の安定につながるかもしれません。まずは、自分の生活リズムや希望を整理し、離婚後の生活を具体的にシミュレーションしてみましょう。
熟年離婚のデメリット
熟年離婚には、経済的・社会的な不安が伴います。とくに収入の確保が難しい場合や老後資金が限られている場合、熟年離婚は経済的不安を大きくする要因の一つです。
内閣府の「令和7年版 高齢社会白書」では、高齢者の単身世帯の生活不安が顕著に示されています。一人暮らしをしている高齢者のうち「家計が苦しく非常に不安」「家計にゆとりがなく多少心配」と回答した割合は、複数人世帯よりも高い傾向があります。
このようなデータからも、熟年離婚後は生活基盤が不安定になりやすく、老後の貧困リスクが高まるといえるでしょう。
また、離婚後に地域とのつながりを断たれることで、孤独感の増加や健康状態の悪化につながるケースも少なくありません。
熟年離婚の準備で押さえるべき3つのポイント
熟年離婚の準備で押さえるべきポイントは、以下の3つです。
一時的な感情だけで離婚を決断せず、これらのポイントを理解した上で判断しましょう。
離婚を切り出すタイミングを見極める
離婚を切り出す適切なタイミングは、定年退職後や子どもの独立後です。定年後であれば、退職金や年金などの見通しが立ちやすく、財産分与や年金分割の準備を進めやすくなります。
また、子どもが独立していれば、親権や扶養などの複雑な問題も回避しやすくなります。子どもの独立前に離婚する場合、収入の柱がなくなって金銭的に苦しくなるリスクもあるでしょう。
熟年離婚では、離婚の意思があっても「いつ切り出すか」が大きなポイントになります。タイミングが適切でないと、金銭面や心理面での負担が大きくなる可能性があります。不利益を被らないよう、慎重にタイミングを見極めましょう。
熟年離婚後の生活費や貯金額を確認しておく
離婚後に必要な生活費や貯蓄額を明確にしましょう。生活の見通しが立たないまま離婚してしまうと、老後の暮らしが不安定になる可能性が高まるためです。
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の高齢者の1カ月あたりの収入は、30万円~40万円未満が15%と最も多いです。一方、一人暮らし世帯では10万円~15万円が最も多く、全体の20.8%を占めています。
また、1カ月あたりの生活費では30万円~40万円未満が15.0%、20万円~25万円未満が14.9%です。複数人世帯では、30万円以上と回答している人が多い傾向ですが、単身世帯は10万円~15万円未満が最も多くなっています。(参照:内閣府|令和7年版高齢社会白書(経済生活全般の状況について))
さらに、65歳以上の二人以上の世帯では、貯蓄の中央値が1,604万円と全世帯の約1.4倍に達しており、貯蓄の有無が老後の暮らしに大きく影響します。(参照:内閣府|令和7年版高齢社会白書(1 就業・所得))
世帯の貯蓄が多くても、離婚後に自分の手元に残るとは限らないため、生活費に見合う資金を事前に確認することが大切です。
統計調査での結果はあくまで目安ですが、離婚を決める前に月々の生活費と収入、貯蓄額のバランスをシミュレーションしましょう。
必要書類や段取りをあらかじめ整理する
熟年離婚をスムーズに進めるには、必要な書類や手続きの流れを事前に整理することが大切です。財産分与や年金分割を適切に進めるには、正確な資料と準備が求められます。
協議離婚で必要な書類には、離婚協議書・戸籍謄本・住民票・年金分割請求書などがあります。年金分割を行う際は、年金分割のための情報提供請求書や標準報酬改定請求書などの書類を用意しなければなりません。(参照:日本年金機構|離婚時の年金分割)
話し合いで財産の分配方法が決まらないときは、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立て、裁判所の仲介の元で分配方法を決める場合があります。
財産分与請求調停では、財産目録や通帳のコピー、固定資産評価証明書などの財産に関する書類が必要です。(参照:裁判所|財産分与請求調停)
事前準備が不十分だと、離婚後に不利益を被る可能性があります。離婚を検討し始めた段階で必要な書類を一つずつリスト化し、専門家に相談しながら整理を進めることをおすすめします。
熟年離婚によるトラブルにお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
離婚問題で有利に立つには、交渉力が必要です。当事務所は、これまで1000件以上の離婚問題の相談実績があります。
経験豊富な弁護士が、あなたにとって最善の道筋をご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
熟年離婚における財産分与・慰謝料
熟年離婚では、長年築いてきた財産をどう分けるかが大きな争点になります。
財産分与とは、夫婦が離婚する際に婚姻中に築いた財産を公平に分け合う制度です。話し合いで分配方法が決まらない場合、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることが可能です。
(参照:裁判所|財産分与請求調停)
また、精神的苦痛への補償である慰謝料についても、条件によって認められるケースとそうでないケースがあります。
ここでは、熟年離婚における財産分与の対象や平均額、財産分与を拒否されたときの対処法を解説します。手続きをスムーズに進めるためにも、以下で基礎知識を確認しましょう。
財産分与の対象と割合
財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産が対象となります。相続によって取得した財産や結婚前に所有していた資産など、個人固有の特有財産は分与の対象外です。
共有財産には、以下のような項目が挙げられます。
- 住宅や土地などの不動産
- 預貯金
- 株式・有価証券
- 自動車
- 家具
- 保険解約返戻金
- 退職金の一部
- 負債(借金)
共有財産かどうかの判断は、以下の基準で行います。
- 基本的な財産:夫婦の協力関係が終了したとき(別居したとき)
- 株式のように価値が常に変動する財産:離婚時を基準(協議離婚の場合は合意時で、裁判離婚の場合は口頭弁論終結時)
上記で確定した共有財産を、基本的には1/2ずつ分与します。
ただし、一方のみの才能に基づいて資産を得ていたような場合(経営者・投資家など)には、その人の割合が多くなることもあります。
離婚時に財産分与の対象となる退職金については、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
関連記事:離婚時に退職金は財産分与の対象となるのか
関連記事:熟年離婚の財産分与はどうすべき?具体的な進め方や起こりやすいトラブルを解説【弁護士監修】
関連記事:財産分与の割合はどのくらい?例外ケースや注意点を弁護士が解説
財産分与の平均額
財産分与の平均額は、実務では数百万〜1,000万円以上と幅広く、金額は資産規模によって大きく左右する傾向があります。
以下は、婚姻期間20年以上の夫婦の財産分与件数と金額をまとめたものです。
| 財産分与の金額 | 婚姻期間20年以上 | 婚姻期間25年以上 |
|---|---|---|
| 総数 | 852件 | 1385件 |
| 100万円以下 | 88件 | 92件 |
| 200万円以下 | 66件 | 86件 |
| 400万円以下 | 115件 | 176件 |
| 600万円以下 | 82件 | 149件 |
| 1000万円以下 | 117件 | 228件 |
| 2000万円以下 | 109件 | 224件 |
| 2000万円以上 | 51件 | 124件 |
婚姻期間20年以上の夫婦で財産分与が行われた件数は、852件です。そのうち、財産分与額が1,000万円以上であった事例が117件となっています。
また、100万円未満の件数も88件あることから、財産の規模によって金額に差が出るとわかります。
具体的な相場は一概には言えませんが、分与額をめぐるトラブルを防ぐためにも財産整理を丁寧に進めましょう。
財産分与を拒否されたときの対処法
財産分与が話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に対して財産分与請求調停の申し立てが可能です。調停を申し立てる場合、離婚してから2年以内に行わなければなりません。(民法第768条第2項)
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
引用:民法 | e-Gov 法令検索
調停は、裁判所において中立の立場の調停委員が双方の意見を聞き取りながら合意を促す手続きです。話し合いでは感情がぶつかりやすくなりますが、調停の場では冷静かつ公平に進めることが可能です。
調停が成立しなかった場合は、審判手続きに移行します。審判では裁判所が提出された証拠を基に、分与すべき財産の範囲や金額を判断し、強制力のある決定を下します。そのため、財産目録や通帳のコピー、不動産の登記簿謄本、退職金の見積資料などを事前に準備しておく必要があります。
財産分与請求調停・審判を行う際は、信頼できる弁護士に相談して丁寧に準備を進めましょう。
熟年離婚で慰謝料請求できるケース
慰謝料は、離婚原因に相手側の法的責任がある場合に限り請求が認められます。
具体的に請求ができるケースは、以下の通りです。
- 浮気・不倫などの不貞行為
- 暴力・モラハラなどの精神的・肉体的苦痛
- 悪意の遺棄(家事育児をしないなど)・生活を渡さないなどの婚姻継続が困難な行為
たとえば、配偶者の不倫が原因で婚姻関係が破綻した場合、法律上の違法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。
熟年離婚では、長年にわたる精神的・身体的苦痛が積み重なっているケースもあり、証拠を十分に集めれば慰謝料の請求が認められる可能性があります。なお、性格の不一致や価値観の違いによる慰謝料請求は、認められないケースがほとんどです。
慰謝料請求が可能かどうかは、法的知識がないと判断しにくいため、離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。
慰謝料請求については、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:離婚の慰謝料はどんな時にもらえるの?性格の不一致でももらえるのか解説
関連記事:熟年不倫とは?発覚後に取るべき行動や慰謝料請求のポイントを解説【弁護士監修】
熟年離婚で慰謝料を請求する際は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所では、慰謝料問題で有利に立てるよう、離婚問題を専門に扱っている探偵と連携しております。
証拠集めに苦戦している方、慰謝料請求でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
熟年離婚後の「年金分割制度」とは
熟年離婚後は、年金分割制度を活用できます。年金分割制度とは、婚姻期間中の保険料納付額に応じた厚生年金を夫婦で分割し、それぞれ公平に受け取れるようにする制度です。(参照:法務所|年金分割)
専業主婦や収入の少なかった配偶者にとって、経済的負担を軽減できる制度とされています。
本章で制度の対象や申請方法、金額の目安を把握しましょう。
年金分割制度の対象夫婦・申請方法
年金分割制度の対象となるのは、厚生年金加入者と結婚していた夫婦で、婚姻期間中に年金記録がある場合です。
分割方法は、合意分割と3号分割の2種類に分けられています。
- 合意分割:婚姻期間中の全ての厚生年金の記録を、夫婦双方の合意に基づいて分割する
- 3号分割:平成20年4月1日以降の婚姻期間における第3号被保険者期間の厚生年金記録を2分の1ずつ分割する
(参照:日本年金機構|離婚時の年金分割)
3号分割を選択する場合、相手の同意は必要ありません。国民年金の第3号被保険者だった方が、期日までに分割手続きを行います。
申請方法は、離婚日の翌日から2年以内に年金事務所に必要書類を提出します。必要書類は合意分割か3号分割かによって異なるため、日本年金機構のホームぺージにてご確認ください。
年金分割で受け取れる金額の目安・計算例
年金分割で受け取れる金額は、婚姻期間中に支払われた厚生年金記録に基づいて計算されます。対象となるのは、厚生年金の報酬比例部分のみで、基礎年金部分には影響しません。(参照:日本年金機構|離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度))
たとえば、以下の共働き夫婦が合意分割で請求した場合、以下のように年金額を計算します。
- 婚姻期間:40年
- 標準報酬額:夫が5,000万円、妻が3,000万円
- 按分割合:50%
1.分割後の標準報酬月額を算出する
夫婦それぞれの標準報酬額を合算後、2分の1ずつに按分します。
- 5,000万円+3,000万円=8,000万円
- 8,000万円÷2=4,000万円
2.厚生年金額(報酬比例部分)を計算する
4,000万円×給付乗率5.769÷1,000=年額23万760円
(※給付乗数は、国で「5.769」と定められています。)
したがって、上記の夫婦の離婚後の老後厚生年金は、年額23万760円です。
上記はあくまでシミュレーションであり、分割後の年金額は、婚姻期間中の報酬額と加入実績によって異なります。
厚生年金・企業年金・遺族年金の違い
厚生年金・企業年金・遺族年金の違いは、以下の通りです。
| 種類 | 主な目的 | 対象者 | 年金分割の対象に入るか |
|---|---|---|---|
| 厚生年金 | 老後の資金生活保障 | 主に会社員・公務員 | 対象 |
| 企業年金 | 厚生年金に上乗せして支給 | 企業の制度に加入した人 | 対象外 (財産分与の対象にはなる) |
| 遺族年金 | 残された家族の生活保障 | 配偶者・子など | 対象外 |
年金分割制度では、分割できる年金とできない年金があります。基本的に対象となるのは、厚生年金の報酬比例部分です。
企業年金は年金分割の対象外ですが、離婚時の財産分与の対象となります。
遺族年金は配偶者が死亡して初めて支給される給付であり、年金分割も財産分与も対象外です。
これら年金の違いを理解することで、熟年離婚後の生活資金の見通しがより明確になります。年金の種類や取り扱いを整理した上で、必要に応じて専門家に相談しましょう。
熟年離婚の手続きと流れ
熟年離婚を円満に進めるには、段階的な手続きを理解することが大切です。
最初は夫婦間の話し合いから始まり、それでも合意に至らなければ調停、さらに裁判へと進む流れが一般的です。
トラブルをできるだけ回避するためにも、以下で熟年離婚のステップを確認しましょう。
熟年離婚は、まず夫婦の話し合いで進める協議離婚が基本です。協議離婚は、お互いに離婚の意思と条件に合意した上で役所に必要書類を提出します。
離婚届に署名・押印し、必要書類を揃えて市区町村役場へ提出することで成立します。
手続きは簡単ですが、財産分与や年金分割などを明文化しないと後でトラブルになる可能性があります。離婚協議書を作成し、必要に応じて専門家に相談しながら手続きを進めましょう。
協議離婚の流れや手続きは、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:協議離婚の進め方―流れや手続について―
協議で折り合わなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では調停委員が間に入り、中立的な立場で双方の意見を調整してくれます。
熟年離婚における財産分与や年金分割、住宅の処分など、感情的になりやすい問題を冷静な環境で進められる点がメリットです。(参照:裁判所|夫婦関係調整調停(離婚))
離婚問題の多くは、裁判まで進まずに調停で終結します。調停の進め方は、以下の記事をご参考ください。
関連記事:離婚調停の有利な進め方!流れと具体的な方法を解説
関連記事:離婚調停は弁護士に依頼すべき?費用相場や相談タイミングを専門家が徹底解説
調停をしても円満離婚に至らなかった場合、離婚裁判へと進みます。離婚裁判では、法的な根拠に基づいて、裁判官が離婚の可否や条件を判断します。
裁判離婚には「不貞行為」「悪意の遺棄」「暴力」など、民法上に定められた離婚原因が必要です。熟年離婚では、長年の不満や精神的苦痛を訴えるケースも多く、証拠(診断書、録音、メール記録など)の提出が重要になります。
解決までに時間と費用がかかる点はデメリットですが、最終的な解決手段として検討すると良いでしょう。
訴訟を起こす際は、法的知識や離婚問題の実績が豊富にある弁護士に相談することが大切です。(参照:裁判所|離婚)
離婚裁判の流れは、以下の記事でも解説しています。こちらも併せてご参考ください。
熟年離婚以外に検討すべき選択肢
熟年離婚には、老後資金の減少や孤独・健康状態に対する不安といった現実的なリスクが伴います。
そのため、離婚ではなく「配偶者と物理的な距離を取る方法」を検討するのも良いでしょう。
具体的には以下の2つの選択肢があります。
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 家庭内別居 | 同じ家に住みながら生活空間や時間を分けて暮らす方法 | ・老後の生活にかかる経済的負担を減らしたい場合 ・配偶者との関係を完全に断ち切るのが困難な場合 |
| 物理的別居 | 別々の住居で生活する方法 | ・同居のストレスを減らしたい場合 ・生活スタイルを見直したい場合 ・離婚準備を着実に進めたい場合 |
ただし、住まいを二つ確保する必要があるため、経済的な見通しは事前に立てておきましょう。
熟年離婚は人生の一大転機ですが、感情だけで決断してしまうと、思わぬ生活の困難に直面する可能性があります。
まずは家庭内別居や物理的別居といった柔軟な手段を通じて、本当に離婚が最適な判断なのか冷静に見極めることが大切です。
熟年離婚に悩んだときにおすすめの相談先
熟年離婚では、財産分与や年金分割、調停・裁判などの複雑な問題が絡みます。そのため、法的な助言や生活設計のアドバイスができる専門家に相談すれば、より現実的な選択がしやすくなります。
熟年離婚で悩んだときにおすすめの相談先は、以下の通りです。
トラブルが生じた際に頼れる窓口として、参考にしてみてください。
熟年離婚に強い弁護士
財産分与や年金分割などの話し合いが進まない場合は、熟年離婚に強い弁護士へ相談しましょう。
不動産や退職金、年金といった資産が絡むケースでは、専門的な知識が必要になるため、自分だけで対応するのは困難です。
また、不貞行為による離婚の場合、調停や裁判まで進む可能性があるため、法的知識が豊富な弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士に相談すれば、法的根拠に基づいたアドバイスを受けられ、相手との交渉や調停の場でも心強い味方になってくれます。無料相談を活用し、離婚に詳しい弁護士を見つけましょう。
「どの弁護士に相談すれば良いかわからない」とお悩みの方は、相談実績1000件以上の弁護士法人アクロピースにご相談ください。
一般的な離婚問題はもちろん、高所得者層の離婚問題、不倫慰謝料問題などの複雑な問題にも対応させていただきます。
離婚問題に悩む全ての方を全力でサポートいたしますので、まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 離婚問題に強い!/
【無料相談受付中】365日対応
法テラス・市区町村の相談窓口
熟年離婚問題で悩んだ際は、法テラスや市区町村の窓口を利用すると良いでしょう。
法テラスでは、年齢や収入に関係なく、無料の法律相談や弁護士紹介を受けられます。法テラスの事務所は全国各地にあるため、困ったときにいつでも相談できる点がメリットです。
また、市区町村によっては、離婚問題の相談に対応している窓口を設けている場合があります。
市区町村の窓口を利用すれば、弁護士に依頼する前段階として、自身の状況を整理できるでしょう。まずはお住まいの自治体ホームページを確認し、利用可能な支援制度や相談窓口をチェックしましょう。
ファイナンシャルプランナー(FP)
離婚後の生活設計や老後資金に不安がある場合は、FPへの相談がおすすめです。FPは中立的な立場から、離婚後の収支バランスや住まいの見直し、年金・保険の活用方法などを具体的に提案してくれます。
とくに貯蓄や資産が限られている人にとっては、現実的な生活を見通す上で大きな助けとなるでしょう。公的年金や医療費、介護にかかる費用を含めたライフプランの相談も可能です。
離婚後の暮らしに不安がある方は、FPに相談して将来像を明確にすると良いでしょう。
熟年離婚に関してよくある質問
60歳で離婚するとどんなデメリットがありますか?
60歳で離婚すると、主に経済的・生活面・孤独感の3つのリスクが生じやすくなります。
| デメリットの例 | 具体的なリスク |
|---|---|
| 収入減少 | ・年金開始前の離婚は、無収入になる期間が生じる可能性がある ・若年層と比べて再就職が難しい傾向があるため、経済的な不安が生じる |
| 生活面のリスク | 万が一病気やケガを患った際に頼れる人がいない |
| 孤独感の増加 | 家族・近隣とのつながりが希薄になり、孤独感が増す |
こうした状況に陥らないためにも、離婚後の生活設計や支援先の確認を事前に行っておくことが重要です。
熟年離婚を切り出されやすい妻の特徴はありますか?
夫が離婚を切り出す背景には、妻との会話不足や感情のすれ違いが積み重なっている場合が多いです。
たとえば、以下のような状況が続くと、夫が限界を感じて離婚を切り出される可能性があります。
- 話しかけても反応が薄い
- 否定的な言葉が多い
- 感情的に物事を捉えられる
- 家の中では互いに無関心になる
自分が一方的に我慢しているつもりでも、こういった状況では夫も限界を迎えている場合があります。
夫婦関係を見直すためにも、日常の会話や感情の伝え方を意識的に変えていくことが大切です。
熟年離婚するのにベストなタイミングはありますか?
退職金や年金が確定した直後、子どもの独立後がベストタイミングだといわれています。
これらのタイミングで離婚するメリットは、以下の通りです。
| 適切なタイミング | メリット |
|---|---|
| 定年退職後 | 退職金や年金の受け取りが確定し、財産分与の判断がしやすくなる |
| 子どもの独立後 | 子どもの離婚に対するショックを抑えやすい子育てにおける金銭的な影響を抑えやすい |
| 賃貸借契約の更新前 | 住まいの見直しと同時に離婚準備を進めやすい |
ただし、上記のタイミングはあくまで一般的な目安にすぎません。
実際の離婚時期は、夫婦それぞれの経済状況や健康状態、家族関係によって大きく変わります。
離婚後の生活を見据え、弁護士などの専門家の助言を踏まえた上でタイミングを冷静に見極めることが重要です。
まとめ|熟年離婚の不安・迷いがあるなら専門家への相談も検討しよう
熟年離婚には、経済・健康・生活環境など多面的な影響が伴います。
感情だけで決断すると、離婚後に想定外の問題に直面するリスクが高まります。とくに年金分割や財産分与の取り扱い、孤独への備えなどは、事前に計画を立てることが大切です。
熟年離婚で不安や迷いがあるときは、一人で悩まず弁護士やFP、法テラスなどの第三者に相談しましょう。こうした専門家は、それぞれの得意分野を生かし、問題解決に向けてサポートしてくれます。
離婚後の人生設計を描くためにも、プロの知見を活かして判断しましょう。
弁護士法人アクロピースでは、離婚問題に強い弁護士が全力でサポートいたします。
当事務所は、これまで1000件以上の離婚・男女問題のご相談を受けた実績があります。
「有利な状況で離婚したい」「離婚調停を行いたい」などとお悩みの方は、初回相談(60分無料)をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応