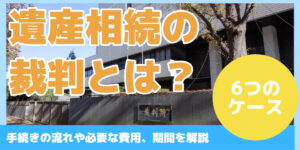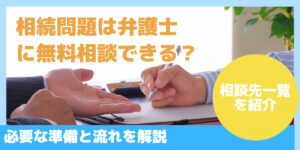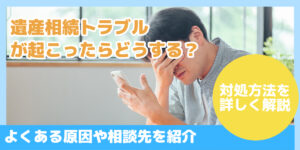【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続の話し合いを拒否されたときの対処法と弁護士に相談すべきケースを解説
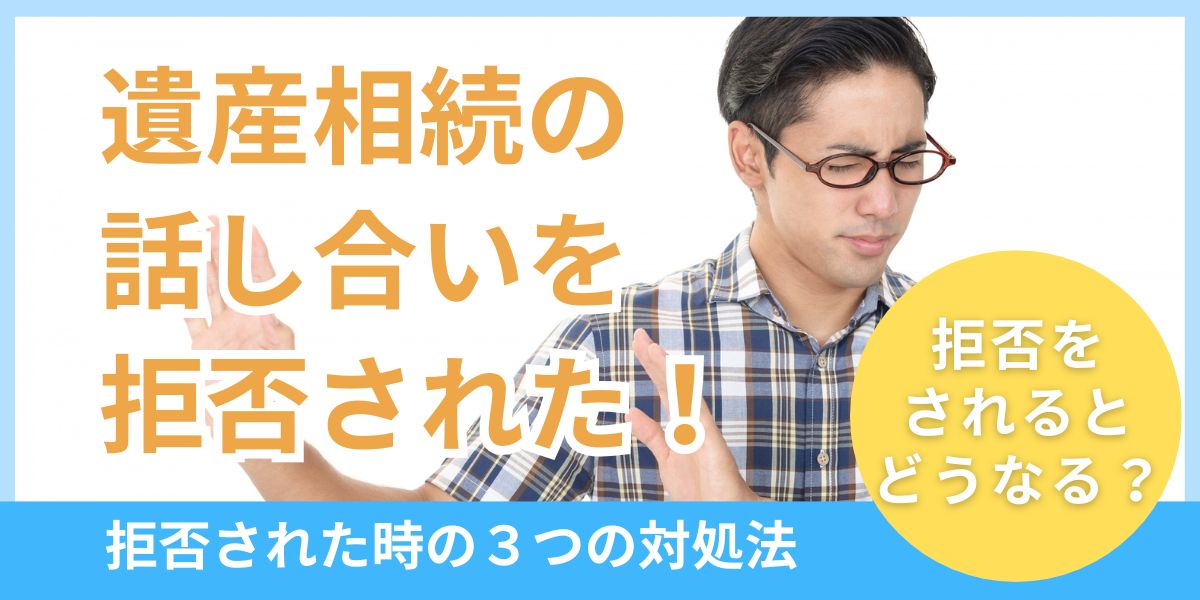
遺産相続の話し合いは遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行って決めなければなりません。
しかし、中には、遺産相続についての「話し合いを拒否する」「連絡を無視する」など、話し合いに非協力的な相続人もいるでしょう。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫相続人の一人でも遺産分割協議の話し合いに応じなければ、遺産分割協議は進められません。
本記事では、遺産分割協議に非協力的な相続人がいて話し合いができない場合の問題と、話し合いを拒否する理由・対処方法を解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続の話し合いを拒否されるとどうなる?


最初に遺産相続で相続人が話し合いを拒否するとどうなるか、影響や起こり得る問題について解説します。
遺産分割協議ができず名義変更などの相続手続きができなくなる
相続人の一人でも話し合いを拒否すれば遺産分割協議ができず、名義変更などの相続手続きができなくなることがあります。
遺言がない場合、全相続人で誰がどの遺産をどのように受け継ぐかを話し合い(遺産分割協議)、不動産や預貯金口座の名義変更や解約などの相続手続きを進めることになります。
相続手続きで、相続人全員が合意した遺産分割協議書の提出を求められる場面も多いでしょう。
遺産分割協議書は、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが基本です。
相続人のうち1人でも話し合いを拒否すれば、遺産分割協議は成立せず、名義変更などに必要な遺産分割協議書を提出できません。
結果として、不動産の活用や預貯金の払い戻しなどができなくなる恐れがあります。
相続人が遺産分割協議に応じない場合の対処法については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:相続人の一人が遺産分割協議に応じない7つの理由と対処法!放置リスクも解説
相続税の申告が期限内にできず税負担が増える
遺産分割が確定しなければ、相続税の申告が期限までにできないこともあります。
相続税の納税が必要な場合、「相続開始を知った日の翌日から10月以内」に申告しなければなりません(相続税法27条1項)。



期限を過ぎると加算税や延滞税が課されます。
分割協議が整わない場合、法定相続分で相続したとして申告することもできますが、小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減の特例などが使えなくなり、相続税額が高くなるリスクもあるのです。
なお、申告期限から3年以内に遺産分割協議が可能な場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、後で特例の適用を受けることはできます。
出典:国税庁|No.4205相続税の申告と納税
出典:国税庁|B1-5 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続
遺言書があれば遺言書に従って遺産相続できる
被相続人が遺言書を残していれば、基本的に遺言書に従って遺産相続をすることになります。
不動産や預貯金・有価証券などの相続人を明確に指定していれば、遺言書を提示して名義変更などの相続手続きが可能です。
遺言書と異なる合意をするのでなければ、遺産分割協議は必要ありません。
遺言書の有無の確認方法については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法は?自筆・公正・秘密の3種類に分けて解説
相続人が遺産相続の話し合いを拒否する3つの理由
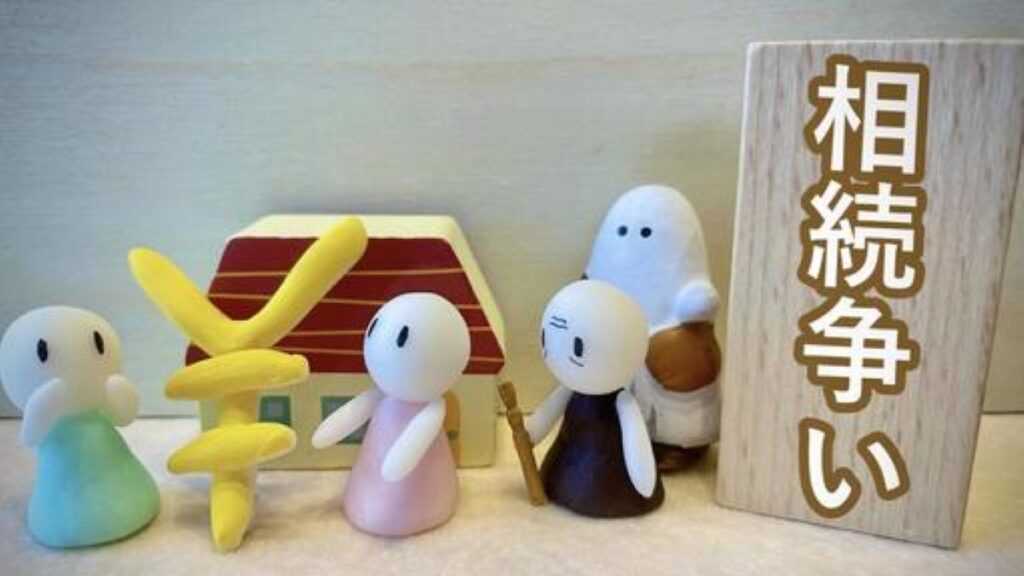
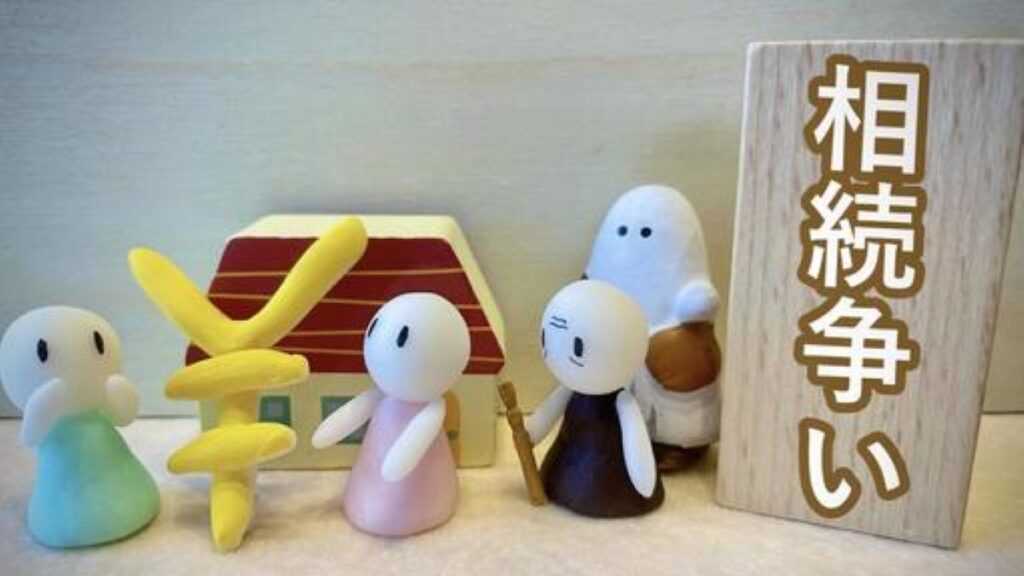
相続人が話し合いの拒否や連絡を無視をすることには、次のような理由があるでしょう。
遺言書や提案した遺産分割の内容に納得できない
遺言書や提案した遺産分割の内容に納得できないことが拒否理由の場合があります。
例えば、遺言書には各相続人が取得する遺産の割合だけを指定されているような場合には、相続人間での話し合いが必要となってきます。
そのため、遺言書で低い割合を指定された場合には、その遺言書に基づいて分割することに納得できず協議に応じないことが考えられます。
他にも、他の相続人に多額の生前贈与があることが特別受益(民法903条)とされていない場合や、逆に、自身が被相続人の財産の維持・増加に貢献した寄与分(民法904条の2)があるのに考慮されていない場合などです。
遺言書がある場合は遺言書に従って遺産分割するのが基本ですが、相続人全員が合意すれば相続人が納得のいく形の遺産分割協議も可能です。
遺言書と異なる合意ができるかどうかについては、以下の記事をご覧下さい。
関連記事:遺言と異なる遺産分割の判例!遺産分割協議の進め方も詳しく解説
遺産分割内容に同意しないとどうなるかについては、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:相続に同意しないとどうなる?遺産分割協議書に同意しない場合に弁護士に依頼するメリット
相続人同士の付き合いがない・仲が悪い
相続人同士が付き合いがない、あるいは仲が悪い場合は、遺産分割協議のため話し合おうと声をかけても、無視される可能性があります。
たとえば、被相続人の前妻の子が相続人とわかった場合、被相続人の死去後に初めて連絡を取ることもあるでしょう。



そのような場合、話し合いを始めること自体が難しいかもしれません。
また、日頃付き合いがないため居場所がわからず、そもそも連絡がつかないこともあるでしょう。
面倒なことに関わりたくない
単に面倒なことに関わりたくないと思っている相続人もいます。
連絡を無視したり、話し合いを拒否したりする相続人は、被相続人や他の相続人と疎遠な場合や仲が悪いとは限りません。
そもそも、遺産相続に関心がなく、面倒で煩わしいことには関わりたくないだけの場合もあるでしょう。
遺産相続の話し合いを拒否された場合の3つの対処法


遺産相続の話し合いを拒否された場合は、次のように対処しましょう。
書面で話し合いに応じるよう説得する
まず書面で遺産相続の話し合いの必要性を説明し説得しましょう。
一方的に遺産分割協議書案を作って押印を求めるのではなく、書面で被相続人の死去の事実、遺産総額・内容、法定相続分などを示したうえで、分割協議が必要なことを説明します。
また、何も連絡が取れない場合には、話し合いに応じなければ調停を提起せざるを得ず、より面倒なことになる可能性があることも説明するのも良いでしょう。
その場合、あらかじめ電話をするなど誠実な対応を心がけるとともに、期限を定めて返事を求めることが大事です。
弁護士と相談する
相続人同士で話し合おうとしても説得に応じず、らちが明かない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、話し合いを拒否する相続人と面談する等して、話し合いに応じるよう冷静に説得することもできます。
弁護士から申し入れをすれば、相手が対応しなければならないという気持ちになり、話し合いに応じる可能性もあるでしょう。(後記「遺産相続の話し合い拒否を弁護士に相談すべき5つの場合」参照)
相続問題を弁護士に依頼した方がよいことについては、次の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、併せてご覧ください。
関連記事:相続問題を弁護士に依頼した方がよいのはなぜ?弁護士の役割の具体例と選び方を解説
遺産分割調停を申し立てる
相続人間あるいは弁護士を介した任意の協議に他の相続人が応じない場合や協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが良いでしょう。
遺産分割調停も話し合いの一環ですが、中立的な立場である裁判官と調停委員が間に入るため、話し合いが進む可能性があるでしょう。
また、裁判所から書類が届いたとなれば、これまで話し合いに応じてなかった相続人も調停には応じることもあります。
遺産分割調停に相続人が出席しない場合や、調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判で遺産分割について決めてもらうこともできます(家事事件手続法49条)。



調停が不成立になった場合は自動的に審判手続へ移行し、裁判官が双方の事情を考慮して最終的な判断を下します。
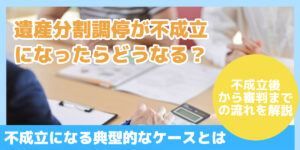
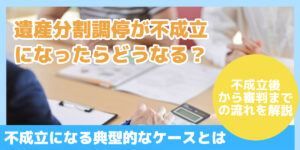
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。(後段略)
家事事件手続法272条(調停の不成立の場合の事件の終了)
4 (略)調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
出典:e-Govポータル|民法907条2項、家事事件手続法272条4項
出典:裁判所|遺産分割調停
遺産分割調停の流れについては、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:遺産分割調停での相続の流れは?申し立ての方法や有利な進め方も紹介
遺産相続の話し合い(遺産分割協議)の進め方
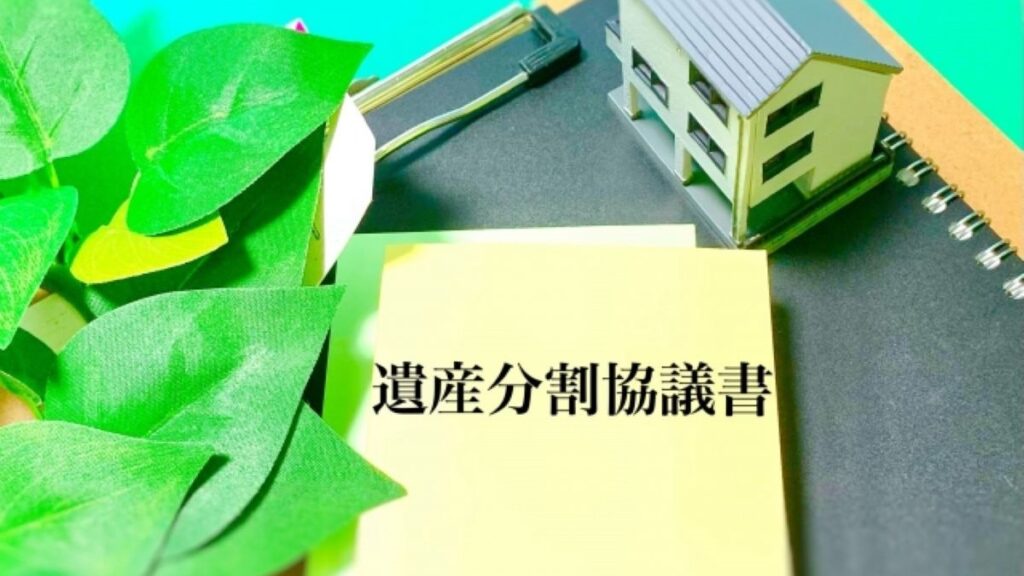
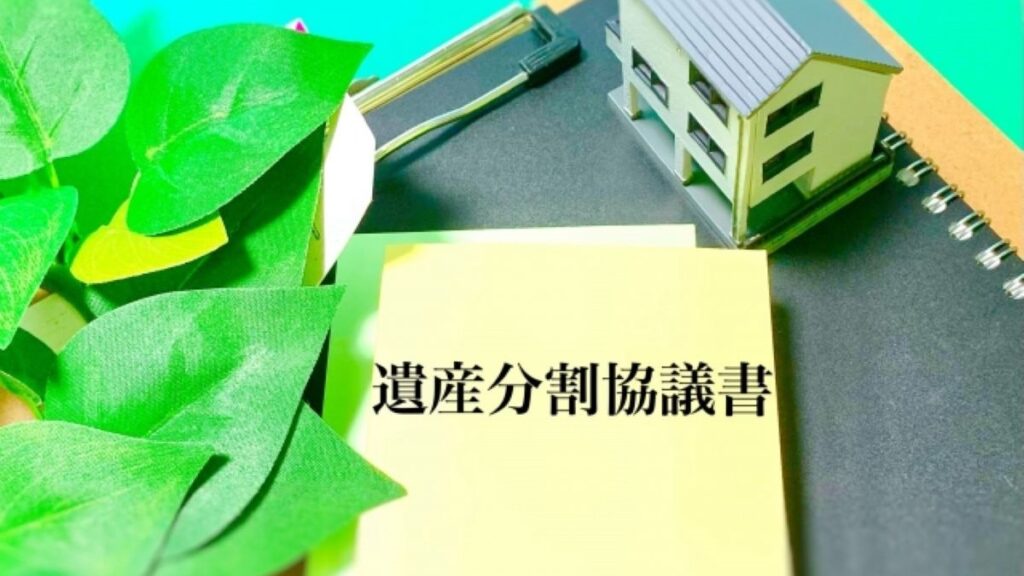
遺産分割協議は次のような手順で進めます。
- 1.相続人と相続財産の調査・確定:
-
相続人調査:まず協議に加わるべき法定相続人を調査します。
法定相続人の範囲と順位は次の通りです(民法887条~民法890条)。
- 配偶者(常に)
- 1位:子(孫・ひ孫)
- 2位:父母(祖父母・曽祖父母)
- 3位:兄弟姉妹(甥・姪)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って、法定相続人を確定させます。
相続財産調査:相続人調査と並行して、不動産・預貯金・有価証券などのプラス財産と、借金やローンなどのマイナス財産をすべて調査し、確定します。
- 2.遺産分割協議:
-
相続人全員で協議し、遺産相続の方法(誰がどの財産をどのような割合で引き継ぐか)を決めましょう(民法907条)。
必ずしも全員が一堂に集まる必要はなく、電話・メール・Web会議も可能です。
- 3.遺産分割協議書の作成:
-
相続人全員が合意したときは遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議に法律で定められた期限はありません。
ただし、相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内、相続税法27条1項)などがあるため、注意が必要です。
遺産分割協議はなるべく早く行うことをおすすめします。
遺産分割の進め方については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:遺産相続でもめたら!もめた場合の対処法と遺産分割協議のスムーズな進め方
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産相続の話し合い拒否を弁護士に相談すべき5つのケース


相続人が遺産相続の話し合いを拒否している場合は、弁護士に相談して対応することをおすすめします。
上記のような場合、弁護士に相談すれば以下のようなメリットがあります。
- 相談者の代理人として遺産分割協議を任せられる
- 法律に則った専門的な知識と豊富な経験に基づき公平な遺産分割ができる
弁護士法人アクロピースは、相続問題に強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。
相続の弁護士費用については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:相続の弁護士費用はいくらかかる?誰が払うのかと安く抑える方法も解説
感情的対立がある場合
相続人の間に感情的な対立がある場合は、相続人間で話し合いを続けても、問題が複雑化し、さらに深刻化する恐れがあります。
たとえば、相続人である兄弟姉妹が日頃から対立しており、相手の言う通りにはしない、嫌がらせをしたいなと思っている場合もあるでしょう。
そのような場合は、弁護士に代理人を依頼すれば、相続人が直接顔を合わせなくても協議を進められます。
冷静に話し合いができる第三者の弁護士を介する方が話し合いが進展しやすいでしょう。
遺産隠しが疑われ相続財産調査が必要な場合
遺産隠しが疑われ徹底した相続財産調査が必要な場合もあります。
たとえば、遺産分割に強固に反対する相続人がいる場合、過去に遺産を使い込んでいたり、遺産隠しをして遺産を独り占めしようとしているかもしれません。



そのような場合は、遺産の全貌を正確に調査し保全する必要があります。
遺産相続に詳しい弁護士と相談して対応を進めた方がよいでしょう。
遺産隠しや相続財産調査のコツについては、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
遺産の分割方法をめぐる争いがある場合
遺産の分割方法をめぐって争いがある場合、遺産相続に不慣れな相続人が自分で遺産分割の割合や方法を他の相続人と話し合うことは、かなり難しいでしょう。
たとえば、不動産の分割問題や、特別受益・寄与分の問題などがある場合は、遺産相続問題の解決実績が豊富な弁護士の力を借りた方がスムーズに進められます。
関連記事:養子縁組による相続トラブルとは?よくある5つのケースやリスク・対処法を解説
相続人が行方不明で連絡できない場合
相続人が行方不明で連絡できない場合は、特別の法的手続きが必要になります。
たとえば、住所地調査(住民票や戸籍の附票を取り寄せる)を行ったうえで、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立て(不在者の代わりに遺産分割などを行える人)や、 失踪宣告の申立て(生死不明で7年以上経過している場合)が必要です。
これらの対応は専門的知識が必要なため、弁護士の力を借りた方がよいでしょう。
連絡が取れない法定相続人がいるときの対処法については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:絶縁中の兄弟との遺産相続トラブルを解説
相続に関与したくないという場合
相続に関与したくないという相続人がいる場合は、相続放棄を求めるのがよい方法です。
家庭裁判所に相続放棄の申述が必要であり、また、相続があったことを知った時から3カ月いないに申立をしなければならないため、弁護士に依頼した方がスムーズに進められます。
早く弁護士に依頼することで、相手方との交渉段階からすべてを任せてスムーズに対応できるため、調停から審判になっても有利な解決が期待できます。
関連記事:相続放棄の手続きの流れは?相続放棄の基本や申述費用・必要書類も解説
関連記事:相続に強い弁護士について解説
音信不通の相続人との遺産分割を成立させた事例
実際に、音信不通の相続人との調整が必要になり、協議を成立させたケースがあります。
“依頼人Bさんは父であるAさんが亡くなったことを受け、Aさんの配偶者であるCさん及び子であるDさんと遺産分割協議を行うこととなりました。しかし、BさんがAさんの戸籍を調査したところAさんには前妻との間に子であるEさんおよびFさんがいることが判明しました。
BさんがEさんとFさんに連絡を取ったところEさんとは連絡が取れましたが、Fさんとは連絡が取れない状況でした。そこで、遺産分割協議を進めるため弊所にご相談。”
この事例の課題としては、
- 被相続人に認知されていない相続人(前妻の子)が存在
- 相続人の一人(Fさん)と連絡が取れない
- 相続人全員の同意が必要な遺産分割協議が進められない状況
があげられます。
そこで
- 弁護士からFさんに書面を送付し、連絡と交渉を行う
- Fさんと連絡を取り協議書の作成や預貯金の解約などの手続きを調整・実行
というご対応をさせていただき、遺産分割協議を完了いたしました。
弁護士が丁寧に状況説明を行いFさんの不安を取り除くことで、法定相続分での協議成立に導くことができました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。
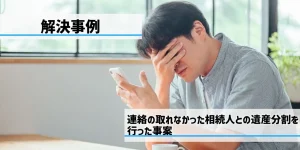
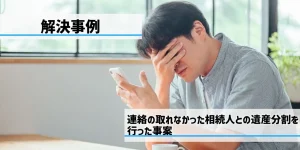
まとめ
遺産相続の話し合いを拒否する相続人がいる場合の問題や対応の仕方をまとめます。
- 一人でも相続人が遺産相続の話し合いを拒否すると、遺産分割協議が進まず、相続手続きができない
- 話し合い拒否や連絡無視の理由は、遺産分割内容に不満・相続人同士の仲が悪い・面倒なことに関わりたくないなどがある
- 話し合いを拒否された場合は、書面で話し合いに応じるよう説得する
- 弁護士に相談する・遺産分割調停を申し立てることも検討する
- 遺産相続について、感情的対立がある・遺産隠しが疑われ相続財産調査が必要・などの場合は、弁護士と相談すべき
遺産相続の話し合いは簡単ではありません。特に話し合いを拒否する相続人がいる場合の対応の仕方は容易でなく、面倒な手続きが必要になる場合もあります。
遺産相続についてわからないことや揉めごとがあるときは、相続分野に精通している弁護士に早めに相談しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応