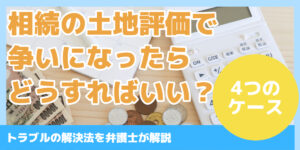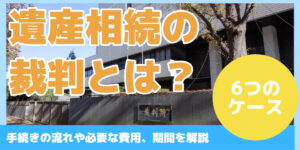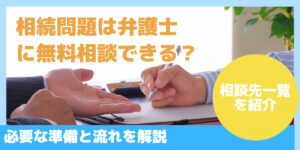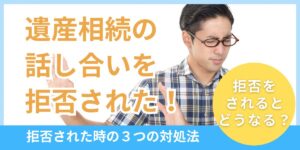【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続トラブルになりやすいケースとは?実例と対処法を弁護士が紹介
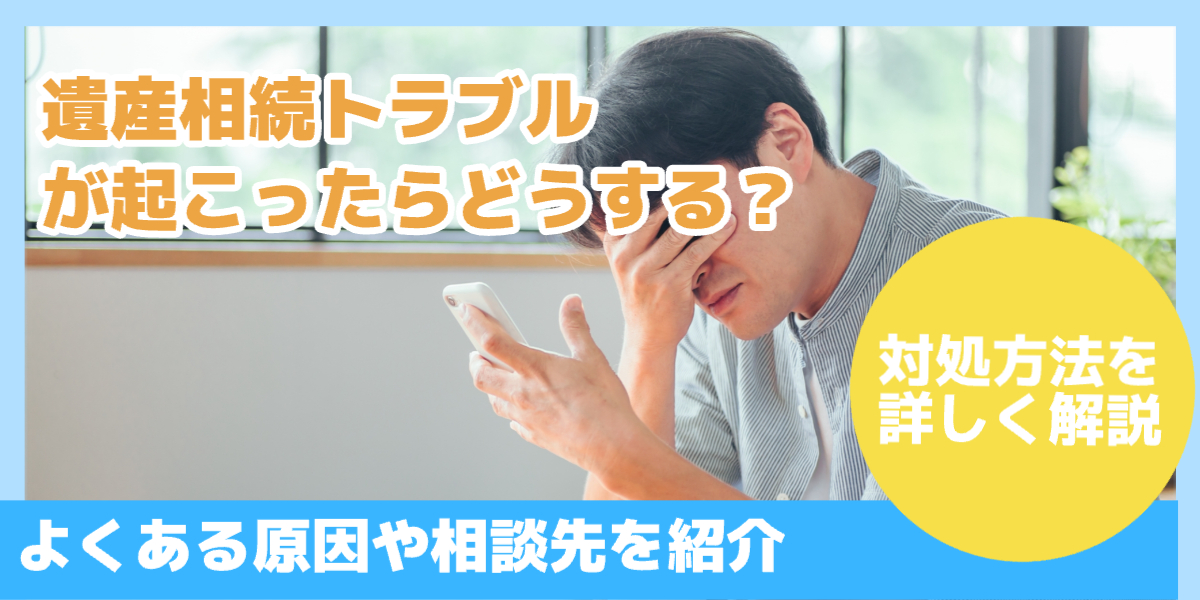
「遺産相続で家族と意見が食い違っていて不安……」
「遺産の分け方や手続きの進め方がわからず、揉めるリスクが気になる」
と悩んでいる人も存在することでしょう。遺産相続トラブルは、対応を誤ると親族関係に深い亀裂を生み、長期化すると精神的・金銭的負担も大きくなります。
本記事では、遺産相続トラブルが起こりやすい家族の特徴やよくあるケースを、弁護士監修のもと、わかりやすく解説します。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
【事例付き】遺産相続トラブルによくある原因とケース6選
相続トラブルとして多いのは、以下6つのようなケースです。
裁判所の統計によると、令和6年の遺産分割事件は15,379件(終局区分別)で前年比約10%増加しています。そのうち約42%は資産1,000万円超〜5,000万円以下の事案であり、中規模の遺産でもトラブルは起きやすいのが実情です。
(参照:裁判所|令和5年 司法統計年報 3 家事編/令和6年 司法統計年報 3 家事編)
以下では、遺産相続における6つの典型的なトラブルのケースと具体的な対策を紹介します。
関連記事:不動産相続のよくあるトラブル例10選|揉める原因と解決方法・注意点を解説
兄弟間で遺産の配分に不満がある
法定相続分と異なる配分がされると、兄弟間で「不公平だ」と感じやすくなります。
たとえば長男が「親と同居していたから」と、遺産を多く相続すると、他の兄弟が不満を抱くことがあります。
こうした感情的な対立を防ぐには、生前の段階で家族全員と相続方針を話し合っておくことが有効です。難しい場合は、第三者である弁護士や司法書士に相談しましょう。
遺産相続における兄弟間のトラブルは下記でも解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:遺産相続で長男は独り占めできる?兄弟間でよくあるトラブルや対処法を解説
生前贈与の有無で不公平感がある
特定の子に高額な贈与をしていると、他の相続人が不公平と感じやすくなります。
たとえば、生前に次男にだけ住宅資金として1,000万円を渡していた場合、長男が特別受益として不満を訴える可能性があります。
贈与を行う際は、契約書や記録を残し、事前に家族へ説明しておくことが大切です。
また、以下の記事では特別受益と生前贈与の違いを解説していますので、気になる方はあわせてご覧ください。
関連記事:特別受益と生前贈与の違いは?計算方法や贈与税・持ち戻しの免除についても解説
遺言書の内容が一方的・不明瞭である
遺言書が曖昧だったり、一部の相続人に偏っていたりすると、トラブルのもとになります。
たとえば「全財産を長男に」といった記載だけでは、他の相続人が遺留分を主張し、争いに発展するおそれがあります。
法的に有効な内容にするため、公証人が作成する公正証書遺言を活用するのが安心です。
遺言書の有無や種類は下記の記事でも解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法は?自筆・公正・秘密の3種類に分けて解説
相続財産に不動産が多く分けづらい
不動産は現物での分割が難しく、相続人間で価値のバランスが取りづらいのが特徴です。
たとえば実家(建物)を長男が、妹が少額の現金を受け取るなどのケースでは、兄妹間での不公平感が生まれやすくなります。
(遺産の分割)民法 第907条
出典:民法 第907条(e-Gov 法令検索)
共同相続人は、遺産の分割について協議をすることができる。協議が調わないときは、家庭裁判所は、共同相続人の請求により、遺産の分割を審判で定めることができる。
早めに不動産の評価額を確認し、代償分割や売却の選択肢も検討しましょう。遺産に不動産が多いケースについては下記でも解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求の方法と注意点を詳しく解説
介護の負担が大きく異なる
介護を担った相続人とそうでない相続人の間では、遺産の分配に対して納得できずトラブルに発展するケースがあります。
たとえば、兄弟の1人が長期間にわたり介護したにもかかわらず、他の兄弟の法定相続分と同じ場合、介護を担った側が不満を訴える可能性があるでしょう。

通院記録や費用の領収書を残し、寄与分として考慮されるよう備えておくことが大切です。
相続人同士の信頼関係が欠けている
相続人同士の関係が良好でない場合、相続の話し合いもスムーズに進まない可能性があります。
過去の確執や金銭トラブルがある場合、「遺産を隠されたのでは」「勝手に使われたのでは」などの疑念が生まれ、感情的対立を招くこともあるでしょう。
日頃から財産の状況や相続の方針を共有し、必要に応じて専門家に介入してもらうことが有効です。
遺産相続で揉めやすい家族の特徴については、下記の記事でもチェックしてみてください。
関連記事:遺産相続で揉める人と揉めない人の差は何?トラブルの原因と予防するコツを解説
関連記事:相続の遺産分割調停で嘘ばかりつかれたらどうする?不利にならない対処法を弁護士が解説
【要チェック】遺産相続でトラブルが起こりやすい親子・兄弟の特徴
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続の場面では思わぬトラブルが起こることがあります。たとえば以下のような傾向を持つ家庭ほど、相続をきっかけに関係が悪化するリスクが高いといわれています。
あてはまる点がある場合は、早めに弁護士に相談し、トラブルを未然に防ぐ準備を始めましょう。
家族の会話がなく信頼関係が築けていない
家族の会話が少ないと、相続時に誤解や不信が生じやすくなります。
たとえば「親は長男に家を継がせるつもりだった」といった前提が他の兄弟に伝わっていないと、不公平感からトラブルになることがあります。
実際には、財産の分け方よりも「気持ちのすれ違い」が対立の原因になるケースが多いです。相続についての話は切り出しにくいものですが、親が元気なうちに方向性を共有することが大切です。
もし当事者同士だけの会話に不安がある場合は、専門家を交えた家族会議も視野に入れましょう。
特定の相続人が財産を独占的に管理している
一部の相続人だけが通帳や不動産などの財産を管理していると、不信感が生まれやすくなります。
以下のように、後から問題が明るみに出ることも珍しくありません。
- 長男に通帳を預けていたら残高が減っていた
- 実家の売却が勝手に進められていた
善意で管理していたとしても、記録が残っていなければ疑念を招くリスクもあるでしょう。
預金の出入りや資産処分について記録を残し、必要に応じて他の相続人と情報を共有することをおすすめします。心配な場合は、弁護士に相談して進めることが安心です。
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説
家族構成が複雑(再婚・内縁・前妻の子など)
再婚や内縁関係、前妻・前夫との子どもがいる場合、相続人同士の関係が希薄なためトラブルが起こりやすくなります。
以下のような事例も少なくありません。
- 同居していた内縁の妻が相続できなかった
- 前妻の子と現妻の子の話し合いが決裂した
このようなケースでは、遺言書によって相続の方針を明確にすることが非常に重要です。
法的に有効な遺言を作成し、意向をきちんと残しておくことがトラブル防止につながります。
関連記事:養子縁組による相続トラブルとは?よくある5つのケースやリスク・対処法を解説
感情的で冷静な話し合いが難しい
相続では金額よりも感情のもつれが対立の原因になることもあります。



「昔から自分だけ冷たくされた」「介護を押し付けられた」といった不満が、相続時に爆発することも考えられます。
このような感情の対立は協議を妨げ、調停や訴訟に発展するリスクが高いです。冷静な話し合いが難しいと感じたら、早めに弁護士を介入させることも検討しましょう。
金銭に執着しやすい相続人がいる
相続人の中に金銭に強い執着を持つ人がいると、協議が難航しがちです。
わずかな金額にも固執する、常識を超えた要求をするといった相続人がいると、他の相続人に負担をかけ、トラブルに発展しやすくなるでしょう。
遺産分割協議がスムーズにいかず中断したり、相続人同士の関係が悪化したりするリスクも考えられます。
こうしたケースでは、早めに弁護士など第三者に相談することが重要です。専門家の中立的な立場で整理することで、冷静な話し合いが可能になるでしょう。
親子関係が断絶していて話し合いが成立しない
長年親子関係が断絶していると、信頼関係が築かれていないため、相続時の合意も困難になります。
以下のようなトラブルの原因になる可能性があるでしょう。
- 10年以上連絡を取っていなかった子が突然相続権を主張してくる
- 財産の内容が把握できていない
親子関係の修復が難しい場合でも、最低限の対話や情報共有は必要です。トラブル予防のためにも、遺言書の作成や専門家への相談を行い、早めに対策を講じましょう。
関連記事:遺産相続の話し合いを拒否されたときの対処法と弁護士に相談すべきケースを解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
【無料相談あり】遺産相続トラブルに強い相談先まとめ|弁護士・家庭裁判所・公的機関
相続問題は、身内だけで解決しようとすると、かえって感情的な対立を深めることがあります。特に、遺産の金額や内容が複雑な場合、専門知識がないまま判断を下すと、不利益を被る可能性もあるため注意が必要です。
ここでは、相続トラブルの相談に役立つ代表的な5つの窓口を紹介します。
| 相談先 | 特徴 |
|---|---|
| 弁護士法人アクロピース | 初回60分の無料相談が可能 遺産分割や遺留分侵害額請求、認知症の親の財産管理など、複雑な事案にも対応 |
| 家庭裁判所 | 裁判官や調停委員が中立の立場で合意形成をサポート |
| 法テラス | 条件を満たせば、弁護士費用の立替制度を利用できる |
| 弁護士会の法律相談センター | 15分間の電話相談が無料 |
| 弁護士以外の士業 | 連携によってスムーズな手続きが可能 不動産の名義変更:司法書士 相続税の申告や財産評価:税理士 |
「誰に相談すればよいか分からない」と迷っている方は、まずこの中から状況に合った先を検討してみてください。
弁護士法人アクロピース|初回60分無料相談
相続問題の初動として、「誰かに相談したいが、面談は抵抗がある」という方には、弁護士法人アクロピースの無料相談がおすすめです。
電話やメールでの相談も可能であるため、面談前に悩みを整理したい方や、まず方向性だけでも確認したい方にも利用しやすいでしょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
家庭裁判所|遺産分割調停
相続人同士の話し合いが難航する場合、家庭裁判所での遺産分割調停が有効です。裁判官と調停委員が中立的に介入し、合意形成をサポートしてくれます。
具体的には、以下のような状況に適しています。
- 兄弟間の感情的対立
- 財産の分け方がまとまらない
- 法律的な判断が必要なケース など
家庭裁判所では公平な環境で話し合いができるため、自力解決に限界を感じたら積極的に利用を検討しましょう。
遺産分割調停の流れは、下記の記事も参考にしてください。
関連記事:遺産分割調停での相続の流れは?申し立ての方法や有利な進め方も紹介
(調停の成立・効力)家事事件手続法 第268条
出典:家事事件手続法 第268条(e-Gov 法令検索)
家事事件について調停が成立したときは、その調書は確定判決と同一の効力を有する。
公的な相談窓口|法テラス・市区町村など
費用面の不安がある場合は、公的機関の無料相談窓口を活用しましょう。
法テラス(日本司法支援センター)では、収入などの条件を満たせば弁護士費用の立替制度を利用できます。また、自治体の役所や地域包括支援センターでは、無料の相続相談会を定期開催している場合があります。
まずは以下のような機関を調べてみてください。
- 法テラス
- 市区町村の役所
- 消費生活センター
- 地域包括支援センター
早期に専門家へ相談することが、トラブルの深刻化を防ぐ第一歩です。
弁護士以外の士業|司法書士・税理士など
相続手続きでは弁護士だけでなく、司法書士や税理士など他の専門家の協力も不可欠です。それぞれの役割は以下のとおりです。
| 専門家 | 主な対応内容 |
|---|---|
| 司法書士 | 不動産の名義変更 |
| 税理士 | 相続税の申告や財産評価 |
これらの手続きをおろそかにすると、登記のミスや税務トラブルにつながる恐れがあります。全体の流れを把握し、必要に応じて連携を図ることで、安心して手続きを進められるでしょう。
関連記事:遺産相続は弁護士と司法書士のどっちに相談する?行政書士との業務内容の違いも解説
弁護士会の法律相談センター
「信頼できる弁護士に相談したいが、どこに行けばいいか分からない」という方には、弁護士会の法律相談センターがおすすめです。
各地域のセンターでは、相続に関する初回相談を比較的安価に提供しています。とくに以下のような方は利用しやすいでしょう。
- 弁護士の選び方が分からない
- 初回からの依頼に不安がある
予約が必要な場合が多いため、利用前に公式サイトや電話で確認しておくことが大切です。
【相談前に必読】遺産相続トラブルを弁護士に依頼するときの5つのポイント
相続トラブルで弁護士に依頼する際は、事前にいくつかのポイントを押さえておくと、スムーズかつ納得のいく対応を受けやすくなります。
この章では、相談・依頼の前に確認しておきたい5つの準備事項を紹介します。
「どの弁護士に、何をどう聞けばいいか分からない」と悩む方も、ここでポイントを把握しておきましょう。
相談前に情報を整理する
弁護士への相談をスムーズに進めるには、事前に情報を整理しておくことが重要です。
相続財産の内容や相続人との関係、これまでのやりとりをまとめておくと、限られた相談時間を有効活用できます。
整理すべき情報は、以下のとおりです。
- 遺言書の有無
- 親族との対立の経緯
- 財産の内訳(預貯金・不動産など)
準備があるだけで、弁護士の理解が深まり、より的確な助言が得られます。
初回無料相談を活用する
初めて弁護士に相談する方は、無料相談を活用すると安心して第一歩が踏み出せます。
多くの法律事務所では、30〜60分程度の無料枠があり、現状の整理や費用の目安を確認できます。
初回無料相談の際は、主に以下の3点を確認することが大切です。
- 今後の対応方針を確認
- 弁護士の説明のわかりやすさ・話しやすさを確認
- 対応範囲(調停・訴訟など)を聞いておく
「信頼できるか」を見極める機会としても、有効に活用しましょう。
関連記事:相続問題は弁護士に無料相談できる?おすすめの相談先や必要な準備も解説【弁護士執筆】
相続問題に強い弁護士に依頼する
相続問題は専門性が高いため、相続に強い弁護士を選ぶことが大切です。遺留分請求や不動産の相続、税金対応には豊富な知識と経験が求められます。
遺産相続トラブルを依頼する弁護士を選ぶときは、以下のポイントをおさえましょう。
- ホームページに相続分野の実績が明記されているか
- 口コミで対応満足度を確認できるか
専門性のある弁護士に相談すれば、過去の事例に基づいた具体的なアドバイスが得られます。
相続に強い弁護士の見分け方は下記の記事も参考にしてください。
関連記事:相続に強い弁護士について解説
関連記事:相続を弁護士に任せるメリット・デメリットとは?後悔しない弁護士の選び方も解説
依頼時は契約内容を確認する
正式に依頼する前に、契約内容を細かく確認することが重要です。業務範囲や報告頻度、費用の詳細などを把握しておかないと、後でトラブルになる可能性があります。
確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 調停・訴訟まで対応するか
- 連絡手段や頻度の指定はあるか
- 成功報酬の有無と金額設定
疑問があれば遠慮せずに確認し、納得したうえで契約を結びましょう。
弁護士費用の内訳・相場を正しく把握する
費用面のトラブルを防ぐには、弁護士費用の内訳と相場を事前に把握しておくことが大切です。
見積り時に詳細を確認し、不明点は必ずその場で尋ねましょう。
代表的な費用内訳は以下のとおりです。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談料 | 初回無料〜30分5,000円前後が相場 |
| 着手金 | 30~50万円が目安 |
| 成功報酬 | 財産の10〜16%程度 |
納得のいく依頼先を見つけるためにも、複数の事務所を比較しましょう。
遺産相続の弁護士費用については、以下の記事もご覧ください。
関連記事:遺産相続の弁護士費用は誰が払う?遺産分割調停や裁判の相場も解説【弁護士監修】
関連記事:相続の弁護士費用はいくらかかる?成果報酬についてや安く抑える方法も解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続トラブル発生から弁護士へ依頼するまでの5ステップ
遺産相続トラブルが起きてから弁護士へ依頼するまでの流れは、以下のとおりです。
早めに弁護士へ相談して方向性を整理する
相続トラブルの予兆を感じたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。問題が大きくなる前に方向性を整理することで、冷静な判断がしやすくなります。
たとえば、以下のようなケースでは、弁護士への相談を検討すべきといえます。
- 兄弟と意見が合わない
- 手続きに不安がある
- 感情的な対立を避けたい
初回無料相談を実施している事務所も多いため、気負わずに行動を起こすことが大切です。
証拠を集めて状況を整理する
相続トラブルでは、「何を根拠に主張するか」が結果を左右します。
自分の立場を裏付ける客観的な証拠を、できるだけ多く集めておきましょう。
たとえば、以下のような資料が役立ちます。
- 預貯金通帳のコピー
- 遺言書の写し
- 介護や同居の記録(日付入りメモや領収書)
- 家族間のやり取り(LINE・メール等)
また、財産内訳や相続人の構成図をまとめておくと、弁護士への説明がスムーズです。
「言った・言わない」の水掛け論を避け、証拠に基づく交渉で有利に進めましょう。
内容証明郵便で請求意思を示す
話し合いが平行線のまま進まないときは、内容証明郵便で正式に意思を示しましょう。
たとえば、「遺留分を請求したい」「財産の開示を求めたい」といった主張を、法的効力を持つ文書で通知できます。
後の調停や裁判でも「いつ・何を主張したか」の証拠にもなります。
弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の文面作成や送付手続きまで、適切なサポートが可能です。話し合いが進まないと感じたら、早めに内容証明郵便での対応を検討しましょう。
話し合いで解決できない場合は調停・審判を検討する
協議だけで解決が難しいときは、家庭裁判所での調停や審判を視野に入れましょう。
調停では、裁判所が選任した調停委員が中立の立場で双方の意見を聞き、合意を目指します。
それでも合意に至らなければ、審判で裁判所が最終判断を下します。
「このままでは解決できない」と感じたら、弁護士と相談しながら、適切なタイミングで調停や審判を申し立てましょう。
不動産が関係する場合は適切に対処する
不動産を含む相続では、放置せずに早期に対応することが重要です。共有名義のままでは、売却や管理でトラブルになりやすいためです。
また、不動産の評価額に納得できない場合は、代償分割や売却による現金化を検討しましょう。
不動産は登記や税務の知識も必要なため、弁護士や司法書士に相談しながら適切に進めましょう。
遺産分割の不動産評価については、以下の記事も参考にしてください。
事前に流れを理解しておくことで、感情的な対立を避けつつ、冷静に問題を解決しやすくなるでしょう。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産相続トラブルを防ぐための生前対策5選|遺言書・生命保険・家族信託
相続トラブルの多くは、実際には“相続開始前”の準備不足が原因です。準備が遅れるほど、家族への負担は大きくなります。
本章では、生前から今すぐ取り組める5つの具体策を紹介します。
遺言書を作成して内容を明確にする
相続トラブルを未然に防ぐには、遺言書の作成が有効です。遺言がないと法定相続分に従って機械的に分配され、実情が反映されず不満が生じやすくなります。
とくにおすすめなのが「公正証書遺言」です。法律の専門家が作成をサポートするため、形式ミスによる無効リスクが大きく下がります。



元気なうちに弁護士や司法書士と相談し、明確で法的に有効な遺言を準備しておきましょう。
公正証書遺言については、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
関連記事:公正証書遺言の作成にかかる時間は?必要な費用や作成の簡単な流れを解説
生命保険や家族信託を活用する
生命保険や家族信託を活用すれば、相続トラブルの回避に役立ちます。これらは、遺産分割協議を経ずに財産を承継でき、争いの火種を減らせます。
主な活用例は以下のとおりです。
- 生命保険:指定した受取人に直接支払われ、原則として遺産分割対象外
- 家族信託:財産を管理する家族と信託契約を結び、認知症リスクにも対応
生命保険や家族信託は、家族構成や財産の種類・額に応じた設計が重要です。専門家と相談し、自分に合った制度を選びましょう。
家族で生前に相続について話し合っておく
生前の話し合いは、相続トラブル防止の基本です。相続は避けがたいテーマである一方、事前に話し合うことで認識のずれを防げます。
話し合いのポイントは以下のとおりです。
- 家族の希望や条件を共有する
- 落ち着いた場で冷静に意見交換する
- 内容を記録として残す
対話を通じて家族の理解を深め、スムーズな相続につなげましょう。
財産管理の権限を適切に分ける
財産管理を一部の人だけが担うと、不透明さから疑念を招く恐れがあります。家族間で明確に役割を分担し、情報を共有することが信頼関係の維持に役立ちます。
具体的な対策としては、以下があげられます。
- 印鑑・通帳・不動産書類の管理を分担
- 月1回の残高報告を実施
- 資産台帳を作成し共有
情報の「見える化」により、不信感を減らしトラブル予防につながるでしょう。
公平感を重視した遺産分割を設計しておく
「平等」ではなく「公平」を意識した遺産分割は、不満を防ぐうえで有効といえます。法律上も「寄与分」や「特別受益」が考慮されるため、貢献度を加味した配分が理想的です。
事前に「寄与分」や「特別受益」についてまとめた一覧表を作成し、話し合いの場で共有することで、納得度の高い相続設計が可能になります。
難しい場合は弁護士や司法書士など専門家に相談することも検討してみてください。
(寄与分)民法 第904条の2
出典:民法 第904条の2(e-Gov 法令検索)
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その者の寄与に応じて相続分を定めることができる。
遺産相続のトラブルに関してよくある質問
遺産相続で一番トラブルが起こりやすい金額はいくらですか?
統計上、1,000万円超〜5,000万円以下の遺産の価額における相続が最も揉めやすい傾向にあります。
家庭裁判所の資料によれば、令和6年に解決された遺産分割事件のうち約42.4%がこの遺産の価額帯で争われており、相続人間での不満が生まれやすいといえます。
(参照:最高裁判所事務局|令和6年 司法統計年報 3 家事編)
金額の多少にかかわらず、事前の話し合いや専門家の活用が重要です。
遺産相続の三か月ルールとは?
相続人は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、相続方法を選択しなければなりません。
この「三か月ルール」は、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを決める法的な期限で、過ぎると単純承認と見なされます。
(参照:裁判所|相続の承認又は放棄の期間の伸長)
負債がある可能性がある場合は、早めの判断と手続きを進めましょう。
(相続の承認又は放棄の期間)民法 第915条
出典:民法 第915条(e-Gov 法令検索)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、単純承認、限定承認又は放棄をしなければならない。
遺産相続で絶縁した兄弟がいる場合はどうすればいいですか?
その兄弟と連絡が取れるかどうかによって、対応方法が変わります。
- 連絡が取れる場合:相続が発生したことを伝えて、遺産分割協議に参加するよう伝える
- 連絡が取れない場合:戸籍謄本や附票を取得して現住所を調べ、連絡を試みる
法律上、完全に縁を切る制度はありません。
事実上絶縁している兄弟であっても、法定相続人にあたる場合は、相続権があります。
どうしても連絡が取れない、あるいは生死が不明の場合は、不在者財産管理人の選任が必要です。
必要に応じて弁護士へ相談しましょう。
絶縁中の兄弟がいる場合の遺産相続は、下記の記事も参考にしてください。
関連記事:絶縁中の兄弟との遺産相続トラブルを解説
遺産相続トラブルが発生したが遺産分割を成立させた事例
実際に、相続人が音信不通であるというトラブルがあったが、協議を成立させたケースがあります。
“依頼人Bさんは父であるAさんが亡くなったことを受け、Aさんの配偶者であるCさん及び子であるDさんと遺産分割協議を行うこととなりました。しかし、BさんがAさんの戸籍を調査したところAさんには前妻との間に子であるEさんおよびFさんがいることが判明しました。
BさんがEさんとFさんに連絡を取ったところEさんとは連絡が取れましたが、Fさんとは連絡が取れない状況でした。そこで、遺産分割協議を進めるため弊所にご相談。”
この事例の課題としては、
- 被相続人に認知されていない相続人(前妻の子)が存在
- 相続人の一人(Fさん)と連絡が取れない
- 相続人全員の同意が必要な遺産分割協議が進められない状況
があげられます。
そこで
- 弁護士からFさんに書面を送付し、連絡と交渉を行う
- Fさんと連絡を取り協議書の作成や預貯金の解約などの手続きを調整・実行
というご対応をさせていただき、遺産分割協議を完了いたしました。
弁護士が丁寧に状況説明を行いFさんの不安を取り除くことで、法定相続分での協議成立に導くことができました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。
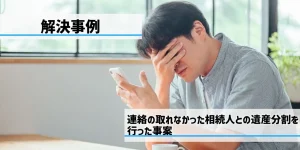
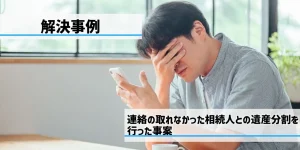
遺産相続トラブルが起こったときの対処法まとめ
遺産相続は話し合い不足や不公平感から深刻な対立に発展しやすいため、事前の備えが重要です。
公正証書遺言の作成や資産情報の共有、生前の家族会議がトラブル予防に役立ちます。不安がある場合は、弁護士や司法書士、法テラスなど専門家の無料相談を活用しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応