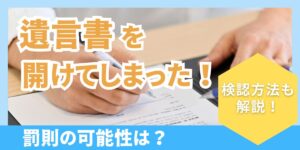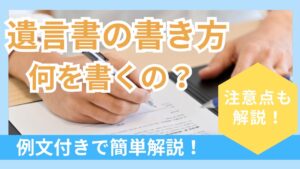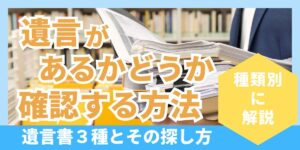【無料相談受付中】24時間365日対応
遺言書検認の弁護士費用は?司法書士に依頼する場合の報酬や手続きの流れも解説
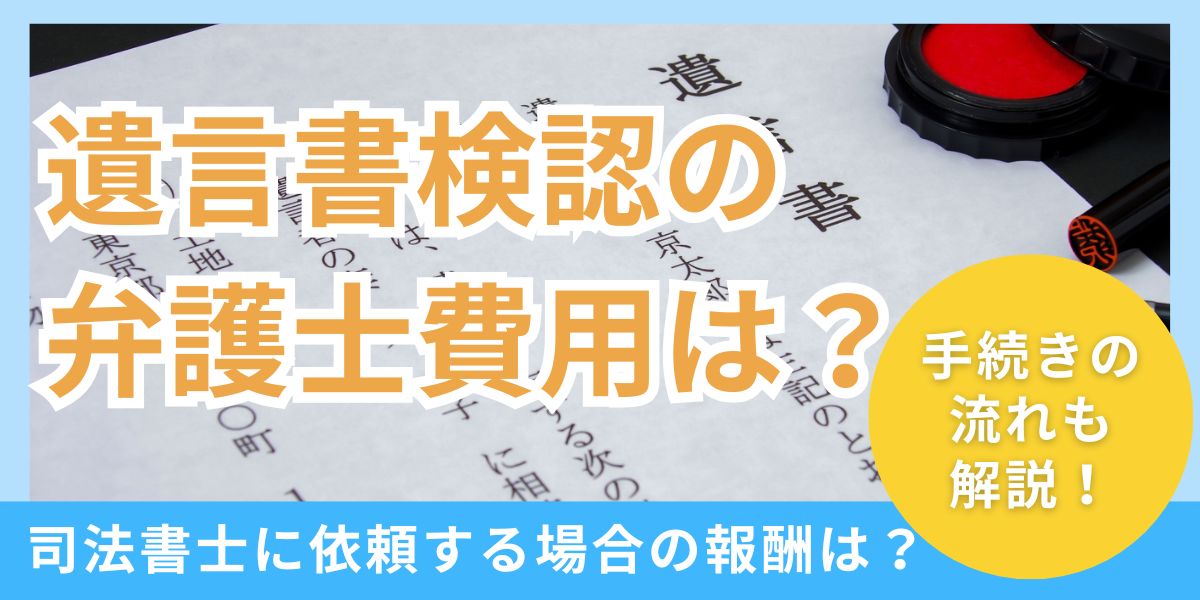
公正証書遺言以外の遺言書を見つけた場合は、「検認手続き」をしなければなりません。
わざわざそんなことする必要ないと考える方も現実には多くいらっしゃいますが、民法では、遺言書を見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければならないと規定されています。
そして、検認をしなかった者には5万円の過料(かりょう)という罰則規定もあります。
今回は、この検認手続きについて詳しくご説明していきます。
遺言書の手続きやトラブルで悩んでいる方は、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺言書と検認はセット
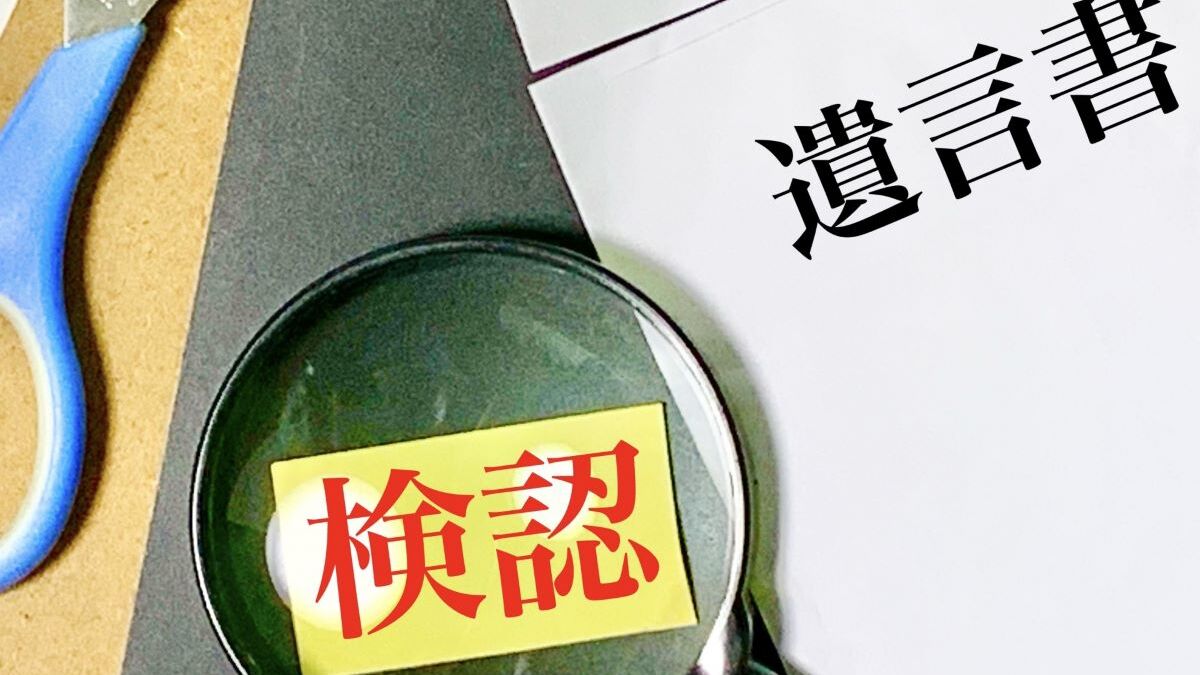
まず必ず覚えておきたいのが、民法にも規定されている通り、遺言書と検認はセットといって過言ではありません。
罰則規定もあるため、必ず検認手続きは行うようにしてください。
ただし、公正証書遺言については検認の必要はありません。
すでに公証人という専門家によって内容が確認されていますし、公証役場にて保管されているため偽造などの恐れがないため検認手続きを経る必要がないのです。
よって、自筆証書遺言か秘密証書遺言の形式によって作成された遺言書が発見された場合にのみ、検認手続きを行うことになります。
詳しい遺言書の種類については、下記を参考にしてください。
関連記事:遺言書には種類がある?書き方の例文やそれぞれのメリット・デメリット
遺言書検認にかかる弁護士費用は?

遺言書検認は自分で行うこともできますが、弁護士に依頼することもできます。
依頼する場合の弁護士費用の相場は、10~15万円程度です。
必要な準備を弁護士が行うのはもちろん、相続人間でトラブルになる可能性が高い場合は、検認期日に同席してもらえるので、スムーズに進められるというメリットがあります。
遺言書検認を司法書士に依頼した場合の報酬は?

遺言書検認は、司法書士に依頼することも可能です。
弁護士のように同席することはできませんが、手続きのサポートをしてくれます。
司法書士に依頼した場合の報酬は、5〜8万円程度です。
相続トラブルが発生しにくい場合や、費用を抑えたい場合には、司法書士に依頼するのが良いでしょう。
検認手続きって何をするの?
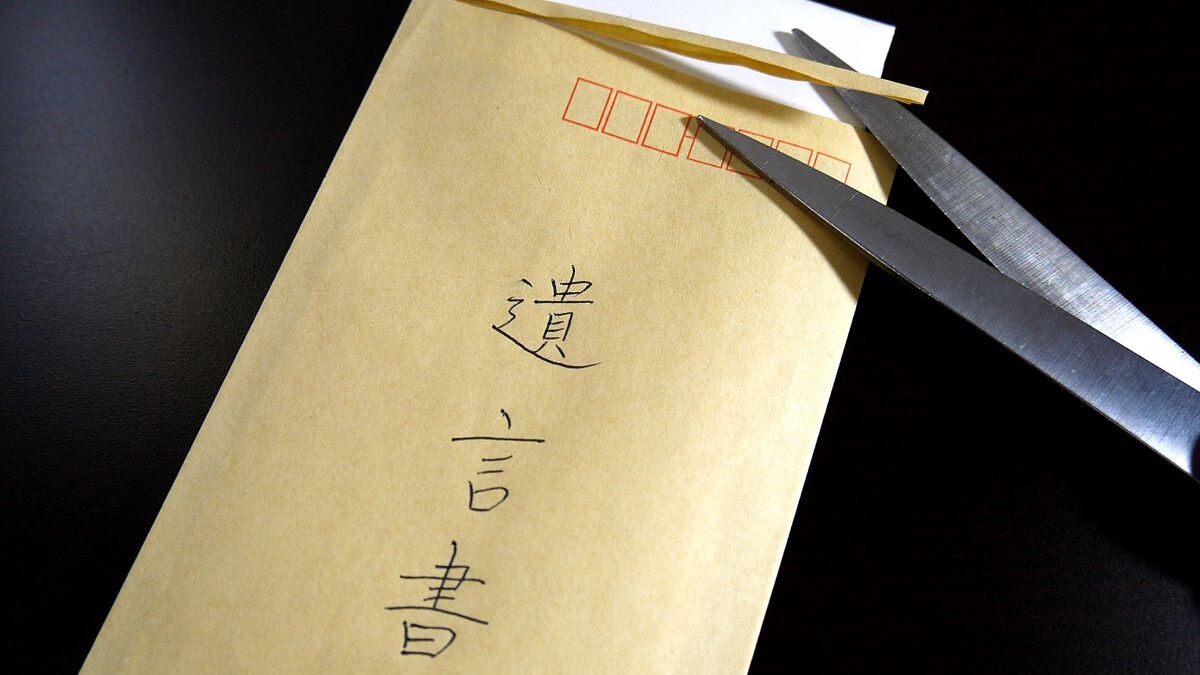
では、具体的に検認手続きというのは何をするのでしょうか?
検認手続きとは、相続人全員に対して遺言の存在を知らせ、遺言の形状や状態、日付署名など、内容を明確にするために行われます。
よって、遺言の内容そのものの有効無効を判断する手続きではないため、検認手続きをしたからといって、必ずその遺言の内容どおりにしなければならないわけでもありません。
また、相続人全員に対して通知するものの、その場で遺産分割協議が始まるわけでも、裁判所が関与するわけでもありません。
さらにいえば、検認手続きをしなかったからといって、遺言そのものがなかったことになるわけでもありません。
法的不備がなければ、遺言は常に有効です。
要するに検認手続きとは、その時点における遺言の状態を確認する、いわば「証拠保全」という役割でしかありません。
ここまで読んで、あまり意味がないのでは?と感じた方も多いかもしれません。
しかし、検認手続きを行うことで遺言書の偽造が防ぐことができますし、遺言自体の法的不備の確認もされます。
つまり、検認手続きには、次のステップである遺産分割協議や受遺者(遺言によって遺贈を受ける者)との話し合いをスムーズに進めるための前準備といった意味合いがあるのです。
下記の記事では、遺言書を勝手に開けてしまった場合の罰則や、法律的な問題がないかについて詳しく解説しています。
関連記事:遺言書を開けてしまったら罰則はある?
検認手続きの簡単な流れ

検認手続きは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
申立が受理されると、家庭裁判所は検認の期日を相続人全員に通知します。
なお、検認の立ち会いは自由で、参加しなかったからといって相続権がなくなるといった心配はありません。
検認当日は、裁判所にて開封や内容の確認作業が行われ、その結果が記載された検認調書が作成されます。
そして検認後の遺言書は検認済みの印がされ、申立人のもとに返還されます。
検認に立ち会わなかった相続人、受遺者に対しては裁判所から検認済みの連絡がされることになり、これをもって検認手続きはすべて終了となります。
検認手続きに必要な書類
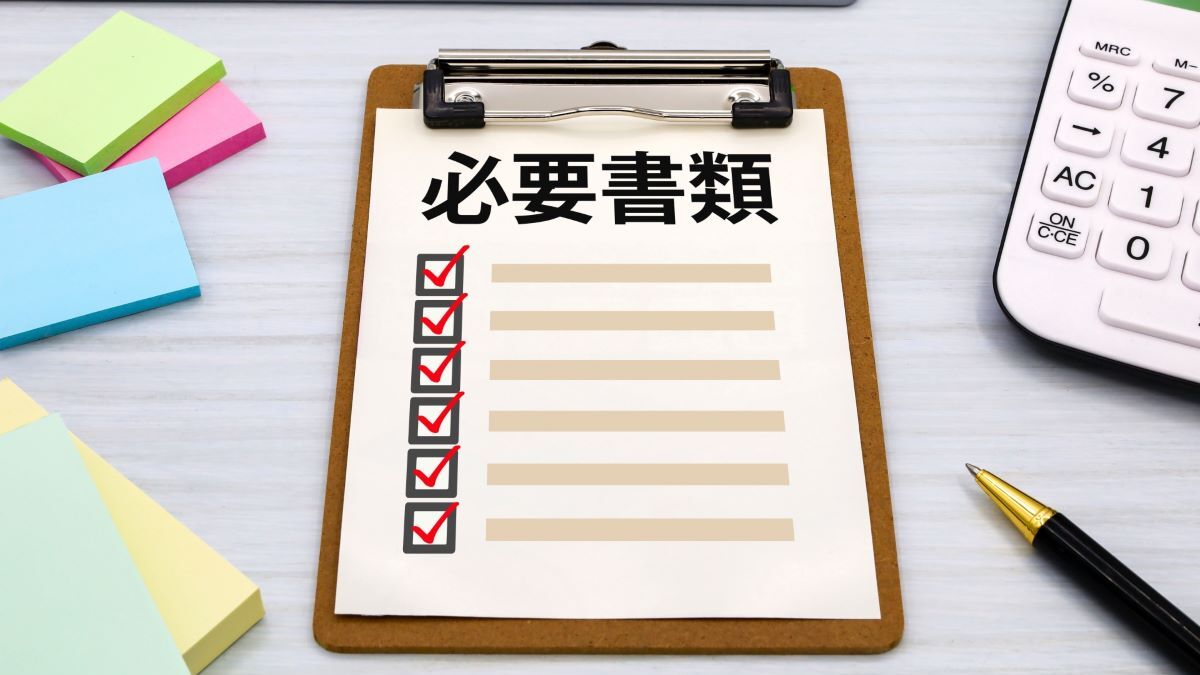
検認手続きに必要となるのは、家事審判申立書と当事者目録です。
いずれもお近くの家庭裁判所や裁判所のホームページにて入手することが可能です。
その他に、誰が相続人であるかを裁判所が確認する資料として、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票などが必要になります。
ちなみに、検認手続きにかかる費用は収入印紙が800円と、連絡用の切手です。
切手については管轄となる裁判所によっても若干異なりますし、相続人の人数によっても異なります。
いずれにしても数百円程度ですが、申し立ての際は事前に確認しておくのが無難です。
検認手続きにお困りの方は当事務所へ

検認手続きはそれほど煩雑な手続きではありません。
しかし、裁判所に提出する書類の作成や入手というのは、慣れていないとどうしても時間がかかってしまうもの。
そこで、検認手続きにお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所であれば、提出書類の作成・入手はもちろん、裁判所とのやり取りもすべてご依頼者様の代理で行うことが可能です。
また、検認期日には一緒に裁判所へ同行させていただきます。
相続というのは、どうしても不安が付き物です。
そして、検認手続きが終了したからといって、相続手続きそのものが終了するわけではありません。
当事務所であれば、検認手続き終了後もサポートもさせていただくことが可能です。
また、相続税の納付や相続登記などの手続きも、提携士業が豊富なため、相続に関するすべての手続きを当事務所で完結させられる利点があります。
検認手続きにお困りの方は、その後の手続きも見据えて、ぜひ当事務所にご相談ください。
相続問題に強い弁護士法人アクロピースは、7000件以上の相談実績があります。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
今すぐご相談したい方はお電話がおすすめです!
【無料相談受付中】24時間365日対応