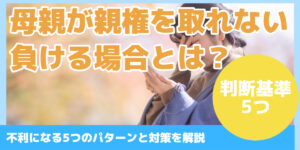子連れ離婚の手続きの順番はどうなる?準備から離婚後までのステップと注意点を弁護士が解説
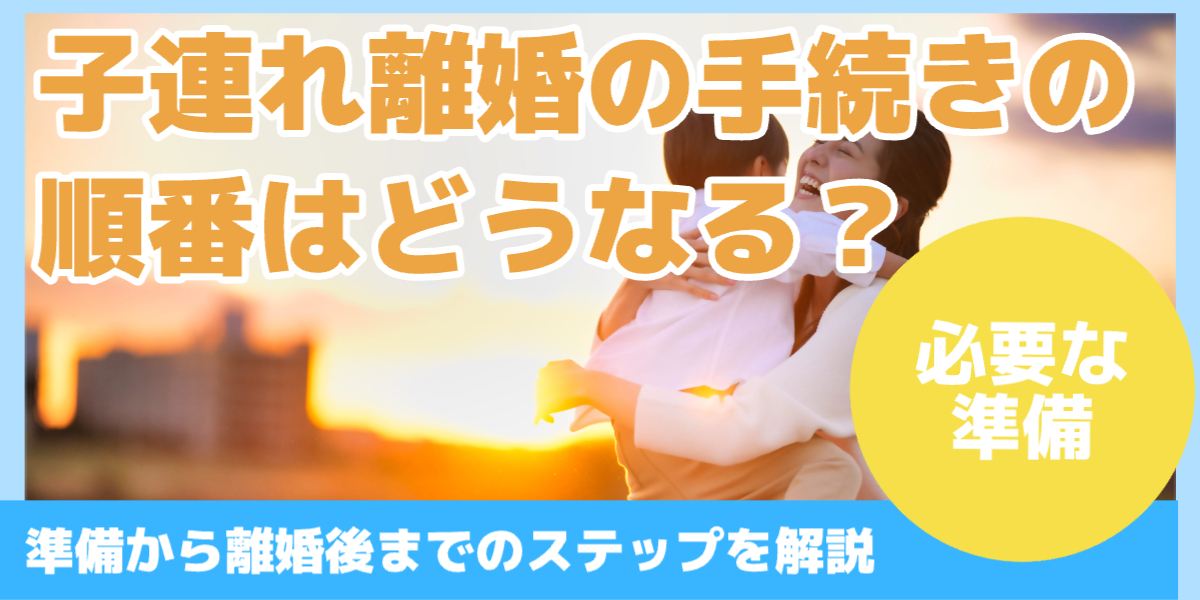
「子どものことを考えると、何から手をつけていいのか分からない…」
「離婚後の生活が不安で、手続きの順番を間違えて損をしたくない…」
子連れでの離婚を控え、このように悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
子連れ離婚は、お子さまの将来や生活の安定を考えなければならないため、不安や戸惑いを抱えている方は少なくありません。しかし、感情的になりやすいときこそ、正しい手続きの順番とやるべきことを冷静に把握することが非常に大切です。
この記事では、法的な観点から「正しい手続きの順番」と各ステップでの具体的な行動、そして陥りがちな注意点を網羅的に解説します。
記事を参考に複雑な手続きの全体像と正しい順番を体系的に理解し、子どもとご自身の未来を守るための一歩を踏み出しましょう。
子連れ離婚に関するあらゆるお悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は、相談実績1000件以上の高い専門性を持っております。
初回60分の無料相談で、あなたに最適な解決策をご提案します。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
子連れ離婚の手続きはどんな順番で進める?全体の流れ
「そもそも子連れ離婚はどういう流れで手続きを進めればいいの?」と疑問に思っている方もいるかもしれません。
子連れ離婚の手続きは、下記の順番で進めるのが基本です。
子連れでの離婚手続きの全体像・流れをあらかじめ把握し、計画的に準備を進めましょう。
離婚方法を決める(協議・調停・裁判)
離婚手続きの第一歩は、離婚の方法を決めることです。主な方法は以下の3つです。
| 離婚の方法 | 特徴 |
|---|---|
| 協議離婚 | ・夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届を役所に提出する方法 ・費用や時間を抑えられるが、当事者だけで冷静な話し合いができない場合には向かない |
| 調停離婚 | ・家庭裁判所で調停委員を介して話し合う方法 ・中立な第三者である調停委員が間に入るため、直接相手と顔を合わせずに協議を進められる |
| 裁判離婚 | ・調停でも合意に至らない場合に、裁判官が法的な判断を下す方法 ・法的な主張と証拠が必要になるため、弁護士のサポートがほぼ必須 |
日本の離婚の多くは、夫婦間の話し合いで合意を目指す「協議離婚」です。しかし、感情的な対立や条件の不一致で合意できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。
どの方法を選択するかで時間や費用、精神的な負担が大きく変わるため、まずは協議離婚を目指し、話し合いが難しい場合は速やかに調停へ移行することを検討しましょう。
親権・養育費・面会交流の取り決め
子連れ離婚で最も重要なのが、「親権」「養育費」「面会交流」という子どもに関する3つの条件を取り決めることです。
| 子どもに関する条件 | 詳細 |
|---|---|
| 親権 | 離婚後の子どもの監護や教育、財産管理を行う権利者 |
| 養育費 | 子どもが経済的に自立するまでにかかる生活費や教育費 |
| 面会交流 | 子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的・継続的に会って交流する方法 |
これらの重要な取り決めは、子どもの将来に直結します。口約束で済ませず、必ず書面に残し、後のトラブルを防ぎましょう。
離婚届の提出と戸籍・住民票の変更
離婚条件の合意後、役所に離婚届を提出することで法律上の離婚は成立します。しかし、それで全ての手続きが終わるわけではありません。
特に注意が必要なのは、子どもの戸籍と氏(姓)です。離婚しても子どもの戸籍や氏は自動的には変わらないため、親権者と同じ戸籍に入れるには別途、家庭裁判所での手続きが必要になります。
その他にも、転居に伴う住民票の異動や、健康保険・年金の切り替えなど、新生活を始めるための手続きが続きます。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫離婚後の手続きを円滑に進めるため、事前に何が必要かを確認しておきましょう。
【準備】子連れ離婚の手続きを進める前にやっておくべきこと
子連れ離婚は、感情的な側面だけでなく、法務、財務、行政手続きが複雑に絡み合うため、全体像を把握した上で念入りに準備しておく必要があります。
離婚協議を進める前に、やっておきたい準備は下記のとおりです。
実際に離婚の手続きが進む前に、まずご自身の状況を整理しておきましょう。
離婚後の生活設計・シミュレーション
離婚準備の第一歩は、離婚をした後に問題なく生活が送れるかどうか、離婚後の生活設計をすることです。
離婚後の生活を現実的にシミュレーションすることで、離婚協議において確保すべき最低限の金銭的条件が明確になります。
シミュレーションを行うときは、まず、今の収入と支出を詳細に洗い出しましょう。具体的には以下の項目を考慮することが大切です。
| 収入 | ・自分の給与、相手から受け取る可能性のある養育費 ・児童扶養手当などの公的支援 など |
|---|---|
| 支出 | ・家賃、光熱費、食費、保険料といった基本的な生活費 ・子どもの成長に伴い増加する教育費や医療費、習い事の費用 など |
収支シミュレーションでは、楽観的な見積もりは避け、現実的かつやや厳しめに試算しておくことをおすすめします。
この生活設計を通して、経済的に自立した生活を送るために必要な金額を把握することが、全ての交渉の土台となるでしょう。
希望する離婚条件の整理
生活設計で経済的な必要額が明確になったら、次はその実現のために離婚協議で何を求めるかを具体的に整理します。
主に決めるべき離婚条件は、以下の6つです。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
これらの条件について、ご自身の希望を明確にし、「絶対に譲れない点」と「譲歩してもよい点」に優先順位をつけておきましょう。
例えば、子どもの生活環境を維持するために親権と住居の確保は最優先とし、慰謝料の金額については状況に応じて柔軟に対応するなど、戦略的に考えることが大切です。
あらかじめ優先度をつけておくことで、交渉が不必要に停滞することを防ぎ、スムーズな合意形成を目指しやすくなります。
証拠収集
証拠は、裁判になった場合だけでなく、協議を有利に進めるための強力な交渉材料です。
一度離婚話を切り出すと、相手が警戒し、証拠の確保が困難になるリスクがあります。その後の交渉や裁判に悪影響を及ぼす可能性が高いため、相手に離婚の意思を伝える前から、慎重に収集を進めましょう。
また、必要な証拠は状況に応じて変わります。具体的には以下のとおりです。
| 状況 | 有効となりうる証拠の例 |
|---|---|
| 不貞行為が疑われる場合 | ・ラブホテルに出入りする写真や動画 ・性交渉を推認させるLINEやメールのやり取り ・クレジットカードの利用明細 など |
| DVやモラハラの場合 | ・怪我の写真や医師の診断書 ・暴言の録音データ、日記などの詳細の記録 ・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録 など |
また、財産分与や養育費の算定や、相手の財産隠しを防ぐためにも、相手の収入や資産に関する資料(源泉徴収票、課税証明書、預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書など)を確保しておきましょう。
関連記事:不倫で慰謝料はいくらもらえる?相場や請求しないほうがいいケースも解説【弁護士監修】
利用可能な公的支援制度の調査
離婚後の生活を支える上では、公的支援制度を活用することも視野に入れましょう。
どのような制度が利用できるかを事前に把握しておけば、経済的な不安が軽減され、交渉の場で精神的な余裕を持ちやすくなります。
国が提供する主な公的支援制度は、以下のとおりです。
| 制度名 | 概要 | 主な対象者 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 一人親家庭等の生活安定と自立を支援する国の手当 | 18歳までの児童を養育するひとり親 | 所得制限あり。毎年現況届の提出が必要。 |
| ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親) | 医療機関での自己負担額の一部または全部を助成 | ひとり親家庭の親と子 | 助成内容や所得制限は自治体により異なる。 |
| 就学援助制度 | 学用品費、給食費などを援助 | 経済的に就学が困難な家庭 | 学校または教育委員会への申請が必要。 |
| 住宅手当 | 家賃の一部を助成 | ひとり親家庭等 | 実施していない自治体も多い。要件確認が必須。 |
特に住宅手当は実施の有無や条件が自治体によって大きく異なるため、お住まいの市区町村の役所のウェブサイトや窓口で必ず確認してください。
弁護士への相談
離婚の交渉がこじれる前の段階で、弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
離婚に関する法律・制度を理解していないまま離婚や離婚の条件の交渉をすると、交渉がまとまらなかったり、不利な条件で合意してしまうリスクもゼロではありません。
弁護士に早い段階から相談しておくことで「どのような請求ができるか」「どのような手続きが必要で、どんな証拠を収集しなければならないか」など、具体的なアドバイスが得られます。
適切な条件で、スムーズな交渉を可能にするためにも、無料相談を活用し、できるだけ早めに相談しておきましょう。
子どものケア
子連れ離婚では、離婚後の生活変化による、子どもへの影響を最小限に抑えるための準備も大切です。
具体的には、転居が必要な場合に新しい住居の周辺環境(治安、公園、小児科など)を調査することや、転園・転校先となる保育園や学校の情報を収集することがあげられます。



特に保育園は待機児童の問題もあるため、離婚を決意したらすぐに役所に相談し、入園の見込みを確認しておくことが重要です。
また、手続きに関する実務的な準備だけでなく、子どもの精神的なケアに目を向けることも重要です。
子どもの心情の変化を観察し、離婚の伝え方やタイミングを慎重に検討することも忘れないようにしましょう。
子連れでの離婚協議をスムーズに進める手続きの順番【4ステップ】
準備が整ったら、いよいよ相手方との離婚を進めます。子連れ離婚の協議では、話し合う順番が極めて重要です。
本章では、「協議離婚」を進める場合の手続きの順番を解説します。
順番や優先度を把握した上で、スムーズに手続きを進めましょう。
関連記事:離婚の手続きは何からするべき? 離婚までの流れや必要書類、注意点を弁護士が解説
ステップ1|子どもに関する事項(親権・面会交流)を具体的に取り決める
最初に決めるべきは、子どもの将来に最も直接的な影響を与える「親権」と「面会交流」です。
日本の法律や家庭裁判所の実務では、何よりも「子の福祉(子どもの利益)」が最優先されます。
この原則に則り、まずは子どもに関する事項から話し合いを始めることで、親としての共通の責任を再確認し、協力的な土台を築けるでしょう。
親権
親権者を決める際、裁判所側は、下記の要素を総合的に考慮します。
- これまで主に子どもの面倒を見てきたのはどちらか(監護の継続性)
- 子どもの年齢(特に乳幼児の場合は母親が優先される傾向)
- 兄弟姉妹を分離させないこと
- (子どもが15歳以上であれば)本人の意思
現状は離婚後の共同親権は認められておらず、離婚届には子の親権を記入する欄があるため、父母のどちらか一方を親権者と定めなければ離婚届は受理されません。
なお、2024年5月に共同親権の導入を盛り込んだ改正民法が成立し、2026年5月までに施行される予定です。(参照:法務省|父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
これにより、今後は父母の協議によって、離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」か、これまで通りどちらか一方が親権を持つ「単独親権」かを選択できるようになります。
2025年9月現在、共同親権は認められていませんが、今後はルールが変わることも頭に入れておきましょう。
関連記事:母親が親権を取れない・負ける場合とは?不利になる5つのパターンと対策を弁護士が解説
面会交流
「面会交流」は親のためだけでなく、子どもが両方の親から愛されていると感じ、健全に成長するための重要な権利です。
トラブルを避けるためにも、以下の内容を具体的に取り決めておきましょう。
- 面会交流の頻度(月1回、2か月に1回など)
- 時間
- 場所
- 宿泊の可否
- 連絡方法 など
関連記事:親権と監護権どっちが強いの?子どもの親権は誰が取る―「親権」と「監護権」の基礎知識
ステップ2|養育費・婚姻費用・財産分与など金銭条件を決める
子どもの生活基盤を整えたら、次に、下記の金銭的な条件を詰めていきます。
養育費
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を基準に算出するのが、離婚における実務でも一般的です。
私立学校の学費や留学費用、高額な医療費など、算定表にはあらわれない特別な支出については別途協議し、負担割合を決めておくと安心です。
関連記事:養育費のトラブルは弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用相場・選び方を解説
婚姻費用
「婚姻費用」とは、離婚が成立するまでの別居期間中に必要となる生活費全般を指します。
夫婦には、その収入に応じてお互いの生活を同程度の水準に保つ義務(生活保持義務)があるため、収入の多い方が少ない方へ支払うのが原則です。
この婚姻費用には、請求する側の衣食住の費用や医療費などに加え、同居している子どもの生活費や学費、医療費といった「養育費」に相当する分も含まれます。
金額は、養育費と同様に裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を基準に決めるのが一般的です。
もし話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てて、法的な手続きを通じて請求できます。
関連記事:別居中の生活費をくれない!生活費を請求する具体的な方法と相場
関連記事:婚姻費用分担請求とは?計算方法から手続きの流れ、払わない相手への対処法まで解説【弁護士監修】
財産分与
「財産分与」は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、公平に分ける手続きです。原則、以下のような財産が分与の対象となり、どちらの名義かは問いません。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 保険
- 有価証券 など
ただし、結婚前から持っていた財産や、親から相続した財産(特有財産)は分与の対象外です。
離婚時の財産分与については下記で詳しく解説しています。あわせてチェックしてみてください。
関連記事:離婚時の財産分与はどうなる?家や貯金の分け方・手続きの流れを弁護士が解説
ステップ3|離婚協議書を作成し公正証書にして残す
話し合いで合意した内容は、必ず書面に残さなければなりません。
単なる夫婦間の離婚協議書でも有効ですが、将来の支払いを確実にするためには、公証役場で「公正証書」を作成しましょう。
公正証書の最大のメリットは、裁判をせずに強制執行ができる点です。
単に当事者で合意をした場合、強制執行をするにはその合意を巡って裁判を起こし、判決や和解調書を取得しなければなりません。
養育費や慰謝料の支払いについて、「支払いを怠った場合は直ちに強制執行に服することを承諾する」という「強制執行認諾文言」を記載しておくことで、万が一支払いが滞った際に、裁判を起こすことなく、相手の給与や預貯金などを差し押さえることが可能です。
これは相手方への強力な心理的圧力となり、不払いを未然に防ぐ効果も期待できます。
作成には、合意内容に応じた手数料(数万円程度)がかかりますが、将来の安心を確保するための重要な投資と考えるとよいでしょう。
ステップ4|離婚届を準備し、提出する
全ての条件について合意し、公正証書の作成が完了したら、最後に離婚届を準備します。離婚届の用紙は、全国どこの市区町村役場でも入手可能です。
協議離婚の場合、成人2名の証人による署名が必要です。親権者の欄など、記載事項を戸籍謄本で確認しながら正確に記入しましょう。
なお、従来は本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には戸籍謄本が必要でしたが、法改正により2024年3月1日から、本籍地以外の役所に提出する場合でも、原則として戸籍謄本の添付は不要です。(参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行))
合意形成ができたら、離婚を法的に成立させるため、記入済みの離婚届を市区町村役場に提出します。



これが受理された時点で離婚は成立します。
子連れ離婚成立後に必要な手続きの順番【4ステップ】
離婚協議を終え、法的に離婚が成立した後も、新生活を始めるためには数多くの行政手続きが必要です。これらの手続きは互いに関連していることもあるため、正しい順番で進めましょう。
例えば、戸籍の変更が完了していないと、ひとり親向けの公的支援の申請ができないなど、後続の手続きに支障が出ることがあります。
以下の順番に沿って、ひとつずつ着実に進めていきましょう。
ステップ1|戸籍・氏の変更や、転居に伴う手続きを行う
婚姻時に氏を変えた側は、原則として「婚姻前の戸籍に戻る」か「自分自身を筆頭者とする新しい戸籍を作る」ことになります。
子どもを自身の新しい戸籍に入れ、同じ氏を名乗らせるためには、以下の手続きが必要です。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得る
- 裁判所の許可を得た後、役所に「入籍届」を提出する
離婚届を提出しただけでは、子どもの戸籍や氏は自動的に変わらない点に注意しましょう。子どもを自分自身の戸籍に入れるためには、新しい戸籍を作ることが必須です。
また、転居を伴う場合は、以下の届け出も必要です。
| 状況 | 転居に伴い必要な届け出 |
|---|---|
| 転居により市区町村が変わった場合 | 旧住所地で「転出届」、新住所地で「転入届」を提出する |
| 転居しても市区町村が変わらない場合(同じ市区町村内で引っ越す場合) | 役所に「転居届」を提出する |
転居しない場合でも、ご自身が世帯主になるための「世帯変更届」が必要になることがあるため、あらかじめ役所に確認しておくことをおすすめします。
ステップ2|健康保険・年金など社会保険の手続きを進める
戸籍の手続きと並行して、生活に直結する社会保険関連の手続きを進めます。
健康保険については、元配偶者の扶養に入っていた場合、資格を喪失するため、以下の手続きが必要です。
- 元配偶者の勤務先から「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう
- 役所で、ご自身の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する手続きを行う
また、年金も同様に、第3号被保険者だった方(夫が会社員で厚生年金に加入もしくは公務員で共済年金に加入し扶養されていた)は、第1号被保険者(国民年金)への種別変更手続きが必要です。
ステップ3|子どもの学校・保育園・住民票の異動など生活環境を整える
次に子どもの生活環境を整える手続きを進めます。たとえば、公立の小中学校を転校する場合は、以下の手続きが必要です。
- 在籍している学校に転校する旨を伝え、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取る
- 新しい住所地の役所で転入手続きを行い、「転入学通知書」の交付を受ける
- これらの書類を新しい学校に提出する
保育園や幼稚園の転園手続きは、自治体によって大きく異なります。ひとり親家庭は入園の優先度が高くなることが多いですが、待機児童が多い地域ではすぐに入園できない可能性もあるでしょう。
離婚後の就労に不可欠なため、準備段階から役所に相談し、早めに手続きを進めることが肝心です。
ステップ4|児童扶養手当や医療費助成など支援制度を申請する
生活基盤が整ったら、最後に経済的支援を受けるための申請手続きを行います。
「児童扶養手当」や「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」などの申請を、お住まいの市区町村役場の担当窓口で行いましょう。
申請には、離婚の事実が記載された新しい戸籍謄本、申請者と子どものマイナンバーが分かる書類、所得証明書、申請者名義の預金通帳などが必要になる場合があります。



必要な書類は制度や自治体によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
子連れでの離婚協議の手続きが難航したらどうすればいい?
当事者間の話し合いだけで離婚条件がまとまらない場合、法的な手続きに移行することになります。感情的な対立が激化する前に、次のステップを検討しましょう。
離婚調停を申し立てる
第一の選択肢は、家庭裁判所での「離婚調停」です。
調停は、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら、合意形成を目指す話し合いの手続きです。
直接相手と顔を合わせる必要がなく、中立的な第三者が関与することで、冷静な議論が進みやすくなります。
裁判所の「令和6年司法統計年報(家事編)」によれば、令和5年中に終局した離婚調停事件35,720件のうち、調停が成立したケースは15,476件、協議離婚の届出をすることで終局したケースは14,628件と、約84%のケースで合意に至っています。
子連れでの離婚協議がまとまらない場合は、調停による解決を目指しましょう。
関連記事:離婚調停は弁護士に依頼すべき?費用相場や相談タイミングを専門家が徹底解説
調停でもまとまらないなら離婚訴訟を提起する
調停でも合意に至らない場合は、最終手段として「離婚訴訟(裁判)」を提起することになります。
訴訟では、当事者の主張や証拠に基づき、裁判官が法的な判断を下します。
手続きが複雑で、解決までに1年から2年程度の期間を要することもあり、弁護士のサポートが不可欠です。費用も調停に比べて高額になります。
離婚裁判については下記の記事でも詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
弁護士法人アクロピースでは、離婚問題に精通した弁護士が、あなたと子どもの明るい未来のために親身に対応いたします。
初回60分の無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
子連れ離婚の手続きで失敗しないための注意点
子連れ離婚は、子どもの人生に大きな影響を与える決断です。後悔しないために、手続きを進める上で特に注意すべき点は以下の2つです。
子連れ離婚をできるだけ円満かつスムーズに進めるためにも、本章の内容を頭に入れておきましょう。
子どもの気持ちに配慮して離婚を伝える
離婚は親の都合ですが、最も影響を受けるのは子どもです。離婚の事実を伝える際は、子どもの年齢や発達段階に応じて、最大限の配慮が求められます。
離婚について子どもに伝える際に重要なのは以下の3つです。
- 可能であれば父母がそろって伝えること
- 離婚は「あなたのせいではない」と明確に伝えること
- 「パパもママも、あなたのことを愛している気持ちは変わらない」と繰り返し伝えること
また、子どもの年齢に応じた伝え方も考慮する必要があります。
例えば、幼児期(3~5歳)の子どもには、「パパはお仕事で遠くに行く」など、子どもが理解しやすい言葉で説明し、「いつでも会える」という安心感を与えてあげることが大切です。
小学生や中学生の場合、離婚についてある程度理解できる場合もあります。今後の生活がどう変わるのか(どこに住むか、転校するかなど)を具体的に話しましょう。ただし、親に心配をかけまいと本心を隠すことがあるため、子どもの気持ちや意見を真摯に聞き、尊重する姿勢が大切です。
また、どの年齢であっても、相手の悪口を言うのは絶対に避けるべきです。子どもにとっては、どちらも大切な親であることに変わりはありません。
話し合いがまとまらないときは早めに弁護士へ相談する
当事者同士の話し合いが行き詰まったとき、それを放置すると感情的な対立が深まるばかりです。
弁護士への相談は、相手を攻撃するためのものではなく、対立状態を打開し、前向きな解決策を見出すための有効な手段といえるでしょう。
法的な専門家が第三者として介入することで、感情論ではなく、法的な論点に基づいた冷静な交渉が可能になります。



これにより、無用な争いを避け、子どもへの影響を最小限に抑えながら、早期の解決を目指せるでしょう。
関連記事:離婚の弁護士費用はいくら?相場や内訳・払えない場合の対処法を弁護士が解説
子連れ離婚で見落としがちな役所・学校関連の手続き
子連れ離婚後の手続きには、戸籍変更以外にも見落としがちなものが多くあります。特に見落としがちな役所・学校関連の手続きの例とそのリスクは以下のとおりです。
| 子連れ離婚で見落としがちな手続きの例 | リスク |
|---|---|
| パスポート・運転免許証・銀行口座など「名義変更」の手続き | 自分の運転免許証や銀行口座の名義が旧姓のままだと、本人確認ができず金融取引や契約に支障が出る |
| 生命保険・学資保険の「契約者・受取人」の変更手続き | 万一の際に子どもへお金が渡らないなどのトラブルの可能性がある |
| 学校・習い事の「緊急連絡先」の更新 | 子どもの急な怪我や病気の際、保護者への連絡が遅れる可能性がある |
| 携帯電話や公共料金などの「契約者名義・支払情報」の確認 | 支払いを元配偶者の名義や口座にしたままだと、サービスが突然停止される、不要な金銭トラブルの原因などになりかねない |
これらの手続きを失念すると、手続きがスムーズに進まなかったり、将来的なトラブルが発生する原因になったりすることもあります。



離婚後の新生活を円滑にはじめるためにも、これらの細かい手続きを見落とさないよう注意しましょう。
子連れ離婚の手続きは弁護士へ依頼|相談する3つのメリット
子連れ離婚は、手続きが複雑で決めるべきことも多くあります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られるでしょう。
子連れ離婚の手続きは自分一人で進めることも可能ですが、子どもの将来を左右する重要な局面だからこそ、弁護士によるサポートを受ける価値があります。
本章を参考に、子連れ離婚の手続きを弁護士に依頼すべきかどうかを検討してみてください。
有利な条件で離婚できる可能性が高まる
離婚条件の交渉では、法的な知識の有無が結果に影響する場合も少なくありません。
弁護士は、法律と過去の裁判例に基づき、獲得できる可能性のある養育費や財産分与、慰謝料の適正額を算出します。
相手方が不当に低い金額を提示してきた場合でも、法的な根拠をもって交渉し、増額を求めることが可能です。
弁護士に依頼することで有利になりやすい主なポイントは、以下の3つです。
| 有利に進められるポイント | 弁護士に依頼するメリット |
|---|---|
| 養育費の算定 | 裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を基準としつつも、私立学校の学費や特別な習い事の費用などを加味した交渉を行う |
| 財産分与 | 相手が隠している可能性のある財産を調査し、全ての共有財産を洗い出した上で、公平な分配を主張できる |
| 慰謝料 | 事実関係に基づいて適正な額を算出し、相手に請求ができます。 |
専門的な知識と交渉力を持つ弁護士が介入することで、本来得るべき正当な権利を確保し、より有利な条件で離婚を成立させられる可能性が高まるでしょう。
相手との交渉による精神的・時間的負担を大幅に軽減できる
離婚協議は、精神的に大きなストレスを伴います。特に、相手との関係が悪化している場合、直接話し合うこと自体が苦痛であり、感情的な対立から冷静な議論ができないことも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、代理人として、相手方との交渉や書面のやり取りを全て代行してもらえるのがメリットです。
相手と直接対峙する精神的な負担から解放され、心穏やかに日常生活を送れるようになるでしょう。
また、複雑な法的手続きや書類作成、裁判所への出廷なども弁護士に任せられるため、仕事や育児に専念する時間を確保できます。
精神的・時間的な負担の軽減は、新しい生活へ向かうための大きな支えとなるでしょう。
将来のトラブルを防ぐ法的に有効な書類を作成できる
離婚時の合意内容は、トラブルを防ぐために、法的に不備のない形で書面化することが極めて重要です。
特に、養育費の支払期間や面会交流の具体的なルールなど、長期にわたる取り決めは、曖昧な表現を避け、明確に定めておく必要があります。
弁護士は、相手方との合意内容に基づき、将来起こりうる様々な事態を想定した上で、抜け漏れのない「離婚協議書」や「公正証書」の原案を作成できます。
例えば、契約書には下記のような内容を盛り込むことができます。
- 養育費の支払いが滞った場合に備え、強制執行を可能にする条項
- 子どもの進学時にかかる学費の具体的な負担割合や支払い方法
専門家ならではの視点で、あなたと子どもの未来を守るための万全な契約書を作成してもらえるでしょう。



弁護士に手続きを任せることで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、離婚後も安心して生活を送れるのがメリットです。
弁護士法人アクロピースでは、離婚問題に精通した弁護士が、あなたと子どもの明るい未来のために親身に対応いたします。
初回60分の無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
子連れ離婚の手続きの順番に関するよくある質問
子連れ離婚をするにはまず何をすればいいですか?
まず着手すべきは、離婚後の生活設計です。具体的には、以下の準備を行いましょう。
- 収入と支出を洗い出し、経済的に自立できるかのシミュレーションを行う
- 仕事や住居の確保に目処をつける
- 利用できる公的支援制度を調べる
離婚を切り出して交渉を始める前に、自分と子どもの生活基盤が安定する見通しを立てることで、冷静な判断ができるようになります。
この準備が整ってから、親権や養育費といった具体的な離婚条件の希望を整理し、相手との話し合いに臨むのが適切な順番といえるでしょう。
公正証書と離婚届はどちらを先に提出すべきですか?
公正証書を作成してから離婚届を提出しましょう。
離婚届は、全ての離婚条件について夫婦間で合意が成立し、その内容を公正証書として作成した後に提出することが重要です。
先に離婚届を提出してしまうと、相手がその後の養育費や財産分与の話し合いに真摯に応じなくなるリスクがあります。
法的に離婚が成立した後では、交渉力が著しく低下してしまうため「離婚条件の合意→公正証書の作成→離婚届の提出」の順番を必ず守りましょう。
子連れ離婚において養育費の取り決めが後回しになるとどうなる?
養育費の取り決めを後回しにして離婚することは、絶対におすすめできません。
離婚後に養育費を請求することは可能ですが、相手が話し合いに応じない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があり、時間も手間もかかります。
さらに、離婚して時間が経つと、相手の連絡先が分からなくなったり、再婚して支払いを拒否されたりするケースも少なくありません。
養育費は子どもの健やかな成長に不可欠な権利です。
離婚時に必ず金額、支払期間、支払方法を明確に取り決め、それを公正証書に残しておくことが、将来にわたる安定した受け取りを確保する上で最も重要です。
子連れ離婚で親権はあとから変更できますか?
親権者を後から変更することは、法的には可能ですが、非常に困難です。
親権者の変更は、父母間の合意だけではできず、家庭裁判所に「親権者変更調停・審判」を申し立て、裁判所の許可を得る必要があります。
裁判所が親権者変更を認めるのは、親権者による虐待や育児放棄がある、あるいは親権者が重い病気で養育が不可能になったなど、「子の利益のために変更が必要である」と判断される極めて例外的なケースに限られます。
「相手の再婚が気に入らない」「自分の方が経済的に豊かになった」といった親の都合による変更は、まず認められません。



離婚時にどちらが親権者となるかは、極めて慎重に決定する必要があります。
まとめ|子連れ離婚の手続きや順番に悩んだら弁護士に相談しよう
子連れ離婚を成功させるためは、感情に流されず、適切に準備を行った上で、正しい手順で進めることが大切です。
しかし離婚手続きは複雑で、一つひとつの判断が自分だけでなく子どもの将来にも大きな影響を及ぼします。
法的な知識がないと、本来得られるはずの権利を見過ごしてしまったり、将来のトラブルの種を残してしまったりするリスクがあります。
自分と子どもの未来を守り、最善の形で新しいスタートを切るためにも、子連れ離婚の手続きの進め方や条件交渉は一人で悩まず、弁護士に相談しましょう。
専門家である弁護士は、状況に合わせた最適な戦略を提示し、精神的な負担を軽減しながら、有利な条件での解決を力強くサポートします。
子連れ離婚に関するあらゆるお悩みは、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は、相談実績1000件以上の高い専門性を持っております。
初回60分の無料相談で、あなたに最適な解決策をご提案します。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応