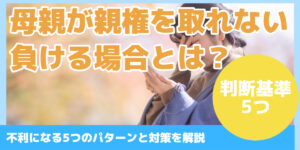養育費の未払いはどうすべき?回収手順や注意点を公正証書の有無別に解説【弁護士監修】

「養育費を支払うと離婚時に約束したのに支払われない」
「請求したくても、どう手続きすればいいのかわからない」
養育費の未払い問題で悩んでいる方は、このような不安を抱えているのではないでしょうか。
養育費の未払いは、子どもの生活や教育に直結する重要な問題です。
しかし、罰則がないことから放置されがちで、回収を諦めてしまう人も多く見られます。実際に取り決めをしても未払いが続いたり、最初から取り決め自体をしていなかったりするケースも少なくありません。
本記事では、養育費の支払い問題の実態や原因、法的な請求手続きの概要を詳しく解説します。
正しい知識を身に付け、確実に支払いを受けるための具体的な行動を整理しましょう。
養育費の未払い問題で悩んでいる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
離婚問題に関する相談件数1,000件以上の実績を活かし、養育費の最適な回収方法を提案いたします。
お子さまの権利を守るため、まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
養育費の未払い問題に関する基礎知識
養育費の未払い問題は、離婚後の子どもの生活や教育における深刻な社会問題の一つです。
法的には支払い義務が明確に定められているものの、実際には取り決めが曖昧なまま放置されることも少なくありません。
まずは、最新の統計データから養育費の未払い問題の実態や起こってしまう背景を理解しましょう。
養育費を受給している割合は全体のうちわずか28.1%
令和3年全国ひとり親世帯等調査によると、養育費を実際に受け取っている母子世帯の割合は、全体のうちわずか28.1%です。
同調査で「養育費を受けたことがない」と回答した人は56.9%に上り、未払い問題は依然として深刻な状況です。(参照:厚生労働省|令和3年全国ひとり親世帯等調査)
その背景には、支払い義務者の経済的困窮や生活環境の変化、支払いへの意識の低さなどが挙げられます。
養育費は、離婚後の子どもの生活と教育を支えるために支払うものです。
何らかの理由で支払いが滞った場合、子どもの生活基盤を整えられなくなったり、進学や習い事などの教育機会を失ったりする恐れがあります。
子どもの未来と生活を守るためにも、元配偶者との間で起きている養育費の未払い問題は放置せず、早めに対策を考えることが大切です。
そもそも養育費の取り決めをしていないケースが多い
養育費の未払いが多数発生する背景には、離婚時にそもそも養育費の取り決め自体をしていない家庭が多いことが関係しています。
厚生労働省の調査では、母子世帯の半数以上(51.2%)が養育費の取り決めをしていません。
取り決めをしない背景には、以下のように感情的な対立や相手への不信感など、複数の要因が関係しています。
| 取り決めをしていない主な理由 | 割合 |
|---|---|
| 相手と関わりたくない | 50.8% |
| 相手に支払う意思がないと思った | 40.5% |
| 相手に支払う能力がないと思った | 33.8% |
| 相手から身体的・精神的暴力を受けた | 15.7% |
| 取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった | 14.6% |
このように「元配偶者と関わりたくない」といった心理的な要因や、「相手に支払う意思・能力がないと思った」という諦めが取り決めを妨げています。
取り決めをしないまま離婚すると、後から請求しても「約束していない」と拒否される可能性があります。
養育費を継続的に受け取るには、取り決めをした内容を離婚協議書や公正証書といった形で書面にすることが不可欠です。
養育費の未払いに罰則は科されないがペナルティはある
養育費の未払い自体に、刑事罰(懲役や罰金など)は設けられていません。
しかし、未払いに関する法的手続きを無視した場合には、刑事罰や行政罰(過料)といったペナルティが科される可能性があります。
| 手続きを無視するケース | 科される可能性のある罰則 | 根拠法 |
| 財産開示命令に応じない | 6カ月以下の拘禁または50万円以下の罰金 | 民事執行法|第213条 |
|---|---|---|
| 正当な理由なく調停に出頭しない | 5万円以下の過料 | 民事調停法|第34条 |
| 家庭裁判所の履行命令に従わない | 10万円以下の過料 | 家事事件手続法|第290条5項 |
財産開示命令とは、強制執行(差し押さえ)のために、支払い義務者の資産状況(給与や預金など)を裁判所に提示させる手続きです。
また、養育費の支払いを怠った場合には以下のような法的なペナルティが課されます。
- 給与・預金などの財産の差し押さえ
- 遅延損害金の発生による最終的な支払い総額の増加
このように、刑事罰がなくても、法的手段によって支払いが強制されたり、金銭的な負担が増えたりする可能性があります。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫「どうすれば養育費を払ってもらえるのか」と悩んでいる方は、未払いの経緯や金額を整理し、家庭裁判所や専門家に相談して取れる手段を確認しましょう。
養育費の未払い問題で悩んでる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。相手方との直接交渉による精神的負担を軽減し、あなたの代理人としてどう対応すべきかを共に考えてまいります。
60分の初回無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
養育費の未払いがあるときはどうすればいい?
過去の養育費の未払い分は、過去の時点で請求意思を明示していれば、その時点からの分を法律に基づいて元配偶者に請求可能です。
また、法的に問題を解決するには「債務名義」の有無が重要です。
ここでは未払い分の養育費を請求できる根拠や、法的に解決するために必要な「債務名義」について解説します。
未払い分の養育費は元配偶者に請求できる
離婚後に養育費が支払われていない場合でも、元配偶者に対して正当な請求を行うことは可能です。ただし、請求できるのは原則として請求意思を示した時点からの分となります。
養育費の支払いは、親が子どもに対して負う扶養義務に基づいています。離婚によって夫婦の関係は解消されても、親子関係や扶養義務は消滅しません。
民法第766条1項では、離婚の際に父母が「子どもの監護に要する費用の分担」を協議によって定めることが明記されています。
したがって、養育費の未払いが発生した場合、元配偶者に対して支払いを請求することが可能です。
まずは過去の取り決め内容や支払い記録を整理し、どの段階から手続きを進めるべきかを確認しましょう。
養育費の未払い問題を法的に解決するには「債務名義」が必要
養育費の未払い問題を法的に解決するには「債務名義(さいむめいぎ)」が不可欠です。
債務名義とは、強制執行ができる権利の存在や範囲を公的に証明した文書です。具体的には以下のようなものが当てはまります。
- 強制執行認諾文言付き公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 確定判決
債務名義があれば、家庭裁判所の手続きを省略し、相手の給与や預金を差し押さえる「強制執行」が可能です。
ただし、離婚時に公正証書を作成していない場合や、作成した公正証書に強制執行認諾文言がなければ、すぐに強制執行はできません。



その場合は家庭裁判所での手続きにより、債務名義を取得した上で強制執行を行う必要があります。
【債務名義がある場合】養育費の未払い問題を解決する3つの法的手続き
養育費の未払い問題を解決するには、「債務名義」があるかどうかで取れる手続きが大きく異なります。ここでは、債務名義がある場合の養育費回収手続きについて解説します。
実務上、弁護士が介入している場合、内容証明郵便の送付や履行勧告・履行命令の申し立てを省略し、強制執行(差し押さえ)に進むのが一般的です。
早期解決を目指すためにも、具体的な手続き内容を確認しながら請求を進めましょう。
内容証明郵便で支払いを正式に催促する
養育費の未払いが発生した場合、先に内容証明郵便を送付するケースもあります。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・どのような内容の文書を相手に送付したかを郵便局が公的に証明する制度です。内容証明には、以下の項目を明確に記載しましょう。
- 未払いとなっている養育費の総額
- 支払期限
- 振込先
- 「期限までに支払いが確認できない場合は、公正証書に基づき直ちに強制執行手続きに移行する」旨の文言
これにより、相手に支払いの意思を確認しつつ、法的対応を示すプレッシャーを与えられます。
内容証明郵便の送付手続きは、内容証明を扱っている郵便局でのみ受け付け可能です。(参照:日本郵便株式会社|内容証明)差し出す際は、以下を用意して郵便局の窓口に提出しましょう。
- 内容文書の謄本(コピー)3通
- 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
- 郵便料金(内容証明の加算料金480円を含む)
内容証明の送付手続きに対応している郵便局や詳しい差出方法は、郵便局のホームページにてご確認ください。
家庭裁判所に履行勧告・履行命令を申し立てる
債務名義が以下の書類である場合は、家庭裁判所に履行勧告または履行命令を申し立てます。
- 調停調書
- 審判書
- 確定判決
履行勧告とは、家庭裁判所が養育費の支払い義務者に対して「速やかに支払うよう勧告する制度」です。
費用はかからず、手続きが簡単なため、まずはこちらを利用しましょう。
履行勧告の申し立てを行うと、家庭裁判所の調査官が義務者へ直接連絡し、支払いを促すことになります。(参照:裁判所|履行勧告手続等)
【補足】履行勧告でも支払いに応じない場合
履行勧告でも支払いに応じない場合「履行命令」を申し立てます。
履行命令とは、裁判所が正式に養育費の支払いを命じるものです。命令に従わない場合、相手に10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
履行命令は、強制執行に移行する前の「最後の警告」のような位置づけで、相手に大きな心理的プレッシャーを与えます。
ただし、この段階では、裁判所が直接的に財産を差し押さえたり支払いを強制したりする力はありません。
「履行命令」は、あくまで義務者が自発的に支払う意思があるかを見極めるための段階と捉えましょう。
強制執行で給与や預金などを差し押さえる
履行勧告や履行命令を経ても養育費の支払いがない場合、最終手段として強制執行(差し押さえ)の手続きに進みます。
なお、公正証書に「強制執行認諾文言」が記載されていれば、裁判を起こさずに相手の財産を直接差し押さえることが可能です。
差し押さえの対象になる財産には、以下のようなものがあります。
- 給与(養育費の場合原則手取り額の2分の1まで)
- 預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 自動車・骨董品などの動産
- 生命保険(解約返戻金相当額)
養育費の請求のために相手の給与を差し押さえの対象とする場合、原則として手取り額の2分の1までが上限です。
給与の差し押えは、相手が勤務先を退職しない限り、継続的に養育費を回収できる強力な手段とされています。
ただし、勤務先や銀行口座など、相手の財産情報を把握していなければ強制執行を進められません。
財産調査では、民事執行法第197条で定められた財産開示手続を利用できます。(参照:裁判所|財産開示手続)
養育費確保のための強制執行の実行には、専門的な判断が求められます。



スムーズに進めたい場合は弁護士へ相談し、確実な回収方法を検討しましょう。
養育費のトラブルを弁護士に相談すべきかどうか迷っている方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:養育費のトラブルは弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用相場・選び方を解説
【債務名義がない場合】養育費の未払い問題を解決する2ステップ
以下のようなケースでは債務名義が無いため、養育費の未払いがあってもすぐに強制執行はできません。
- 離婚時に公正証書を作成していない
- 公正証書に強制執行認諾文言が付記されていない
- 「調停調書」「審判書」「確定判決」などがない
上記のケースに該当する場合、まずは家庭裁判所の「養育費請求調停」や「審判」といった手続きで債務名義を取得する必要があります。
これらの手続きを踏むことで、初めて給与や預金の差し押さえなどの強制執行が可能になるのです。
債務名義がない場合に取るべき2つのステップを順に解説します。
法的な手続きの根拠を確認し、未払いの養育費を確実に回収する道筋を立てましょう。
家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる
公正証書などの「債務名義」(強制執行の根拠となる書類)がない場合、まず家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。
ここで当事者の合意が成立すれば「調停調書」が作成されるため、養育費の支払いが滞った場合には強制執行(差し押さえ)が可能になります。
| 用語・手続き | 概要 |
| 養育費請求調停 | 裁判所が間に入り、裁判官や調停委員を交えて養育費の金額や支払い方法を話し合い、双方の合意を目指す手続き。 (参照:裁判所|養育費請求調停) |
|---|---|
| 調停調書 | 「債務名義」となり、これに基づいて強制執行(差し押さえ)が可能になる。 |
養育費請求調停を申し立てるには、申立書や収入印紙などの必要書類を用意し、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所への提出が必要です。
提出先は元配偶者と話し合って決めた家庭裁判所でも構いません。
もし相手が調停に出席しない場合や話し合いがまとまらない場合は、次の審判手続きへ移行します。
審判を得て強制執行に移行する
調停で合意が得られなかった場合や相手が調停に出席しない場合は、家庭裁判所による審判に移行します。
審判では、双方の収入や生活状況、子どもの年齢などを考慮して、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定する流れです。
審判で決まった内容は、確定審判書として残り、判決と同様の効力を持っています。審判書は「債務名義」として残り、強制執行の手続きに進むための法的な根拠となります。
債務名義を取得した後は、給与・預金・不動産などの差し押さえが可能です。
ただし、審判の手続きは法律的な要素が多く、養育費請求に関する主張の整理や証拠提出が求められる場面もあります。



強制執行を自力で進めるのは難易度が高いため、離婚問題に強い弁護士への依頼も検討しましょう。
未払いの養育費請求は弁護士なしでも可能?
養育費の未払い請求は、弁護士に依頼せず進めることも可能です。
弁護士を介さず養育費請求をするメリットは、費用を抑えながら請求準備を進められる点です。ただし、法的知識が求められる場面も多く、スムーズに準備が進まないデメリットもあります。
ここでは、弁護士なしで養育費を請求する際のメリットとデメリットを比較しながら、どのような場合に弁護士を依頼すべきかを整理します。
本項を参考に、自分で請求手続きを進められるのか、弁護士と連携しながら準備すべきかどうかを考えましょう。
未払いの養育費請求を弁護士なしで進めるメリット
未払いの養育費請求を弁護士なしで進めるメリットは、弁護士費用を節約できる点です。
自分で養育費請求を行った場合、弁護士依頼で発生する着手金や成功報酬(一般的に回収額の10〜20%)はかかりません。また、回収できた養育費は(実費を除き)そのまま受け取れます。
ただし、弁護士なしで進める場合でも、申し立てに必要な収入印紙代や郵便切手代などの実費は発生します。
離婚時の取り決め内容が書面で残っており、未払いの証拠がそろっている場合は、弁護士なしでも有利に進めやすいでしょう。
弁護士に依頼する場合の費用については、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:養育費のトラブルは弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用相場・選び方を解説
未払いの養育費請求を弁護士なしで進めるデメリット・注意点
未払いの養育費請求を自分で進めるデメリットは、手続きや主張立証(法的な主張と証拠の提出)をすべて自分で行わなければならない点です。
これには、以下のような負担やリスクが伴います。
| デメリットの種類 | 具体的な内容・リスク |
| 手続き・知識の負担 | 裁判所への書類作成、証拠の整理、法的な主張の準備を自力で行う必要がある。 |
|---|---|
| 時間・スケジュールの負担 | 裁判所は平日の日中に開廷するため、仕事をしている人は出廷や準備の負担が大きくなりやすい。 |
| 交渉・主張の不利 | 相手に弁護士がいる場合、法律知識や手続きの差が裁判の結果に影響しやすい。 |
| 強制執行の困難 | 差し押さえ(強制執行)に必要な相手の勤務先や銀行口座を自力で特定するのは困難。 |
| 精神的な負担 | 元配偶者と直接対立するため、感情的なやり取りが長期化し、精神的な負担が大きくなりやすい |
養育費請求を弁護士なしで行う場合は、法律知識がないと対応に時間がかかる場合があります。手続きに不備があれば、やり直しになるケースも少なくありません。
また、相手に弁護士がついている場合、法律の専門知識や手続きの差がそのまま結果に影響する可能性があります。



これらのリスクを避け、養育費を回収する確率を上げるためには、専門家である弁護士への相談を検討しましょう。
養育費の未払いを回収するときの注意点
養育費の未払いを回収する際は、以下の3点に注意して手続きを進めましょう。
確実な回収につなげるためにも、手続きに伴うリスクを正しく把握しておきましょう。
時効に注意して早めに請求手続きを進める
養育費の請求権には消滅時効があり、一定期間が過ぎると法的に請求できなくなります。未払いが発生したら、長期間放置せず早めに手続きを進めましょう。
時効の期間は、養育費の「取り決め方法」によって異なります。
| 取り決め方法 | 時効 | 根拠・備考 |
| 当事者同士の取り決め (口約束、契約書、公正証書) | 支払い期日から5年 | 民法第166条1項に基づく |
|---|---|---|
| 裁判所の手続き (調停、審判、裁判) | 支払い期日から10年 | 既に支払期日が到来した過去の未払い分に適用 |
なお、養育費の取り決めをしていない場合、離婚から何年経過していても請求する権利があります。
しかし、養育費は「請求した時点から」支払い義務が生じると考えられているため、過去にさかのぼって全て受け取るのは困難です。
まずは家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、早めに請求する権利を得ることが重要です。
未回収の養育費は元配偶者の親に原則請求できない(ケースバイケース)
養育費の支払い義務は、子どもに対する親の扶養義務に基づくもので、原則として子どもの父母間のみにあります。
そのため、元配偶者が支払いを怠っていても、その親(子どもにとっての祖父母)に代わりに支払いを命じることは基本的にできません。
ただし、元配偶者の両親が養育費の支払い契約に「連帯保証人」として署名しているようなケースでは、契約上の義務として、例外的に請求が認められる可能性があります。
元配偶者からの支払いが見込めない場合は、まず弁護士に相談し、財産開示請求や強制執行などの法的手段を優先的に検討しましょう。
公正証書などの債務名義がない場合はすぐに強制執行できない
債務名義がない場合は、まず、以下のような方法で債務名義を取得する必要があります。
- 相手と交渉をして公正証書を作成する
- 調停・審判によって調停調書・審判書を取得する
これらの書面がある場合、家庭裁判所を通さずに強制執行の手続きに移行できます。
一方で、取り決めを口約束で行っただけ、あるいはLINEやメールで合意しているだけでは法的効力が認められません。



まずは早めに債務名義の有無を確認し、弁護士と相談しながら取得を目指しましょう。
未払いの養育費の回収に伴い、相手に対して強制執行の実行を検討している方は、まずは弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は、離婚問題の相談実績が1,000件以上と豊富で、状況に応じた最適な回収方法を提案しています。まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
養育費の未払い問題解決に向けた新制度とは?【民法等改正】
養育費の未払い問題は、ひとり親家庭の貧困に直結する深刻な社会課題です。この状況を改善するため、民法などの改正が進められており、2026年5月までに施行予定です。
改正後は、これまで泣き寝入りせざるを得なかった未回収の養育費を受け取れる可能性が高まります。
ここでは、養育費の未払い問題解決に向けた主な新制度のポイントとして、以下3つを解説します。
「法定養育費」の新設により、取り決めがなくても法定額を請求できる
養育費の取り決めがないために泣き寝入りするケースをなくすため、新制度として「法定養育費」が新設されます。
法定養育費の制度は、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、法律で定められた基準に基づき、最低限の養育費を請求可能にするものです。
この制度により、家庭裁判所の手続きを経なくても、取り決めがないという理由だけで養育費の請求を諦める必要がなくなります。
元配偶者との接触を避けたい場合など、養育費に関する協議が難しいケースにおいて、子どもの権利保護を可能にする制度です。(参照:民法等の一部を改正する法律の概要 )
「先取特権」が付与され、養育費の未払いを回収しやすくなる
民法等改正では、養育費の回収の確実性を高めるために養育費債権に「先取特権」が付与される予定です。
先取特権(さきどりとっけん)とは、債務者に複数の債権者がいる場合に、他の債権よりも優先して弁済を受けられる権利です。
先取特権が付与されれば、元配偶者が他の借入金などを抱えている場合でも、養育費の回収が後回しにされにくくなります。
また、従来の手続きの課題が改善され、より迅速な差し押さえが可能になる点も期待されています。
| 比較 | 内容 |
|---|---|
| 従来(課題) | 裁判所の判決や調停調書などの「債務名義」が必要で、取得に時間がかかった。 |
| 改正後(想定) | 養育費の取り決めの事実を証明できる書面があれば、より迅速に差し押さえを申請できる見込み。 |
先取特権の付与は、養育費が子どもの生活基盤を整えるために必要な費用である旨を法的に重視し、その回収の確実性を高めるための強力な措置です。(参照:民法等の一部を改正する法律の概要 )
養育費の支払い義務者の財産・給与情報の開示が強化される
養育費請求の強制執行における「相手の財産がどこにあるかわからない」といった問題を解消するため、新制度では財産・給与情報の開示制度が強化される見込みです。
| 比較 | 内容 |
|---|---|
| 従来(課題) | 相手の勤務先や銀行口座を自力で特定できないと、差し押さえの申し立てが困難だった。 |
| 改正後(強化) | 家庭裁判所を通じて、行政機関に照会し、以下の情報を取得できる見込み。 ・勤務先、給与 ・年金 ・不動産 など |
なお、開示請求の対象となる第三者には、金融機関や市区町村が含まれます。(参照:民法等の一部を改正する法律の概要 )



財産・給与情報の開示が強化されることで、強制執行の申し立てに必要な情報の特定が容易になり、未払いの養育費の回収率向上が期待できます。
養育費の未払いで生活が苦しいときに利用できる支援制度
養育費が支払われず、生活が苦しい場合は、以下のような公的支援制度を活用できます。
| 制度 | 実施主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 国(こども家庭庁) | ひとり親世帯で子どもを養育している保護者に支給される手当 |
| 就学援助制度 | 市町村 | 経済的な理由で学校生活に支障がある家庭に対して、学用品費・給食費・修学旅行費などを援助する制度 |
| ひとり親家庭等医療費助成制度(自治体によって名称が異なる) | 自治体(都道府県・市町村) | ひとり親家庭の保護者と子どもの医療費の自己負担分を助成する制度 |
| 生活福祉資金貸付制度 | 都道府県社会福祉協議会 | 低所得世帯が生活資金や教育資金を一時的に借りられる制度(返済が必要) |
これらの制度を併用することで、一時的に生活を安定させながら法的手続きを進めることが可能です。自治体によって条件が異なるため、早めに市区町村の福祉課に相談してみましょう。
養育費の未払いに関するよくある質問
養育費を差し押さえるまでに何ヶ月かかりますか?
差し押さえまでの期間は「債務名義」(強制執行認諾文言付きの公正証書や調停調書など)の有無で大きく異なります。
債務名義が既にある場合は、申し立てから1〜3ヶ月程度が差し押さえまでの目安です。
債務名義がない場合は、まず家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる必要があり、この手続きに半年から1年程度かかります。
養育費が未払いのまま相手が死亡したらどうなりますか?
支払い義務者が死亡した場合、将来の養育費の支払い義務は、扶養義務が本人固有のもの(一身専属)であるため原則として消滅します。
しかし、死亡前に既に発生していた「過去の未払い分」は、故人の金銭債権(借金)として扱われます。
そのため、この未払い分については、元配偶者の相続人に請求できる可能性があります。
ただし、請求には法的な判断や相続人との交渉が必要になるため、まずは弁護士に相談して対応を確認しましょう。
養育費を強制執行するデメリットは何ですか?
養育費の強制執行をしても、未払いの養育費を必ず回収できるとは限らない点はデメリットです。相手の資産や収入の状況によっては、差し押さえる金銭そのものが無いケースも考えられます。
また、強制執行申し立ての手続きは専門的で、ご自身で行うには多くの手間と時間がかかる点もデメリットといえます。
養育費回収の可能性を上げるためにも、実行する際は事前に弁護士に相談し、慎重に検討しましょう。
まとめ|養育費の未払い問題に悩んだら信頼できる弁護士に相談しよう
養育費の未払い問題は、ひとり親家庭の生活や子どもの将来に直結する深刻な課題です。
取り決めをしていても支払いが滞るケースは多く、放置すると時効によって回収できなくなる可能性があります。
未払いの養育費を回収するには、債務名義の有無に応じた複雑な法的手続きや、時効に配慮した迅速な行動が不可欠です。
ご自分で手続きを進めることも可能ですが、複雑な法的手続きを正確かつ迅速に進めるには、離婚問題に強い弁護士に相談するのが最も確実です。
専門家の力を借りることで、子どもの生活を安定させるための一歩を踏み出せます。
弁護士法人アクロピースでは、養育費の未払い請求や強制執行のサポートをはじめ、相手方との交渉・調停対応まで対応しております。
初回60分の無料相談も実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応