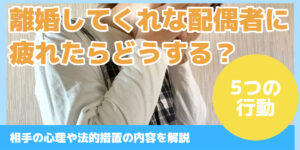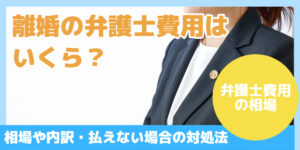離婚の手続きは何からするべき? 離婚までの流れや必要書類、注意点を弁護士が解説
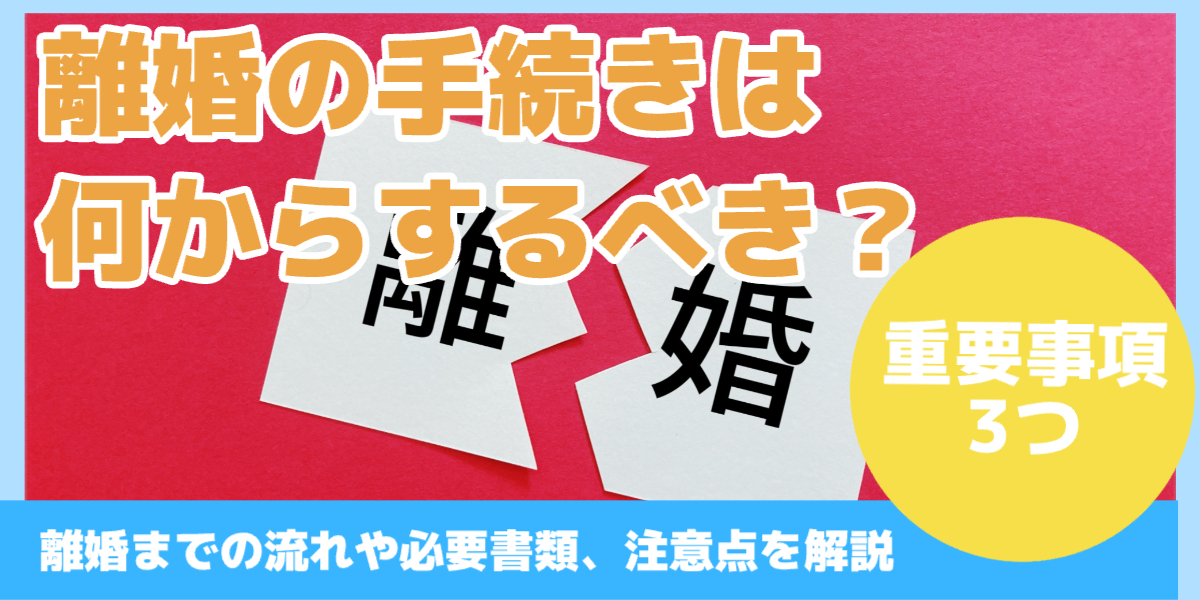
「離婚を決意したが、何から手をつければいいかわからない」
「手続きが複雑そうで、不利な条件にならないか不安」
このような不安や疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
離婚の手続きは、人生の大きな岐路であり、非常に複雑です。進め方を間違えると、財産分与や養育費などで大きな損をしたり、必要以上に時間がかかって精神的に消耗したりするリスクがあります。
この記事では、離婚手続きの全体像から、事前に決めるべき重要事項、離婚後の手続きまで、網羅的に解説しています。
離婚に関する不安を解消し、ご自身の状況で何をすべきか検討するときの参考にしてください。
離婚手続きでお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は相談件数1,000件以上の実績を活かし、あなたに合った解決策をご提案いたします。
一人で悩まず、まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
まず知っておきたい離婚手続きの全体像【3ステップ】
離婚の手続きは、大きく「準備」「離婚の成立」「離婚後の手続き」の3つのステップに分けられます。
全体像を把握することで、今自分がどの段階にいるのかを冷静に判断でき、計画的に進めることができます。
離婚前の準備
離婚を相手に切り出す前に、必ず済ませておくべき準備があります。感情的に行動するのではなく、冷静に情報を整理し、証拠を集めることが、後の交渉を有利に進める鍵となります。
- 夫婦の共有資産の把握
- 財産分与に必要な証拠収集(通帳のコピーや残高証明書など)
- 親権に関する自分の希望(親権をどちらが持つか、養育費、面会交流など)
まずは、財産・預金・年金など夫婦で築いた共有資産を正確に把握しておくことが重要です。
相手名義の財産も財産分与の対象になるため、通帳のコピーや残高証明書などの証拠を集めておきましょう。
子どもがいる場合は、親権をどちらが持つか、養育費や面会交流をどうするか、ご自身の希望を整理しておく必要があります。
もし、DV・モラハラがある場合は、診断書や録音、SNSの履歴といった客観的な証拠を確保してください。
離婚後の生活費、住居、仕事など、具体的な生活設計の見通しを立てておくことが、精神的な安定につながります。
離婚の成立(協議・調停・裁判)
準備が整ったら、離婚を成立させるための具体的な手続きに進みます。
まずは夫婦での話し合い(協議離婚)を検討し、離婚の意思や条件について話し合います。
ここで合意した内容は、必ず離婚協議書などの書面に残すことが重要です。
もし直接の話し合いが難しい場合や、合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、第三者を介して話し合いを進めましょう。
それでも解決できない場合は、最終的に離婚裁判で裁判官に判断を委ねることになります。
一連の手続きにおいて、弁護士が関与すると、複雑な手続きや書類作成の負担が大幅に軽減されます。
離婚後の手続き
離婚届が受理され、法的に離婚が成立した後も、多くの手続きが待っています。これらは期限が定められているものも多いため、迅速な対応が必要です。
- 住民票の異動
- 世帯主変更
- 年金・保険・税金関係の変更・届出
- 子どもの戸籍変更
- 学校関連の手続き
- 児童扶養手当の申請
また、銀行口座やクレジットカード、運転免許証などの名義変更や、引っ越し後の住所変更も忘れずに行わなければなりません。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫離婚後はやらなければならないことが多いため、自分専用のチェックリストを作成して、手続きの漏れを防ぐと良いでしょう。
離婚手続きの4つの方法とは?
離婚を成立させる方法には、主に4つの種類があります。まずはどの方法を目指すのかを決めておくと良いでしょう。
協議離婚|夫婦の話し合いで円満に進める方法
日本の離婚の約9割が、この協議離婚によるものです。協議離婚は夫婦が話し合い、離婚条件に合意して離婚届を提出すれば成立します。
協議離婚で最も重要なのは、慰謝料・養育費・財産分与などの取り決めを、必ず離婚協議書などの合意書で明確化することです。
さらに、この合意書を公証役場で公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書化することで、養育費などの支払いが滞った場合に、裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)が可能になるのです。


調停離婚|話し合いがまとまらない場合の解決方法
調停離婚は夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合に利用する法的手続きです。
家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立書を提出して開始します。
調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を個別に聞きながら調整を図ります。相手と直接顔を合わせずに話し合いを進められるのがメリットです。
調停で合意が成立すると、調停調書が作成されます。この調書があることで、調停で合意したことが守られない場合に地方裁判所に強制執行の申し立てが可能になるのです。


関連記事:離婚調停は弁護士に依頼すべき?費用相場や相談タイミングを専門家が徹底解説
審判離婚|調停不成立でも裁判所に職権で離婚を判断してもらう方法
審判離婚は調停離婚の一種ですが、実務上は非常に稀な手続きです。調停が不成立となった場合でも、裁判所が職権で離婚を命じることがあります。
- 双方が離婚自体には合意しているものの、ごくわずかな条件(例:財産分与の金額)で折り合わない
- 意見がまとまらない
- 一方が調停を欠席し続けている
審判離婚は調停が長期化・形骸化した際、裁判官が審判の形で判断を下すのが相当と判断した場合に適用されます。
審判離婚は家庭裁判所の判断によってなされるものであり、当事者が臨んで審判離婚の申し立てをすることはできません。
離婚の審判が下されても、当事者のどちらかが2週間以内に異議申立てをすると、審判は効力を失います。効力を失った場合、裁判離婚の手続きに移行するのが一般的です。
裁判離婚|最終手段として訴訟で離婚を求める方法
調停でも合意に至らなかった場合、最終手段として訴訟(裁判)を起こします。調停とは異なり、話し合いではなく、裁判官が法に基づいて判決を下します。
裁判で離婚を認めてもらうには、法律で定められた5つの離婚原因(民法|第770条1項)のいずれかが必要です。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由なく同居しないなど)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラ、長期の別居など)
なお、「回復の見込みがない強度の精神病」は2026年5月までに施行される予定の法改正で削除されます。これは、婚姻関係が破綻しているかではなく、「病気であること」自体を離婚原因とすることが問題視されたためです。
裁判離婚は、訴状や証拠を家庭裁判所に提出し、口頭弁論(お互いの主張と証拠の提出)を数回繰り返した結果、裁判官が離婚の可否や条件を決定します。



法的な主張や証拠の整理など、高度な専門知識が必須となるため、弁護士による訴訟代理を依頼することをおすすめします。
関連記事:離婚裁判の流れ!期間や費用など基礎知識を解説
関連記事:婚姻費用分担請求とは?計算方法から手続きの流れ、払わない相手への対処法まで解説【弁護士監修】
離婚手続きでのお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。
離婚問題の経験が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて適切な対処をご提案いたします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ一度相談してみてください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
【準備】離婚手続きをする前に決めておくべき3つの重要事項
離婚届を出す前に、決めておくべき重要な条件が3つあります。
これらを曖昧にしたまま離婚すると、将来的に深刻なトラブルに発展する可能性があります。
お金に関すること(財産分与・慰謝料・年金分割)
離婚後の生活設計に直結する、最も重要な取り決めの一つです。
具体的には、主に以下の3つの項目について、夫婦間でしっかりと話し合い、合意する必要があります。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 財産分与 | 婚姻期間中に夫婦で協力して築いた共有財産(預貯金、不動産、車など)を分けること。 名義に関わらず、原則として2分の1ずつ分ける。 |
| 慰謝料 | 不貞行為やDV・モラハラなど、離婚の原因を作った側が相手に支払う精神的損害の補填。 離婚原因が相手にない場合は請求できない。 |
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金(または共済年金)の納付実績を分割する制度。 |
特に財産分与は、預貯金だけでなく不動産、保険、退職金なども対象となり複雑になりがちです。
これらのお金に関する取り決めは、金額、支払方法、支払期限などを具体的に決定し、書面に明記しておくことが後のトラブル防止につながります。
関連記事:離婚時の財産分与はどうなる?家や貯金の分け方・手続きの流れを弁護士が解説
関連記事:【弁護士監修】財産分与は弁護士に相談すべき?依頼のメリットや費用相場を解説
子どもに関すること(親権・養育費・面会交流)
お子さんがいる場合、その福祉を最優先に決定する必要があります。お金の問題以上に重要なのが子どもの将来に関する取り決めです。
主に以下の3つの点を明確に決めておく必要があります。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 親権 | 未成年の子の身上監護や財産管理を行う権利義務。 離婚届に親権者を記載しなければ受理されない。 |
| 養育費 | 子どもが経済的に自立するまでにかかる生活費や教育費。 裁判所の「養育費算定表」を基準に、双方の収入に応じて決めるのが一般的。 |
| 面会交流 | 子どもと離れて暮らす親が子どもと会う頻度(月1回など)や方法(宿泊の可否、連絡方法など)を具体的に合意しておく。 |
特に親権は、離婚届を提出するまでに必ず決めておかなければなりません。
これらは夫婦間の感情的な対立ではなく、「子どもの健やかな成長にとって何が最善か」を基準に冷静に判断することが重要です。
なお、2026年5月までに施行される予定の法改正により、離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能になる予定です。
書面に関すること(離婚協議書・公正証書)
離婚の条件は、絶対に口約束で済ませてはいけません。口約束には法的な拘束力がなく、後になって「言った・言わない」の深刻なトラブルに発展するケースが非常に多いからです。
お金や子どもに関する重要な取り決めは、証拠として残すことが鉄則です。この準備段階で、「合意した内容はすべて書面にする」ということを強く意識しておきましょう。
具体的には、後述する離婚協議書や、さらに支払いの強制力を持つ公正証書といった形で文書化します。
作成した書面に法的な不備がないか、将来のトラブルの種にならないか、事前に弁護士などの専門家に確認してもらうことも重要です。



「言った言わない」を防ぐため、養育費などお金の合意は、必ず書面に残しておきましょう。
離婚手続きの進め方【協議から離婚届の提出まで】
ここでは、最も一般的な協議離婚の進め方と、離婚届の提出方法について解説します。
協議離婚は、裁判所を利用しない唯一の方法ですが、手順を誤ると将来大きなトラブルの原因となるため、慎重に進める必要があります。
夫婦間での話し合いを行い、離婚の重要条件(親権・養育費・財産分与など)を決定する
離婚手続きの第一歩は、夫婦間での話し合い(協議)です。
これは、単に「離婚したい」という意思を確認するだけでなく、以下についての具体的な条件を決定するための交渉の場です。
- お金(財産分与・慰謝料・年金分割)に関する事項
- 子ども(親権・養育費・面会交流)に関する事項
この話し合いに臨むにあたり、準備段階で作成した財産リストや証拠、ご自身の希望条件をまとめたメモが重要になります。
準備が不十分なまま感情的に「別れたい」とだけ伝えてしまうと、相手も感情的になり、冷静な条件交渉が難航しがちです。
協議の場では感情的にならず、お互いの希望や条件を冷静に提示し、一つずつ合意を目指すことが求められます。
もし相手が威圧的になってしまったり、自分が感情的になってしまったりする場合は、メールや手紙を通じて意見を交換する方法も有効です。
合意内容を書面化する
話し合いで合意した内容は、離婚届を提出する前に書面として残します。
書面にする場合には、夫婦間で協議し合意した内容をまとめたいわゆる離婚協議書と、公証役場で作成する公正証書の形式で作成しましょう。
それぞれの特徴は以下の通りです。
| 書面の種類 | 概要 | 主な効力・特徴 |
| 離婚協議書 | 夫婦間で合意した内容(親権、養育費、財産分与など)をまとめた契約書。 | ・法的な「合意の証拠」となる。 ・これだけでは強制執行(差し押さえ)はできない。 |
|---|---|---|
| 公正証書 | 離婚協議書を基に、公証役場で作成する公文書。 | ・非常に高い証明力を持つ。 ・強制執行認諾文言を付ければ、支払いが滞った際に裁判なしで直ちに給与や財産を差し押さえできる。 |
特に養育費や慰謝料など、将来にわたる金銭の支払いが発生する場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておきましょう。
離婚届を作成し、市区町村役場へ提出する
すべての条件合意と書面化(できれば公正証書化)が完了したら、離婚届を市区町村役場に提出します。
提出先は、夫婦の本籍地、または所在地の役所(住民票がある場所以外でも可)です。
離婚届の提出には以下のものが必要です。
- 離婚届(役所の窓口やウェブサイトで入手可能。成人の証人2名の署名・押印が必須)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
ここで最も注意すべき点は、離婚届が一度受理されると、法的に婚姻関係は即座に終了し、原則として撤回・取り消しができないことです。
もし、相手に勝手に離婚届を出される不安がある場合は、お住まいの市区町村役場に「離婚届不受理申出」を提出しておくことをおすすめします。



すべての条件交渉と公正証書の作成が完了してから、不受理申出を取り下げ、離婚届を提出するのが最も安全な流れです。
【一覧】離婚成立後に必要な手続きとは?
離婚届を提出した後も、新生活のために必要な手続きが数多くあります。期限が設けられているものや、申請しないと受けられない支援もあるため注意が必要です。
主な手続きは以下の4つに大別されます。
| 手続きの分類 | 主な手続きの例 | 特に注意すべき点(期限など) |
| 役所関連 | ・住民票の異動(転入・転居届) ・印鑑登録(旧姓に戻す場合) ・マイナンバーカードの氏名、住所変更 | ・住民票の異動は14日以内の期限あり。 ・他の名義変更の前提となるため優先的に行う。 |
|---|---|---|
| 保険・年金 | ・国民健康保険への加入(または社保加入) ・国民年金の種別変更(第3号被保険者だった場合) ・年金分割の手続き | ・扶養から外れた場合、手続きが遅れると医療費が一時全額自己負担になるため注意。 ・年金分割は離婚をした日の翌日から2年の期限あり。 |
| 子ども関連 | ・子の氏の変更許可(家裁)と入籍届(役所) ・児童扶養手当、児童手当の手続き ・ひとり親家庭支援制度の申請 | ・子の戸籍・姓は自動で変わらない。家裁の許可後に役所への届出が必要。 ・各種手当は申請しないと受給できない(多くは申請翌月分から)。 |
| 各種名義変更 | ・運転免許証、パスポート ・銀行口座、クレジットカード ・生命保険、不動産登記(財産分与時) | ・氏名や住所が変わった場合、ほぼ全ての契約で変更が必要。 ・本人確認書類となる運転免許証や銀行口座から進めるとスムーズ。 |
特に「年金分割の手続き」や、子どもの戸籍・姓を変更するための「子の氏の変更許可」は忘れがちであるため注意が必要です。



これらは生活基盤を整えるために不可欠であり、期限が定められているものも多いため、チェックリスト化して漏れなく対応しましょう。
関連記事:熟年離婚したらどうなる?知っておきたい知識や後悔しないポイントを現役弁護士が解説
離婚手続き(協議)が難航したときの対処法
夫婦間での話し合い(協議)がスムーズに進まないケースは少なくありません。
感情的な対立や知識不足が原因であることが多いため、冷静に対処法を検討しましょう。
弁護士に交渉の代理を依頼する
夫婦間での直接の話し合い(協議)が難しい場合、弁護士に交渉の代理を依頼する方法が有効です。
協議が難航する典型的な理由には、以下のようなケースが挙げられます。
- お互いが感情的になってしまい、冷静な話し合いができない
- 相手が威圧的(モラハラなど)で、怖くて自分の意見を言えない
- 法律知識がなく、相手から不利な条件を飲まされそうになっている
このような状況で弁護士が代理人となると、法的な観点から冷静に交渉を進めることができます。
専門家が間に入ることで相手も真剣に応じやすくなるメリットがあるほか、ご自身が相手と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されるでしょう。
家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てる
相手が話し合いに一切応じてくれない場合や、弁護士を立てて交渉しても協議がまとまらない場合は、法的な手続きである離婚調停を検討します。
離婚調停(夫婦関係調整調停)は、訴訟のように勝ち負けを決める場ではなく、あくまで家庭裁判所を介した話し合いの場です。
| 離婚調停について | 詳細 |
|---|---|
| 概要 | 協議離婚が難しい場合の、最も一般的な法的手段。 |
| 体制 | 調停委員が間に入り、話し合いを仲介する。 |
| 期日当日の流れ | ・原則として夫婦が顔を合わせることはない。 ・別々の待合室で待ち、交互に調停室に呼ばれて調停委員に事情や希望を伝える。 |
調停委員は、双方の意見を整理し、公平な解決案を提示するなど、合意に向けた調整役を果たしてくれるでしょう。
関連記事:離婚調停は弁護士に依頼すべき?費用相場や相談タイミングを専門家が徹底解説
【DV・モラハラの場合】まず身の安全を確保し、別居する
話し合いが難航する理由が、相手からのDV(身体的暴力)や深刻なモラハラ(精神的暴力)である場合、対処法の優先順位が根本的に異なります。
交渉や調停を試みること自体が相手を刺激し、暴力や威圧行為が悪化する危険性があるためです。安全を守るためにも、以下の行動を優先しましょう。
- 実家に身を寄せる、または公的なシェルターを利用する。
- 警察の生活安全課などに相談する。
- 身の危険が差し迫っている場合、裁判所に「保護命令」を申し立てる(相手は一定期間、接近や連絡が法的に禁じられます)。
交渉の前に、まず別居してご自身(と、いる場合はお子さん)の安全を確保することが何よりも重要です。
別居する際は、相手に気づかれないよう準備を進め、診断書や録音などの証拠も可能な限り持ち出しましょう。



安全を確保した上で、弁護士に連絡を取り、その後の法的手続きを安全に進める方法を相談することが重要です。
離婚手続きでお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は相談件数1,000件以上の実績を活かし、あなたに合った解決策をご提案いたします。
一人で悩まず、まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
離婚手続きでよくある3つの失敗と対策
焦りや知識不足から、離婚手続きで失敗し、後で後悔するケースも多く見られます。典型的な失敗例と対策を知っておきましょう。
書類不備で再提出になってしまう
離婚届や関連書類の不備は、手続きを遅らせる典型的な失敗です。
- 離婚届の親権者欄記載漏れ(親権者が決まっていないと受理されません)
- 証人欄の署名・押印の不備(印鑑が不鮮明、夫婦で同じ印鑑を使っている、など)
役所の窓口ではその場で訂正印を押せる程度の軽微な修正しかできません。そのため、不備があれば、離婚届を持ち帰って再提出する必要があります。
再提出になると、児童扶養手当の申請開始日などの手続きも遅延する可能性がありますし、何より相手の気持ちが変わってしまうリスクもゼロではありません。
養育費や財産分与を口約束で済ませてしまう
離婚を急ぐあまり、「養育費は月〇万円払う」「家は財産分与で君にあげる」といった金銭の取り決めを口約束だけで済ませてしまうのはよくある失敗です。
口約束には法的な強制力がありません。離婚当初は支払われていても、数年後に相手が再婚したり経済状況が変わったりした途端に、「そんな約束はしていない」と支払いを拒否されるケースが後を絶たないのです。
取り決めの方法によって、以下のような違いがあります。
| 取り決め方法 | 法的な強制力 | 将来のリスク・効力 |
| 口約束 | なし | ・法的な証拠が残らない。 ・支払いが停止しても対抗が困難。 |
|---|---|---|
| 公正証書 | あり (強制執行認諾文言付) | ・「合意の証拠」として高い証明力を持つ。 ・支払いが滞れば、裁判なしで強制執行(差し押さえ)が可能。 |
この最悪の事態を避けるためにも、合意した内容は、金額、支払方法、支払期限などを必ず文書化する必要があります。
可能であれば、裁判の判決と同じ執行力を持つ公正証書にしておくことが、将来のご自身と子どもの生活を守るための確実な対策です。
感情的な対立で調停が長期化してしまう
法的な話し合いの場である「調停」で、感情論を優先してしまうと解決が遠のきます。
調停委員は、あくまで中立な立場で法律に基づいた解決策を探る役割であり、「相手がどれだけひどい人間か」といった感情的な主張ばかりでは話し合いが平行線になります。
調停の場では、主張の仕方が結果を左右します。
| 主張のタイプ | 調停委員の受け取り方 | 結果 |
| 感情的な主張 (過去の不満、相手への恨み言) | 感情は伝わるが、法的に「何を求めているか」が不明瞭になる。 | ・話し合いが平行線になり、長期化する。 ・法的な解決案を提示しにくい。 |
|---|---|---|
| 法的な主張 (離婚条件、証拠に基づく要求) | 争点が明確になり、法律に基づいた公平な調整(解決案)をしやすくなる。 | ・有利な形での調整が期待できる。 ・早期解決につながりやすい。 |
調停委員に「自分が何を求めているのか」が的確に伝わらなければ、ご自身に有利な形での調整は期待できません。
調停を有利かつ迅速に進めるためには、弁護士を介して法的な主張を整理することが重要です。



弁護士が代理人となることで、冷静な交渉が可能になり、争点を明確にして「離婚を成立させ、条件を確定させる」という本来の目的を見失わずに手続きを進められるでしょう。
離婚手続きにかかる費用はどのくらい?
離婚手続きにかかる費用は、ご自身で手続きを進めるか、弁護士に依頼するかで大きく変わります。
ご自身で進める場合は、調停申立ての手数料(数千円)や、取り決めを公正証書にする際の手数料(数千円~数万円)といった実費が中心です。
弁護士に依頼する場合は、これらの実費に加え、契約時に支払う「着手金」や、成果に応じて支払う「報酬金」などが別途発生します。
手続きごとの費用目安は、以下の通りです。
| 手続きの種類 | 自分で進める場合の費用目安 | 弁護士に依頼する場合の費用目安(合計) |
| 協議離婚 | ・無料(離婚届のみの場合) ・数千円~数万円(公正証書作成時) | 20万~100万円程度 (交渉代理の有無、書類作成のみか等で変動) |
| 調停離婚 | 数千円程度(収入印紙1,200円+郵便切手代) | 60万~120万円程度 (調停の回数、争点の多さなどで変動) |
| 裁判離婚 | 数万円~(訴額に応じた収入印紙代+切手代) | 80万~150万円以上 (財産分与の額、親権争いなどで変動) |
ご自身で進めれば費用は最小限ですが、「相手との交渉が難しい」「財産分与が複雑で不利になりそう」といった場合は、弁護士への依頼を検討する価値があります。
経済的に弁護士費用を支払うのが難しい場合、収入などの条件を満たせば、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度(無料相談や弁護士費用の立替え・分割払い)を利用できる可能性もあります。



弁護士に依頼するかお悩みの場合は、ご自身のケースで費用に見合うメリットがあるか、ぜひ無料相談にてお問い合わせください。
離婚手続きでのお悩みは、弁護士法人アクロピースにお任せください。
離婚問題の経験が豊富な弁護士が、一人ひとりの状況に合わせて適切な対処をご提案いたします。
初回60分の無料相談も実施しているので、ぜひ一度相談してみてください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
関連記事:離婚の弁護士費用はいくら?相場や内訳・払えない場合の対処法を弁護士が解説
離婚手続きにかかる期間はどのくらい?
離婚が成立するまでの期間は、選択する方法で大きく異なります。
夫婦間の話し合いで完結する「協議離婚」が最も短く、裁判所が関与する「調停離婚」「裁判離婚」の順に長期化します。
司法統計などに基づく、一般的な目安期間は以下の通りです。
| 手続きの種類 | 期間の目安 | 期間が変動する主な要因 |
| 協議離婚 | 1ヶ月~1年程度 | ・交渉次第。財産分与や親権がスムーズに決まれば1ヶ月、難航すれば1年近くかかる。 |
| 調停離婚 | 数ヶ月~1年程度 | ・月1回程度の開催。 ・平均3~6回(3~6ヶ月)で成立することが多い。 ・争点が多いと1年以上かかる。 |
| 裁判離婚 | 1年~2年程度 | ・平均審理期間は約1年3ヶ月~1年8ヶ月。 ・調停期間はこれに別途加算される。 |
裁判所|令和5年 司法統計年報(家事編)
裁判所|令和6年 人事訴訟事件の概況
特に裁判離婚の期間は、それ以前の調停期間(半年〜1年程度)に加算されます。そのため、トータルの解決期間は非常に長くなる点に注意が必要です。



調停の段階でいかに法的に有利な交渉をするかが、早期解決の鍵になります。
関連記事:離婚するまでの期間は?離婚をするにはどのくらい時間がかかるのか流れを解説!
離婚手続きに関するよくある質問
最後に、離婚手続きに関してよく寄せられる質問にお答えします。
離婚手続き前にやってはいけないことはありますか?
焦りや怒りに任せた行動は、後の法的手続きで不利になるため避けるべきです。
特に以下のような行動はリスクが高いため注意しましょう。
- 正当な理由なき別居(悪意の遺棄とみなされるリスク)
- 共有財産の勝手な処分(財産隠しとみなされる)
- SNSでの相手の悪口(名誉毀損リスク)
- 弁護士相談前の書類へのサイン(不利な内容でも合意したとみなされる)
これらの行動は、ご自身の立場を著しく不利にしたり、相手に攻撃材料を与えたりするため、行動を起こす前に弁護士へ相談しましょう。
離婚は即日できますか?
協議離婚の場合のみ、即日離婚は可能です。以下の条件を満たした上で、離婚届を役所の時間内に提出すれば成立します。
- 夫婦双方に離婚の意思が固まっている。
- 未成年の子の親権者が決定している。
- 離婚届に記載漏れや不備がない。
- 成人2名の証人の署名・押印がすでにもらってある。
子連れ離婚をするにはまず何をすればいいですか?
お子さんがいる場合、子どもの将来を最優先に考える必要があります。 まずは、以下の最優先事項を整理し、決定することが重要です。
- 子どもの親権者をどちらにするか(※離婚届に必須の記載事項)
- 養育費はいくらにするか、いつまで支払うか
- 面会交流の頻度や方法はどうするか
これらの条件を、夫婦の感情的な対立ではなく、「子どもの視点」で整理することが求められます。



離婚後の生活環境の変化や精神的なケアなども具体的にシミュレーションし、焦って行動する前に弁護士と最善の手順を整理しましょう。
まとめ|離婚手続きは焦らず計画的に進めよう
離婚の手続きは、準備から離婚後の手続きまで、多くのステップがあります。やるべきことが多岐にわたるため、焦るほどミスが起きやすくなりがちです。
後悔しない離婚をするためには、以下の点に注意しましょう。
- 感情的にならず、冷静に準備を進めること
- 養育費や財産分与など、決めるべき条件を明確にすること
- 取り決めた内容は、必ず書面化(可能なら公正証書)すること
- 各種手続きの期限を守り、漏れなく対応すること
これらの対策を確実に行い、法的に不利にならないように進めるためには、離婚問題に強い弁護士のサポートが欠かせません。



一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士に相談し、最善の解決策を見つける第一歩を踏みましょう。
離婚手続きでお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は相談件数1,000件以上の実績を活かし、あなたに合った解決策をご提案いたします。
一人で悩まず、まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応