母親が親権を取れない・負ける場合とは?不利になる5つのパターンと対策を弁護士が解説
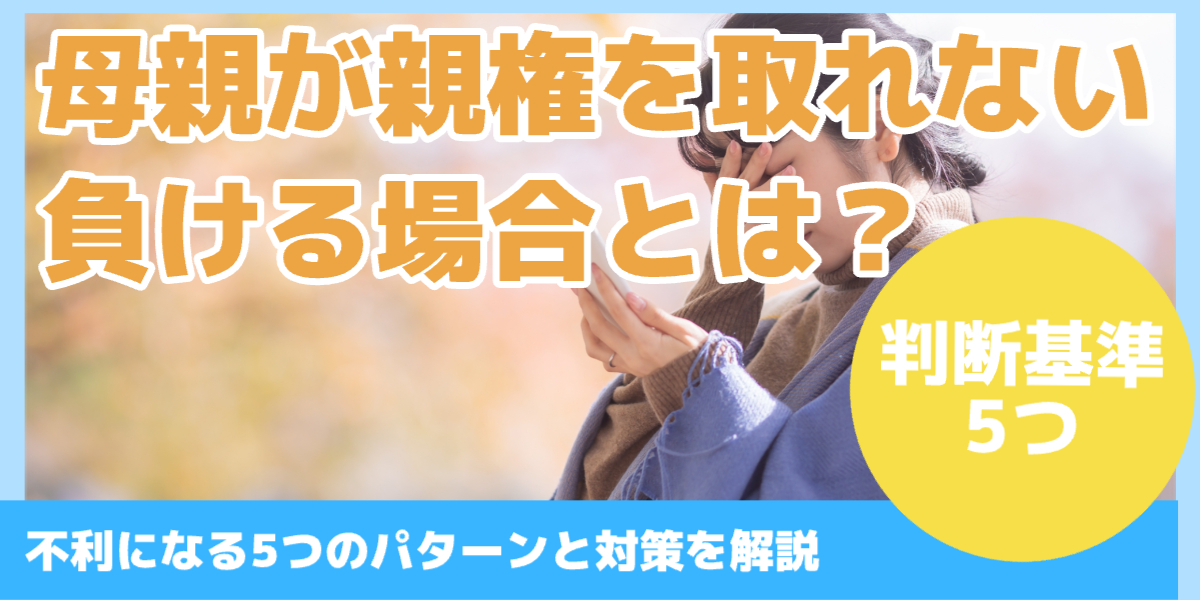
「親権で母親が負けることなんて本当にあるの?」
「万が一、親権を失ったらどうしよう……」
このような考えや不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
確かに統計上、離婚後の親権者の多くは母親ですが、「母親だから」という理由だけで自動的に親権が認められるわけではありません。
裁判所が重視するのは子どもの健全な成長と幸福であり、育児実績や監護環境に問題があると判断されれば、母親でも親権を失う(負ける)ケースは存在します。
親権を失えば、お子さんと一緒に暮らせなくなるだけでなく、養育費の支払い義務が生じるなど、精神的・経済的にも大きな負担を負うことになるでしょう。
この記事では、親権争いで母親が負けてしまう代表的なケースや、不利になる原因、負けないための対策を具体的に解説します。
ご自身の状況と照らし合わせ、今何をすべきかの検討にお役立てください。
親権争いに不安を感じる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
経験豊富な弁護士が状況を正確に分析し、あなたにとって最善の解決策を提案します。
まずは、初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
母親が親権を取れない・負ける5つのパターンとは?
一般的に「母親有利」と言われる親権争いには、母親が不利になる特定の状況が存在します。
裁判所が「子の福祉」を最優先する結果、母親が親権者として不適格と判断されれば、父親が選ばれることになります。
ここでは、母親が親権争いで負ける典型的な5つのパターンを解説します。 ご自身の状況と照らし合わせ、リスクがないか確認してください。
パターン1:育児の中心が父親だった
裁判所が最も重視するのが「これまでの監護実績」です。これは、日常的にどちらが子どもの世話をしてきたか、という客観的な事実を指します。
母親が仕事で多忙、あるいは育児に関心が薄く、以下のように実質的な育児を父親が担っていたと認められると、母親は著しく不利になります。
- 保育園や学校の送迎、連絡帳の記入を主に父親が担当していた
- 日常的な食事の準備、入浴、寝かしつけを父親が担っていた
- 子どもの通院や習い事の付き添い、学校行事への参加を父親が中心に行っていた
特に、別居時に父親が子どもを監護していると、「現状維持の原則」(後述)が強くはたらきます。
裁判所は、子どもの生活環境を急に変えることによる精神的負担を非常に重く見るため、「現状の安定した環境を維持すべき」と判断され、そのまま父親の親権が認められるケースも少なくありません。
パターン2:精神疾患・依存症で安定した養育が難しい
母親自身が、子どもの健全な養育を妨げる問題を抱えているケースでは、親権争いで不利になる場合があります。
裁判所は、子どもの安定した生活環境を最優先に考えるためです。ただし、病気や障害があること自体が、即座に親権が取れない理由にはなりません。
重要なのは、症状の程度と治療への取り組みであり、それらが子の養育にどう影響するかです。
以下のような状況では、子どもへの適切な監護が困難と判断されることがあります。
- 精神疾患の症状が重く、安定した日常生活(起床・食事など)が送れない
- 医師の指示に従わず、治療や服薬を自己判断で中断・拒否している
- アルコールや薬物への依存があり、子どもに悪影響(暴言や放置)が及ぶ懸念がある
- 心身の不調が原因で、子どもが家事や親のケアを担う「ヤングケアラー」の状態になっている
心身が不安定な状態は、ネグレクト(育児放棄)や虐待につながるリスクもはらんでいます。
裁判所が「母親による養育は子の福祉に反する」と判断すれば、父親側に親権が認められる可能性は高くなります。
パターン3:子どもを無断で連れ去る・面会を拒否する
離婚協議中や別居時に、感情的になって不適切な行動を取るケースです。 これは「子の福祉」に反する行為と見なされ、母親に不利にはたらきます。
| 不適切な行動 | 詳細 |
|---|---|
| 無断の連れ去り | 子どもの生活環境を一方的に変え、精神的負担をかける行為 |
| 面会交流の拒否 | 「父親に会わせたくない」という感情的な理由で、子どもから父親と会う機会を奪う行為 |
こうした行動は、母親が「自分の感情を優先し、子の利益を考えない親」と評価される原因です。
正当な理由(DVや虐待からの避難)がない限り、厳に慎む必要があります。
パターン4:子どもが父親との生活を希望している
家庭裁判所は、子どもの意思も重要な判断材料とします。
特に10歳前後から子どもの意見を丁寧に聴取するようになり、15歳以上の子どもについては、その意思が強く尊重される傾向にあります。
思春期の子どもが、自らの判断で「お父さんと暮らしたい」と明確に述べた場合、その希望が親権判断に大きく影響します。
ここで絶対に避けなければならないのは、無理に子どもの意見を誘導したり、「お父さんは悪い人だ」といった悪口を吹き込むことです。
家庭裁判所調査官は、そうした親による不当な影響をすぐに見抜きます。誘導が発覚すれば、かえって「子の精神的発達を阻害する親」として、不利になる恐れがあります。
パターン5:父親の生活環境がより安定している
裁判所は、親の経済力そのものよりも「子どもが安定して暮らせる環境」を重視します。収入の大小が親権を決めるわけではありません。
父親側に定職があり、持ち家などで住環境が整っていたり、祖父母と同居しているなど育児に協力してくれる人が多い場合、生活基盤の「安定性」で母親が不利になることがあります。
対して、母親側に以下のような事情があると、子の福祉の観点から不利にはたらく傾向があります。
- 離婚後の住まい(実家など)の目処が立っていない
- 転居や転職を短期間で繰り返しており、生活基盤が不安定
- 心身の不調により、家の中がゴミ屋敷状態など著しく不衛生である
経済的な不利は、養育費や公的支援、実家の援助などで補えることを具体的に説明できれば問題ありません。
しかし、住環境や生活リズムといった環境そのものの不安定さは、子の福祉に直結する問題として厳しく評価されています。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫「母親だから大丈夫」という考えは非常に危険です。ご自身の状況がこれらのパターンに当てはまらないか、客観的に確認することが重要です。
なぜ親権争いは母親が有利なのか?
母親が不利になるパターンを紹介してきましたが、それでも「親権は母親が有利」という現実は依然として存在します。
この章では、母親有利の背景にある統計データと、裁判実務の実情を見ていきましょう。
統計で見る親権者の割合:約8〜9割が母親
厚生労働省の「人口動態調査」を見ると、親権者の実態がわかります。
離婚した夫妻のうち、子どもの親権者を妻(母親)が行う割合は、長年にわたり8〜9割で推移しており、この数字自体に大きな変動はありません。
2023年における、親権者の割合は以下の通りです。
| 親権者の内訳 | 割合 |
|---|---|
| 妻(母親)が全児の親権 | 約86.6% |
| 夫(父親)が全児の親権 | 約10.6% |
| 子どもごとに親権が分かれた | 約2.8% |
この数字を見る限り、「母親有利」という認識は今も事実です。ただし、この統計には裁判で争ったケースだけでなく、話し合い(協議離婚)で「それなら母親が」と決まったケースも大多数含まれています。
そのため、この数字だけを見て「裁判でも絶対に母親が勝てる」と考えるのは早計です。
裁判所が重視するのは「これまで主に子育てしてきたのは誰か」
統計上、母親が親権者となりやすい最大の理由は、乳幼児期から現在に至るまで、子育てを主に担っているのが母親であるケースが多いためです。
裁判所は「監護の継続性(現状維持)」を非常に重視します。そのため、これまで通り母親が育てるのが子の福祉にかなうと判断されやすい、というのが実情です。
過去には「母性優先原則(乳幼児は母親が育てるべき)」という考え方が慣例的に影響していました。
しかし、現代の裁判実務ではその考え方は薄れ、性別よりも監護実績と安定性重視へと明確に移行しています。
「父親=外で働く人」という画一的な構図が崩れ、育児に積極的な父親が増加した社会的変化が、親権の判断実務にも確実に影響を与えつつあるのです。



裁判所は性別で判断しているわけではなく、あくまで「これまでの監護実績」を最重視していることには注意が必要です。
自分のケースでも親権が取れるか不安を感じる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
経験豊富な弁護士が状況を正確に分析し、あなたにとって最善の解決策を提案します。
まずは、初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
親権争いで家庭裁判所が重視する5つの判断基準
家庭裁判所が親権者を決めるとき、その根底には常に「子の福祉」という絶対的な基準があります。
その判断のため、裁判所は以下の5つの具体的な基準を、個別の事情に応じて総合的に比較検討します。
くわしく見ていきましょう。
1. 監護の継続性(現状維持の原則)
可能な限り現状を維持できることは、裁判所が重んじる基準の一つです。
これは、子どもの住まいや学校、友人関係などの生活環境を急激に変化させるべきではない、という考え方に基づきます。
大人が思う以上に、環境の変化は子どもにとって大きな精神的負担となります。
そのため、「これまで主に育児を担ってきた親」が引き続き監護することが、子の安定につながると判断されやすくなるのです。
父親が主に育児を担い、その環境で子どもが安定している場合、母親が親権を取ることは「子の福祉に反する」と判断されるリスクがあります。
関連記事:親権と監護権どっちが強いの?子どもの親権は誰が取る―「親権」と「監護権」の基礎知識
2. 父母の心身・経済状態
親の心身や経済状態も、安定した養育環境を測る上で考慮されます。ただし、これは単純な優劣を決めるものではありません。
精神疾患があること自体が、直ちに不適格と判断されるわけではなく、以下のような病状や養育環境を具体的に確認します。
- 病状が安定しており、治療を継続しているか
- 育児に支障が出るほどの症状ではないか
- 周囲(親族や公的機関)のサポート体制が整っているか
これらを示せれば、不利な状況を回避できる可能性があります。
経済状態についても同様で、収入の大小が直接的な決め手にはなりません。 収入が少なくとも、計画的な生活を送れるかを具体的に示すことが重要です。
- 相手からの養育費
- 児童扶養手当などの公的支援
- 親族からの援助
- 自身の就労による収入
これらで安定した生活を送れることを示せれば、大きな不利にはならないでしょう。
3. 面会交流への柔軟性(フレンドリーペアレントルール)
離婚後、子どもがもう一方の親と会う面会交流に協力的かどうかも、重要な判断材料です。これを「フレンドリーペアレントルール」と呼びます。
裁判所は、子どもにとって親は二人ともかけがえのない存在であり、双方との良好な関係を維持することが子の健全な成長に不可欠だと考えています。
そのため、相手への個人的な感情から面会交流を不当に拒否したり、子どもの前で相手の悪口を言ったりする親は、子の福祉を深く理解していないと見なされる可能性があるのです。
- 相手への個人的な感情を優先している
- 子どもの気持ちや利益を理解していない
- 親権者としての適格性に疑問がある
DVや虐待など、会わせることが子どもの安全を脅かす正当な理由がないにもかかわらず、非協力的な姿勢を続けると、親権者としての適格性を疑われ、不利な状況を招きかねません。
4. 子どもの意思の尊重
子どもの年齢が上がるにつれて、その意思は親権判断において大きな比重を占めるようになります。
家庭裁判所は、心理学や社会学の専門家である家庭裁判所調査官による面談などを通じて、子どもの本音を丁寧に聞き取ります。
おおむね10歳前後から子どもの意見が参考にされ、15歳以上になるとその意思は最大限尊重されるのが実務上の扱いです。
親が無理に意思を誘導しようとしても、専門家である調査官には見抜かれる可能性が高いと心得ておくべきです。
5. 子の福祉・安定性
これまで挙げた4つの基準は、すべてこの「子の福祉・安定性」という最終的な目的に集約されます。
経済力がある、という一点だけでは親権は決まりません。裁判所は、以下のようなあらゆる側面から、どちらの親と暮らすのが子どもにとって最善かを総合的に判断しています。
- 子どもへの虐待やネグレクト(育児放棄)の有無
- きょうだいを分離すべきでないか(きょうだい不分離の原則)
- 親族などからのサポート体制
- 子どもへの愛情や養育の意欲
- 乳幼児期における母親の必要性(母性優先の原則)
裁判所はこれらの基準を総合的に見て「子の福祉」を判断します。



どれか一つでも大きな問題があると、他の基準で有利でも、不利な結果につながる可能性があります。
母親が親権争いで負けないための準備と行動ステップ
親権を確実に獲得するためには、感情に流されず、冷静かつ戦略的に準備を進める必要があります。
離婚を考え始めた段階から、以下の4つのステップを意識して行動してください。
同居中の準備期|静かに記録を積む
離婚の意思を相手に伝える前から、親権を取る準備は始まっています。
この段階で最も重要なのは、日々の監護実績を客観的な証拠として記録し続けることです。感情的な主張よりも、事実の積み重ねが裁判所を動かします。
- 育児日記(食事、入浴、就寝時間、その日の様子など)
- 通院記録(病院の領収書、お薬手帳、母子手帳の記録)
- 学校・保育園との連絡帳(自分が主にやり取りしていたことがわかるもの)
- 学校行事や日常の写真(子どもと自分が密接に関わっていることがわかるもの)
同時に、子どもの生活リズムを崩さないことを最優先し、精神的な安定を維持するよう努めましょう。
別居準備期|弁護士と戦略を立てる
感情的な勢いで家を飛び出す「連れ去り別居」は、親権争いにおいて致命傷になりかねないため、DVなどからの緊急避難を除いて絶対に避けなければなりません。
別居に踏み切る前には、必ず親権問題に詳しい弁護士へ相談し、別居の合意書や子の監護者指定の調停申立など法的に正しい手続きを確認してください。
弁護士に相談することで、これまで集めてきた監護実績の証拠を法的な観点から整理し、有効な証拠として体系化できます。
さらに、子どもの学区や住環境を含め、実家に戻ったり公的支援を受けたりといった別居後の具体的な生活計画を立て、養育環境の安定性を具体的に主張できるように準備します。
別居・調停期|誠実さと一貫性を持つ
別居後、あるいは離婚調停の段階では、一貫して「子の福祉を最優先する誠実な親」としての姿勢を示すことが重要です。
まずは、新しい環境でも子どもの生活リズムを崩さず、安定した生活を継続させることに全力を注ぎましょう。
相手からの面会交流の申し出には、感情的にならず冷静に対応し、そのやり取りもメールやLINEなどの記録に残すようにします。
家庭裁判所調査官による家庭訪問や面談の際には、準備した資料に基づき、感情的にならず、正確な状況と子どもの利益を第一に考えている姿勢を具体的に説明できるようにしましょう。
審判・裁判期|証拠と主張で勝負する
調停が不成立となり、審判や裁判に移行した場合は、これまでに積み重ねてきた客観的な証拠と、一貫した主張で臨むことになります。集めた記録や証拠を時系列に整理し、弁護士と最終的な戦略を練り上げましょう。
必要に応じて、子どもの監護状況を客観的に証言してくれる医師や教師、保育士といった第三者の協力を得ることも検討します。
裁判の場では、相手を非難することに終始するのではなく、つねに「子の利益」を軸にして、なぜ自分が親権者としてふさわしいのかを論理的に主張することが親権争いの勝利へとつながります。



感情的にならず、別居前から冷静に証拠を集めることが、お子さんとの未来を守る鍵です。
関連記事:子連れ離婚の手続きの順番はどうなる?準備から離婚後までのステップと注意点を弁護士が解説
【母親向け】親権を取られてしまった場合の対処法
万が一、審判や裁判で親権者になれなかったとしても、それで親子の関係が絶たれるわけではありません。父親に親権を取られてしまった場合には、以下の対処法を取ることをおすすめします。
法的に取りうる選択肢と、子どもとの未来のためにできることを知っておくことが大切です。
即時抗告(不服申立)の可否を確認する
家庭裁判所の決定に納得できない場合、即時抗告という不服申し立てが可能です。これは、高等裁判所に対して、もう一度判断を求める手続きです。
ただし、申立てができる期間は、審判書を受け取ってから2週間以内と非常に短く、迅速な対応が求められます。
また、第一審の結果を覆すには、手続き上の重大な誤りや、判断を覆すほどの新たな証拠が必要となるため、ハードルは非常に高いのが実情です。
まずは弁護士に、抗告の成功可能性がどれだけあるか、相談する必要があります。
面会交流で子どもとの関係を保つ
親権を失っても、親であることに変わりはなく、子どもと定期的に会う「面会交流権」は法的に保障されます。
親権を失ったショックは計り知れませんが、ここで子どもとの関係を断ち切ってしまうのは最悪の選択です。
面会交流を継続的に行うことは、子どもとの信頼関係を維持し、子どもの健全な成長を支える上で重要です。
後のトラブルを避けるためにも、面会の頻度や場所、時間などのルールを家庭裁判所の調停などで明確に取り決めておくことをおすすめします。
環境変化があった場合には親権変更の申立を検討する
親権は、一度決まったら永久に固定されるものではありません。
離婚後に親権者(この場合は父親)の生活環境が大きく変わり、「子の利益に反する状態」になった場合には、親権者の変更を家庭裁判所に申し立てることが可能です。
- 父親が再婚し、再婚相手が子どもを虐待している
- 父親が育児放棄(ネグレクト)の状態にある
- 父親が遠方へ転勤し、子どもが転校を強く拒否している
逆に、母親側の生活が安定し(例:病気が完治し、安定した職に就いた)、父親側の環境が悪化した場合なども対象となります。
この申立ての際にも、これまで面会交流を良好に継続してきた実績が、「子を想う親」としての重要な評価材料になります。
支援制度や専門家を活用し、再出発に備える
親権を失った直後は、精神的にも経済的にも困難な状況に陥りがちです。
一人で抱え込まず、各自治体が設けている公的な相談窓口や支援制度(※親権がなくても利用できる場合があります)を積極的に活用しましょう。
弁護士や心理カウンセラーといった専門家の力も借りながら、生活と心の安定を取り戻すことが、子どもとの関係を再構築することにつながります。
「負けた=終わり」ではなく、子どもと関わる形を変えながら、長期的に親としての役割を果たしていく道を探す姿勢が大切です。



万が一親権を失っても、親子の縁が切れるわけではありません。諦めずに子どもとの関わりを持ち続けることが大切です。
親権争いに不安を感じる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
経験豊富な弁護士が状況を正確に分析し、あなたにとって最善の解決策を提案します。
まずは、初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応
親権争いで母親が負ける場合に関するよくある質問
ここでは、親権争いに関してよく寄せられる質問にお答えします。
母親の収入がない場合でも親権は取れますか?
収入がないことだけを理由に親権が取れなくなるわけではありません。多くのケースで、専業主婦であったり、パートタイムであったりする母親が親権を獲得しています。
裁判所が重視するのは、経済力そのものよりも「これまでの監護実績」と「今後の生活の安定性」です。
相手方から支払われる養育費や、児童扶養手当などの公的支援、親族からの援助などを組み合わせることで、離婚後の安定した生活計画を具体的に示すことができれば、大きな不利になることはありません。
精神疾患があっても親権は取れますか?
病気の事実だけで親権者になれないと決まるわけではありません。
重要なのは、病状が安定しており、治療を継続することで「安定した監護能力」を維持できるかという点です。
定期的な通院や服薬を続け、医師の診断書や、実家などのサポート体制を具体的に示すことができれば、裁判所もその状況を理解してくれます。
「治療をしながらでも、周囲の助けを得て、子どもの生活をしっかりと守れる」ことを客観的に証明することが大切です。
父親に子どもと会わせないのは違法ですか?
子どもを父親に合わせないのは、違法行為ではありませんが、親権争いの上ではきわめて不利になる行為です。
DVや虐待の危険があるなど、子どもの心身の安全を脅かす正当な理由がない限り、一方的に面会交流を拒否し続けることは「子の福祉に反する」と判断される可能性があります。
「相手が憎いから」といった母親の感情的な理由で拒否を続けると、調停や裁判の場で「非協力的な親」と見なされ、親権争いにおいて不利な立場に置かれるリスクがあるのです。



面会交流は子の権利であるという視点を忘れてはいけません。
まとめ|親権争いでは母親が負ける場合もある!今すぐ対策を始めよう
親権は「母親だから」という理由だけで自動的に認められるものではなく、あくまで「子の福祉」を最優先に、個別の事情に基づいて判断されます。
裁判所に「母親に任せるのが不適当だ」と判断されれば、母親でも親権を失う(負ける)リスクは現実に存在します。
このような事態を避け、お子さんとの生活を守るためには、以下のような事前の準備が不可欠です。
- 日常の監護実績を「客観的な証拠」として記録すること
- 子どもの生活環境の安定性を最優先に考え、計画すること
- 面会交流などには誠実に対応し、非協力的と見なされないこと
- 子どもの連れ去りなど、感情的で違法な行動を絶対に取らないこと
これらの対策を確実に行い、法的に不利な状況に陥らないためには、離婚や親権問題に強い弁護士のサポートが欠かせません。



お子さんの未来を守るためにも、専門家である弁護士に相談し、最善の解決策を見つける第一歩を踏み出しましょう。
親権争いに不安を感じる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
経験豊富な弁護士が状況を正確に分析し、あなたにとって最善の解決策を提案します。
まずは、初回60分の無料相談をご利用ください。
\ 初回60分無料!/
【無料相談受付中】365日対応







