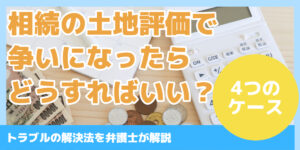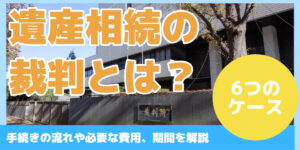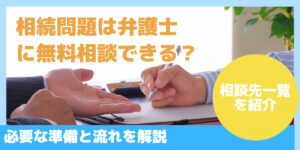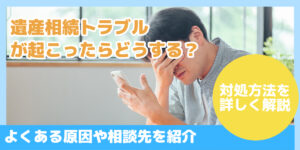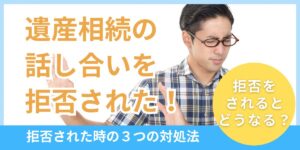【無料相談受付中】24時間365日対応
養子縁組による相続トラブルとは?よくある5つのケースやリスク・対処法を解説
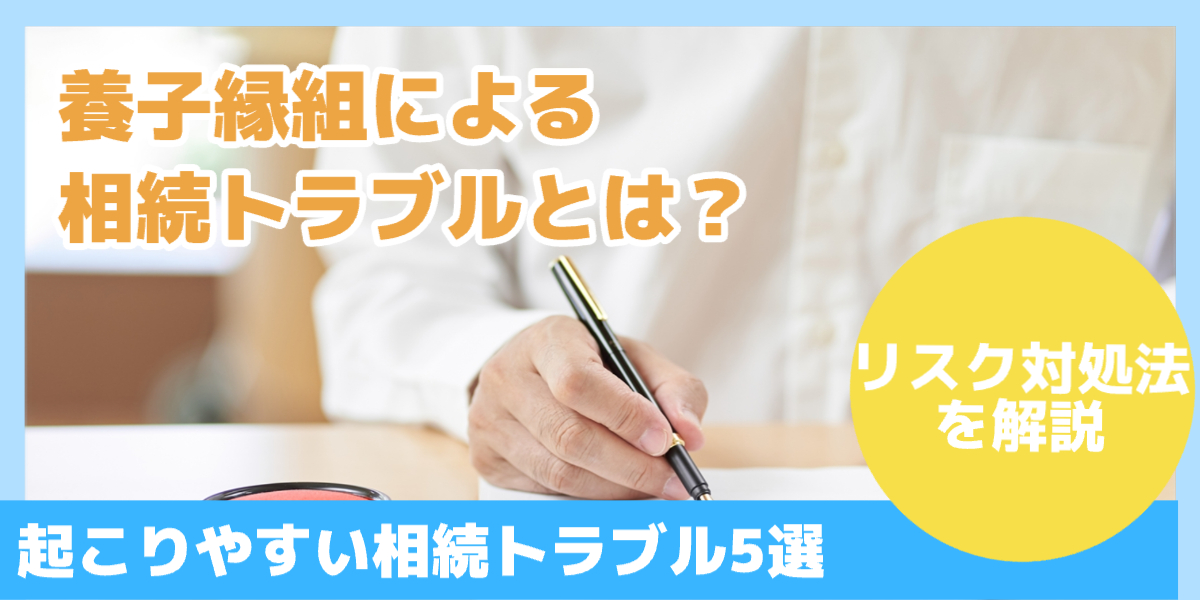
「養子縁組をしたことで、相続でもめてしまうのではないか」
「実子と養子の取り分に差が出るのだろうか」
上記のような不安や疑問をお持ちではありませんか。
養子縁組は、家族の絆を法的に結ぶ制度ですが、相続の場面では思わぬトラブルの火種になることがあります。
本記事では、養子縁組と相続の関係性、よくあるトラブルの実例とその回避策を、法律の専門知識に基づいてわかりやすく解説します。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
【基礎知識】養子縁組とは?
養子縁組とは、法律上の親子関係をつくる制度であり、相続人の範囲や順位にも直接影響します。
本章では、基礎知識として、養子縁組についての概要や相続への影響を解説します。養子縁組を検討している方や、家族内で養子がいる場合は参考にしてください。
養子縁組の種類
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。両者の大きな違いは「実親との関係性」です。
| 養子の種類 | 実親との関係 |
|---|---|
| 普通養子縁組 | 養親との関係が成立しても、実親との親子関係はそのまま残る |
| 特別養子縁組 | 実親との親子関係は完全に終了する |
民法上、養子は実子と同じく法定相続人として扱われ、普通養子の場合は実親との親子関係も残ります。
また、税法では養子による相続税の控除枠には上限があり、基礎控除や生命保険の非課税枠に使える養子の数は最大2人までと定められています(相続税法第15条)。
(特別養子の効果)民法 第817条の2
出典:民法 第817条の2(e-Gov 法令検索)
特別養子縁組が成立すると、養子は実方の親族との親族関係を含め、実親との親子関係が終了する。
養子の相続順位
養子は実子と同じく第一順位の相続人として扱われ、法定相続分も等しいとされています。
民法第887条と889条による相続順位は以下のとおりです。
- 子(実子・養子)
- 親(直系尊属)
- 兄弟姉妹
※なお、被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法第890条)。
養子縁組で相続の優先順位が変わり、親族間トラブルの引き金になるケースも少なくありません。

家族の意向や感情をふまえて計画的に進めることが大切です。特定の人に財産を残したい場合は、遺言書の作成も視野に入れましょう。
養子縁組の相続上のメリット・デメリット
養子縁組における相続上のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | ・相続税の基礎控除額が増える ・生命保険の非課税限度額も増える |
|---|---|
| デメリット | ・税務署から否認されるリスクがある ・相続税2割加算の可能性がある ・実子や養子間で相続トラブルが起こる可能性がある |
養子縁組は、特定の人に財産を遺せるだけでなく、節税効果も期待できます。
ただし、節税目的だけで形式的に養子縁組をすると、税務署から否認される可能性があるため注意が必要です。
さらに、孫を養子にした場合、相続税が2割加算される特例が適用され、想定以上の税負担が発生することがあります。(相続税法第18条第2項)
また、実子・養子間の相続トラブルに発展するリスクも考えられます。法的に実子と養子の取り分は平等になるため「なぜ他人である養子に同じ財産を渡すのか」と実子が不満を抱くケースは少なくありません。
こうしたリスクを避けるには、養子縁組の制度的な特徴や税法上の扱いを親族間で十分に理解しておくことが重要です。



必要に応じて、専門家のサポートを受けながら準備を進めましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
養子縁組で起こりやすい相続トラブル5選
養子縁組で起こりやすい相続トラブルには、以下5つのケースがあげられます。
養子縁組に関する相続トラブルを未然に防ぐためにも、どのような場面で対立が起きやすいのかを知っておきましょう。
実子と養子の取り分で揉める
民法第900条により、養子と実子の法定相続分は同じと決められています。しかし、実子が養子と同じ取り分であることを不公平に思い、トラブルに発展する可能性があります。
とくに再婚などで血縁がない養子が加わると、「他人に取り分を奪われた」と反発を招きやすくなるでしょう。
実子と養子の相続トラブルを未然に防ぐには、遺言書で配分の理由を明確に記し、生前に家族と方針を共有することが重要です。



遺言書の作成方法については以下の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:遺言書作成の注意点は?自筆証書遺言の場合や遺言執行者の指定についても解説
兄弟や親族が不満を抱き相続権を主張する
養子縁組によって相続順位が変わり、兄弟姉妹が相続権を失うことで、トラブルに発展するケースがあります。
たとえば、子どもがいない人が養子を迎えた場合、これまで法定相続人だった兄弟姉妹は相続順位が下がり、相続人から除外されるケースもあります。
対策としては、養子縁組や相続対策そのものの手続きを専門家に任せ、透明性を確保することが欠かせません。
養子縁組によって兄弟姉妹の相続権が無くなる場合は、関係する親族への事前説明も必要です。
節税目的とみなされることで否認される
形式だけの養子縁組を行うと「節税目的」とみなされ、否認されるおそれがあります。
相続税法第15条第2項では、養子縁組によって相続税の基礎控除額が増えるしくみが認められています。
しかし生活実態や扶養関係がない養子縁組の場合、税務調査が入り、控除が否認されるリスクもあります。税務調査の対象となりやすいケースは、以下のとおりです。
- 相続直前に成人の孫を養子にしたケース
- 高齢の被相続人が短期間に複数の養子縁組を行っていたケース
税務調査による否認のリスクを回避するためにも、税理士に相談の上、日常的な扶養関係や生活実態を証明する記録を残しておきましょう。
養子に出した子や孫養子の誤解・反発が起こる
孫を養子にすると「代襲相続」ではなく「子」として扱われ、他の相続人との配分に影響します。
代襲相続とは:本来相続人となるべき人が相続の開始以前に死亡していたり相続権を失っていたりする場合、その子どもが代わりに相続できる仕組み
この仕組みを他の相続人が理解していないと、「なぜ孫に相続権が?」と反発され、トラブルに発展するリスクも考えられます。
孫を養子縁組する場合は、意図を丁寧に説明し、必要に応じて遺言書で補足することで、誤解を防ぎましょう。
養子の死亡・相続放棄など想定外の事態が起こる
養子の死亡や相続放棄などにより、計画していた分配が崩れることがあります。
とくに、以下のようなケースでは分配のやり直しや相続人同士のトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
- 養子が相続開始前に死亡しており、養子の子へ代襲相続が発生することが発覚した
- 養子が相続を放棄し、他の相続人への再分配が必要になった など
トラブルを防ぐには、複数の相続パターンを想定し、予備的遺言や家族信託の準備など法的な準備をしておくことが大切です。



必要に応じて弁護士への相談も視野に入れましょう。
養子縁組で相続トラブルが起こりやすい関係性【一覧】
養子縁組は、孫・再婚相手の連れ子・子の配偶者・甥姪・同性パートナーなど、多様な関係で行われます。
しかし婚姻や血縁と親子関係は別の制度であり、相続時に誤解や対立が起こりやすくなります。
それぞれの関係性で起こりやすい相続トラブル・注意点は以下のとおりです。
| 関係性 | 起きやすいトラブル | 注意点・対策 |
|---|---|---|
| 孫 | 相続税が2割加算される | 税理士に相談し、遺言や家族信託を併用する |
| 子の配偶者 | 離婚後も相続権が残る | 離婚時に「離縁届」を提出して関係を解消する |
| 再婚相手の連れ子 | 離縁しないまま相続権が残る | 離婚時に親子関係も整理し、遺言で補足説明する |
| 同性パートナー | 他の親族から反発されやすい | 公正証書遺言で意思を明示し、親族にも説明しておく |
| 甥・姪 | 兄弟姉妹との関係悪化 | 相続順位の変化を丁寧に説明し、誤解を防ぐ |
それぞれのケースに応じた備えを行うことで、相続時の感情的な衝突を回避しやすくなります。
関連記事:
腹違いの兄弟に相続権はあるのか?異母兄弟の遺産分割をめぐるトラブルと対処法を解説
【配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり】の相続はどうするの?相続させたくない場合の対処法も解説!
養子縁組の相続トラブルが発生した時の対処法
養子縁組の相続トラブルが発生したときは、以下のような対処法が有効です。
養子縁組による相続トラブルにお悩みの方は、本章を参考に対処法を検討してみてください。自分自身で対応できないと感じたら、早めに弁護士へ相談を進めましょう。
話し合いで解決できるか冷静に見極める
養子縁組に関連する相続トラブルが起きたら、まず当事者間で冷静に話し合えるかを見極めましょう。感情的なまま話を進めると関係が悪化しやすく、争いが悪化するリスクもあります。
家庭裁判所の遺産分割調停では、事前に相続人の確定や養子縁組の有効性確認が必要になることもあります。(参照:裁判所|遺産分割調停の手続について)
感情の高ぶりを抑えるためにも、最初は事実関係を整理する場を設けることが大切です。
必要な証拠・資料を整理する
養子縁組に関するトラブルでは、戸籍謄本や遺言書、贈与契約書などの証拠が重要です。
特に養子縁組の有効性が争点となる場合、戸籍記録の整理が前提となります。
裁判所でも、申立ての前提として「相続人の確定」を必要としています。(出典:裁判所|遺産分割調停手続のご利用にあたって)



事前に関連書類を整理しておくことで、調停や訴訟がスムーズに進みやすくなります。
家庭裁判所に調停を申し立てる
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも視野に入れましょう。裁判官や調停委員が中立の立場から関与し、冷静な合意形成を支援してくれます。
ただし、養子縁組が有効かどうか争いがある場合には、先に家庭裁判所での人事訴訟による判断が必要なケースもあります。(参照:裁判所|遺産分割調停の手続について)
調停の申立て時には、戸籍や相続関係説明図などの準備も欠かせません。



自分自身で申立てを進めるのが難しいと判断した場合は、弁護士へ相談しましょう。
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説
弁護士に相談して法的対応を検討する
相続人の構成や養子縁組の有効性に争いがある場合、早めに弁護士に相談することが重要です。
遺留分侵害額請求や養子縁組無効確認訴訟など、法的手段の選択肢を正確に判断してもらえます。
家庭裁判所の資料でも、調停より前に訴訟対応が必要な場面があることが明記されています。(参照:裁判所|遺産分割調停の手続について)
専門家の力を借りて、法的に正当な主張を整理しておきましょう。
関連記事:遺産相続を弁護士に相談・依頼する流れは?手続き完了までの流れ・費用も詳しく解説
養子縁組の相続トラブルを防ぐ5つの方法
養子縁組は相続対策として有効ですが、親族の理解不足や関係の変化によって、思わぬ相続トラブルにつながるおそれもあります。
特に「感情面のもつれ」や「相続人間の利害対立」は、制度の効果だけでは解消できません。
本章では、養子縁組にともなうリスクを未然に防ぐためにおすすめな以下5つの対策を紹介します。
すべて生前から実行できる具体策のため、早めに取り入れることで安心した相続につなげられます。
親族への事前説明で理解を得ておく
養子縁組の誤解や不信感は、相続人間でのトラブルや感情的対立が起こる原因になります。
トラブルを回避するには、養子縁組の理由や遺産の分け方について、事前に相続人へ共有することが効果的です。
相続人に事前説明をする際は、以下の3点を意識しましょう。
- 養子縁組の背景や目的を率直に説明する
- 財産配分の方向性を共有しておく
- 想定される誤解(「取り分が減るのでは?」など)を先に解消する
相手の立場に配慮しながら、タイミングを見て丁寧に対話を重ねましょう。
遺言書で相続の方針を明確にしておく
遺言書は、相続配分に関する本人の意思を明文化する唯一の手段です。養子縁組がある家庭では、配分の理由も明記することで誤解や感情的な対立を防げます。
- 配分の理由や特別な事情に関する説明
- 養子と実子の取り扱いについて明記
- 寄与分・特別受益を考慮した遺産配分
公正証書遺言にしておけば、裁判所での検認が不要でスムーズに手続きを進められるため、将来の相続トラブルを避けるためにも、早めに作成しておきましょう。
公正証書遺言の作成については、以下の記事でも解説しています。
関連記事:公正証書遺言の作成にかかる時間は?必要な費用や作成の簡単な流れを解説
関連記事:【例文付き】遺言書の書き方とは?必須項目や注意点を解説
関連記事:【遺言書を開けてしまったら】罰則の可能性や検認方法についても解説!
相続税対策としての養子縁組は慎重に行う
養子縁組は相続税対策として使えますが、節税目的とみなされると否認されるリスクがあります。
形式的な手続きだけで実態のない親子関係とみなされた場合、税務調査で否認されるケースも少なくありません。
実際に扶養関係や生活支援があることを証明する必要があります。必要に応じて税理士に相談し、節税効果と家族間の信頼を両立させましょう。
離婚・家族構成の変化には柔軟に対応する
養子縁組後に離婚や再婚、死亡といった家族構成の変化があった場合、相続関係も見直す必要があります。
相続は法的な親子関係に基づいて判断されるため、状況が変わった時点で戸籍や遺言の内容を見直すことが欠かせません。
実際に相続が発生してから、想定外の相続人が存在することが発覚し、遺産分割協議をやり直すといったトラブルも考えられます。



できる限り生前に、自分の相続関係の見直しを行いましょう。
関連記事:ダメな遺言書とは?トラブル事例や揉めないために考えておくことも解説
信頼できる専門家に相談する
養子縁組に関する相続対策では、法務・税務・家族関係が複雑に絡むため、信頼できる専門家への相談を検討する必要があります。
弁護士・税理士・司法書士はそれぞれの立場から実務的な対策を提案してくれます。
| 専門家 | 担当業務 |
|---|---|
| 弁護士 | 遺言・相続トラブル対応、遺留分の調整 |
| 税理士 | 相続税の計算・節税対策、税務署対応 |
| 司法書士 | 相続登記、戸籍整理・遺産分割協議書作成支援 |
とくに、遺留分の調整、節税の合法性確認、遺言の形式選びは専門知見が不可欠であるため、早めに相談を進めましょう。
相続に強い弁護士の見極め方については、下記の記事もご覧ください。
関連記事:相続に強い弁護士とは?費用や失敗しない選び方を解説【弁護士監修】
関連記事:相続問題は弁護士に無料相談できる?おすすめの相談先や必要な準備も解説【弁護士執筆】
養子縁組と相続トラブルに関するよくある質問
養子縁組を勝手にされることはある?
養子縁組は、本人の同意がなければ成立しません。
養子縁組は、単なる家族間の口約束ではなく、養親・養子の双方の合意と、戸籍法に基づく正式な手続きが必要です。
具体的には、養子の年齢に合わせて以下のものが必要です。
- 15歳以上:原則単独で養子縁組ができる(未成年者である間は家庭裁判所の許可が必要)
- 15歳未満:法定代理人が縁組の承諾をする
また、養子縁組は市区町村への戸籍届出が受理されて初めて効力を持つため、たとえ親族であっても本人に無断で進めることはできません。
無理やり行われた養子縁組は、家庭裁判所で取り消しや無効の申し立てが可能です。
不安な場合は、早めに弁護士などの専門家に相談し、戸籍や書類の確認を行いましょう。
養子は代襲相続の対象になる?
養子が被相続人より先に亡くなっていた場合、一定の条件を満たす養子の子(被相続人から見ると孫)が代わって相続することが可能です。
具体的には、養子の子が被相続人の「直系卑属」に該当することが必要です。
養子縁組後に出生した子であれば直系卑属となり代襲相続が可能ですが、養子縁組前に出生していた子は直系卑属には当たらず、代襲相続は認められません。
長男が先に亡くなっても、長男の子が養子縁組後に出生していれば代襲相続人になる。
=長男に予定されていた相続分を、長男の子が引き継ぐ
相続関係が複雑な場合は、事前に専門家へ確認することが重要です。
養子縁組したことを知らなかったらどうなる?
養子縁組されていた場合、知らなくても法的な効力は発生します。
養子縁組は戸籍に記載されるため、手続き自体は公的に記録されます。
ただし、家族や関係者に事前に伝えられていないと、相続発生時に初めて判明することもあります。
このような場合でも、養子は法律上の「子」として相続権を有するため、遺産分割協議には必ず参加する必要があります。
知らなかったという事実だけでは、相続権が否定されることはありません。
親族間の混乱を防ぐためにも、養子縁組を行った際は、家族や相続に関わる人への事前共有が重要です。
兄弟を養子にした場合どんな影響がある?
兄弟を養子にすると、その人が“子ども”として扱われ、他の兄弟よりも相続順位が高くなります。
養子は法律上、実子と同じ「第一順位の相続人」になります。
兄弟姉妹を養子にすると親の財産を相続できる立場になり、他の兄弟より優先的に遺産を受け取れます。
しかし「なぜ兄弟姉妹のなかで一人だけ養子縁組して相続人となるのか?」といった不満・不信感が生じやすいです。
兄弟姉妹間の不公平感から、相続トラブルの火種となることも少なくありません。
兄弟を養子にするには、特別な事情(介護・扶養など)の説明や、他の相続人への事前の共有が欠かせません。



感情的な対立を防ぐためにも、慎重な判断と丁寧な対応が重要です。
養子縁組をしたら元の親の相続権はなくなるの?
以下のように、養子縁組の種類によって実親の相続権が残るかどうかは異なります。
| 普通養子縁組 | ・実親との親子関係は維持される ・養子は実親と養親の両方から相続できる |
|---|---|
| 特別養子縁組 | ・実親との親子関係が法律上完全に終了する ・実親の相続権はなくなる |
相続関係に大きな影響を与えるため、どちらの制度を選ぶかは慎重に検討しましょう。
制度の違いを正しく理解し、目的に応じて適切な手続きを行うことが大切です。
(普通養子縁組および特別養子縁組の効力)民法 第817条・第817条の2
出典:民法 第817条・第817条の2(e-Gov 法令検索)
普通養子縁組では、養子は実親との親子関係を維持したまま養親との親子関係を新たに結ぶ。
特別養子縁組では、養親との親子関係のみが存続し、実親との親子関係は終了する。
まとめ|養子縁組に関するトラブルは弁護士へ相談しましょう
養子縁組は、法的な親子関係を築ける有効な手段であり、相続にも大きな影響を与えます。
実子と同様に養子にも相続権が認められますが、関係性や目的によっては、以下のようなトラブルに発展する可能性があります。
- 実子との取り分をめぐる争い
- 親族からの反発や不信感
- 税務署による節税目的の否認や追徴課税
こうした問題を防ぐには、親族への事前説明・遺言書の作成・専門家の助言が欠かせません。
また、離婚や再婚など家族構成の変化に応じた見直しも重要です。
相続は「財産の分け方」だけでなく、「家族関係」にも影響する重大な節目です。
後悔のない選択をするためにも、早めの準備と冷静な判断を心がけましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応