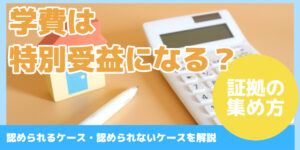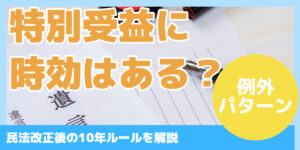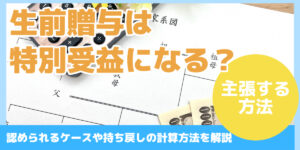【無料相談受付中】24時間365日対応
特別受益の持ち戻し免除とは?認められるケースや注意点を弁護士が解説

「特別受益の持ち戻しとは法的にどんな意味があるの?」
「特別受益の持ち戻し免除はどのようなケースで認められる?」
このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
特定の相続人が受けた利益(特別受益)は、相続時に遺産に加算して計算(持ち戻し)するのが原則です。
しかし、被相続人の意思を尊重し、この「持ち戻し」を免除する制度も存在します。これが「特別受益の持ち戻し免除」です。
この記事では、特別受益の持ち戻し免除とは何か、どのような場合に認められるのか、そして主張する際の注意点について、法律の専門家である弁護士が分かりやすく解説します。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
特別受益の持ち戻し免除とは?「被相続人の意思を優先する制度」
特別受益の持ち戻し免除とは、被相続人(亡くなった方)の意思に基づき、特定の生前贈与や遺贈を遺産分割の計算から除外する制度です。
本来、特別受益は相続人間の公平を図るため、遺産に加算して(持ち戻して)相続分を計算します。
しかし、被相続人が「この贈与は持ち戻さなくて良い」という意思を持っていた場合、その意思を尊重するのが本制度の趣旨です。
法的根拠は民法第903条3項にあります。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。引用:民法|第903条3項
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫この規定により、被相続人の明確な意思があれば、法定相続分とは異なる柔軟な財産承継が可能になります。
関連記事:特別受益とは?持ち戻しの計算方法や特別受益として扱われる贈与のパターンを分かりやすく解説
特別受益の持ち戻し免除が認められる3つのケース【判例あり】
特別受益の持ち戻し免除が法的に認められるには、大きく分けて3つのパターンがあります。
被相続人による明確な意思表示がある場合が基本ですが、法改正によって新設された配偶者への優遇措置や、裁判所の判断によって認められるケースも存在します。
本章では特別受益の持ち戻し免除が認められる主な3つのケースをみていきましょう。
被相続人による持ち戻し免除の意思表示があるとき(明示の持ち戻し免除の意思表示)
最も明確なのは、被相続人自身が「持ち戻しを免除する」という意思を法的に有効な形で残しているケースです。 これを「明示の意思表示」と呼びます。
前述の民法第903条3項が根拠となり、被相続人の意思が相続人間の公平性よりも優先されます。
具体的な方法としては、以下の2つが一般的です。
| 持ち戻し免除の意思表示の方法 | 例 |
|---|---|
| 遺言書に記載する | 「長男Aに生前贈与した事業用資金〇〇万円については、特別受益の持ち戻しを免除する」 |
| 贈与契約書に記載する | 「受贈者Bに贈与する自宅購入資金〇〇万円について、贈与者(被相続人)は相続時における特別受益の持ち戻しを免除する」 |
このように書面で明確な意思が残っていれば、他の相続人から特別受益の持ち戻しを主張されても、原則として免除を主張できます。
ただし、この意思表示は遺留分を侵害しない範囲でのみ有効です。 遺留分を超える部分については、免除の効力が制限され制限されますので注意しましょう。
婚姻年数が20年を超える配偶者への居住用不動産を贈与したとき(おしどり贈与)
2019年7月施行の改正民法により、婚姻期間が20年以上の配偶者に対し、居住用不動産(自宅)またはその取得資金を遺贈、または生前贈与した場合は、原則として「持ち戻し免除の意思表示があった」と推定されます。 (参照:法務省|民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正))
これは通称「おしどり贈与」と呼ばれる制度に関する改正です。「被相続人が配偶者に自宅を贈与するのは、長年の貢献に報いるためであり、相続分の前渡しではない」という考え方が背景にあります。
この規定により、残された配偶者は自宅を相続財産として計算に含める必要がなくなり、生活基盤を失うリスクが大幅に減少しました。
ただし、これはあくまで「推定」にすぎません。例えば、被相続人が、遺言書で「持ち戻しを免除しない」と書くなど、持ち戻し免除をしない明確な意思を残していた場合等は、免除が認められない点に注意が必要です。
関連記事:【弁護士監修】生前贈与は特別受益になる?認められるケースや持ち戻しの計算方法を解説
「黙示の持ち戻し免除の意思表示」が認められるとき
遺言書や契約書に明確な記載がなくても、被相続人の生前の言動や状況証拠から「持ち戻しを免除する意思があった」と法的に推認されるケースがあります。 これが「黙示の持ち戻し免除の意思表示」です。
例えば、以下のような事情が総合的に考慮されます。
- 被相続人が、特定の相続人(受贈者)を特に優遇する明確な動機があったか
- 他の相続人も、その贈与の事実や背景を長期間認識・容認していたか
- 贈与の額が、遺産全体に対して比較的小額であるか
- 被相続人が、その相続人の貢献(介護など)に報いる意図があったか
過去には、被相続人が、東京で一人暮らしをしていた相続人に対して約2年間で4回、合計250万円を送金していたこの送金について、被相続人が一人暮らしをする相続人を心配して生活資金を贈与したものとし、黙示の持ち戻し免除の意思表示を認めた判例もあります(平成15年8月8日 神戸家庭裁判所伊丹支部審判)。



ただし、これはあくまで例外的な扱いであり、裁判所が認めるハードルは非常に高いのが実情です。
特別受益の持ち戻し免除を他の相続人に主張する方法
特別受益の持ち戻し免除が認められる場合、それを他の相続人に主張し、遺産分割協議で合意を得る必要があります。
持ち戻し免除の根拠となる事実と、それぞれの主張方法は以下のとおりです。
| 根拠となる事実 | 主な主張の方法 |
|---|---|
| 明示の意思表示がある場合 | 遺言書や贈与契約書を提示する。 |
| おしどり贈与(民法903条4項) | 婚姻期間が20年以上であること(戸籍謄本など)と、贈与されたのが居住用不動産であること(登記事項証明書など)を証明する。 |
| 黙示の意思表示の場合 | 被相続人の生前の言動、他の相続人とのやり取り、贈与の背景事情などを具体的に説明し、免除の意思があったことを法的に構成して主張する。(※弁護士の助言が不可欠) |
まずは遺産分割協議(相続人全員での話し合い)の場で根拠と共に主張し、もし話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停では、調停委員を介して、持ち戻し免除の妥当性を法的な観点から話し合います。



調停でも不成立の場合は、「審判」に移行し、最終的に裁判官が持ち戻し免除の可否を判断する流れになるでしょう。
持ち戻し免除を主張するために必要な証拠・資料
特別受益の持ち戻し免除を主張する際、客観的な証拠の提示が不可欠です。 被相続人の明確な意思や、贈与の具体的な状況を示す資料を準備しましょう。
口頭での主張のみでは、他の相続人の同意を得たり、家庭裁判所に認められたりすることは困難です。特に遺産分割調停や審判の場では、以下の資料が重要視されます。
| 証拠の種類 | 具体的な資料の例 |
|---|---|
| 被相続人の明示の意思 | 遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言など) |
| 生前贈与の事実 | 贈与契約書、金銭の振込記録(預貯金通帳の写しなど) |
| 婚姻期間20年以上の夫婦間贈与 | 戸籍謄本(婚姻期間の証明)、不動産登記簿謄本(居住用不動産の贈与証明) |
| 黙示の意思(状況証拠) | 被相続人の生前の言動録、介護日誌、生活状況の記録、第三者の証言 |
このほか、被相続人との関係性を示す手紙やメールなども、補完的な証拠となり得ます。 特に「黙示の意思表示」を立証する場合、多角的な資料収集が求められるでしょう。



どのような証拠を集めるべきか判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
関連記事:特別受益は証拠がないと認められない?証拠の探し方と立証の流れを弁護士が解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
特別受益の持ち戻し免除における3つの注意点
特別受益の持ち戻し免除は強力な制度ですが、無条件にすべてが認められるわけではありません。 持ち戻し免除を主張するときは以下3つの注意点を把握しておく必要があります。
これらの注意点を怠ると、かえって相続トラブルを深刻化させる恐れがあるため注意しましょう。
持ち戻しが免除されても特別受益は遺留分の計算に含まれる
非常に重要な注意点として、「遺産分割(相続分)」の計算で持ち戻しが免除されても、「遺留分」の計算では持ち戻し(加算)されるというルールがあります。
遺産分割(相続分)の計算と、遺留分の計算における違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 遺産分割(相続分)の計算 | 遺留分の計算 |
|---|---|---|
| 目的 | 相続人間の実質的な公平を図る | 相続人に最低限保障される取り分を確保する |
| 持ち戻し免除 | 有効(被相続人の意思が優先される) | 原則無効(遺留分権利者の権利が優先される) |
| 計算対象 | 相相続開始時の遺産 +持ち戻し免除「されない」特別受益 | 相続開始時の遺産 + 持ち戻し免除「された」ものも含む特別受益 |
被相続人が「持ち戻しを免除する」と遺言書に記載があっても、その贈与によって他の相続人の遺留分(最低限の取り分)が侵害されていれば、その相続人は遺留分侵害額請求を行えます。
例として、遺産が1,000万円、相続人が子A・Bの2人、子Aが4,000万円の生前贈与(持ち戻し免除あり)を受けていたケースを考えてみましょう。
この場合、Aは遺産分割では持ち戻し免除を主張できますが、遺留分の計算基礎には4,000万円が加算されます。よってBはAに対して遺留分侵害額を請求できる可能性が非常に高いです。
関連記事:特別受益は遺留分侵害額請求の対象になる?対象とならない時効についても解説
特別受益の持ち戻しにおける期間制限がある
2023年4月1日の民法改正により、特別受益の持ち戻し計算の対象となる生前贈与の期間について、新たなルールが設けられています。(※施行は2025年4月1日以降の相続)
これまで特別受益の持ち戻しには明確な期間制限がありませんでした。
しかし民法の改正により、相続開始時(死亡時)から10年経過すると、新たに特別受益の持ち戻しの主張はできなくなりました。(民法904条の3)
関連記事:特別受益に時効はある?民法改正後の10年ルールを弁護士が解説
持ち戻し免除の主張により相続人とトラブルに発展する可能性がある
法的に持ち戻し免除が認められる権利があったとしても、それを主張することは、他の相続人との関係悪化に直結する可能性があります。
持ち戻し免除の主張は、他の相続人から見れば「自分だけ多くの財産をもらおうとしている」と映りがちです。 特に「黙示の意思表示」のような明確な証拠がないケースでは、感情的な対立が激化し、「争続」に発展するリスクが高まるでしょう。
持ち戻し免除の主張によるトラブルを回避するには、以下のような対策が不可欠です。
- 権利を主張する前に、他の相続人に対して誠実な説明を試みる。
- 話し合いが困難な場合は、すぐに弁護士を代理人として立て、法的な交渉に移行する。



法的な正当性だけを振りかざすのではなく、他の相続人の心情にも配慮し、冷静な話し合いを心がける姿勢が、円満解決には不可欠です。
関連記事:特別受益の主張は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用を解説【弁護士監修】
特別受益の持ち戻し免除に関するよくある質問
持ち戻し免除の意思表示の文例は?
遺言書や贈与契約書に記載する場合の基本的な文例は以下のとおりです。
遺言書に記載する文例
第〇条 遺言者は、相続人である長男・〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に対し、令和〇年〇月〇日に贈与した下記不動産の購入資金(金〇〇〇万円)について、民法第903条第3項に基づき、その特別受益の持ち戻しを免除する。
贈与契約書に記載する文例(特約条項)
(特別受益の持ち戻し免除)
第〇条 贈与者(甲)は、本契約に基づく金〇〇〇万円の贈与について、甲の相続開始時において、受贈者(乙)の特別受益として持ち戻すことを要しないものとする。
ただし、これらはあくまでも一例です。実際の作成時は必ず弁護士にご相談ください。
持ち戻し免除された財産は、相続税の対象になりますか?
持ち戻し免除された財産が、必ずしも相続税対象になるとは限りません。
特別受益の持ち戻しが免除されたとしても、相続税の計算では別ルールが適用されます。
例えば、相続開始前3年以内(順次7年以内に延長)の贈与は、持ち戻し免除に関わらず原則として相続財産に加算して相続税を計算します。
「持ち戻し免除=相続税もかからない」とはならないため、混同しないよう注意が必要です。
遺贈は特別受益になりますか?
相続人に対する遺贈(遺言による贈与)は、特別受益に該当する可能性があります。
遺贈は生前贈与とは異なり、「生計の資本のため」といった目的を問わず特別受益として扱われるのが一般的です。
ただし、生前贈与と同様に、被相続人が遺言書の中で「この遺贈については持ち戻しを免除する」と明確に意思表示していれば、持ち戻しの計算から免除されます。
まとめ|特別受益の持ち戻し免除に関するトラブルは弁護士に相談しよう
特別受益の持ち戻し免除は、被相続人の意思を尊重する重要な制度です。
しかし、遺言書などに明確な意思表示がない場合や「黙示の意思表示」をめぐっては、相続トラブルに発展しがちです。まずは感情的にならず、遺言書や贈与契約書などの内容を冷静に確認しましょう。
その上で、ご自身のケースが持ち戻し免除の対象になるか判断に迷う方、あるいは他の相続人から持ち戻しを主張されて困っている方は、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
早期に手を打つことで、家族間の無用な対立を防ぎ、ご自身の正当な権利を守ることにつながります。



相続問題は、法律論だけでなく、家族間の感情が複雑に絡み合う非常にデリケートな分野です。一人で抱え込まず、あなたの権利を守るためにも、ぜひ一度ご相談ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応