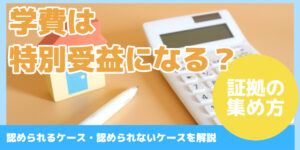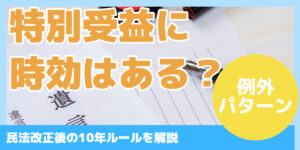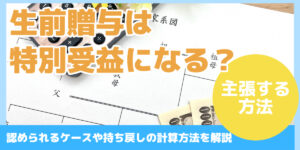【無料相談受付中】24時間365日対応
寄与分とは?認められる条件や請求方法をわかりやすく解説

「親の介護を長年一人で担ってきたのに、他の兄弟姉妹と相続分が同じなのは納得できない」
「実家の事業を無給で手伝ってきた貢献は、遺産分割で考慮されないの?」
このようなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
被相続人の財産の維持・増加のための特別な貢献をしたと認められる相続人がいる場合、他の相続人よりも取り分の上乗せができる「寄与分」という制度があります。
本記事では寄与分の概要や認められる条件、請求手続きの流れなどを解説します。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
寄与分とは「被相続人への特別な貢献が相続の取り分に反映される」制度
寄与分(きよぶん)とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした人がいる場合、その貢献を金銭として法定相続分に上乗せできる制度です。
この制度は、相続人間の公平を図るために民法で定められています。
(寄与分)
第九百四条の二
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。引用:民法|第904条の2
寄与分が考慮されなければ、介護や家業の手伝いを一切しなかった相続人も、多大な貢献をした相続人がいても法定相続分で遺産を分けることになり、不公平な遺産分割となってしまいます。
よって寄与分は、相続人の間で公平を保つための制度といえるでしょう。
寄与分の対象となる人は?
寄与分の対象となるのは「相続人のみ」です。ただし相続人以外の親族が被相続人への貢献をした場合、「特別寄与料」の請求が認められる場合があります。
本章では、寄与分や特別寄与料の主張ができる人について解説します。
対象となるのは「相続人のみ」
寄与分を主張できるのは、「相続人」に限られます。具体的には下記にあたる人です。
- 配偶者
- 子(またはその代襲相続人)
- 直系尊属(父母や祖父母)
- 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
例えば、長男が被相続人の介護を一身に担っていた場合、その長男は相続人として寄与分を主張できます。しかし、長男の妻が熱心に介護を手伝っていたとしても、彼女は相続人ではないため、「寄与分」を主張することはできません。
相続人以外でも「特別寄与料」を請求できる場合がある
寄与分を主張できるのは、相続人にあたる人のみです。しかし相続人以外であっても、被相続人への貢献分を「特別寄与料」として金銭を請求できる場合があります。
2019年7月1日より施行された民法の改正で、相続人ではない親族(例:先ほどあげた長男の妻など)が、無償で被相続人の介護などを行った場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました。(参照:法務省|相続に関するルールが大きく変わります)
寄与分と特別寄与料の主な違いは以下のとおりです。
| 制度 | 対象者 | 請求相手 |
|---|---|---|
| 寄与分 | 相続人 | 他の共同相続人 |
| 特別寄与料 | 相続人ではない親族 | 相続人 |
相続人ではない親族が特別寄与料を請求する時は、まずは直接相続人と直接交渉を行い、合意できない場合は、調停を申し立てて、調停委員を間に入れて話し合いを進めます。
それでも話し合いがまとまらない場合は審判へ移行し、提出された書類や主張内容を基に、特別寄与料の金額等を裁判官が判断する流れが一般的です。
特別寄与料請求時の注意点
特別寄与料を請求できるのはあくまでも「被相続人の親族」に限られます。内縁の妻など親族にあたらない方は請求できない点に注意が必要です。
また、特別寄与料の請求期限は短く、以下のいずれか早い期間内に請求手続きを始める必要があります。
- 相続と相続人を知ってから6か月
- もしくは相続開始から1年
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫後の紛争を防ぐためにも、期間内に請求の意思表示をした証拠として、内容証明郵便などを活用するとよいでしょう。


寄与分を主張するために必要な5つの条件
寄与分が法的に認められるためには、単に「手伝った」などといった事実だけでは不十分です。家庭裁判所などの第三者を納得させるための、客観的な条件を満たさなければなりません。
寄与分を主張するためには、以下の5つの条件を全て満たす必要があります。
自分のケースと照らし合わせ、寄与分を主張できるかを本章で判断してみましょう。
親族の助け合いの範囲を超えた「特別な貢献」であること
寄与分はあくまでも、親族の助け合いの範囲を超えた「特別な貢献」であることが重要です。
民法では、親子や夫婦、兄弟姉妹といった親族間には互いに助け合う義務(扶養義務)があると定められています。そのため、この通常の扶養義務の範囲内で行われるような協力は、寄与分には該当しません。
「特別な貢献」と判断されやすいケースとしては以下のとおりです。
- 要介護認定を受けた親のために、仕事を辞めて24時間体制で介護を行った。
- 自身の預貯金から、高額な先進医療の費用を立て替えて支払った。
- 長年に渡り無償で親の事業を手伝って支えた。
- 遠方に住みながらも、毎週末に飛行機で帰省して介護を続けた。
- 親の借金を代わりに返済した。
通常の助け合いと見なされるか、特別な貢献として認められるかの判断には、専門的な知識が必要な場合があります。ご自身で判断が難しいと感じる場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
給料や十分な対価を受け取っていないこと(無償性)
寄与分は「無償、もしくは社会通念上それに近い状態で貢献していたこと(無償性)」が極めて重要です。
被相続人への貢献に対して、相続人が十分な見返り(対価)を受け取っていた場合、雇用契約や贈与と見なされ、寄与分として認められない可能性があります。
無償性が認められ、寄与分を主張できる可能性が高い例は、以下のとおりです。
- 一切の報酬を受け取らずに、実家の農業を10年間手伝った。
- 被相続人からお小遣い程度の謝礼はもらっていたが、労働内容に見合わない少額だった。
寄与分の「無償性」を証明するには、対価を受け取っていないことを示す客観的な証拠が重要です。
例えば家業を無償で手伝っていたことを寄与分として主張する場合、以下のような書類が有効となるでしょう。
- 貢献した人(相続人)の給与明細書・源泉徴収票
- 被相続人の確定申告書・預金通帳 など
寄与分の主張をスムーズに進めるためにも、このような書類は早めに集めておきましょう。
一時的な手伝いではなく、長期間にわたり継続していること
寄与分が認められる貢献は、一過性のものでなく、ある程度の期間にわたって継続的に行われている必要があります。
貢献の期間が長ければ長いほど、その負担の大きさや貢献度が高いと評価されやすくなります。
法律で「何年以上」という明確な基準はありませんが、過去の判例などを見ると、数年以上の継続性が一つの目安となることが多いです。
継続性が高いと判断されやすい例としては、以下があげられます。
- 5年以上にわたり、被相続人の通院の付き添いを毎週欠かさず行った。
- 3年間にわたり被相続人の在宅介護を行った。
貢献の継続性を証明するためにも、被相続人に介護が必要な状態であったことがわかる診断書や、介護用品を購入したときの領収書などの客観的な書類を用意しておきましょう。
貢献によって被相続人の財産が維持・もしくは増加したこと
相続人の貢献が、被相続人の財産の「維持」または「増加」に直接的につながったという因果関係を説明する必要があります。
たとえ多大な労力を費やしたとしても、それが財産に影響を与えていなければ寄与分は認められません。
「もし寄与者(相続人)の貢献がなければ、相続財産はもっと少なかったはずだ」と客観的にいえることが必要です。
相続人の貢献で、財産が維持、または増加したと認められる例としては、以下があげられます。
| 貢献により財産が「維持」された例 | ・在宅介護をしたことで、本来かかるはずだった介護施設への入居費用(例:月額25万円)の支出を免れ、その分財産の減少が防げた。 ・無償で賃貸アパートの管理を行ったことで、不動産管理会社に支払う管理手数料が節約できた。 |
|---|---|
| 貢献により財産が「増加」した例 | ・事業資金として1,000万円を援助した結果、事業が成功して資産が増えた。 ・被相続人所有の土地の価値を高めるために私財を投じて整備し、売却価格が上昇した。 |
この因果関係を明らかにするには、「貢献がなければ発生したはずのコスト」や「貢献によって増加した価値」を具体的に示す、以下のような資料が求められます。
- 近隣の介護施設のパンフレットや料金表、見積書
- 不動産管理会社やリフォーム業者の見積書、契約書
- 金銭援助の事実がわかる預金通帳の写しや振込明細書
これらの資料を基に、寄与者である相続人の貢献がいくらの財産維持・増加につながったのかを客観的・合理的に算出することが重要です。
片手間ではなく、多くの時間と労力を費やしていること(専従性)
貢献が、ご自身の仕事や生活の合間に片手間で行ったものではなく、そのために多大な時間と労力を犠牲にしていること(専従性)が重要です。
専従性が高いほど、貢献の負担が大きかったと評価され、寄与分が認められやすくなります。
専従性が高いと判断されやすい例として、以下のようなケースがあります。
- 親の介護に専念するために、長年勤めた会社を早期退職した。
- 家業を手伝うために、自身のキャリアアップの機会を諦め、他の兄弟姉妹が都会で働く中、一人だけ地元に残った。
- 看病のため、病院の近くにアパートを借りて長期間滞在した。
専従性の高さを証明するには、貢献のために自身の仕事や生活にどのような影響があったかを示す、以下のような客観的な証拠が必要です。
- 介護離職した場合の、勤務先の退職証明書や離職票
- 勤務時間を短縮した場合の、給与明細書や源泉徴収票(収入の減少を証明)
- 介護に費やした時間を記録した日誌やタイムカード



専従性の高さを客観的に証明できそうな書類を複数揃えておきましょう。
寄与分が認められる代表的な5つのパターン
寄与分は、貢献の内容によって主に5つの類型(パターン)に分けられます。
ご自身の貢献がどのパターンに当てはまるか、複数のパターンにまたがるかを具体的にイメージすることが重要です。
それぞれのケースについて、どのような行為が評価されるのかを詳しく見ていきましょう。
療養看護型|被相続人の介護や看病を行ったケース
「療養看護型」とは、被相続人の介護や看病を行い「貢献」と認められるパターンです。
相続人が被相続人の介護や看病を献身的に行うことで、本来であれば外部の介護サービスなどに支払うはずだった費用を節約できます。その節約できた金額が、財産の維持に直接貢献したと評価されます。
ただし、単なる身の回りの手伝いでは不十分であり、あくまでも親族としての通常の協力関係を超えた、負担の大きい療養看護であることが重要です。
- 食事、入浴、排泄といった全面的な身体介助
- 頻繁な通院の送迎や入院中の付き添い
- 認知症の被相続人の見守りや、深夜の徘徊への対応
- 痰の吸引や床ずれの処置といった医療的ケア
特に、介護のために仕事を辞めたり、勤務時間を減らしたりした場合は、その負担の大きさが認められやすくなるでしょう。
家業従事型|被相続人が経営する事業(農業、商店など)を無給または低賃金で手伝ったケース
「家業従事型」とは、被相続人が営む家業を、相続人が無給、または市場の相場より著しく低い給与で長年手伝い、事業の維持や発展に貢献したと評価されるパターンです。
寄与者である相続人の労働力がなければ、事業の規模は縮小し、財産も減少していた可能性があるため、「被相続人への貢献」と評価されます。
このパターンでは、相続人が十分な報酬や対価を受け取っていないことを客観的に示す必要があります。
- 実家の農家を継ぐため、都会から戻り長期間にわたり無給で働いた。
- 親が経営する飲食店の調理や接客を、最低賃金を大幅に下回る給与で続けた。
- 経理や事務の専門知識を活かし、無償で家業の経営をサポートした。
もし寄与者である相続人が家業に従事していなければ、被相続人は他の人を雇う必要があり、その分の人件費が発生していたと考えられます。
その支払われなかった人件費相当額が、相続人の貢献分として考慮されるのです。
金銭出資型|事業資金や不動産購入資金などを援助したケース
「金銭出資型」は、相続人が被相続人に対して、自己の財産から金銭的な援助を行い、財産の維持・増加に直接的に貢献したパターンです。
- 被相続人が自宅を新築する際に、頭金として数百万円を援助した。
- 被相続人が事業を始める際の開業資金や、経営難に陥った際の運転資金を提供した。
- 被相続人が抱えていた借金を、代わりに一括で返済した。
- 高額な医療費や老人ホームの入居一時金を、被相続人に代わって支払った。
ただし、寄与分として認められるのは、返済を求めない「贈与」や「出資」の形での資金提供です。
単なる「貸したお金(貸付金)」は返してもらうべき債権であり、相続財産に含まれるため、寄与分にはなりません。
金銭出資型として寄与分を主張する場合、自分が被相続人へ行った行為が「貸付」にあたるのか「贈与や出資」にあたるのかを区別する必要があります。
扶養型|生活が困窮している被相続人を経済的に支えたケース
「扶養型」とは、相続人が被相続人に対し、通常の親族間の扶養義務の範囲を超えて経済的な援助を続け、被相続人の財産が消費されるのを防いだ場合に認められるパターンです。
扶養型として寄与分を主張するには、「被相続人が特別な扶養を必要とする状態にあったこと」「その扶養が相続人にとって大きな負担であったこと」を示す必要があります。
- 被相続人の年金だけでは生活できないため、毎月10万円の仕送りを10年以上続けた。
- 被相続人が住むアパートの家賃や光熱費を、長期間にわたり全額負担した。
- 本来であれば被相続人の預貯金から支払うべき施設利用料を、代わりに支払い続けた。
ただしこの類型は、親族間の扶養義務との線引きが難しく、主張が認められるハードルは他のパターンより高い傾向にあります。
扶養型として寄与分を主張したい場合は、弁護士に相談し、法的な視点からアドバイス・サポートを受けることをおすすめします。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
財産管理型|不動産の管理や賃料の徴収などを代わりに行ったケース
「財産管理型」とは、被相続人が賃貸アパートや駐車場などの収益不動産を所有しており、高齢や病気で自ら管理することが難しくなった場合に、相続人が無償でその管理を代行し、財産の維持に貢献したパターンです。
- 賃貸アパートの入居者募集、家賃の集金、クレーム対応などを全て無償で行った。
- 株式や投資信託などの金融資産について、専門的な知識を活かして無償で管理・運用し、資産を増やした。
- 被相続人に代わって、固定資産税の支払いや確定申告といった煩雑な手続きを無償で代行した。
相続人が被相続人に代わって管理をしなければ、不動産管理会社に委託する必要があり、その分の管理費用が発生する可能性があるでしょう。



相続人の貢献によって節約できた管理委託料相当額が、相続人の貢献として評価されるのです。
寄与分が認められない可能性がある5つの想定ケース
「これだけ貢献したのだから、寄与分が認められて当然だ」と考えていても、法的な観点から見ると主張が難しいケースが存在します。
後から「こんなはずではなかった」と後悔しないために、寄与分が認められない、または減額されてしまう代表的な5つのケースを事前に確認しておきましょう。
被相続人の介護・看病が「親子の扶養義務の範囲」と判断された
親子や夫婦といった近しい親族の間には、民法上、互いに協力し扶養する義務(扶養義務)があると定められています。
寄与分は、「扶養義務を超えた特別な貢献に対して認められるもの」です。そのため、貢献の内容が扶養義務の範囲内と判断されると、寄与分の主張は認められません。
- 高齢の親と同居し、身の回りの世話や家事をしていた。
- 定期的に実家に顔を出し、買い物を代行したり安否を確認したりした。
- 短期間の入院中に、身の回り品の差し入れや着替えの洗濯をした。
これらの行為は、多くの家庭でごく自然に行われている親族間の協力と見なされます。
特別な貢献と認めてもらうには、介護離職や多額の金銭的負担といった、扶養義務を明らかに超える客観的な事実が必要です。
家業に従事しており、相応の給与・生活費援助があった
寄与分が認められるための重要な要件の一つに「無償性」があります。これは、貢献に対して十分な対価を受け取っていない、ということです。
もし家業を手伝っていたとしても、その働きに対して社会通念上、相応の対価を得ていた場合は「労働契約」と見なされ、寄与分は認められません。
「相応の対価」には、直接的な給与以外にも様々なものが含まれます。具体的には以下のとおりです。
- 他の従業員と同水準の給与や賞与(ボーナス)
- 被相続人の家に無償で居住させてもらっていた(家賃相当額の利益)
- 食費や光熱費など、生活費の大部分を被相続人に負担してもらっていた
- 相続とは別に、生前贈与として多額の金銭や不動産を受け取っていた
これらの利益を総合的に判断し、提供した労働に見合うと評価された場合、「無償性」の要件を満たさないことになります。
貢献を裏付ける客観的資料がなかった
相続人間の話し合い(遺産分割協議)や家庭裁判所での手続きでは、感情的な訴えは通用しません。
「私が一番大変だった」「誰よりも親の面倒を見た」と主張するだけでは、法的な権利として認めてもらうことは困難です。
自分の貢献を第三者に納得してもらうためには、その事実を裏付ける客観的な証拠が重要です。証拠がなければ、他の相続人から「そんな事実は知らない」と反論された際に、それ以上話を進めることができません。
- 療養看護の事実を示す資料(介護日誌、病院の領収書、医師の診断書など)
- 金銭援助の事実を示す資料(通帳など銀行の振込記録、送金明細など)
- 家業従事の事実を示す資料(業務日報、取引先など第三者の証言)
たとえ被相続人の生前に多大な貢献をしていたとしても、それを証明する資料が何もなければ、寄与分の主張は認められないでしょう。
遺産分割協議が成立した後に寄与分を主張した
寄与分は、相続財産をどのように分けるかという「遺産分割」の前提となる重要な要素です。そのため、寄与分の主張は、必ず遺産分割協議が完了する前に行わなければなりません。
相続人全員が遺産分割の内容に合意し、遺産分割協議書に署名・押印したとします。この遺産分割協議書は法的に有効な契約書であり、一度成立すると、原則としてその内容を覆すことはできません。
後から「やはり寄与分を認めてほしい」と主張しても、他の相続人が応じない限り、やり直しは極めて困難です。
寄与分を主張したいのであれば、遺産分割協議の最初の段階で、その意思と具体的な根拠を明確に他の相続人に伝える必要があります。
寄与分主張の期間制限(相続開始後の10年)を経過した
寄与分そのものに時効はありません。
ただし、寄与分を巡って他の相続人と対立し、家庭裁判所に判断を求める場合、家庭裁判所での手続き(遺産分割調停・審判)には、実質的なタイムリミットが存在します。
法改正により、相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過すると、原則として法定相続分または指定相続分で遺産を分けることになりました。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
引用:民法904条の3
よって、相続開始後、10年を過ぎてから家庭裁判所に遺産分割を申し立てても、寄与分のような個別事情は考慮されません。また、遺産分割協議がまとまらないまま10年が経過してしまうと、家庭裁判所で寄与分を主張する手段が事実上失われてしまうのです。
ただし、相続開始から10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をすれば、10年を過ぎてしまっても寄与分を主張することが可能です(参照:民法904条の3)。



期間満了が迫っている場合は、早めに家庭裁判所へ調停を申し立てましょう。
寄与分はどうやって計算する?
寄与分の金額は、法律で正式な計算式が定められているわけではありません。
まずは相続人全員の話し合いによって、貢献の内容や期間、負担の度合いなどを総合的に考慮し、全員が納得できる金額を決めるのが原則です。もし話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所が最終的に判断することになります。
その際、実務では一定の計算式が用いられることが多いのも事実です。寄与分の計算については下記記事で詳しく解説しているので、こちらをご覧ください。
関連記事:寄与分は弁護士に相談すべき?制度の仕組みや計算方法・依頼すべきケースを解説
寄与分を主張・請求する手続きの流れ
寄与分は、自動的に認められるものではなく、貢献した相続人自身が、適切な手順に沿って権利を主張していく必要があります。
本章では、寄与分の主張・請求するときの具体的な手続きを詳しく紹介します。
1. 貢献の証拠を揃え、寄与分の金額を具体的に算出する
寄与分を主張する上では、被相続人への貢献を客観的に証明する証拠を揃えることが不可欠です。
感情的に「私だけが被相続人に貢献した」と訴えるだけでは、他の相続人や第三者を納得させることはできません。
集めるべき証拠としては、以下のようなものがあげられます。
| 寄与分のパターン | 証拠となりうる資料の例 |
|---|---|
| 療養看護型 | 介護日誌要介護認定通知書、病院や薬局の領収書、ケアマネージャーとの連絡記録、通院の交通費の記録 など |
| 家業従事型 | 業務内容や勤務時間の記録、無給・低賃金であったことを示す給与明細や源泉徴収票、第三者(取引先や従業員)の陳述書 など |
| 金銭出資型 | 銀行の振込明細書、預金通帳のコピー、被相続人が作成した借用書や念書 など |
これらの証拠を基に、前の章で解説した計算方法などを参考にして、主張したい寄与分の金額を具体的に算出します。
その際、法外な寄与分の金額を請求すると交渉がこじれる原因になってしまいます。根拠に基づいた、合理的で説得力のある金額を算出することが、円満な解決への鍵となるでしょう。
2. 遺産分割協議で他の相続人に寄与分の主張と根拠を提示し、合意を求める
証拠と金額の準備が整ったら、次は相続人全員が参加する遺産分割協議の場で、自分の寄与分を主張します。
協議をスムーズに進めるためにも、高圧的な態度や感情的な物言いは避け、集めた証拠を冷静に提示しながら、なぜこの金額が妥当と考えるのかを丁寧に説明しましょう。
「この貢献があったからこそ、皆で分け合える財産がこれだけ維持された」という視点で伝えることで、他の相続人の理解も得やすくなります。
ここで相続人全員があなたの主張に納得し、寄与分を考慮した遺産の分割方法に合意できれば、その内容を遺産分割協議書に明記します。その遺産分割協議書に全員が署名・押印すれば、法的に有効な合意となり、手続きは完了です。
3. 協議で合意できなければ、家庭裁判所に「寄与分を定める調停」を申し立てる
遺産分割協議でどうしても寄与分について合意に至らない場合や、そもそも話し合いが困難な場合は、家庭裁判所で「寄与分を定める処分調停」を申し立てます。これは遺産分割調停と同時に行うのが一般的です。
調停では、中立な調停委員が間に入り、話し合いによる円満な解決を目指します。感情的な訴えではなく、準備した証拠に基づいて冷静に寄与分を主張することが重要です。
もし調停で合意できなければ、手続きは自動的に「審判」へ移行します。審判は、提出された書面と証拠のみを基に、裁判官が寄与分の有無や金額を法的に判断し、最終的な決定を下す手続きです。



寄与分の主張で調停や審判に進む際は、弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
寄与分に関するよくある質問
ここからは、寄与分に関してよくある質問を紹介します。
寄与分の相場はいくらですか?
寄与分には、不動産価格のような決まった相場は存在しません。寄与分は一件一件の事情が全く異なり、個別に金額を判断する必要があるためです。
家庭裁判所が金額を判断する際には、以下のような様々な要素が総合的に考慮されます。
- 貢献の具体的な内容、期間、負担の度合い
- 貢献が無償であったか、もしくはそれに近い状態だったか
- 遺産総額の多寡
- 相続人の人数や被相続人との関係性
過去の裁判例では120〜200万円の寄与分が認められた例もあります。(参照:法務省|寄与分に関する裁判例)
ただし、どのような貢献であっても、寄与分が遺産の総額を超えることはありません。
寄与分の上限については、以下の記事もご覧ください。
寄与分と遺留分の違いは何ですか?
寄与分と遺留分は、どちらも相続財産の分け方に関わる重要な権利ですが、その目的や性質は全く異なります。
寄与分は自身の「貢献」に基づいて主張するプラスアルファの権利です。一方、遺留分は相続人という「立場」に基づいて法律上保障されている、最低限の取り分の権利といえます。
関連記事:寄与分と遺留分の関係性の記事を見る
関連記事:寄与分と遺留分はどっちが優先?よくあるケースからわかる関係性を徹底解説
寄与分主張整理表とは?
「寄与分主張整理表」とは、家庭裁判所に寄与分の調停などを申し立てる際に、主張を整理してわかりやすく伝えるために使用する書式のことです。
裁判所のウェブサイトで書式のテンプレートが公開されている場合があります。
この整理表には、主に以下のような項目を具体的に記入していきます。
- 寄与行為の内容(いつ、誰が、どこで、どのように貢献したか)
- 貢献行為が「特別」である理由
- 貢献によって財産が維持・増加したことの関連性
- 寄与分として請求する金額とその具体的な計算根拠
「寄与分主張整理表」を作成することで、自身の主張や証拠を客観的に見直すことができるのがメリットです。
特別寄与料の請求期間はいつまでですか?
相続人以外の親族が請求できる「特別寄与料」の請求期間は、非常に短く設定されており、厳格に適用されるため特に注意が必要です。
具体的には、以下のいずれか早い方が到来した時点で、請求権は時効によって消滅します。
- 特別寄与者が、相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月
- 相続開始の時から1年
相続人による寄与分の主張が「遺産分割協議がまとまるまで(実質最長10年)」であることと比較すると、特別寄与料は短い期間で請求を進めなければいけません。
特別寄与料の請求を行う場合は、早めに弁護士へ相談し、手続きを進めることをおすすめします。
まとめ|寄与分の主張をスムーズに行うなら弁護士への相談も視野に入れよう
寄与分とは、被相続人へ特別な貢献をした相続人(寄与者)がいる場合に、その貢献分を法定相続分に上乗せして遺産分割を行うものです。
ただし寄与分が認められるためには複数の条件があり、法的な知識と客観的な証拠がなければ、他の相続人の理解を得ることが難しいのが現実です。
もし、ご自身の貢献が寄与分にあたるかもしれないと感じたら、まずはその証拠を確保することから始めましょう。
その後、相続人間での話し合いが難航しそうな場合や、ご自身の貢献をどのように評価・計算すればよいかわからない場合は、できるだけ早めに相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。



専門家のサポートを得ることで、被相続人への貢献が寄与分として正当に評価され、円満な相続を実現するための道筋が見えてくるはずです。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応