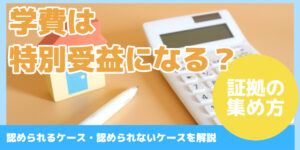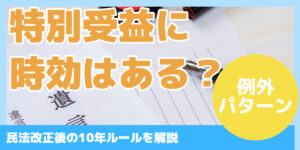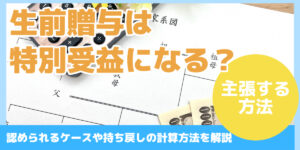【無料相談受付中】24時間365日対応
寄与分と遺留分はどっちが優先?よくあるケースからわかる関係性を徹底解説

「長年親の介護を一身に背負ってきたのに、他の兄弟と同じ相続分は納得できない…」
「寄与分と遺留分はどちらが優先されるのだろう…」
相続において、自身の貢献と法律で定められた権利がどう交差するのか、不安に感じますよね。適切に相続を実施するためには、寄与分と遺留分の関係性を理解することが欠かせません。
この記事では、相続における公平性を図るための2つの重要な制度、「寄与分」と「遺留分」の複雑で誤解されがちな関係性を徹底的に解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫両制度がどのような場面で衝突し、法的にどう整理されるのかを知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
そもそも寄与分・遺留分とは?制度の目的と違いを比較
「寄与分」と「遺留分」はいずれも相続に関する制度ですが、目的や性質・問題になるシーンは全く異なります。
適切に相続を行うためには、まずそれぞれの言葉の意味をしっかり理解することから始めましょう。
寄与分とは
寄与分とは、特定の相続人が被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加に対して「特別な貢献」をした場合に、その貢献度に応じて法定相続分に上乗せして財産を取得できる制度です。
民法第904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
出典:e-Gov法令検索|民法
この制度の目的は、相続人間の実質的な公平を図ることにあります。例えば、無償で家業を手伝ったり、長年にわたり献身的な介護を行ったりした相続人と、そうでない相続人が同じ相続分では不公平が生じるため、その差を是正するために設けられています。
ただし、寄与分が認められるハードルは低くありません。「特別な寄与」と評価されるためには、以下のような厳しい要件を全て満たす必要があります。
- 親族として通常期待される範囲を超える貢献であること
- 無償または無償に近いこと
- 貢献と財産の維持・増加との間に明確な因果関係があること
たとえば「仕事を辞めて5年以上にわたり親の介護に専念し、高額な介護施設の費用を節約できた」といったケースであれば「特別な寄与」と認められる可能性が高いでしょう。
一方で「週末に実家へ顔を出し身の回りの手伝いをしていた」「月1回だけ通院に付き添った」という程度では、寄与分として認められるのは難しいのが実情です。
関連記事:寄与分とは?認められる条件や請求方法をわかりやすく解説
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母など)といった一定の相続人に対して、最低限保障されている遺産の取り分を指します。
この制度の根底にあるのは、遺された家族の生活保障や遺産の公平な分配という考え方です。たとえ遺言書に「全財産を愛人に遺贈する」と書かれていたとしても、他の相続人は自身の遺留分に相当する金額を請求することが可能です。
ただし、この権利は被相続人の兄弟姉妹には認められていない点には注意が必要です。あくまで生活保障の必要性が高い近親者を保護する趣旨であることを覚えておきましょう。
遺留分については、以下の記事でも詳しく解説しています。遺留分について理解を深めたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介
寄与分と遺留分はどちらが優先?複雑な関係を3つのポイントで整理
「寄与分と遺留分はどちらが優先されるのか?」は、相続問題でもよく聞かれる質問の一つです。ただ、実はこの問いの立て方自体が、両者の関係を正しく理解する上での妨げになっています。
寄与分と遺留分は単純な優先劣後関係ではなく、それぞれが異なるルールと手続きで運用される独立した制度として捉えることが重要です。
ここでは、その複雑な関係を3つのポイントに分けて解説します。
ポイント1:単純な優先関係はなく、主張する手続きが全く異なる
寄与分と遺留分に、単純な優劣関係は存在しません。両者が主張され、判断される法的な手続き(土俵)が全く異なるためです。
| 項目 | 寄与分 | 遺留分侵害額請求 |
|---|---|---|
| 主張の場面 | 遺産分割の中 | 独立した民事請求 |
| 担当裁判所 | 家庭裁判所(調停・審判) | 家庭裁判所または地裁・簡裁 |
| 性質 | 公平な分割を目的とする | 侵害された権利の回復を目的とする |
寄与分は、相続財産を具体的にどう分けるかを決める「遺産分割」のプロセスの中で主張されます。
まずは相続人間の話し合い(遺産分割協議)で決め、まとまらなければ家庭裁判所での調停や審判へと進みます。その後、寄与分を考慮するかどうかや、どの程度考慮するかを判断し、最終的な遺産分割をします。
一方、遺留分侵害額請求は、遺産分割の結果や遺言・贈与によって自己の遺留分が侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払いを求める民事上の権利です。
まず遺留分を侵害した人に任意の支払いを請求します。請求に応じない場合には、家庭裁判所で『遺留分侵害額の請求調停』を申し立て、調停不成立や不要事由がある場合には民事訴訟(請求額により簡裁/地裁)へ進みます。なお、実務では最初から訴訟を起こすことも少なくありません。
この遺留分侵害額請求においては、寄与分は考慮されないことになっているため、寄与分と遺留分でどちらが優先されるかという議論自体がありません。
このように、両者は最終的な判断をする場合には異なる裁判所で、異なる手続きに則って判断されるため、「どちらが優先か」という問いは成り立ちません。
ポイント2:遺留分の計算において寄与分は考慮されない
遺留分がどれだけ侵害されているかを計算する際、基礎となる財産額(遺留分算定の基礎財産)を確定させる必要があります。この計算は、被相続人が亡くなった時点の財産に、一定期間内の生前贈与などを加え、借金などの債務を差し引いて算出します。
ここでの重要なポイントは、民法で定められたこの計算式の中に、「寄与分」を加算したり減算したりする項目は存在しないということです。つまり、ある相続人にどれだけ高額な寄与分が認められようとも、他の相続人の「遺留分額」そのものが変動することはありません。
寄与分は、あくまで遺産分割の最終的な取り分を決める段階で考慮されるものであり、遺留分の権利額を算定する段階では完全に切り離して考えられます。
ポイント3:寄与分の決定において「その他一切の事情」として遺留分の存在は考慮される可能性がある
寄与分の金額には、「他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で」といった上限規定がありません。あるのは「財産の価額-遺贈の価額の残額を超えない範囲で」という規定のみです。
そのため、理論上は、ある相続人に認められた寄与分が非常に高額であった結果、他の相続人が受け取る財産がその人の遺留分額を下回ってしまう事態は起こり得ます。
しかし、実際の裁判実務では、上記のような事態は極力避けられる傾向にあります。過去の重要な判例(東京高裁平成3年12月24日決定)では、家庭裁判所が寄与分を定める際には、他の相続人の遺留分についても「その他一切の事情」として考慮すべきである、との考え方が示されました。
したがって、裁判所の手続きにおいて、他の相続人の遺留分を侵害するほどの高額な寄与分が認められるのは例外的です。具体的には、寄与を主張する相続人の貢献が遺産の大部分を形成したといえるような「特段の事情」がある極めて例外的なケースに限られると考えてよいでしょう。
遺留分がもらえる条件や割合について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:【弁護士監修】遺留分は必ずもらえる?割合や侵害された場合の対処法・事例を解説
関連記事:遺産相続で寄与分に上限はある?上限まで寄与分を認めてもらうために必要な行動を解説
寄与分・遺留分の主張でよくあるトラブル例
寄与分や遺留分は、相続における公平性を実現するための重要な制度です。しかし、法律で定められた権利だからといって、必ずしもスムーズに主張が認められるわけではありません。
むしろ、金銭が絡む相続の話し合いでは、これらの主張がきっかけで親族間の感情的な対立が激化し、深刻なトラブルに発展するケースが非常に多いのが実情です。
ここでは、寄与分や遺留分の主張においてよくある、代表的な3つのトラブル例を紹介します。
長年にわたり介護・看護したのに認められない
「親の介護を一身に背負ってきたのだから、その分は財産を多くもらって当然だ」と考えて寄与分を主張しても、他の相続人から「親族なのだから当たり前だ」と反論され、トラブルになるケースはよくあります。
寄与分として法的に認められる介護は、親族として通常期待される扶養義務の範囲を超える「特別な貢献」でなければならないとされています。
例えば、ヘルパーを頼めば月に数十万円の費用がかかるような介護を相続人が無償で長期間行っていた場合などは、「特別な貢献」と認められる可能性があります。また、介護のために仕事をやめたなどの事情があれば、なお「特別な貢献」と認められやすくなります。
しかし、その貢献度を客観的な証拠で示すのは簡単ではありません。介護日誌や医療費・交通費の領収書といった証拠がなければ適切な評価を得られず、感情的なしこりだけが残る結果になりがちです。
家業における無償同然の労働が「給料をもらっていた」と反論される
被相続人が経営していた商店や工場、農家などを無給同然で手伝い、そのおかげで財産が維持・増加したとして寄与分を主張するケースです。
この場合、他の相続人から「給料や生活費の援助という形で、既に対価を受け取っていたのではないか」と反論されるのが典型的なトラブルのパターンといえます。
例えば、給与明細はないものの、毎月一定額の生活費を受け取っていたり、家賃や光熱費を被相続人に負担してもらっていたりした場合、その経済的利益が労働の対価とみなされ、寄与分が否定されることがあります。
たとえその金額が、本来もらうべき給与よりはるかに低かったとしても、「無償またはそれに近い状態だった」ことを明確な証拠で立証できなければ、貢献を正当に評価してもらうことは難しくなるでしょう。
他の相続人が「遺留分」を主張してくる
寄与分と遺留分はまったく別の権利であり、この2つが衝突することでトラブルはさらに複雑化します。
例えば、被相続人が「私の介護を最後まで看てくれた長男に、全財産を相続させる」という遺言を残したとします。長男の多大な貢献を考慮すれば、一見すると妥当な内容に思えるかもしれません。
しかし、相続人には法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」があります。そのため、他の兄弟姉妹は、遺言の内容にかかわらず「自分たちの遺留分が侵害されている」として、財産を多く受け取った長男に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。こ2つは全く別の制度だからです。
その結果、長男は自身の寄与があるにもかかわらず、他の兄弟姉妹へ遺留分相当額の金銭を支払わなければならないという事態に陥る可能性があります。このように、新たな争いへと発展するケースは少なくありません。
なお、遺留分について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介
寄与分と遺留分で問題になりやすい3つのケース
寄与分と遺留分の関係は、具体的な事例に当てはめてみることで、より深く理解できます。
ここでは、相続の現場で実際に起こりがちな3つの典型的なケースを取り上げ、それぞれの法的な考え方を解説します。
これらのケースを通じて、抽象的なルールがどのように現実の問題に適用されるのかを見ていきましょう。
ケース1:遺留分を侵害するほど高額な寄与分は認められるか
他の相続人の遺留分を侵害する可能性のある高額な寄与分も、裁判所で法的に認められることはあり得ます。また、裁判所が認めなくても相続人間の話し合い(遺産分割協議)で全員が合意すれば、遺留分を侵害するような寄与分を考慮して遺産分割協議を成立させることも可能です。
しかし、話がまとまらず家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれた場合、裁判所が遺留分を侵害する寄与分をそのまま認める可能性は低いでしょう。裁判所は、寄与分を定めるにあたり、他の相続人の遺留分を考慮する傾向にあるためです。
寄与分は認められつつも、最終的には侵害した遺留分相当額を金銭で支払う形で調整が図られることになります。よほどの特段の事情がない限り、裁判所が遺留分を侵害する寄与分を積極的に認めることはありません。
ケース2:遺留分侵害額請求に対し、寄与分を主張して支払いを拒否できるか
遺留分侵害額請求をされた側が、「自分には寄与分があるから支払わない」と主張して支払いを拒否することはできません。
遺留分侵害額請求は、あくまで「遺贈」や「贈与」を受けた人に対して、その侵害額の支払いを求める手続きで、その額を算出するにあたって寄与分は考慮要素とされていないからです。主張する手続きが異なるため、一方の権利を他方の権利に直接ぶつけて相殺するような扱いは認められていません。
遺留分侵害額請求をされた場合は、まずその請求が正当なものか(時効や計算の妥当性など)を検討する必要がありますますが、寄与分を考慮することができないことは覚えておきましょう。
自身の寄与を主張することができる場合は、遺留分侵害額請求の場面ではなく、遺産分割調停で主張・決定します。
遺留分侵害請求について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は?相場や安く抑える方法を解説
ケース3:寄与分が認められる相続人に対して遺留分侵害額請求はできるか
寄与分が認められたという理由では遺留分侵害額請求をすることはできません。
なぜなら、遺留分侵害額請求の対象となるのは、あくまで「遺贈(遺言による譲渡)」または「贈与」によって財産を得た人に限られているためです。
寄与分は、あくまで相続分の修正要素であるため、寄与分が認められたからといって受遺者・受贈者になるわけではありません。
別途遺言によって遺贈を受けていたり、生前に贈与を受けていない限り、遺留分侵害額請求の対象外となることを覚えておきましょう。



上記のほかにも、さまざまなケースが考えられます。一度、ご自身のケースを弁護士に相談してみるとよいでしょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
自分の貢献度を主張したい!寄与分が認められるケースと証拠集めのポイント
「自分の頑張りを正当に評価してほしい」と願う方にとって、寄与分制度は重要な権利です。しかし、その主張が認められるためには、法律が定める「特別な寄与」に該当すること、そしてそれを客観的な証拠で裏付けることが不可欠です。
ここでは、寄与分が認められる典型的なケースと、そのために必要な証拠集めのポイントを解説します。
寄与分が認められる5つの類型と具体例
寄与分は、その貢献の態様によって大きく5つの類型に分類されます。自分の状況がどれに当てはまるかを確認してみましょう。
| 寄与の類型 | 寄与の類型 具体例(認められやすいケース) | 立証に有効な証拠 |
|---|---|---|
| 1.家業従事型 | 被相続人が経営する個人商店で、10年以上にわたり給与を受け取らずに働き、店の経営を支えた。 | ・被相続人の確定申告書 ・業務日誌 ・タイムカード ・取引先とのメールや証言 |
| 2.金銭等出資型 | 被相続人が自宅を購入する際に、頭金として500万円を援助した。また、被相続人の事業の運転資金が不足した際に、300万円を貸し付けではなく贈与した。 | ・自身の口座からの振込記録 ・被相続人の通帳の入金記録 ・不動産売買契約書 ・金銭贈与の念書 |
| 3.療養看護型 | 要介護5の認定を受けた被相続人を介護するため、仕事を退職した。5年間にわたり、ほぼ24時間体制で在宅介護を続けた。 | ・医師の診断書 ・要介護認定通知書 ・詳細な介護日誌 ・介護用品の領収書 ・自身の退職証明書 |
| 4.扶養型 | 病気で収入が途絶えた被相続人に対し、15年間にわたり毎月10万円の生活費を仕送りし続けたことで、被相続人の預貯金の減少を防いだ。 | ・自身の口座からの定期的な振込記録 ・被相続人の非課税証明書など要扶養状態を示す資料 |
| 5.財産管理型 | 被相続人が所有する賃貸アパートの管理を全面的に請け負い、家賃の徴収、入居者対応、修繕手配などを無報酬で行い、安定した収益を維持した。 | ・賃貸借契約書 ・入居者や業者とのやり取りの記録(メール等) ・管理業務に関する記録 ・管理を業者に委託した場合の見積書 |
評価の軸は、期間の長さ・代替可能性・金額換算の客観性・因果関係の明確さです。
たとえば療養看護では、介護保険サービスを使った場合との差額を代替人件費として見積もる方法が用いられます。家業従事では、賃金相当額や利益増加分を材料に、過大評価・二重取りを避ける調整が行われます。
寄与分の主張に必要な証拠
寄与分の主張は、「これだけ大変だった」という感情的な訴えだけでは認められません。他の相続人や裁判所を納得させるためには、客観的な証拠が何よりも重要です。
証拠集めのポイントは、以下の4項目を証明することです。
- 貢献の特別性
- 無償性
- 期間
- 因果関係
例えば、療養看護型であれば、単に「介護した」というだけでなく、以下の要素を診断書や介護日誌、給与明細といった第三者が見てもわかる資料で示す必要があります。
- 要介護度がどれだけ高く、専門職に頼めば月々いくらかかったか(財産維持への貢献)
- そのために自分の仕事をどれだけ犠牲にしたか(特別性)
- 被相続人から対価を受け取っていないこと(無償性)
証拠は、時間が経つほど集めにくくなります。将来的に寄与分を主張する可能性が少しでもあるなら、日頃から日記や記録をつけ、書類を保管しておきましょう。



どのような証拠が必要かがわからない場合は、弁護士に相談して証拠集めのアドバイスを受けることも重要です。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
寄与分や遺留分で揉めた際に弁護士に相談するメリット
寄与分や遺留分をめぐる争いは、法律の知識だけでなく家族間の感情も絡み合うため、当事者同士での解決が非常に困難な場合があります。感情的な対立が深刻化する前に、専門家である弁護士に相談することが大切です。
寄与分や遺留分で揉めた際に弁護士に相談することで、主に以下のようなメリットを得られます。
以下、それぞれ具体的に解説します。
関連記事:寄与分は弁護士に依頼すべきケースを解説
関連記事:遺留分問題を弁護士に相談するメリットを解説
必要な証拠の収集方法についてアドバイスをもらえる
寄与分を主張するにせよ、遺留分侵害に反論するにせよ、その成否は「証拠」にかかっています。しかし、何が法的に有効な証拠となるのかを一般の方が判断するのは容易ではありません。
弁護士に相談すれば、ご自身の主張を裏付けるためにどのような証拠が必要か、それをどうやって集めればよいか、具体的かつ的確なアドバイスを受けられます。
これにより、無駄な労力を省き、効果的な準備を進めることが可能になるでしょう。
複雑な相続財産の評価や計算を正確に行ってくれる
相続財産に不動産や非上場株式などが含まれる場合、その評価額を正確に算出することは専門家でなければ困難です。しかも、相続を専門とする弁護士でなければ、これらの財産の評価は弁護士でも困難です。
遺留分や寄与分の計算は、この財産評価が基礎となるため、最初の評価額が間違っていると、請求できる金額も不正確になってしまいます。
弁護士に依頼すると、必要に応じて不動産鑑定士や税理士などの専門家と連携し、財産の価値を正確に評価・算定してくれます。また、相続専門の弁護士はある程度自分で評価して目安を算出することも可能な場合があります。
面倒な交渉や書類作成を弁護士に任せられる
他の相続人との交渉や、家庭裁判所に提出する調停申立書、訴状などの専門的な書類の作成は、精神的にも時間的にも大きな負担となります。
弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きをすべて任せることが可能です。
法的な知識に基づいた的確な書類作成はもちろん、交渉の代理人として前面に立ってもらうことで、ご自身の負担を大幅に軽減できます。
感情的な対立を避け、冷静な交渉が期待できる
相続問題では、感情的な対立も少なからず存在します。肉親だからこそ、一度生じた溝は修復が難しくなりがちです。
弁護士という第三者が間に入ることで、当事者同士が直接対峙するのを避けられます。弁護士は、感情的な主張を法的な論点に整理し、相手方と冷静に交渉を進めるためです。
無用な争いを避け、建設的な話し合いを通じて、双方にとって納得のいく解決を目指すことが期待できるでしょう。
以下の記事では、相続に強い弁護士の選び方について詳しく解説しています。どのように弁護士を選べばよいかわからず悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:相続に強い弁護士の選び方とは?確認すべき8つのポイントや費用相場を解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
寄与分・遺留分を正しく理解するための弁護士相談のタイミング
寄与分や遺留分の主張は、法的な知識だけでなく、どのタイミングで行動を起こすかが重要です。時期を逸すると、本来得られるはずだった権利を失うことにもなりかねません。
ここでは、ご自身の状況に合わせて最適な行動を取れるよう、弁護士に相談すべき代表的な4つのタイミングを解説します。
相続が開始する前
相続トラブルを未然に防ぐ最善の策は、相続が開始する前の「生前対策」です。
被相続人がご健在のうちに弁護士へ相談すれば、将来の寄与分の主張を見据え、介護や家業への貢献度を示す証拠(日記、写真、資金移動の記録など)を効果的に集める方法について助言を受けられます。
また、特定の相続人に財産を多く残したいと考える被相続人にとっては、他の相続人の遺留分を侵害しない、法的に有効な遺言書の作成サポートや、家族信託を利用した相続対策も受けられます。
生前に手を打っておくことで、相続人間の感情的な対立を避け、円満な相続を実現できる可能性が格段に高まるでしょう。
相続が開始した直後(遺産分割協議の前)
相続が発生したら、遺産分割協議を始める前に弁護士へ相談することをおすすめします。
この段階で専門家が介入するメリットは、感情的な話し合いになる前に、法的な観点から状況を正確に把握し、交渉の土台を固められる点です。
まずは戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定させ、同時に不動産や預貯金などの相続財産を漏れなく調査します。
その上で、ご自身の寄与分や遺留分がどの程度主張できるのか、具体的な見通しを立てることが可能になります。
遺産分割協議が始まったが、話がまとまらない時
相続人同士で遺産分割について話し合いを始めたものの、寄与分や遺留分の主張が対立し、議論が平行線をたどるケースは少なくありません。当事者だけでは感情的なもつれから抜け出せず、話し合いが膠着状態に陥ってしまいます。
このような場合も、弁護士が第三者として介入すべきタイミングです。
弁護士が代理人として交渉の窓口となることで、感情的な対立を避け、法的な根拠に基づいた冷静な議論が可能になります。
また、家庭裁判所での調停や審判といった次のステップに進むべきかの判断や、その際の手続きもスムーズに進められるため、問題の長期化を防げるでしょう。
なお、遺産分割調停を申し立てられた場合の対処法について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:相続で遺産分割調停を申し立てられたらどうする?対応方法や欠席するリスクを解説
遺留分侵害額請求の時効が迫っている時
遺留分を請求する権利には、「相続の開始と遺留分を侵害する事実を知った時から1年」という短い時効が定められています。この期間を過ぎると権利は消滅し、請求できなくなるため注意が必要です。
もし「遺言書の内容が不公平だ」と感じ、時効が迫っているかもしれないと少しでも不安に思ったら、迷わず直ちに弁護士に相談しましょう。時間がない状況でも、弁護士はまず時効の進行を中断させるための「内容証明郵便」を迅速に送付し、権利を保全してくれます。
その上で、相手方との交渉や法的手続きを代行してくれるため、知識不足から権利を失うという最悪の事態を回避することが可能です。
なお、遺留分の事項については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
寄与分と遺留分に関するよくある質問(FAQ)
寄与分と遺留分に関しては、具体的な状況に応じた疑問が多く寄せられます。ここでは、特に質問の多い3つのテーマについて、専門家の視点からお答えします。
遺言で寄与分が指定されていても遺留分は請求できる?
前提として、遺言で「寄与分」そのものを指定することはできません。寄与分は、相続人間の協議または家庭裁判所の審判によって決定されるものだからです。
ただし、遺言で「長年の介護に感謝し、長男に財産の8割を相続させる」といったように、特定の相続人の貢献に報いるために多くの財産を与えること(実質的な寄与分の趣旨を含む遺贈)は可能です。
このような遺言によって他の相続人の遺留分が侵害された場合、その相続人は遺留分侵害額請求を行えます。遺留分は遺言よりも優先される強力な権利だからです。
したがって、遺言の内容がどうであれ、ご自身の遺留分が侵害されていれば、その権利を主張することは可能です。
相続人ではない親族(子の配偶者など)の介護の貢献は認められる?
相続人ではない親族、例えば「長男の妻」が被相続人の介護に尽力した場合、その方は相続人ではないため、「寄与分」を主張することはできません。
しかし、このような不公平を是正するため、2019年7月の民法改正で「特別寄与料」という制度が創設されました(民法第1050条)。
これにより、相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が無償で療養看護などの労務提供を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになっています。
寄与分が相続分の上乗せであるのに対し、特別寄与料は相続人に対する金銭請求権であるという違いがあります。また、請求できる期間が非常に短い(相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内・または相続の開始から1年を経過した日まで)ため、注意が必要です。
出典:e-Gov法令検索|民法
寄与分を主張できる期間に時効はある?
かつて寄与分の主張には明確な時効規定がありませんでした。
しかし法改正により、2023年4月1日以降、寄与分の主張には「相続開始の時から10年」という期間制限が設けられました(民法第904条の3)。この期間を過ぎると、原則として寄与分を主張できなくなります。
なお、この期間制限は特別受益の主張においても同様に適用されます。
したがって、相続開始から10年たってしまうと、寄与分や特別受益などの個別事情を考慮した遺産分割はできなくなってしまうのです。
この法改正は、長期間確定しない相続関係を早期に安定させることを目的としています。相続が発生した際は、自身の権利を主張するためにも、早めに行動を起こすことが大切です。
出典:e-Gov法令検索|民法
まとめ|寄与分と遺留分の関係性を理解して適切に相続を進めよう
この記事では、相続における「寄与分」と「遺留分」の2つの重要な制度について、目的の違いから複雑な相互関係などを解説しました。
寄与分は「過去の貢献に対する公平性」を目的とし、遺留分は「未来の生活保障」を目的とする全く別の制度です。両者の間に単純な優先関係はなく、それぞれが異なる法的手続きの中で判断されます。遺留分の計算に寄与分は影響しませんが、高額な寄与分の認定が結果的に他の相続人の遺留分を侵害する可能性も理論上は存在します。
もし自身の貢献を主張したいなら、まずはその貢献を客観的に証明する証拠を集めることから始めましょう。



また、感情的な対立が深まる前に、専門家である弁護士の力を借りることも重要です。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応