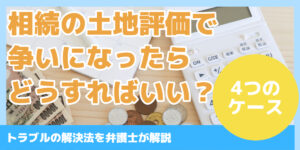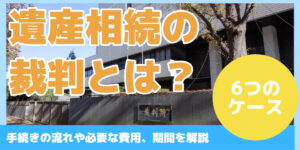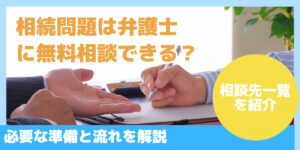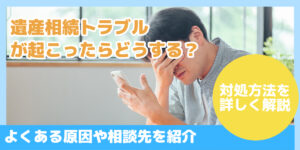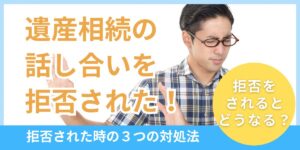【無料相談受付中】24時間365日対応
代襲相続でよくあるトラブルとは?回避策や発生後の対応を弁護士が解説
「代襲相続で自分の取り分がどうなるのか分からない」
「親族間で話がこじれて、遺産分割協議が一向に進まない」
代襲相続が発生する家庭では、このような悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。
被相続人の孫や甥姪が相続人となる仕組みは複雑で、理解不足から思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。
本記事では、代襲相続の基本知識から実際に起こりやすいトラブルの例、回避策を詳しく解説します。
代襲相続の仕組み:被相続人の子供や兄弟姉妹が亡くなっている際、孫や甥姪が代わりに相続権を持つ制度です。
代襲相続の範囲:子供・孫の直系は下の世代へ無制限に続きますが、兄弟姉妹の代襲(甥姪)は一代限りで終了します。
相続税の注意点:代襲相続人が増えることで基礎控除額が増えるメリットがある一方、甥姪には「2割加算」が適用されます。
代襲相続のトラブルの回避策:面識のない親族との協議は揉めやすいため、財産調査や遺言書の確認など、早めの専門家相談が鍵となります。
トラブルを未然に防ぐために生前できる対策も紹介しているため、代襲相続でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
そもそも代襲相続とは?【基礎知識】
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった相続人が亡くなっていた場合に、その子どもや孫などが代わりに遺産を受け継ぐ制度です。
ここでは、代襲相続の基本的な考え方や仕組みを順を追って解説します。正しく代襲相続のステップを踏めるよう、まずは基礎知識を押さえておきましょう。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫相続人の範囲を誤認したまま協議を進め、後から真の相続人が現れてすべてやり直しになるケースは後を絶ちません。
とくに甥・姪の子や養子の子が関わる場合は、戸籍謄本を慎重に読み解く必要があるため、注意が必要です。
代襲相続とは「被相続人の孫や甥姪などが財産を相続すること」
代襲相続とは、本来であれば相続人となる立場の人が既に亡くなっている場合に、その子や孫が代わって相続人となる制度です。
たとえば被相続人の子どもが死亡しているとき、その子の子ども、すなわち孫が相続人になります。被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人になる仕組みです。
また、代襲相続は法定相続人の死亡以外でも「相続廃除」と「相続欠格」があった場合に発生する場合があります。それぞれの詳細は以下のとおりです。
| 法定相続人の死亡以外で代襲相続が発生するケース | 詳細 |
|---|---|
| 相続廃除 | 被相続人が生前に、何かしらの理由で相続人を廃除する手続きを家庭裁判所で行い相続権を奪う制度 |
| 相続欠格 | 遺言書の偽造や隠匿などの不正行為を行った相続人が、法律上当然に相続権を失う制度 |
いずれの場合も、その子や孫に権利が移るため、代襲相続を進める際は死亡以外のケースも押さえておくことが重要です。
遺言書の効力や無効なケースは、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:遺言書の効力はどこまで?いつから効力が発生する?書き方や無効なケースも解説
代襲相続の相続分は「相続人が得るはずだった相続分と同じ」
代襲相続では、もともと相続人となるはずだった人の相続分を、そのまま代襲相続人が引き継ぎます。
たとえば、父・母・子という家族構成で父が亡くなった場合、母は2分の1、子は2分の1を相続します。
しかし、子どもが既に亡くなっていた場合は、孫が代襲相続人となり、本来の子が受け取るはずだった2分の1を引き継ぐ仕組みです。
なお、孫がいるときは2分の1の相続分を均等に分け合います。孫が2人であれば、それぞれ4分の1ずつ相続し、母の相続分は2分の1のままです。代襲相続だからといって、相続分が減らされることはありません。
法定相続分(遺産を分ける目安となる割合)については、別記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:法定相続分とは?法定相続人の順位と計算方法や遺留分との違いを解説!
代襲相続がどこまで続くかは相続人が誰なのかによって異なる
代襲相続の範囲は、相続人が誰かによって異なります。
被相続人の子どもが相続人だった場合、孫・ひ孫と下の世代に代襲が繰り返されます。(民法第887条2項)これを「再代襲」と呼び、民法第887条2項・889条1項・2項で規定されています。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。引用:民法|第887条2項
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
一方、相続人が亡くなった方の兄弟姉妹であった場合、その子ども(被相続人からみて甥・姪)までしか代襲相続しません。
また、直系尊属(父母や祖父母など上の世代)には代襲相続が認められず、被相続人の両親が亡くなっている場合は祖父母が直接相続人となります。
このように、代襲が何世代も続くのは「子の系統」のみであり、兄弟姉妹や直系尊属の場合は範囲が限定される点を押さえておきましょう。
代襲相続できない場合もある
代襲相続は、被相続人が亡くなった時点で相続人となるはずの人が既に死亡している場合に発生します。
しかし、以下のようなケースでは代襲相続は認められません。
- 相続人が相続放棄した場合
- 相続人が被相続人より後に死亡した場合
- 遺言書で指定されていた人が死亡していた場合
相続放棄とは「初めから相続人でなかったことにする手続き」であるため、その子どもに権利が引き継がれることはありません。
また、相続権はあくまで被相続人が亡くなった時点で確定するため、相続人が被相続人より後に死亡した場合も対象外です。
遺言書で指定されていた人が死亡していた場合も同様です。遺言によって財産を受け取る予定だった人が既に死亡している場合、その指定は効力を失い、代襲相続は起こりません。
遺言で代わりの受遺者を定めていない限り、その部分は法定相続人に分配されることになります。
また、以下の方は、制度上代襲相続とは無関係です。
- 相続人の配偶者
- 直系尊属(父母や祖父母)
- 甥・姪の子ども(姪孫)
- 養子縁組前に生まれた養子の子
- 相続人の配偶者の連れ子



代襲相続が認められるのは「子の系統」と「兄弟姉妹の子」に限られるため、この仕組みを正しく理解しておきましょう。
代襲相続の範囲はどこまで?孫と甥・姪の違い
代襲相続でよく誤解されるのが、「どの世代まで相続できるのか」という点です。
代襲できる範囲は、被相続人との関係(子や孫などの直系卑属か、兄弟姉妹か)によって大きく異なります。この点を誤ると本来相続人となる人を正しく確定できず、遺産分割協議が無効になるおそれもあるため、注意が必要です。
以下、直系卑属と兄弟姉妹(甥・姪)、養子縁組の代襲相続について解説します。
直系卑属(子ども・孫)は下の世代へ無制限に続く(再代襲)
被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの子、つまり孫が代わりに相続人になります。孫も亡くなっているときは、ひ孫が相続権を引き継ぐのが特徴です。
この仕組みを再代襲(さいだいしゅう)といいます。子や孫などの直系卑属の場合、世代に制限はなく、下の世代へと順に相続権が受け継がれていきます。
直系卑属の代襲ルールは、以下のとおりです。
| 世代 | 代襲相続の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 子 | 相続人 | 本来の相続人 |
| 孫 | 可能 | 子が死亡等の場合に代襲 |
| ひ孫 | 可能(再代襲) | 孫も死亡等の場合に再代襲 |
| 玄孫(やしゃご) | 可能(再々代襲) | 理論上は無制限に続く |
直系卑属(子・孫等)の代襲は、民法の定める要件(死亡・欠格・廃除等)を満たす限り、下の世代へ順次及びます。しかし、代襲が認められるのは被相続人の直系卑属に限られます。
出典:e-Gov法令検索|民法
兄弟姉妹(甥・姪)は一代限りで終了する
一方、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、代襲相続の範囲が大きく制限されます。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子どもである甥・姪までは代襲相続が認められます。
しかし、甥や姪も亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見て又甥・又姪)には相続権は引き継がれません。
違いをまとめると、次のとおりです。
- 直系卑属(子・孫):再代襲あり(ひ孫・玄孫へ続く)
- 傍系血族(兄弟姉妹):再代襲なし(甥・姪でストップ)
甥や姪が亡くなっている場合、その家系の相続権は消滅し、他の相続人の取り分が増えることになります。
養子縁組の場合の代襲相続(連れ子の扱いなど)
養子縁組をすると、養子は実の子どもと同じように相続権を持ちます。
しかし、養子の子ども(被相続人から見ると孫にあたる人)が代襲相続できるかどうかは、いつ生まれたかによって判断が分かれます。
養子縁組より前に生まれていたのか、後に生まれていたのかで大きく異なる点に注意が必要です。以下の表で、ケースごとの代襲相続の可否を確認していきましょう。
| 養子の子どもの出生時期 | 被相続人との血族関係 | 代襲相続権 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 養子縁組後に出生 | あり | あり | 養子縁組後に生まれた子は、養親の「孫」とみなされる |
| 養子縁組前に出生 | なし | なし | いわゆる連れ子。養親との血縁関係が生じないため代襲不可 |
養子縁組前に生まれていた子どもは、被相続人(養親)から見ると直系卑属にあたりません。養子が先に亡くなっても、連れ子が代襲して相続することはできない点に注意しましょう。
出典:国税庁|養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
代襲相続で注意すべき相続税の基礎知識
代襲相続が発生すると、民法上の権利関係だけでなく、相続税の計算にも大きく影響します。
相続人が誰になるのか、何人いるのかによって税額が変わるため、基礎控除や各種加算のルールを理解しておくことが重要です。
ここでは、代襲相続ならではの税務上のポイントを解説します。
相続税の基礎控除額における「法定相続人の数」の数え方
相続税には、基礎控除があります。基礎控除の計算式は、以下のとおりです。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
代襲相続が起きた場合、この「法定相続人の数」の数え方に注意が必要です。
例として、本来の相続人である子どもが1人いたものの、その子どもがすでに亡くなっており、孫3人が代襲相続するケースを考えてみましょう。
| ケース | 法定相続人の数 | 基礎控除額の計算 | 控除額合計 |
|---|---|---|---|
| 通常相続(子が存命) | 1人(子) | 3,000万円 + (600万円 × 1) | 3,600万円 |
| 代襲相続(孫3人) | 3人(孫×3) | 3,000万円 + (600万円 × 3) | 4,800万円 |
このように、代襲相続によって相続人の人数が増えると、基礎控除額も増えます。
結果、課税の対象となる遺産総額が少なくなり、相続税の負担が軽くなったり、場合によっては税額がゼロになったりすることもあります。



代襲相続は手続きが複雑になりやすい一方で、税務面では有利に働く場合があることも押さえておきましょう。
孫や甥・姪が相続する場合の「2割加算」ルール
相続税には、2割加算という制度があります(相続税法第18条)。
これは、配偶者や一親等の血族(子ども・親)以外の人が遺産を受け取る場合、相続税が2割増しになる仕組みです。
代襲相続人が孫の場合と甥・姪の場合とでは、この2割加算が適用されるかどうかが異なります。
| 代襲相続人の属性 | 2割加算の適用 | 理由 |
|---|---|---|
| 孫(代襲相続) | なし | 子の代わりとして相続するため、実子と同じ扱いを受ける(※) |
| 甥・姪(代襲相続) | あり | 被相続人の一親等の血族ではないため、加算対象となる |
被相続人の兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪は、2割加算の対象です。そのため、通常よりも税負担が重くなります。
本来の相続税額が100万円であれば、甥や姪は120万円を納めなければなりません。資金計画を立てる際は、この加算分を見落とさないよう注意しましょう。
代襲相続をする側(孫・甥姪など)に起こり得る5つのトラブル
代襲相続人は他の相続人との関係性が薄く、知らぬ間に不利な立場へ追い込まれることも少なくありません。
代襲相続人(孫・甥姪など)に起こり得るトラブルは以下の5つです。
具体的にどのようなトラブルにつながりやすいのか理解しましょう。
関連記事:遺留分は代襲相続でももらえる?孫と甥姪の違いや計算方法を解説【弁護士監修】
代襲相続人が不利な条件で署名を急かされる
代襲相続人は相続手続きに不慣れな場合が多く、他の相続人から不利な条件を提示されても十分に理解できないまま署名を迫られるケースがあります。
たとえば「早く片付けたい」「他に迷惑をかけるな」といった言葉で圧力をかけられ、そのまま遺産分割協議書に署名してしまうケースが挙げられます。
一度署名・押印した書面は、原則として法的な効力を持ち、後から「不利だったからやめたい」と撤回することは極めて困難です。結果として、本来の相続分を大幅に失うだけでなく、親族間での不信感や長期的な対立を招く原因となります。
とくに代襲相続人が若年層や遠方居住で孤立している場合には、こうしたリスクが高まりやすく、深刻なトラブルへと発展する可能性があります。
代襲相続人と連絡が取れず協議が進まない
相続手続きは相続人全員の合意が必要なため、代襲相続人と連絡が取れないと協議が迅速に進みません。
相続人の一人が欠ければ遺産分割協議は成立せず、財産の名義変更や処分ができないまま長期間手続きが停滞します。
代襲相続人が遠方に住んでいる、長年疎遠で所在が不明といったケースでは、協議が何カ月も進まないケースもあり得ます。
連絡がつかないこと自体が親族間の不信を生み、「わざと連絡を返していないのではないか」といった疑念から新たな争いに発展する可能性も少なくありません。
代襲相続人が他の相続人から財産の内容を教えてもらえない
代襲相続人が遺産の全体像を知らされずに協議へ参加させられるケースも、よくあるトラブルの一つです。
相続財産には不動産や預貯金、株式、生命保険、借金など多岐にわたる項目があります。しかし、すべての財産を正しく把握できなければ、自分の取り分を判断できません。
なかには意図的に財産を隠したり、評価額を過小に見積もって提示したりする相続人もおり、代襲相続人が内容を確認しないまま署名してしまうリスクがあります。
表面的には円満に見える協議でも、隠し財産が発覚すれば「騙された」と感じ、訴訟に発展することも少なくありません。
他の相続人から相続を放棄するように強いられる
代襲相続人が、家族内の力関係や心理的な弱みにつけ込まれ「相続を放棄するように」と強い圧力を受けるケースもあります。
代襲相続人は孫や甥姪など、比較的若い世代であるケースが多いです。そのため、知識や経験が乏しいことから「あなたには権利がない」「もらう資格はない」と言われてしまうことがあります。
しかし、代襲相続人には法律で定められた正当な権利があり、放棄を強いられる理由はありません。
不当な圧力によって権利を奪われた場合、親族間の関係が大きく損なわれ、後に深刻な対立や訴訟に発展する危険性もあります。
代襲相続人が知らないうちに被相続人の借金を引き継いでしまう
代襲相続に関わらず、相続ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金・債務)も対象となります。
そのため、代襲相続人が財産の調査を十分に行わないまま相続を承認すると、気付かないうちに被相続人の借金を抱える事態が起こり得るのです。
たとえば銀行からの借入金や連帯保証、税金や社会保険料の滞納などが隠れていた場合、相続人は返済義務を負うことになります。自分とは関係なくても、相続人になってしまえば放棄を選ばない限り、負債を返済し続けなければなりません。
財産内容を知らされずに承認してしまえば、借金の返済義務を負うことになり、生活に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
代襲相続人以外の相続人に起こり得る3つのトラブル
代襲相続が絡む相続において、代襲相続人以外の相続人が直面する可能性が高いトラブルは以下のとおりです。
代襲相続では、代襲相続人となる本人だけでなく、それ以外の相続人が注意すべきポイントもあるため、本章で確認しておきましょう。
代襲相続人を無視して遺産分割協議を進めてしまった
代襲相続人を無視したまま遺産分割協議を行っても、その合意は無効となり、やり直しが必要になります。
相続権を持つ人を排除した協議は、法律上成立しないためです。
たとえば、被相続人の子どもが亡くなっている場合、その子の子ども(孫)には代襲相続権があります。しかし、残された家族が「孫は関係ない」と考えて協議を進めてしまうと、後日、代襲相続人である孫から権利を主張され、遺産分割協議を1からやり直すことになるでしょう。
一度合意した内容が白紙になると、相続人間の不信感が強まり、感情的な対立に発展する可能性が高いです。
そもそも代襲相続が発生することを知らなかった
代襲相続の制度を知らずに協議を進めると、相続が一見終わったように見えても、後から代襲相続人に権利を主張され協議がやり直しになる場合があります。
代襲相続の制度そのものを理解していない場合、「相続人はもういない」と誤解し、実際には権利がある人を抜いたまま協議を終えてしまうケースが代表例です。
最悪の場合、相続人同士の信頼関係が崩れ、家庭内で長期的な争いに発展する可能性も考えられます。知識不足が原因で、不要なトラブルを招く典型例といえるでしょう。
遺産分割の割合をめぐって代襲相続人と対立する
代襲相続では、遺産の分け方をめぐって強い対立が生じる可能性があります。
具体的には、被相続人の介護や生活支援を担ってきた人が「自分は多くもらうべきだ」と主張する一方で、代襲相続人は「法律に従って公平に分けるべきだ」と反論するケースが挙げられます。
実際「被相続人にどれくらい貢献したのか」という基準で遺産分割の割合を調整する仕組みはあります。しかし、その評価は状況ごとに異なり、明確な基準がわかりにくいのが実情です。



このような状況では、感情的な不満が積み重なり、冷静な話し合いが困難になるケースが少なくありません。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
代襲相続でトラブルが起こったときはどうする?
代襲相続でトラブルが起こった際は、以下のステップで冷静に対応しましょう。
落ち着いて対応し、大きなトラブルに発展しないよう手順を確認しておきましょう。
まずは相続人同士で冷静に話し合って円満解決を目指す
代襲相続でトラブルが起きたときは、まず相続人同士で冷静に話し合うことが解決の第一歩です。感情的な対立が先行すると協議が進まず、無用な裁判に発展するリスクが高まります。
たとえば、代襲相続人が署名を急かされたり、遺産の情報が共有されないまま協議に参加させられると、後から「無効だ」と争いになるケースがあります。
こうしたトラブルを避けるためには、全員が同じ情報を認識し、納得した上で協議を進める姿勢が重要です。
法律上、遺産分割は相続人全員の合意がなければ成立しません。
早い段階で率直な意見交換を行うことで、調停や訴訟に進まずに解決できる可能性が高まります。まずは話し合いで歩み寄りを試みましょう。
相続財産を調査する
代襲相続でのトラブルを防ぐには、相続財産を正確に調査することが欠かせません。
財産の全体像を把握しないまま協議を進めると、不透明な分配が行われて後から「知らなかった」と争いになる恐れがあります。
具体的には、以下のような証明書を集め、プラス・マイナスの財産すべてを確認する必要があります。
- 不動産の登記事項証明書
- 預金残高証明
- 証券会社の取引報告書 など
被相続人が生前に行った贈与や保険契約も対象に含まれる場合があり、漏れがあると正しい相続分を算出できません。
徹底した相続財産の調査は、公平な分配を実現させるために必要なステップです。相続人同士で資料を共有し、客観的な証拠を基に話し合うことで、不要な不信感や紛争を避けられます。
なお、財産調査で負債が多いとわかった場合は、相続放棄を検討する必要があります。
ただし、相続放棄をすると借金の支払い義務からは逃れられますが、すべての財産を引き継げないため、慎重に判断しましょう。
相続放棄の手続きの流れは、以下の記事を参考にしてみてください。
寄与分や特別受益などを考慮して相続割合を算出する
代襲相続の割合を算出する際には、法定相続分だけでなく「寄与分」や「特別受益」も考慮しなければなりません。
| 寄与分 | 被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした相続人(長年介護を担った子どもや、事業の経営に協力した家族など)に与えられる加算分 |
|---|---|
| 特別受益 | 生前贈与や住宅購入の援助などを既に受けている相続人の取り分を調整する仕組み |
単に法律上の割合だけで分けてしまうと、過去の貢献や贈与の有無を反映できず、不公平な結果となる可能性があります。
寄与分や特別受益を適切に反映させることで、各相続人が実質的に公平な分配を受けられるようになります。
代襲相続人は、親世代の状況を直接知らないケースも多く、寄与分や特別受益の存在を見落としがちです。正確な割合を導き出すためには、相続人全員で情報を共有し、必要に応じて専門家の判断を取り入れることが重要です。
遺産分割協議書の内容に同意する(安易に同意しない)
遺産分割協議書には安易に署名してはいけません。
一度署名・押印すると法的拘束力が生じ、後から取り消すことが難しいためです。内容を十分に理解しないまま同意すると、自身の取り分を大きく損なう可能性があります。
たとえば、代襲相続人が知識不足を理由に不利な条件を受け入れてしまうケースは少なくありません。遺産の範囲や評価額が曖昧なまま署名を求められるケースもあり、そのまま合意すると「知らなかった」では済まされず、大きな損失につながります。
協議書は全員の合意を記録する重要な書面であり、財産調査や割合計算が不十分な段階での署名は危険です。
不利益を避けるためには、協議書の文言を細部まで確認し、不明点はその場で質問することが大切です。必要に応じて弁護士や専門家のチェックを受け、協議内容に合意した上で手続きを進めましょう。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。(参照:法務省|遺産分割調停)
相続は全員の合意が必要なため、一人でも同意しなければ協議は成立しません。長期化すれば、人間関係の悪化や財産管理の停滞につながります。
調停では裁判官と調停委員が中立の立場で双方の意見を整理し、合意形成をサポートします。感情的な対立を防ぎ、冷静な話し合いを進められる点が大きな利点です。
代襲相続人が財産の内容を知らされないまま主張が平行線をたどる場合でも、調停を通じて情報開示が促され、透明性のある協議が実現します。
調停を申し立てる場合、弁護士に早めに相談すると良いでしょう。



弁護士に依頼すれば、法的な根拠を踏まえた主張が可能になり、不利な合意を避けられる可能性が高まります。
遺産分割調停が不成立になった場合の対応は、以下の記事をご覧ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
代襲相続のトラブルを防ぐための生前対策
代襲相続が発生すると相続人同士の認識にずれが生じやすく、遺産分割をめぐる争いが起こりがちです。
被相続人の生前から準備しておけば、相続時の混乱を避けやすくなります。
具体的な対策は、以下のとおりです。
代襲相続が想定される場合は、生前から対策を講じてトラブルを防ぎましょう。
財産目録を作成しておく
財産目録を作成し、財産がどれくらいあるのかを把握しましょう。財産の全体像がわからないと、相続時に代襲相続人が「財産を隠されているのではないか」と疑念を抱く可能性があるためです。
財産目録とは、被相続人の財産や負債をすべて書き出した一覧表のことです。不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務といったマイナスの財産まで正確に整理する必要があります。
特に借金の存在を知らないまま代襲相続人が相続してしまうと、後から返済義務を負う事態になりかねません。財産目録があれば、相続放棄や限定承認を検討する際の判断材料にもなります。
また、透明性を確保できるため、特定の相続人が情報を独占して不信感を招くようなトラブルも避けやすくなります。
なお、財産目録は裁判所が公表しているテンプレートを参考に作成すれば、抜け漏れのない一覧を作りやすいでしょう。(参照:裁判所|相続財産目録)
遺言書で被相続人の意向を明確にしておく
代襲相続が発生すると、孫や甥姪など普段はあまり接点がない親族が新たに相続人となるケースも少なくありません。法定相続分に従って遺産を分けるだけでは、被相続人の思いが十分に反映されない場合があります。
たとえば「介護を担ってくれた孫に多めに財産を渡したい」といった希望がある場合、遺言書に残しておけば、その意向を明確に伝えられます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、形式不備のリスクを避けるには公正証書遺言が適しています。公証人が関与するため確実に効力を発揮し、相続人間の解釈違いによる争いを未然に防げます。
遺言書があれば「誰がどの財産をどの割合で受け取るのか」が明確になり、協議がスムーズに進む効果も期待できるでしょう。
遺言書の書き方や注意点は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【例文付き】遺言書の書き方とは?必須項目や注意点を解説
生前贈与・死因贈与を活用して相続財産を分配する
生前贈与や死因贈与を上手に使うことで、代襲相続をめぐる不要な対立を防ぎながら、被相続人の意向に沿った形で財産を計画的に分けられます。
生前贈与は、被相続人が生きている間に財産を移転する方法です。暦年課税制度を利用すれば、年間110万円まで非課税で贈与できます。(参照:国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合)
死因贈与は「死亡時に財産を渡す」と契約で定めるもので、遺言と似ていますが契約行為であるため生前に受贈者と合意が必要です。
いずれの方法も相続開始後の協議を減らし、円滑な遺産継承につながります。
ただし、生前贈与は「特別受益」として相続分に影響する可能性があるため、金額や内容を記録に残しておくことが大切です。
生前贈与を非課税で行う方法は、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:生前贈与を非課税で行う6つの方法と契約書の書き方のポイントを徹底解説
代襲相続人とコミュニケーションを取っておく
代襲相続人は孫や甥姪など、普段は疎遠な関係にあることが多く、相続開始後に初めて存在を知るケースもあります。
こうした状況では、相続人同士の意思疎通が不足して遺産分割協議が進まなかったり、感情的な衝突に発展したりするリスクが高まります。
他の相続人が被相続人の生前から代襲相続人と交流を持ち、財産の大まかな内容や自らの意向を伝えておけば、協議での混乱を避けやすくなります。
代襲相続人自身も自分の立場や権利を早く理解できるため、話し合いに積極的に参加しやすくなるでしょう。
とくに若い世代は相続に関する知識が乏しい場合が多いため、事前に情報を共有しておくことが重要です。



コミュニケーションを重ねることは、相続発生後の信頼関係を保ち、円滑に手続きを進めるための大切な準備といえます。
代襲相続のトラブルを放置するリスク
「面倒だから」といって、代襲相続の問題を後回しにするのは危険です。時間がたつほど、金銭的にも精神的にも負担は大きくなっていきます。
トラブルを放置すると、主に以下のようなリスクが生じます。
- 預金口座の凍結が解除できない
- 相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わない
- 不動産の価値が下落し続ける
- 次の相続が発生し、権利関係が複雑化する(数次相続)
銀行の手続きには、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要です。代襲相続人の協力が得られなければ預金を引き出せず、葬儀費用や当面の生活費に困るおそれがあります。
また、遺産分割の話し合いがまとまっていなくても相続税の申告期限は延びません。期限を過ぎると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの優遇措置が使えなくなり、税額が大幅に増える可能性があります。



「あのとき動いておけばよかった」と後悔しないためにも、不安を感じたら早めに弁護士に相談することが大切です。
代襲相続でトラブルが発生したら弁護士に相談|依頼するメリット
代襲相続では、孫や甥姪などの幅広い相続人が関わるため、トラブルが発生すると当事者同士の話し合いだけでは収拾がつかなくなるケースがあります。
弁護士に相談すれば、相続財産の調査や評価を客観的に進め、正確な情報に基づいて協議を整えられます。
さらに、遺産分割協議書の作成や寄与分・特別受益などの複雑な主張にも対応できるため、自分の権利を適切に守れます。
また、調停・訴訟に進んだ際も、弁護士が代理人として対応してくれる点は大きな安心材料です。専門家の関与があれば、相続人同士の感情的な衝突を避けやすく、解決までの道筋も明確になります。



代襲相続に関する不安や対立が生じたときは、早めに弁護士へ相談することが円滑な相続の第一歩です。
相続に強い弁護士の選び方は、以下の記事を参考にしてみてください。
関連記事:相続に強い弁護士とは?費用や失敗しない選び方を解説【弁護士監修】
関連記事:相続問題は弁護士に無料相談できる?おすすめの相談先や必要な準備も解説【弁護士執筆】
代襲相続のトラブルを弁護士に相談するタイミングは?
「弁護士に相談するのは、裁判沙汰になってからでいいのでは?」と考える方も少なくありません。
しかし、代襲相続については、早めに相談するほど、解決までの時間や費用を抑えやすくなります。とくに、次のタイミングでの相談が効果的です。
- 親族へ連絡や話し合いを始める前(もっとも望ましいタイミング)
- 遺産分割協議書に署名・押印する前
- 家庭裁判所へ調停を申し立てる前
- すでにトラブルになっていたり、連絡を無視されていたりする場合
疎遠な代襲相続人に、いきなり「遺産分割協議書」や「印鑑証明書の提出依頼」を送ると、警戒されて関係がこじれることがあります。最初の連絡方法や手紙の書き方について事前にアドバイスを受けておけば、円満に話し合いを始めやすくなるでしょう。
もちろん、すでに揉めている場合でも対応は可能です。弁護士名義で通知を送ることで、相手が真剣に向き合うようになるケースも多くあります。



「まだ早いかもしれない」と感じる段階こそ、実は相談に適したタイミングです。手遅れになる前に、専門家の知見を取り入れましょう。
代襲相続のトラブル対応にかかる弁護士費用
代襲相続でトラブルが発生し弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
以下の表に、主な費用項目と内容、相場をまとめました。
| 費用項目 | 内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 弁護士に初回・継続相談を行う際の費用 | 無料~30分5,000円程度 |
| 着手金 | 弁護士に依頼する際に最初に支払う費用 | 20万円〜50万円程度 |
| 成功報酬 | 弁護士の関与によって獲得できた財産額に応じて支払う報酬 | 弁護士の関与によって得られた財産の10〜15% |
| 実費 | 裁判所への申立費用、郵送代、交通費、コピー代など | 5万円~7万円程度 |
| 日当 | 出廷や遠方への対応が必要になった場合の時間拘束料 | 3万円~5万円程度 |
| 遺産調査費用 | 不動産登記や金融機関の残高調査など、財産を確認するための費用 | 3万円~5万円程度 |
弁護士費用は、依頼する事務所や案件の複雑さによって変動します。
成功報酬は「弁護士の関与によって実際に取得した財産額」に対して設定されるのが一般的で、最初に取り決めた割合が基準となります。
着手金は結果に関係なく必要になるため、依頼前に支払い条件を確認することが大切です。



法律相談料は初回のみ無料にしている事務所も多いため、まずは相談して見積もりを出してもらうと良いでしょう。
相続にかかる弁護士費用は、以下の記事でも解説しています。資金計画を立てる際の参考にしてみてください。
関連記事:相続の弁護士費用はいくらかかる?誰が払うのかと安く抑える方法も解説
関連記事:相続問題は弁護士に無料相談できる?おすすめの相談先や必要な準備も解説【弁護士執筆】
代襲相続のトラブルに関するよくある質問
代襲者が相続放棄をしたらどうなりますか?
代襲相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになります。
ただし、相続放棄は次世代に引き継がれるため、放棄をした代襲相続人の子どもがいる場合は、その子どもがさらに代襲相続人となります。
たとえば、被相続人の子が亡くなり孫が代襲相続人になったものの、その孫が相続放棄をすれば、ひ孫が代襲相続人として権利を得ることになります。
ただし、甥や姪が代襲相続人である場合には、その下の世代には相続権が移りません。
代襲相続人から「放棄したい」との申し出があったときは、自分の世代だけでなく次世代にもどのような影響が及ぶかを踏まえて判断しましょう。
代襲相続人と連絡が取れない場合はどうしたら良いですか?
代襲相続人と連絡が取れないと、遺産分割協議は成立しません。その場合はまず、戸籍や住民票をたどって居場所を特定します。
自分で調べるのが難しい場合は、弁護士に依頼して調査を進める方法も検討しましょう。
もし住所が分かっても、そこに実際に住んでいないなど所在不明の場合は「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申し立てて選任する必要があります。(参照:裁判所|不在者財産管理人選任)
不在者財産管理人は不在者に代わって遺産分割協議に参加し、手続きを進めてくれる代理人です。
代理人が決定すれば協議が進められますが、手続きには専門的な知識が必要になるため、弁護士への相談を検討しましょう。
代襲相続をさせない方法はありますか?
代襲相続は法律(民法)で定められた正当な権利のため、他の相続人同士の話し合いだけで、一方的に代襲相続人の権利をなくしたり、相続から排除したりすることはできません。
被相続人の遺言の内容や生前の状況によっては、代襲相続人の最終的な取り分が変動する可能性があります。
- 「特定の財産を別の相続人に渡す」といった内容が遺言に明記されている
- 代襲相続人以外の相続人が、自身の寄与分を主張する
- 代襲相続人以外の相続人が、代襲相続人の親が生前に受けた援助(特別受益)を指摘する など
ただし、子が亡くなって孫やひ孫が代襲相続する場合は、子と同じように遺留分を主張できるため、完全に代襲相続人を排除することは難しいでしょう。
遺留分侵害額請求の流れや計算方法は、以下の記事を参考にしてみてください。
孫に代襲相続させたくない場合はどうしたら良いですか?
孫に代襲相続させたくない場合には、被相続人が遺言書を作成して財産の分け方を指定する必要があります。
代襲相続は法律で定められた仕組みですが、遺言で「特定の財産を別の相続人に渡す」と意思表示をすれば、代襲相続人に権利が移るのを防ぐことが可能です。
ただし、遺留分と呼ばれる最低限の取り分は、一部の相続人(孫やひ孫)にも認められています。
万が一遺留分を侵害した遺言を残した場合、代襲相続人から遺留分侵害額請求をされるリスクもあります。
孫に代襲相続をさせたくない場合は、どのように対応すべきか弁護士に相談すると良いでしょう。
父と母の数次相続で遺産分割協議を行った事例
実際に、世代をまたぐ相続が重なり、代襲相続も含めて協議を整理したケースがあります。
“Aさんとその配偶者Bさんが亡くなり数次相続が発生した事例。
Aさんには依頼人CさんとDさんの二人のお子さんがいました。Aさんの遺産は主に自宅不動産で、預貯金は多くありませんでした。
Cさんは相続登記を行おうとしましたが、法務局でAさんに前配偶者との間に子どもがいることが判明し、代襲相続人としてEさんとFさんが存在することが判明。
これらの相続人との遺産分割協議を経なければ手続きを進めることができないと判断し、弊所にご相談。”
この事例の課題としては、
- 数次相続・代襲相続が発生しており、相続関係が複雑
- 依頼人Cさんの寄与分(介護や金銭援助)をどのように評価するか
があげられます。
そこで
- Aさんの相続人を正確に洗い出し、相続関係を整理
- Eさん・Fさんに対し、CさんがAさん・Bさんの介護を長年行っていたことなどを丁寧に説明した手紙を送付
というご対応をさせていただき、全相続人の同意のもとで遺産分割協議書を作成し、Cさんは問題なく相続登記を完了することができました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


まとめ|代襲相続のトラブルは弁護士に相談して円満解決を目指そう
代襲相続は、通常の相続よりも関係者が増えやすく、法律の知識がないまま進めると大きなトラブルに発展するおそれがあります。
とくに、代襲相続の範囲の誤認や相続税の2割加算の見落としは、後から取り返しのつかない損失を生む原因となるため注意が必要です。
また、疎遠になっている親族(甥・姪など)と遺産分割の話し合いをする場合、精神的な負担も小さくありません。トラブルを防ぎ、手続きを円滑に進めるためには、次の点を意識しましょう。
- まず戸籍を集めて、正確な相続人を確定させる
- 自分たちだけで抱え込まず、早い段階で専門家に相談する
- 感情的な対立を避けるため、公平な第三者(弁護士)を間に入れる
代襲相続の問題は、時間がたつほど解決が難しくなります。
家族の財産と関係を守るためにも、不安を感じたら早めに弁護士へ相談し、円満解決への一歩を踏み出しましょう。



早い段階で専門家に相談し、適切な方法で解決を目指しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応