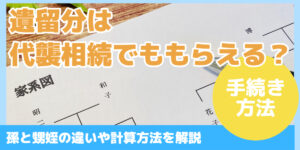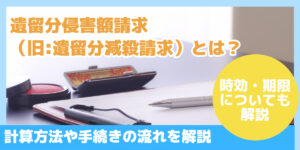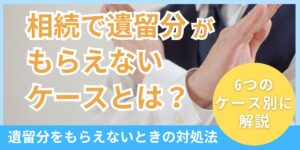【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分を渡さなくていい方法や支払い拒否できる方法はある?生前からできる6つの対策を弁護士が解説
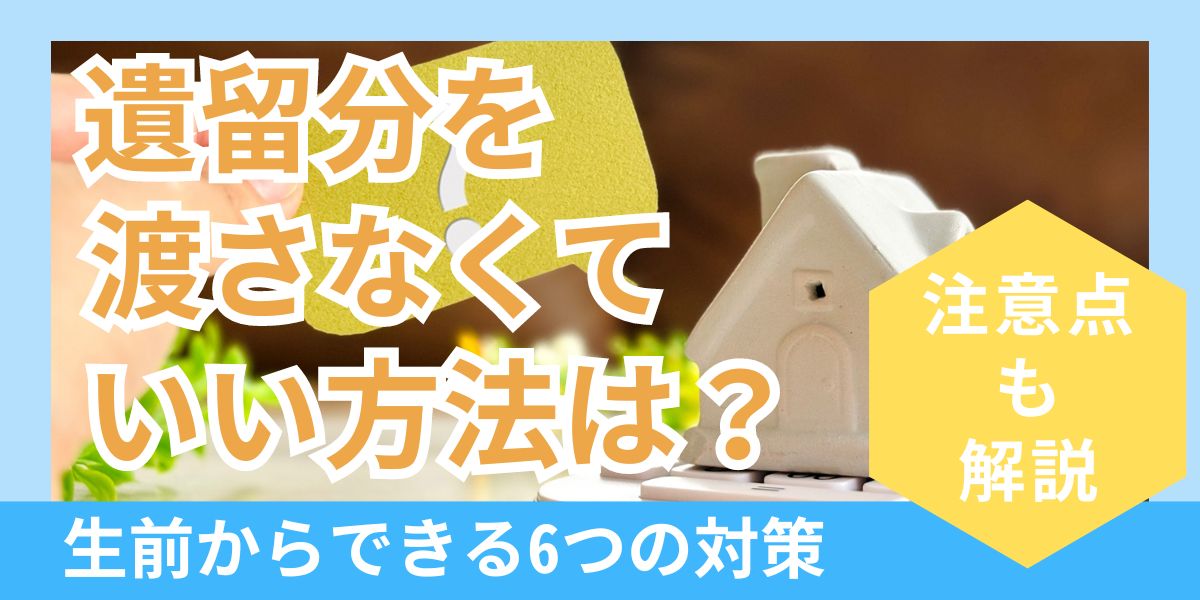
一定の相続人(配偶者・子ども・父母)には、相続において最低限保障された「遺留分」が存在します。
しかし、なかには特定の相続人に対して「絶対に遺留分を渡したくない」、「遺留分を渡さなくていい方法があれば知りたい」という方もいるのではないでしょうか。
相続人が遺留分の事前放棄や、相続放棄をしているケースでは、遺留分を渡さなくて済みます。
特定の相続人に遺留分を渡したくない場合は、生前に対策をしておくことが大切です。
そこで今回は、遺留分を渡さなくていい方法はあるのか、どうしても渡したくないときの対策と注意点について解説します。

本記事では、特定の人に遺留分を渡したくないと考える、遺言者とその家族向けに生前・生後別に対処法を解説します。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺留分は渡さなくてもいいパターンもある
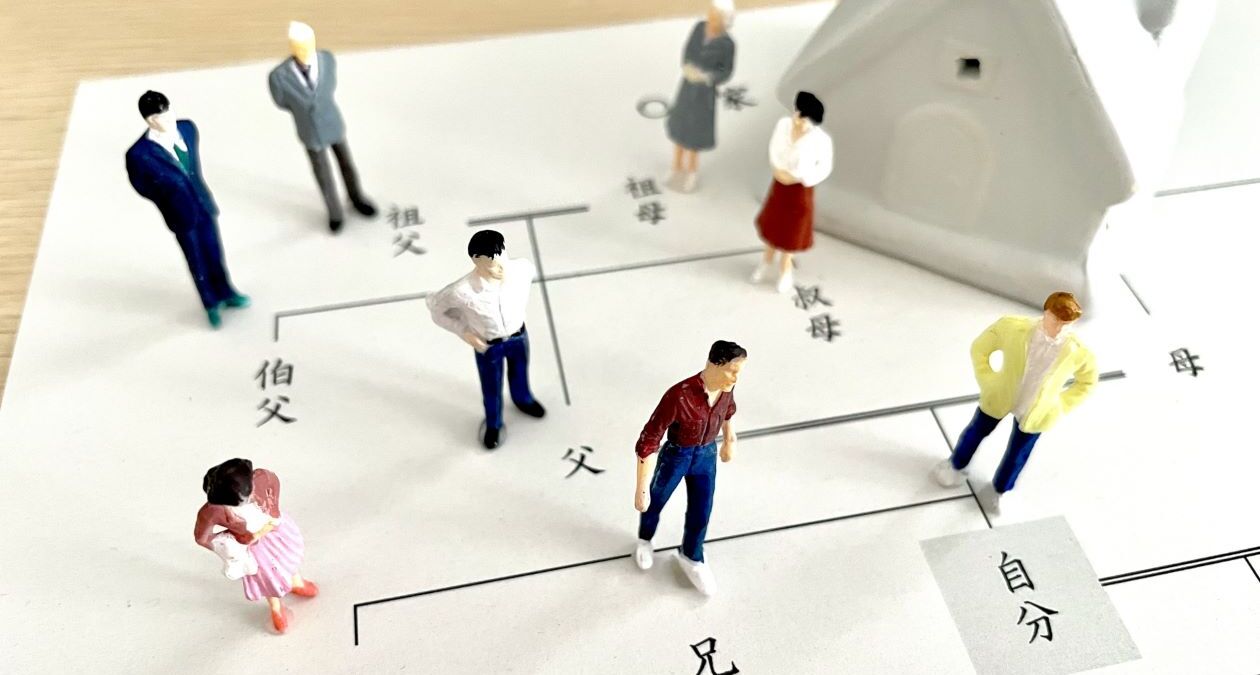
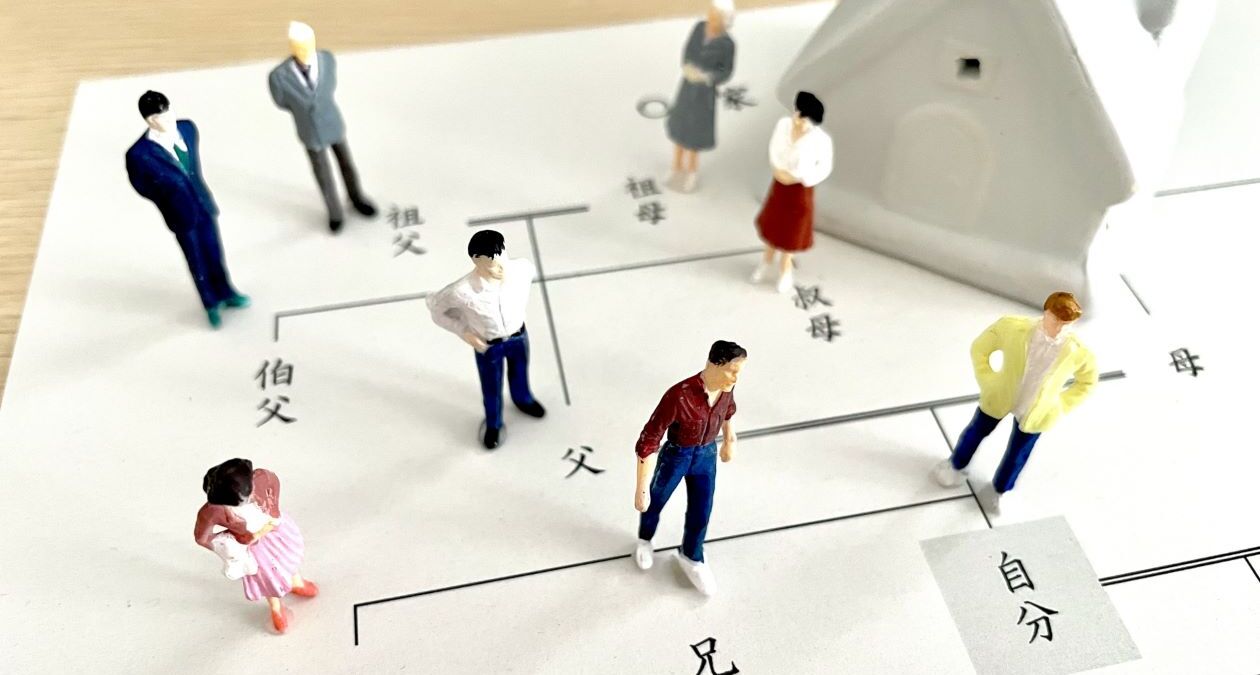
配偶者や子どもなど、一定の相続人には遺留分を受け取る権利が保障されています。
これは、民法で定められているものであり、たとえ遺言であっても奪うことはできません。
ただし、例外的に遺留分を渡さなくても良いパターンも存在します。
たとえば、以下のようなケースでは、遺留分を渡さなくていいとされています。
- 遺留分を事前放棄している場合
- 遺留分権利者が請求してこない場合
- 相続人が相続放棄をしている場合
- 相続廃除されている相続人の場合相続欠格に該当する相続人の場合
- 遺留分侵害額請求の時効が成立している場合
生前にできる遺留分を渡したくないときの対策6選


続いては、特定の相続人に遺留分を渡したくないと考えている方に向けて、生前にできる具体的な対策方法を説明します。
1.遺留分を事前放棄してもらう
相続人に遺留分を事前放棄してもらうことができれば、当然ながら遺留分を渡す必要はなくなります。
ただし、遺留分の放棄には、相続人本人の同意と家庭裁判所の許可が必要です。
また、申し立ての手続きは相続開始前(被相続人の生前)に行わなければなりません。
なお、遺留分の放棄は、申し立てを行えば必ず認められるわけではなく、所定の条件を満たす必要があります。
一般的に、遺留分放棄の認可基準になると考えられているのは、以下の3つです。
- 遺留分放棄が相続人本人の自由な意思に基づいていること
- 遺留分を放棄する理由に合理性と必要性がある
- 放棄に見合うだけの見返り(代償)がある
さらに、遺留分放棄の申し立て手続きは、被相続人ではなく、相続人本人が行うことになっています。
参考:裁判所「遺留分放棄の許可」
つまり、本人の意思に基づく遺留分放棄の申し出があるか、または遺留分の代わりとなる財産を渡さなければ、遺留分放棄が認められる可能性は低いといえるでしょう。
2.遺言書に遺留分を渡したくない旨を記載する
先に紹介したとおり、遺留分請求権があっても請求されなければ遺留分を渡す必要はありません。
そこで、「遺留分を渡したくない」という願いを、遺言書の付言事項として記載する方法もあります。
付言事項とは、被相続人の気持ちや願いを伝える文章のことです。
相続の割合やその理由、「遺留分を請求してほしくない」という旨を遺言に記載することで、相続人に自分の思いを伝えることができます。
ただし、遺言書の付言事項に、法的拘束力はありません。
そのため、相続人から遺留分を請求されれば支払わなければいけません。
3.相続の放棄について打診する
相続人が相続放棄をしていれば、遺留分を渡さなくていいパターンに該当します。
相続放棄は、プラス遺産だけでなく、マイナスの遺産(債務)も対象です。
そのため、一般的には被相続人の残した負債が多い場合に行われることが多く、プラスの遺産が多いにも関わらず、相続放棄をする人は少ないです。
また、相続放棄の手続きは、被相続人の死後に行われます。
相続人に対して相続放棄を強制することはできないため、あくまでもお願いにはなりますが、ダメ元で打診してみても良いでしょう。
4.相続人廃除の申し立てをする
相続人廃除の申し立てとは、被相続人の意思に基づいて、特定の人物から相続人としての地位を奪うことです。
相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
具体的な申し立ての方法は、以下の2通りです。
- 被相続人が、生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする
- 遺言書で相続人廃除をする
遺言書で相続人廃除の手続きを行うには遺言執行者が必要ですし、次に紹介する廃除の理由を証明するのがより難しくなるため、特別な理由がなければ、生前に家庭裁判所で申し立て手続きをするほうが確実です。
相続人廃除の申し立てが認められる主なケースとしては、以下のようなものがあります。
- 相続人が被相続人を虐待していた場合
- 相続人が被相続人に対して、重大な侮辱を与えていた場合
- 相続人が、被相続人の財産を不当に処分したことがある場合
- 相続人の多額の借金を被相続人が肩代わりしていた場合
- 配偶者が浮気を繰り返すなど家庭を顧みずに、被相続人が苦労していた場合
ただし、相続人廃除が認められた場合も、代襲相続の権利は残ります。
つまり、相続人本人が死亡している場合、相続権は子どもや孫に受け継がれます。
5.相続欠格に該当する場合は渡さなくていい
相続人が相続欠格に該当する場合は、特別な手続きを行わなくても遺留分を渡す必要はありません。
民法891条で定められた相続欠格事由には、以下の5つがあります。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
6.遺留分をできるだけ減らす
特定の相続人に渡す遺留分を減らしたいなら、そもそもの遺留分を減らしてしまうという方法があります。
具体的な方法をいくつか紹介しましょう。
養子縁組をして相続人の人数を増やす
養子縁組をして相続人の人数を増やせば、相続人1人あたりの遺留分が少なくなります。
ただし、その養子縁組が「遺留分を減らす目的で行われたものだ」と判断されてしまうと、養子縁組そのものが無効になる可能性もあるため、注意が必要です。
関連記事:養子縁組による相続トラブルとは?よくある5つのケースやリスク・対処法を解説
生命保険として他の相続人に渡す
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく「受け取った人の固有財産」として扱われます。
遺産にカウントされないため、遺留分侵害額請求の対象になることもありません。
つまり、遺産に含まれる金融資産をあらかじめ生命保険に変えておけば、遺留分そのものの額を減らすことができます。
たとえば、2,000万円をそのまま金融資産として保有していると、相続財産として遺留分侵害額請求の対象となります。
しかし、同額の2,000万円を生命保険の掛金にし、受取人を別の相続人にすれば、相続財産にはカウントされず、遺留分侵害額請求の対象にもならないのです。
ただし、生命保険金の額があまりにも大きいと、特別受益に該当し、遺留分の計算に組み込まれる可能性があります。
生命保険を活用した相続対策については、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
他の相続人や相続人以外の人に生前贈与をする
他の相続人や相続人以外の人への生前贈与も有効な対策方法の一つです。
ただし、以下の2つに当てはまるものについては、遺留分の基礎財産額に含まれるため、注意しましょう。
- 1年以内に行われた相続人以外への生前贈与
- 10年以内に行われた特別受益に該当する生前贈与
遺留分を減らすために生前贈与を行う場合は、できるだけ早めに行うことが大切です。
また、1年以上前に生前贈与を受けた相続人が相続放棄をすることで、遺留分侵害額請求を免れるケースもあります。
相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったという扱いになるため、特別受益には該当せず、+遺留分侵害額請求の対象から外れる可能性が高いのです。
関連記事:生前贈与を非課税で行う6つの方法と契約書の書き方のポイントを徹底解説
関連記事:生前贈与で遺留分はどうなる?請求の流れと注意点を弁護士が解説
遺留分を渡したくないときの注意点3選


遺留分を渡したくないときに注意したいポイントを3つ解説します。
遺言書に「遺留分を渡したくない」と書かれていても法的な効力はない
遺言書に付言事項として「遺留分を渡したくない」「請求しないでほしい」と記載したとしても、その文言に法的な効力はありません。
残念ながら、+相続人には遺留分侵害額を請求する権利が認められるため、「絶対に遺留分を渡したくない」という場合でも、成功するとは限りません。
関連記事:遺言書があっても遺留分は請求できる?優先順位と対処法・遺留分侵害額請求の流れを弁護士が解説
相続欠格に該当する場合でも、その子どもには遺留分請求の権利がある
相続人本人が民法891条で定められた相続欠格事由に該当する場合でも、代襲相続は認められます。(民法887条)
相続人本人が亡くなっている場合でも、その子どもには遺留分請求の権利が認められるため、注意しなければなりません。
基本的に遺留分を渡さないことはかなり難しい
ここまで「遺留分を渡さなくていい方法」について説明してきましたが、いずれも例外的な方法であり、現実的には、遺留分を渡さないことはかなり難しいです。
遺留分は、法律で認められた「最低限の取り分」なので、被相続人の死後に遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合、正当な請求であれば支払う義務が生じます。
遺留分の支払いを拒否した場合の対応は、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:遺留分を支払わないとどうなる?支払い拒否のリスク、現金がないときの対処法を解説
また、「相続を放棄してもらう」など生前にできる対策についても、相続人の意思や家庭裁判所の許可が必要なため、よほどの理由がない場合は相続人との交渉が必要になるでしょう。
どうしても遺留分を渡したくない場合は、弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。
特定の相続人に遺留分を渡さなくてもいい方法は弁護士に相談
遺留分を渡さずに済ませるには、弁護士への相談も視野に入れましょう。
遺留分は法律で保護された権利のため、遺言書だけで完全に回避するのは難しい可能性があります。専門家である弁護士に相談し、適切な対策を立てることが大切です。
弁護士は、生前贈与の持ち戻し免除など、専門的な観点から最適な方法を提案してくれます。
相続人の廃除や相続欠格といった、法的に認められた手段が使えるかどうかも判断してくれるのもメリットです。
また、弁護士に依頼すれば、相続人との交渉を代行してもらい、トラブルを未然に防ぐことができます。
遺留分を渡したくない場合の手続きは複雑になる可能性が高いため、弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。
遺留分について弁護士に相談すべきかどうかは、以下の記事でも解説しています。合わせてチェックしてみてください。
関連記事:遺留分問題を弁護士に相談するメリットを解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
被相続人の死後にできる遺留分を渡さないための対策
遺留分は法的に保証された「最低限の取り分」ですから、現実的には、遺留分を渡さないことはかなり難しいです。
ただし、「払わずに済む可能性を検討する」「やむを得ない場合でも負担を最小化する」**という観点から取れる手段があります。
感情的に無視してしまうと、調停・訴訟・強制執行へ進みかねません。まずは事実と法的根拠を丁寧に点検し、争点を絞って交渉や調停で早期に着地点を探ることが肝要です。
方法① 請求の適否を精査して「払わなくてよい/大幅減額」を狙う
- 権利者かの確認
相続人であっても兄弟姉妹には遺留分が認められていません。代襲相続の有無、配偶者・子・直系尊属かを最初に確認します。 - 期間制限(時効)の主張
「侵害を知ってから1年」「相続開始から10年」を超えていないかをチェックします。期限を過ぎていれば時効援用または除斥期間経過により拒むことができることがあります。 - 算定基礎から外れる財産の点検
生命保険金(受取人固有財産)、祭祀財産、死亡退職金等は、事情により算定基礎に含めない取扱いがされることがあります。名寄せ・通帳・保険証券・規程類で裏づけを揃えます。 - 相続財産の評価見直し
不動産は評価手法で金額が大きく変動します。路線価・取引事例比較・賃貸事業用の減価要因、共有持分減価などを吟味し、不動産鑑定士の意見書等を活用して減額を図ります。 - 特別受益の主張(相手方の過去の贈与)
住宅取得資金・学費・開業資金等の生前贈与を受けていれば、遺留分額から控除され、ゼロ~減額となることがあります。振込記録・贈与契約書・領収書の収集が有効です。 - 債務・葬儀費用等の控除
被相続人の債務や相続手続費用等は純資産から控除され、請求額が下がることがあります。 - 立証資料の例
預金通帳・入出金明細、保険証券、贈与契約書、学費や住宅資金の領収書、鑑定評価書、固定資産税課税明細、ローン残高証明、会社の決算書 など。
上記はいずれも事実関係の立証が鍵です。主張可能な事実を見落とさず、早期に資料を確保し、主張立証の設計を行うことが重要です。
方法② 丁寧に説明・交渉して遺留分を受け取らないことに同意してもらう
相続開始後でも、権利者本人の自由意思に基づく「不行使(請求しない)」の合意や、和解による権利放棄が成立することがあります。
強制はできませんが事実関係の開示と合理的な理由提示、納得感のある代替案、適切な書面化の3点を外さなければ、請求を思いとどまってもらえることがあります。
進め方の基本ステップ
- ①情報を開示し、論点を可視化する
相続財産の内訳・評価根拠・負債・葬儀費用・被相続人の生前の意思(メモ・メール・付言事項)を整理し、「どこまでが算定基礎か」「評価はいくらが妥当か」を資料付きで説明します。疑念を減らすことが合意への近道です。 - ②納得理由を丁寧に伝える
介護・事業承継・生前贈与のバランス、被相続人の希望、居住保護(自宅を手放すと生活が成り立たない等)など、感情論ではなく具体的事実を中心に説明します。 - ③代替メリットを提示する(例)
- 香典返し的な少額の見舞金・費用負担(葬儀費用の全額負担、形見分けの優先など)
- 将来の相続に向けた配慮(親の遺品整理・墓守の費用負担、実家名義の維持管理を引き受ける等)
- 分割や時期の工夫(今は請求しない代わりに、一定条件が生じたときの協議条項)
いずれも過度な金銭供与は贈与課税リスクや新たな不公平感を招くため、「合理的な実費・役務の提供」を基本に設計します。
- 香典返し的な少額の見舞金・費用負担(葬儀費用の全額負担、形見分けの優先など)
- ④書面化する(合意書/和解調書)
「遺留分侵害額請求権を行使しない」旨、合意の背景事実、提供内容、清算条項(将来互いに請求しない)、秘密保持、撤回・解除の不可、連絡方法を明記。家事調停での和解(調書化)にすれば、後日の蒸し返しを抑止できます。 - ⑤第三者関与で中立性を担保
弁護士が間に入り、説明資料の作成・交渉・合意書案のリーガルチェックを行うことで、「自由意思」「不当な圧力なし」を担保し、無効リスクを下げます。
注意点(NGとリスク)
- 威迫的な言動・一方的な期限設定・不利益事実の隠匿は無効主張(強迫・錯誤)や紛争激化の火種になります。
- 過大な金銭提供は贈与課税の対象となることがあり、また新たな特別受益争いの原因にもなります。税務面を含めた設計が必要です。
- 兄弟姉妹はそもそも遺留分権利者に当たらないため、対象者の確認を先に行い、不必要な交渉を避けることが肝要です。
- 相続人間に未解決の特別受益・寄与分の争点があると合意が崩れやすいため、並行して整理します。
うまくいきやすい場面の例
- 被相続人の明確な意思が客観資料で示せる(付言事項、手紙、録音、介護日誌等)
- 相手方に現実的なメリット(費用負担の軽減、手続の簡便、関係維持)があり、心理的配慮(言葉選び・時間配分・説明順序)がなされている
- 弁護士関与で、評価・時効・特別受益など法的論点と代替案がセットで提示されている
どの方法にも適用の可否やリスクがあり、個別事情の精査が不可欠です。
請求書面が届いた直後の初動で、結果が大きく変わることがあります。
「何から手を付けるべきか」だけでも、当事務所へご相談ください。早期関与により、減額・分割化・早期解決の可能性を高められることがあります。
兄弟からの遺留分請求|生前贈与を主張し大幅減額した実例
遺言などで財産を多く受け取った場合、他の相続人から「遺留分」を請求されることがありますが、言われるがまま支払う必要はありません。相手方が過去に親から援助を受けていれば、交渉で支払額を減らせる可能性があります。
“依頼人Bさんの親御さんのAさんの死後、Cさんが、Bさんに遺留分侵害額請求をしてきました。
Bさんは、実家の家業を継ぎ、献身的に両親を介護していましたが、Cさんは家のことにはほとんど関わりがありませんでした。
過去の資料を丁寧に拾い上げることで、実質的にCさんの生前贈与を裏付け、請求額の大幅減額に成功”
この事例では、
- 依頼者の記憶を頼りに「留学費用・住宅資金」等の贈与事実を掘り起こしたこと
- 被相続人Aさんの遺言書や日記・メモまで徹底的に調査・分析し、贈与の裏付けを行ったこと
により、当初の請求額から大幅な減額ができました。 理不尽な請求を受けても、過去の家族間のやり取りの中に解決のヒントが隠されていることがあります。請求を受け入れる前に弁護士へご相談ください。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


遺留分を渡さなくてもいい方法に関するよくある質問
遺留分侵害額請求をされた場合はどう対応すべきですか?
突然の内容証明に驚かれると思いますが、まず無視しないことが肝心です。実務では次の順番で進めると安全です。
- 権利関係と期限の確認:相手が遺留分権利者か(配偶者・子・直系尊属)、時効(「知った時」から1年/相続開始から10年)を満たしているかを点検します(民法1042条、民法1048条)。
- 金額の妥当性を精査:遺産範囲、評価(とくに不動産)、相手の特別受益(生前贈与など)の有無を検討します。評価や受益次第で減額できることがあります。
- 支払方法の選択肢を提示:分割払い・期限の猶予・担保提供など「支払える形」を提案すると合意に近づきます。
- 調停→訴訟を見据えた対応:交渉が難しければ家庭裁判所の調停で整理し、必要に応じて訴訟で最終判断を仰ぎます。
- “もう一つの時効”の管理:相手が意思表示後に長期間動かない場合、請求は金銭債権(原則5年)として消滅時効にかかることがあり、時効の完成猶予・更新(裁判上の請求等)との関係を踏まえた防御も検討されます(民法166条、民法147条)。
感情的な対立が激しくなる前に、資料収集(遺言・戸籍・評価書・通帳等)と時系列の整理を行い、早期に弁護士へご相談ください。
関連記事: 遺留分を支払わないとどうなる?
遺留分の支払いを拒否した場合はどうなりますか?
正当な法的根拠のない「拒否」や放置は、次のリスクを招くことがあります。
- 調停→訴訟→強制執行:判決・和解に基づき、預金・給与・不動産等が差押えされることがあります。
- 遅延損害金や費用負担:解決が長期化すると、法定利息分の負担や訴訟費用等が増えることがあります。
- 交渉条件の悪化:任意の分割払・猶予・担保付き合意の余地が狭まりがちです。
一方で、時効完成(1年/10年)、権利者でない、評価・計算の誤り、特別受益の参入など法律上の抗弁がある場合は、支払額の減額や請求棄却が認められることがあります(民法1048条)。
まずは法的に争える論点があるかを専門家と精査し、現実的な支払計画(期限の許与・分割・担保)と併せて提案するのが得策です。
関連記事: 遺留分を支払わないとどうなる?
遺留分の請求をされた際にかかる弁護士費用はいくらになりますか?
弁護士費用は事件の難易度・経済的利益(請求額・減額幅)・手続段階(交渉/調停/訴訟)などで変動します。一般には次の項目から構成されます。
- 相談料:初回無料〜有料まで事務所により運用が分かれます
- 着手金:交渉のみと訴訟対応とで金額が異なることがあります
- 報酬金:獲得・減額・早期解決などの成果に応じて発生することがあります
- 実費:収入印紙・郵券、資料取り寄せ費、不動産鑑定費用など
弁護士法人アクロピースでは、遺留分を請求された側では、着手金は抑え、減額に成功した時に報酬金をいただくプランをご用意しています。
早期に費用感を把握して方針を決めるのがおすすめです。
原則として弁護士費用は各自負担ですが、和解・判決で一部の費用負担が考慮されることもあります。
関連記事: 遺留分を請求された側の費用
まとめ|遺留分を渡さなくていい方法はあるが判断には法的知識が必要
遺留分を渡さなくてよいケースはありますが、法的に認められるのはごく一部です。代表的なのは、相続人による遺留分の事前放棄、相続放棄、相続人廃除、相続欠格、そして時効の完成などです。
ただし、いずれも厳格な要件や手続きがあり、自己判断で進めると無効になるおそれがあります。生前の対策としては、家庭裁判所の許可を得た放棄の申立てや、養子縁組・生命保険活用などで遺留分割合を調整する方法が有効です。
請求を受けた場合は、相続財産の範囲や評価、特別受益の有無を精査し、減額や分割交渉を検討すべきです。最終的には弁護士の助言のもと、法的リスクを抑えた形での解決を目指しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応