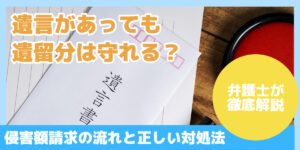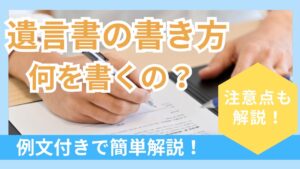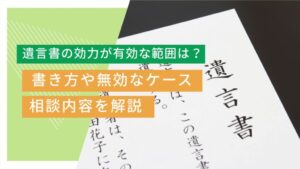【無料相談受付中】24時間365日対応
遺言書でできることは?できないことや書いたほうが良い場合も紹介
遺言書と聞くと、自身の遺産を配偶者や子どもに譲り渡す配分を指定できるもの、と考えている方が多いのですが、実は遺言書でできることはそれだけではありません。
たとえば、相続人とはまったく関係のない相手に遺産を譲り渡すこともできますし、遺言執行者を指定したり、隠し子を認知したりといったことも可能です。
遺言書はいわば自身の最後の意思表示であり、様々な効力を付与できるのです。
しかし、多くの方はわざわざ遺言書まで作成する必要はないと考えているのが現実です。
そこで今回は、遺言書でできることと遺言書を作成した方が良い場合についてご説明します。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺言書でできること
遺言書でできることといえば、大きくわけて6つのことがあります。
1.相続分の指定
民法では法定相続分といって、相続順位などによって相続人が相続できる相続分は決められています。
しかし、法定相続分よりも遺言書によって指定した相続分のほうが優先されるため、自らの指定したとおりの相続分を実現することができます。
2.相続人の廃除
相続人になる予定の方(推定相続人)の中で、被相続人への虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行などがみられる場合は、被相続人は自らの意思で相続人の廃除を行えます。
通常、家庭裁判所にて手続きを行うのですが、遺言書にて相続人廃除の意思表示をすることが可能です。
3.遺言執行者の指定
遺言の内容をより確実に実行するため、「遺言執行者」を指定することもできます。
指定された遺言執行者(委託による指定も可)は、相続人の廃除や相続分の分配などの手続きを、亡くなった方の代わりに行うことになります。
4.後見人の指定
遺言書では、遺言執行者の指定の他にも、「後見人」を指定することも可能です。
たとえば、相続人となる残された子が未成年である場合には、第三者を後見人に指定し、未成年者の財産管理などを委ねることが可能となっています。
関連記事:相続で胎児の場合の遺産分割協議はどうする?相続税申告の進め方についても紹介
5.相続人以外への贈与(遺贈)
遺言書では、相続人以外の相手への遺贈を指定することも可能です。
たとえば、そのままでは相続人になれない内縁の妻や夫、生前お世話になった友人などに遺贈ができます。
特に、誰も相続人がいない場合、そのままでは残された財産は国庫へと帰属してしまうため、譲り渡したい相手がいる場合に遺贈は有効な手段の一つです。
6.子の認知
婚姻していない女性との間に子どもがいた場合、その子を遺言で認知することができます。
当然、子として認知するため、相続人にすることができ、認知された子は、法定相続分を得ることになります。
遺言書でできないこと
遺言書は、亡くなった方の最後の意思表示ではあるものの、なんでもできるわけではありません。
できないことといえば、上記以外のことはほぼすべてなのですが、特に注意しなければならないのが「遺留分」までは侵すことができないという点です。
たとえば、認知した子どもに全財産を相続させるといった記載の遺言書を作成しても、他の法定相続人の遺留分までは侵害することができません。
他の法定相続人は、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)によって認知した子から自身の遺留分を取り戻すことができてしまいます。
相続人同士の争いの火種になる危険が強いため、遺留分権の侵害については注意して遺言書作成に臨まなければなりません。
関連記事:遺言書作成の注意点について解説
サービス一覧
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、お悩みを解決します。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺言書を作ることをお勧めする理由
近年高齢化が進み、世間では「相続」をめぐる様々な問題が発生しています。相続人を確定するために戸籍謄本を収集し、相続財産・相続債務を確定した上で相続人全員の間で遺産分割協議を行う。
これが相続手続きの一般的な流れですが、被相続人が遺言を残さないまま亡くなった以上は、相続財産をどのように分配するのかは各相続人の意思決定に委ねられることとなります。
相続人にすべてを委ねるというのも選択肢の1つではあります。
しかし、相続人同士の仲が良くない場合や、過去に婚姻していた際の子どもがいる(現在の家族が誰も知らない子がいる)場合などは、遺産分割協議が揉めてしまい、深刻なトラブルへと発展する恐れもあります。
せっかく相続人を確定し相続財産の特定・評価が終わっても、相続人間での協議がまとまらなければ元も子もありません。
また、相続人の廃除や後見人の指定、より確実に相続を実行するための遺言執行者の指定といった、遺言書でしかできないことを望む場合、遺言書は必須です。
被相続人の意思を実現する手段として、また、相続人間の紛争を予防する手段として、「遺言書」を作成しておくことが重要であると考えられます。
遺言書を用意したほうがいいケース
遺言書を作成すべきケースは、数えたらキリがありませんが、特に代表的なケースは以下が挙げられます。
- 配偶者の居住不動産を確保したい場合
- 相続財産の中に「自社株」や「事業用の資産」がある場合
- 相続財産が「現金・預貯金以外の財産」である場合
- 「相続人以外の者」に財産を承継させたい場合
- 先妻の子供と後妻が相続人となる場合
- 相続人の中に意思能力を欠く方がいる場合
- 相続人の中に連絡を取れない方がいる場合
- 被相続人にペットがいる場合
配偶者の居住用不動産を確保したい場合
たとえ相続財産が配偶者の居住用不動産であっても、全相続人が賛成しない限り、当該配偶者は居住用不動産を確保できないこととなってしまいます。
このような事態を避けるべく、居住用不動産を当該配偶者へ相続させる旨の遺言を残すのが望ましいと考えられます。
相続財産の中に「自社株」や「事業用の資産」がある場合
事業の後継者を指定したい場合、当該相続人に自社株や事業用の資産を相続させ、それ以外の相続人には他の資産を相続させることで、事業の円滑化を図ることができます。
遺言を残さなければ遺産分割協議の中で相続方法を決めることになりますが、協議がまとまらなければ自社株や事業用資産を後継者となる相続人へ承継させることはできません。
さらに相続財産は各相続人の共有状態のままとなり、会社の意思決定等の重要な局面でさえも各相続人の関与が必要となってしまいます。
このような事態を避けるため、自社株や事業用の資産の相続について遺言書の中で遺産分割方法の指定をしておくことが重要となります。
相続財産が「現金・預貯金以外の財産」である場合
相続財産の中にある程度の現金・預貯金があれば分割も容易で協議もまとまりやすいですが、相続財産の中に現金・預貯金がほとんどなく、不動産や株式のような財産が相続財産となる場合には、当該相続財産を換価した上で金銭を分配する等、遺産分割の方法・手段を指定することも有効な手段となります。
相続税の申告が必要な事例では、相続財産の換価に先立つ遺産分割協議を省略することができるため、申告期間内に迅速に手続きを進められることとなります。
相続人間で協議がまとまらないと想定される場合
相続財産が現金・預貯金だけであっても、「特別受益」や「寄与分」を主張する相続人もいます。
被相続人の意思として、相続人間で公平に分配してほしい場合や他に希望の分配方法がある場合には、遺言をもって相続分の指定や遺産分割方法の指定をすることも可能です。
また、相続人によって異なる相続割合を定めた場合であっても、各相続人の遺留分を侵害しない限り、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象とはならないため、被相続人の意思が実現されることとなります。
関連記事:遺産相続でもめたら!もめた場合の対処法と遺産分割協議のスムーズな進め方
「相続人以外の者」に財産を承継させたい場合
法定相続人がいないものの、生前に自分の面倒をよく見てくれた相続人以外の方や内縁の配偶者がいるような場合においては、遺言を残すことにより、はじめてその方たちに財産を承継させることが可能となります(法定相続人がいない状況で遺言をしないまま相続が発生した場合、被相続人の財産は国庫へ帰属することとなります)。
一方で、法定相続人がいるものの、相続人以外の者に財産を承継させたい場合においては、当該法定相続人の遺留分を確保する等、遺留分侵害額請求を回避するための措置を講ずることも重要となります。
先妻の子供と後妻が相続人となる場合
先妻の子供と後妻が相続人となる場合には、相続財産の有無にかかわらず、感情的な対立等により遺産分割協議をまとめることが困難な場合が少なくありません。
紛争予防の観点からも各相続人の遺留分に配慮した遺言書を書いておくことが重要となります。
相続人の中に意思能力を欠く方がいる場合
相続人の中に認知症等により意思能力を欠く方がいる場合には、遺言をもってあらかじめ遺産分割方法を指定しておくことにより、相続手続きを円滑に進めることが可能となります。
一方で、このような場合に遺言書を残さず相続が発生してしまった場合には、意思能力を欠く相続人について成年後見人等の選任が必要となってしまい、通常の相続手続きの場合に比べて費用と労力がかかってしまいます。
相続人の中に連絡を取れない方がいる場合
相続人の中に連絡を取れない方がいる場合、当該相続人の関与なしで遺産分割協議を行うことができないため、相続手続きが難航することが予想されます。
このような場合には、遺言書で遺産分割方法を指定しておくことで、遺産分割協議を省略でき、当該相続人の関与が不要となるため、相続発生後の手続きを円滑に進めることができます。
関連記事:【遺産相続で兄弟が絶縁】連絡が取れない法定相続人がいるときの対処法
被相続人にペットがいる場合
被相続人にペットがいる場合、同居の親族がいれば良いのですが、同居の親族がいないような場合、相続人の誰かがペットの面倒を見てくれるとは限りません。
遺言書でペットの面倒を見ることを条件に財産を相続させるような遺言をすることも認められています(このような遺言を「負担付遺贈」と言います)。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺言作成時には遺留分の侵害に注意する
相続人が「配偶者」・「被相続人の子」・「被相続人の直系尊属」である場合には、法律上定められた割合の遺留分が認められることになります。
特定の相続人にのみ全ての財産又はほとんどの財産を相続させる遺言を行ったような場合には、他の相続人の遺留分が侵害されることになるため、遺留分侵害額請求の対象となります。
被相続人にある程度の財産があるような場合、他の相続人にも遺留分を侵害しない範囲で財産を相続させる旨の遺言を残しておけば遺留分侵害額請求を回避することができます。
しかし、遺留分侵害額請求は遺留分を有する相続人が請求をして初めてその効果が生じるものであり、法律上も遺留分侵害額請求権の行使について、期間制限が設けられています。
逆に言えば、遺留分侵害額請求がされない以上は、遺言書で指定されたとおりの相続を進めることも可能となります。
関連記事:遺留分侵害額請求の記事を見る
他方で、「被相続人の兄弟姉妹」には、法律上そもそも遺留分が認められないため、遺留分侵害額請求を受けること自体考慮する必要はありません。
例えば、「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」が相続人となる場合で「配偶者」に全ての財産を相続させる遺言をした場合には、当該配偶者へ全ての財産を確実に相続させることが可能となります。
もし、遺言書の作成について何か不安に感じていることがあれば、ぜひ弊所にご相談ください。
ご事情をすべて伺った上で、遺言書の必要性についてアドバイスさせていただきます。
関連記事:遺言書の遺留分に関する記事を見る
姉妹で共有するマンションで、片方が亡くなった後も住み続けられるよう遺言で備えられた事例
相続においては、故人の財産がどのように承継されるかによって、残された家族の生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
特に、共有名義の不動産は、遺言がなければ予期せぬ形で権利が分散し、住み続けることが困難になるリスクを伴います。実際に当事務所で解決した、次のような事例です。
Aさんは妹のBさんと共有名義で購入したマンションで共に暮らしていましたが、Bさんの健康状態悪化に伴い、将来どちらかが亡くなった場合にも、残された一方が安心して住み続けられるかという不安を抱えていました。遺言がない場合、マンションの持分は他の兄弟姉妹やその子に相続されてしまい、残された姉妹がマンションに住み続けられなくなる可能性がありました。
そこで弁護士が、現状のヒアリングを通じて法的なリスクを説明し、遺言の必要性を提案しました。その結果、お互いのマンション持分を相手に相続させる内容の公正証書遺言を作成し、法的な効力を確保しました。
これにより、どちらかが亡くなっても、残された姉妹が引き続きマンションに安心して住み続けられる環境が整いました。
今回の解決ポイントは以下の通りです。
- 相続人が兄弟姉妹のみであり、遺留分侵害額請求のリスクがないため、柔軟な遺言内容が可能であったこと。
- お互いの持分を相手に相続させる遺言により、残された姉妹の住まいを確実に守ることができたこと。
- 遺言によって相続トラブルを未然に防ぎ、依頼者の長年の生活基盤の安心を確保できたこと。
本事例が示すように共有不動産を巡る相続では、将来の生活を守るための適切な法的備えが不可欠です。
遺言の有無によって、住み慣れた家を失うリスクを回避し、安心して生活を継続できるかどうかが大きく左右されます。
ご家族との関係が良好であっても、法的な観点からの準備が重要であり、専門家への相談を通じて将来を見据えた対策を講じることが、不測の事態を防ぐための鍵となります。

相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応