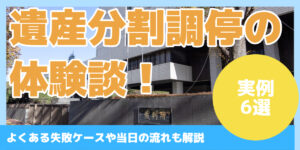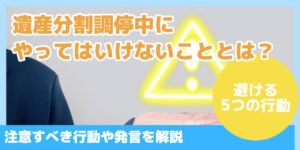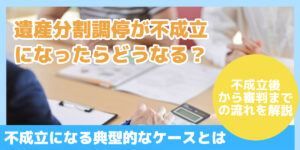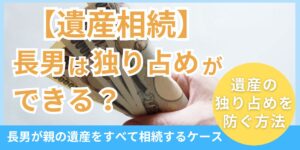【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割協議における預貯金の分け方、記載方法を弁護士が解説
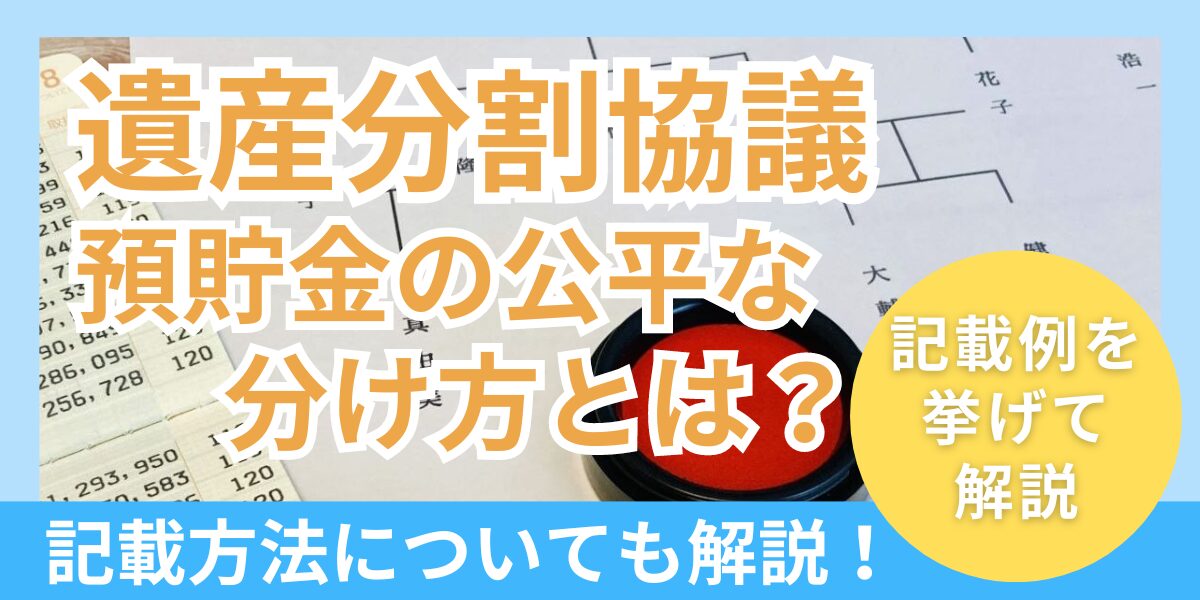
相続が発生すると、相続人が全員集まって遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議において、意外と悩んでしまうのが「預貯金の分け方」です。

この記事では、遺産相続における預貯金の公平な分配方法、遺産分割協議書への記載方法を弁護士がわかりやすく解説します。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割協議書とは
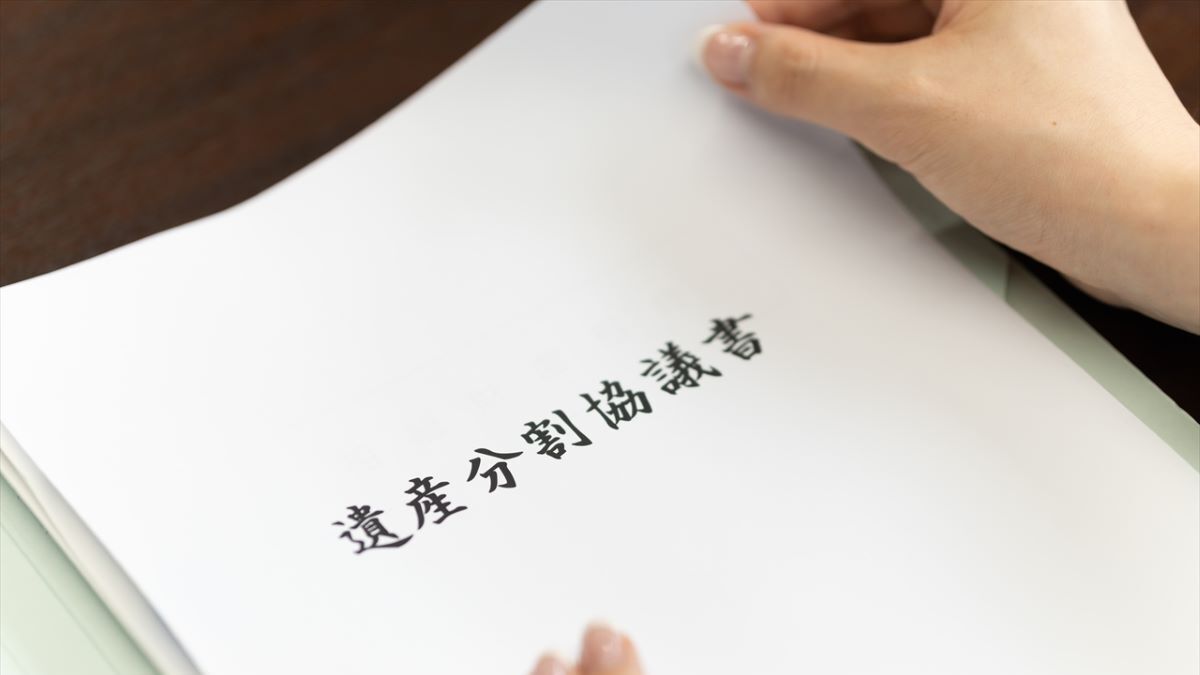
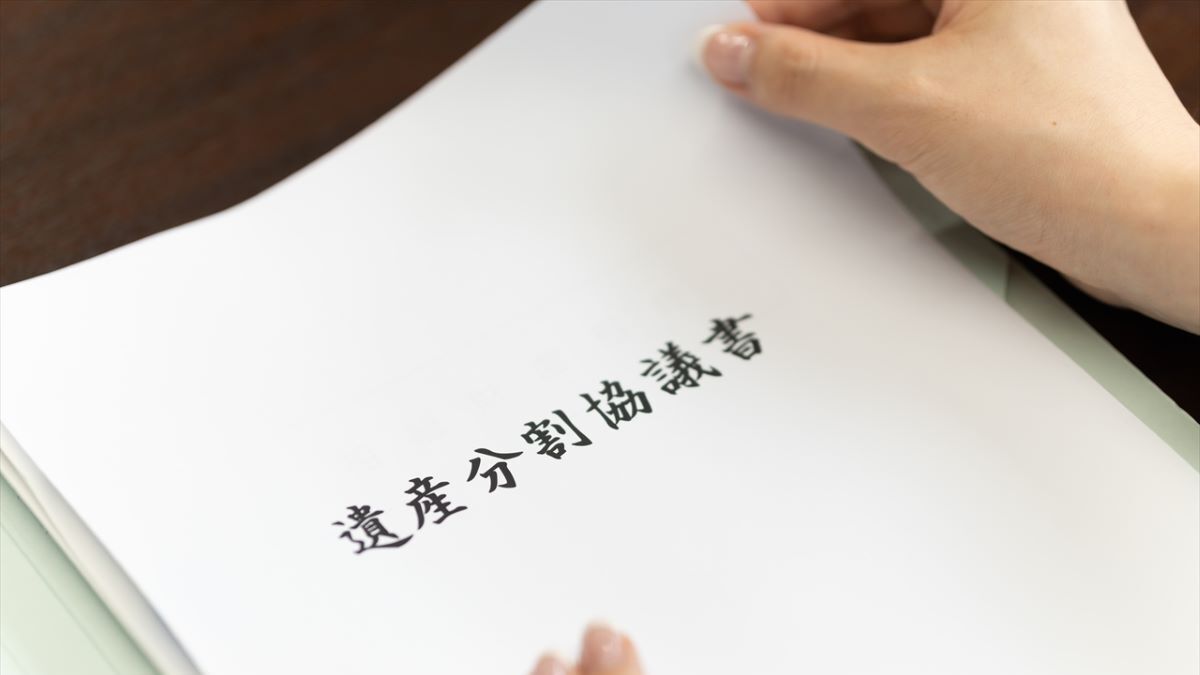
遺産分割(遺産分割協議)とは、法定相続人が全員参加し、相続財産の分け方を決定する手続きのことです。
遺産分割協議で決まった内容をもとに、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、話し合いによって決定した各相続人への分割割合などを記載するのが一般的です。
遺産分割協議書は、以下のような相続手続きの際に、提出を求められることがあります。
- 相続税の申告・納付
- 不動産相続登記の申請
- 被相続人名義の口座の解約や払い戻し
- 株式の相続 など
遺産分割の具体的な進め方については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:遺産分割協議の進め方と揉めた場合の解決策
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産分割における預貯金の分け方・手順


ここからは、遺産分割における預貯金の分け方と手順について解説します。
STEP1:相続財産を調査する
まずは、預貯金も含めた相続財産がどのくらいあるのか、全体像を把握しましょう。
相続の財産調査の対象となる財産には、以下のようなものがあります。
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 有価証券
- 投資信託
- 貴金属
- 美術品
- 骨董品
- 車両
- 借金
- ローン など
相続財産には、プラスの財産だけではなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄も可能です。
相続放棄の手続きは、相続開始から3ヶ月以内に行いましょう。
STEP2:分割割合を決める
相続の対象となる財産が明確になったら、次に分割割合を決定します。
法定相続の場合、相続権が認められるのは、配偶者と一部の血族のみです(民法887条~890条)。
- 被相続人の配偶者(常に相続人となる)
- 被相続人の子ども(第1順位)
- 被相続人の直系尊属(第2順位・父母や祖父母など)
- 被相続人の兄弟姉妹(第3順位)
参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
第1順位から第3順位の誰が相続人になるかによって、それぞれの相続割合が変わります(民法900条)。
| 配偶者と子どもが相続人の場合 | 配偶者2分の1 子ども(2人以上のときは全員で)2分の1 |
|---|---|
| 配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1 |
例えば、預貯金5,000万円を配偶者と子ども2人が相続する場合、以下のように分割します。
配偶者(1/2):2,500万円
長男(1/4):1,250万円
次男(1/4):1,250万円
もちろん、預貯金以外の財産がある場合は、不動産が妻、有価証券が長男、預貯金が次男という分け方でも構いません。
遺言書に分割割合の記載がある場合、それに従うのが原則です。
ただし、相続人全員の同意があれば、必ずしも遺言書通りに分ける必要はありません。
いずれの場合も相続人全員で話し合い、納得のうえで決定することが大切です。
関連記事:相続に同意しないとどうなる?遺産分割協議書に同意しない場合に弁護士に依頼するメリット
STEP3:分割方法を決める
預貯金の分割割合が決まったら、次に分割方法を決めます。
預貯金の相続における分割方法は、主に以下の4パターンがあります。
- 払い戻した現金を分ける
- 銀行口座ごとに分割する
- 代償分割を行う
- 預貯金以外の財産で調整する
払い戻した現金を分ける
払い戻した現金を分ける場合、被相続人名義の銀行口座の解約手続きが必要です。
払い戻した現金は代表相続人の銀行口座に振り込まれ、代表相続人が各相続人に振り込むというのが基本的な分割方法ですが、金融機関によっては、各相続人の口座に直接振り込んでくれるケースもあるようです。
銀行口座を解約する手間はかかるものの、相続割合に応じた現金をわかりやすく分配できるため、公平な遺産分割ができるというメリットがあります。
銀行口座ごとに分割する
被相続人が複数の金融機関に預貯金を残していた場合、A銀行は長男、B銀行は次男…というように、銀行口座ごとに分割することも可能です。
ただし、各銀行口座の残高によっては、公平な分割ができないケースもあります。
代償分割を行う
被相続人が残した銀行口座の数が多い場合、代表相続人が解約・払い戻し手続きをして現金を受け取り、それを各相続人の口座に振り込むまでに、時間がかかることが予想されます。
その場合、代表相続人が各相続人に対して先に代償金を支払う代償分割を行うことも考えられます。
例えば、複数の銀行口座にある預貯金残高の合計が1,200万円で、それを配偶者と子ども2人で相続する場合、配偶者から長男・次男に300万円ずつの代償金を支払います。
そして配偶者は遺産分割完了後、被相続人の銀行口座をひとつずつ解約し、現金の払い戻しを受けるという流れです。
預貯金の相続で代償分割の方法がとられることは、あまり多くはありません。
代償分割を行う際は、代償金が贈与税の対象とならないように、遺産分割の方法が代償分割である旨を、遺産分割協議書にも明記しておきましょう。
預貯金以外の財産で調整する
預貯金以外にも財産がある場合には、相続財産全体で調整することも可能です。
例えば、以下のような分け方が考えられます。
配偶者:不動産を相続
長男:有価証券を相続
次男:預貯金を相続
完全に公平な相続とはいかない場合が多いですが、相続人全員で話し合い、合意のもとで決められた分割方法であれば問題ありません。
また、公平な相続を目指すのであれば、価値の高い遺産を相続した相続人が、それ以外の相続人に代償金を支払って相続額を公平に調整するということも考えられます。
STEP4:遺産分割協議書を作成する
預貯金の相続割合と分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
ここでは、相続財産が預貯金のみの場合の遺産分割協議書の書き方、サンプル(記載例)をいくつか紹介します。
銀行口座が1つの場合
被相続人の預貯金がある銀行口座が1つのみで、解約して払い戻した現金を分割する際の遺産分割協議書のサンプル(記載例)です。
以下の遺産については、Aが3分の1、Bが3分の1、Cが3分の1の割合でそれぞれ取得する。
Aは相続人を代表し、以下の遺産の解約・払い戻しの手続きを行う。
なお、B・Cの取得分については、それぞれが指定する口座に振り込んで引き渡すものとする。
また、振込手数料はB・Cの負担とする。
(1)預貯金
〇〇銀行〇〇支店 普通預金
口座番号:〇〇〇〇〇〇
上記は、代表相続人の口座に振込み、代表相続人が各相続人に振り込むパターンのサンプル(記載例)です。
遺産分割協議書には3分の1、3分の2などの割合のみの記載で問題ありません。
1円以下の端数については記載不要です。
銀行口座が複数ある場合
続いては、複数の銀行口座があり、複数の相続人がいる場合の遺産分割協議書のサンプル(記載例)を紹介します。
相続人Aは、以下の遺産を取得する。
(1)預貯金
1. 〇〇銀行〇〇支店 普通預金
口座番号:〇〇〇〇〇〇
2. ◻︎◻︎銀行 ◻︎ ◻︎支店 普通預金
口座番号:〇〇〇〇〇〇
3.△△銀行△△支店 普通預金
口座番号:〇〇〇〇〇〇
相続人Aは、(1)に記載の遺産を取得する代償として、B・C対し、それぞれ2,000,000円を20XX年XX月XX日までに支払うものとする。
上記は、代償分割のパターンにおける遺産分割協議書のサンプル(記載例)です。
この場合も、預貯金残高の記載は不要です。



各銀行口座の残高を記載すること自体は問題ありませんが、利息などの影響で、協議書に書かれた残高と実際の残高に相違がでてしまった場合、遺産分割協議書の再作成が必要になります。
預貯金の遺産分割で知っておきたいポイント・注意点


続いては、預貯金の遺産分割でよくある疑問やトラブル、注意点について説明します。
被相続人の銀行口座は凍結される
銀行が被相続人の死亡の事実を知った時点で、被相続人の銀行口座は凍結されます。
銀行口座の凍結後は預貯金を引き出せなくなり、クレジットカードや公共料金等の口座振替もできなくなるので、注意しましょう。
ただし、死亡届を提出したからといって、自治体から銀行に死亡の事実が伝わるわけではありません。
銀行は、家族からの連絡を受けて、初めて被相続人が亡くなったことを知ることになります。
また、銀行間で被相続人の死亡の事実を共有するようなシステムもありません。
被相続人が複数の銀行口座を保有していた場合、すべての銀行口座が同時に凍結されるわけではなく、金融機関ごとに手続きが必要となります。
遺産分割前に勝手に預貯金を引き出すのはNG
銀行口座が凍結する前に、相続人の一人が勝手に預貯金を引き出してしまうと、相続トラブルのもとになります。
銀行口座が凍結されると、遺産分割が完了するまで原則引き出しはできないため、いくらかの現金を手元に置いておきたい気持ちはわかりますが、被相続人の口座は原則として触らないようにしましょう。
葬儀費用などは預貯金の仮払い制度を利用できる
遺産分割前に葬儀費用などでどうしても現金が必要な場合に限り、金融機関の仮払い制度を利用できます。
仮払い制度は、2019年7月から開始された新制度です。
家庭裁判所への申し立て等を行わずとも、一定の範囲内であれば、金融機関から単独で払い戻しを受けられます(民法909条の2)。
【仮払い制度による払い戻し可能額】
相続開始時の預貯金残高×3分の1×払い戻しを行う相続人の法定相続分



ただし、同一金融機関からの払い戻しは、150万円が上限です。
預貯金の遺産分割における必要書類一覧
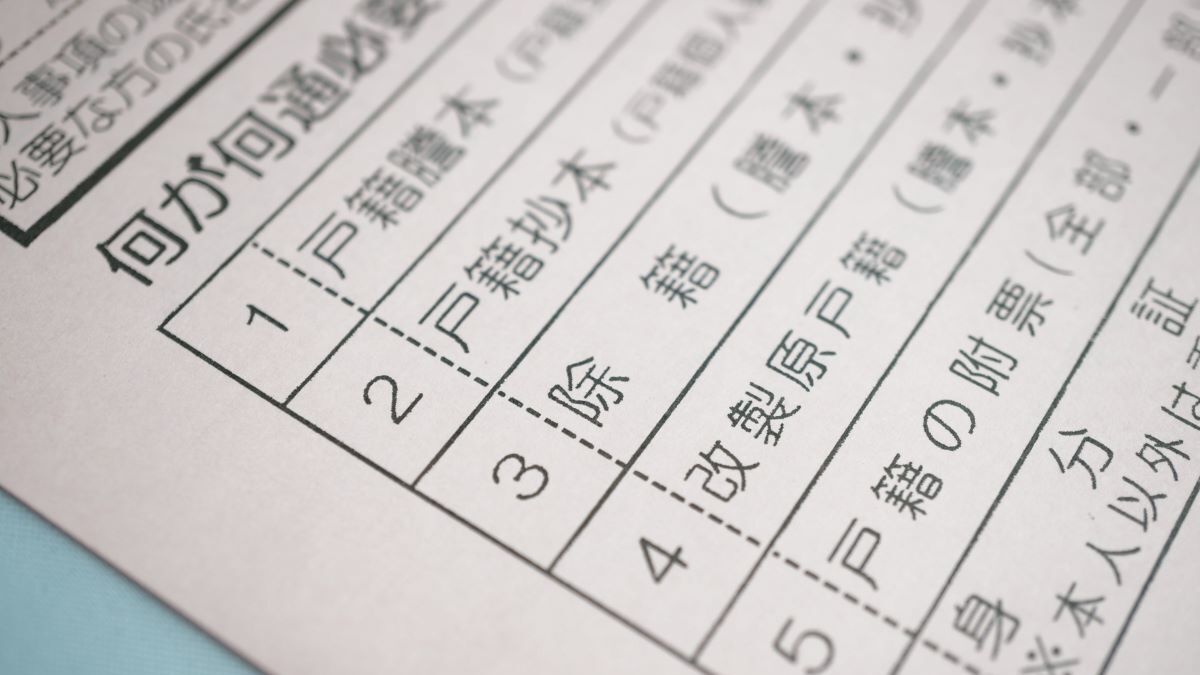
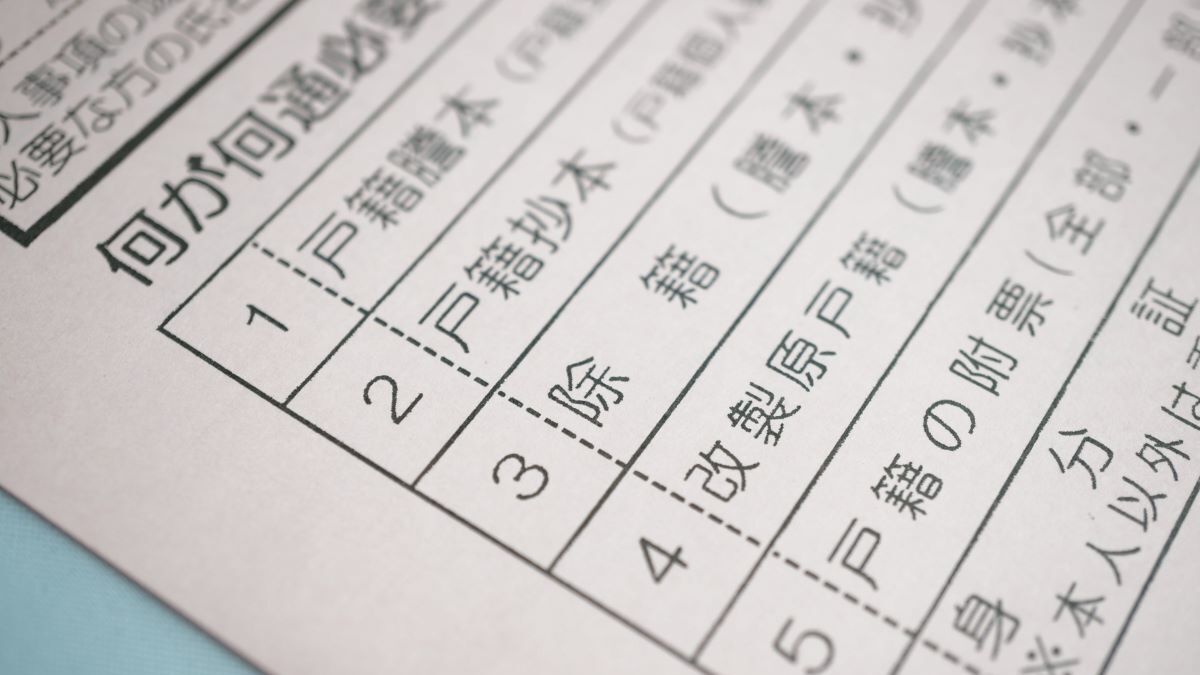
預貯金の遺産分割においては、以下のような書類が必要になります。
- 金融機関指定の相続手続き依頼書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人名義の通帳およびキャッシュカード
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本など
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 窓口で手続きする人の本人確認書類 など
相続人全員の印鑑登録証明書については、発行から3ヶ月以内など、期限の定めがあるので注意してください。
上記はあくまでも一般的な必要書類であり、金融機関によって異なるケースもあります。



預貯金の遺産分割手続きの際は、被相続人の銀行口座がある金融機関に確認しましょう。
【遺産分割協議書】預金の分け方についてよくある疑問
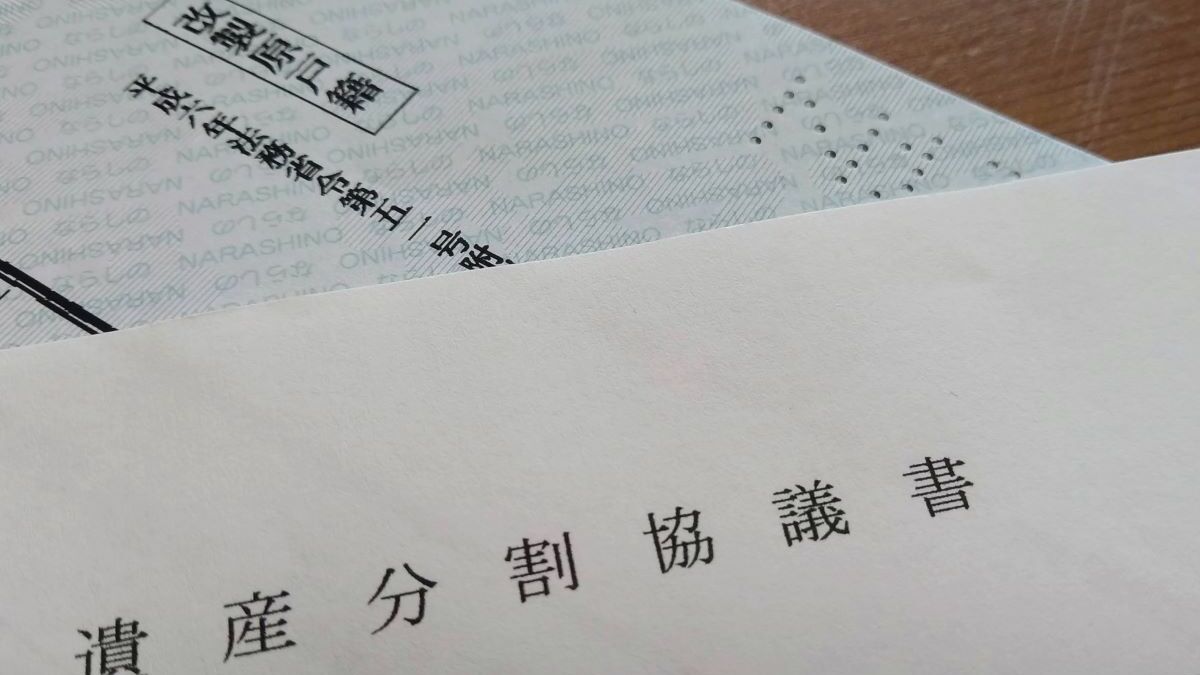
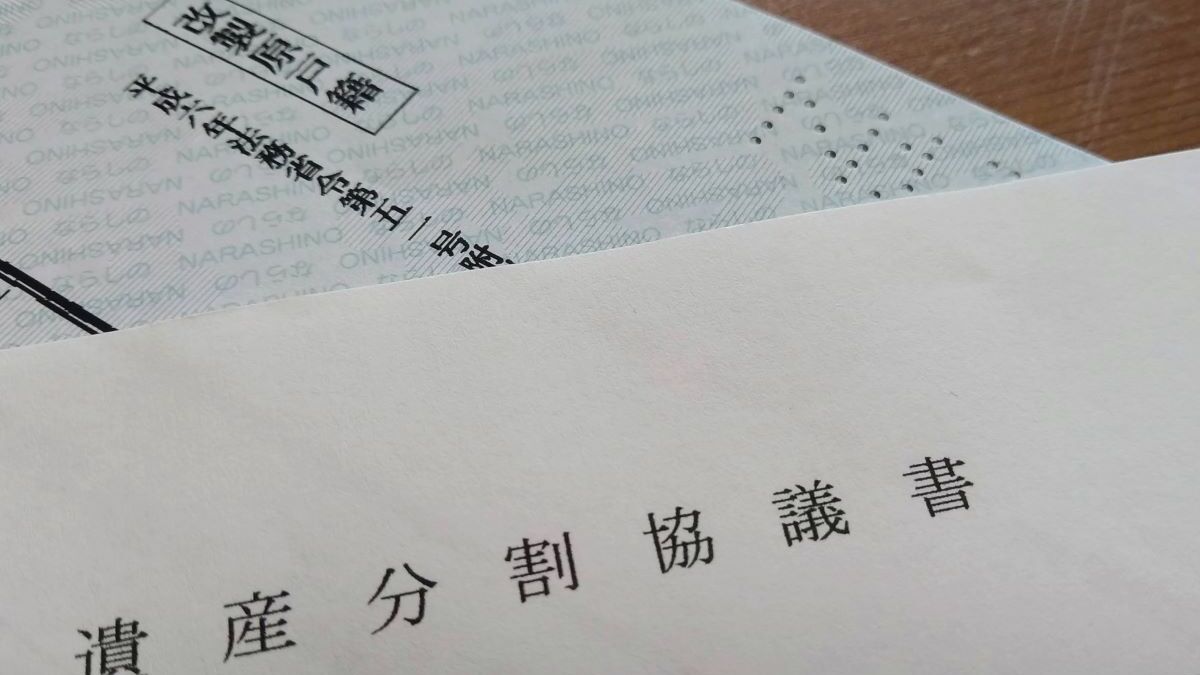
続いては、遺産分割協議書における預金の分け方についてのよくある疑問にお応えしていきます。
端数がでる場合はどうしたらいいですか?
相続人全員の合意があれば、必ずしも1円単位で等分する必要はありません。
端数分をどうするかは、話し合って決めましょう。
遺産分割協議書には具体的な金額を記載せず、「3分の1ずつ」など相続割合を記載すれば問題ありません。
遺産分割協議書には預貯金の残高を記載すべきですか?
遺産分割協議書には、必ずしも預貯金の残高を記載する必要はありません。
残高を記載したほうがわかりやすいというメリットはあるものの、利息などの影響で、協議書に記載された残高と実際の残高に相違がでてしまった場合、遺産分割協議書の再作成が必要となります。
遺産分割協議書は自分で作成できますか?
遺産分割協議書に決められた書式はないため、自分で作成することも可能です。
「遺産分割協議書 ひな形」などで検索し、インターネット上にあるテンプレートをダウンロードして使うこともできるでしょう。
ただし、遺産分割協議書は金融機関や税務署、法務局などに提出する重要な書類です。
正確な記載のためには相続財産の調査などが必要で、記載にミスは許されません。
そのため、基本的には弁護士などの専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
被相続人の預貯金に関するトラブルを解決した事例
預貯金の扱いをめぐり争いとなり、調停で整理して解決したケースがあります。
“被相続人Aさんが亡くなったが、生前に兄のCさんが管理していたAさん名義の預金口座から多額の金銭が引き出されていた。依頼人Bさんとしては出金された金銭を使途不明金として追及したいとのご相談。”
この事例の課題としては、
・Aさんの財産を管理していた相続人Cさんの使途不明金について調査すること
があげられます。
そこで
- 依頼人Bさんの日記やCさんへのメール等から預金口座からの出金額が介護の実態と比較して過剰であると主張
- 過去の時系列と金額の整合性を丁寧に組み立て、主張を論理的に展開
というご対応をさせていただき、家庭裁判所の調停委員にも理解を得ることができました。
被相続人のAさんの預金口座から出金された半分以上が使途不明金と認められ、依頼人Bさんに納得していただき、和解が成立しました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


まとめ


預貯金の遺産分割は、相続人全員の合意のもとで行われます。
遺産が預貯金のみの場合は、銀行口座を解約し、払い戻した現金を相続割合に応じて分ければ良いため、比較的公平な遺産分割がしやすいでしょう。
しかし、不動産や有価証券など、ほかの財産がある場合には、遺産分割協議に時間がかかることも考えられます。
- 遺産分割における預貯金の分け方は複数ある
- 遺産分割協議書には相続人の分割割合と預貯金の分割方法を明記する
- 遺産分割協議書の作成は、弁護士などの専門家に依頼するとスムーズ
- 被相続人が亡くなったことを銀行に連絡すると銀行口座は凍結される
- どうしても現金が必要な場合、相続人は仮払い制度を利用できる
預貯金の遺産分割や遺産分割協議書の作成は、弁護士に依頼するとスムーズです。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応