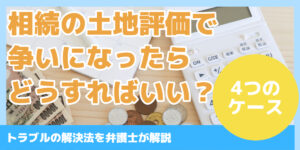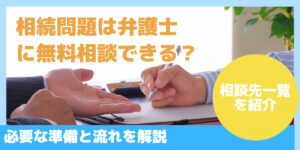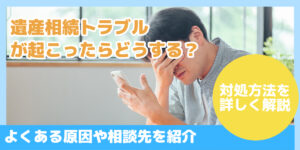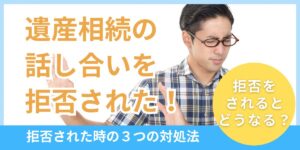【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続の裁判とは?手続きの流れや必要な費用、期間を弁護士が解説
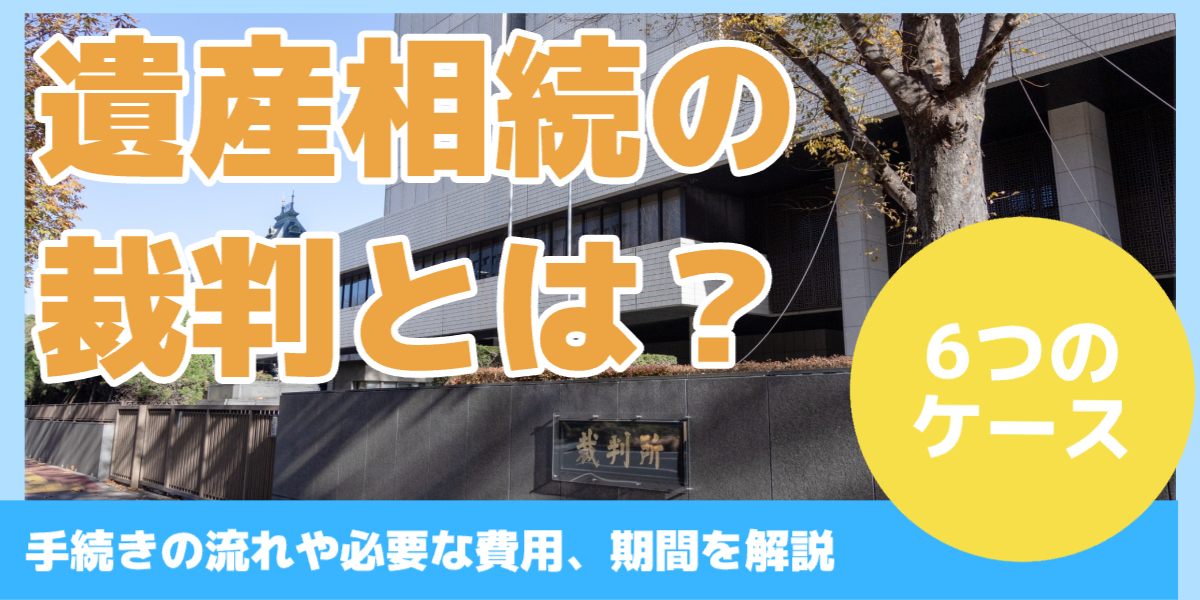
「相続のトラブルが起こっていて、もう話し合いでは解決できなさそうだ」
「遺産相続の裁判はどのように進むのだろう?」
遺産相続をめぐる対立が深刻化し、このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
遺産相続では、「遺産分割」それ自体のトラブルは調停や審判で解決を目指しますが、遺産分割以外のトラブルは裁判(訴訟)で争うこともあります。
裁判で争うのは、例えば相続人が誰なのかという問題や、どれが遺産に属するのかというような問題です。
この記事では、遺産相続トラブルで裁判になるケースや具体的な手続きの進め方、費用や期間を弁護士が解説します。
法的手続きへ進むための確かな知識を得て、ご自身の正当な権利を守る準備を始めましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続トラブルの多くは「裁判(訴訟)」ではなく「調停・審判」で解決を目指す
遺産相続トラブルは、「裁判(訴訟)」で解決するものと「調停・審判」で解決するものに分かれています。ですからなんでも訴訟になるわけではありません。
法廷で争う訴訟は、相続の「前提問題」と言われるような相続人の範囲、遺産の範囲に争いがあるような場合や、遺言の有効性や使い込み等の問題解決をしたい場合に行います。
ただ、実際には、それらのケースが訴訟を行わずとも家庭裁判所の調停・審判の手続きを行うことで解決されています。
まず「遺産の分け方(遺産分割)」そのものは、訴訟で争えません。 これは家事事件手続法により、家庭裁判所の調停または審判で扱うと定められているためです。(参照:家事事件手続法|第244条)
そのため、協議がまとまらない場合は、まず「遺産分割調停」で話し合います。 調停が不成立なら「審判」に移行し、裁判官が判断を下します。
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 遺産分割調停 | 調停委員を介した「話し合い」による合意を目指す手続き。 |
| 遺産分割審判 | 調停不成立の際に、裁判官が法的に分割方法を「決定」する手続き。 |
遺産相続で裁判(訴訟)を起こすのは、遺産分割の前提となる事柄(前提問題)に法的な争いがあるケースや、遺言の有効性に争いがある場合、遺産の使い込みを争いたい場合などです。
例えば、以下のような争点が該当します。
- 遺言書の有効性(例:偽造の疑い)
- 遺産の範囲(例:他人名義の預金)
- 相続人の範囲(例:親子関係の存否)
これらの前提問題は調停・審判では判断できないため、まず「訴訟」で白黒をつけます。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫その判決が確定した後、遺産分割(調停・審判)の手続きに進むのです。
関連記事:遺産分割調停が不成立になったその後はどうなる?審判移行や強制執行についても解説【弁護士監修】
遺産相続トラブルで「裁判(訴訟)」になりうる6つのケース
遺産分割の前提問題として「訴訟(裁判)」に発展する可能性が高いのは、主に以下の6つのケースです。
これらの訴訟で判決が確定して初めて、具体的な遺産分割(調停・審判)の話し合いに進めます。各ケースでどのような裁判が行われるのかを詳しく見ていきましょう。
関連記事:遺産相続の裁判で負けるケースとは?リスクや事前にすべき対策を弁護士が解説
ケース1:遺言書の有効性を争う(遺言無効確認訴訟)
「遺言書の内容が不自然だ」「作成時の父は認知症だったはずだ」といったケースでは、遺言書の効力そのものを争う「遺言無効確認訴訟」に発展することがあります。
遺言の有効性によって、その後の遺産分割の方法が根本から変わる可能性があるため、最も重要な前提問題の一つです。
もし遺言が無効と判断されれば、その遺言は初めからなかったものとして扱われます。 その結果、法定相続人が法律に基づいた相続分で遺産を分けるか、改めて相続人全員で遺産分割協議を行うことになるでしょう。
この訴訟が提起される主なケースは、以下の通りです。
| 主張内容 | 詳細 |
|---|---|
| 遺言能力の欠如 | 遺言書作成時、被相続人が認知症などで正常な判断能力(遺言能力)を欠いていたと主張する場合。 |
| 方式(形式)の不備 | 法律で定められた遺言の要件を満たしていない場合。 ・自筆証書遺言が自筆がされていない ・秘密証書遺言を作ったが日付が記載されていない |
| 偽造・変造の疑い | 筆跡が被相続人のものと異なるなど、第三者によって偽造された疑いがある場合。 |
これらの主張を裏付けるためには、客観的な証拠が不可欠です。 特に遺言能力の欠如や偽造の立証は専門的な判断を要するため、弁護士との綿密な準備が必要となります。
ケース2:遺産の「使い込み」を取り戻す(不当利得返還請求訴訟)
特定の相続人による遺産の「使い込み」が疑われ、話し合いでの返還に応じないといったケースでは、「不当利得返還請求訴訟」という裁判手続きが必要になることがあります。 これは遺産分割調停・審判とは別立ての「民事訴訟」として提起されます。
この訴訟において、使い込みを主張する側が立証する必要がある点は以下のとおりです。
- 被相続人の財産から出金があったこと
- その出金が、被相続人の意思や利益に基づかないこと(=不当であること)
- それによって出金した相続人が利益を得たこと
例えば、被相続人の預金を管理していた相続人が、無断で多額の出金や送金を繰り返していたケースが該当します。
裁判では、まず出金をしたのが誰だったのかが問題になることが多いでしょう。その後、預金取引履歴などの証拠に基づき、その出金が本当に被相続人のための支出(医療費や生活費など)だったのかが厳しく問われます。
使い込みが認定されれば、その金額を遺産に戻す、または当該相続人の相続分から差し引く形で清算されるのが一般的です。
ケース3:「遺産の範囲」に争いがある(遺産確認訴訟)
「他人名義のこの預金は、実質的に故人の遺産ではないか」といったように、財産が遺産に含まれるか否かで見解が対立するケースでは、「遺産確認訴訟」を提起する必要があります。
遺産分割調停は、あくまで「遺産であること」に争いがない財産をどう分けるかを話し合う場です。 そのため、ある財産が遺産か否かで相続人間の見解が対立する場合、まずこの訴訟で法的に確定させる必要があります。
この訴訟の対象となりやすい財産には、以下のようなものがあります。
| 争いになりやすい財産の例 | 概要と争点 |
|---|---|
| 名義預金 | 故人が配偶者や子の名義で積み立てていた預金。 (争点:実質的な所有者は故人か、名義人への贈与か) |
| 名義不動産 | 故人が購入資金を出したが、登記名義が他人になっている不動産。 (争点:実質的な所有権は故人にあるか) |
| 生命保険金 | 特定の相続人が受取人だが、その金額が著しく不公平を生む場合。 (争点:実質的に遺産の前渡し(特別受益)と評価すべきか) |
特に名義預金は典型的な争点です。 裁判所は、資金の出所(故人の口座からか)、通帳や印鑑の管理者、名義人がその預金の存在を知っていたかなどを総合的に考慮し、実質的な所有者を判断します。
この訴訟で「遺産である」と確定して初めて、その財産は遺産分割調停・審判の対象となります。
ケース4:「相続人」の範囲に争いがある(相続人不存在確認訴訟など)
「戸籍上の親子関係は実在するのか」「故人の認知は有効か」など、相続人の範囲自体が争点となるケースも、裁判(訴訟)で解決を図る必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。 相続人が一人でも欠けていたり、相続人でない人が加わっていたりすると、その協議は無効となります。
そのため、戸籍上の記載だけでは判断できない複雑な身分関係に争いがある場合、まずこの「人事訴訟」で相続人を確定させます。
具体的な訴訟の種類は以下のとおりです。
| 訴訟の種類 | 概要 |
|---|---|
| 親子関係不存在確認訴訟 | 戸籍上は親子でも、血縁関係がない(例:妻が夫以外の男性との間にもうけた子)ことを法的に確認する場合。 |
| 認知の訴え | 被相続人から生前に認知されなかった子が、死後に認知を求め、相続権を確定させる場合。 |
| 養子縁組無効確認訴訟 | 当事者間に縁組の意思がなかった(例:相続目的で一方的に届出された)として、養子縁組の効力を争う場合。 |
これらの訴訟では、DNA鑑定などの科学的証拠や、当事者の意思に関する証言が重要な判断材料となります。
相続人が一人でも増減すれば、法定相続分は大きく変動します。 よって、遺産分割の前に、まず相続人の範囲を法的に確定させる必要があるのです。
ケース5:「遺留分」を請求する(遺留分侵害額請求)
遺言や贈与によって最低限の取り分(遺留分)が侵害されたケースでは、交渉や調停がまとまらなければ、最終的に「遺留分侵害額請求訴訟」に発展します。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)です。 「長男に全財産を相続させる」といった遺言や、生前の多額の贈与により、他の相続人の取り分が遺留分を下回った場合が典型例です。
2019年の民法改正により、この権利は「遺留分侵害額請求」として、不足分を金銭で支払うよう請求する権利に変わりました。(以前は現物返還)
これは遺産分割とは別の手続きであり、財産を多く受け取った相手方(相続人以外の場合も含む)に対して個別に権利行使します。
| 手続きの流れ | 概要 |
|---|---|
| 1. 交渉(内容証明郵便) | まずは相手方に対し、遺留分を侵害している旨と遺留分侵害額請求権を行使すること、また請求額を記載した内容証明郵便を送付し、交渉を開始します。 |
| 2. 調停 | 交渉でまとまらない場合、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立て、調停委員を介して話し合います。 |
| 3. 訴訟 | 調停でも不成立となった場合、地方裁判所(または簡易裁判所)に「訴訟」を提起し、裁判官の判決を求めます。 |
最も重要な注意点は「時効」です。 この権利は「相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年間」もしくは「相続開始から10年」で権利は消滅します。
期限が非常に短いため、迅速な対応が不可欠です。
ケース6:遺産分割協議を無効にしたい(遺産分割協議無効確認訴訟)
「脅されてサインしてしまった」「重要な財産を隠されていた」など、一度成立した遺産分割協議の前提に重大な問題があったケースでは、「遺産分割協議無効確認訴訟」を提起する可能性があります。
一度成立した合意を覆すため、認められるハードルは非常に高いです。 「合意した内容が気に入らない」といった理由だけでは、無効は認められません。
無効が法的に認められる主な理由は、以下の通りです。
| 無効が認められる主な理由 | 概要 |
|---|---|
| 相続人の欠落 | 相続人の一部が参加していなかった(全員参加が必須要件)。 |
| 詐欺・強迫 | 他の相続人による詐欺(嘘の説明)や脅迫によって、無理やり合意させられた。 |
| 錯誤(重大な勘違い) | 遺産の重要な部分について、重大な勘違いがあった(例:高額な不動産の存在を全員が知らずに協議した)。 |
| 判断能力の欠如 | 相続人の一部が、協議当時に認知症などで正常な判断能力を欠いていた。 |
これらの事実を客観的な証拠で立証する必要があります。



もし無効の判決が確定すれば、成立していた遺産分割協議は白紙に戻り、相続人全員で改めて遺産分割協議をゼロからやり直すことになります。
遺産相続で裁判を起こすべきか判断するポイント
遺産相続トラブルで裁判(訴訟)は多くの時間と費用がかかります。裁判を起こすべきかどうか検討する際は、慎重な判断が必要です。
本当に裁判を起こすべきか、以下のポイントで総合的に判断しましょう。
| 判断ポイント | 確認すべき内容・裁判を検討すべきケース |
|---|---|
| 証拠の有無 | 主張を裏付ける客観的な証拠が揃っているか(証拠が不十分だと望む結果が得られない可能性がある) |
| 経済的メリット | 弁護士費用などを考慮しても、経済的な利益が見込めるか |
| 時効の接近 | 遺留分侵害額請求権など、時効が迫っているか(時効が近い場合は訴訟も視野に入れる必要がある。) |
| 争点の内容 | 遺言の有効性など、調停・審判では扱えない争点か |
| 相手方の対応 | 相手が弁護士を立てており、話し合いでの解決が困難な状態か |
これらの点を総合的に考え、ご自身での判断が難しい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
遺産相続トラブルの裁判(訴訟)から判決までの流れ【7ステップ】
もし遺産相続トラブルで裁判を起こす場合、手続きは一般的に以下の流れで進みます。 これは調停や審判とは異なり、厳格なルールに基づいた法的な争いとなります。
弁護士への相談と証拠の収集・保全
訴訟は「証拠がすべて」であり、感情的な主張だけでは勝訴できません。まずは相続問題に精通した弁護士に相談し、法的な見通しを立てることが最優先です。
弁護士は、主張を裏付ける客観的な証拠を法的な観点から精査し、収集します。証拠がなければ裁判所に権利を認めてもらえません。
訴訟の種類ごとに必要な証拠の例は以下のとおりです。
| 訴訟の種類の例 | 収集する証拠の例 |
|---|---|
| 遺言無効確認訴訟 | ・被相続人の診断書、カルテ、介護記録 ・遺言書(原本または写し) ・被相続人の生前の筆跡(日記、手紙など) |
| 使い込み(不当利得返還) | ・被相続人の預金取引履歴(可能な限り長期間) ・医療費や施設費の領収書、家計簿など |
集めた証拠は、相手方による破棄や隠蔽を防ぐため「証拠保全」の手続きをとることもあります。訴訟の勝敗は、この証拠収集の段階で大勢が決まると言っても過言ではありません。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
「訴状」を作成し、管轄裁判所へ提訴(申立て)
法的な主張と証拠が固まったら、弁護士が「訴状」を作成します。
訴状とは「誰に、何を、なぜ請求するのか」を裁判所へ明確に示す公式書類です。 請求の趣旨と、それを裏付ける法的な理由(請求原因)を詳細に記載します。
作成した訴状(正本・副本)と証拠の写しは、管轄の裁判所へ提出し「提訴」します。 管轄裁判所は、原則として相手方(被告)の住所地などです。
また、提訴時には、以下の費用を納付する必要があります。
- 収入印紙:請求金額(訴額)に応じた手数料
- 郵便切手:裁判所からの書類送達(予納郵券)
この訴状が裁判所に受理された時点で、正式に訴訟(裁判)が開始されます。
相手方(被告)への訴状送達と、第1回期日の指定
裁判所が訴状を受理すると、相手方(被告)へ訴状の副本が「特別送達」で郵送されます。 これは、被告に対し正式に訴訟が提起されたことを法的に通知する手続きです。
訴状を受け取った被告は、記載内容に対する認否や反論を記した「答弁書」を作成します。
裁判所は提訴から約1ヶ月〜1ヶ月半後に第1回の裁判期日(口頭弁論期日)を指定し、被告に対してこの期日までに答弁書を提出するよう求めるのが一般的な流れです。
口頭弁論期日(主張・反論の応酬)
指定された日時に裁判所へ出廷し、口頭弁論期日が開かれます。 ただし、相続訴訟の実質的な審理は、法廷での口頭のやり取りではなく、書面を通じて行われるのが一般的です。
当事者双方は「準備書面」という書面を裁判所に提出します。 これは、お互いの主張や反論、証拠の申出などを詳細に記した反論書・主張書です。
期日は約1ヶ月に1回のペースです。当事者はそれまでに準備書面と証拠を提出し、次回の期日で相手方が反論する、という流れを繰り返します。
この書面の応酬を通じて、訴訟の争点(何が法的に問題なのか)を明確にしていきます。
証拠調べ・尋問(証人・当事者)
準備書面による主張と反論が出尽くし、裁判所が争点を整理した段階で「証拠調べ」の手続きに入ります。
まずは提出された書証(書類の証拠)の内容を精査し、それでも事実関係に争いが残る場合は「尋問」が行われます。尋問は、法廷で裁判官の目の前で行われる質疑応答です。
尋問には以下のような種類があります。
| 尋問の種類 | 対象者と目的 |
|---|---|
| 証人尋問 | 事実を知る第三者(例:介護担当者、遺言作成時の状況を知る人)に質問し、客観的な証言を得る。 |
| 当事者尋問 | 原告本人と被告本人が法廷に立ち、相手方代理人(弁護士)や裁判官からの質問に直接回答する。 |
裁判官は、この尋問での証言の信用性や態度なども含め、どちらの主張に正当性があるかを最終的に判断します。
和解勧告または判決の言渡し
尋問が終了し、裁判官が「どちらの主張がどの程度認められるか」という心証を固めた段階で、裁判は最終局面に移ります。
多くのケースでは、判決を下す前に、裁判官から「和解勧告」がなされます。 これは、裁判官が「判決になったらこうなる可能性が高い」という法的見通しを示した上で、双方に歩み寄りを促す手続きです。
双方が和解案に合意すれば「和解調書」が作成されます。 この和解調書は、確定した判決と同一の法的な効力を持ち、裁判はここで終了です。
もし一方が和解を拒否する、あるいは条件が折り合わなければ、和解は不成立になります。その場合、裁判官が法と証拠に基づいた最終的な判断として「判決」を言い渡します。
判決の確定または控訴(不服申立て)
言い渡された判決(第一審判決)に不服がある当事者は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に「控訴」することができます。
控訴とは、上級の裁判所(例:地方裁判所が第一審なら高等裁判所)に対し、第一審判決の取り消しや変更を求める不服申立ての手続きです。
もし双方がこの2週間の控訴期間内に何もしなければ、その判決は「確定」します。 確定した判決には強い法的拘束力(既判力)が発生するため、当事者はその内容に従わなければなりません。



同一の争点を再び裁判で争うことは原則としてできなくなります。
遺産相続の裁判にかかる期間はどのくらい?
遺産相続の裁判手続きに要する期間は、一概には言えません。争点の多さや事案の複雑性、選択する法的手続きによって大きく変動します。
調停・審判と訴訟では、解決までにかかる時間の目安が異なります。手続きごとの一般的な期間の目安は以下のとおりです。
| 手続きの種類 | 期間の目安 | 長期化する主な要因 |
|---|---|---|
| 遺産分割調停・審判 | 約1年〜2年 | ・相続人間の感情的対立が激しい ・財産の評価額に争いがある ・調停期日が1〜2ヶ月に1回程度しか開かれない |
| 裁判(訴訟) | 最低1年半〜3年 | ・争点が多岐にわたる(例:遺言無効と使い込みが同時発生) ・証人尋問や当事者尋問など、厳格な証拠調べが必要 ・鑑定手続きに時間がかかる |
特に訴訟(裁判)は、厳密な主張と立証を繰り返すため、時間がかかります。
第一審判決に不服があり、控訴(高等裁判所)や上告(最高裁判所)に進む場合も少なくありません。その場合、最終的な解決までに5年以上の歳月を要するケースも想定されます。
しかも、裁判が終わった後に、その裁判を前提とした遺産分割協議が行われることになりますから、遺産分割の前提問題を訴訟にした場合には遺産分割の最終解決まで5年以上の期間がかかることも決して珍しくありません。



相続トラブルの解決は、長期戦になる覚悟が必要です。
遺産相続の裁判にかかる費用はいくら?
遺産相続の裁判(訴訟)には、大きく分けて2種類の費用が発生します。
| 費用の種類 | 主な内訳 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 裁判所に納める実費 | ・申立手数料(収入印紙代) ・予納郵券(郵便切手代) | ・印紙代:訴額(請求額)に応じて変動(例:1,000万円請求で5万円) ・切手代:数千円〜1万円程度 |
| 弁護士費用 | ・着手金(依頼時に支払う) ・報酬金(成功時に支払う) ・その他(日当、実費など) | (旧)日弁連基準の例(経済的利益に基づく): ・着手金:5% + 9万円(300万円超3,000万円以下) ・報酬金:10% + 18万円(300万円超3,000万円以下) ※着手金無料で対応する事務所もあり(弁護士法人アクロピースは原則として着手金無料で対応しています。弁護士法人アクロピースの報酬体系はこちら。) |
これらの費用は、請求する金額や事案の複雑さによって変動するため、あらかじめ全体像を把握しておくことが重要です。
弁護士費用は法律事務所によって異なり、現在は自由化されています。



多くの場合、着手金や報酬金は、確保を目指す「経済的利益」(請求額や獲得額)を基準に計算されますので、依頼する際は必ず事前に見積もりを確認しましょう。
関連記事:遺産相続の費用は誰が払う?弁護士の遺産分割調停や裁判の成功報酬にする注意点も解説【弁護士監修】
遺産相続の裁判(訴訟)で失敗・後悔しないための注意点
遺産相続の訴訟は、多大な時間と費用、そして精神的負担を伴うものです。「裁判で負けた(敗訴した)」という後悔を避けるには、感情論を排し、法に基づいた戦略的な準備が不可欠です。
訴訟を有利に進めるため、特に以下の5つの点に細心の注意を払いましょう。
| 注意すべきポイント | 具体的な行動と理由 |
|---|---|
| 1. 客観的証拠の早期確保 | 訴訟は推測ではなく客観的証拠(カルテ、預金履歴等)で決まります。 早期の確保が最重要です。 |
| 2. 法的主張への徹し | 感情論は法的な争点になりません。 裁判官の心証を害するリスクを避け、法的主張に徹することが重要です。 |
| 3. 権利の時効・期限の厳守 | 権利には厳格な期限(例:遺留分侵害額請求は1年)があります。 時効が成立すると、証拠があっても請求自体が不可能になります。 |
| 4. 安易な和解・合意の回避 | 一度成立した和解(和解調書)を後から覆すのは極めて困難です。 利な内容や納得できない場合は、安易に合意してはいけません。 |
| 5. 相続分野に強い専門家の活用 | 相続訴訟は高度な専門知識を要します。 手続きが複雑化し取り返しがつかなくなる前に、相続分野の専門家に依頼すべきです。 |
これらの中でも「時効の管理」と「証拠の確保」は、訴訟の成否を分ける致命的な要素です。権利が時効で消滅すれば、裁判を起こすことすら叶わなくなります。
また、証拠がなければ、裁判所に正当な権利を認めてもらうことは困難です。



手続きが複雑化し、取り返しがつかなくなる前に、早期に弁護士へ相談することが賢明な判断と言えます。
関連記事:遺産相続の裁判で負けるケースとは?リスクや事前にすべき対策を弁護士が解説
遺産相続の裁判に関するよくある質問
遺産相続の裁判費用は誰が払うのですか?
遺産相続の裁判費用は、以下の2種類に大別され、負担原則が異なります。
| 費用の種類 | 負担の原則 |
|---|---|
| 1. 訴訟費用(印紙代・郵便切手代など) | 原則「敗訴者負担」です。判決で負けた側が支払います。 ただし、和解で終了した場合は「各自の負担」となるのが一般的です。 |
| 2. 弁護士費用(着手金・報酬金など) | 原則「各自の負担」です。裁判で勝訴したとしても、ご自身の弁護士費用を相手方に請求することは、特別な事情がない限り認められません。 |
「訴訟費用」は敗訴者が負担する可能性がありますが、「弁護士費用」は勝敗にかかわらず各自が負担するのが原則です。
遺産相続のトラブルで相手が弁護士を立ててきた場合、こちらも立てるべきですか?
相手方が弁護士を立てた場合、こちらも弁護士に依頼することを強く推奨します。
弁護士なしで交渉や裁判に臨むと、法的知識、証拠の収集能力、交渉力において圧倒的に不利な状況に置かれてしまうためです。
特に調停が不成立となり、審判や訴訟に移行した場合、法的な主張や書面作成を弁護士なしで対応するのは現実的ではありません。
ご自身の正当な権利を守り、対等な立場で手続きを進めるためにも、必ず弁護士に相談してください。
遺産相続調停や審判、裁判でやってはいけないことはなんですか?
調停・審判や裁判でご自身の立場を著しく不利にする行為は、絶対に避けるべきです。特に以下の行為は、敗訴や権利失効に直結するリスクがあります。
| 遺産相続調停や審判、裁判でやってはいけない行為 | 理由 |
|---|---|
| 虚偽の主張・証拠の偽造 | 発覚した場合、裁判官の心証を最悪にし、主張全体の信用性が失われます。 (※第三者証人が尋問で嘘をついた場合には、偽証罪などの刑事責任を問われる可能性もあります) |
| 感情的な相手への誹謗中傷 | 法的な利益は一切ありません。調停委員や裁判官に悪印象を与え、話し合いによる解決の余地をなくします。 |
| 裁判所からの呼出しや期限の無視 | 相手の主張がそのまま認められる(欠席判決など)リスクがあります。 権利(例:控訴権)を失うことにも繋がります。 |
| 財産隠し | 意図的な財産隠しが発覚した場合、相続権そのものを失う(相続欠格)可能性があります。 |
遺産分割の調停で嘘をつかれた場合の対処法は?
調停などで相手が事実と異なる主張(嘘)をしても、感情的に反論するだけでは効果がありません。 調停委員や裁判官は、どちらが正しいかを「証拠」で判断するためです。 「それは嘘だ」と叫んでも、水掛け論に終わってしまいます。
最も有効な対処法は、相手の主張を崩すための「客観的な証拠(反証)」を冷静に提示することです。
例えば「生前贈与は受けていない」という嘘に対しては、過去の銀行振込履歴や通帳のコピーを示します。 証拠に基づき、相手の主張の信用性を失わせることが重要です。
まとめ|遺産相続の裁判は早期の弁護士への相談と証拠準備が大切
原則として「遺産分割」自体は調停・審判で解決を目指しますが、遺言の有効性や財産の範囲が争点となる場合は、別途「裁判(訴訟)」を起こすケースもあります。
どの手続きに進むにせよ、ご自身の正当な権利を守るためには「客観的な証拠」が不可欠です。 特に「訴訟」は手続きが非常に専門的であり、多大な労力と時間を要するでしょう。
法的な準備が不十分なまま手続きに臨むと、望まない形で遺産が分けられたり、不利な条件を飲まされたりするリスクを負うことになります。
もしご親族との話し合いがこじれ、「裁判」という言葉が頭をよぎったら、一人で抱え込まず、手遅れになる前に弁護士へ相談してください。



早期に法的な見通しを立て、証拠を保全することが、紛争を有利に解決するための最大の鍵となります。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応