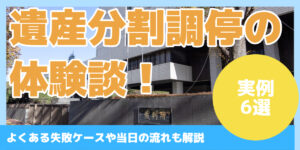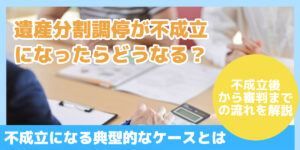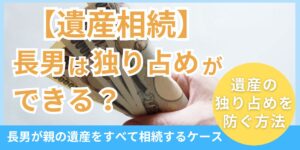【無料相談受付中】24時間365日対応
相続の遺産分割調停で嘘ばかりつかれたらどうする?不利にならない対処法を弁護士が解説
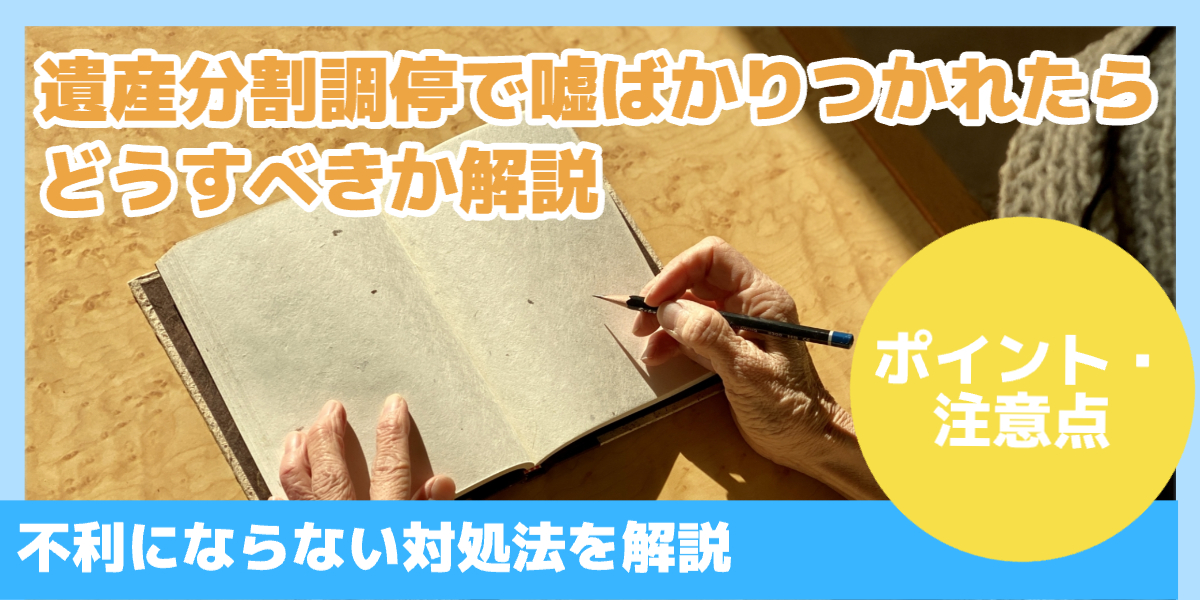
「遺産分割調停で嘘をつかれている。どうすればいい?」
「遺産分割調停での嘘で自分が不利になってしまったらどうしよう」
相続の遺産分割調停において、他の相続人の嘘に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
調停をスムーズに進めたくても、実際には嘘や不正な主張が持ち込まれることも少なくありません。嘘の発言に振り回されると、自分にとって不公平な結果に終わってしまう可能性があります。
本記事では、遺産分割調停でよくある嘘のパターンや、不正行為に直面したときの対処法、証拠の収集方法などを解説します。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
相続の遺産分割調停でよくある嘘のパターン5つ
遺産分割調停は、遺産分割協議が難航した場合に家庭裁判所で行われる手続きです。第三者である調停委員を交えて話し合うため、公平な解決が期待できます。
しかし、残念ながら嘘や誇張を交えた主張が持ち込まれる場合があります。
代表的な嘘のパターンは次のとおりです。
よくある嘘のパターンを押さえて、適切に対応できるよう準備しましょう。
財産隠し|遺産を隠したまま逃げ切られる
財産隠しとは、預貯金や不動産、株式などを申告せず、存在自体を隠してしまう行為です。
例えば、別の金融機関にある口座を黙っていたり、名義を変更して相続財産から外したりするパターンがあります。
相続の対象になる財産は、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産・債務(借金)です。調停では、通帳の取引履歴や不動産登記簿を調べることで、隠された財産が見つかる場合があります。
財産隠しは、特定の相続人しか把握できない事実のため、証拠が掴めないまま逃げられてしまうケースも少なくありません。
疑わしい点があれば、隠している財産がないか徹底的に調べる必要があります。
財産の使い込み|特定の相続人が私的目的で遺産を使用する
被相続人の介護や生活費を理由にしつつ、実際には自分の生活費や娯楽などに充ててしまうケースです。
被相続人名義の口座から必要以上に引き出し、私的利用していたものの「本人のために使用していた」と主張するといったケースが該当します。この場合、使途を裏付ける領収書や振込明細が重要になります。
使い込みが判明した場合、他の相続人は、遺産分割調停とは別の民事訴訟を提起し、民法第703条の不当利得返還請求権により返還を求めることが可能です。
(不当利得の返還義務)
第七百三条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。引用:民法|第703条
関連記事:死亡した人・亡くなった人の預金をおろすと罪になる?よくある相談例と解決策を解説 | 弁護士法人アクロピース
遺言書の偽造・変造|内容を書き換えて嘘の主張をする
本来の遺言書に手を加えたり、存在しない遺言書をでっちあげたりするケースです。遺産の取り分を増やすために行うことが多いとされています。
遺言書の偽造・変造は、刑法第159条に違反するとして、3カ月以上5年以下の拘禁刑が科されます。
また、遺言書の偽造・変造は民法第891条の「相続欠格事由」に該当し、相続人としての資格を失う重大な行為です。
筆跡や日付の不自然さが見抜きのヒントです。被相続人の生前の日記や、被相続人の方の当時の介護記録などで判断能力がしっかりしていたかを確認してみましょう。
関連記事:遺言書でできることは?できないことや書いたほうが良い場合も紹介
介護負担に関する嘘|介護の程度を誇張して取り分を増やそうとする
「長年介護してきたから相続分を増やしてほしい」と主張するケースは少なくありません。ただし、実際の介護時間や内容を大きく誇張して話す人もおり、争いの火種になりやすい部分です。
相続では、被相続人に特別な貢献をした相続人が「寄与分」を請求できる制度があります。寄与分が認められれば、ほかの相続人より多く財産を受け取ることが可能です。
こうした制度を活用しようと、介護を担った事実を過大に主張するケースがあります。
本当に介護をしていたかどうか確認するには、介護サービスの利用明細や診療記録、介護日誌といった資料をチェックすることが大切です。
寄与分については、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:相続で生前に貢献した人への増額は?相続人以外にも認められるのか寄与分の仕組みを解説
遺産分割協議が無断で進行|勝手に相続手続きが進んでいた
他の相続人から「すでにみんな合意している」と言われても、実際には一部の相続人しか関わっていないことがあります。
例えば、長男が中心となって協議を進め「弟も同意している」と伝えながら、実際には誰にも内容を共有していなかったというケースです。
被相続人が所有していた不動産を自分の単独名義に登記しようとしたり、他の相続人の同意を得ずに売却しようとしたりする場合があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫特定の相続人が勝手に協議を進めると、分割方法をめぐって大きな対立につながり、調停で嘘の事実が明らかになることがあります。
関連記事:遺産相続で何も言ってこない?連絡がこない理由と勝手に相続されていたときの対処法
関連記事:相続を知らなかった場合はどうする?取るべき対応や相続回復請求権、相続放棄の流れも解説
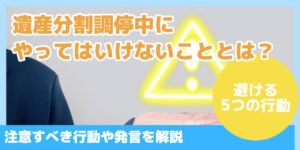
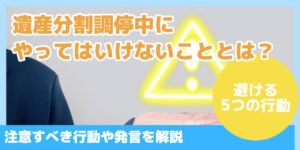
調停委員は嘘の証言をどう判断するのか
遺産分割調停において嘘の証言があった場合でも、調停委員は証拠のない主張をもとに結論を出すことはありません。
調停では、当事者それぞれの主張を聞いた上で、中立的な立場から解決策を探ります。
その主張がどれだけ真実味を帯びていても、それを裏付ける客観的な証拠がなければ、調停委員はあくまでも「一つの意見」として扱います。
例えば、「被相続人から生前に多額の援助を受けていた」という主張があっても、銀行の取引記録や領収書といった証拠がなければ、調停委員はその発言だけを根拠に判断することはありません。



嘘の証言に対しては、感情的にならず、冷静に「そのような事実はありません」と反論し、具体的な証拠を提示することが重要です。
【状況別】相続の遺産分割調停で嘘ばかりつかれたときの対処法
相続で嘘ばかりつかれた際は、感情的に反論するのではなく、まずは冷静になって初動対応を取ることが大切です。
調停委員は、客観的な証拠がない発言は鵜呑みにしません。相手が嘘を主張しても、それだけで不利になることは少ないため、冷静に証拠を整理し、調停委員に伝わる形で提示することが重要です。
ここでは嘘に直面したときの初動対応から具体的な反論の仕方、調停委員への証拠の提示方法まで、実際に役立つ流れを整理します。
相手の思うつぼにならないよう、冷静にステップを踏んでいきましょう。
遺産分割調停での嘘に気づいたとき|2つの初動対応
嘘をつかれたと感じたときに、すぐに感情的に反論するのは避けましょう。まずやるべきことは、以下の2つです。
嘘や不正行為の事実を確認し、証拠を整理しておくことで、その後の調停を有利に進められる可能性が高まります。
以下で具体的な初動対応を確認し、相手の嘘の主張に振り回されないようにしましょう。
1.遺言書の偽造・変造がないか確認する
前提として、遺言がある場合は遺産分割にならない可能性が高いです。
ただし、被相続人が遺言書を残しており、遺産分割割合を指定していた場合、調停で遺言書の内容を争うことがあります。この場合、筆跡や書式から遺言書の偽造・変造がないか確認しましょう。
遺言の内容が特定の相続人にあまりに有利に偏っている、筆跡が不自然で統一されていないといった点は不正の手がかりになります。
また、遺言書の作成当時に遺言者が認知症にかかっていたような場合、遺言能力を欠き遺言が無効となることもあります。遺言書の偽造や変造は刑法第159条で禁止されており、違反すれば拘禁刑に処される重大な行為です。
加えて、遺言書の出どころや財産の分割割合も併せて確認しておきましょう。
例えば、近親者ではなく疎遠になっている親族や遠縁の親戚が突然遺言書を見つけて提示してきた場合、不自然な部分がないか確認しましょう。
不審に思った場合は、公証役場で遺言検索を行い、原本を確認すると良いでしょう。
遺言書が手元にない方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法は?自筆・公正・秘密の3種類に分けて解説
関連記事:遺言と異なる遺産分割の判例!遺産分割協議の進め方も詳しく解説
2.嘘の事実と証拠を固める(財産調査・介護の記録確認など)
相手の主張に嘘が含まれていると感じたときは、感情的に反論するのではなく、事実を裏付ける証拠を集めることが重要です。
調停や審判などの法的手続では証拠が重視されるので、あらかじめ資料をそろえておけば、相手の嘘を明らかにできる可能性が高まります。
相手がついている嘘の内容と、それぞれの証拠集めのポイントは以下のとおりです。
| 調停でつかれた嘘の内容 | 証拠集めのポイント |
|---|---|
| 財産に関する嘘 | 金融機関に取引明細の開示を求めることで、隠された預金や不自然な引き出しを確認できる |
| 不動産に関する嘘 | 法務局で登記事項証明書を取得すれば、所有権移転に関する情報を確認できる |
| 介護負担の誇張 | ・介護サービスの利用明細や医療機関の診療記録、家族が書いていた介護日誌などが有力な証拠になる ・時系列で整理して提示すれば、実際にどの程度介護を担っていたのかを明確に示せる |
証拠をしっかり固め、遺産分割調停で相手方の主張が嘘であることを伝えましょう。
財産調査や相続人の調査については、以下の記事をご覧ください。
遺産分割調停で嘘の主張をされたとき|具体的な反論方法
相手方の嘘への反論は、証拠を示しながら冷静に伝えるのがポイントです。
以下のような表現を意識すると、調停委員に理解してもらいやすくなります。
| 嘘のパターン | 反論の伝え方(例) |
|---|---|
| 財産隠しが疑われる場合 | 被相続人名義の口座が一部申告されていないように思います。こちらの金融機関に照会したところ、預金が残っている記録がありましたので確認をお願いします。 |
| 財産の使い込みを指摘する場合 | 生活費に充てたと説明されていますが、通帳の記録を見ると通常の生活費の範囲では説明できない大きな引き出しが続いています。これらのお金の用途について説明を求めたいです。 |
| 遺言書の偽造・変造が疑われる場合 | この遺言書ですが、筆跡が不自然で違和感があります。遺言者本人が書いたものではない可能性があるので吟味をしてもらいたいです。 |
| 介護負担の誇張を主張する場合 | 介護を一手に担ったとの主張ですが、介護サービスの利用明細によると、週に複数回は事業者が入っていました。実際の介護状況について、記録に基づいて判断していただきたいです。 |
| 遺産分割協議の無断進行を主張する場合 | 長男からすでに合意済みと伝えられましたが、私は内容を聞かされていませんので合意していません。 |
あくまで一例ですが、嘘に対して反論する際はこのように冷静に事実を伝えることが大切です。
また、遺産分割調停で嘘をつかれたときは感情的になってしまう方も多いかもしれません。しかし強い口調で反論しても調停委員に事実は伝わりにくく、かえって不利になる恐れがあります。
冷静さを保つためには、事前に主張したい内容をメモにまとめておくのがおすすめです。要点を整理しておけば、落ち着いて話しやすくなります。
一呼吸おいてから発言する、事実と感情を切り分けて話すなど、落ち着きを保ちつつ「調停委員に事実を正しく理解してもらうこと」を意識しましょう。
遺産分割調停の嘘が手に負えないとき|早めに弁護士に相談する
遺産分割調停での嘘に対し、一人で対応するのが困難だと感じたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。
専門家の視点から証拠の集め方や主張の整理方法をアドバイスしてもらえるため、後手に回らず落ち着いて対応できるようになります。
さらに、裁判へ移行した場合でも、早い段階から弁護士に相談していればスムーズに対応可能です。
相続は一度こじれてしまうと解決までに時間や労力がかかることが多く、精神的な負担も大きくなります。また、証拠集めや財産調査といった労力のかかる手続きも、法的観点から効率的に進めてもらえるため安心です。



「どのような資料を集めればよいか」「どこまで主張できるのか」といった疑問が解消され、不安を抱え込まずに進められる点も相談するメリットの一つです。
相続問題を弁護士に相談するメリットは、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:相続争いに疲れたときの対処法と弁護士に相談する5つのメリットを解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
嘘を放置するとどんなリスクがあるのか
遺産分割調停で相手の嘘を放置してしまうと、不利な状況に追い込まれるリスクがあります。
たとえ嘘の証言であっても、訂正されないまま進むことで、相手方の言い分を認めたものとしてネガティブな印象を調停委員に与えかねません。印象が悪くなると、本来主張すべき正当な内容まで信じてもらえなくなる可能性もあります。
相手の嘘を放置することは、受け取れるはずの遺産相続分を減らしてしまう結果にもつながるリスクがあります。
調停で相手が嘘をついている場合は、放置せずに早めに行動を起こすことが大切です。



具体的な証拠を集めたり、弁護士に相談したりすることで、主張の正当性を裏付け、不利な状況を回避できるでしょう。
相続の遺産分割調停での嘘に対抗する証拠収集・提示のポイント
遺産分割調停で相手が事実と異なる主張をしても、必要な証拠を集めることで公平な遺産分割を進められる可能性が広がります。
相手方の嘘を主張し、調停委員に認めてもらうためにも、事前にポイントを確認しておきましょう。
金融機関からの情報収集方法
預金の出金記録や残高は、調停で相手の嘘を立証するにあたって重要な証拠になります。
通帳や口座残高の確認だけでなく、金融機関に依頼して正式な証明(取引明細書・残高証明書など)を取得しましょう。
例えば、取引明細書を取得すれば入出金の履歴が確認でき、残高証明書を使えば特定の日付時点の資産を示せます。
さらに、弁護士や裁判所を通して口座照会を行えば、相手が隠そうとしている口座情報を得られる可能性があります。
特に亡くなる直前に大きな出金がある場合、その明細は不自然な財産移動を示す根拠になりやすいです。金融機関の窓口で依頼できるケースが多いため、早めに動いて必要な資料をそろえておくと良いでしょう。
公的機関からの証明書取得方法
役所や法務局で発行される証明書は客観性が高いため遺産分割調停で有力な証拠になる可能性があります。
有力な証拠となりうる証明書の種類と、証明できる内容は以下のとおりです。
| 証明書の種類 | 証明できる内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 誰が相続人かを正確に示せる |
| 住民票の除票 | 被相続人の住所を証明する資料になる |
| 不動産登記事項証明書 | 不動産の所有者や権利関係を明らかにできる |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の価額の参考にできるため、遺産の評価をめぐる争いを整理しやすくなる |
これらは法務局や市区町村役場で入手でき、郵送やオンラインでも申請できます。
調停で相手の主張に反論するための有効な証拠になるため、早めに取得しましょう。
日常記録の重要性と記録方法
遺産分割調停では、日常の記録を証拠として提示することが大切です。介護や生活費の負担などは、金融機関や公的書類だけでは立証が難しいためです。
例えば、介護を行った日や内容を日記に記しておけば「継続的に支えてきたこと」を裏づけられます。「介護は全て私がやった」と主張する相手に対し、病院への付き添いをスマホにメモしたり、支払いの領収書やレシートを提示するのも良いでしょう。
また、被相続人とのやり取りを示すメールやLINEのスクリーンショットを日付つきで保存しておくと、その当時の状況を裏づける有力な資料になります。
写真や動画も実際の様子を示す客観的な証拠として役立つため、相手の嘘を裏付けられるデータがないか確認してみましょう。
調停委員に納得してもらえる証拠の提示方法
遺産分割調停を円滑に進めるためには、調停委員に信頼性のある資料を提示することが大切です。口頭の主張だけでは説得力に欠けるため、できる限り客観的な証拠をそろえましょう。
また、証拠となる資料はただ提出するだけでなく、時系列や項目ごとに整理してファイル化すると伝わりやすくなります。
「どの時期に、どのような支出や出来事があったのか」が一目でわかるようにしておくのがおすすめです。
証拠がしっかりと整理されていれば、調停委員も冷静に判断しやすくなり、スムーズな合意形成につながります。
嘘の証拠がない場合にどうすべきか
銀行の取引記録や正式な書類など、公的な書類や客観的な資料がなくても、諦めずに代替となる証拠をできるだけ多く集めましょう。
例えば、相続人や被相続人の知人など、当時の状況を知る人物の証言は有力な証拠になり得ます。また、以下のような証拠も、その時の状況を裏付ける重要な資料です。
- 自分でつけていた日記やメモ
- 被相続人や相手との間で交わされたメール・LINEのやりとり
これらの記録を時系列に整理し、相手の嘘がいかに不自然であるかを丁寧に説明することで、調停委員を納得させられる可能性が高まります。
客観的な証拠が用意できなくても、代替となるものを用意することで、調停を有利に進められる可能性があります。



些細なものでもいいので、過去を振り返り、事実を証明できるものを探してみましょう。
相続の遺産分割調停で噓ばかりつかれて不成立になったらどうなる?その後の流れ
遺産分割調停が嘘の主張によって不成立になっても、解決の道が閉ざされるわけではありません。
次の段階である「審判」に移行し、裁判所が証拠や証言をもとに判断を下します。(参照:裁判所|遺産分割調停)
調停はあくまで「相続人同士の話し合い」であり、相続人全員の合意がなければ成立しません。しかし、不成立になった時点で手続きが終わるのではなく、裁判所が法的ルールに基づき解決を図る仕組みが整えられています。
例えば、相手が「財産は存在しない」と嘘をついても、嘘や不正行為を裏付ける証拠を提示すれば、裁判所は客観的な証拠をもとに当該財産の存否を判断します。
調停で出した証拠や主張もそのまま審判に引き継がれるため、ゼロからやり直すわけではありません。



大切なのは、相手の嘘に振り回されないように証拠をしっかり準備しておくことです。信頼できる弁護士に相談し、どうすべきか検討しながら有力な証拠を集めていきましょう。
遺産分割調停が不成立になった場合の対応は、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:遺産分割調停が不成立になった場合について解説
関連記事:遺産相続の裁判とは?手続きの流れや必要な費用、期間を弁護士が解説
相続の遺産分割調停で嘘ばかりつかれたら弁護士依頼も検討|依頼時のポイント
遺産分割調停では、相手との主張が対立してなかなか話し合いが進まないケースも多くあります。そうした状況で一人で対応するのは負担が大きく、準備不足のまま臨むと不利な結果に終わることもあるでしょう。
遺産分割調停を有利に進めるには、早めに弁護士に相談して手続きを円滑に進めることが大切です。
以下では、弁護士に依頼するタイミングや選び方、弁護士費用の相場を解説します。内容を参考にしながら、自分に合った弁護士への依頼を検討してみましょう。
弁護士依頼の適切なタイミングとは?
遺産分割調停で弁護士に依頼するタイミングは、調停が始まる前のできるだけ早い段階がおすすめです。準備を整えてから調停に臨めば、相手の主張に振り回されず落ち着いて対応しやすくなります。



特に次のようなケースでは、不利な立場に追い込まれる前に早めに依頼を検討しましょう。
- 相続人同士の話し合いで合意が難しいと感じたとき
- 相手が事実と異なる主張をしていると疑われるとき
- 嘘や不正行為を裏付ける証拠の収集が難航しそうなとき
- 財産の範囲や評価額をめぐって争いが起きそうなとき
- 相続人の人数が多く、手続きに時間がかかりそうなとき
- 相手とのやり取りによる精神的な負担が限界に達したとき
これらの状況に直面したら、一人で抱え込むよりも弁護士の力を借りる方が効率的です。弁護士は証拠の集め方や主張の整理を助けてくれるため、調停を有利に進めやすくなります。
相続問題が難航すると、肉体的・精神的に疲弊してしまいます。法律に基づいて客観的に話し合いを進め、自分の不利益を主張するためにも、まずは一度弁護士に相談してみましょう。
関連記事:遺産相続を弁護士に相談・依頼する流れは?手続き完了までの流れ・費用も詳しく解説
相続問題に強い弁護士の選び方
遺産分割調停での嘘に対抗するなら、相続問題に強い弁護士を選ぶことが大切です。
相続の争いは一度こじれると長期化しやすく、専門的な知識と経験がなければ不利な立場に追い込まれる恐れがあります。
経験豊富な弁護士は、過去の事例をもとに調停委員への効果的な説明方法や、証拠をどのように提示すればよいかを熟知しています。そのため、調停を有利に進めるためには専門性の高い弁護士を選ぶのがおすすめです。
具体的には、弁護士事務所のホームページなどで相続案件の相談・解決実績を確認してみましょう。相続問題の相談・解決実績が多い事務所は、調停でどのような主張を組み立てればよいか、証拠をどう提示すれば良いかアドバイスをしてくれます。
また、相談のしやすさや弁護士との相性も重要です。初回相談の際に、説明がわかりやすいか、こちらの話をきちんと聞いてくれるかを確認しましょう。
弁護士の選び方をさらに知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:相続に強い弁護士とは?費用や失敗しない選び方を解説【弁護士監修】
関連記事:相続トラブルで後悔しない弁護士の選び方とは?口コミなど確認すべきポイントを解説
弁護士費用の相場
遺産分割調停を弁護士に依頼する場合、費用がかかります。
事前におおよその相場を知っておくと、依頼後に「こんなにかかると思わなかった」という不安を避けやすくなるでしょう。
相続案件の弁護士費用の費用項目と相場は、以下の通りです。
| 費用項目 | 概要 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 相続問題の相談にかかる費用 | 無料~30分5,000円程度 |
| 着手金 | 案件に着手するときに支払う費用 | 20万〜50万円程度 |
| 成功報酬金 | 調停が成立したときに得られる成果に応じて支払う費用 | 得られた財産の10〜15%程度 (※弁護士の介入によって得られた経済的利益に応じて変動) |
| 遺産調査費用 | 遺産調査にかかる費用 | 15万〜30万円程度 |
| 日当 | 弁護士が出張・出廷した場合の報酬 | 移動距離や拘束時間によって金額が変動 |
| 実費 | 郵送代、コピー代、交通費などの実費負担 | 5万円~7万円程度 |
費用は決して安くありませんが、弁護士に依頼することで得られる金額や安心感を考えれば十分に費用対効果が見込めます。
ただし、上記はあくまで目安です。正確な金額は、初回相談時に担当の弁護士にご確認ください。
関連記事:遺産分割調停の費用について解説
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停での嘘に関するよくある質問
相続の遺産分割調停で揉める家族の特徴は?
相続で揉める家族には、いくつかの共通点があります。
- 財産の内容や価値が十分に共有されていない
- 相続人同士の信頼関係が弱く、感情的なしこりが残っている
- 特定の相続人だけが金銭を管理していた
- 生前贈与や特別な貢献(介護・事業支援など)の評価をめぐって対立している
- 相続人の人数が多く、意見がまとまりにくい
例えば、兄弟の一人だけが親の預金通帳を管理している場合、他の相続人は残高を把握できません。
そのまま調停に臨むと「隠し財産があるのでは」と疑念が生まれ、話し合いがこじれることがあります。
調停を円滑に進めるには、弁護士と連携しながら証拠集めをする必要があります。まずは専門家に相談し、どのように対処すべきか判断を仰ぎましょう。
遺産相続で揉める人の特徴や回避策は、以下の記事をご覧ください。
遺産分割調停で聞かれることは何ですか?
遺産分割調停では、遺産の範囲や遺産の分割方法、生前贈与や寄与分の有無などの基本的な確認が行われます。
遺産の内容(預金・不動産・有価証券など)、相続人の人数や関係、これまでの話し合いの経緯などを調停委員がヒアリングするイメージです。
また「遺産をどのように分けたいと思っているか」「遺産分割にあたって考慮した方が良い点はあるか」といった意向を確認される場合もあります。
冷静に落ち着いて話せるよう、事前に回答をまとめておきましょう。
遺産分割調停の流れや有利な進め方は、以下の記事で解説しています。
遺産を独り占めした人の末路とは何ですか?
遺産を独り占めしようとした場合でも、実際にはうまくいかないことが多いです。
例えば遺言書を偽造した場合には、文書偽造罪に問われた上で相続欠格となるのは先述の通りです。
親に遺言書を作成させた場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺留分侵害額請求が可能なため、相続人の一人が独り占めすることはできません。
遺産分割協議をしないで遺産分割協議書を偽造した場合も、有印私文書偽造や行使、詐欺罪などに問われることになります。
(私文書偽造等)
第百五十九条
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法 第159条
協議で他の相続人を脅すようなことがあっても、遺産分割協議を取り消すことができる上に、恐喝罪などに問われることもあります。
特定の相続人が財産を独り占めした場合の対処法は、以下の記事を参考にしてみてください。
相続の遺産分割調停で使途不明金を追求し解決した事例
実際に被相続人の通帳から不自然な出金が見つかり、調査と調停で解決したケースがあります。
“被相続人Aさんが亡くなったが、生前に相続人である兄のCさんが管理していたAさんの預金口座から多額の金銭が引き出されていた。依頼人Bさんは出金された金銭を使途不明金として追及したいとのご相談。”
この事例の課題としては、
・Aさんの財産を管理していたCさんの使途不明金が正当なものか否かを見極めること
があげられます。
そこで
- 依頼人Bさんの日記や兄のCさんへのメールなどを基に、出金額がAさんの介護の実態と比較して過剰であることを主張
- 過去のやりとりの時系列と金額の整合性を丁寧に組み立て、主張を論理的に展開
というご対応をさせていただき、家庭裁判所の調停委員にも理解を得ることができました。
使途不明金のうち半分以上が認定され、依頼人Bさんにとって納得のいく水準で和解が成立いたしました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


まとめ|相続の遺産分割調停で噓ばかりつかれたときは弁護士への依頼も検討しよう
遺産分割調停では、相手が事実と異なる主張を繰り返すこともあります。嘘をついている相続人に対して感情的に対立するのではなく、客観的な証拠を集めて冷静に対応することが大切です。
金融機関からの取引明細や不動産の登記事項証明、介護記録など、証拠となる資料は多く存在します。事前に準備を進めておけば、相手の嘘に振り回されず、公平な解決へと近づけます。
自分だけで対応するのが難しいときは、相続問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、調停が不成立になっても審判へスムーズに移行できるように助けてくれます。



遺産分割調停を有利に進め、公平に遺産分割するためにも早めに弁護士に相談しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。