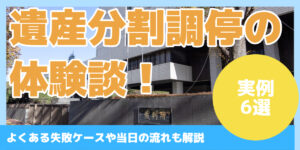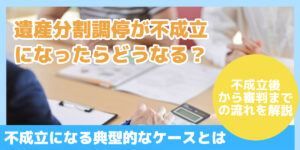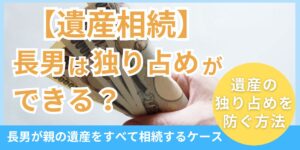【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説

「遺産分割調停でやってはいけないことはある?」
「調停委員に悪い印象を与えたくない。」
遺産分割調停に臨む際、このような疑問や不安を抱えることもあるかもしれません。
遺産分割調停には、知らずに行うと調停不成立や、審判で不利になる「やってはいけない行動」が存在します。
調停を有利に進めるためにも、あらかじめ注意すべき行動や発言を知っておくことが大切です。
この記事では、遺産分割調停中に避けるべき5つの行動と、調停を有利に進めるためのポイントについて、具体例を交えながら詳しく解説します。
遺産分割調停では「無断欠席・感情的発言・嘘」は致命的:無断欠席や感情的な攻撃、事実と異なる主張は、調停委員の心証を大きく悪化させ、調停不成立の原因になる。
調停委員の印象は結果に直結する:不誠実な態度や非協力的な姿勢は記録に残り、調停不成立後の審判で不利に扱われる可能性がある。
調停不成立になると「審判」に移行し、希望が通りにくくなる:審判では裁判官が法定相続分をベースに判断するため、柔軟な解決が難しくなる。
調停を有利に進める鍵は「事前準備と冷静な対応」:財産資料・主張整理・証拠準備を行い、事実ベースで簡潔に伝えることが重要。
対立が激しい・相手に弁護士がいる場合は早期に弁護士相談が有効:精神的負担や不利な合意を避けるため、弁護士法人アクロピースなど相続に強い弁護士への相談が合理的。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫遺産分割調停を予定している、あるいは現在調停中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停中にやってはいけないこと|不利になる行動と注意点
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が中立的な立場で相続人間の話し合いを仲介する手続きです。
調停委員は双方の主張を聞き、法的な観点から妥当な解決案を提示する立場です。ただし当事者の態度や言動によっては印象が大きく左右されることがあります。
ここでは調停中に絶対に避けるべき5つの行動を取り上げ、NG理由とその影響を解説します。本章を参考に、調停をスムーズに進めるための心構えを持ちましょう。
調停期日を無断で欠席する
調停期日の無断欠席は、遺産分割調停において最も避けるべき行動の一つです。
家事事件手続法第51条、第258条により、調停期日への出頭は義務付けられており、正当な理由なく欠席した場合は、5万円以下の過料に処される可能性があります。
(事件の関係人の呼出し)
第五十一条 家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。
2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
3 前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。
引用:家事事件手続法|第51条
(家事審判の手続の規定の準用等)
第二百五十八条 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
実際に過料に処されることはほとんど稀と言っていいですが、無断欠席は過料リスクだけでなく、「真剣に話し合う意思がない」「相続問題を軽視している」という悪印象を調停委員や相手方に与えかねません。
やむを得ず欠席する場合は、必ず事前に裁判所に連絡し、期日変更の申立てを行うことが大切です。



病気や仕事の都合など、正当な理由があると裁判所側に判断されれば、柔軟に対応してくれます。
関連記事:相続の調停を申し立てられたらどうする?対応方法や注意点を解説
感情的になって相手を攻撃する
遺産分割では長年の感情的なしこりが表面化することがあります。たとえば「あなたは親の面倒を見なかった」といった、過去の恨みを持ち出してしまうケースです。
調停の場では「遺産をどう分けるか」という現在の問題に焦点を当て、冷静に自分の主張を伝えることが重要です。
調停で不利にならないためにも、感情的な攻撃は避けましょう。相手の人格を否定するような発言は避け、事実に基づいた話し合いを心がけてください。
相続争いの対処法は、以下の記事でも解説しています。気になる方はあわせてご覧ください。
関連記事:相続争いに疲れたときの対処法と弁護士に相談する5つのメリットを解説
調停委員に嘘をつく・事実を隠す
調停において虚偽の主張をすることは、最も信頼を失う行為の一つです。
実際には存在する預金口座を「ない」と主張したり、被相続人から生前に受けた贈与を隠したりすることは避けましょう。存在する財産を「ない」と否定しても、金融機関照会や証拠提出で明らかになります。
一度でも嘘が発覚すると、その後の主張全体の信頼性が損なわれるリスクが高いです。



分からないことは「分からない」と正直に答え、不利な内容でも正直に伝えることが、調停委員からの理解と信頼を得る近道です。
他の相続人の意見を全く聞かない
「自分の主張だけが正しい」という頑なな態度は、調停の本質に反するため、避けるべきです。
遺産分割調停は、話し合いによる解決が目的です。相手の意見を一切聞かず自分の要求だけを繰り返す態度は、調停委員に「協議困難」と判断されやすくなるでしょう。
調停の多くは、双方が一定の譲歩をすることで合意に至ります。相手の主張にも一定の理解を示し、「この点については理解できるが、こちらの事情も考慮してほしい」といった建設的な対話を心がけることが大切です。



調停委員は、両当事者の主張を聞いた上で、法的に妥当で、かつ双方が納得できる解決案を探っています。柔軟な姿勢を示すことで、調停委員からも「話し合いに前向きな人」という良い印象を持たれるでしょう。
遺産分割協議に応じない相続人がいるときの対処法は、以下の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:相続人の一人が遺産分割協議に応じない7つの理由と対処法!放置リスクも解説
調停委員に不誠実な態度を取る
調停委員への態度は、調停の成否を左右する重要な要素です。
調停委員は中立的な第三者として、公平な解決を導く役割を担っています。「裁判所は相手の味方」といった発言や横柄な態度は避けましょう。
また、求められた資料の提出を拒否したり、期限を守らなかったりすることも、不誠実な態度と受け取られます。
質問には丁寧に答え、求められた資料は速やかに提出しましょう。誠実な対応こそが調停を円滑に進める鍵です。
遺産分割調停中にやってはいけない行動を取るとどうなる?
遺産分割調停中にやってはいけない行動をしてしまった場合でも、一度のミスですべてが台無しになるわけではありません。
しかし、繰り返しNG行動を取ると、深刻な結果を招く可能性があります。ここでは、具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。
調停不成立のリスクが高まる
調停委員は当事者間の合意形成を促す立場です。一方または双方が非協力的な態度を続けると、「合意は困難」と判断され、調停不成立となる可能性もあるでしょう。
遺産分割調停が不成立になると、自動的に遺産分割審判へ移行します。審判は裁判官が法律に基づき強制的に決定するため、当事者の意向が反映されにくく、法定相続分に従った機械的な分割になることも少なくありません。
また、審判終了までには6か月から1年程度かかる場合があり、その間は遺産を処分したり利用することが難しいです。
できるだけ当事者の意見を反映しスムーズに遺産分割を行うためにも、調停不成立にならないよう行動することが大切です。
遺産分割調停が不成立になった場合については、以下の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:遺産分割調停が不成立になったその後はどうなる?審判移行や強制執行についても解説【弁護士監修】
審判移行時に不利になる可能性がある
調停が不成立となり審判に移行した場合、調停での態度や言動は審判官に引き継がれます。
調停調書には各当事者の主張や態度が記録されているため、嘘や非協力的態度があった場合、審判官の印象に影響するでしょう。
例えば、調停で財産を隠していたことが発覚すると、「信頼できない人物」と見なされ、本来認められるはずの主張が却下される可能性もゼロではありません。
審判は証拠と法律に基づき一方的に判断が下されるため、悪い印象を覆すことは困難です。
不利にならないためにも、遺産分割調停は誠実で協力的な態度で望みましょう。
調停委員の心証が悪くなり、判断に影響する可能性がある
遺産分割調停でNGとされる行動の結果、調停委員の印象が悪くなるリスクがあります。
調停委員との信頼関係は、調停の成否を大きく左右します。以下は、調停委員の印象が悪化する可能性がある例です。
- 書類提出の遅延:提出を求められた預金通帳のコピーを複数回の期日で「忘れた」と繰り返し、意図的な隠蔽と判断された。
- 相手への人格攻撃:遺産分割と関係のない過去の行動を批判し続け、調停委員から「建設的な話し合いは困難」と判断された。
- 反抗的な態度:提案に対し「受け入れられない」「裁判所は何も分かっていない」と批判を繰り返し、調停委員が調整を断念した。 など
調停委員からの信頼を得て、解決に向けたサポートも受けるためにも、協力的で誠実な対応を心がけましょう。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産分割調停を有利に進めるためのポイント
調停を成功させるためには、事前の準備と当日の対応、そして相手方への対処法を理解しておくことが重要です。
特に弁護士に依頼していない方は、これらのポイントをしっかりと押さえる必要があります。本章を参考に、遺産分割調停を有利に進める準備をしておきましょう。
調停前に行うべき準備
遺産分割調停を有利に進めるためには、十分な事前準備が欠かせません。調停前の段階でどれだけ情報と資料を整えておけるかが、当日の交渉力や説得力を大きく左右します。
具体的には、以下の準備をしておきましょう。
| 遺産分割調停前にすべき準備 | 内容 |
|---|---|
| 必要書類の整理 | 例:預金通帳、不動産登記簿謄本、株式の評価証明書、生命保険証書など。 特別受益・寄与分を主張する場合は、その証拠も用意する。 |
| 主張内容の整理 | 自分が何を主張したいのか、その根拠は何かを明確にする。 民法の条文や具体的な金額を根拠としてまとめる。 |
| タイムラインの作成 | 被相続人の生前から相続発生後までの経緯を時系列で整理する。 特別受益や寄与分に関わる事実は、日時・方法まで明確に記録しておく。 |
準備不足は、不利な状況を招く原因にもなります。調停委員に事実関係を的確に理解してもらい、自分の立場をより強く伝えるための土台を作っておきましょう。
関連記事:相続の遺産分割調停とは?流れや有利な進め方を弁護士が紹介
調停当日の発言で気をつけること
調停当日は、限られた時間の中で自分の主張を整理し、効率的かつ明確に伝えることが大切です。説得力のある発言をするために、以下のポイントを押さえましょう。
- 結論を先に述べる:「私の主張は○○です。理由は3つあります」と冒頭で要点を提示。
- 具体的な数値を示す:「たくさん援助した」ではなく「月5万円を3年間、合計180万円援助した」と明示。
- 感情と事実を分ける:感情的表現を控え、「このような事実がありました」と事実ベースで説明。
- 認めるべき点は認める:相手の主張で正しい部分は認めることで、調停委員からの信頼を得やすくなる。



これらを意識することで、調停委員の理解と信頼を得やすくなり、より円滑な合意形成につながります。
相手方が嘘をついている場合の対処法
遺産分割調停で相手から事実に反する主張をされた場合、冷静かつ論理的に対応しましょう。
具体的には、以下のような対処法が有効です。
- 客観的資料を提示:通帳記録や契約書など、事実を裏付ける資料を示して説明する。
- 調停委員への確認依頼:必要に応じて、相手方に証拠の提出を求めてもらうよう調停委員に依頼する。
- 記録の保持:相手の発言内容を記録し、矛盾があれば次回の調停で指摘する。
感情的に反論するのではなく、冷静に事実を積み重ねて対応することが大切です。調停委員からの信頼を損なうことなく、自分の主張をより確かなものとして伝えましょう。
相続人の一人が遺産分割に応じないなどのトラブルは、以下の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:相続人の一人が遺産分割協議に応じない7つの理由と対処法!放置リスクも解説
関連記事:相続の遺産分割調停で嘘ばかりつかれたらどうする?不利にならない対処法を弁護士が解説
遺産分割調停で不利にならないためには?弁護士に依頼すべき4つの状況
調停を有利に進め、時間や精神的な負担を減らしたいと考えるのであれば、弁護士のサポートを検討すべきです。また、状況によっては弁護士への依頼が必須な場合もあります。
遺産分割調停を弁護士に依頼すべき具体的なケースは以下のとおりです。
上記のケースに当てはまる場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
遺産分割調停が弁護士なしでも可能かどうかについては、以下の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:遺産分割調停は弁護士なしで可能かどうかについて解説
相手方が弁護士を立てている
遺産分割調停で、相手方が弁護士を立てている場合、こちらも早急に弁護士に依頼すべきです。法律知識や交渉経験に圧倒的な差が生まれてしまうため、相手のペースで話が進みやすくなります。
不利な条件で合意させられてしまうリスクが非常に高くなるため、こちらも早めに弁護士へ相談しましょう。
相手と対等な立場で交渉し、ご自身の正当な権利を守るためにも、弁護士への依頼は不可欠です。
関連記事:相続で代理人(相手方)が弁護士を立ててきた場合の注意事項とトラブル対応のコツ
相続人間の対立が激しく、冷静な話し合いが困難
「顔も見たくない」「何を言っても聞く耳を持たない」など、相続人同士の感情的な対立が激しい場合は、弁護士に依頼すべきといえます。
当事者同士では感情的な言い争いに終始してしまい、本来の目的である遺産分割の話がまったく進まないこともあるでしょう。
弁護士が代理人となることで、ご自身は相手と直接話す必要がなくなり、精神的な負担が大幅に軽減できるのがメリットです。
また、弁護士が法的な観点から冷静に交渉を進めることで、感情論を排した建設的な話し合いが期待できます。
関連記事:遺産相続でもめた場合の対処法と遺産分割協議のスムーズな進め方
遺産が高額または複雑で、法的な争点がある
遺産の内容や金額が以下のケースに当てはまる場合は、専門知識を持つ弁護士のサポートが有効です。
- 相続税の基礎控除額を超える高額な財産がある
- 不動産や非公開株式など、評価や分割が難しい財産が含まれる
- 「特別受益」や「寄与分」の主張をしたい、または相手から主張されている
特に、相続税の基礎控除額を超える財産がある場合、期限(相続開始から10か月以内)までに相続税の申告・納税が必要です。遺産分割が難航すると手続きが間に合わず、延滞税や加算税といった余計な費用が発生するリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、複雑な計算や法的な主張を正確に行い、ご依頼者様の利益を最大化するためのサポートが受けられるでしょう。
手続きの手間や精神的な負担を減らしたい
遺産分割調停は、解決するまで1年以上かかることも珍しくありません。
平日の昼間に裁判所へ出廷したり、主張をまとめた書面や証拠を準備したりと、多くの時間と手間がかかります。
弁護士に依頼すれば、以下のような煩雑な手続きの多くを任せることができます。
- 申立書や主張書面など、複雑な裁判所提出書類の作成
- 法的に有効な証拠の収集と整理
- 調停期日への代理出廷
- 相手方との交渉や調停委員への説明
仕事や日常生活への影響を最小限に抑え、調停のストレスから解放されたいと考えるなら、弁護士への依頼することも検討しましょう。
遺産分割調停に関するよくある質問
遺産分割調停は平均して何年くらいかかりますか?
遺産分割調停の平均期間は1年程度です。(出典:裁判所|5 家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等)
これはあくまで平均値であり、事案によって大きく異なります。遺産分割調停は、財産の調べや評価が必要になることが多く、この平均より長くかかる場合も少なくありません。
相続人が2~3人で争点が少ない場合は、3~6ヶ月程度で解決することもあります。一方、相続人が多数いたり、不動産の評価で対立したりする場合は、1年を超えて長期化することもあるでしょう。
遺産分割調停に家族が同席してもいいですか?
調停は非公開で行われ、プライバシーに配慮した手続きとなっているため、調停室に入れるのは原則「当事者本人と代理人弁護士のみ」です。
待合室で待機してもらうことは可能なため、精神的なサポートとして同行してもらうことはできます。(参照:裁判所|裁判所データブック2025 2 調停事件(民事調停事件・家事調停事件の平均審理期間))
また、当事者が高齢で判断能力に不安がある場合や、身体的な介助が必要な場合は、裁判所の許可を得て付添人として同席が認められることがあります。
やむを得ない事情で家族の同席・同行を考えている場合は、事前に裁判所に相談することをおすすめします。
相続人以外が遺産分割に関与できるケースについては、以下の記事でも解説しています。気になる方はあわせてチェックしてみてください。
遺産分割調停で弁護士に頼むといくらかかりますか?
遺産分割調停の弁護士費用は、遺産の総額や事案の複雑さによって変わります。
料金体系も法律事務所によって異なり、着手金を低く設定して成功報酬を高めにしている場合や、タイムチャージ制(時間単価)を採用しているケースもあります。
複数の事務所で見積もりを取り、費用だけでなく、弁護士との相性や専門性も考慮して選ぶことが大切です。
関連記事:遺産分割調停の費用について解説
遺産分割調停は何回くらい開かれるのですか?
遺産分割調停の回数は、事案によって大きく異なりますが、平均的には3〜5回程度です。
調停期日は1~2ヶ月に1回のペースで設定されることが多く、1回の調停時間は2時間程度が標準です。
回数を重ねても合意に至らない場合は、調停委員会が「これ以上の調停は困難」と判断し、調停不成立となることもあります。
できるだけ少ない回数で解決するためには、事前準備と柔軟な対応が鍵となるでしょう。
遺産分割調停の流れはどのようになっていますか?
遺産分割調停は、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きで、一般的には次のような流れで進みます。
調停申立て:相続人の一人が家庭裁判所に調停を申し立てます。
第1回調停期日:調停委員が双方の主張を聞き取り、争点を整理します。
複数回の調停期日:1~2か月に1回のペースで調停が開かれ、資料提出や条件調整が行われます。
合意成立または不成立:合意できれば調停成立となり、合意内容が法的に確定します。合意できない場合は調停不成立となり、遺産分割審判へ移行します。
事案によって回数や期間は異なりますが、平均で3~5回、期間は半年~1年程度かかることが多いです。
遺産分割調停で相手が嘘ばかりついている場合はどうすればいいですか?
遺産分割調停で相手が事実と異なる主張をしている場合でも、感情的に反論するのは逆効果です。
重要なのは、嘘を指摘することよりも、客観的な証拠を示すことです。
具体的には、以下の対応が有効です。
- 通帳や契約書などの証拠資料を提出する
- 調停委員に対し、相手方に資料提出を求めてもらうよう依頼する
- 発言内容の矛盾を冷静に整理して説明する
調停委員は証拠に基づいて判断するため、事実を裏付ける資料があれば、相手の嘘が不利に働くことも少なくありません。
相手の虚偽主張が続く場合や、自分で対応するのが難しい場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ|遺産分割調停中にやってはいけないことを理解し、早めに適切な対応を
遺産分割調停を成功させるには、やってはいけない5つの行動(無断欠席、感情的な攻撃、嘘、相手の意見を無視、不誠実な態度)を理解することが重要です。これらの行動は調停不成立のリスクを高めてしまいます。
成功の鍵は、十分な事前準備と冷静な対応です。主張を整理し、証拠に基づいて建設的な話し合いを進めましょう。
状況によっては弁護士への依頼も有効です。冷静な対応を心がけ、納得のいく解決を目指してください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応