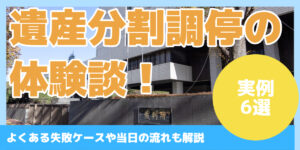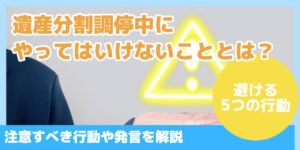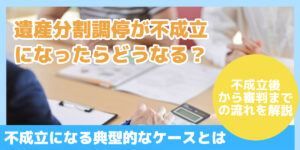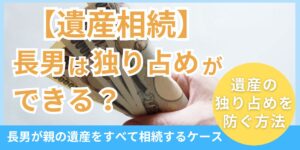【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停は弁護士なしでできる?依頼するメリットや調停の進め方を弁護士が解説
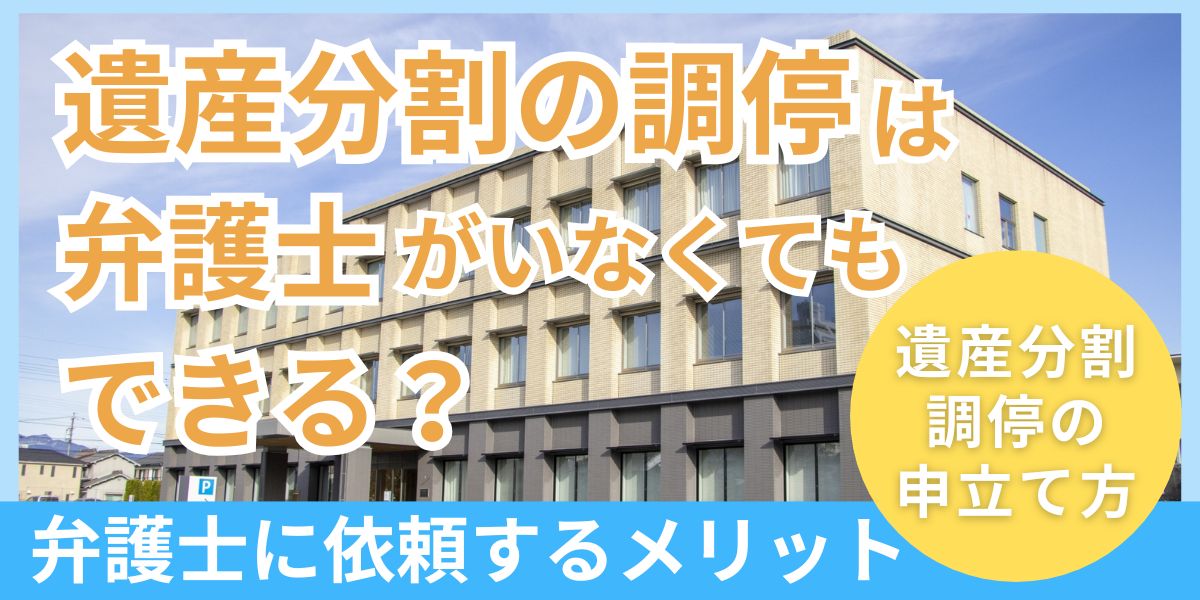
相続人同士での遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
しかし、遺産分割調停は弁護士なしで自分一人でできるのか、調停はどのように進められるのか、弁護士費用はどれくらいなのかなどと、不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、自分一人で調停手続きを進められるかと悩んでいる方のために、遺産分割調停の進め方や遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット・費用などを解説します。ぜひ最後までご覧ください。

制度的には弁護士に依頼しなくても遺産分割調停はできますが、弁護士なしで自分だけで遺産分割調停を進めることは難しい場合も多いことは事実です。
-佐々木 一夫-
- 遺産分割調停を弁護士なしで進めると、法的知識の不足から不利な条件で合意してしまったり、手続きが長期化するリスクがあります。
- 感情的になりがちな調停の場で、客観的な資料に基づき冷静に主張を行うには、代理人として弁護士のサポートが不可欠です。
- 弁護士が関与することで、調停の準備から主張立証、他の相続人との交渉までを一括して担い、依頼者様の精神的な負担を大幅に軽減できます。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割・遺産分割調停とは?


最初に遺産分割・遺産分割調停とは何かについて説明します。
遺産分割とは「相続人全員で協議して遺産を分割する手続き」
遺産分割とは、共同相続人が協議して遺産の全部又は一部の分割をすることです(民法907条1項参照)。
遺産分割は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、全員の意見が一致しなければ成立しません。
しかし、当事者だけで話し合いを続けても合意に至らない場合も多いでしょう。
たとえば、次のような場合です。
- 被相続人が多額の生前贈与をしていた
- 遺言によって相続財産を受け取れない・受け取る額が大きく減少する



上記のような場合は、遺産分割をめぐって争いになることもよくあります。
関連記事:相続の遺産分割調停の流れについて解説
遺産分割調停とは「調停委員が間に入って遺産分割の合意形成を目指す手続き」
遺産分割調停は、家庭裁判所の「家事調停」で取り扱われます。
第三者である家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、調停委員が解決案を提示し合意形成を目指すものです。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用できます。
調停が不成立になった場合は自動的に遺産分割の審判手続へ移行され、裁判官が双方の事情を考慮し、最終的な判断を下します(民法907条2項、家事事件手続法272条4項)。
民法907条2項(遺産の分割の協議又は審判)
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。(後段略)
家事事件手続法272条(調停の不成立の場合の事件の終了)
4 (略)調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
出典:民法|第907条
出典:家事事件手続法|第272条4項
出典:裁判所|遺産分割調停
遺産分割については、次の記事で詳しく解説しています。
併せてご覧ください。
関連記事:【遺産相続でもめたら?】もめた場合の対処法・遺産分割協議のスムーズな進め方
遺産分割調停は弁護士なしでも進められる?


遺産分割調停は弁護士なしでも可能かはケース・内容により異なりますが、一般的には次のようにいえるでしょう。
制度的には弁護士なしでも遺産分割調停は可能
遺産分割調停は、制度的には弁護士に依頼しなくても申し立てることは可能です。
法律や制度の制限・問題はなく、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
調停の手続きや必要書類をインターネットなどで調べて、自分で調停を申し立てることもできます。
しかし、調停になる場合は、相続人間の話し合いが難航している場合であり、思うほど容易でないことも事実です。
たとえば、調停委員に、相続人の範囲、遺産の全貌や分割方法についての考え方などを正確にわかりやすく説明する必要があります。
弁護士なしでの遺産分割調停は難しい場合も多い
実際には法律の専門家以外の方が、弁護士なしで自分だけで遺産分割調停を進めることは難しい場合も多いでしょう。
相続人間の協議がもめて遺産分割調停になる場合、遺言や生前贈与の有効性などをめぐる争いも多く、場合によっては遺留分侵害の問題が絡むケースもあり、複雑で面倒な場合があるのです。
そのような場合、相続に関する法律の正確な知識・理解が必要で、判例などの実務を踏まえた検討が必要になることもあります。
調停不調の場合は審判になるため、調停でも審判を見据えて、きちんとした説明・主張が必要です。
調停の手続きや進め方に不案内な場合、不安感から精神的に大きな負担になる懸念もあります。



無理をせずに、弁護士の力を借りた方がよい場合も多いでしょう。
遺産分割調停を弁護士なしで進めやすいケース・危険なケース


制度上、遺産分割調停は弁護士なしの本人申立て(本人訴訟)も可能です。
しかし、すべてのケースで自力での対応が推奨されるわけではありません。争いの深刻度や遺産の内容によって、難易度は異なります。
安易に「費用を節約したい」という理由だけで自分で行うと、法的に不利な条件で合意してしまったり、調停が不成立となり審判へ移行して長期化したりするリスクがあります。
ご自身の状況がどちらに当てはまるか、冷静な見極めが必要です。
弁護士なしで進めやすいケース
相続人同士の関係が比較的良好で、感情的な対立が少ない場合は自分でも進めやすいでしょう。例えば、「分割案の細部が決まらないだけ」という場合や、「話し合い自体はできているが、念のため裁判所で合意を形にしたい」というケースです。
また、遺産が現金や預貯金のみで、不動産や非上場株式といった「評価の分かれる財産」が含まれていない場合も、法的な論争になりにくいため、弁護士なしで対応できる可能性が高いと言えます。
弁護士なしでは危険なケース
相続人間で感情的な対立が激しく、顔を合わせるのも苦痛な場合は、精神的負担から冷静な判断ができなくなるため危険です。
また、遺産に不動産が含まれる場合や、生前贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)が争点になる場合は、専門的な法的主張と証拠が不可欠です。
法的知識がないまま臨むと、調停委員を味方につけられず、相手方の弁護士に主導権を握られ、本来得られるはずの遺産を失う致命的な結果になりかねません。
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説
遺産分割調停の流れ・進め方4ステップ
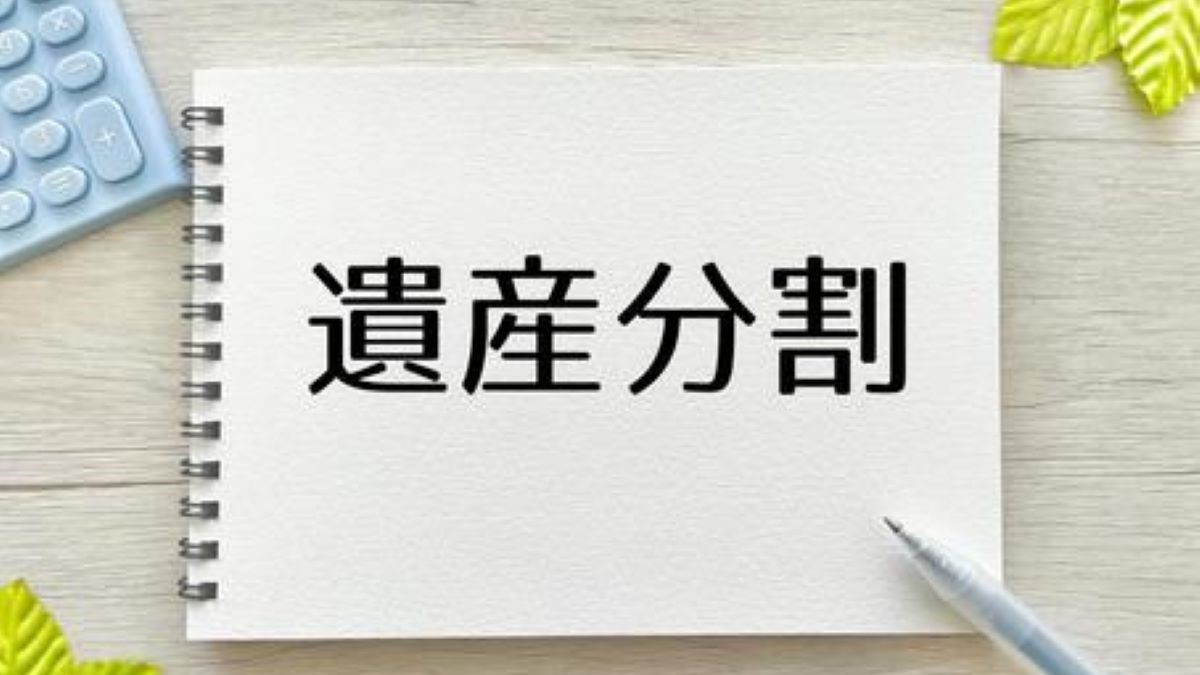
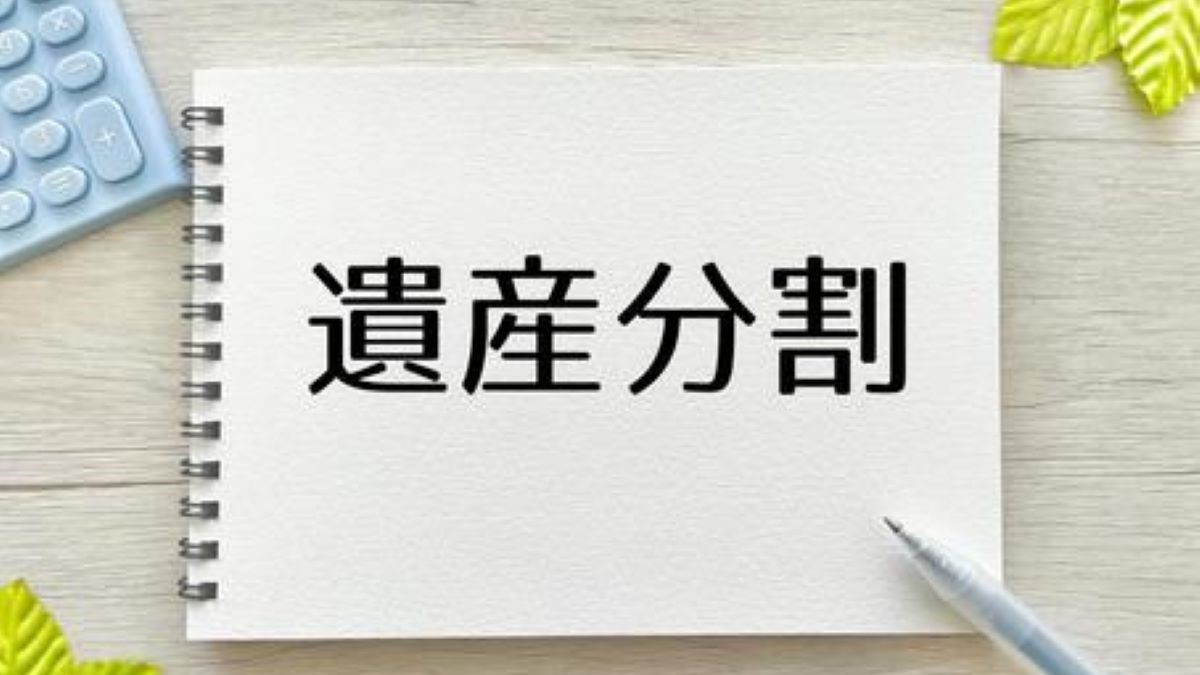
遺産分割調停の流れ・手続きの進め方は、概ね次のようになります。
遺産分割協議に向けて準備する(相続人・相続財産・遺言書の確認)
まず相続人と相続財産・遺言書の有無などを確認します。
戸籍調査等を行い法定相続人を確認する
法定相続人とは、次の人です(民法890条・887条・889条)。
- 被相続人の妻(常時)
- 子(第1順位)
- 直系尊属(第2順位)
- 兄弟姉妹(第3順位)
なお、法定相続人には、法定相続分があります(民法900条)。
遺産分割の前提となる相続財産を確認する
借入金やローンなどの可分負債も相続されますが(民法896条)、相続開始と同時に法定相続分に応じて承継されるため遺産分割の対象にはなりません(参照:裁判所|昭和34年6月19日最高裁第二小法廷判決)。
一方、不可分債務(例:共有物を売却した場合の引渡義務、共同賃借人の賃料支払義務)は共同相続人の全員に帰属し、各相続人が債務全体について責任を負います。
遺言書の有無を確認する
遺言書があれば、基本は遺言書で指定された内容(指定相続分)に沿って遺産分割を行います(民法902条1項)。
そのため、遺言書の有無の確認は重要です。
遺言書の確認方法については、次の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、併せてご覧ください。
関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法
遺産分割協議で相続財産の分割方法を話し合う
遺産分割は、通常、調停・審判の前にまず当事者である相続人間で遺産分割協議をします。
被相続人の遺言書がある場合、遺言内容に相続人が異論なければ遺産分割は基本必要ありません。
しかし、遺言自体に異論はなくても、内容が具体的でなければ、どの財産をどのように分けるかを協議する必要があります。
遺言がない場合は、基本は法定相続分での相続になりますが、遺言の有無にかかわらず、全員が合意すれば異なる遺産分割も可能です。
また生前贈与への疑義・寄与分の主張などがある場合も遺産分割協議が必要ですが、難航することが多いでしょう。
遺産分割協議の進め方については、次の記事で詳しく解説しています。ぜひ、併せてご覧ください。
協議でまとまらなかった場合は遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議がまとまらなければ、相続人は家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。
遺産分割調停での話し合いで相続人全員が合意すれば調停成立です。
調停委員を介して話し合っても、相続人間の意見がまとまらず調停不成立になることもあるでしょう。
遺産分割調停が不成立になった場合、自動的に家庭裁判所での審判に移行します。
遺産分割調停の流れについては、次の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、併せてご覧ください。
参考:裁判所|手続き
調停が不成立になったら遺産分割審判に移行する
遺産分割審判は、遺産分割の方法を裁判官が決定する手続きです。
調停とは違い、当事者の合意を目指す手続きではありません。
審判では、双方が証拠の提出や主張を行います。
裁判官は、提出された資料、当事者の主張などを考慮に入れて審判を下します。



審判には執行力があり(家事事件手続法75条)、金銭支払いや登記移転などの命令が出されれば、審判書に基づいて、強制執行が可能となります。
関連記事:不動産の遺産分割協議について解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産分割調停の申立方法


遺産分割調停の申立方法は次の通りです。
| 1. 申立人 | 共同相続人 包括受遺者 |
|---|---|
| 2.申立先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(当事者が合意で定める家庭裁判所も可) |
| 3.申立費用 | 収入印紙1200円分 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認) |
| 4.必要書類 | 申立書及びその写し(裁判所用と相手方用(全員分)) 申立添付書類(被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、代襲者の全戸籍謄本) 相続人全員の住民票又は戸籍附票・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し(ある場合) 遺産証明書(登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金残高証明書等) |
| 5.申立書を提出 | 直接持参又は郵送 |
遺産分割調停申立後の流れ


遺産分割調停申立後の流れは、概ね次のようになります。
1. 調停期日の通知
通常、調停申立後、2週間程度で調停期日通知書が送られてきます。
調停期日通知書には、1回目の調停期日の日時・場所・持ち物などが記載されています。
調停期日は、裁判所の開庁時間内で裁判所が指定する日で、第1回期日は申立てから1~2か月前後が一般的です。
関連記事:遺産分割調停の期間はどれくらい?平均回数や流れを徹底解説
2. 第1回の調停期日
調停期日当日は、呼び出されるまで待合室で待機しましょう。
申立人と相手方は別々の待合室で待ち、調停委員が調停室で交互又は同時に話を聴きながら調停を進めていきます。
調停の時間は、1〜2時間程度です。
当日の主な持ち物は、次の通りです。
- 調停期日通知書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印でよい)
- 調停期日通知書で指定された書類(指定があった場合)
- 調停で話したいことをまとめたメモなど
3. 第2回以降の調停に出席する
ほとんどの場合、1回で終わることはなく、何回か調停を行い合意形成を目指すことになるでしょう。
調停期日は通常1〜2か月に1回のペースで行われます。
解決までには相応の時間を要することもあるでしょう。
司法統計年報によれば、遺産分割事件の審理期間は6月~1年以内、期日回数は6~10回が最も多くなっています。
出典:裁判所|令和5年司法統計年報(家事編)「遺産分割事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所」
4. 調停の終了
調停は、次のいずれかの形で終了します。
- 調停成立:話し合いで合意できた場合、調停成立となる
- 調停不成立:合意ができなかった場合、調停委員会の判断により調停不成立として終了
(調停が必要なくなった場合は、いつでも取下げが可能)
5.審判の開始
調停不成立の場合、自動的に審判が開始されます。
審判では、提出された証拠・資料、当事者の主張などを考慮して、裁判官が審判(決定)を下します。
審判は執行力があり(家事事件手続法75条)、金銭支払いや登記移転などの命令が出されれば、審判書に基づいて、強制執行が可能となります。



審判の決定に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に即時抗告できます。
参考:家事事件手続法
関連記事:不動産の遺産分割審判について解説
遺産分割調停を弁護士に依頼する5つのメリット


遺産分割調調停は自分だけでなく、弁護士にも依頼して進めることをおすすめします。
遺産分割調停を弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあります。
手続きをすべて任せられる
調停は、申立書をはじめ、添付書類など数多くの書類の作成・提出が必要です。
- 遺産分割調停申立書の作成・提出
- 家庭裁判所への申立て代行
- 主張書面の作成・提出
- 証拠書類の提出・整理
- 調停調書の確認・受領
- 調停条項案の作成・チェック
弁護士に依頼すれば、書類の作成・収集から提出まですべてスムーズに代行できます。
交渉を一任できストレスも軽減される
当事者が直接話し合っても感情的に対立し進まないことも多いものです。
弁護士に協議段階の交渉から調停・審判まですべて任せれば、感情的対立を避け、スムーズに話し合いを進められます。
精神的な負担も軽減されるでしょう。
調停・審判になっても、法律や判例に熟知した弁護士がタイミングを逃さず的確に対応できます。
有効なアドバイスをもらえる
調停に臨む前に、相手への提案や相手からの提案への対応など、状況に応じた適切なアドバイスをしてもらえます。
弁護士からは、あなたの希望が法的に認められるか否か、過去の裁判例に基づいた客観的な見通しを得られます。
具体的には、「調停委員に響く主張の組み立て方」や「有利な証拠の選定」など、実践的な戦略を授けてもらえます。また、審判へ移行した場合のリスクも踏まえ、早期解決に向けた妥当な着地点(譲歩ライン)の助言をもらえるため、感情論による無駄な長期化を回避できるでしょう。
調停への出席や発言も可能
調停期日では、自分一人では話すべき内容をうまく整理できないことや、つい感情的になることもあるでしょう。
弁護士が同行してアドバイスや発言することも可能です。
代理人として出席することもできます。
結果として有利な遺産分割を期待できる
遺産分割では、対象財産・特別受益や寄与分等、難しい問題がある場合も多いでしょう。
弁護士は専門知識を活用してこれらの問題にも的確に対応可能です。



有利な遺産分割になることが期待できます。
遺産相続を弁護士に依頼するメリットについては、次の記事で詳しく解説しています。
ぜひ、併せてご覧ください。
関連記事:遺産相続を弁護士に相談した方がいいケース・メリット・弁護士の選び方
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停を弁護士に依頼した場合の費用相場
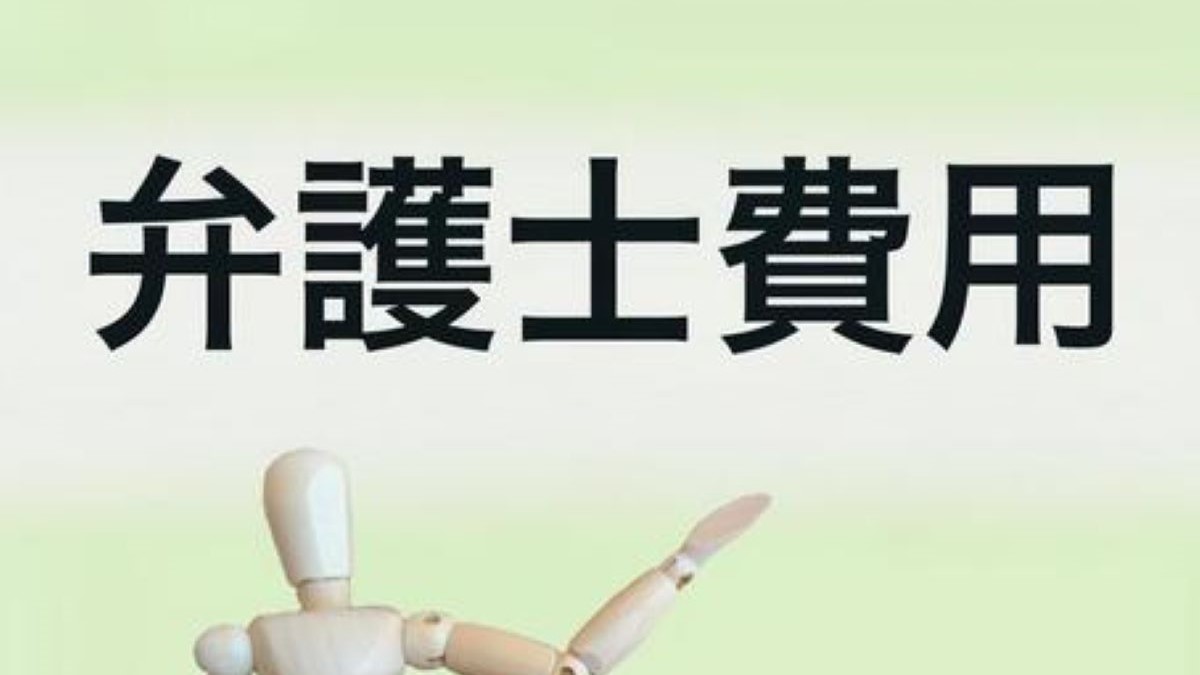
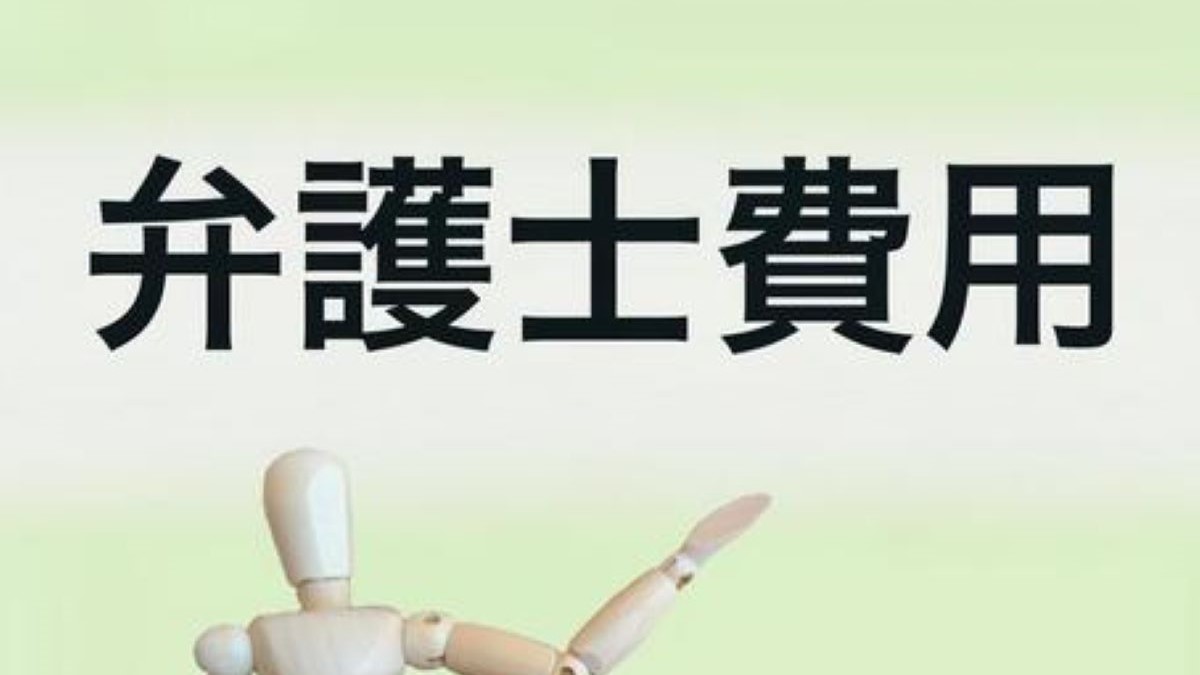
遺産調停の弁護士費用の相場は法律事務所により異なりますが、概ね次のようになるでしょう。
| 相談料 | 30分5000円程度が一般的 無料相談がある事務所も多い |
|---|---|
| 着手金 | 調停の結果にかかわらず発生する 20万円~50万円程度(遺産総額の5~8%程度の場合もある) |
| 成功報酬 | 決め方はいろいろある 得られた財産の10~15%程度 |
| 日当・実費 | 実費:事件処理に実際にかかる費用(印紙代、切手代、交通費など) 日当:出張費用(5万円~7万円程度) |
費用はかかるが弁護士に依頼することで最終的に手にできるお金が増える可能性があります。弁護士費用以外の遺産分割調停にかかる費用についてはこちらをご覧ください。
弁護士法人アクロピースでは、着手金を無料とする料金体系もあります。
遺産分割調停に強い弁護士を選ぶ3つのポイント


遺産に強い弁護士を選ぶ3つのポイントを解説します。
- 遺産など相続分野の解決実績が豊富:
- 弁護士は法律全般の専門家ですが弁護士にも得意分野がある
- 遺産分割の問題は特に相続分野に強い弁護士に依頼する
- 弁護士事務所の公式サイトで、相談実績などを見て相続問題に精通している弁護士か確認する
- 弁護士費用・料金体系が明確:
- 弁護士に依頼した場合の費用・料金体系は事務所によって異なる
- どのような料金体系がよいかは相談者の状況によるため一概にはいえない
- HPなどで料金体系が明示されていなければ比較検討できない
- 料金体系を選択できる事務所に頼む方が安心
- 初回相談時の対応も重要:
- 初回相談料無料などを利用して、弁護士や事務所の対応を確認する
- 相談者の話をしっかり聴き、具体的な解決策を提示してくれるようであれば安心
関連記事:相続に強い弁護士の選び方とは?確認すべき8つのポイントや費用相場を解説
遺産分割調停は早めに弁護士へ相談を


遺産分割調停は早めに弁護士と相談しましょう。
遺産分割問題は、親族間の感情的対立でもめて、深刻な対立に発展することがよくあります。
相手方との交渉でもめれば、調停や審判で争うことになりますが、準備や対応に多くの時間と労力が必要です。
自分一人でもできると思うかもしれませんが、法律の知識も必要なため、弁護士の力を借りた方が間違いなく、しかも論理的に適切な対応ができます。
弁護士費用はかかりますが、弁護士に相談すれば、前述「遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット」のようなメリットがあります。
何よりも、遺産をきちんと受け取れる可能性が高まるでしょう。



早く弁護士に依頼することで、相方との交渉段階からすべて任せてスムーズに対応ができ、調停から審判になっても有利な解決が期待できます。
弁護士なしの遺産分割調停に関するよくある質問
遺産分割調停を弁護士なしで行う際にやってはいけないことは?
最も避けるべきは、感情的になり相手方の誹謗中傷をすることです。 弁護士がいない分、調停委員への心証形成はあなた自身の発言にかかっています。 理不尽な態度は「話が通じない」と判断され、調停不成立や不利な心証につながります。 また、嘘をつくのもNGです。あくまで法的な手続きであることを忘れず、客観的な証拠に基づき、冷静かつ論理的に主張を伝える姿勢が不可欠です。
遺産分割で弁護士なしで対応する割合はどれくらいですか?
相当数が「本人のみ(弁護士なし)」で対応している一方、 一定数は弁護士が関与しています。
日本弁護士連合会の集計では、遺産分割調停における代理人弁護士の関与はおおむね4割前後、本人のみは6割弱という水準が示されています(年度・地域で変動あり)。日本弁護士連合会
出典:日本弁護士連合会「4 遺産分割調停事件における代理人弁護士の関与状況」
争点が複雑(特別受益・寄与分・不動産評価など)なほど弁護士関与率が高まる傾向がみられます。ご自身だけで進めるべきか迷われたら、一度弁護士に相談し、リスクと費用対効果を把握しておくと安心です。
遺産分割調停の費用は誰が払いますか?
費用は性質ごとに負担が異なります。
- 裁判所費用(収入印紙・郵券など):原則、申立人が先に負担(予納)します。調停が成立する際に、当事者間の合意で分担を取り決めることがあります。
- 鑑定・評価などの実費(不動産評価、戸籍・登記事項の取得費、郵送費など):通常は立替えた側がいったん負担し、合意や審判で按分されることがあります。
- 弁護士費用:原則、各当事者が自己負担です。合意の条項で費用負担を取り決めることもありますが稀です。
費用配分は事件の内容・進行・合意内容で変わり得ます。費用感や最適な分担案は個別に検討が必要です。
関連記事:遺産相続の弁護士費用は誰が払うのか
遺産分割調停に弁護士だけが出席することは可能ですか?
可能です。 適切な委任状があれば、代理人弁護士のみが期日に出席して、手続を進めることができます。
もっとも、合意成立時の最終意思確認や重要な事実関係の聴取など、裁判所が本人出頭を求める場面もあります。オンライン参加や電話参加を認めるかは裁判所の判断によります。
実務上は、日程の都合などで一部期日は代理人のみ、要所では本人同席という進め方がよく見られます。相手方に弁護士が付いている場合や論点が複雑な場合は、代理人出席のメリットが大きいことがあります。
迷われる場合は、事前に弁護士へ相談し、最適な出席体制を整えましょう。
兄の使途不明金を追求し遺産分割調停で解決した事例
被相続人の通帳から不自然な出金が見つかり、調査と調停で解決したケースがあります。
“被相続人Aさんが亡くなったが、生前に相続人である兄のCさんが管理していたAさんの預金口座から多額の金銭が引き出されていた。弟である依頼人Bさんは出金された金銭を使途不明金として追及したいとのご相談。”
この事例の課題としては、
・Aさんの財産を管理していたCさんの使途不明金が正当なものか否かを見極めること
があげられます。
そこで
- 依頼人Bさんの日記や兄のCさんへのメールなどを基に、出金額がAさんの介護の実態と比較して過剰であると主張
- 過去の時系列と金額の整合性を丁寧に組み立て、主張を論理的に展開
というご対応をさせていただき、家庭裁判所の調停委員にも理解を得ることができました。
使途不明金のうち半分以上が認定され、依頼人のBさんが納得する水準で和解が成立いたしました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


まとめ|遺産分割調停は弁護士なしで進めるのは難しい!不安があれば早めに相談しよう
遺産分割調停を弁護士なしで行うことについてまとめます。
- 遺産分割は相続人全員で話し合う必要(遺産分割協議)、全員の意見が一致しなければ成立せず、争いになることも多い
- 遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、合意形成を目指す家事調停
- 遺産分割調停は制度上は弁護士なしでも可能、実際には弁護士なしでは難しい場合が多い
- 遺産分割の進め方は、まず分割協議、合意が見込めないときは調停申立、調停不成立の場合は自動的に審判に移行する
- 弁護士に遺産分割調停を依頼するメリットは、手続きをすべて任せられる・交渉を一任できストレスも軽減・タイミングを逃さず的確に対応できることなど
- 遺産分割に強い弁護士を選ぶポイントは、相続分野の解決実績が豊富・弁護士費用が明確・初回相談時の対応がよいこと
遺産分割は合意が容易でなく、法律に関する専門的な知識が必要なうえ、面倒な手続きもあります。



遺産分割調停など相続についてわからないことやもめごとがあるときは、相続分野に精通している弁護士に早めに相談した方がよいでしょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応