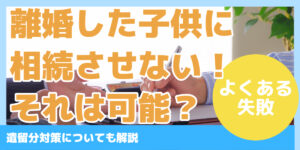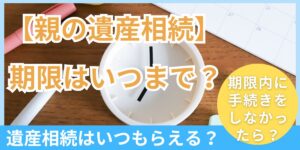【無料相談受付中】24時間365日対応
生命保険は相続財産になる?遺産分割と相続税の扱いを弁護士が解説

「特定の相続人だけが多額の生命保険金を受け取った。遺産分割で考慮すべきではないのか?」
「他の兄弟との差が大きすぎて不公平だ。法的にどうなるのか知りたい」
相続における生命保険の扱いについて、このように悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
生命保険金は、金額が大きくなることも多く、相続人間のトラブルの原因になりがちです。 特に、特定の相続人だけが受取人に指定されている場合、その扱いは深刻な問題となるでしょう。
生命保険金が相続財産になるかどうかは、「遺産分割(民法)」と「相続税(相続税法)」で異なります。
この記事では、生命保険金が相続財産になるかどうかについて、民法上、相続税法上の取り扱いの違いや税金について弁護士が解説します。
生命保険が法的にどのような扱いになるのか、ご自身のケースと照らし合わせながら確認していきましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
生命保険金は「相続財産」になる?民法上・相続税法上の取り扱いの違い
生命保険金が「相続財産」になるかどうかは、前提とする法律が「民法」か「相続税法」かによって変わります。
遺産分割のルールを定める民法と、税金計算の根拠となる相続税法とでは「相続財産」の定義が異なるためです。
それぞれの法律における扱いの違いを、下表にまとめました。
| 法律 | 取り扱い | 主な理由 |
|---|---|---|
| 民法 | 原則として相続財産ではない | 保険金は「受取人固有の財産」とみなされるため |
| 相続税法 | 相続財産とみなす(みなし相続財産) | 相続税の課税の公平性を保つため |
民法上、生命保険金は原則他の相続人との遺産分割協議の対象には含まれません。ただし、受取人が被相続人(故人)本人に指定されている場合などは、例外的に相続財産となるケースもあります。
一方、相続税法では「みなし相続財産」として扱われます。相続税法上、生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられており、それを超えた金額が課税対象です。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫この違いを理解していないと、相続トラブルや想定外の税負担につながる恐れがあるため、それぞれの法律における定義の違いは正確に押さえておきましょう。
【民法】生命保険金は原則「遺産分割の対象外(受取人固有の財産)」
遺産分割協議(相続人間での遺産の分け方の話し合い)において、生命保険金は原則として相続財産に含まれません。民法上、生命保険は「受取人固有の財産」と考えられるためです。
本章では、以下について解説します。
生命保険が遺産分割の対象にならない理由
法律上、生命保険金(死亡保険金)は「受取人固有の財産」と考えられています。
これは、被相続人(亡くなった方)の財産が相続人に引き継がれる「相続」とは異なり、生命保険契約に基づいて、保険会社から受取人へ直接支払われるお金と解釈されるためです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相続財産 | 被相続人から相続人へ引き継がれる財産(例:預貯金、不動産) |
| 生命保険金 | 保険契約に基づき、受取人が直接取得する財産 |
したがって、特定の相続人が受取人に指定されていた場合、その保険金は受取人個人のものです。他の相続人が「その保険金も遺産の一部だから分けてほしい」と要求しても、原則として応じる義務はありません。
生命保険金の受取人が「相続人」と指定されていた場合の扱い
生命保険金の受取人が、個人名ではなく単に「相続人」と指定されるケースがあります。この場合は、相続人全員が保険金を受け取る権利者となります。
ただし、この場合も保険金は遺産分割の対象外という原則は変わりません。あくまでも保険契約に基づく「受取人固有の財産」として扱われるためです。
受取人指定の方法によって、保険金の扱いに以下の違いがあります。
| 指定方法 | 受取人 | 分配方法 |
|---|---|---|
| 個人名で指定(例:「長男A」) | 指定された個人(長男A) | 全額を長男Aが取得 |
| 「相続人」と指定 | 相続人全員 | 各相続人が法定相続分に応じて取得 |
上記のとおり、「相続人」と指定した場合は、相続人全員が法定相続分に応じて権利を持ちます。
重要なのは、どちらのケースも遺産分割協議の対象とはならない点です。保険会社は遺産分割協議の結果を待つ必要がありません。保険契約(約款)に基づいて、機械的に分配処理を行います。
例えば、相続人指定で保険金1,000万円、相続人が配偶者と子2人(法定相続分1/2、各1/4)なら、配偶者に500万円、子2人に各250万円が支払われます。
生命保険金が「特別受益」として遺産分割で考慮されるケース
生命保険は原則受取人固有の財産ですが「保険金の額が他の相続財産と比較して著しく高額で、相続人間の著しい不公平を生む場合」は例外です。
この場合、その保険金は被相続人からの「特別受益(特別な贈与)」に準ずるものとして、遺産分割の計算上、考慮(持ち戻し)される可能性があります。
- 遺産の総額が1,000万円しかないのに、特定の相続人だけが5,000万円の保険金を受け取る
- 被相続人が意図的に特定の相続人にだけ多額の保険金を残そうとした事情がある
- 他の相続人がほとんど遺産を受け取れない



ただし、これはあくまで例外的な扱いです。「不公平だ」と感じた場合は、法的な判断が必要になるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
関連記事:特別受益は遺留分侵害額請求の対象になる?対象とならない時効についても解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
【税法】生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象
民法上、生命保険金は遺産分割の対象とならない「受取人固有の財産」です。 しかし税法上は、生命保険金は「みなし相続財産」として扱われ、原則として課税対象です。
本章では、生命保険における相続税法上の考え方として、以下を解説します。
生命保険が相続税の対象になる理由
生命保険金が相続税の対象となるのは、課税の公平性を担保する重要な役割があるためです。
仮に、生命保険金が相続税の対象外となった場合、被相続人が亡くなる直前に、預貯金や他の資産をすべて生命保険契約に切り替えるだけで、相続税を不当に回避する行為(租税回避)が横行するリスクが考えられます。
このような事態を防ぎ、公平な課税を実現する目的があるのです。
よって税法上、保険金は「被相続人の死亡によって実質的に取得した財産(みなし相続財産)」とされます。
生命保険の非課税枠の計算方法(500万円×法定相続人の数)
生命保険金は、課税の公平性のために「みなし相続財産」として扱われるのと同時に、遺された家族の生活を保障するという重要な役割も担っています。
よって税法上は遺族の生活に配慮し、一定の金額まで税金がかからない「非課税枠」を設けています。
この非課税枠(非課税限度額)の算出方法は以下のとおりです。
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
計算における重要な注意点は「法定相続人の数」の考え方です。相続人の中に相続放棄をした人がいた場合でも、その放棄がなかったものとして、法定相続人の数に含めて計算します。
また、法定相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子の数には法律上の制限(実子がいれば1人、いなければ2人まで)がある点にも注意が必要です。
【計算例】死亡保険金の課税対象額
前述の非課税枠の計算方法を、具体的な事例で確認しましょう。
【ケース1】受け取った死亡保険金が1,000万円、法定相続人が3人
前提条件
- 受け取った死亡保険金:1,000万円
- 法定相続人:3人(例:妻、長男、長女)
計算方法
- 非課税枠の計算:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 課税対象額の計算:1,000万円(保険金) - 1,500万円(非課税枠) = -500万円
よって、受け取った保険金額(1,000万円)が非課税枠(1,500万円)を下回っているため、この保険金1,000万円には相続税がかかりません。
【ケース2】受け取った死亡保険金が2,000万円、法定相続人が3人
前提条件
- 受け取った死亡保険金:2,000万円
- 法定相続人:3人(例:妻、長男、長女)
計算方法
- 非課税枠の計算:ケース1と同様1,500万円
- 課税対象額の計算:2,000万円(保険金) - 1,500万円(非課税枠) = 500万円
この場合、非課税枠を超えた「500万円」がみなし相続財産として、他の預貯金や不動産などの相続財産と合算され、相続税の計算対象となります。
生命保険金が相続財産になる例外ケース
前述のとおり、生命保険金は原則として受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割の対象には通常含まれません。
しかし、以下のような特定の状況下では例外的に相続財産として扱われる場合があります。
| 生命保険が相続財産となるケース | 詳細 |
|---|---|
| 受取人が「被相続人本人」と指定されている | 保険金は被相続人の財産となり、遺産分割の対象になります。 |
| 保険金が著しく高額で、相続人間に不公平が生じる | 特別受益と判断され、遺産分割で考慮されることがあります。(特別受益と認められると、その金額は遺産分割の計算に含められます。 ) |
これらの例外に該当する場合、生命保険金も遺産分割の対象となるため注意が必要です。
死亡保険金にかかる税金の種類
死亡保険金を受け取った際、かかる税金は必ずしも相続税とは限りません。 契約の形態によって、税金の種類は以下の3つに分かれます。
なお、どの税金が課されるかは、保険契約における以下の3者の関係性によって決まります。
- 契約者(保険料を負担する人)
- 被保険者(保険の対象となる人=亡くなった人)
- 受取人(保険金を受け取る人)
それぞれの税金の種類について、詳しく見ていきましょう。
相続税|「契約者」と「被保険者」が同一のケース
死亡保険金に相続税がかかるのは、「契約者(保険料負担者)」と「被保険者(亡くなった人)」が同一であるケースです。 これは、家族の生活保障のために加入する最も一般的な契約形態です。
例えば、夫が自分自身を被保険者として保険に加入し、保険料も夫が支払い、受取人を妻や子に指定していた場合がこれに該当します。
この場合、保険金は前章でも解説した「みなし相続財産」として扱われます。 このパターンの課税上の特徴は以下の通りです。
- 相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が適用される
- 生命保険金独自の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使える
死亡保険金に課税される3つのパターンの中で、唯一この非課税枠が適用されます。
贈与税|「契約者」「被保険者」「受取人」の3者がすべて異なるケース
死亡保険金に贈与税がかかるのは、「契約者」「被保険者」「受取人」の3者がすべて異なるケースです。
例えば、契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が子である場合が該当します。
この場合、妻の死亡によって保険金が支払われますが、その保険金の原資(保険料)を負担していたのは夫です。そのため税法上は、「保険料を負担した夫」から「保険金を受け取った子」へ財産が贈与されたものとみなされます。
このパターンには、以下のような税務上の大きなデメリットがあります。
- 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)や相続税の基礎控除が適用できない
- 適用されるのは贈与税の基礎控除(年間110万円)のみ
- 贈与税は一般的に相続税よりも税率が高く、3つのパターンの中で税負担が最も重くなる可能性がある
名義変更などで意図せずこの形になっている場合があるため、保険証券で確認しましょう。
所得税(一時所得)|「契約者」と「受取人」が同一のケース
「契約者(保険料負担者)」と「受取人」が同一の場合、受け取った保険金は「一時所得」として所得税の対象です。これは、自身が支払った保険料が保険金として戻ってきたとみなされるためです。
一時所得の課税対象額は、以下の計算式で算出されます。
- 利益の計算:受け取った保険金額 - 支払った保険料の総額
- 特別控除の適用:1で算出した利益 - 特別控除額(最大50万円)
- 課税対象額:2で算出した金額 × 1/2
この金額が他の所得と合算され、総合課税されます。ただし支払保険料が受取額を上回る(利益なし)場合は課税されません。
また、受け取った保険金は受取人の財産となり、将来の相続時には相続税の対象となります。



なお、受取人が確定申告前に死亡した場合、相続人による準確定申告が必要です。
相続で生命保険の取り扱いに不公平を感じた場合の法的手段
相続において、特定の相続人だけが多額の生命保険金を受け取っているなどで「不公平だ」と感じた場合、法的な対抗手段の検討が必要です。
まずは感情的にならず、冷静に以下の対処法を検討しましょう。
| 法的手段 | 概要 |
|---|---|
| 相続財産全体と保険金の詳細確認 | 相続財産総額と、問題の生命保険の詳細(金額・契約内容)を正確に把握します。 |
| 遺産分割協議での「特別受益」の主張 | 保険金額が著しく高額な場合、遺産分割協議で「特別受益」に準ずると主張・交渉します。 |
| 「遺留分」侵害額請求の検討 | 特別受益と認められれば「遺留分」の計算基礎に含まれるため、侵害額請求が可能か弁護士に相談します。 |
これらの判断には高度な法律の専門知識が必要です。 相続での不公平を法的に解決したい場合は、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。
生命保険と相続財産に関するよくある質問
生命保険の受取人指定が無い場合、相続財産になりますか?
保険契約の受取人指定がない場合、その保険金が相続財産となるかは、契約時の保険約款の規定によって決まります。
多くの保険契約では、受取人指定がない場合は「法定相続人」が受取人となると定められています。
この場合、保険金は遺産(相続財産)として分割協議の対象にはなりません。
各法定相続人が、それぞれの法定相続分に応じて、保険金を受け取る権利(固有の財産)を取得するのが一般的な扱いです。
生命保険の入院給付金や解約返戻金は相続財産になりますか?
生命保険の入院給付金や解約返戻金は、死亡保険金とは異なり、原則として相続財産に含まれます。
入院給付金とは、被相続人が生前に受け取る権利が確定していた給付金で、未受領でも相続財産です。死亡後に遺族が請求した場合も、被相続人に帰属する財産として遺産分割や課税の対象になります。
解約返戻金は、被相続人が契約者であった保険が死亡時に解約されていない場合、その「保険契約に関する権利」が相続財産として評価されます。この権利(解約返戻金相当額)も、相続財産に含まれ、遺産分割および相続税の対象です。
相続放棄しても生命保険金は受け取れますか?
原則として受け取ることが可能です。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの負債もすべて含めた「相続財産」を引き継がない手続きです。生命保険金は民法上「受取人固有の財産」とされ、相続財産には含まれません。
したがって、ご自身が受取人に指定されていれば、相続放棄をしても保険金を受け取れます。
ただし、相続放棄をすると税務上「相続人」の地位を失います。 そのため、相続税の生命保険非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用は受けられなくなる点に注意が必要です。
生命保険金は遺留分の対象ですか?
生命保険は原則として、遺留分の計算対象には含まれません。
遺留分は、あくまで相続財産(遺産)に対して計算される最低限の取り分です。 生命保険金は民法上「受取人固有の財産」であり、相続財産ではないため、原則として遺留分侵害額の計算には含まれないのです。
ただし、保険金の額が遺産総額に対して著しく高額で、相続人間に極端な不公平を生むようなケースでは、「特別受益に準ずる」ものとして、遺留分の計算に加味される可能性があります。
まとめ|生命保険金の相続は「遺産分割」と「税金」の両面で弁護士に相談しよう
生命保険金が相続財産にあたるかどうかは、「遺産分割」と「税金」それぞれで扱いが異なります。
生命保険金は、相続において非常に特殊な財産であり、「受取人固有の財産」という原則を理解していないと、遺産分割協議で他の相続人と不必要なトラブルに発展しかねません。
また、「みなし相続財産」という相続税法上のルールを知らなければ、非課税枠の適用や相続税申告で重大なミスを犯す恐れがあります。



生命保険金の扱いや相続手続き、相続人間のトラブルで少しでも不安がある場合は、相続問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応