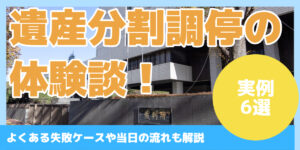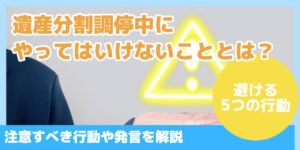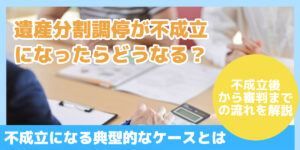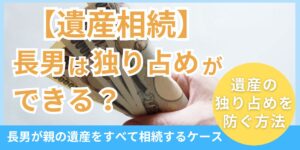【無料相談受付中】24時間365日対応
相続の遺産分割調停とは?流れや有利な進め方を弁護士が紹介
「相続人同士で話し合いがまとまらず、どうすれば良いのかわからない」
「家庭裁判所で調停をすることになったけれど、具体的にどのような流れなのか」
遺産分割協議では親族間で感情がぶつかりやすく、冷静に進めるのが難しいケースもあります。
協議で話がまとまらないときは遺産分割調停に移行します。遺産分割調停の全体や当日の流れを把握することで円滑に手続きが進みやすくなるでしょう。
本記事では、遺産分割調停の基礎知識から全体像、当日の流れをわかりやすく解説します。
遺産分割調停は「協議がまとまらない場合の法的な話し合い手続き」:家庭裁判所が関与し、裁判官・調停委員が中立的立場で相続人の合意形成を支援する。
調停は「合意が原則」、不成立なら自動的に審判へ移行する:話し合いでまとまれば調停調書が作成され、まとまらなければ裁判所が分割方法を決定する。
期間の目安は「半年〜1年程度」:月1回ペースで進行し、不動産評価や相続人の対立が大きいと長期化しやすい。
有利に進める鍵は「証拠資料と冷静な主張」:感情論を避け、財産資料・寄与分・特別受益などを客観的証拠に基づいて整理することが重要。
実務上は「早期に弁護士を入れる方が不利益を防ぎやすい」:手続き負担や主張漏れを防ぎ、調停不成立後の審判まで一貫対応できる。
調停の仕組みや進み方を把握しておけば、不安を減らし、適切に対応しやすくなります。相続問題を解決へ導く一歩として、ぜひ最後まで読んでみてください。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
相続時の遺産分割調停とは?【基礎知識】
遺産分割調停とは、遺産分割協議で話しがまとまらなかったときに必要になる法的手続きです。
必ずしも必要になるわけではありませんが、調停を申し立てるのであれば、まずは基礎知識を押さえることが大切です。
遺産分割調停がどのようなものなのか、誰が申立人になるのか理解しましょう。
遺産分割調停とは「家庭裁判所を介して遺産の分け方を決める法的手続き」
遺産分割調停とは、遺産分割協議で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所を通じて遺産の分け方を決定する法的手続きです。(参照:裁判所|遺産分割調停)
調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で関与し、相続人それぞれの意見を聞き取りながら公平な解決策を提示します。遺産の価値を正確に評価し、必要な資料を提出した上で解決を目指すため、客観的な根拠に基づいた分割案を検討できます。
裁判に比べて柔軟性が高く、合意が成立すれば「調停調書」という法的効力を持つ文書にまとめられるため、将来のトラブル防止にも有効です。
遺産分割調停を申し立てるのは「法定相続人」「包括受遺者」「相続分譲受人」のいずれか
遺産分割調停は遺産を受け取る立場にある人のみ、裁判所へ申し立てが可能です。具体的には、以下に当てはまる人です。
| 遺産分割調停を申し立てる人 | 詳細 |
|---|---|
| 法定相続人 | 配偶者や子ども、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹など、法律で定められた相続人 |
| 包括受遺者 | 遺言で「財産の全部」または「一定割合」を包括的に相続することを指定された人 |
| 相続分譲受人 | 相続人からその相続分を譲り受けた人 |
これらの立場以外の人は、調停を申し立てることはできません。親族であっても、法定相続人に該当しない場合は申立権を持たないため注意が必要です。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫遺産分割調停を検討している方は、誰に申立権があるのかを正しく理解しておきましょう。
相続における遺産分割調停の全体の流れ【10ステップ】
相続における遺産分割調停の流れを、以下の10ステップで紹介します。
まずは調停の全体の流れを把握し、どのようにステップが進むのか確認しましょう。
なお、こちらで紹介するステップは、裁判所の「遺産分割調停のしおり」に基づいて作成しています。
相続人の範囲を確認する
遺産分割を進める上で、まず誰が相続人になるのかを正確に確定する必要があります。
相続人の範囲は民法で定められており、配偶者は常に相続人となります。その次に子ども、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹などが続く流れです。
詳細は、以下のとおりです。
| 相続における順位 | 法定相続人の立場 |
|---|---|
| 常に相続人となる相続人 | 被相続人の配偶者 |
| 第1順位 | 被相続人の子ども |
| 第2順位 | 直系尊属(父母や祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
たとえば、被相続人が亡くなった場合、配偶者と一緒にその子どもが相続人になります。子どもが亡くなっている場合、配偶者と同順位で相続人になるのは、被相続人の父母・祖父母などの直系尊属です。
子ども・直系尊属が亡くなっているケースでは、第3順位である兄弟姉妹が財産を受け継ぎます。なお、相続放棄をした人や内縁関係の人は、相続人には含まれません。
誤った範囲で協議を進めると、後で無効となる可能性があるため注意が必要です。
相続人の範囲を確認する際は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、家族関係をさかのぼって整理します。
遺言書の有無を確認する
遺産分割を始める際は、最初に遺言書があるかを確認しましょう。遺言は被相続人の意思を反映する効力を持ち、存在すれば原則その内容に沿って手続きが進むためです。
遺言書の種類は、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類に分かれています。
それぞれの特徴や確認方法は、以下のとおりです。
| 遺言書の種類 | 特徴 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 被相続人が自ら手書きで記載する形式 | 遺言書が保管されている可能性が高い場所を探す |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成する信頼性の高い方式 | 公証役場、日本公証人連合会の検索システムで確認する |
| 秘密証書遺言 | 本人が作成し、公証役場に存在のみを証明させる形式 | 日本公証人連合会の検索システムで確認する |
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。(参照:裁判所|遺言書の検認)
自宅のタンスや被相続人の部屋、貸金庫などに保管されている可能性があるため、探してみましょう。
公正証書遺言は、平成元年以降に作成された遺言書に限り、公正役場の遺言検索システムで存在の確認が可能です。(参照:日本校紹介連合会|Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?)
秘密証書遺言は本人が封をした状態で公証役場に提出し、その存在だけを証明してもらう方式です。公正証書遺言と同じく、公証役場の遺言検索システムで有無を調査できます。
これらの確認を経て遺言の存在が確認できれば、原則その内容に沿って遺産分割が進められます。
遺言書の確認方法は、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
相続財産の範囲を確認する(遺言書がない場合)
遺言書がない場合は、相続財産が何に当たるのかを網羅的に洗い出す作業に入ります。
何が遺産に含まれるのかを明確にしないと、公平な分割も調停も成立しません。プラス・マイナスの財産をすべて洗い出し、財産の全体像を確認しましょう。
プラスの財産には、不動産、預貯金、有価証券、生命保険の一部解約返戻金などが該当します。一方、マイナスの財産には、借金や未払い税金、保証債務などが該当します。
相続財産に不動産がある場合、法務局で不動産登記事項証明書を取得し、土地・建物の名義を確認しましょう。金融資産は、銀行や証券会社に照会し、残高証明書を取り寄せる方法があります。
借入金や債務については契約書や請求書を確認し、必要に応じて債権者に直接問い合わせると良いでしょう。
相続財産の金銭的価値を評価する
相続財産を公平に分けるためには、それぞれの財産を金銭的に評価する必要があります。価値を明確にしないままでは取り分を正しく計算できず、不満や争いの原因になります。
不動産は路線価や固定資産税評価額を基準としますが、実際の市場価格を反映させるには不動産鑑定士へ依頼するのが確実です。正確な評価額が割り出せることで、公平な遺産分割が期待できるでしょう。
預貯金や株式は、被相続人が亡くなった時点の残高や株価を基準にし、金銭的価値を評価します。金融機関から残高証明書を取り寄せ、正確な価値を把握しましょう。
客観的な証明資料をそろえ、透明性の高い評価を行うことが、公平な相続を実現するための鍵となります。
遺産分割の不動産の評価方法は、以下の記事を参考にしてみてください。
遺産分割協議で分割方法や取り分を話し合う
相続人が確定し、財産の範囲と価値を評価したら、遺産分割協議を行います。
相続人全員が集まり、誰がどの財産をどの割合で受け取るかを話し合いましょう。協議が成立した場合は、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
書面化することで、認識違いによるトラブルを防ぎやすくなります。
なお、遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印することで法的効力を持ちます。一人でも反対する相続人がいた場合、協議が成立しません。
不成立に終わった場合は、次のステップである家庭裁判所への遺産分割調停申し立てに進みます。
協議の際には不動産の評価額や預金の残高など具体的な資料をそろえ、公平性を保つことが大切です。
協議内容に合意できなければ遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議で全員の合意が得られなければ、家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てる必要があります。
調停は中立的な第三者を介した法的手続きであり、親族間の話し合いが行き詰まった場合の現実的な解決手段です。
家庭裁判所への調停申し立ては、以下の手順で進めます。
正しく手順を踏み、スムーズに申し立てが受理されるようにしましょう。
6-1.必要書類を準備する
遺産分割調停を申し立てるには、まずは必要書類を用意する必要があります。
以下は、調停の申し立てに必要な書類をまとめたものです。
| 相続のケース | 書類名 |
|---|---|
| すべての方が共通で用意する書類 | 申立書 |
| 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍でも可能) | |
| 相続人全員の戸籍謄本 | |
| 死亡した相続人の出生から死亡までの戸籍 | |
| 相続人全員の住民票(戸籍附票でも可) | |
| 遺産に関する証明書 | |
| 第二順位(父母・祖父母など直系尊属)が相続する場合 | 死亡している直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本(除籍・改製原戸籍でも可) |
| 第三順位(兄弟姉妹・甥姪など)が相続する場合 | 被相続人の死亡している父母・直系尊属・兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍でも可) |
| 被相続人が配偶者のみもしくは配偶者と同順位で兄弟姉妹・代襲者(甥姪)が相続する場合 | 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍でも可) |
| 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍でも可) | |
| 死亡している被相続人の兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍でも可) | |
| 死亡している甥姪の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍でも可) |
これらの書類に加え、調停の申し立てには、収入印紙1,200円分と郵便切手代がかかります。郵便切手代は家庭裁判所ごとに異なるため、各家庭裁判所のホームページで金額をご確認ください。
6-2.相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる(合意で決めた裁判所でも可)
必要書類をそろえたら、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。
原則として、相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが基本です。(参照:裁判所|遺産分割調停)
ただし相続人全員が合意すれば、別の家庭裁判所を選ぶことも可能です。
管轄を誤ると手続きが差し戻され、時間を浪費するため、事前に申し立て先はどこなのか確認しておきましょう。
家庭裁判所が申し立てを受理する
遺産分割調停の申立書と必要書類を提出すると、家庭裁判所は内容を審査し、受理の可否を判断します。
受理されてからの流れは、以下のとおりです。
どのような流れで受理されるのか確認しましょう。
7-1.家庭裁判所が調停委員・調停期日を決める
申し立てが受理されると、家庭裁判所は調停を担当する調停委員を選任し、初回の期日を決定します。
調停には裁判官だけでなく、法律に詳しい弁護士や家庭問題に精通した有識者など、2名以上の調停委員が関与します。(参照:日本調停協会連合会|裁判所の調停とは)
専門知識を持つ第三者が中立の立場で関わることで、感情的な対立を和らげ、公平な話し合いを進めやすくなります。
指定された日程に合わせて必要資料を整理し、円滑に調停を進められるよう準備を整えておきましょう。
7-2.家庭裁判所から調停期日通知書が届く(申し立てから約2週間後)
調停委員と期日が決定すると、当事者には「調停期日通知書」が送付されます。
調停期日通知書とは、調停に関する正式な案内で、申し立てからおおむね2週間程度で届くのが一般的です。
通知書には調停の日時や場所が明記されており、当日持参すべき書類や事前に準備すべき事項も示されています。
通知を受け取った時点で、必要な資料の確認や当日の流れの把握を進めておくと、調停当日に落ち着いて臨めるでしょう。
遺産分割調停で分割方法や取り分を話し合う
調停期日には相続人が家庭裁判所に集まり、調停委員を介して話し合いが行われます。調停委員は中立の立場で双方の意見を順番に聞き取り、感情的な衝突を避けながら議論を整理します。
通常、相続人が同じ部屋に入るのではなく、個別に呼ばれて意見を述べる「別席方式」で進められるのが一般的です。
調停では、不動産の評価額や預貯金の残高など客観的な資料を基に、公平な分割案を検討します。感情に流されるのではなく、数字や証拠をもとに話し合うことで、納得度の高い合意形成が期待できます。
遺産分割調停の内容に合意したら調停調書を作成する
調停で全員の合意が成立すると、家庭裁判所は「調停調書」を作成します。
調停調書は判決と同じ効力を持ち、法的な強制力が付与されます。そのため、合意後に約束が守られなくても、強制執行によって履行を確保できます。
調停調書は不動産登記や金融機関での相続手続きに利用できるため、合意内容を確実に反映させるための基盤となります。
後のトラブルを防ぐためにも、調書の記載内容を細部まで確認し、不明点はその場で解決しておくことが欠かせません。
遺産分割調停が不成立の場合は審判に自動的に移行する
調停で合意できなかった場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。
審判では家庭裁判所の裁判官が当事者の主張や提出資料を踏まえ、公平性の観点から一方的に分割方法を決定します。
調停とは異なり、合意を前提としないため必ずしも希望どおりの結果になるとは限りません。少しでも調停を有利に進めるには、審判に備えて早めに証拠や資料を整理しておくことが重要です。
時間や費用の負担はかかりますが、遺産分割を最終的に確定させる強制的な手段として機能します。
遺産分割調停が不成立になった場合の対応は、以下の記事でご確認ください。
審判に納得いかなければ即時抗告が可能(期限あり)
家庭裁判所の審判に不満がある場合は、高等裁判所に対して「即時抗告」という不服申し立てを実行できます。これは審判の内容を見直してもらう唯一の手段であり、審判に納得できない当事者にとって重要な救済方法です。
ただし、即時抗告には期限があり、審判の告知を受けた日から2週間以内に申し立てを行わなければ効力を失います。(参照:裁判所|即時抗告)
抗告が受理されれば高等裁判所で再度審理が行われますが、単に不満を述べるだけでは判断が覆ることはありません。判決を覆すには、第1審の不合理性を的確に指摘する必要があります。
十分な根拠や証拠を示さないと、即時抗告をしても認められない可能性が高いのが実情です。



審判に不服がある場合は、期限内に専門家の助力を得て抗告理由を整理し、説得力のある抗告理由書を作成することが必要です。
相続の遺産分割調停当日の流れ【7ステップ】
遺産分割調停がどのように進むのかわからず、不安を感じている方がいるのではないでしょうか。
ここでは、当日調停の流れを以下の7ステップに分けて紹介します。
当日の流れを押さえ、少しでも不安要素をなくした状態で調停に臨みましょう。
調停当日を慌ただしく迎えないためには、前日までに必要な書類や持ち物を整理しておくことが重要です。
調停の持ち物は、以下のとおりです。
- 調停期日通知書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 遺産の内容を証明する資料
遺産の内容を証明する資料には、不動産の登記事項証明書や固預貯金通帳の写し、残高証明書、株式や保険契約の資料などが該当します。
忘れ物があると当日の進行に支障をきたすため、前日までに書類をファイルにまとめ、印鑑や通知書と一緒にバッグに入れて準備しておきましょう。
当日は指定された時間までに家庭裁判所へ到着し、受付を済ませて待合室で呼び出しを待ちます。
調停は長時間に及ぶこともあるため、開始時間の少し前に到着して落ち着いた状態で臨むのが理想です。裁判所内は静粛が求められる環境なので、私語や携帯電話の使用は控えましょう。
待機中に緊張する人は多いですが、事前にまとめたメモで伝えたい要点を確認しておけば落ち着いて準備ができます。自分の意見を冷静に述べられるよう、心構えを整える大切な時間と捉えましょう。
調停が始まる前には、裁判所の担当者から手続きの流れや注意点について説明があります。
具体的には、調停は裁判のように判決を下す場ではなく、当事者同士が話し合いによって合意を目指す手続きである旨を説明されます。
説明を終えると、職員の案内に従って調停室に入室します。
調停室は裁判官と調停委員の席、申立人や相手方の席に分かれており、必要に応じて当事者が顔を合わせないよう配慮されています。
両者が同席するのではなく、申立人と相手先が交互に呼ばれ、自分の意見を述べる「別式方式」が一般的です。この形式により、感情的な衝突を避けつつ、冷静に話を進めやすくなります。
調停が始まると、申立人と相手方が交互に呼ばれ、調停委員から事情を聞かれます。
調停委員は双方の希望や主張を丁寧に確認し、相続財産の範囲や評価、分割方法の希望を把握していきます。
1回の調停にかかる時間は、2時間程度です。双方が同席して2時間かかるわけではなく、30分ずつ交互に聞き取りを行う形式が一般的です。
必要な資料やメモを手元に置いておくと、緊張せずにスムーズに答えられるでしょう。
その日の調停が終盤に差しかかると、調停委員が合意できた内容を整理し、当事者に確認します。
合意ができた部分は記録として残され、今後の基礎資料になります。残された争点については次回の期日で話し合う流れです。
たとえ完全に合意できなくても、一部合意を積み重ねることが次の解決につながります。
遺産分割調停は1回で終わることは少なく、複数回にわたるのが一般的です。次回期日でも申立人と相手方が交互に呼ばれ、調停委員へ意見を述べ、合意を探っていきます。
最終的に全員の合意が得られれば調停調書が作成され、法的効力をもって遺産分割が確定しますが、もし合意に至らなければ、手続きは審判に移行します。
しかし、まずは調停段階で柔軟な解決を目指すことが、当事者にとって負担の少ない方法です。



冷静に話し合い、一歩ずつ合意形成を目指しましょう。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
相続の遺産分割調停の期間はどれくらいかかる?
遺産分割調停は家庭裁判所を通じて相続人同士の意見を調整し、合意形成を目指す手続きです。
話し合いを重ねながら進めるため、申し立てから解決までには時間がかかり、想定より長期化する可能性があります。
ここでは、遺産分割調停のおおよその期間や長引くケースを解説します。
スケジュールの見通しを立て、調停に臨む準備を整えましょう。
遺産分割調停が終わるまでは半年~1年程度かかる
遺産分割調停は、1回あたり1〜2時間の期日を月1回ほどの頻度で進めます。そのため、解決までに半年から1年程度かかるのが一般的です。
令和6年度の司法統計によると、全国の家庭裁判所で扱われた遺産分割事件数は1万5,379件です。うち審理期間が6カ月以内だったケースは5,361件、1年以内が5,016件になっています。(参照:裁判所|令和6年司法統計年報 3家事編)
一方、2年以内に及んだ案件も3,575件あり、合意形成が難しい場合は長期化する傾向があります。
半年前後で解決できるケースもありますが、1年程度かかると見込んでおくと良いでしょう。
調停の期間が長引くケースとは
調停が長引く典型例は、相続財産の調査に時間を要する場合や、相続人間の意見が大きく食い違っている場合です
不動産の鑑定や未上場株式の評価といった専門家の関与が必要なケースでは、評価結果が出るまでに数カ月かかります。
さらに相続人が多いと日程調整が困難になり、期日が先延ばしになりがちです。また、一部の相続人が出頭しなかったり、必要資料を提出しなかったりする場合、調停の進行そのものが止まってしまう場合があります。



これらの要因が重なると、調停は数年単位に延びる可能性もあるため、各相続人が協力的に手続きを進める姿勢が重要です。
遺産分割調停の期間は、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:遺産分割調停の期間はどれくらい?平均回数や流れを徹底解説
相続の遺産分割調停を有利に進める5つのポイント
相続の遺産分割調停を有利に進めるには、以下の5つのポイントを意識しましょう。
不利な立場で調停が終わらないよう、有利に進めるポイントを確認しましょう。
感情的にならず冷静に主張する
遺産分割調停では、冷静に発言することが合意への近道です。感情をぶつけると議論が停滞し、親族間の関係が一層こじれる恐れがあります。
相続人同士は親族であるがゆえに、感情的な発言が火種となりやすいのです。たとえば「納得できない」「不公平だ」と強い言葉を口にすると、相手の反発を招き、対立が深まる場合があります。
調停は裁判と異なり、双方の合意を前提とする話し合いの場です。感情論ではなく、相続財産の範囲や希望する分割方法を整理し、事実に基づいた回答を心がけましょう。
調停委員が納得しやすい資料を提出する
調停で自分の主張を裏付けるには、客観的で信頼性の高い資料の提出が欠かせません。資料が不足していると「根拠が不明確」とされて、不利になってしまう可能性もあります。
不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書、金融資産であれば預貯金残高証明書や通帳のコピーなど、公的証明書が必須です。さらに、相続財産に関する契約書や領収書などを補足資料として添付すると、より説得力が増します。
事実を裏付ける資料がそろっていれば、調停委員は各主張の根拠を正確に把握でき、議論が具体的に進むでしょう。
虚偽の主張せず正直に事実を伝える
調停では、虚偽の主張はせず正直に事実を伝えましょう。
事実と異なる説明をした場合、その場では有利に思えても、提出資料や他の相続人の証言によって矛盾が明らかになります。とくに遺産を隠そうとする行為は、その場の状況はしのげても、後から不利な判断につながる恐れがあります。
調停は、感情的な対立を和らげ、当事者が納得できる解決策を探るための場です。正直に財産状況や希望を伝えれば、調停委員は客観的な判断を下しやすくなり、公平な分割案を提示できます。
合意形成を目指すためにも、事実は包み欠かさず話しましょう。
遺産隠しのリスクは、以下の記事をご覧ください。
関連記事:遺産隠しはバレる?時効についてや独り占めされている可能性がある際の相続財産調査のコツも解説
納得できなくても相手方の主張は一旦聞き入れる
相手の主張が納得できなくても、まずは一旦聞き入れましょう。納得できない意見に反論すると、議論がかみ合わず、合意形成から遠のいてしまう可能性があります。
相続人同士は親族関係にあるため、感情的になりやすく「相手の意見は間違っている」と思い込みがちです。相手方の発言にも一定の根拠がある場合が多く、発言の意図を理解することで妥協点や解決の糸口が見えてきます。
資料や事実をもとに冷静に反論すれば、調停委員にも理解してもらいやすくなり、自分の立場を正当に主張できるでしょう。
寄与分や特別受益など法律上の権利を適切に主張する
寄与分や特別受益の法律上の権利を行使できる場合は、調停の場でしっかりと主張しましょう。
寄与分・特別受益の内容や具体的なシーンは、以下のとおりです。
| 制度名 | 制度の内容 | 具体的なシーン |
|---|---|---|
| 寄与分 | 被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした相続人が、通常の相続分に加えて取り分を増やせる制度 | ・親の事業を長年無償で手伝った ・病気の親を数年間自宅で介護した ・仕事を辞めて被相続人の事業を何年も無償で手伝っていた |
| 特別受益 | 生前に多額の贈与を受けていた相続人の相続分をあらかじめ差し引く仕組み | ・生前に多額の住宅資金を援助してもらった ・結婚の際に多額の持参金を受け取った ・開業資金を援助してもらった |
相続の場で権利を主張しなければ、貢献度に見合わない不公平な分割方法になる可能性があります。
こうした権利を認めてもらうには、単なる主張では不十分であり、介護日誌や領収書、贈与契約書などの客観的な資料を示す必要があります。



証拠があれば調停委員も判断しやすく、妥当な解決案が提示されやすくなります。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停を弁護士なしで進めるのは難しい!依頼するメリット5つ
遺産分割調停は一見すると話し合いの場に思えますが、実際には法律の知識や手続きに関する正確な理解が欠かせません。専門的な判断が求められる場面も多く、個人だけで対応するには大きな負担がかかります。
遺産分割調停を申し立てる際は、手続きを円滑に進め、公平な遺産分割を実現するためにも弁護士に依頼しましょう。
依頼するメリットと、以下のようなメリットを得られます。
- 複雑な相続財産や権利関係を正確に整理できる
- 法的根拠を踏まえた主張で調停を有利に進められる
- 調停に必要な書類作成や手続きを一任できる
- 相続人同士の感情的な対立を緩和できる
- 調停不成立時の審判移行にもスムーズに対応できる



肉体的・精神的な疲弊を少なくするためにも、相続問題に強い弁護士に相談しましょう。
遺産分割調停を弁護士なしで進めると苦労する理由についてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。
【一覧】相続の遺産分割調停を弁護士に依頼する場合の費用
相続の遺産分割調停を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。費用の種類と相場を把握しておけば、依頼を検討する際の判断材料になります。
遺産分割調停にかかる弁護士費用の内訳は、以下のとおりです。
| 項目 | 費用相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 無料~30分5,000円程度 | 弁護士に初回相談や方針確認を行う際にかかる費用 |
| 着手金 | 20万円〜50万円程度 | 調停を正式に依頼するときに支払う費用(結果に関係なく発生する) |
| 成功報酬 | 弁護士の関与によって得られた経済的利益の10〜15% | 調停や審判で有利な結果が得られた場合に支払う報酬 |
| 実費 | 5万円~7万円程度 | 書類の取得費用や収入印紙、郵便切手代など、手続きに必要な経費 |
| 日当 | 3万円~10万円程度 | 調停や裁判所への出廷、遠方での対応など、弁護士が時間を割いて動いた場合に発生する費用 |
| 遺産調査費用 | 15万円~30万円程度 | 不動産や預貯金、株式など遺産の全容を調査するための費用 |
弁護士費用は事務所ごとに大きく異なり、相続財産の規模や争いの複雑さによって変動します。
たとえば、財産が複数の不動産や未上場株式を含む場合、調査費用や日当が高額になるケースがあります。成功報酬も「経済的利益」をどう定義するかで金額が変わるため、依頼前に見積もりを確認することが大切です。



初回相談を無料で受けられる事務所もあるため、複数の弁護士に相談して比較すると良いでしょう。
相続分野の弁護士費用は、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:相続の弁護士費用について解説
関連記事:遺産分割調停の費用について解説
相続時の遺産分割調停の流れに関するよくある質問
遺産分割調停を早く終わらせる方法はありますか?
遺産分割調停をできるだけ早く終わらせるには、入念な事前準備が欠かせません。
相続財産の内容や評価資料をあらかじめそろえ、主張を整理しておくと、調停委員が理解しやすく議論が進みやすくなります。
また、相手方の意見も一旦受け入れ、冷静に対応することで合意形成に近づきます。
ただし、数日で終わることはほとんどなく、実際には半年から1年程度かかるのが一般的です。
遺産分割調停に家族が同席してもよいですか?
遺産分割調停は「非公開の手続き」で行われるため、原則として当事者以外の人は期日に立ち会えません。(参照:大阪家庭裁判所 家事第3部 遺産分割係|~遺産分割調停に関するよくある質問~)
家族であっても同様で、基本的には調停室に同席することは認められていないのです。
ただし、当事者以外でも裁判所の許可を受けた場合などは立ち会いが可能です。体調不良や障がいなどで参加が難しい場合は、早めに家庭裁判所に申し出ましょう。
遺産分割調停で相手が嘘ばかりつくときはどう対応すべきですか?
調停で相手が虚偽の主張をした際に、感情的に反論するのは逆効果です。
預金通帳や残高証明書、不動産登記事項証明書、領収書などを準備し、調停委員へ冷静に事実を伝えましょう。
調停委員は提出された資料を基に判断するため、根拠を示すことで主張の信頼性を高められます。
相続の遺産分割調停で嘘ばかりつかれたときの対応は、以下の記事をご覧ください。
遺産分割調停の費用は誰が負担しますか?
遺産分割調停にかかる費用は、原則として申立人が負担します。
申し立てには、収入印紙1,200円分や郵便切手代、戸籍や証明書などの取得費用が必要です。これらに加えて、弁護士に依頼する場合は着手金や報酬などの費用が発生します。(参照:裁判所|遺産分割調停)
ただし、相続人同士が合意すれば分担も可能であり、調停成立後には実費部分を相続財産から精算できる場合もあります。
費用の取り扱いはケースによって異なるため、事前に家庭裁判所や弁護士に確認しておくことが大切です。
調停費用を誰が支払うのか気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:遺産相続の弁護士費用は誰が払うかを解説
遺産分割調停でやってはいけないことは何ですか?
遺産分割調停で避けるべきなのは、感情的な言動や虚偽の主張です。怒りに任せて発言したり相手を非難したりすると、調停委員に不利な印象を与え、合意形成が遠のく可能性があります。
また、財産を隠したり事実と異なることを述べると、証拠で矛盾が明らかになり信用を失ってしまいます。
さらに、調停に出席しない、資料を提出しないなどの不誠実な対応も進行を妨げ、かえって不利益を招く可能性も考えられるでしょう。
冷静さを保ち、相手の主張は一旦受け入れながら納得できる形での合意を目指しましょう。
遺産分割調停中にやってはいけないことは、以下の記事でも詳しく解説しています。
生前贈与があった相続人の取得財産を遺産分割調停で解決した事例
生前の金銭授受が争点となり、取得額を調整できたケースがあります。
“依頼人Bさんは、兄弟Cさんが生前に親Aさんから毎月数万円を受け取っていたことを遺産分割で考慮できないか悩んでいました。
Cさんは「介護費用だった」と主張していましたが、Aさんは施設に入所中で、実際に現金を使う必要もない状況でした。BさんはCさんとの関係も悪く、弊所にご相談。”
この事例の課題としては、
- 被相続人の生前贈与(特別受益)にあたるかどうか
- Cさんが贈与と主張する金銭が介護費用等の必要経費であったか
があげられます。
そこで
- Cさんが金銭を受け取っていたことについて、客観的な証拠をもとに「生前贈与」にあたるかを精査
- 裁判所において金銭の受領そのものが重視されるように法的に整理
というご対応をさせていただき、依頼人Bさんにとって有利な分割案が提示され、調停成立ができました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。
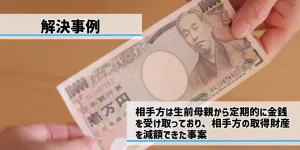
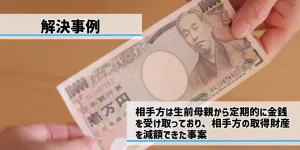
まとめ|相続時の遺産分割調停の流れを把握して円満解決を目指そう
遺産分割調停は、相続人同士の意見がまとまらない場合に家庭裁判所で解決を図る手続きです。申し立てから期日通知、調停委員との話し合い、合意に至れば調停調書の作成、不成立なら審判へ移行するという流れをたどります。
調停の期間は、半年から1年ほどかかるのが一般的で、資料準備や冷静な対応が解決を早める鍵になります。
調停を円滑に進めるには、法律や証拠に基づいた主張が不可欠です。弁護士に依頼することで、複雑な手続きや交渉を有利に進めやすくなります。
調停の流れを理解し、必要に応じて専門家の力を借りながら、納得のいく解決を目指しましょう。



遺産分割調停でお悩みの方は、7,000件以上の相談実績を持つ弁護士法人アクロピースへご相談ください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応