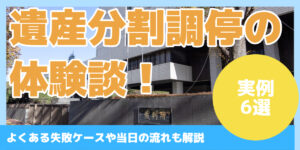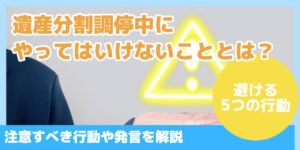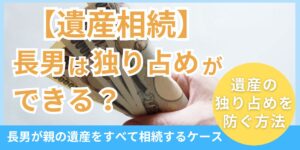【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停が不成立になったその後はどうなる?審判移行や強制執行についても解説【弁護士監修】
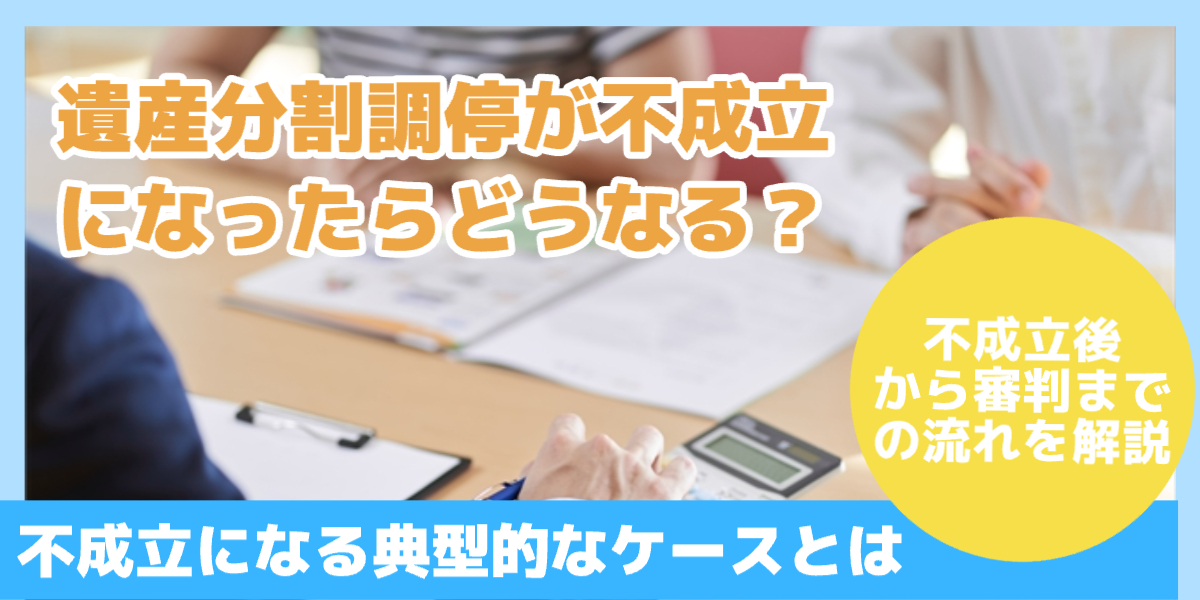
「調停が不成立になったらどうなるの?」
「裁判になったら不利にならないか不安…」
遺産分割調停が不成立になったとき、今後どうなるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
遺産分割調停が不成立になると、自動的に「審判手続」に移行します(家事事件手続法272条4項)。審判では、裁判官が法律や証拠に基づいて判断を下すため、主張の準備や証拠の整理が非常に重要です。
本記事では、調停が不成立になる典型的なケースや、審判に移行した後の流れ、準備すべき対策までをわかりやすく解説します。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産分割調停が不成立になる4つのケース
遺産分割調停が不成立になる典型的なケースは、下記の4つです。
該当しそうな点があれば、早めに対応を検討しましょう。
相手が調停に出席しない・呼び出しを無視する
相続人の一人が家庭裁判所からの呼び出しに応じず、調停に出席しない場合、手続きは進まず不成立となります。
調停は全員参加が前提のため、1人でも欠けると話し合い自体が成立しません。
家庭裁判所は、呼び出しを無視する相手に過料(行政罰)を科すことはできますが、強制的に出席させることはできません。
こうした非協力的な態度が続く場合は、審判への移行を視野に入れるべきです。不成立を見越して、弁護士に相談しながら次の準備を始めておくと安心です。
相続人が遺産分割協議に応じないケースについては、以下の記事でも解説しています。気になる方はあわせてお読みください。
関連記事:相続人の一人が遺産分割協議に応じない7つの理由と対処法!放置リスクも解説
話し合いを続けても合意に至らない
調停では、相続人同士が譲り合いながら合意を目指しますが、意見が対立したまま平行線をたどると不成立となります。
たとえば、以下のような状況では話し合いが進みません。
- 特定の財産を誰が取得するかで譲らない
- 「長男だから」「介護したから」と主張が強い
- 生前の贈与や預金の使い込みなどを巡って意見が対立する
- 相手の提案を一切受け入れず譲歩できない
調停委員が間に入っても解決が見込めないと判断されれば、遺産分割調停が不成立になる可能性があります。
遺産分割協議でもめたときの対処法は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:遺産相続でもめたら!もめた場合の対処法と遺産分割協議のスムーズな進め方
不動産や預金など分割対象で意見が対立している
主要な財産である不動産や預貯金の分け方をめぐって意見が食い違うと、調停がまとまりにくくなります。
とくに不動産は物理的に分割しにくく、代償金や売却などの提案にも反発があると合意は難航します。
また、以下のようなケースでは一層こじれやすくなります。
- 預貯金の引き出しを巡って疑念がある
- 財産の評価額について意見が割れる
- 財産の存在そのものが争点になっている(子供や孫の名義預金など)
話し合いで解決できなければ、調停は打ち切られ、不成立になる可能性があります。
不動産や預貯金の遺産分割方法については以下の記事も参考にしてください。
関連記事:不動産の遺産分割の4つの方法とは?遺産分割協議書についても解説
関連記事:遺産分割協議における預貯金の分け方、記載方法を弁護士が解説
調停中にしてはいけない行動を取ってしまった
調停の場で感情的な発言や攻撃的な態度を取ると、信頼関係が壊れ、話し合いが成立しにくくなります。
たとえば、以下のような言動は避けましょう。
- 他の相続人を責める・怒鳴る
- 嘲笑や威圧的な態度を取る
- 持ち時間を無視して話し続ける
こうした行動により合意を得るのは不可能と判断され調停が打ち切られ、審判へ移行するケースもあります。調停中は冷静な態度を保ち、発言内容にも注意しましょう。
関連記事:遺産分割協議がまとまらない!スムーズに解決するための方法とは
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこととは?注意すべき行動や発言を弁護士が解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産分割調停が不成立になったら審判に移行する|調停との違い
遺産分割調停が不成立になったら、自動的に審判に移行します。
審判が話し合い中心で解決を目指す一方、審判では、裁判官が法と証拠に基づいて判断します。
調停と審判の違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 調停(話し合い) | 審判(裁判所の判断) |
|---|---|---|
| 決定方法 | 相続人どうしの合意 | 裁判官が法と証拠に基づいて判断 |
| 証拠の必要性 | 重要だが必須ではない | 証拠の提出は極めて重要 |
| 柔軟な解決の可否 | 当事者間による自由で柔軟な内容の合意が可能 | 法定相続分その他の相続法の規定に沿った厳格な分割が基本 |
| 手続きの雰囲気 | 協議的で比較的穏やか | 法律に則って進行 |
| 結果の拘束力 | 全員が合意した場合のみ成立 | 裁判所の判断に拘束される |
| 費用 | 審判に移行する場合に比べて追加着手金や出廷日当が少なくなる分費用が抑えられることがある。 | 出廷回数や書面対応が増えるため、その分の追加費用が発生する。 着手金や報酬の加算が行われる場合もある。 |
遺産分割の審判については、以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:
遺産分割調停での相続の流れは?申し立ての方法や有利な進め方も紹介
相続の調停を申し立てられたらどうする?対応方法や注意点を解説
遺産分割調停が不成立になってから審判までの流れ
審判では裁判官が法に基づいて遺産の分け方を決定するため、調停とは進め方が大きく異なります。
以下では、審判手続きの一般的な流れを5ステップで解説します。
調停が不成立になると「審判」に自動移行する
調停が成立せず家庭裁判所が「話し合いでは解決できない」と判断し不成立とされると、自動的に審判手続きに移ります。あらためて申し立てを行う必要はありません。
審判では、裁判官が法的根拠に基づき分割内容を決定します。調停で出した資料や主張はそのまま引き継がれます。
(協議不調時の分割)民法 第907条
出典:民法 第907条(e-Gov 法令検索)
遺産の分割について協議が調わないとき、または協議できないときは、家庭裁判所が分割の方法を定めることができる。
令和6年の司法統計によれば、全国で15,379件あった遺産分割事件数に対し、調停成立率は約44%、審判がなされた割合は約8%%ですから、審判への移行は珍しいとはいえません。
家庭裁判所から審判期日の通知が届く
審判開始後、家庭裁判所から「呼出状(よびだしじょう)」が届きます。そこには第1回の審判期日の日時・場所が記載されています。
記載された日時には、必ず出席する必要があります。欠席すると、一方的に不利な判断が下される可能性があるため、注意しましょう。
審判に向けた書類・証拠の準備をする
審判では、自身の主張を裏づける証拠や資料を裁判所に提出する必要があります。具体的には、次のような書類を準備するとよいでしょう。
- 遺産の一覧表や財産の評価資料
- 生前贈与や特別受益に関する証拠
- 遺産分割に関する希望をまとめた書面 など
主張が曖昧なままだと不利になる可能性があるため、準備は入念に行いましょう。
審判に出席して主張・証拠を提示し判断を待つ
審判当日は、裁判所に出頭し、主張を述べたり証拠を提出したりする必要があります。
審理は1回で終わるとは限らず、複数回にわたることが一般的です。裁判所の統計によると、調停から審判まで1年以上かかる事案は約33%にのぼります。(出典:令和6年司法統計年報家事編)
審判の基本的な流れは以下のとおりです。
- 第1回審理:裁判所へ出頭し、主張を陳述
- 証拠提出:書類や資料で立場を補強
- 調査・審問:裁判官による事実確認や質問
- 複数回審理:月1回程度の頻度で継続実施
- 審判告知:判決内容を文書で受け取る
精神的・時間的負担が大きいため、早めに弁護士に相談し、準備や同席を依頼しておきましょう。
弁護士法人アクロピースは、相続トラブルの実績が豊富にあります。無料相談も可能なので、問い合わせフォームもしくは、公式LINEから気軽にお問い合わせください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
相手が審判結果に従わない場合は「強制執行を申し立てる」
遺産分割の審判が確定しても、相手が代償金を支払わない、不動産を明け渡さないといったケースがあります。
こうした義務の不履行に対しては、裁判所を通じた「強制執行」を申し立てることで、法的に対応できます。
たとえば以下のような執行手段があります。
- 代償金の支払いを拒否された場合:預貯金や給与の差し押さえ
- 不動産の明け渡しに応じない場合:強制的な退去の執行
(債務名義)民事執行法 第22条
出典:民事執行法 第22条(e-Gov 法令検索)
強制執行は、確定判決・審判・和解調書・調停調書などの債務名義に基づいて行う。遺産分割審判や調停調書も執行の根拠となる。
強制執行は専門的な知識と慎重な準備が必要な手続きです。少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
関連記事:遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説
遺産分割調停が不成立にならないための5つの対策
遺産分割調停が不成立にならないためには、事前に以下5つのような対策を講じておくことをおすすめします。
本章を参考に、遺産分割調停がスムーズに進むための準備をしておきましょう。
相続人全員と事前に話し合っておく
遺産分割の調停を円滑に進めるためには、相続人同士で事前に話し合いの場を持っておくことが大切です。
調停の場で初めて主張をぶつけ合うと、感情的な対立に発展しやすく、不成立に至るリスクが高まります。
以下のような点を事前に話し合っておくことで、認識のズレを解消しやすくなります。
- 特定の財産を誰が取得するか
- 生前の援助について不満がないか
- 今後の手続きにどう関わるかの意向確認
難しい内容であっても、メールや手紙で意向を伝えるだけでも意味があります。話しにくいことこそ先に共有しておくことで、調停時のトラブルを減らし、合意への道筋が見えてくるでしょう。
関連記事:遺産相続の話し合いを拒否されたときの対処法と弁護士に相談すべきケースを解説
関連記事:相続の遺産分割調停で嘘ばかりつかれたらどうする?不利にならない対処法を弁護士が解説
遺産の内容を正確に把握・整理しておく
遺産の全体像を明らかにすることは、調停をスムーズに進めるうえで欠かせません。財産の内容が不明確だと、相続人間での不信感や対立を招きやすくなります。
整理すべき主な項目は以下の通りです。
| 財産の種類 | 内容例 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 銀行口座、ゆうちょ口座など | 金融機関名と残高 |
| 不動産 | 自宅、賃貸物件、土地など | 評価額、所在地など |
| 有価証券 | 株式、投資信託など | 銘柄、保有数など |
| 借入金 | 住宅ローン、借金など | 借入先・残債額など |
一覧にまとめて相続人全員で共有することで、「何をどう分けるか」の議論がしやすくなりますし、そもそもこれを明らかにしないままでは正しい遺産分割ができません。
遺産の調べ方については以下でも解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:親の財産の調べ方は生前と死後で異なる?相続の流れを図で表しながら解説
生前贈与や特別受益について確認しておく
特定の相続人が生前に多額の支援を受けていた場合、その内容を他の相続人と共有しておかないと、不公平感から調停がこじれる原因になります。
特別受益に該当する例は以下のようなケースです。
- 親から住宅購入資金を援助された
- 結婚や留学に際して多額の援助を受けた
- 一人だけ学費を全額負担してもらった
こうした支援は「相続分の前渡し」とみなされる可能性があるため、金額や時期を明確にしておきましょう。先に情報を開示しておくことで、無用な疑念を避けやすくなります。
特別受益については以下でも解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:特別受益とは?代表的な贈与のパターンや持ち直しの計算方法、免除を分かりやすく解説
(特別受益)民法 第903条
出典:民法 第903条(e-Gov 法令検索)
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けた者があるときは、その利益は相続分の算定に際し持戻しの対象となる(※要旨)。
第三者(税理士・不動産業者など)の評価を入れる
不動産や自社株など、評価が分かれやすい財産が含まれている場合は、第三者の専門家による評価を取り入れるとよいでしょう。

当事者同士の認識や主張が食い違っていると、調停の合意は難しくなります。
たとえば、財産の種類ごとに以下のような専門家に評価を依頼すると、トラブルを回避しやすくなります。
| 財産の種類 | 評価を依頼すべき専門家 |
|---|---|
| 不動産 | 不動産鑑定士、宅建士 |
| 事業用資産 | 税理士、公認会計士 |
| 上場株・有価証券 | 証券会社の取引価格を参考 |
専門的かつ中立的な意見を挟むことで、感情ではなく事実に基づいた話し合いができるようになるでしょう。弁護士に依頼しておけば、弁護士がたくさんの財産の評価を取りまとめて行うことができます。
弁護士に早めに相談しておく
調停を円滑に進めたいなら、早い段階で弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
相続に関するルールを正確に理解し、調停に必要な準備を整えるためには、専門家のサポートが欠かせません。
弁護士に相談することで得られる主なメリットは以下の通りです。
- 自分の主張や立場を明確にできる
- 調停に必要な資料を事前に準備できる
- 相手側の主張にどう反論すべきかがわかる
- 法的に不利にならない判断ができる
「争いが起きてから」ではなく、「争いを防ぐため」にこそ、専門家を味方につけましょう。
遺産分割調停を弁護士に依頼するメリットは以下の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:遺産分割調停は弁護士なしで可能かどうかについて解説
解決事例:遺留分侵害額請求の調停を得て解決した弊所事例
遺産分割の調停を弁護士依頼するときのポイント
遺産分割調停や審判には、法律知識だけでなく交渉力や戦略立案も求められます。そこで重要になるのが、信頼できる弁護士のサポートです。
以下の5つのポイントを押さえて弁護士を選ぶことで、納得のいく解決につながりやすくなります。
「どの弁護士に頼むべきか」で迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
遺産トラブルの対応実績が豊富か
弁護士を選ぶ際は、相続トラブルの対応実績がどれだけあるかを最優先で確認しましょう。
相続分野は法律・税務・不動産の知識が複雑に絡み合うため、未経験者では対応が難しい場面も多くあります。
具体的には、以下の情報をチェックしておきましょう。
- 公式サイトに掲載された解決事例
- 過去の対応件数や得意分野
- 顧客からの感謝の声・実績紹介
実績が豊富な弁護士なら、複雑な案件でも的確に対応してくれる可能性が高まります。
調停・審判への対応力が高いか
調停では冷静な交渉力、審判では法的主張の構成力が求められます。これらに不慣れな弁護士では、判断が不利になることもあります。
以下の点を事前に確認しましょう。
- 「調停」「審判」対応の経験や方針が明記されているか
- 初回相談時に戦略や見通しを丁寧に説明してくれるか
- 強引な提案をせず、納得のいく形で進められるか
調停や審判を有利に進めるためにも、対応力の弁護士を見極めましょう。
費用・報酬の説明が明確か
弁護士費用は事務所によって体系が異なり、内訳も複雑です。予想外の請求にならないためにも、費用の内訳は事前にしっかり確認しましょう。
確認すべきポイントは以下のとおりです。
| チェック項目 | 確認すべき内容の例 |
|---|---|
| 対応範囲 | 調停のみか、審判まで含むか |
| 着手金・報酬 | 固定額か成果連動型か |
| 追加費用 | 審判移行時などに発生するか |
費用説明が丁寧な弁護士は、信頼性も高い傾向があります。安心して依頼できる弁護士かどうか見極めましょう。
関連記事:遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用は?
関連記事:遺産分割調停の費用はいくら?不動産鑑定にかかる費用や誰が払うのかも解説
相談しやすい人柄と信頼感があるか
相続問題は感情的な対立を含みやすいため、相談しやすく、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。
話しにくいと感じる相手では、納得のいく解決につながりにくくなります。
初回相談時は、以下の点をチェックしておきましょう。
- 専門用語をかみくだいて説明してくれるか
- 質問しやすい雰囲気があるか
- 真摯に話を聞き、立場を理解してくれるか
相性や信頼感は「この人と一緒に進めたい」と思えるかどうかで判断しましょう。
口コミや評判での満足度が高いか
弁護士選びで迷ったときは、実際に依頼した人の口コミや評判を参考にするのも有効です。経験者の評価は、対応力や誠実さを知る手がかりになります。
確認先の例は以下のとおりです。
- 公式サイトの「お客様の声」
- 法律相談ポータルや口コミサイト
- Googleマップなどのレビュー
ただし、口コミは主観的な側面もあるため、複数の評価を比較しながら総合的に判断することが大切です。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
遺産分割調停の不成立に関するよくある質問
遺産分割調停を取り下げられたらどうすればいい?
ご自身で調停を申し立て直す必要があります。
調停が取り下げられた場合には、遺産分割審判には移行しません。
ですから、調停が取り下げられたまま放置すると、遺産分割はいつまで経っても終わらなくなってしまいます。
引き続き調停や審判での解決を望むなら、ご自身が申立人となって、改めて家庭裁判所に調停を申し立てましょう。



不安があれば、弁護士に相談するのが安心です。
審判結果に不服がある場合、自分で即時抗告できる?
即時抗告は、自分で手続きを進めることも可能です。
審判書を受け取った翌日から2週間以内に、家庭裁判所へ「抗告状」を提出する必要があります。
ただし、即時抗告が認められるためには、家庭裁判所の判断に法的な誤りがあることを、証拠に基づいて主張しなければなりません。
高等裁判所での審理は、法律論や証拠の評価が中心となるため、専門知識がなければ適切な対応は難しいのが実情です。



手続きを正確に進め、納得のいく結果を目指すなら、弁護士のサポートを受けることを検討しましょう。
(即時抗告の期間)家事事件手続法 第95条
出典:家事事件手続法 第95条(e-Gov 法令検索)
即時抗告は、裁判書の送達を受けた日から2週間以内にしなければならない。
遺産分割調停で時間稼ぎをされている場合はどうしたらよい?
調停が長引くと感じたら、早めに原因を整理し、対応を見直すことが大切です。
相手との主張が平行線をたどり、合意が難しい場合には、審判への移行も視野に入れるべきでしょう。
ただし、やみくもに手続きを進めるのではなく、なぜ調停が進まないのかを見極める必要があります。
たとえば、ご自身の主張に法的な根拠が乏しい、あるいは相手の意見をまったく受け入れない姿勢であれば、話し合いが進まないのも当然です。



冷静に状況を分析し、建設的な方向性を探るためにも、遺産分割に詳しい弁護士に相談し、客観的なアドバイスを受けることをおすすめします。
まとめ
調停が不成立になると、手続きは自動的に審判に移行し、裁判官の判断により強制的に遺産が分割されます。
不利にならないためには、主張の整理や証拠の準備が重要です。
審判がなされた後に、強制執行や即時抗告が必要になることもあるため、早めに相続に強い弁護士へ相談し、納得のいく解決を目指しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応