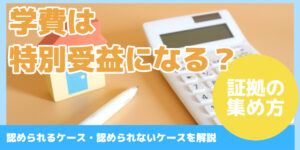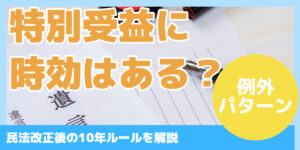【無料相談受付中】24時間365日対応
【弁護士監修】生前贈与は特別受益になる?認められるケースや持ち戻しの計算方法を解説
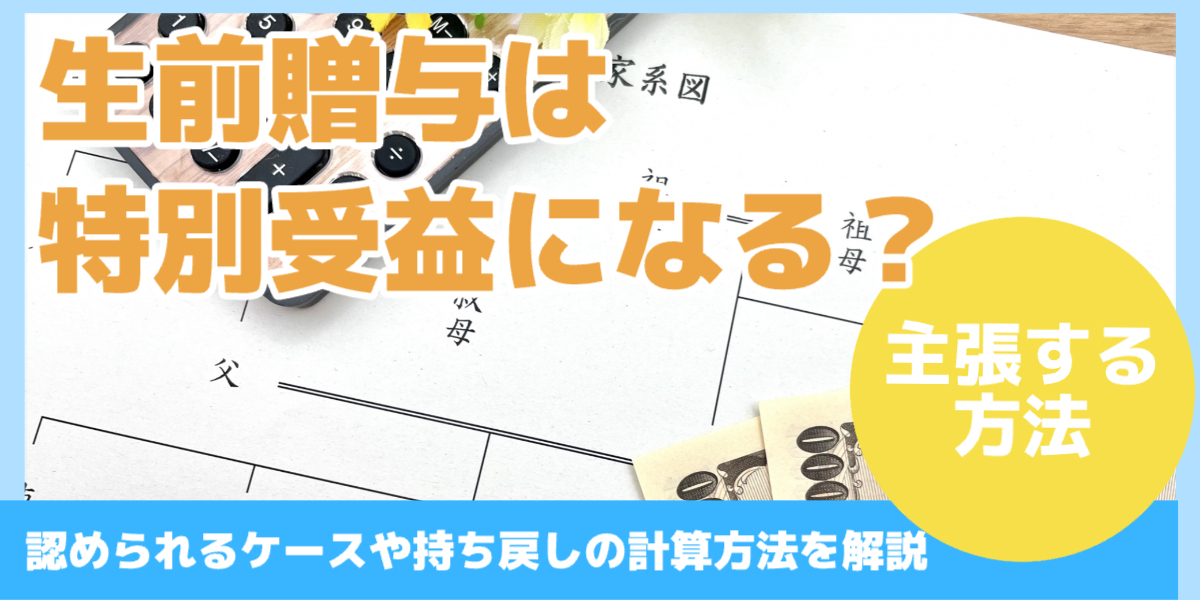
「兄だけ親から多額の援助を受けていたけど、私の相続分は増えないの?」
「一部の相続人の生前贈与が特別受益になる場合、どのように対処すればいい?」
相続は、単なる財産の問題ではなく、家族の歴史や感情が深く関わるデリケートな問題です。特に生前贈与は不公平を感じやすくトラブルに発展しやすいため、悩みを抱える人は多いのではないでしょうか。
この記事では、相続において重要な制度である「特別受益」と、その中心的な論点となる「生前贈与」の関係について、専門家の視点から深く掘り下げて解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫生前贈与が相続に与える影響を正確に理解し、自身の適切な権利を守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
特別受益と生前贈与との違い・関係性
相続の話し合いにおいて「特別受益」という言葉を耳にすることがあるでしょう。これは、相続人間の公平を図るための法的な仕組みであり、特に生前贈与があった場合に重要な意味を持ちます。
まずは、この制度の基本的な考え方を理解することが大切です。
特別受益とは|相続人間の不公平をなくすための制度
特別受益とは、複数の相続人の中で、特定の相続人だけが被相続人(亡くなった方)から受け取った特別な利益のことです。法律は、このような特別な利益を「遺産の前渡し」と捉えます。
例えば、子どもが2人いるケースで、兄だけが生前に住宅購入資金として1,000万円の援助を受けていたとします。この事実を考慮せずに残りの遺産を半分ずつ分けると、弟は「兄だけが多く財産をもらっていて不公平だ」と感じるでしょう。
特別受益制度は、このような相続人間の不公平感を解消し、実質的な公平を実現するために設けられています。
重要な点として、この制度が対象とするのは原則として「相続人」に限られます。相続人ではない孫や親族への贈与は、通常、特別受益にはあたりません。
出典:e-Gov法令検索|民法
関連記事:特別受益とは?持ち戻しの計算方法や特別受益として扱われる贈与のパターンを分かりやすく解説
すべての生前贈与が特別受益になるわけではない
すべての生前贈与が特別受益と判断されるわけではありません。法律は、日常的な親子間の援助と、遺産の前渡しと評価されるべき特別な援助とを区別しています。
生前贈与が特別受益と認められるのは、民法で定められた「婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた」場合のみです。
民法第903条
同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
出典:e-Gov法令検索|民法
この基準の背景には、その贈与を受け取った相続人の経済的基盤を形成する上で、どれだけ大きな影響を与えたかという視点があります。
例えば、少額のお祝い金は生活を大きく変えませんが、事業の開業資金や住宅の購入資金は、その後の人生における経済的なスタートラインを大きく左右します。
法律では、特別受益に該当するか判断するためには、経済的な影響が大きいかどうか、客観的に判断することになります。
特別受益と「通常の贈与」の違い
相続における「特別受益」と「通常の贈与」は、どちらも被相続人から生前に財産を受け取る点では同じですが、全く異なる意味を持ちます。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた「遺産の前渡し」と評価される生前贈与のことです。具体的には、以下のように他の相続人と比べて著しく多額で、生活の基盤を作るための援助が該当します。
- マイホームの購入資金
- 事業の開業資金
- 高額な学費(例:私立大学医学部の学費)
一方、通常の贈与とは、社会通念上、遺産の前渡しとは考えられない贈与を指します。例えば、以下のようなものが挙げられます。
- お祝い金
- お年玉
- 生活費の範囲内での仕送り
- 一般的な金額の学費援助
これらは扶養義務の範囲内と判断されることが多く、特別受益とはみなされず、遺産分割の際に持ち戻しの対象とはなりません。
「他の相続人との間に不公平が生じるほどの、特別な援助であったか」という点が、両者を見分けるポイントです。金額の大小だけでなく、被相続人の資産状況や社会的地位、他の相続人とのバランスなどを総合的に考慮して行われます。
関連記事:学費は特別受益になる?認められるケース・認められないケースを判例付きで解説【弁護士監修】
【具体例】特別受益と判断される生前贈与のケース
ここからは、どのような生前贈与が特別受益にあたるのか、具体的なケースを紹介します。特別受益と判断される生前贈与の主なケースは、以下のとおりです。
それぞれの特徴について、詳しく解説します。
生計の資本となる贈与(住宅購入資金・事業資金など)
「生計の資本」とは、独立して生計を立てるための基礎となる財産を意味します。これに該当する贈与は、特別受益の典型例です。
具体的には、住宅を購入するための資金援助や事業を始めるための開業資金の提供、会社の株式の贈与などが挙げられます。
これらの贈与は、受け取った相続人に対して、他の相続人にはない強固な経済的基盤を与えるため、遺産の前渡しと評価されやすいでしょう。
婚姻・養子縁組のための贈与(持参金・支度金など)
結婚や養子縁組に際して親が子に渡す財産も、特別受益に該当する場合があります。
具体的な例としては、嫁入り道具としての持参金や、新生活を始めるための支度金がこれにあたります。
ただし、現代においては、一般的な金額の結納金や挙式費用そのものは親の社会的儀礼として行われる側面が強く、子の独立した生計の資本とはいえないケースも少なくありません。
贈与の金額や目的、地域の慣習などを総合的に考慮して判断されます。
関連記事:遺贈は特別受益になる?該当するケースを弁護士が解説


高等教育の費用(私立大学の医学部・海外留学など)
学費は、特別受益にあたるかどうかの判断が難しい分野の一つです。すべての高等教育費が特別受益になるわけではありません。
裁判例などから見えてくる判断基準は画一的なものではなく、「その家族にとっての標準」がどこにあるかという点です。具体的には、以下の要素が総合的に考慮されます。
| 被相続人の資産状況や社会的地位 | 裕福な家庭で、子ども全員が私立大学に進学するのが当たり前という環境であれば、それは扶養の範囲内とみなされやすいです。 一方、親が経済的に無理をして特定の子だけを学費の高い大学に行かせた場合は、特別受益と判断される可能性が高まります。 |
|---|---|
| 他の相続人との比較 | 一人の子だけが数千万円かかる私立大学医学部に進学し、他の子は高卒で就職している場合、その著しい差額は特別受益と認められやすくなります。 |
このように、「〇〇大学の学費は特別受益」と具体的に決めているわけではありません。各家庭の状況を個別に見て、その援助が扶養の範囲を超えた「特別な利益」であったかを判断します。
土地や建物の無償利用(使用貸借)
親が所有する土地や建物に、子どもの一人が無償で長期間住んでいるケースも、経済的な利益を受けているとして特別受益に該当する可能性があります。これは「使用貸借」と呼ばれ、家賃相当額の利益を得ていると評価されるためです。
ただし、この場合の利益の評価額は、単純な賃料合計ではありません。
「使用貸借権」の価値として評価され、実務上は相続開始時点での更地価格の1割から3割程度とされることが多くなっています。つまり、使用貸借権の負担がついた土地は、更地価格の7〜9割程度に下がる点には注意が必要です。



見過ごされがちですが、土地や建物の無償利用も立派な特別受益となり得ることを覚えておきましょう。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
特別受益のトラブルが起こりやすい典型的な場面
相続人の中に、被相続人から生前に特別な援助を受けていた人がいると、「特別受益」として相続トラブルに発展することが少なくありません。しかし、何が特別受益にあたるのか、その評価をどうするかで揉めやすいのも事実です。
ここでは、特にトラブルになりやすい典型的な3つの場面を見ていきましょう。
住宅購入資金や開業資金の援助を受けた相続人がいる
相続人の一人が、被相続人からマイホームの購入資金や事業を始めるための開業資金といった多額の生前贈与を受けているケースは、トラブルになりやすい典型的な状況です。
住宅購入資金や開業資金の援助は、遺産の前渡しとみなされ、特別受益に該当します。遺産分割の際には、この援助額を遺産に足し戻して(持ち戻し)、各相続人の取得分を計算し直す必要があります。
他の相続人からすれば、自分はもらっていないのに不公平だと感じるのは当然です。そのため、この持ち戻しをめぐって、金額の評価や認識の違いから揉めることは少なくありません。
特定の相続人だけ高額な学費や留学費用の援助を受けている
被相続人の資産や社会的地位から見て、通常の扶養の範囲を超えるような高額な教育費は特別受益と判断されることがあります。
たとえば、兄弟の中で一人だけ私立大学の医学部に進学したり、海外の大学院へ留学したりした際の多額の費用がこれにあたります。
他の相続人が同等の援助を受けていない場合、その差額が遺産の前渡しと評価されるのが一般的です。ただし、どこからが特別受益にあたるかの線引きは難しく、相続人間の感情的な対立を生みやすい点が特徴です。
特定の相続人が受取人になっている生命保険金がある
特定の相続人が受取人に指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象外です。
しかし、保険金の額が遺産総額に対して著しく高額で、これを受け取った相続人と他の相続人との間に看過できないほどの不公平が生じる場合には、例外的に特別受益に準ずるものとして扱われることがあります。
この判断はケースバイケースであり、相続財産のほとんどが保険金であるといった極端なケースで問題となりやすいです。
特別受益に該当しない生前贈与のケース
一方で、親子間の金銭のやり取りであっても、特別受益とは見なされないケースも多く存在します。どのような場合に特別受益に該当しないのかを理解することは、無用な争いを避けるために重要です。
特別受益に該当しない生前贈与は、主に以下のとおりです。
以下、それぞれの特徴を具体的に解説します。
扶養義務の範囲内と判断される学費や生活費の援助
親には、子を扶養する義務(扶養義務)があります。この義務の履行として行われる支出は、特別な利益とはみなされません。
具体的には、未成年の子に対する生活費の仕送りや、義務教育や高校までの学費、病気の際の医療費などが該当します。
大学の学費についても、その家庭の資産や社会的地位から見て、親が子に高等教育を受けさせることが扶養の一環と認められる場合は、特別受益にはあたりません。
生命保険金や死亡退職金(原則)
被相続人の死亡によって相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金は、原則として特別受益には該当しません(最高裁判所 昭和40年2月2日判決)。これらの金銭は被相続人の遺産ではなく、保険契約や会社の規程に基づいて受取人が直接受け取る「受取人固有の財産」と考えられるためです。
しかし、保険金の額が遺産の総額に対して大きく、「著しく不公平」な結果となる場合は、例外的に特別受益に準じて扱われるケースも少なからず存在します(最高裁判所 平成16年10月29日判決)。
厳格な法形式を貫くことでかえって不公平が生じる場合に、裁判所が実質的な公平性を確保しようとする姿勢の表れといえるでしょう。
出典:裁判所|最高裁判所 昭和40年2月2日判決
出典:裁判所|最高裁判所 平成16年10月29日判決
少額のお祝い金やお小遣い
誕生日や入学・卒業、結婚などのお祝い金、あるいは日常的なお小遣いなど、社会通念上相当と認められる範囲の少額な贈与は、特別受益にはあたりません。
これらは遺産の前渡しという性格を持つものではなく、家族間の愛情表現や儀礼的な贈答の範囲内と解釈されるためです。
特別受益を相続分に反映させる「持ち戻し」とは
特別受益があると認められた場合、その利益を遺産分割に反映させるために「持ち戻し」が行われます。
持ち戻しとは、相続が開始した時点(被相続人が亡くなった時点)の遺産に、生前贈与などによる特別受益の価額を加えて、計算上の相続財産(みなし相続財産)を算出する手続きです。
これは、特別受益を「遺産の前渡し」と捉え、一度遺産全体を元の状態に戻してから、改めて全員の取り分を計算し直すという考え方に基づいています。
ここで注意すべき重要な点は、持ち戻しをする財産の評価時期です。不動産や株式など価値が変動する財産の場合、贈与された時点ではなく「相続が開始した時点」の時価で評価されます。
現金の贈与の場合は、贈与時から相続開始時までの物価変動を考慮して、貨幣価値を換算するのが原則です。
特別受益の「持ち戻し免除の意思表示」とは?
本来は公平性を確保するために、特別受益を遺産に持ち戻して計算しますが、被相続人が「この贈与は持ち戻さなくてよい」と意思を示すことが可能です。
これを「持ち戻し免除の意思表示」と呼びます。
持ち戻し免除の意思は、遺産分割の際に大きな影響を与える重要なポイントです。以下、具体的に解説します。
「持ち戻し免除の意思表示」があった場合に起こり得ること
被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていた場合、その特別受益は遺産に合算されません。
たとえば、生前に一人の子どもへ住宅購入資金を贈与していても、遺言などで「その分は持ち戻す必要がない」と書かれていれば、他の相続人との遺産分割に加算せず、そのまま受け取ることになります。
相続財産の総額が減った状態で分割が進むため、相続人間の取り分に影響が出ます。したがって、持ち戻し免除の有無は、相続配分の公平性や遺族間の調整を左右する大切な要素といえるでしょう。
関連記事:特別受益の持ち戻し免除とは?認められるケースや注意点を弁護士が解説
20年以上連れ添った配偶者への居住用不動産の贈与は「持ち戻し免除の意思表示」になる
2019年の民法改正により、新しいルールが設けられました。婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産を生前贈与または遺贈した場合、被相続人はその贈与について「持ち戻しを免除する意思表示」をしたものと推定されます(民法第903条4項)。
これは通称「おしどり贈与」の特例とも呼ばれています。高齢化社会が進む中で、残された配偶者が住み慣れた家を失うことなく、安定した生活を送れるようにすることが主な目的です。
この規定により、原則として自宅の贈与は遺産分割の計算から除外され、配偶者は他の財産についても法定相続分を確保しやすくなりました。
出典:e-Gov法令検索|民法
【計算例付き】特別受益の持ち戻し計算方法を3ステップで解説
特別受益の持ち戻し計算は一見複雑に思えますが、3つのステップに沿って進めれば理解しやすくなります。以下の状況を仮定して、具体的な事例で見ていきましょう。
- 被相続人:父
- 相続人:長男と次男の2人
- 相続開始時の遺産:6,000万円
- 長男への特別受益:生前に住宅購入資金として2,000万円の贈与があった
- 次男への特別受益:なし
ステップ1:相続財産に生前贈与の価額を加算する(みなし相続財産)
まず、相続開始時の遺産に、特別受益の価額を足し戻して「みなし相続財産」を算出します。
計算式
6,000万円(相続財産)+ 2,000万円(長男の特別受益)= 8,000万円(みなし相続財産)
この8,000万円が、遺産分割の計算の基礎となります。
ステップ2:法定相続分を計算する
次に、ステップ1で算出したみなし相続財産を基に、各相続人の法定相続分に従って、一応の相続分を計算します。
計算式(相続人が子2人の場合、法定相続分は各1/2)
- 長男の一応の相続分:8,000万円 × 1/2 = 4,000万円
- 次男の一応の相続分:8,000万円 × 1/2 = 4,000万円
ステップ3:特別受益を受けた相続人の取得分から贈与額を差し引く
最後に、特別受益を受けた相続人(特別受益者)の「一応の相続分」から、すでに受け取った特別受益の額を差し引きます。
これが、その相続人が最終的に取得する具体的な相続分です。
計算式
- 長男の具体的相続分:4,000万円− 2,000万円(特別受益)= 2,000万円
- 次男の具体的相続分:4,000万円− 0円 = 4,000万円
結果として、長男は残りの遺産から2,000万円、次男は4,000万円を相続することになり、生前贈与を考慮した公平な分割が実現されます。
なお、もし特別受益の額が一応の相続分を上回る場合、その相続人は遺産を取得できませんが、超過分を他の相続人に返還する必要はありません。
「持ち戻し免除の意思表示」があっても遺留分は請求できる可能性がある
被相続人は遺言などで「この贈与は特別受益として持ち戻さなくてよい」という意思(持ち戻し免除の意思表示)を示せます。この意思表示は、遺産分割の場面では有効です。
しかし、この意思表示で遺留分の権利を侵害することはできません。つまり、持ち戻し免除の意思表示があったとしても、相続開始前10年以内の特別受益であれば、遺留分を計算する際には財産に加算されます。
被相続人が自由に財産を処分する意思は尊重されるべきですが、親族の生活を保障するという遺留分制度の趣旨が優先されることは覚えておきましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
生前贈与を特別受益として主張する方法
特定の相続人が特別受益を受けているのではないかと感じた場合、どのように主張すればよいのでしょうか。感情的に対立するのではなく、法的な手続きに沿って冷静に進めることが重要です。
以下、生前贈与を特別受益として主張する方法を具体的に解説します。
ステップ1:特別受益を裏付ける証拠を収集する
特別受益の存在を主張する側には、その事実を証明する責任(立証責任)があります。口頭での主張だけでは、相手方が認めない限り実現することは困難です。
有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 金銭の贈与:銀行の振込履歴・預金通帳の写し・被相続人の日記やメモ・メールのやり取りなど
- 不動産の贈与:不動産の登記事項証明書・贈与契約書
- 学費の援助:学費の領収書・振込記録
- 事業資金の援助:会社の登記簿・開業資金の送金記録
客観的な証拠をどれだけ集められるかが、その後の交渉や手続きを有利に進めるための鍵となります。証拠の集め方やどのような証拠を集めるべきかがわからない場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
関連記事:特別受益は証拠がないと認められない?証拠の探し方と立証の流れを弁護士が解説
ステップ2:遺産分割協議で特別受益を主張・交渉する
証拠を整理した上で、まずは相続人全員で行う話し合い(遺産分割協議)の場で特別受益の存在を主張します。
この段階で、収集した証拠を提示し、持ち戻し計算を適用した遺産分割案を提案します。
相続人全員が納得すれば合意書を作成し、円満に解決することが可能です。
ステップ3:話がまとまらなければ遺産分割調停・審判を申し立てる
遺産分割協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
調停では、裁判官や調停委員という中立的な第三者が間に入り、双方の主張を聞きながら、話し合いによる解決を目指します。
調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判の手続きに移行します。審判では、相続人が提出した証拠などに基づいて、裁判官が遺産の分割方法を法的に決定します。
審判で特別受益を認めてもらうためには、客観的で説得力のある証拠が不可欠です。
生前贈与・特別受益のトラブルを弁護士に相談すべき理由
生前贈与や特別受益に関する問題は、法律的な知識だけでなく、感情的な対立も絡むため、当事者だけで解決するのは非常に困難です。
専門家である弁護士に相談することには、以下のような大きなメリットがあります。
ここからは、それぞれのメリットについて具体的に解説します。
関連記事:特別受益の主張は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用を解説【弁護士監修】
特別受益の主張に必要な証拠収集のアドバイスがもらえる
何が法的に有効な証拠となるのか、どうやって入手すればよいのか、一般の方には判断が難しいことが多いです。
弁護士に依頼すると、事案に応じてどのような証拠が必要かを的確に判断し、収集方法について具体的なアドバイスを提供してくれます。
また、弁護士会照会制度など、弁護士でなければ利用できない調査手段を用いて、金融機関などから情報を取得することも可能です。
感情的な対立を避け、代理人として冷静に交渉してくれる
親族間の争いは、感情的になりがちです。また、一度関係性が悪くなると修復が困難になります。
弁護士が代理人として間に入ることで、当事者同士が直接対峙するのを避けることが可能です。
法的な論点に絞って冷静に交渉を進めてくれるため、感情的な対立を緩和し、建設的な解決を目指すことが可能になります。
調停や審判に移行した場合もスムーズに対応できる
家庭裁判所での手続きは、申立書の作成から証拠の提出、期日での主張まで、専門的な知識と経験が求められます。
弁護士に依頼すれば、これらの複雑な手続きをすべて任せられ、依頼者の精神的・時間的な負担を大幅に軽減することが可能です。
法廷で説得力のある主張を展開し、依頼者にとって最善の結果が得られるよう尽力してくれるでしょう。



無料相談を実施している弁護士であれば、初期費用を抑えることが可能です。まずは一度相談してみることをおすすめします。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
生前贈与と特別受益に関するよくある質問
ここでは、生前贈与と特別受益に関して、特によく寄せられる質問にお答えします。
孫への生前贈与は特別受益の持ち戻し対象になる?
原則として、孫への生前贈与は特別受益の持ち戻し対象にはなりません。特別受益は「相続人」に対する贈与が対象であり、親が健在である場合、孫は相続人ではないためです。
ただし、例外もあります。例えば、親(相続人)が子(孫)に対する扶養義務を十分に果たしておらず、祖父母が代わりに孫の学費を支払ったような場合です。実質的には親(相続人)への贈与と同視できるとして、特別受益と判断される可能性があります。
また、親が先に亡くなって孫が代わって相続人(代襲相続人)になった場合も例外です。孫自身が相続人として受けた贈与や、亡くなった親が受けていた贈与は、特別受益として考慮されることになります。
特別受益を証明する証拠がない場合はどうすればよい?
特別受益を主張する側がその存在を証明しなければならないため、証拠がない場合は厳しい状況といえます。主張が認められる可能性は低くなるでしょう。
しかし、独断で諦める前に弁護士に相談することが大切です。直接的な証拠がなくても、状況証拠を積み重ねることで主張が認められるケースもあります。
例えば、被相続人の口座から多額の現金が引き出された時期と、特定の相続人が不動産や車などの高額な買い物をした時期が一致する場合などです。関連性を示すことで、贈与の事実を推認できます。
特別受益の持ち戻しに時効はある?
特別受益の「持ち戻し(相続分の計算に含めること)」自体に時効はありません。相続開始から何年経っていても、特別受益として持ち戻し計算の対象にすることは可能です。
ただ、2023年(令和5年)の民法改正で、「遺産分割協議」については相続開始から10年を経過すると、特別受益の主張自体ができなくなり、持ち戻しでの調整ができなくなることが定められました。
つまり、「相続開始から10年以内」に遺産分割調停等を申し立てていれば持ち戻しの主張は可能ですが、そうでない場合は時効と同様に主張できなくなります。
相続の時効について不明点がある場合は、早めに相続に詳しい専門家(弁護士など)に相談して確認することが重要です。
まとめ|公平な遺産分割のために生前贈与と特別受益の正しい知識を身につけよう
この記事では、生前贈与が特別受益として相続にどう影響するのかを解説しました。
特別受益は、特定の相続人が受けた特別な利益を「遺産の前渡し」と考え、相続人間の公平を図るための制度です。すべての生前贈与が特別受益になるわけではなく、「生計の資本」となるような経済的インパクトの大きい贈与が対象となります。
もし、自身の相続において不公平を感じたり、特別受益に該当するかもしれない贈与があったりする場合は、決して一人で抱え込まないでください。



まずは事実関係を整理し、自身の権利を適切に理解することから始めましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応