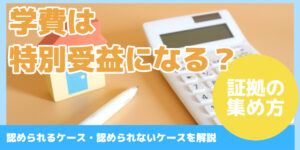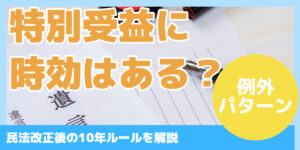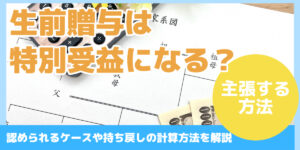【無料相談受付中】24時間365日対応
特別受益の主張は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用を解説【弁護士監修】

「特別受益を主張したいが、弁護士に相談すべき?」
「特別受益の主張を弁護士に依頼したら費用はどのくらいかかる?」
他の相続人の特別受益を主張したいときに、このように悩む方は多いのではないでしょうか。
特別受益を受けている相続人がいる場合、遺産分割は複雑になりやすく、公平な解決に向けて専門的な判断が求められます。
弁護士に依頼することで、相続人同士の対立を抑えながら公平な分割案を提示でき、話し合いをスムーズに進めやすくなるのがメリットです。
本記事では、特別受益を弁護士に依頼するメリットや相談すべき理由を詳しく解説します。
特別受益の自己判断は失敗のもと:生活援助か特別受益かの境界線は曖昧で、法的な判断が極めて難しい。自己判断で特別受益を主張するのは言いがかりとされ、泥沼化するリスクが高い。
証拠収集の決定的な差:個人の調査には限界があるが、弁護士は弁護士会照会等の権限で金融機関へ開示請求が可能。客観的証拠がなければ裁判所は認めないため、プロの介入が不可欠。
特別受益の10年の壁に注意:2023年の法改正により、相続開始から10年経過すると特別受益の持ち戻し主張ができなくなった。悠長に構えていると、正当な権利でも時効のように消滅する。
弁護士依頼の費用対効果:弁護士費用(着手金20~50万円+成功報酬)はかかるが、数百万円単位の増額が見込めるなら依頼メリットは大きい。費用倒れを防ぐためにも、初回相談での見積もりが重要。
精神的負担の軽減:代理人を立てる最大の利点は、感情的な親族との直接交渉を避けられること。ストレスを最小限に抑えつつ、調停・審判を見据えた有利な解決を目指せる。
弁護士の選び方や依頼費用も紹介しているため、特別受益の問題を解決して公平な遺産分割を行いたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
特別受益とは?弁護士に依頼する前に知っておきたい基礎知識
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前に受け取った贈与や遺贈を指します。
一部の相続人だけが多額の援助を受けている場合、そのまま遺産分割を行うと不公平が生じかねません。そのため、民法ではこれらの利益を相続財産に持ち戻して計算する仕組みが設けられています。
ただし、すべての贈与が対象になるわけではなく、特別受益として認められるには主に以下の要件を満たす必要があります。(参照:裁判所|Q14 特別受益とは何ですか?)
- 受贈者が法定相続人であること(孫や相続人の配偶者への援助は、原則として対象外)
- 生活の基盤となる援助であること(扶養の範囲を超える、まとまった資産の移動が要件)
具体的にどのようなケースが特別受益にあたるのか、判断の目安を以下の表に整理しました。金額の多寡だけでなく、贈与の目的や時期なども総合的に考慮される点に留意が必要です。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 特別受益にあたる(資産の前渡し) | ・結婚資金や結納金 ・住宅購入資金、ローン返済 ・事業の開業資金 ・高額な留学費用 |
| 特別受益にあたらない(扶養・儀礼の範囲) | ・義務教育の学費 ・日常的な生活費や仕送り ・少額の祝金や見舞金 |
証拠が揃っていても、金額が少額であったり贈与の目的が曖昧だったりする場合、特別受益と認められないケースも考えられます。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫法的な判断が難しい場合は、自己判断せずに専門的な知識を持つ弁護士へ相談することをおすすめします。
関連記事:
【弁護士監修】生前贈与は特別受益になる?認められるケースや持ち戻しの計算方法を解説
特別受益の主張を弁護士に依頼すべき4つの理由
特別受益の主張は、法的な要件を満たしているかどうかの判断が難しく、当事者間だけで進めると深刻な対立を招く恐れがあります。公平な遺産分割を実現し、手続きを円滑に進めるためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士に依頼することで得られる主なメリットとして、以下の4点が挙げられます。
特別受益にあたるかを法的に正確に判断できる
特別受益に該当するか否かの判断は、一見明確なように見えても、実際には複雑な法的検討を要します。例えば、以下のような金銭の移動があったとしても、直ちに特別受益と認められるわけではありません。
- 住宅購入資金の援助
- 留学費用の負担
- 結婚資金の提供
金額の多寡だけでなく、当時の被相続人の資産状況や生活水準など、諸般の事情を考慮して法的性質が決定されます。
具体的には、贈与の目的が「生計の資本」か「扶養の一環」かによって、以下のように結論が分かれる可能性があります。
| 判断のポイント | 法的な評価の傾向 |
|---|---|
| 生計の資本としての贈与(生活の基盤づくり) | 遺産の前渡しとみなされ、特別受益にあたる可能性がある |
| 扶養義務の範囲内(扶養の一環) | 親族間の扶養義務の履行とされ、特別受益にあたらない可能性がある |
このように、生計の資本としての贈与といえるかどうかは、個別の事情に応じた詳細な事実認定が必要です。弁護士であれば、過去の裁判例や法的基準に照らし、ご自身のケースが主張として成り立つかを正確に見極められるでしょう。
関連記事:遺贈は特別受益になる?該当するケースを弁護士が解説
弁護士会照会等で強力に証拠収集ができる
特別受益を裁判所に認めてもらうには、単に「援助を受けたはずだ」という主観的な説明だけでは足りません。 主張を裏付けるためには、以下のような客観的かつ信用性の高い資料を揃える必要があります。
- 銀行の取引履歴や預金通帳
- 贈与契約書や領収書
- 当時の状況を知る関係者の陳述書
しかし、個人ではどの資料が法的に有効な証拠となるかの選別が難しく、また金融機関が開示に応じないケースも珍しくありません。 弁護士に依頼すれば、膨大な資料の中から立証に必要なものを選別し、法的な主張として構成することが可能です。
また、ご自身での収集が困難な場合でも、「弁護士会照会(23条照会)」という制度を利用して金融機関等へ情報開示を求められます。 確実な証拠を収集・整理することで、調停や審判において説得力のある主張を展開できるようになるでしょう。
持ち戻し免除の主張に対する適切な反論ができる
被相続人が生前に持ち戻し免除の意思表示をしていた場合、民法第903条第3項に基づき、その贈与を相続財産に含めない取り扱いがなされます。
しかし、この免除の意思表示が有効に成立しているかどうかは、実務上争いになりやすいポイントの一つです。具体的には、以下のような点が主な争点として挙げられます。
- 免除の意思表示をした客観的な証拠(遺言書等)が存在するか
- 遺言書などの記載内容が、法的に免除の意思と認められるか
- 意思表示をした当時、被相続人に判断能力があったか
なお、2019年の相続法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与については、持ち戻し免除の意思表示が推定されます(民法第903条第4項)。ただし、この推定も反証により覆すことが可能です。
一見すると有効な免除があるように見えても、形式や内容に不備があれば、その効力を否定できる余地があります。
弁護士が介入することで、遺言書の有効性や文言の解釈を法的に精査し、相手方の主張に対する反論の構築が可能です。 適切な反論を行うことで、不当に相続分を減らされる事態を防ぎ、正当な権利を守ることにつながります。
感情的な対立を防ぎ、調停・審判を有利に進められる
特別受益の有無は各相続人の取得額に直結するため、当事者同士の話し合いは極めて感情的になりやすい傾向があります。過去の金銭授受をめぐる不満が噴出し、家族関係に修復不可能な亀裂が入ってしまうことも少なくありません。
弁護士を代理人に立てることで、当事者同士が直接対峙する必要がなくなり、以下のようなメリットが期待できます。
| 項目 | 具体的なメリット |
|---|---|
| 交渉の代行 | 相手方と直接顔を合わせる必要がなく、冷静さを保てる |
| 議論の整理 | 感情論を排し、法的な争点に絞った客観的な議論が可能になる |
| 負担の軽減 | 交渉の矢面に立つ精神的ストレスから解放される |
このように、弁護士が間に入ることで冷静な議論が可能となり、解決までのプロセスが円滑化します。仮に話し合いがまとまらず遺産分割調停や審判へ移行した場合でも、煩雑な申立手続や法的主張を一任することが可能です。



精神的な負担を最小限に抑えつつ、調停委員や裁判官に対して説得力のある主張を行い、有利な解決を目指せるでしょう。
関連記事:相続の遺産分割調停とは?流れや有利な進め方を弁護士が紹介
特別受益の主張にかかる弁護士費用の相場・内訳
特別受益の主張を弁護士に依頼する際、どのような名目で費用が発生するのかを把握しておくことは、資金計画を立てる上で非常に重要です。
弁護士費用は、依頼する事務所や案件の難易度によって異なりますが、一般的には以下の5つの項目で構成されています。
法律相談料|無料~30分5,000円程度
正式に依頼する前の段階で、事案の概要を話し、法的なアドバイスを受けるために支払う費用です。 多くの法律事務所では、30分5,000円(税抜)程度を相場としていますが、相続問題に関しては初回相談を無料とする事務所も増えています。
相談の場では、契約の有無にかかわらず以下の点について専門的な見解を確認可能です。
- 自身のケースが特別受益として主張可能か
- 解決までにかかる期間や費用の概算
- 想定されるリスクや相手方の反論
「そもそも主張が認められるかわからない」という段階でも、相談を通じて今後の見通しがクリアになるでしょう。 まずは無料相談などを活用し、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。
着手金|20万円~50万円程度(案件によって変動)
着手金は、弁護士との委任契約締結時に支払う費用のことで、結果の成否にかかわらず発生します。相場は20万円~50万円程度ですが、請求する金額(経済的利益)や事案の複雑さに応じて変動するのが一般的です。
具体的な金額は、日本弁護士連合会の旧報酬基準を参考に設定されることが多く、以下の要素によって増減します。
| 変動の要因 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 請求額の規模 | 特別受益として主張する金額が大きいほど高額になる傾向がある |
| 事案の難易度 | 証拠収集が困難な場合や、争点が多岐にわたる場合は加算される |
生前贈与の金額が数千万円に及ぶようなケースでは、詳細な調査や計算が必要となるため、着手金が高めに設定される可能性があります。依頼前に見積書を作成してもらい、内訳について十分な説明を受けるようにしましょう。
成功報酬|経済的利益の10%~15%程度
成功報酬は、遺産分割協議や調停が成立し、依頼者が実際に利益を獲得した際に支払う費用です。弁護士の介入によって確保できた金額(経済的利益)を基準に算出され、相場は10%~15%程度とされています。
獲得金額に応じた報酬額のイメージは以下のとおりです。
| 獲得した遺産額(経済的利益) | 成功報酬の目安(10%の場合) |
|---|---|
| 500万円 | 50万円 |
| 1,000万円 | 100万円 |
| 2,000万円 | 200万円 |
たとえば、当初の提示額よりも増額できた場合、その増額分だけでなく「最終的に取得した遺産総額」を基準にするケースが一般的です。
報酬の計算方法は事務所によって異なるため、契約書の内容をよく確認しておく必要があります。
実費|5万円~7万円程度
実費は、弁護士の作業に対する報酬ではなく、手続きを進めるうえで実際にかかる経費のことです。 一般的な相場は5万円~7万円程度ですが、複数の金融機関に対して取引履歴の開示請求を行う場合などは、数万円単位で費用が上乗せされる可能性があります。
特別受益の主張において発生する主な実費は以下のとおりです。
- 裁判所への申立手数料(収入印紙代)
- 予納郵券(裁判所からの連絡用切手代)
- 戸籍謄本や登記事項証明書の取得費用
- 弁護士会照会の手数料
通常は着手金とは別に、概算額を預かり金として事前に支払うケースが多く見られます。 実費の残額は、事件終了後に精算されて返金されるのが通例です。
日当|移動距離や拘束時間によって金額が変動
日当は、弁護士が事務所を離れて活動する際に、その拘束時間や移動距離に応じて支払われる手当です。特に、遠方の家庭裁判所へ出廷する場合や、現地調査などを行う際に発生します。
拘束時間に応じた日当の一般的な目安は、以下の表のとおりです。
| 拘束時間(移動含む) | 日当の目安 |
|---|---|
| 半日(2~4時間程度) | 3万円~5万円 |
| 一日(4時間以上) | 5万円~10万円 |
近隣の裁判所での手続きであれば日当が発生しない事務所もありますが、特別受益の争いは調停期日が複数回に及ぶことも少なくありません。



出廷のたびに費用がかさむ可能性があるため、日当の有無や計算基準については事前に確認しておくと安心です。
特別受益を主張するために必要な証拠
特別受益を主張するには、贈与や援助があったと示す証拠をそろえる必要があります。代表的な証拠は、以下の通りです。
| 特別受益の主張に必要な証拠 | 詳細 |
|---|---|
| 振り込み記録・通帳の写し | 被相続人から相続人への資金援助があった事実を示す資料 |
| 領収書・契約書 | 住宅購入費や事業資金として援助された内容を裏付ける書面 |
| 借金の完済証明書 | 被相続人の借金を肩代わりしたことを証明できる資料 |
| クレジットカードの取引明細 | 被相続人の生活費をカードで支払った事実を示す記録 |
| 贈与契約書・公正証書 | 生前贈与の意思を明確に示す書面 |
| 不動産登記簿謄本 | 土地や建物の贈与があったことを証明する書類 |
| メッセージ履歴 | メールやLINEで援助の趣旨や金額についてやり取りした記録 |
これらの証拠をそろえることで、単なる扶養や一時的な援助ではなく「特別受益」にあたる行為だったことを客観的に立証しやすくなります。



特に契約書や登記簿のような客観的資料は重視されるため、早めに収集・整理しておくことが望ましいです。
関連記事:特別受益は証拠がないと認められない?証拠の探し方と立証の流れを弁護士が解説
特別受益の主張で失敗する典型ケース
特別受益の主張は、十分な準備なしに行うと認められないばかりか、親族間の亀裂を深める原因となりかねません。法的な見通しが甘かったために失敗してしまうケースとして、以下の3つのパターンが多く見られます。
- 証拠不十分による泥沼化(客観的資料がなく「言いがかりだ」と反発され、協議が停滞する)
- 扶養の範囲内との判断(援助額が常識の範囲内とされ、特別受益に該当しないと判断される)
- 期間制限による権利消滅(特別受益の10年制限や遺留分侵害額請求権の期間制限を知らず、請求権を失う)
なお、特別受益の主張には法的な期限があります。それぞれの期間制限は以下のとおりです。
| 項目 | 期間制限 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 特別受益や寄与分 | 相続開始の時から10年 ※10年経過前に家庭裁判所に遺産分割請求をした場合など、例外的に主張が可能なケースあり | 民法904条の3 |
| 遺留分侵害額請求権 | 消滅時効:相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年 ※意思表示や訴訟提起による時効の中断・更新が可能 除斥期間:相続開始の時から10年 ※期間経過により自動的に権利が消滅し、途中で停止できない | 民法1048条 |
ご自身のケースが該当するかどうかを早期に弁護士へ相談し、正確な見通しを立てることが重要です。
関連記事:特別受益に時効はある?民法改正後の10年ルールを弁護士が解説
特別受益の主張を弁護士に依頼して公平な遺産分割につながった事例
当事務所の弁護士が関わることで、特別受益の主張を行い、公平な遺産分割につながった事例をご紹介します。
| 依頼者 | Bさん |
|---|---|
| 相手(他の相続人) | 兄弟のCさん |
| 被相続人 | Aさん |
| 相続財産 | 預貯金その他 |
| 遺言 | なし |
| 相談内容 | 兄弟のCさんが「介護費用として受け取った」と主張している金銭は、特別受益に該当しないのか |
| 詳細 | 兄弟Cさんが被相続人Aさんから毎月数万円を受け取っており、依頼者Bさんは遺産分割で考慮すべきだと考えていた。Cさんは「介護費用だった」と主張したが、Aさんは施設入所中で実際に現金を使う必要はなかったので「贈与なのでは?」と疑問を抱いて弁護士に相談 |
| 弁護士が行った対応と時系列 | Cさんに遺産分割協議を呼びかけ、Cさんの言い分を伺った。 しかし、Cさんは、被相続人Aさんから定期的に金銭を受け取っていたことは認めるものの、Bさんと意見が異なり、双方の意見が平行線をたどったことから、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた。 介護費用として金銭を受け取っていたことを裏付ける証拠がなかったため、調停では金銭の受領の事実が重視された。 結果として、調停委員から依頼者Bさんが有利になるような分割案が提示され、兄弟のCさんも納得し無事に調停が成立した。 |
この事例では、被相続人の支出目的を証拠に基づいて整理し、法的に主張を組み立てたことが決め手となりました。
当初は感情的な対立が強かったものの、調停という第三者を交えた場で冷静に話し合いが進みました。結果として、Bさんは疑問を解消しつつ、公平な形で遺産分割を進められる道筋を得られたのです。
このように、弁護士に依頼することで複雑な特別受益の問題も整理しやすくなります。



特別受益の扱いで迷うときは、早めに弁護士へ相談しましょう。
解決事例:生前母親から定期的に金銭を受け取っていた相手方の取得財産を減額できた事案
特別受益の主張を依頼する弁護士の選び方【チェックリスト】
特別受益の主張は、相続分野の中でも判断や証拠の整理が難しい場面が多いため、弁護士選びが解決の大きなカギとなります。専門性や経験の有無を意識して選ぶことで、公平な遺産分割につなげやすくなります。
弁護士を選ぶときは、以下の点を重視しましょう。
- 相続分野を専門としているか
- 特別受益の案件に関する解決実績があるか
- 持ち戻し免除など複雑な事例にも対応できるか
- 特別受益の証拠収集や主張整理を具体的にサポートしてくれるか
- 初回相談で費用や見通しを丁寧に説明してくれるか
たとえば、兄弟の一方が親から結婚資金としてまとまった金額を受け取っていたケースでは、「特別受益に含めるべきか」「慣習的な祝い金にとどまるのか」で判断が分かれることがあります。
相続を専門に扱う弁護士に依頼すれば、過去の判例をもとに判断し、調停や裁判に発展した際にも的確に主張を整理してもらえます。
特別受益を主張する弁護士を選ぶ際は、専門性と実績に加え、依頼者の立場に寄り添ってくれるかどうかを見極めることが大切です。



まずは無料相談を利用して、自分に合った弁護士を探してみましょう。
特別受益を主張する際の流れ
特別受益を主張するには、段階を踏んで手続きを進めることが重要です。具体的な流れは以下の通りです。
- 特別受益の事実を裏付ける証拠を収集する
- 遺産分割協議で主張する
- 話し合いで解決できなければ家庭裁判所に調停を申し立てる
- 調停でも決着がつかない場合は審判へ進む
まず行うべきは、特別受益があったことを裏付ける証拠の収集です。贈与契約書や通帳の出入金記録、不動産の登記事項証明書など、具体的な証拠をそろえることで説得力が増します。
証拠を確保したら、遺産分割協議で特別受益の有無について主張し、相続人同士の話し合いで合意を目指します。
意見が対立して話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停に移行する流れです。それでも解決に至らなければ、裁判所が判断を下す審判手続きに移行します。(参照:裁判所|遺産分割調停)



自己判断で進めると不利になりかねないため、主張してからの流れを理解して弁護士に相談しながら適切にステップを踏みましょう。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
特別受益の弁護士依頼についてよくある質問
特別受益はどこまでさかのぼって主張できますか?
特別受益の持ち戻しには、時効がありません。過去に受けた贈与が何十年前であっても、遺産分割の対象に含めて計算することが可能です。
ただし、実際に主張できる期間は制限されており、相続が始まってから10年以内に申し立てなければなりません。このルールは2023年4月の民法改正で導入されたルールです。(参照:民法|第1044条3項)
なお、相続開始から10年以内に家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てていれば、この制限は適用されません。
主張を考えている場合は、証拠の確保とあわせて早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
特別受益の証拠が見つからない場合はどうすればいいですか?
調査をしても証拠が見つからない場合は、特別受益の主張が認められない可能性が高くなります。
特別受益の主張には証拠が欠かせません。通帳の出入金記録や振込履歴、メールや手書きのメモなど、金銭や財産の授受を裏付ける資料が証拠になります。
遺産分割協議で相続人同士が話し合って円満に分割できるなら良いですが、主張に反論された場合は何らかの形で証拠集めをしなければなりません。
弁護士なら金融機関や関係先に対して開示請求を行える場合もあり、自力では難しい調査も進められる可能性があります。早めに相談し、どのように対応すべきか検討しましょう。
遺産分割協議が10年以内に成立しなかった場合はどうなりますか?
遺産分割協議そのものには期限がないため、10年を過ぎても協議を行うことは可能です。
しかし、相続開始から10年を超えると「特別受益の持ち戻し」は主張できなくなる点には注意しましょう。
その場合、遺産は特別受益を考慮せず、原則は法定相続分に基づいて分けることになります。
持ち戻しを主張する権利を失う前に、早めに弁護士に相談して遺産分割を進めることが大切です。
生前贈与の特別受益の持ち戻し期間は?
生前贈与の持ち戻し期間には、時効がありません。
ただし、前述のとおり主張できる期間は10年と決められているため、権利を失う前に弁護士と連携しながら手続きを進めましょう。
特別受益の持ち戻し期間は、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
まとめ|特別受益に関する争いは弁護士相談で公平な解決を目指そう
特別受益を得た相続人がいる場合、どの贈与が対象になるのか、持ち戻しが必要かの判断が難しくなります。
自己判断で証拠集めや手続きを進めると、相続人同士の意見が食い違う可能性があるため、弁護士に相談して冷静な話し合いを進めましょう。
また、自分一人で手続きを進めた場合、十分な証拠を揃えられず不利な結果につながる可能性もあります。



協議や調停、裁判で有利に立ち、公平な遺産分割を行うためにも早めに弁護士に相談しましょう。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応