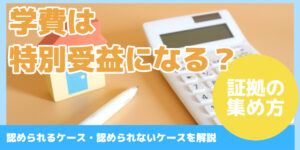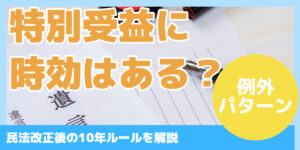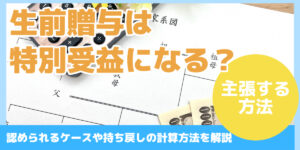【無料相談受付中】24時間365日対応
特別受益は証拠がないと認められない?証拠の探し方と立証の流れを弁護士が解説
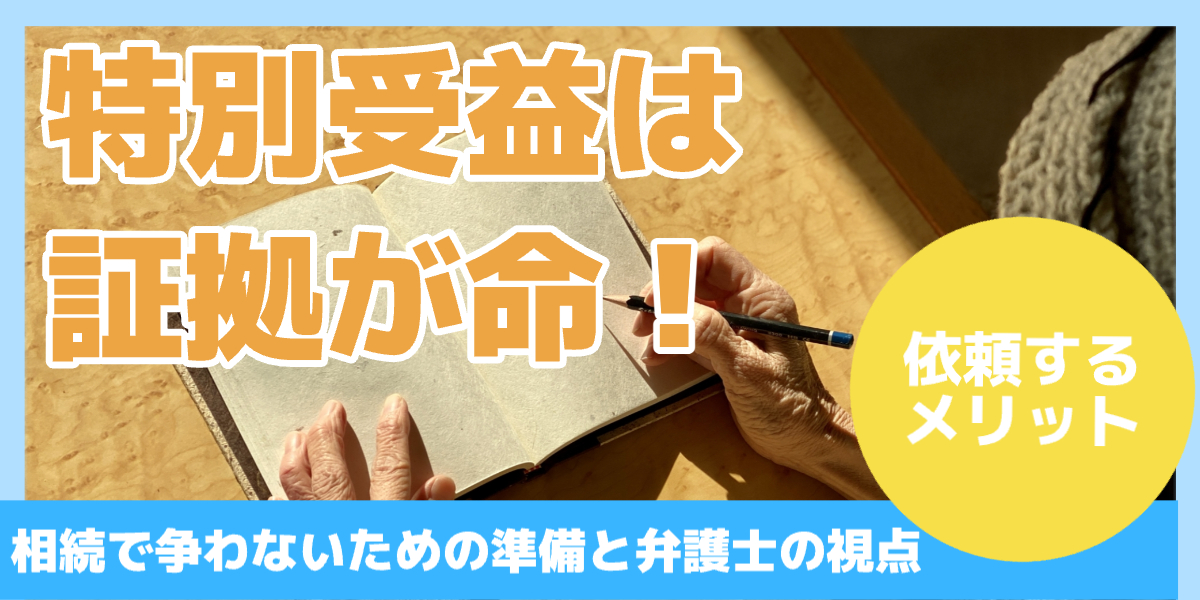
「特別受益を主張したけれど証拠がないとダメ?」
「特別受益の証拠がないと、遺産分割調停や審判で不利になってしまう?」
遺産分割で、他の相続人の特別受益を主張したくても、証拠が見つからず悩んでいませんか。
特別受益は証拠がなければ認められず、相続分の調整ができなくなるケースも珍しくありません。
さらに証拠集めには時間がかかり、古い贈与ほど資料が残っていないことが多いため、早期の行動が重要です。
本記事では、特別受益の基礎知識から財産別の証拠例、効率的な探し方、弁護士に依頼するメリットを解説しています。
特別受益の証拠集めに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
特別受益とは生前にもらう相続分の前渡しのこと
特別受益とは、特別受益とは、特定の相続人が被相続人から贈与や遺贈を受けたときの利益をいいます。
特別受益の仕組みを理解しておくと、証拠の重要性や交渉の方向性も見えてくるでしょう。
特別受益の定義
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から贈与や遺贈を受けたときの利益を言い、特別受益がある場合には、その分を相続分から差し引いて調整が図られます(民法第903条1項)。
特別受益の対象となるのは、遺贈の他にも、婚姻又は養子縁組のための贈与や生計の資本となる贈与です。
特別受益がある場合には、一度相続財産に戻し、相続分を計算し直す「持ち戻し」という調整を行います。特別受益の持ち戻しは、全相続人間に公平な遺産を分配するためになされます。
そのため、どのような援助や贈与が特別受益に該当するのかを正確に理解しておくことが、適切な相続手続きの第一歩となるでしょう。
関連記事:特別受益とは?持ち戻しの計算方法や特別受益として扱われる贈与のパターンを分かりやすく解説
特別受益と生前贈与の違い
相続の文脈では「生前贈与」と「特別受益」という二つの言葉がよく使われます。
生前贈与は、「誰かが亡くなる前に、その人から財産を受け取ること」を指す一般的な言葉です。
法律上は「贈与」という契約の一種で、特に人が亡くなることを条件とする死因贈与と区別する目的で使われます。
また、相続税の負担を減らすために、亡くなる前に財産を贈与する行為を指す場合もあります。つまり、生前贈与は「贈与する行為そのもの」を指す言葉です。
一方、特別受益は、特定の相続人が被相続人(亡くなった人)から受けた贈与の中でも、特別な利益のことを指します。
それぞれ異なる意味を持っているため、違いを理解しておきましょう。
生前贈与については以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:相続財産の範囲に生前贈与は含まれる?特別受益に当たらない場合やみなし相続財産も解説
関連記事:【弁護士監修】生前贈与は特別受益になる?認められるケースや持ち戻しの計算方法を解説
参考:国税庁|贈与税がかかる場合
特別受益には時効がない
特別受益の持ち戻しについては、民法上で明確な時効の規定がありません。
そのため、20年前や30年前に行われた贈与であっても、証拠が揃っていれば、特別受益として扱われるケースも過去にはみられました。
しかし、2023年の民法改正により、相続開始から10年を経過してからの遺産分割では、持ち戻し計算は原則できなくなっています。(民法第904条の3)
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫相手方の特別受益を主張するには、早期に遺産分割を行うことが不可欠といえるでしょう。
関連記事:特別受益に時効はある?民法改正後の10年ルールを弁護士が解説
特別受益は証拠がないと主張できない?
特別受益は証拠がないと主張できないのか、疑問に思う方もいるでしょう。
結論からいえば、条文上「特別受益の主張は証拠がなくても可能」です。当事者がこれに合意していれば、証拠がなくても特別受益自体は認められます。
本章では、合意による特別受益の認定ができない場合の立証責任や、特別受益が認められる基準を解説します。
特別受益を主張する側には立証責任がある
特別受益があったことを主張し、指摘された相続人がこれを否定した場合、合意による特別受益の認定はできません。
調停・審判で特別受益があったことを認定してもらうためには、主張する人に立証責任があります。
立証責任とは、ある事実が実際に存在したことを第三者が納得できる形で証明する義務のことです。
特別受益があったことを他の相続人に主張する場合には、遺贈・生前贈与があった証拠を取得する必要があります。
参考:家事事件手続法
裁判所や調停で特別受益が認められる判断基準
裁判所は、通帳や契約書、公正証書などの客観的な証拠を高く評価してます。
例えば、他の相続人に送金されていることが通帳に記載されている場合や不動産の所有者が移転していることが契約書で明らかになる場合特別受益の有無の判定に当たって重要な証拠になります。
これに対して、メールや日記などに贈与の記録があった場合でも、個人的な記録も証拠にはなりますが、単独では弱いものです。



他の客観的資料と組み合わせると説得力が高まります。
参考:裁判所|遺産分割調停
関連記事:特別受益の主張は弁護士に相談すべきかどうかについて解説
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
特別受益の証拠として認められるものとは
特別受益を立証するためには、第三者が見ても事実が明らかな客観的資料を揃えることが大切です。
特別受益の財産の種類によって有効な証拠は異なるため、対象財産ごとに最適な証拠を把握し、早めに集めるようにしましょう。
以下の特別受益の内容ごとに、有効な証拠等について見ていきます。
現金預金の贈与
- 有効な証拠:振込明細、通帳記録
- 裏付けとなる証拠:証言(同日出金の裏付け)
- 証明時のポイント:日付順に整理し、取引履歴は早期に請求して確保
現金や預金の贈与を証明するには、振込明細や通帳の記録がもっとも有効です。
特に大口の引き出しと同日に贈与が行われた事実を示す証言を組み合わせることで、裁判所に認められやすい立証が可能になります。
また、預貯金については、送金先が記載されていれば、金銭が渡されたことは履歴から明らかになります。
複数回の取引がある場合は、日付順に並べて時系列で整理し、一貫した流れがあった事実を示すことが大切です。
銀行の取引履歴には保存期限があります。時間が経つほど証拠の入手が難しくなるため、相続開始後できるだけ早く請求して確保しておきましょう。
生前の受け取ったお金が特別受益となるケースについては、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:生前にもらったお金は相続税・贈与税の対象?計算方法や特別受益について解説
居住用不動産の贈与
- 有効な証拠:登記事項証明書(「贈与」の記載)
- 裏付けとなる証拠:贈与契約書、固定資産税の納税記録
- 証明時のポイント:法務局で旧登記簿も含めて取得、経緯や使用状況も記録
居住用不動産の贈与は、登記事項証明書において、登記原因に「贈与」と明記されていれば、強力な証拠となります。
さらに贈与契約書や固定資産税の納税記録を揃えることで、贈与の実態を補強して立証力を高められるでしょう。贈与が無償で行われた経緯や、その後の所有・使用状況も証拠として有用です。
不動産の登記情報は法務局で取得できるため、古い事案の場合でも旧登記簿を含めて調査することをおすすめします。



登記原因が売買とされている場合でも、金銭の移転がなく、実態としては贈与と認定できることもあるので、不動産の所有権が移転していると見られる場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
学費の援助
- 有効な証拠:振込明細、授業料や入学金の領収書
- 裏付けとなる証拠:奨学金返済免除の記録
- 証明時のポイント:高額な留学費用や私立校費用は特別受益になりやすい
学費の援助を特別受益と証明するには、振込明細や領収書が重要な証拠となります。
特に留学費用や私立大学医学部の入学金などの高額な支払いは、「生計の資本」として特別受益に該当する可能性があります。
また、被相続人が全額肩代わりした奨学金の返済免除も、援助の一形態として証拠に利用できます。
ただし義務教育や扶養義務の範囲内の学費は特別受益の対象外となることが多く、被相続人の資産状況や社会的地位等も踏まえて検討するのが判定のポイントになるでしょう。
関連記事:学費は特別受益になる?認められるケース・認められないケースを判例付きで解説【弁護士監修】
生活費援助
- 有効な証拠:家賃振込記録、公共料金の支払記録
- 裏付けとなる証拠:同居時の家賃相当額や食費負担の記録
- 証明時のポイント:期間・金額・支援背景
生活費援助を特別受益だと証明するには、家賃振込記録や公共料金の支払記録などの具体的な支出証拠を揃えることが重要です。
同居していた場合には、家賃相当額や食費負担の記録を加えることで、援助の金額や内容をより明確に示せます。
長期的な扶養は特別受益として認められにくいものです。しかし、支援総額が収入や生活水準に比べて高額であれば、認定される余地は十分にあります。



期間や金額、支援の背景をセットで整理し、客観的資料と一緒に提出することで、説得力が格段に増すでしょう。
事業資金の援助
- 有効な証拠:送金記録
- 裏付けとなる証拠:設備購入の領収書、法人設立登記簿謄本
- ポイント:提供目的・時期・金額を正確に把握して時系列を整理
事業資金援助を立証するためには、送金記録を確保することが大切です。
さらに、設備購入の領収書や法人設立資金の登記簿謄本など、資金提供と事業運営の関連性を示す資料を揃えると説得力が増します。
事業立ち上げや拡大のための援助は高額になることが多く、特別受益として認められる可能性があります。
資金の提供目的や時期、金額を正確に把握し、時系列で整理した上で客観的証拠と一緒に提出することが成功の鍵になります。
特別受益の証拠を探す3つの方法
特別受益の証拠は、やみくもに探すよりも取得できる可能性が高いルートから計画的に進めていくことが重要です。
ここでは、効率的かつ実務でよく使われる証拠入手方法を3つご紹介します。
銀行・金融機関への取引履歴照会
相続人であれば、被相続人の銀行口座の取引履歴を請求できるため、贈与の有無を裏付ける有効な資料を手に入れられます。
裁判所の制度を使用すると、10年以上前の履歴といった通常より長い期間を照会できる場合もあり、古い贈与の立証にも役立ちます。
取得した履歴は、大口の出金や特定の振込先を特定し、贈与の事実と結び付けることが重要です。銀行のデータは一定期間を過ぎると廃棄される場合があるため、できるだけ早い段階で照会を行いましょう。
参考:個人情報保護法
法務局での不動産登記確認
法務局で登記事項証明書を取得すると、不動産の所有権移転や贈与の事実を証明可能です。特に贈与契約書がある場合は、特別受益の主張を大きく後押しする有力な証拠になります。
贈与が古い場合でも、閉鎖登記簿もしくは旧土地台帳を取得することで過去の所有権移転の履歴を確認できるでしょう。
弁護士に依頼すれば、複数物件や古い記録も効率的に入手できるため、調査の負担を軽減できます。
第三者の証言・状況証拠の活用
親族や近隣住民、職場関係者からの証言書は、直接的な証拠が不足している場合の有力な補強材料です。
また、贈与や援助の場面を撮影した写真や映像記録も、状況証拠として活用できます。
裁判や調停では、証拠だけでなく証言による印象も判断に影響を与えるため、証人の信頼性や具体性が重要です。



証人や資料を複数組み合わせ、証拠全体の整合性を高めると、説得力が増すでしょう。
参考:民事訴訟法
特別受益の証拠探しを弁護士に依頼する3つのメリット
特別受益の主張には証拠が必要な場合もありますが、証拠がない、あるいは見つからない場合でも、弁護士に相談することで状況を打開できる可能性があります。
弁護士に依頼するメリットは、以下の3つです。
関連記事:特別受益の主張は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや費用を解説【弁護士監修】
特別受益の証拠集めの代行・サポートをしてもらえる
特別受益の証拠がない、またはどうやって探せばいいかわからない場合、弁護士は法的な権限を駆使して証拠収集をサポートしてくれます。
具体的には、以下のような調査を代行してもらえるのがメリットです。
| 弁護士に代行してもらえる証拠集め | 内容 |
|---|---|
| 不動産登記情報の取得 | 不動産の購入資金援助や、不動産の無償贈与がないかなどを確認 |
| 遺言書や贈与契約書の有無確認 | 故人宅に残された書類などから、特別受益の証拠となる文書を探す |
また、個人では入手が難しい資料でも、弁護士が裁判所を通じて文書提出命令や調査嘱託といった手続きを申し立て、強制的に提出を求めることも可能です。
集めた証拠が法的に有効なものか、調停や審判でどう活用すべきかといったアドバイスも受けられるため、証拠の価値を最大限に高められるでしょう。
特別受益による家族間の対立を最小限に抑えられる
相続問題では、感情的な対立がこじれてしまうケースが少なくありません。
特に、特別受益を巡る主張は「親のひいき」や「不公平」といった感情が絡みやすく、当事者同士での話し合いは難航しがちです。
弁護士が第三者として中立かつ冷静に手続きを進めることで、当事者同士の直接的な衝突を回避できます。
相手へ向けた感情的な発言や攻撃的な主張を、法律的かつ穏やかな表現に変えて伝えるため、受け手の印象も和らぎやすくなるでしょう。



特に、意見が真っ向から対立しており、長期化が避けられないと予想される場合ほど、弁護士を介した交渉は有効です。
調停・審判で代理人として交渉できる
特別受益の主張は、調停や審判の場で説得力をもって伝える必要があります。しかし、法的な知識がないまま臨むと、主張がうまく伝わらなかったり、相手の反論にどう応じればいいかわからなかったりするでしょう。
弁護士は調停委員や裁判官に対して、事実関係を整理したうえで法的根拠を明確に示し、説得力ある主張を適切なタイミングで行います。
必要に応じた反証活動も実施するため、相手方の主張の矛盾や弱点を突いて効果的に論破することが可能です。



弁護士に依頼することで、最終的に有利な条件での和解や判決に近づける可能性を高められるでしょう。
参考:家事事件手続法
関連記事:相続に強い弁護士とは?費用や失敗しないためのポイントを解説【弁護士監修】
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
特別受益について場合によくある質問
特別受益の証拠が見つからない場合にはどうすれば良いですか?
証拠がまったくない場合は、原則として特別受益を立証することは困難です。
ただし、直接的な証拠が不足していても、間接証拠を積み上げ、事実を推認させる形で立証できる場合があります。
具体的には、贈与を受けた可能性を示す複数の状況証拠や、相手からの供述を引き出す交渉が有効です。
また、弁護士による法務局等への照会を通じて、新たな証拠が発見されるケースも少なくありません。
特別受益にあたらないものはありますか?
以下に示すものは、原則として特別受益とはみなされず、遺産分割の計算には含められません。
| 特別受益にあたらないケース | 内容 |
|---|---|
| 相続人以外への贈与 | 相続人ではない孫や子の配偶者などへの贈与 |
| 扶養義務の範囲内の援助 | 日常生活費や義務教育までの学費など、被相続人の扶養義務の範囲内で行われた援助 |
| ごく少額な贈与 | 遺産全体の額に比べて極めて少額な贈与 |
このように、一部の贈与や援助は特別受益にあたらず、遺産分割の際に考慮されない場合があります。
自分の相続において、特別受益にあたらない財産の有無を確認しておきましょう。
また、特別受益に当たったとしても、被相続人が特別受益分を持ち戻す必要がないとの意思表示をしている場合には、特別受益に該当しても持ち戻しをしないことになります。
参考:民事訴訟法(文書提出命令等)
関連記事:特別受益に当たらない生前贈与とは?主張方法や必要な証拠も解説【弁護士監修】
関連記事:遺贈は特別受益になる?該当するケースを弁護士が解説
特別受益があるかないかを調べる方法は?
特別受益の有無を調べるには、まず被相続人の財産の流れを明確に把握することが必要です。
銀行口座の取引履歴や不動産登記情報、契約書類など、資産や取引の記録を収集してください。
贈与時期や用途を記載したメモが残っていれば、証拠の補強として有用です。
これらの資料を時系列で整理し、他の相続人や第三者からの証言と照合することで、全体像が浮かび上がってくるでしょう。
まとめ|特別受益の証拠がない時は弁護士にサポートを依頼してみよう
特別受益は証拠がなければ認められにくく、相続分の持ち戻し計算ができなくなる可能性があります。
古い贈与でも証拠が揃えば認められる場合はありますが、相続開始から10年を経過すると法律上主張できなくなる点は注意が必要です。
証拠の収集は時間との勝負になることも多く、早めの着手が有利に働きます。自分だけでは難しい場合も、弁護士の支援を受けることで、効率的かつ確実に立証の可能性を高められるでしょう。



相続トラブルを不安なまま進めず、まずは弁護士に相談する一歩を踏み出してみることをおすすめします。
相続問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。
まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応