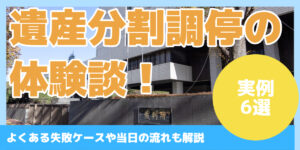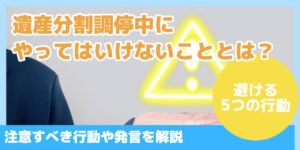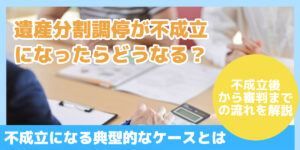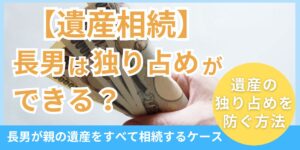【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続に嫁が口出しするときの対処方法|もめないための進め方・嫁の権利について解説
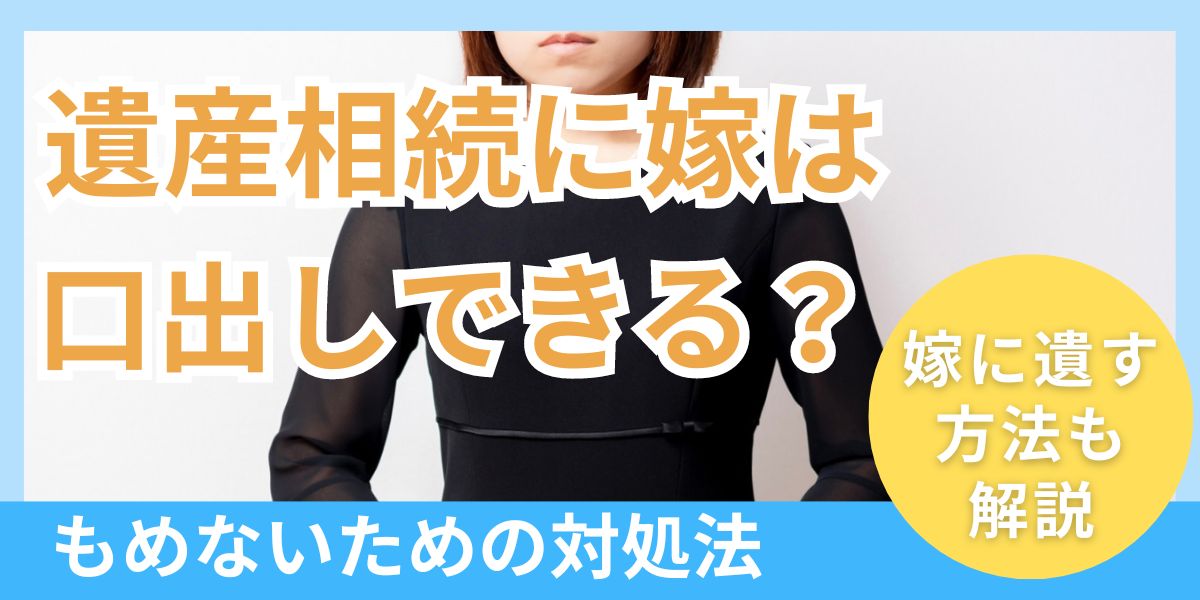
嫁が遺産相続に口出しするため、次のように悩み、対応に困っている相続人もいるでしょう。
- そもそも、相続の権利がない嫁が、遺産相続に口出しできるのか?
- 遺産相続がもめないためには、どうするべきか?
遺産分割協議は、法定相続人だけで行い、相続人全員が合意すべきものです。
本記事では、遺産相続に嫁が口出しすることの可否、もめないための進め方とトラブルが生じた場合の対処法を解説します。
遺産相続に嫁が口出しするため対応に困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
嫁が遺産相続に口を出して悩んでいる方は、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
【無料相談受付中】24時間365日対応
遺産相続とは
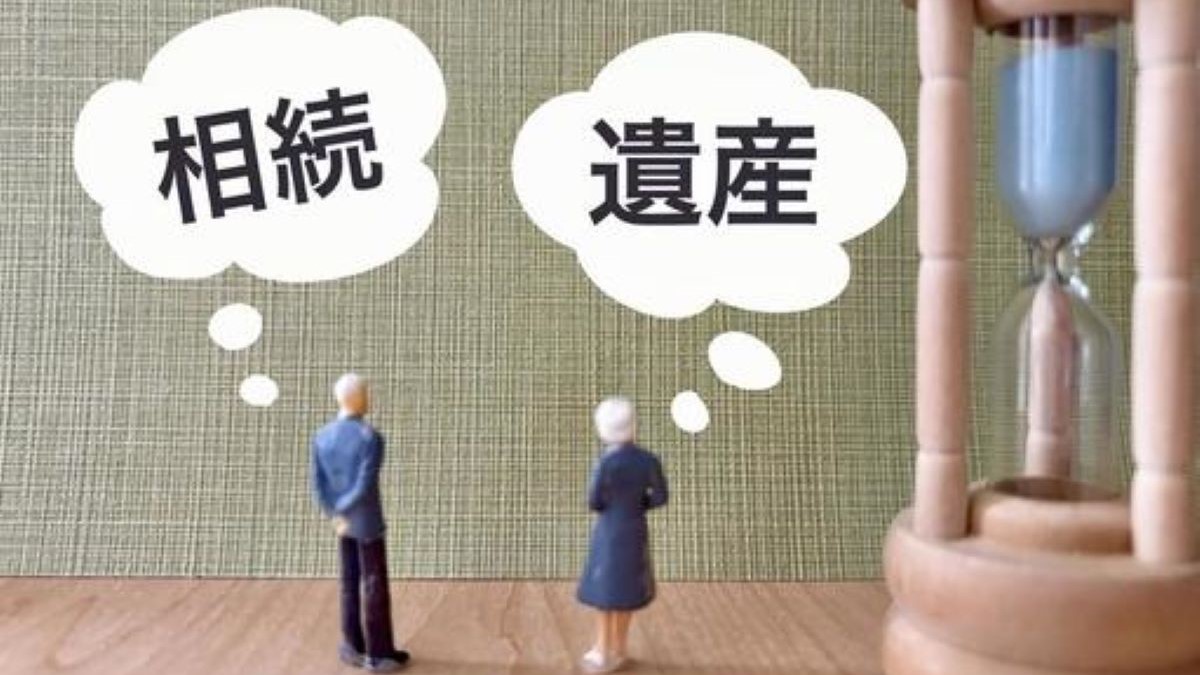
最初に遺産相続の基礎知識を3つ紹介します。
遺産の範囲
遺産の範囲は、亡くなった人(被相続人)が残した全財産です。
民法は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定しています(民法896条)。
プラスの財産(預貯金や株式、不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金や負債)も含まれます。
| プラスの財産の例 | マイナスの財産の例 |
| 現金・預貯金・株券 | 借金 |
| 不動産(土地・建物) | 住宅ローン |
| 動産(貴金属・自動車など) | 未払金(税金・医療費など) |
| 会員権など | 買掛金 |
運転免許など、被相続人の一身に専属したものは遺産ではありません。
法定相続人の範囲と順位
相続する権利を持つ相続人(法定相続人)の範囲と順位は、次のとおりです。
- 被相続人の子(民法887条)
- 直系尊属(父母、祖父母等)(民法889条1項1号)
- 兄弟姉妹(民法889条1項2号)
相続順位1位が被相続人の子で、2位が直系尊属、3位が兄弟姉妹です。
被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
法定相続分
民法は、同順位の相続人の相続割合を定めています(法定相続分、民法900条)。
| 同順位の相続人 | 相続割合 |
| 子と配偶者 | 各1/2 |
| 配偶者と直系尊属(父母・祖父母等) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は同等です(民法900条4号)。
嫁は遺産相続の協議に口出しできるか?

相続人の嫁が、遺産相続の協議に口出しすることについて、次の2点を説明します。
嫁は遺産分割協議に口出しできない
被相続人の息子の嫁は、遺産分割協議に口出しできません。
なぜなら遺産分割協議は、法定相続人だけで行い、全員の合意で決定するものだからです。
遺産分割協議は、遺産相続について法定相続人の協議によって、それぞれが相続する財産やその割合を決めるものです(民法907条1項)。
被相続人の息子の嫁は法定相続人でないため、遺産分割協議に加わる資格がなく、口出しはできないのです。
遺産相続に嫁が口出しするのはトラブルのもと
嫁が遺産相続に口出しすれば、トラブルのもとになります。
他の相続人は、遺産分割協議に嫁が口出しすることを、通常、歓迎しないでしょう。
しかし、話し合いへの参加が禁じられているわけではなく、実態としては嫁が夫に同行し遺産分割協議に加わるケースもあるでしょう。
他の相続人にしてみれば「相続人でない嫁がなぜ口出しするのか」と不快に感じ、トラブルになるおそれがありますので注意が必要です。
遺産相続に嫁が口出ししようとするのはどんなとき?

遺産相続に嫁が口出ししようとするのは、次のような場合です。
夫の相続分が少ないとの不満があるとき
嫁が口出しする可能性があるのは、夫の相続分が少ないと嫁が不満を持つときです。
嫁の言い分としては、次のような理由が考えられます。
- 夫は長男だから、弟たちより多く配分してほしい
- 親から資金援助を受けていた兄弟は、減らすべき
- 親の生活費を援助していたから、その分を返してもらいたい
内容や程度にもよりますが、嫁が口出ししたくなるほど、大きな不満を感じることもあるでしょう。
嫁が被相続人の世話をしたとき
嫁が被相続人の介護や身の回りの世話をした場合も、口出しする可能性があります。
夫の親の介護や世話は負担が大きいものです。
嫁が、長期間にわたり被相続人の介護をし、被相続人の財産形成に助力した場合には、相続人である夫の「寄与分」として、法定相続分以上の遺産を相続することが認められる場合もあります。
献身的に故人の面倒をみた方であれば「あれだけ献身的に支えたのだから、遺産も考慮してほしい」と思うことはあるでしょう。
相続人である夫がすでに死去していて子が代襲相続するとき
子(被相続人の孫)が代襲相続する場合(民法887条第2項)も、嫁が口出しする可能性があります。
夫がすでに死去しているため、子の代わりに協議に加わりたいと思うのでしょう。
子が成年の場合は、代理を立てる必要はなく、嫁が口出しすることはできません。
未成年の子が1人であれば、親権者(民法818条第1項)である嫁は、法定代理人として遺産分割協議に参加することができます。
未成年の子が複数いる場合は、嫁は1人の子の法定代理人になれますが、他の子には特別代理人の選任が必要です(民法826条第2)。
代襲相続の場合、嫁は相続人ではありませんが、子の将来も考えて口出ししようとする可能性は高いでしょう。
出典:国税庁|共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
出典:eーGovポータル|民法
遺産相続に嫁が口出しする権利を持つ場合もある

遺産相続に嫁が口出しする権利を持つ場合もあります。
具体的に解決します。
嫁に遺産を贈与するとの遺言があるとき
嫁が口出しする権利がある1つ目のケースは「嫁に遺産を贈与する」との遺言があるときです。
嫁への贈与が包括遺贈の場合は、嫁は「相続人と同一の権利義務」を有する(民法990条)とされているからです。
遺贈には、次の2種類があります(民法964条第1項参照)。
- 包括遺贈:贈与財産を特定せず贈与する割合を指定、債務も引き継ぐ
- 特定遺贈:特定の財産の贈与、債務は引き継がない
特定遺贈の場合は「相続人と同じ立場」になるわけではないため、遺産分割協議に加わることはできません。
包括遺贈の場合は、相続人と同じ立場で遺産分割協議に参加することになります。
ただし、遺贈が遺留分(相続人に最低限保証される遺産取得分、民法1042条)を侵害する場合は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求される可能性があります(民法1046条)。
出典:eーGovポータル|民法
関連記事:包括遺贈と特定遺贈の違いとは?知っておきたい意味・注意点をわかりやすく解説
被相続人を長期間介護した特別寄与料がある
嫁が口出しする権利がある2つ目のケースは、被相続人を長期間介護した特別寄与料がある場合です。
特別寄与料を持つ特別寄与者は、相続人に対して、特別寄与料に相応する金銭の支払を請求できます(民法1050条)。
特別寄与者とは、次の3つを満たす者です。
- 被相続人の親族(相続人や相続放棄者等を除く)
- 被相続人を無償で療養看護などした
- 被相続人の財産の維持・増加に特別寄与した
嫁の貢献を認めた判例は、以前からありますが、あくまでも相続人である夫の寄与分との判旨でした(東京高裁平成22年9月13日決定など)。
特別寄与料は、2019年の相続法改正で新設された制度で、特別寄与者(嫁)の貢献を相続人(夫)ではなく、寄与者本人の権利として認めたものです。
出典:法務省|相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)
出典:法務省|寄与分に関する裁判例
被相続人と養子縁組していた
嫁が口出しする権利がある3つ目のケースは、被相続人と養子縁組していた場合です。
被相続人は、息子の嫁を養子にできます(民法792条)。
養子は、嫡出子の身分を取得するため(民法809条)実子と同様の扱いになります。
嫁が養子縁組をする場合、普通養子縁組になるため、実親との親子関係は変わりません。
嫁が被相続人と養子縁組していた場合、遺産分割協議の正当な参加者となりますが、実子である相続人との間でトラブルが起こる懸念もあります。

遺産相続が嫁の口出しによりもめないための進め方
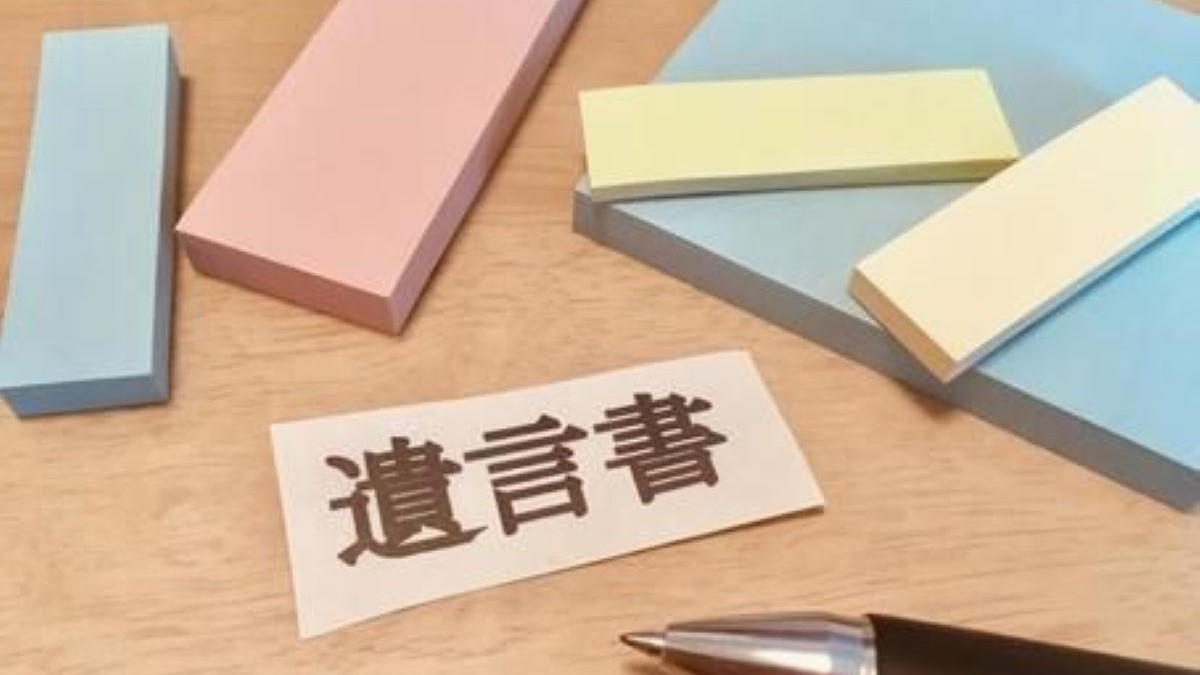
遺産相続が嫁の口出しによりもめないための進め方があります。
ぜひ、参考にしてください。
遺言の有無を確認する
遺産分割協議の必要性や内容に影響するため、まず遺言の有無を確認しましょう。
遺言がある場合は、遺産分割協議をしなくても、遺言どおりの相続が発生します(民法902条1項参照)。
被相続人が遺言を残していない場合は、相続人で遺産分割協議をする必要があります。
遺言書は、自宅にない場合、法務局か公証役場などで保管されているかもしれません。
遺言の有無が不明な場合は、法務局に問い合わせる・公証役場の遺言検索システムを活用するなどして確認しましょう。
遺言書を確認する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:遺言書があるかどうかを確認する方法は?遺言書の種類ごとに解説
参考:法務省|自筆証書遺言書保管制度
参考:日本公証人連合会|遺言
誰が相続人か明確にする
遺産分割協議を始める前に、相続人は誰なのかを正確に把握しておく必要があります。
遺産分割協議は、法定相続人全員の参加と全員の合意が必要だからです。
相続人が一人でも欠けている場合、新たな相続人が見つかった場合などは、協議のやり直しになるおそれがあります。
被相続人の戸籍謄本や改製原戸籍などを確認して、遺産分割協議を始める前に相続人をきちんと確定させましょう。
遺産の全貌を把握する
遺産の全貌(プラスとマイナスの両方)を明確にして把握しておくことも重要です。
遺産の総額に影響する、遺贈や生前贈与、特別受益・寄与料を含めて、遺産の全貌をできる限り確認しましょう。
生前贈与や特別受益・寄与分を確認する
生前贈与や特別受益・寄与分の有無は、協議の前提となるため、しっかり確認しましょう。
- 生前贈与:被相続人による存命中の贈与(民法549条)
- 特別受益:遺贈と生前贈与のうち、婚姻や養子縁組のための贈与・生計資本としての贈与(民法903条1項)
- 寄与分:相続人が、被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した場合に、通常の相続分にプラスして受け取れる額(民法904条の2)
被相続人から優遇を受けた相続人はその分相続割合が減少し、被相続人に貢献した相続人はプラスアルファが認められるため、しっかり確認しましょう。
生前贈与されたお金と特別受益の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:生前にもらったお金は相続税・贈与税の対象になる?特別受益について解説
相続人だけで話し合う
相続人だけで話し合うことは、特に重要なポイントです。
遺産分割協議は、本来相続人だけで行うものです。
相続人の嫁など、相続人以外の人が参加して口出しすれば、相続人を不快にさせ、トラブルの原因にもなりかねません。
包括遺贈を受けたなど遺産分割協議に参加できる権利がある場合を除き、相続人だけで話し合いましょう。
遺産分割協議書を作成する
相続人全員の合意が得られたときは、必ず遺産分割協議書を作りましょう。
遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更などで必要です。
「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも欠かせません。
遺産分割協議書を作って、公正証書にしておけば、改ざんや紛失の恐れがなく安心できます。
参考:法務省|公証制度について
遺産相続協議がまとまらないときの対処法

どうしても遺産相続協議がまとまらないときは、次の方法で対処しましょう。
遺産分割調停を申し立てる
協議がまとまらないときは、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
裁判官と調停委員が公平な立場で当事者の話し合いを仲介してくれます。
当事者でない嫁は、遺産分割調停には加われません。
調停が不成立の場合、家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を行い解決案を示すことがあります。
審判に対する異議の申立ての有無により、その後の手続きが変わります。
- 一定期間内に異議を申し立てないとき:審判内容で遺産分割が確定(家事事件手続法287条)
- 異議を申し立てたとき:自動的に家事審判手続に移行(家事事件手続法286条7項)
公平な立場で進められる調停の申立ては、遺産相続協議がまとまらないときに活用できる有効な方法です。
参考:裁判所|遺産分割調停
弁護士に相談する
協議が難航しているときは、弁護士に相談するのもよい方法です。
遺産相続問題に詳しい弁護士が、適切な条件で解決できるよう交渉します。
他の相続人との協議だけでなく、調停や訴訟もしっかりサポートしてくれます。
相続財産の全貌がわからないときは調査も可能なため、弁護士に相談することがおすすめです。
専門家のアドバイスを受けることで、法的に適切な手続きを踏み、トラブルを未然に防ぐことができます。
弁護士法人アクロピースでは、初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\相続トラブルはお任せください/
今すぐご相談したい方は、お電話がおすすめです!
【無料相談受付中】24時間365日対応
息子の嫁に遺産を遺す方法

息子の嫁に遺産を遺したい場合もあるでしょう。
息子の嫁に遺産を遺す方法としては、次のような方法があります。
生前贈与する
生前贈与をすれば、嫁に財産を早く渡せます。
生前贈与とは、文字通り生前、存命中に贈与することです。
贈与額によっては贈与税がかかる場合があるため、暦年贈与(年間110万円まで非課税)を活用するとよいでしょう。
生前贈与は、息子の親が自分が生きている間にできるため、嫁に遺産を残す確実な方法と言えます。
ただし、相続開始前1年以内の贈与は、遺留分侵害額請求の対象になりますし、贈与する側も贈与を受ける側も遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与については、1年以内の贈与でなくても遺留分侵害額請求の対象となります(民法1044条)。
参考:国税庁|No.4402 贈与税がかかる場合
生命保険を活用する
生命保険の活用も、嫁に財産を渡す1つの方法です。
生命保険金は受取人固有の権利として取得するもので、原則、遺産となりません(平成14年11月5日最高裁判所第一小法廷判決)。
遺産分割の対象財産でないため、相続人と協議する必要もありません。
ただし、支払われた生命保険金の額が大きく、他の相続人との間に著しい不平等が生じる場合は、例外的に遺産分割の対象となることがあります(平成16年10月29日最高裁判所第二小法廷決定)。
嫁を受取人とする生命保険は、相続人とトラブルになる可能性が比較的低く、嫁に財産を渡せる有効な手法です。
参考:裁判所|死亡保険金支払請求権確認請求事件
参考:裁判所|遺産分割及び寄与分を定める…事件
遺言書を作る
嫁に財産を遺すため、遺言書を作ることもできます。
遺言で財産を相続人以外の人に贈与することは可能です(民法964条)。
遺言書に「嫁に財産を譲る」旨を明記しておけば、その遺言は有効です。
遺言書は自筆も可能ですが、不安な場合は公正証書を作ってもらう方法もあります。
遺言は、相続人の遺留分(最低限保証される遺産取得分、民法1042条)は侵害できませんが(民法1046条参照)、遺言書を作っておくことで、嫁に遺産を遺せます。
出典:eーGovポータル|民法
参考:法務省|自筆証書遺言書保管制度
参考:法務省|公証制度について
まとめ
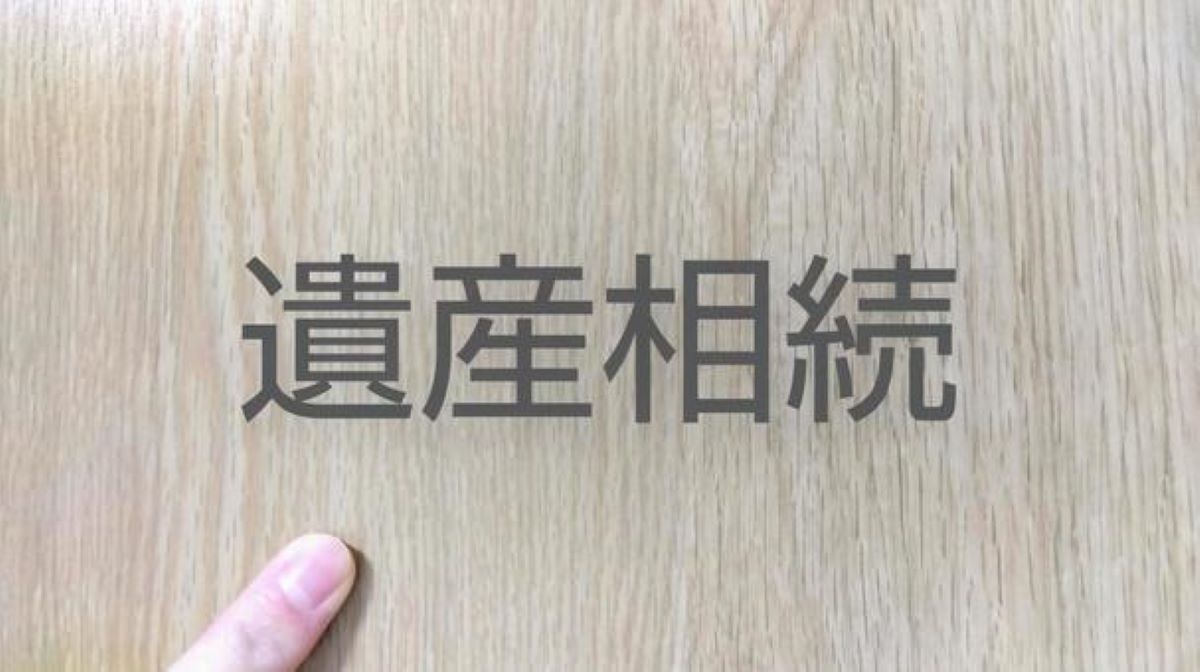
遺産相続に嫁が口出しすることについてまとめると、次のようになります。
- 嫁は法定相続人でないため、遺産分割協議に口出しできない
- 遺産相続に嫁が口出しするのはトラブルのもと
- 舅の遺言や特別寄与料がある場合など、嫁が口出しする権利を持つ場合もある
- 嫁に口出しさせないため、遺言の有無・相続人は誰か・遺産の全貌を要確認
- 協議がまとまらないときは、弁護士に相談・遺産分割調停を申し立てる
- 嫁に遺産を遺す方法は、生前贈与・生命保険の活用・遺言書の作成がある
遺産相続に困っているとき、悩むときは弁護士に相談するのが最短の解決策となりおすすめです。
弁護士法人アクロピースは累計7000件以上の相談実績があり、相続問題に強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。
初回60分の相談は無料です。
お気軽にご連絡ください。
\ 相談実績7000件(突破)/
今すぐご相談したい方は、お電話がおすすめです!
【無料相談受付中】24時間365日対応