【無料相談受付中】24時間365日対応
共有者が固定資産税を払わないときは?立て替えた際の請求方法や解決策を解説
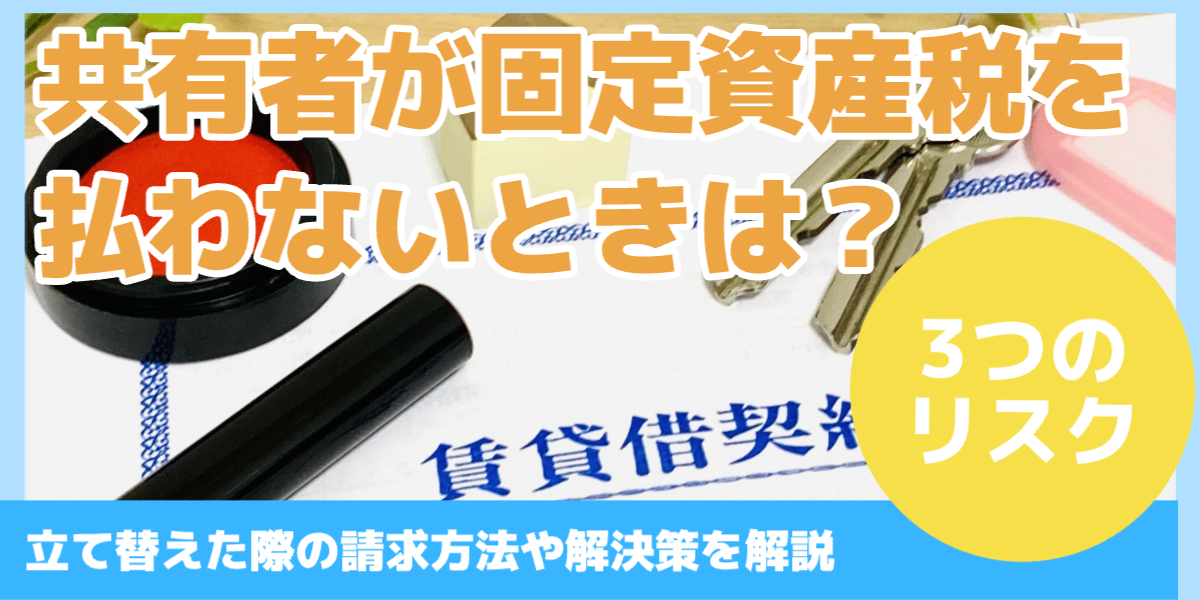
「共有名義の不動産なのに、兄弟が固定資産税を払ってくれなくて困っている…」
「自分が立て替えた税金を、どうやって法的に請求すればいいんだろう?」
共有名義の不動産に関する税金のトラブルは、金銭的な問題だけでなく、親族間の感情的なしがらみも絡みます。上記のような悩みを抱える人も多いのではないでしょうか。
この記事では、共有者が固定資産税を支払わない場合の法的な義務関係から、具体的な対処法、立て替えた税金の回収手続きまでを解説します。また、トラブルを根本から解決する方法も紹介します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫立て替えた税金を適切に回収するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義の固定資産税は「共有者全員の連帯納税義務」がある
共有名義の不動産における固定資産税は、共有者の一人が代表して支払うケースが一般的ですが、法律上の納税義務は共有者全員が連帯して負っています。これは「連帯納税義務」と呼ばれ、地方税法第10条の2第1項で定められている重要な原則です。
つまり、市区町村などの自治体から見れば、各共有者が持分割合に応じて個別に税金を納めるのではなく、各共有者が連帯して全額に責任を負います。
そのため、誰か一人が支払いを怠れば、自治体は他の共有者に対して、滞納分を含めた税金の全額を請求することが可能です。
この仕組みを理解しておくことが、トラブル解決の第一歩となります。
共有者が固定資産税を払わない場合に起こり得るリスク
共有者の一人が固定資産税の支払いを拒否し、誰も立て替えずに滞納状態が続くと、他の共有者にも深刻なリスクが及びます。単に金銭的な負担が増えるだけでなく、最終的には大切な財産を失う事態にもなりかねません。
ここでは、起こり得る3つの重大なリスクを具体的に解説します。
延滞金が発生して納税額が増える
固定資産税を納付期限までに支払わない場合、その翌日から延滞金が加算されます。延滞税の税率は決して低くなく、納付が遅れれば遅れるほど、本来支払うべき税額は雪だるま式に膨らんでいきます。
たとえば、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間は年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用されます。また、それを過ぎると年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されるため注意が必要です。
共有者の一人が支払わないばかりに、他の共有者までが余計な金銭的負担を強いられることになります。問題を先送りにせず、早期に対処することが経済的損失を最小限に抑える上で重要です。
出典:国税庁|延滞税の計算方法
他の共有者に督促状が届いて一括請求される
代表者名義で納税通知書が届いていても、滞納が発生すれば、自治体は他の共有者に対して督促状を送付し、納税を要求します。前述のとおり、共有者全員に連帯納税義務があるため、自治体は持分割合に関係なく、どの共有者に対しても滞納分の全額を請求することが可能です。
ある日突然、役所から自分宛に督促状が届き、他の共有者の滞納分まで含めた高額な税金を請求される事態は、精神的にも大きな負担となります。この段階で無視を続けると、事態はさらに深刻化し、最終手段である「差し押さえ」へと進んでしまいます。
督促状が届いた場合は、決して放置せず、すぐに行動を起こすことが大切です。
最終的には共有不動産や個人の財産が差し押さえられる
督促状を送付しても納税されない場合、自治体は法律に基づき、滞納者の財産を差し押さえます(地方税法第373条)。
差し押さえの対象となるのは、問題となっている共有不動産や共有者の預貯金や給与、生命保険、自動車などです。
不動産が差し押さえられると、最終的には競売にかけられ、市場価格よりも大幅に安い金額で強制的に売却されてしまう可能性があります。
共有者一人の無責任な行動が、他の共有者の生活基盤そのものを揺るがす重大な事態に発展するリスクにつながる可能性があるため注意が必要です。
【ステップで解説】固定資産税を払わない共有者への対処法
共有者が固定資産税を支払わない場合、感情的に対立する前に行動を起こすことが重要です。ここでは、問題を解決するための具体的な3つのステップを解説します。
冷静かつ段階的に手続きを進めることで、無用なトラブルを避け、円滑な解決を目指しましょう。
ステップ1:まずは代表者が全額を立て替え払いする
共有者の一人が支払いを拒否していても、まずは納税通知書を受け取った代表者が責任をもって期限内に全額を立て替え払いすることが最優先です。滞納による延滞税の発生や、最悪の場合の差し押さえといったリスクを回避するために、この初動が極めて重要になります。
立て替え払いをする際は、後で他の共有者に請求する際の証拠として、納税した事実がわかる領収書などを必ず保管しておきましょう。銀行振込で支払うなど、客観的な記録を残しておくことも有効です。
まずは納税義務を果たしてリスクを回避し、その上で共有者間の内部的な問題解決に着手する順序で進めるのが賢明です。
ステップ2:立て替えた負担分を払わない共有者に請求する
税金を立て替えたら、次に支払いをしない共有者に対して、その人の持分割合に応じた負担分を明確に請求します。まずは電話やメール、対面での話し合いといった穏便な方法で、立て替えた事実と支払ってほしい金額、支払い期限を伝えましょう。
この際、感情的にならず、あくまで事務的に「あなたの負担分である〇〇円を立て替えたので、〇月〇日までに支払ってください」と冷静に伝えることが大切です。
支払いに応じない理由(経済的な困窮など)によっては、分割払いを提案するなど、柔軟な対応を検討することも、円満な解決のためには有効な場合があります。
まずは、直接のコミュニケーションで解決を図る努力をしましょう。
ステップ3:話し合いに応じない場合は内容証明郵便で請求する
直接話し合いをしても支払いに応じてもらえない、あるいは連絡が取れないといった場合には、内容証明郵便を利用して正式に請求書を送付します。内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出したか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。
文書には、立て替えた固定資産税の金額、請求日、支払い期限、そして「期限内に支払いがない場合は、やむを得ず法的措置を検討します」といった文言を記載します。
内容証明郵便自体に法的な強制力はありませんが、相手に対して「本気で回収する意思がある」との強いプレッシャーを与え、支払いを促す心理的効果が期待できます。また、将来的に裁判手続きに移行した場合に、請求の意思を示した重要な証拠となります。
固定資産税を払わない共有者への請求で注意すべきポイント
共有不動産の固定資産税は、共有者全員に納税義務があります。代表者が立て替えた場合、他の共有者へ負担分を請求できます。
しかしスムーズに解決するためには、段階を踏んで冷静に対処することが重要です。
感情的な対立による関係悪化を避ける
共有者が親族である場合、金銭の請求は感情的なしこりを残しやすく、関係悪化の大きな原因になり得ます。
トラブルを避けるためには、初めから事務的かつ冷静に対応することが重要です。まずは納税通知書などの客観的な資料を提示し、支払うべき金額と根拠を明確に伝えましょう。
その際、相手の状況を詮索したり、高圧的な態度をとったりするのは避けるべきです。
分割払いや支払期限の猶予など、相手の事情にも配慮した柔軟な支払い計画を提案することで、話し合いの余地が生まれます。
あくまで「共有財産の維持に必要な事務手続き」というスタンスを保ち、個人的な感情を交えずに交渉することが重要です。
納税通知書などの証拠書類を保管しておく
共有者が固定資産税の支払いに応じない場合に備え、納税通知書や支払いを証明する領収書などの書類は必ず保管しておきましょう。
これらの書類は、立て替えて納税した事実 を客観的に証明するための重要な証拠となります。
特に、後述する内容証明郵便での請求や、訴訟などの法的措置に移行する際には、これらの証拠がなければ手続きを進めることが困難になります。
いつでも法的な手続きに移れるよう、関連書類は整理して大切に保管することが大切です。
立て替えた固定資産税を回収する手続き
話し合いや内容証明郵便でも解決しない場合、法的な手続きを通じて立て替えた金銭を回収することになります。
ここでは、状況に応じて選択できる3つの主な法的手続きを紹介します。手続きが複雑になるため、この段階では弁護士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
支払督促|簡易裁判所を通じて督促状を送ってもらう手続き
支払督促は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てることで、裁判所から相手方へ金銭の支払いを命じる督促状を送ってもらう手続きです。
通常の訴訟と異なり、申立人の主張のみに基づいて書類審査が行われるため、裁判所に足を運ぶ必要がなく、迅速かつ低コストで進められるのが大きなメリットです。
相手方が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、申立人は「仮執行宣言」を得られます。仮執行宣言が付された支払督促は確定判決と同じ効力を持ち、強制執行の申し立てが可能になります。



相手が請求の事実自体を争ってこない可能性が高い場合に有効な手段です。
出典:裁判所|支払督促
少額訴訟|60万円以下の金銭トラブルを迅速に解決する裁判手続き
請求する金額が60万円以下の場合には、少額訴訟という特別な裁判手続きを利用できます。
少額訴訟は、原則として1回の期日で審理を終えて判決が下されるため、通常の訴訟に比べてスピーディーに解決を図れる点が特徴です。
審理では、裁判官が当事者双方の言い分を直接聞き、証拠をその場で確認します。相手方が支払いを拒否する理由を主張してくる場合など、双方の意見が対立しているケースに適しています。
勝訴判決を得られれば、その判決に基づいて強制執行を申し立てることが可能です。ただし、相手方が少額訴訟での審理を拒否した場合は、通常の訴訟手続きに移行することになります。
出典:裁判所|少額訴訟
強制執行|判決等に基づき相手の財産を差し押さえる最終手段
支払督促や少額訴訟などで勝訴判決を得てもなお相手が支払いに応じない場合、最終手段として強制執行を申し立てることになります。これは、裁判所の力を借りて、強制的に相手の財産から立て替え分を回収する手続きです。
強制執行の対象となる財産は、預貯金や給与、不動産など多岐にわたります。
たとえば、相手の預金口座を差し押さえれば、銀行はその口座から強制的に請求額分を引き出して支払います。給与を差し押さえる場合は、勤務先から給与の一部を直接支払ってもらうことが可能です。
これは強力な手続きですが、相手の財産を特定する必要があるなど、専門的な知識が求められるため、弁護士に依頼して進めるとよいでしょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
【ケース別】特殊な事情で共有者が固定資産税を払えない場合の対処法
共有者が税金を支払えない背景には、経済的な問題だけでなく、さまざまな特殊な事情が隠れている場合があります。相手の状況に応じて適切な対処法を選択しなければ、問題はさらに複雑化してしまいます。
ここでは、代表的な3つのケースとその対処法を解説します。
共有者が死亡した場合
共有者の一人が亡くなった場合、その人の納税義務を含むすべての権利義務は、相続人に引き継がれます。したがって、立て替えた固定資産税は、亡くなった共有者の相続人に対して請求することになります。
まずは戸籍謄本などを取り寄せて相続人を確定させ、その全員に対して支払いを求める話し合いを行いましょう。



相続関係が複雑な場合は、早期に弁護士へ相談することが重要です。
共有者が認知症など支払い能力がない場合
共有者が認知症や精神疾患などで、民法第3条の2における「意思能力を有しなかったとき」に該当する場合には、家庭裁判所に成年後見制度の利用を申し立てる必要があります。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人に代わって財産管理や契約行為を行う「成年後見人」を裁判所が選任する制度です。
成年後見人が選任されれば、その人が本人に代わって財産の管理を行うため、立て替えた固定資産税の支払いについても、成年後見人と交渉することになります。
手続きには時間がかかるため、状況を把握したら速やかに行動に移すことが求められます。
共有者が行方不明・音信不通の場合
共有者の居場所がわからず、連絡も取れない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人とは、行方不明者に代わってその人の財産を管理・保存する役割を担う専門家(弁護士などが選任されることが多い)です。
不在者財産管理人が選任されれば、その管理人に対して立て替えた固定資産税の支払いを請求できます。管理人は、行方不明者の財産の中から、裁判所の許可を得て支払いを行います。
また、税金の支払いだけでなく、共有関係の解消に向けた不動産の売却などについても、不在者財産管理人と協議を進めることが可能になります。
共有名義の不動産のトラブルについては、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有名義の不動産売却はトラブルに要注意!回避策とスムーズに売る方法
【要注意】立て替えた固定資産税を請求する権利(求償権)には時効がある
立て替えた固定資産税は、法的に保護された権利に基づいて請求できますが、その権利は永久に保証されるわけではありません。請求を怠っていると、時効によって権利が消滅してしまう可能性があります。
ここでは、請求権の根拠となる「求償権」とその時効について解説します。
立て替えた固定資産税を請求できる「求償権」とは
共有者の一人が他の共有者の負担分まで含めて固定資産税を支払った場合、その立て替えた分を他の共有者に対して請求する権利を「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。これは、連帯納税義務者の一人が全体の義務を果たした際に、他の義務者に対してそれぞれの負担部分の支払いを求められる、民法で認められた正当な権利です。
つまり、「代わりに払っておいたから、あなたの分を返してください」と法的に主張できる根拠が、この求償権です。固定資産税のトラブルにおいて、立て替え払いをした共有者を保護するための重要な制度といえます。この権利を行使するためには、自分が立て替えたことを証明する領収書などの証拠を保管しておくことが不可欠です。
求償権の時効は5年または10年
重要な点として、この求償権には時効が存在します。民法の規定により、立て替えた固定資産税を請求できる権利は、以下のとおりです。
民法第166条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき
出典:e-Gov法令検索|民法
時効の起算点は、立て替え払いをした日(各納期に支払った日)から5年(※)です。たとえば2020年に立て替えた分は、2025年には時効にかかる恐れがあります。
毎年立て替えを続けていると、古いものから順次時効にかかっていくため、長期間放置してしまうと多額の債権を回収できなくなるリスクがあります。
時効の進行を止めるためには、内容証明郵便による催告や、裁判上の請求(支払督促や訴訟の提起)といった法的な手続きが必要です。



共有者との関係性から請求をためらう気持ちも理解できますが、自身の権利を守るためにも、時効を意識し、早めに行動を起こしましょう。
※2020年4月1日に改正民法が施行される前に立て替えた分については、旧民法の規定が適用され、時効は10年となります。
固定資産税トラブルを未然に防ぐ共有管理の工夫
共有不動産の固定資産税トラブルは、事前の取り決めで防ぐことができます。共有者全員が納税意識を共有し、管理方法について明確なルールを設けることが重要です。
具体的な対策を講じ、円滑な共有関係を維持しましょう。
「共有不動産に関する合意書」を作成する
不動産を共有する際は、固定資産税の負担割合や支払方法などを明記した「共有不動産に関する合意書」を作成しましょう。口約束だけでは、将来的に「言った・言わない」のトラブルに発展しかねません。
合意書には、以下の点を盛り込むのがおすすめです。
- 各共有者の持分割合
- 固定資産税の負担割合(通常は持分割合に応じる)
- 代表して納税する人
- 具体的な支払方法(集金方法や期日など)
- 支払いが遅れた場合のペナルティ
これらの内容を共有者全員で確認し、署名・捺印して各自が保管します。
法的な拘束力を持たせたい場合は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼して、公正証書として作成することも有効です。
後々のトラブルを避けるためにも、最初の段階で書面による明確な合意を形成しておきましょう。
管理用の共有口座を開設する
固定資産税や修繕費といった不動産の維持管理にかかる費用を管理するための共有口座を開設するのも、有効なトラブル防止策です。個人の口座で管理すると、お金の流れが不透明になりやすく、他の共有者から不信感を持たれる原因にもなりかねません。
共有口座を設けることで、各共有者がいつ、いくら入金したのか、また、いつ、いくらの支払いがあったのかといった金銭の動きが通帳に記録され、全員がいつでも確認できる状態になります。
これにより、管理の透明性が格段に向上し、立て替え払いや集金の手間も省けます。最初に各共有者から一定額を口座に入金しておき、そこから固定資産税などを支払うルールにすれば、よりスムーズな管理が実現できるでしょう。
定期的に共有者全員で連絡を取り合う
共有不動産の管理を円滑に進めるためには、共有者全員が定期的にコミュニケーションを取る機会を設けることが不可欠です。
固定資産税の納税時期が近づいたタイミングだけでなく、普段から不動産の状況や将来の活用方針について情報交換をしておくことで、認識のズレや意見の対立を防げます。
年に1〜2回程度の定例会を開いたり、グループチャットなどを活用してこまめに連絡を取り合ったりするのがよいでしょう。
共有者全員が当事者意識を持ち、協力して不動産を管理していくという共通認識を育むことが大切です。
固定資産税トラブルを根本から解決する方法
立て替えた税金を請求し続けるのは、精神的にも時間的にも大きな負担です。毎年同じ問題で悩まされる状況から抜け出すためには、トラブルの原因である「不動産の共有状態」そのものを解消することが根本的な解決策となります。
ここでは、共有関係を解消するための4つの主な方法を紹介します。
自身の共有持分のみを専門の不動産会社に売却する
共有関係を解消したいけれど、他の共有者が話し合いに応じてくれない場合に有効な手段の一つが、自身の共有持分のみを売却することです。共有持分は個人の財産であるため、他の共有者の同意がなくても自由に売却できます。
一般の個人や不動産会社は共有持分のみの購入に消極的ですが、共有持分を専門に扱う不動産買取業者であれば、複雑な権利関係を前提とした上で適正な価格で買い取ってくれます。
売却してしまえば、固定資産税の納税義務から解放されるだけでなく、まとまった現金も手にできます。何よりも、トラブルの相手方であった他の共有者との関係を断ち切れる点が、精神的に大きなメリットといえるでしょう。
ただ、固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日時点の所有者」との決まりがあります。そのため、1月1日を過ぎてから持分を売却しても、その年度分の納税義務はかかってくる点には注意が必要です。
出典:総務省|固定資産税
共有者全員で不動産全体を売却する(換価分割)
もし共有者全員が不動産の所有を望んでいないのであれば、不動産全体を第三者に売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する「換価分割(かんかぶんかつ)」が最適な方法です。
この方法は、売却代金という明確な基準で分割するため、1円単位で公平な分配が可能となり、後のトラブルが生じにくいというメリットがあります。また、売却によって得た資金で、これまでに立て替えた固定資産税を精算することも可能です。
ただし、この方法を選択するには、売却すること自体はもちろん、売却価格や依頼する不動産会社など、すべての点について共有者全員の合意が必要です。一人でも反対すれば進められないため、全員の協力が得られる場合に有効な選択肢です。
共有不動産の売却に関するトラブルが気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:共有名義不動産は売却できない?よくあるトラブルと持分売却方法を解説
他の共有者に持分を買い取ってもらう(代償分割)
共有者の中に、その不動産を単独で所有したいと希望する人がいる場合は、その人に自身の持分を買い取ってもらう「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法があります。
たとえば、兄弟の一人が実家に住み続けたいと願っている場合、他の兄弟は自身の持分をその一人に売却し、代わりに適正な対価(代償金)を受け取ります。これにより、不動産を維持したい人の希望を叶えつつ、他の共有者は持分を現金化して共有関係から抜け出すことが可能です。
この方法が成立するかどうかは、持分を買い取る側に十分な資金力があるかどうかにかかっています。代償金の金額や支払い方法について、当事者間でしっかりと合意することが重要です。
関連記事:代償分割とは?メリット・注意点や手続きの流れを弁護士が徹底解説
関連記事:兄弟での不動産共有名義は危険?起こり得るリスク・解消方法を弁護士が解説
共有物分割請求訴訟で裁判所に判断を委ねる
共有者間での話し合いがどうしてもまとまらない場合の最終手段が、裁判所に共有物の分割方法を決めてもらう「共有物分割請求訴訟」です。
この訴訟を提起すれば、裁判所が当事者の主張や不動産の状況などを考慮し、最終的に「現物分割」「代償分割」「換価分割(競売)」のいずれかの方法で分割するよう命じる判決を下します。判決には法的な強制力があるため、相手が反対していても共有関係を確実に解消することが可能です。
ただし、訴訟は時間と費用がかかる上、裁判所が競売を命じた場合、市場価格より大幅に低い価格で売却されるリスクもあります。あくまで他の方法で解決できなかった場合の最終手段と位置づけ、慎重に検討すべきでしょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有者との固定資産税の支払いトラブルを弁護士に相談するメリット
固定資産税のトラブルは、法律や税金、不動産、そして家族間の感情が複雑に絡み合うため、当事者だけで解決しようとすると事態がこじれがちです。専門家である弁護士に相談することで、スムーズかつ有利に問題を解決できる可能性が高まります。
ここでは、弁護士に依頼する3つの大きなメリットを解説します。
代理人として交渉を任せられ、精神的負担を大幅に軽減できる
親族間の金銭トラブルは、大きな精神的ストレスを伴います。関係性の悪化を恐れて強く請求できなかったり、逆に些細な一言から感情的な対立に発展してしまったりすることも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人としてすべての交渉窓口になってもらえます。法的な観点から冷静かつ論理的に相手方と交渉を進めてくれるため、あなたは直接相手とやり取りする精神的な負担から解放されます。
第三者である専門家が間に入ることで、感情的な対立が緩和され、建設的な話し合いが進みやすくなる効果も期待できます。
法的根拠に基づき、立て替えた税金を適切に請求・回収できる
立て替えた税金を回収するには、求償権の行使、内容証明郵便の送付、支払督促や訴訟といった法的な手続きが必要です。これらの手続きを個人で行うには、専門的な知識が求められ、書類の不備があれば効果がなかったり、手続きが滞ったりするリスクがあります。
弁護士は、法律の専門家として、証拠に基づき法的に有効な請求を行います。求償権の時効管理はもちろん、相手の財産を調査し、最終的な強制執行による回収までを見据えて行動してくれます。
正当な権利を守り、回収の可能性を最大限に高められるのは、弁護士ならではの強みです。
「共有関係の解消」まで見据えた提案が受けられる
固定資産税のトラブルの根本原因は、「不動産が共有状態であること」にあります。目先の立て替え金回収だけでなく、将来にわたって同様のトラブルが再発しないよう、共有関係そのものを解消することまで視野に入れた解決策を提案できるのが、弁護士に相談する最大のメリットの一つです。
希望や他の共有者の状況を総合的に判断し、持分売却、共有物分割請求訴訟など、適切で有利な解決策を提示し、その実現までをサポートしてくれます。
共有関係の解消については、以下の記事でも具体的に解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有名義を解消する方法とは?費用・手続き・リスクもわかりやすく解説



一時的な問題解決ではなく、将来の安心を手に入れるための最適な道筋を示してくれるでしょう。
固定資産税の共有者トラブルに関するよくある質問
ここでは、固定資産税の共有者トラブルに関して、多くの方が抱く疑問点について回答します。正しい知識をもつことで、不要な不安を解消し、適切な次の一歩を踏み出しましょう。
納税通知書の代表者を変更することは可能?
納税通知書の代表者を変更することは可能です。固定資産税の納税通知書が送付される代表者は、共有者間の話し合いで決められます。
代表者を変更したい場合は、不動産の所在地を管轄する市区町村の役所(資産税課など)に「固定資産税納税義務者(代表者)変更届」を提出することで手続きができます。
ただし、代表者を変更しても、他の共有者の連帯納税義務がなくなるわけではない点に注意が必要です。
共有者が自己破産した場合、立て替えた税金は請求できる?
共有者が自己破産した場合、請求することは困難です。
破産手続きが開始されると、他の借金と同様に、裁判所の手続きを通じて配当を受けられる可能性がありますが、全額が返ってくるケースは稀です。
多くの場合、ほとんど回収できないまま免責が確定してしまいます。
共有持分を放棄すれば納税義務はなくなる?
共有持分を放棄しても、納税義務はなくなりません。共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属することになります。
共有関係からは離脱できますが、放棄した年の1月1日時点では所有者であったため、その年度分の固定資産税の納税義務は残ります。
また、持分放棄は単独で行えますが、登記手続きには他の共有者の協力が必要となるため、関係性が悪化している状況では現実的な解決策とはいえません。
持分放棄について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
まとめ|共有不動産の固定資産税トラブルは専門家への早期相談が重要
この記事では、共有者が固定資産税を支払わない場合の法的な仕組みから、具体的な請求方法、そしてトラブルの根本的な解決策までを網羅的に解説しました。
共有不動産の固定資産税は、共有者全員に連帯納税義務があり、一人の滞納が全員のリスクに直結します。立て替えた場合は求償権を行使して請求できますが、それには時効があり、手続きも複雑です。
もし共有者との話し合いに行き詰まりを感じたり、法的な手続きに不安を感じたりした場合は、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家に相談しましょう。



専門家の力を借りて、一日も早く金銭的・精神的な負担から解放されることが大切です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









