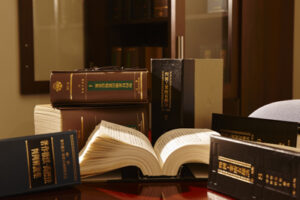【無料相談受付中】24時間365日対応
換価分割とは?メリットや適しているケース・よくあるトラブル例を徹底解説

「遺産が実家しかないけど、兄弟でどうやって公平に分ければいいんだろう?」
「不動産を売ってなんとかしたいけど、手続きが複雑そうで不安…」
遺産が不動産中心だと「どう分ければ公平か」が最大の課題になります。兄弟間で不公平感が生じると、相続トラブルに発展しかねません。
この記事では、不動産などの遺産を売却して現金で分ける「換価分割」について、その仕組みからメリット・注意点、具体的な手続きの流れまで解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫換価分割がご自身の状況に最適な選択肢なのかを判断できるようになるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
換価分割とは
換価分割は、不動産のように物理的に分けにくい財産を公平に分割するための有効な手段の一つです。
しかし、他の分割方法との違いを理解し、その特性を把握しなければ、思わぬ不利益を被る可能性もあります。
まずは基本的な知識を整理し、遺産分割全体における換価分割の位置づけを正確に理解しましょう。
換価分割とは|不動産などを売却して現金で分ける方法
換価分割(かんかぶんかつ)とは、不動産や株式といった遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人間で分配する方法です。「価値に換えて分割する」という文字どおりの意味を持ちます。
たとえば、遺産が評価額3,000万円の土地のみで、相続人が子ども3人だったとします。この土地を売却して得られた現金(諸経費を差し引いた後)を、3人で1,000万円ずつ分けるのが換価分割です。
この方法は、物理的に分けられない財産であっても、1円単位で公平に分割できるという明快さがメリットです。相続人の誰もその不動産を必要としていない場合や、相続税の納税資金を確保したい場合などに特に有効な選択肢となります。
現物分割・代償分割・共有分割との違い
遺産分割には、換価分割以外にも主に3つの方法があります。それぞれの特徴を比較し、どの方法が自分の状況に適しているかを見極めることが重要です。
| 分割方法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 遺産をそのままの形で各相続人に割り当てる方法。(例:妻が不動産、長男が預貯金) | ・手続きが比較的シンプル ・財産をそのまま残せる | ・各相続人の取得価値に差が出やすく不公平になりがち ・土地を分筆すると価値が下がる可能性がある |
| 代償分割 | 特定の相続人が不動産などを取得し、他の相続人に代償金を支払う方法。 | ・財産を売却せずに残せる ・金銭で調整するため公平を保ちやすい | ・財産を取得する相続人に十分な資力が必要 ・財産の評価額で揉める可能性がある |
| 換価分割 | 遺産を売却して現金化し、その現金を分配する方法。 | ・1円単位で公平に分割できる ・納税資金を確保しやすい | ・思い出の財産が失われる ・売却に手間や費用がかかる |
| 共有分割 | 一つの財産を複数の相続人で共有名義にする方法。 | ・一時的に公平に見える ・分割協議がまとまらない場合の一時的な解決策になる | ・将来の売却や活用に全員の同意が必要で、トラブルの元凶になりやすい |
これらの方法の中で、共有分割は将来のトラブルリスクが非常に高いため、原則として避けるべき選択肢とされています。



まずは現物分割や代償分割が可能かを検討し、それが難しい場合には換価分割を検討するとよいでしょう。
また、どの分割にするべきか悩んでいる人は、一度弁護士に相談してみることも一つです。専門家の意見を取り入れることで、自分では気づけなかった解決策が見つかる可能性があります。
共有分割について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:共有持分とは?所有するリスクや主なトラブル事例、回避策を解説
関連記事:代償分割とは?メリット・注意点や手続きの流れを弁護士が徹底解説
換価分割の4つのメリット
換価分割は、特に相続財産が不動産中心の場合に、他の方法では得られない多くのメリットをもたらします。
ここでは、換価分割が持つ4つの主要なメリットを詳しく見ていきましょう。
以下、それぞれ具体的に解説します。
相続人間で公平に分割しやすい
換価分割の最大のメリットは「公平に分けられる」ことです。
兄弟姉妹の誰かが「自分だけ損をしている」と感じにくく、感情的なしこりを残さずに済みます。結果として、親族関係の悪化を防ぎ、トラブル回避につながります。
現物分割では、どの財産を誰が取得するかで価値に差が生まれ、不公平感からトラブルに発展しがちです。代償分割でも、不動産の評価額をめぐって意見が対立することは少なくありません。
その点、換価分割は「実際に売れた金額」という客観的で誰もが納得せざるを得ない基準で分配するため、「自分の取り分が少ない」といった不満が出にくく、円満な解決につながりやすいのです。相続人間の関係性が複雑な場合でも、感情的なしこりを残さずに手続きを進められる合理的な方法といえるでしょう。
相続税の納税資金や諸経費を確保できる
相続税の納税資金を確保できることも、換価分割の大きなメリットです。相続税は、原則として相続開始を知った翌日から10か月以内に現金で一括納付しなければなりません。
遺産の大部分が不動産で、手元に十分な現金がない場合、納税資金の準備は深刻な問題となります。納税のために金融機関から借り入れをしたり、他の資産を慌てて売却したりする必要に迫られるかもしれません。
換価分割を選択すれば、遺産である不動産を売却して得た代金から、そのまま相続税や、売却にかかる仲介手数料などの諸経費を支払うことが可能です。これにより、相続人が自己資金から多額の現金を準備する必要がなくなり、納税に関する精神的・経済的な負担を大幅に軽減できます。
出典:国税庁|相続税の納付
特定の相続人が代償金を準備する必要がない
代償分割を行う場合、不動産などを取得する相続人が、他の相続人に対して自己の財産から代償金を支払う必要があります。不動産の価値が高額な場合、代償金も数千万円にのぼることがあり、支払い側の相続人に相当な資力がなければ実現は困難です。
一方、換価分割では、このような特定の相続人への資金的な負担は発生しません。遺産そのものを売却した代金が分配の原資となるため、誰も自己資金を用意する必要がありません。
相続人の中に不動産を取得したいという強い希望がなく、かつ代償金を支払えるほどの資力を持つ人もいない、というケースは非常に多く見られます。このような状況において、換価分割はすべての相続人にとって負担が少なく、現実的で実行可能な解決策となるでしょう。
不動産の評価額をめぐる争いが起きない
遺産分割におけるトラブルの火種の一つが、不動産の評価額です。
代償分割を行う場合、代償金の額を算出するために不動産の価値を決める必要があります。用いる評価基準(時価、相続税評価額、固定資産税評価額など)によって金額が大きく異なるため、相続人間の利害が対立し、協議が紛糾しがちです。
換価分割の場合、「実際に売却できた価格」が分割の基準となるため、評価額をめぐる争いそのものが発生しません。市場での取引価格という客観的な数値をベースにするため、相続人全員が納得しやすいでしょう。
不動産の評価という専門的で複雑なプロセスを省略できるため、協議の長期化を防ぎ、スムーズな遺産分割を実現する上で大きなメリットといえます。
換価分割をする際の注意点
換価分割は公平で分かりやすい方法ですが、メリットばかりではありません。税金の問題や市場の不確実性など、事前に理解しておくべき注意点も存在します。
これらのリスクを軽視すると、期待していた結果と大きく異なる事態になりかねません。必ず確認して参考にしてみてください。
譲渡所得税などの税金が発生する可能性がある
換価分割のために不動産を売却し、利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税と住民税、復興特別所得税が課税されます。これは、相続財産を「売却」するという行為によって生じる税金であり、相続税とは別に納付が必要です。
譲渡所得は、「売却価格」から「取得費(被相続人がその不動産を購入したときの価格など)」と「譲渡費用(仲介手数料など)」を差し引いて計算されます。
被相続人が不動産をかなり昔に購入していて取得費が不明な場合や、土地の価値が購入時より大幅に上昇している場合は、高額な税金が発生する可能性があります。
ただし、一定の要件を満たせば、税負担を軽減できる特例制度もあります。税務リスクを正確に把握せずに売却を進めると、手残りが想定より大幅に少なくなる恐れがあるため、注意が必要です。
弁護士などの専門家に相談し、適切に手続きを進めるようにしましょう。
出典:国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
出典:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
希望の価格で売れない場合がある
不動産を売却する以上、必ずしも希望どおりの価格で売れるとは限らないという市場リスクをともないます。不動産市況の変動、物件の立地や状態、売却を急ぐ必要性の有無など、さまざまな要因が売却価格に影響します。
相続税の納税期限が迫っているなどの理由で売却を急ぐと、買い手から足元を見られてしまい、市場価格よりも安い価格で手放さざるを得ない状況に陥ることも考えられます。
また、そもそも買い手が見つからず、長期間売れ残ってしまうリスクもゼロではありません。売却が長期化すれば、その間の固定資産税などの維持管理費も負担し続けなければなりません。換価分割を計画する際は、このような不確実性を考慮し、時間に余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
仲介手数料や登記費用などの諸経費がかかる
不動産を売却する際には、さまざまな諸経費が発生します。これらは売却代金から差し引かれるため、相続人が手にする金額に直接影響します。
主な諸経費としては、以下のようなものが挙げられます。
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬 |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙代 |
| 登記費用 | 相続登記や抵当権抹消登記などにかかる登録免許税と司法書士への報酬 |
| その他 | 測量費用、建物の解体費用、遺品整理費用など |
これらの諸経費は、不動産の価格によっては合計で100万円を超えることも珍しくありません。売却によってどれくらいの現金が手元に残るのかを試算する際には、これらの費用を漏れなく計算に入れる必要があります。
思い出のある資産を手放すことになる
換価分割は、被相続人が遺した財産を物理的に失うことを意味します。特に、家族で暮らした実家など、金銭的な価値だけでは計れない「思い出の詰まった資産」を手放すことになる点はデメリットかもしれません。
相続人間の経済的な公平性を優先するあまり、家族の想いを軽視してしまうと、後々になって「売らなければよかった」という後悔や、家族間の感情的なしこりを残す原因になり得ます。
換価分割を選択する前には、相続人全員で「本当にこの財産を売却してもよいのか」という点について、十分に話し合うことが不可欠です。



経済的な合理性だけでなく、家族それぞれの感情にも配慮し、全員が心から納得した上で手続きを進めることが、円満な相続の鍵となります。
換価分割について不安がある方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。弁護士に相談することで、注意点や対策なども教えてくれます。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
換価分割が適しているケース
換価分割は、どのような状況でも最適な選択肢となるわけではありません。しかし、特定の条件下では、他のどの方法よりもスムーズで公平な解決をもたらします。
ご自身の状況が以下のケースに当てはまるかどうかを確認し、換価分割を検討する際の参考にしてください。
相続人の誰も不動産を必要としていないケース
相続財産である不動産(実家など)について、相続人の誰もが居住や利用を希望していない場合、換価分割は合理的な選択肢となります。
たとえば、相続人がすでに全員持ち家を持っており、実家に戻る予定がないケースや、実家が遠方にあり管理が難しいケースなどがこれに該当します。
誰も必要としていない不動産を無理に誰かが相続したり、共有名義で持ち続けたりしても、固定資産税や維持管理費の負担だけが重くのしかかり、将来的なトラブルの原因になりかねません。
このような場合、速やかに売却して現金で分けることで、不要な資産を整理し、各相続人が自由に使える資金を確保できます。全員の利害が一致しやすいため、スムーズに合意形成に至る可能性が高いでしょう。
共有名義の不動産で発生する可能性のあるトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有名義の不動産売却はトラブルに要注意!回避策とスムーズに売る方法
相続税の納税資金が必要なケース
遺産の大部分が不動産であり、相続税を支払うための現金が不足している場合、換価分割は極めて有効な手段となります。
前述のとおり、相続税は原則として現金での一括納付が求められ、期限は相続開始を知った翌日から10か月以内と非常にタイトです。
この期限内に納税資金を準備できないと、延滞税というペナルティが発生してしまいます。
換価分割を選択すれば相続した不動産そのものを売却して納税資金に充当できるため、相続人が自己資金から多額の現金を用意したり、不利な条件で借り入れをしたりする必要がありません。
相続税の支払いが困難と予想される状況では、遺産分割協議の早い段階で換価分割を視野に入れ、計画的に売却活動を進めていくことが重要です。
相続財産を公平に分けたいケース
相続人間の関係性などから、1円単位での厳密な公平性を重視したい場合にも、換価分割は適しています。
たとえば、法定相続分どおりにきっちりと分割することを望む場合や、相続人間で特定の財産の評価額について意見がまとまりそうにない場合です。現物分割や代償分割では、どうしても不動産等の評価をめぐる対立が生じやすくなります。
その点、換価分割は「実際に売れた金額」という客観的な数値を基に分配するため、評価をめぐる主観的な争いを完全に排除できます。
相続トラブルを避け、後腐れのない明確な形で遺産分割を完了させたいと考える家族にとって、納得感を得やすい方法といえるでしょう。
他の分割方法を選択した方がいいケース
換価分割は公平に分割しやすい反面、資産の売却が前提となるため、必ずしも最善の選択とは限りません。
相続財産の種類や相続人の希望によっては、現物分割や代償分割など、他の方法を検討した方が円満な解決につながるケースがあります。
以下、それぞれ具体的に解説します。
相続人の誰かがその不動産に住み続けたいケース
被相続人と同居していた、あるいは特定の相続人がその不動産に強い愛着があり、今後も住み続けることを希望している場合、換価分割は適していません。
換価分割は不動産を売却して代金を分割する方法であり、住居を失うことになるためです。
このようなケースでは、その不動産に住み続けたい相続人が物件を単独で相続し、他の相続人に対して法定相続分に相当する現金(代償金)を支払う「代償分割」が有効な選択肢となります。
この方法であれば、住み慣れた家を守りつつ、他の相続人も公平に自身の権利分を受け取ることができます。
ただし、不動産を相続する側に、代償金を支払うための十分な資力が必要になる点が課題です。
事業用の不動産や賃貸物件を相続するケース
相続財産に事業用の店舗や工場、あるいは家賃収入を生む賃貸アパートなどが含まれる場合、安易に換価分割を選ぶべきではありません。
これらの不動産は、将来にわたって収益を生み出す可能性のある重要な資産です。売却してしまえば、その収益源を永久に失うことになります。
もし相続人の誰かが事業を引き継ぐ意思があるなら、その相続人が事業用不動産を相続する「現物分割」や、他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」を検討するとよいでしょう。
これにより、事業を継続しながら相続人間の公平も保てます。
賃貸物件の場合も同様に、売却せずに共同で所有を続けるか、代表者が相続して他の相続人へ代償金を支払う方法で、長期的な収益を確保することを優先するのが賢明でしょう。
複数の不動産や預貯金などさまざまな財産があるケース
遺産の内容が自宅不動産だけでなく、別の土地やマンション、有価証券、十分な預貯金など多岐にわたる場合は、換価分割以外の方法で柔軟に対応できる可能性が高いです。
たとえば、「長男が自宅を、次男が賃貸マンションを相続し、評価額の差額は預貯金で調整する」といった「現物分割」が可能になります。
この方法の大きなメリットは、資産を売却する必要がないため、不動産会社への仲介手数料や譲渡所得税といったコストが発生しない点です。
それぞれの相続人の希望やライフプランに合わせて資産を組み合わせることで、時間や費用を節約し、全員が納得する形での分割が実現しやすくなります。
わざわざ全ての資産を現金化する手間をかける必要はありません。
【ステップで解説】換価分割の手続きの流れ
換価分割を円滑に進めるためには、正しい手順を踏むことが不可欠です。
ここでは、相続人同士の合意形成から現金の分配まで、換価分割を行う際の具体的な流れを5つのステップに分けて分かりやすく解説します。
各ステップでやるべきことを正確に理解し、計画的に進めていきましょう。
ステップ1:遺産分割協議で相続人全員の合意を得る
まず行うべきことは、法定相続人全員による「遺産分割協議」です。この協議で、遺産を換価分割するという方針について、全員の合意を得る必要があります。一人でも反対する人がいれば、協議では換価分割は実行できません。
この段階で重要なのは、なぜ換価分割が最善の選択肢なのか、その理由やメリットを丁寧に説明し、全員の理解と納得を得ることです。売却の必要性、公平性、納税資金の確保といった観点から話し合いを進めましょう。
また、売却活動を誰が主導して行うか、不動産会社の選定はどうするか、売却価格の目標をどの程度に設定するかといった、具体的な進め方についても、この時点で大まかなコンセンサスを形成しておくと、後の手続きがスムーズになります。
ステップ2:換価分割の内容を盛り込んだ遺産分割協議書を作成する
相続人全員の合意が固まったら、その内容を法的に有効な書面である「遺産分割協議書」として作成します。この書類は、相続後の不動産登記や税務申告など、あらゆる手続きで必要となるため、極めて重要です。
換価分割を行う場合の遺産分割協議書には、通常の記載事項に加え、以下の点を必ず明記する必要があります。
- 対象となる財産を換価分割すること
- 売却代金の具体的な分配割合(例:各2分の1ずつ)
- 売却にかかる諸経費(仲介手数料、税金など)の負担方法
- 売却手続きの担当者(代表者)
これらの記載が曖昧だったり、欠けていたりすると、後々のトラブルの原因や、税務署から予期せぬ課税を受けるリスクにつながります。相続人全員が内容を確認した上で、署名し、実印を押印しましょう。
以下の記事では、相続人で遺産分割協議がまとまらない場合の対処法について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
ステップ3:不動産の名義を相続人へ変更する(相続登記)
不動産を売却するためには、その前提として、亡くなった被相続人の名義から相続人の名義へと変更する手続き(相続登記)を法務局で行う必要があります。
相続登記には、遺産分割協議書や被相続人・相続人全員の戸籍謄本など、多数の書類が必要です。名義は、相続人全員の共有名義にするか、売却手続きの代表者一人の単独名義にするかのいずれかが一般的です。どちらにするかによって遺産分割協議書の書き方や税務上の扱いが若干異なるため、事前に決めておく必要があります。
なお、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。換価分割を進める上でも必須の手続きですので、速やかに行いましょう。
ステップ4:不動産会社等に依頼し、資産を売却する
相続登記が完了したら、不動産の売却活動を開始します。一般的には、信頼できる不動産会社に仲介を依頼し、売却を進めることになります。
不動産会社の選定は、売却の成否を左右する重要なポイントです。複数の会社から査定を取り、担当者の対応や販売戦略などを比較検討して慎重に選びましょう。
不動産会社と媒介契約を締結した後は、購入希望者の内覧対応や価格交渉などを行います。相続人全員が売却の方針について情報を共有し、協力して進めることが、よりよい条件での売却につながります。無事に買い手が見つかり、条件がまとまれば、売買契約を締結し、物件の引き渡しと代金の決済を行います。
ステップ5:売却代金から諸経費を差し引き、相続人で分配する
売買代金の決済が無事に完了したら、最終ステップとして現金の分配を行います。
まず、受け取った売却代金の中から、不動産会社への仲介手数料や登記費用、印紙税といった売却にかかった諸経費をすべて支払います。譲渡所得税が発生する場合は、その納税資金も確保しておく必要があります。
これらの諸経費をすべて差し引いて手元に残った金額を、遺産分割協議書で定めた分配割合に従って、各相続人に分配します。分配が完了すれば、換価分割に関するすべての手続きは終了です。



適切に手続きを進めたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
換価分割の遺産分割協議書に記載すべき項目
換価分割を円滑かつ安全に進めるために重要なのが「遺産分割協議書」です。
具体的には、以下の項目を網羅的に記載する必要があります。
- 被相続人の情報(氏名、最後の住所、死亡年月日など)
- 相続人全員の合意(相続人全員が協議に参加し、合意した旨)
- 換価分割の対象となる財産の特定(不動産の場合は登記事項証明書どおりに正確に記載)
- 財産を換価分割する旨の明確な意思表示
- 売却手続きの担当者(代表者)の指定(誰が責任を持って売却を進めるか)
- 売却代金の分配割合(法定相続分どおりか、特定の割合かなどを明記)
- 売却にかかる諸経費(仲介手数料、税金等)の負担方法
- 遺産分割協議書に記載のない他の財産の取り扱い
- 相続人全員の署名と実印の押印
- 作成年月日
この書類の内容に不備があると、後々のトラブルや予期せぬ税金問題に発展しかねません。記載すべき項目を正確に理解し、抜け漏れのない協議書を作成することが極めて重要です。
記載項目に不安がある場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。弁護士に相談することで、遺産分割協議書を適切に作成するためのアドバイスが受けられます。



まずは無料相談で相談してみて、親身に対応してくれるかどうかを確認することが大切です。
換価分割の遺産分割協議書の書き方
換価分割を行う際の遺産分割協議書の書き方は、売却の前提となる相続登記を「共同名義」で行うか、「代表者一人の単独名義」で行うかによって、記載のポイントが異なります。特に単独名義の場合は、贈与税課税のリスクを避けるために細心の注意が必要です。
相続人が共同で名義変更(共同登記)する場合
相続人全員の共有名義で相続登記を行った上で売却する方法は、安全でトラブルが少ない方法とされています。この場合、遺産分割協議書には、まず対象の不動産を法定相続分などの割合で共有取得する旨を記載し、その上で、その不動産を売却して代金を分配する旨を記載します。
【記載例】
第〇条 相続人A(持分1/2)、相続人B(持分1/4)、および相続人C(持分1/4)は、別紙物件目録記載の不動産を、上記持分割合にて共有で相続する。
第〇条 相続人全員は、前条の不動産を売却(換価)し、その売却代金から諸費用を控除した残額を、前条記載の各持分割合に応じて分配する。
この方法のメリットは、各相続人が自身の持分に応じて譲渡所得税の申告を行うため、税務上の処理が明快である点です。
ただ、完全にトラブルがないわけではありません。共有名義の不動産を売買する際に起こりうるトラブルについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:共有名義不動産は売却できない?よくあるトラブルと持分売却方法を解説
代表者一人の名義に変更(単独登記)する場合
手続きの煩雑さを避けるため、相続人のうちの一人を代表者として、その人の単独名義で相続登記をしてから売却するケースもあります。この方法は手続きがシンプルになる反面、遺産分割協議書の書き方を間違えると、代表者から他の相続人へ「贈与」があったとみなされ、高額な贈与税が課されるリスクがあります。
このリスクを避けるためには、遺産分割協議書に以下の3点を必ず明記しなければなりません。
- 登記名義は便宜上、代表者一人のものとすること
- 真の目的は換価分割であること
- 売却代金の具体的な分配割合
【記載例】
第〇条 相続人A、B、Cは、別紙物件目録記載の不動産を換価分割の便宜のため、相続人Bが単独で相続取得することに合意する。
第〇条 相続人Bは、前条の不動産を速やかに売却し、その売却代金から諸費用を控除した残額を、相続人A、B、Cがそれぞれ1/3の割合で分配する。
適切な記載方法がわからない場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、換価分割の遺産分割協議書の作成をサポートしてくれます。
換価分割で必要な税金は?
換価分割を行う際には、主に以下の2種類の税金が関係してきます。
- 相続税
- 譲渡所得税
これらの税金は、それぞれ課税の対象や計算方法、申告時期が異なるため、混同しないよう正確に理解しておくことが重要です。特に譲渡所得税は、売却によって利益が出た場合に発生するもので、換価分割特有の税金といえます。
場合によっては、これらの税金の支払いで手残りが大きく減ってしまう可能性もあるため、事前にどのくらいの税金がかかるのかをシミュレーションしておくことが、換価分割を成功させるための鍵となります。
換価分割でよくあるトラブル例
換価分割は公平な分割方法ですが、不動産の売却という不確定要素を含むため、思わぬトラブルに発展することもあります。
事前に典型的なトラブル例を知っておくことで、対策を講じ、円満な解決を目指せます。ぜひ参考にしてみてください。
ケース1:不動産がいつまでも売れない
想定していた価格や期間で不動産が売れないケースは数多く存在します。市場の状況や物件の条件によっては、買い手がなかなか現れず、売却活動が長期化してしまうことがあります。
売却が長引くと、その間の固定資産税や管理費は相続人が負担し続けなければなりません。特に相続税の納税期限が迫っている場合、売却が間に合わなければ納税資金を別途用意する必要に迫られ、計画が大きく狂ってしまいます。
対策としては、不動産会社の査定を鵜呑みにせず、現実的な売却価格を設定することや、期限までに売れなかった場合の代替案(買取業者への売却など)を事前に話し合っておくことが重要です。
ケース2:相続人の一人が売却に非協力的
遺産分割協議で換価分割に合意したにも関わらず、いざ売却活動が始まると、相続人の一人が非協力的になるケースもあります。
たとえば、内覧の立ち会いを拒否したり、売買契約に必要な書類への署名・押印を拒んだりといった行動です。「やはり思い出の家を売りたくない」といった感情的な理由や、売却価格への不満などが原因となることが多いです。
一人の非協力によって、売却手続きは完全にストップしてしまいます。このような事態を防ぐためには、最初の遺産分割協議の段階で、売却に関する全員の意思をあらためて確認し、その合意内容を詳細に遺産分割協議書に残しておくことが不可欠です。
ケース3:売却価格や諸経費の負担をめぐり意見が対立
売却活動中の価格交渉や、売却後に判明した諸経費の負担割合をめぐって意見が対立することもあります。
たとえば、購入希望者から値下げ交渉があった際に、早く売りたい相続人と、少しでも高く売りたい相続人の間で意見が割れてしまうケースです。
また、売却後に建物の修繕費用や測量費用など、想定外の経費が発生した場合に、その負担を誰がどの割合で行うかで揉めることもあります。



こうしたトラブルを避けるためには、遺産分割協議書に「売却価格の最低ライン」や「経費の負担割合」について、できるだけ具体的に定めておくことが有効です。
換価分割でトラブルを防ぐためのポイント
換価分割は公平ですが、進め方によってはトラブルの種になります。
不動産の売却条件や税金の扱いなど、事前に相続人全員で詳細なルールを決め、「遺産分割協議書」に明記することが大切です。
「遺産分割協議書」に詳細な条件を明記する
遺産分割協議書には、不動産を売却して代金を分割する旨を記載するだけでは不十分です。
後のトラブルを避けるためにも、以下のように具体的な条件まで明記しましょう。
- 売却価格の下限
- 売却活動の期限
- 売却にかかる諸経費(仲介手数料、登記費用など)の負担割合
- 代表して手続きを進める人
上記の取り決めが曖昧だと、売却価格や時期を巡って意見が対立したり、経費の支払いで揉めたりする原因になります。
全員が納得した条件を詳細に書面に残すことで、安心して手続きを進められるでしょう。
売却活動の進捗はこまめに共有する
不動産の売却手続きは相続人の一人が代表して進めるのが一般的です。
しかし、他の相続人からすると、活動状況が見えにくく「いつまで経っても売れない」「安売りしようとしているのでは?」といった不安や不満を抱きがちです。
これを防ぐため、代表者は不動産業者からの報告、内覧の状況、購入希望者からの交渉内容などを、定期的に他の相続人へ共有しましょう。
手続きの透明性を確保することが、信頼関係を維持し、トラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。
「譲渡所得税」について全員が理解する
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」が課税されます。
換価分割では、相続人全員がそれぞれの法定相続分に応じた納税義務を負います。売却代金から経費を引いた額が手取りになると勘違いしていると、後から発生する税金の負担で揉めることになりかねません。
事前に税理士などの専門家に相談し、税額がいくらになるのか、いつまでに申告・納税が必要なのかを全員で正しく把握しておきましょう。
換価分割について弁護士に相談した方がいいケース
換価分割は、相続財産を売却して金銭で公平に分配する方法ですが、手続きの過程で相続人間の意見が対立し、トラブルに発展するケースは少なくありません。
以下のようなケースの場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
- 相続人同士の意見がまとまらず、対立している
- 不動産の評価額や売却方法で揉めている
- 相続人の一部が遠方に住んでいる、または非協力的である
- 売却後の税金や手続きに不安がある
特に、売却価格や時期、不動産業者の選定などで合意形成が難しい場合、感情的なしこりが残り、話し合いが進まなくなることがあります。また、相続人の中に行方不明者や非協力的な方がいると、売却手続き自体を進めることが困難です。
弁護士に依頼すれば、代理人として他の相続人との交渉を冷静に進め、法的な観点から最適な解決策を提示してくれます。売却後の譲渡所得税といった税務処理や、法的に有効な遺産分割協議書の作成も任せられるため、煩雑な手続きによる負担を軽減し、後のトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。



当事者間での解決が難しいと感じたら、早期に専門家である弁護士へ相談することを推奨します。
換価分割に関するよくある質問
換価分割を検討する中で生じるさまざまな疑問について解説します。具体的な疑問点を解消し、手続きへの不安を少しでも取り除きましょう。
換価分割する不動産がなかなか売れない場合はどうすればいい?
まずは、売れない原因を分析することが重要です。不動産会社と相談し、価格設定が市場と合っているか、物件の魅力が広告で十分に伝わっているかなど、販売戦略を見直しましょう。価格の引き下げや、リフォームによる価値向上、仲介を依頼する不動産会社の変更なども有効な対策です。
それでも売れない場合は、不動産会社による「買取」を検討するのも一つの手です。市場価格よりは安くなりますが、確実に現金化できるメリットがあります。相続税の納税期限が迫っているなど、時間的な制約がある場合に有効な選択肢となります。
換価分割の譲渡所得税は、誰がいつまでに支払う?
譲渡所得税は、不動産を売却した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、各相続人がそれぞれ確定申告を行い、納税します。
不動産を相続人の共有名義で登記して売却した場合は、各共有者が自身の持分割合に応じた譲渡所得を計算し、申告・納税します。
代表者一人の単独名義で売却した場合でも、遺産分割協議書で分配割合が定められていれば、その割合に応じて各相続人が納税義務を負うのが原則です。
納税資金は、分配された売却代金の中から支払うのが一般的ですが、申告と納税は各個人の責任で行う必要があることを覚えておきましょう。
亡くなった親が住んでいた家を売る場合、税金の特例は使える?
一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(通称:空き家特例)を利用できる可能性があります。
この特例が適用できれば、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することが可能です。
適用できるかどうかは個別のケースによるため、税務署や税理士などの専門家に事前に相談することをおすすめします。
出典:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
換価分割にかかる費用(仲介手数料など)は誰が負担する?
換価分割にかかる諸経費の負担方法に法的な決まりはなく、相続人同士の話し合いによって自由に決められます。
一般的には、売却代金からすべての経費を差し引き、残った金額を分配割合に応じて分けるという方法が公平でトラブルが少ないため、広く採用されています。この方法であれば、特定の相続人が一時的に費用を立て替える必要もありません。
重要なのは、どの費用を誰がどのように負担するのかを事前に明確に合意し、その内容を遺産分割協議書に明記しておくことです。曖昧なまま進めると、後々「言った、言わない」の争いに発展する原因となります。
まとめ|換価分割を円満に進めるには専門家への相談が重要
この記事では、換価分割の基本的な仕組みから、メリット・注意点、具体的な手続きの流れ、税金問題までを網羅的に解説しました。
換価分割は、分けにくい不動産などの遺産を、相続人間で公平に分割するための非常に有効な手段です。特に、相続人の誰もが不動産を必要としていない場合や、納税資金の確保が課題となる場合には、円満な相続を実現する上で強力な選択肢となり得ます。
しかし一方で、不動産の売却という不確定要素をともなうため、希望価格で売れないリスクや、譲渡所得税といった専門的な知識が不可欠な課題も存在します。
後悔のない相続を実現するためには、まずご自身の状況を正確に把握し、他の分割方法の可能性も含めて慎重に検討することが大切です。



なお、少しでも手続きに不安を感じたり、相続財産に不動産が含まれていたりする場合には、迷わず相続問題の専門家である弁護士に相談しましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応