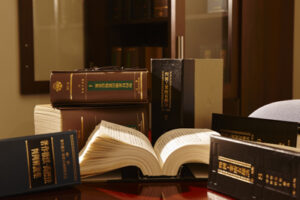【無料相談受付中】24時間365日対応
現物分割とは?メリット・デメリット、注意点や適しているケースを紹介〜手続きの流れや代償分割との違いは?

「実家を相続することになったけど、どう分ければいいんだろう…」
「財産をそのままの形で分けたいけど、不公平にならないか心配」
相続が発生したとき、上記のような悩みに直面する人は少なくありません。大切な家族が遺してくれた財産だからこそ、円満に、そして公平に分けたいと願うのは当然のことでしょう。
この記事では、遺産分割の基本的かつ一般的な方法である「現物分割」について、具体的な手続きやメリット、注意点を専門家の視点から徹底的に解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫将来の不動産相続トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
現物分割とは
現物分割は、遺産分割の基本となる考え方であり、すべての分割方法を検討する上での出発点となります。
まずは、現物分割の正確な定義と、遺産分割全体におけるその位置づけを深く理解することから始めましょう。
現物分割とは|財産をそのままの形で分ける方法
現物分割とは、相続財産を売却したり金銭に換えたりせず、その財産そのものを特定の相続人が取得する形で分割する方法を指します。
たとえば、「配偶者が不動産を、長男が株式を相続する」といったように、個々の財産をそのままの形で割り当てるのが一般的です。
この方法は、遺産分割の原則的な方法と位置づけられており、家庭裁判所での調停や審判においても、まず最初に検討される方法です。
土地のような財産の場合、一つの大きな土地を複数の土地に法的に分割(分筆)し、それぞれの土地を各相続人が取得する方法も現物分割の一種とされます。
他の遺産分割方法(代償分割・換価分割・共有分割)との違い
現物分割のほかにも、さまざまな分割方法が存在します。
- 代償分割(だいしょうぶんかつ)
- 換価分割(かんかぶんかつ)
- 共有分割(きょうゆうぶんかつ)
それぞれの特徴は、以下のとおりです。
| 代償分割(だいしょうぶんかつ) | 特定の相続人が法定相続分を超える価値の財産(たとえば不動産)を取得する代わりに、他の相続人に対して自己の資金から代償金(金銭)を支払うことで公平性を担保する方法です。 この方法は、財産を売却せずに特定の相続人が引き継ぎたい場合に有効ですが、財産を取得する側に十分な支払い能力があることが大前提となります。 |
|---|---|
| 換価分割(かんかぶんかつ) | 相続財産を市場で売却して現金化し、現金を相続人間で分配する方法です。この方法は、金銭によって明確に公平な分割が実現できるため、評価額で揉めるリスクを避けられます。 しかし、先祖代々の土地など、思い出の詰まった財産が永久に失われるという大きなデメリットを伴います。 |
| 共有分割(きょうゆうぶんかつ) | 遺産を複数の相続人の共有名義にする方法です。これは分割方法の合意ができない場合の最終手段であり、問題の先送りに過ぎない側面があります。 共有状態の不動産は、売却や大規模なリフォームなど重要な意思決定に共有者全員の同意が必要となり、将来的にさらに複雑なトラブルを生む温床となりがちです。 |
上記の分割方法は、それぞれ適しているケースが異なります。自分のケースの場合どれを選択すべきか悩んでいる場合は、一度弁護士に相談しましょう。
なお、共有分割した不動産については注意が必要です。以下の記事でよくあるトラブルや回避方法を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有名義不動産は売却できない?よくあるトラブルと持分売却方法を解説
関連記事:換価分割とは?メリットや適しているケース・よくあるトラブル例を徹底解説
現物分割をするメリット
現物分割が広く行われている分割方法であることには、明確な理由があります。ここでは、現物分割が持つ3つの主要なメリットを解説します。
手続きが比較的シンプルで費用を抑えやすい
現物分割の魅力の一つは、手続きの相対的なシンプルさです。
換価分割のように不動産会社と媒介契約を結び、買主を探し、売買契約を締結するといった一連の複雑なプロセスは不要です。
また、代償分割で求められるような、不動産の厳密な評価や代償金の算定、資金調達といった手間も原則として発生しません。
基本的な手続きは、遺産分割を行った上で、不動産であれば法務局で、預貯金であれば金融機関で、それぞれの財産の名義を変更することで完了します。
思い出の不動産などをそのままの形で残せる
現物分割は、相続財産に込められた家族の歴史や想いを尊重し、未来へと引き継ぐことを可能にします。
先祖代々受け継がれてきた土地や、家族が共に過ごした思い出深い自宅を、売却という形で手放すことなく、そのままの形で残せるためです。
金銭的な価値だけでは測れない、情緒的な価値を最優先したいと考える家族にとって、何物にも代えがたいメリットといえるでしょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
現物分割をする際の注意点
現物分割はシンプルで分かりやすい反面、そのシンプルさが故に多くの落とし穴が存在します。
ここでは、現物分割を選択する前に必ず理解しておくべき3つの重要な注意点を、具体的なリスクと共に解説します。
相続人間で不公平が生じやすい
現物分割が抱える根源的な問題は、各相続人の法定相続分と、個々の財産の価値を完全に一致させることが難しい点にあります。
現物分割は、法定相続分と財産の価値を一致させるのが難しく、不公平が生じやすい方法です。さらに、時間の経過による資産価値の変動で、後になって不満が生じるリスクもあります。
このような将来の変動可能性は、たとえ分割時に悪意がなかったとしても、長期的な不満やしこりを残す原因となり得るため注意が必要です。
土地を分筆すると価値が下がる可能性がある
相続財産である土地を相続人の数に応じて分筆し、それぞれが単独所有するという方法は、一見すると公平な現物分割に見えます。
しかし、一つの大きな土地を細かく分割することで、それぞれの土地が以下のようになる可能性があります。
- 小さく使い勝手の悪いものになる
- 不整形な土地や道路に接しない土地(無道路地)が生まれる
- 法的な規制によって価値の毀損が生じる
特に深刻なのは、法的な規制による価値の毀損です。
たとえば、分筆後の土地が、建築物を建てるために必要な道路への接道義務や、自治体が定める最低敷地面積の基準を満たさなくなった場合、その土地は「再建築不可物件」となり、資産価値が暴落してしまいます。
このように、分筆によって法的な制約が原因で価値が失われる可能性もあるため、注意が必要です。
物理的に分割できない財産には不向き
現物分割は、物理的に分割することが不可能な財産には適用できません。
一戸建ての家やマンションの一室、美術品といったものは、物理的に分割すればその価値自体が失われてしまうため、現物分割の対象とはなり得ません。
資産の持つ「機能」や「目的」を損なうような分割は、たとえ物理的に可能であっても避けるべきであり、これも現物分割の限界といえるでしょう。
こうしたリスクを避けるためには、早い段階で弁護士などの専門家に相談することが有効です。弁護士であれば、不動産の評価方法や税務上のリスク、法的な規制など、見落としがちなトラブルについて教えてくれます。
現物分割が適しているケース
現物分割には注意すべき点が多い一方で、特定の条件下では最もスムーズで円満な解決をもたらす優れた方法となります。
ここでは、現物分割が最適解となり得る3つの典型的なケースについて具体的に見ていきましょう。
以下、それぞれ具体的に解説します。
相続財産の種類が多く、公平に分けやすい場合
遺産の中に、複数の不動産・預貯金・株式・自動車など、多種多様な財産が含まれている場合、現物分割は有効な選択肢となります。
さまざまな価値を持つ財産を組み合わせることで、各相続人の取得する財産の合計額が、それぞれの法定相続分に近くなるように調整しやすくなるためです。
この調整を成功させる上で重要な役割を果たすのが、預貯金などの流動資産の存在です。現金は1円単位で正確に分割できるため、不動産や株式といった評価額に幅のある資産の価値の差を埋めるための「調整役」として機能します。
相続人全員が分割内容に納得している場合
相続において重要なのは、法的な正しさだけでなく、相続人全員が感情的に納得できる合意を形成することです。
たとえ各相続人が取得する財産の評価額が法定相続分と完全に一致していなくても、全員がその分割内容に心から同意しているのであれば、現物分割は最も円満な解決策となり得ます。
ただし、このような円満な合意であっても、その内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として書面で残しておくことが極めて重要です。
明確な書面を作成することで全員の合意を確定させ、将来のトラブル防止につなげられるでしょう。
とある財産を特定の相続人が引き継ぐことを全員が希望している場合
相続人全員の共通認識として、「この財産は、この人が引き継ぐべきだ」という希望がある場合、現物分割は効果的な方法です。
たとえば、被相続人が経営していた事業を長年手伝ってきた長男がその事業と関連資産を引き継ぐケースや、被相続人と最後まで同居し介護を担った次女がその自宅を引き継ぐケースなどが典型例です。
このような場合、相続人間の合意形成は比較的スムーズに進むことが多いでしょう。
しかし、その特定の財産の価値が他の財産に比べて著しく高い場合には、公平性の問題が浮上します。その財産を相続する相続人は、他の相続人に対して代償金を支払う「代償分割」を組み合わせる必要が出てくるかもしれません。



「価値」の大きさによっては、公平性を担保するために他の分割方法を組み合わせる柔軟な発想が求められます。
現物分割を選ぶか迷ったときの判断ポイント
現物分割は「財産をそのまま残せる」一方で、不動産が中心だと公平性や将来の価値変動に不安が残ることもあります。
判断する際は、以下の4つの項目を確認しましょう。
- 財産の種類や数が十分か
- 相続人全員の合意があるか
- 代償金などで公平性を担保できるか
- 将来の利用や価値変動に耐えられるか
不安があれば代償分割・換価分割も併せて検討するのが安全です。
現物分割以外の分割方法を検討すべきケース
現物分割は万能ではありません。遺産の状況や相続人間の関係性によっては、現物分割に固執することがかえって事態を悪化させ、深刻なトラブルを引き起こすことがあります。
現物分割の限界が露呈し、代償分割や換価分割といった他の選択肢を真剣に検討すべきケースは、以下のとおりです。
以下、それぞれ詳細に解説します。
遺産がほぼ自宅不動産のみなど分割しにくい場合
相続財産が「ほぼ自宅不動産のみ」というケースは現物分割が不得手とする典型的な状況です。
物理的に分割できない一つの家を複数の相続人で分けることは不可能であり、かつ特定の相続人のみが不動産を相続すれば不均衡です。このような状況に陥った家族は、厳しい「強制選択」を迫られることになります。
選択肢は主に以下の3つです。
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
1つ目は、誰か一人が家を相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」です。しかし、これには資金が必要となります。
2つ目は、家を売却して現金で分割する「換価分割」です。これは公平ですが、家族の思い出が詰まった家を失うことになります。
3つ目は、とりあえず共有名義にする「共有分割」です。これは問題を先送りするだけで、将来さらに大きなトラブルの火種を残します。
どの選択肢にもメリットとデメリットが存在します。家族は単なる経済的な計算だけでなく、それぞれのライフプランや家に対する想いといった感情的な側面も含めて、適切な解決策を模索しましょう。
なお、共有分割については以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:共有不動産の相続はどうなる?手続きの流れや共有名義のメリットデメリットを弁護士が解説
相続人の間で取得したい財産が重複している場合
遺産の中に複数の財産があったとしても、相続人の希望が特定の財産に集中してしまった場合、現物分割での解決は困難を極めます。
たとえば、兄弟それぞれが「親が住んでいた実家を自分が相続したい」と強く主張し、互いに譲らないケースがこれにあたります。このような希望の重複は、感情的な対立に発展しやすく、当事者間での話し合いが行き詰まる典型的なパターンです。
感情的なしこりが話し合いを妨げ、客観的な議論ができなくなるケースも少なくありません。この段階に至った場合は、速やかに弁護士などの第三者の専門家を交えることが賢明です。



専門家であれば、法的な観点から公平な解決策を提示し、感情的な対立を整理しながら交渉を前に進める手助けをしてくれるでしょう。
公平性を金銭で担保したい場合
相続人間の信頼関係や個々の事情よりも、「法定相続分に従った金銭的な公平性」を最優先事項と考える場合には、現物分割は最適な方法とはいえません。不動産や非上場株式などの資産は評価額に幅があり、どうしても価値の算定で曖昧さが残るためです。
もし、相続人全員が1円単位での厳密な公平性を望むのであれば、「換価分割」が適切な方法となります。すべての財産を売却して現金化すれば、その総額を法定相続分に従って正確に分配できるため、評価額を巡る争いは生じません。
また、特定の財産を残しつつも公平性を担保したいのであれば、「代償分割」が次善の策となります。このように、分割方法を選択する際は、家族が何を重視するかを考えることが大切です。
【ステップで解説】現物分割の手続きと流れ
現物分割を実現するためには、いくつかのステップを正確に踏む必要があります。
ここでは、現物分割を円滑に進めるための5つのステップを、具体的な注意点と共に解説します。
ステップ1:相続人全員で遺産分割協議を行う
すべての遺産分割手続きの出発点が、「遺産分割協議」です。
法定相続人全員が参加して、誰がどの財産を、どのような割合で相続するのかを話し合い、合意形成を行います。一人でも欠けた状態で行われた協議は法的に無効となるため、必ず全員が参加しなければなりません。
この段階で、現物分割を基本方針とする場合、具体的な財産の割り当てについて、全員の合意を得ることが目標となります。
円満な合意形成のためには、感情的な対立を避け、お互いの希望や事情を尊重しながら冷静に話し合う姿勢が大切です。
ステップ2:合意内容を遺産分割協議書にまとめる
遺産分割協議で合意した内容は、「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
この書類は、後の不動産登記(名義変更)や預貯金の解約手続きなど、あらゆる相続手続きにおいて必要となる重要な文書です。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
記載する財産の情報は、第三者が見ても明確に特定できるように、正確に記述しなければなりません。
たとえば、不動産の場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されているとおりに、以下の情報を一字一句間違えずに記載します。
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
預貯金であれば、以下の項目を正確に記載します。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座種別
- 口座番号
以下の記事では、遺産分割協議がまとまらない場合の対象について解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
ステップ3:【土地の場合】土地の測量・分筆登記を行う
相続財産に土地が含まれ、それを複数の相続人で分割してそれぞれが単独所有する場合は、「分筆登記」という手続きをしなければなりません。
ひとつの土地を複数に分け、それぞれに新しい地番を付与する作業のことです。
分筆登記の前提として、対象となる土地の境界が、隣接するすべての土地の所有者との間で確定していなければなりません。そのために、土地家屋調査士が行う「土地の測量」が必要になります。
隣地の所有者との間で境界について争いがあったり、協力が得られなかったりすると、手続きが大幅に遅延する可能性があるため注意が必要です。
ステップ4:不動産や預貯金の名義変更をする
遺産分割協議書が完成し、必要な場合は分筆登記も完了したら、次に行うのが各財産の名義変更手続きです。
不動産の場合は、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類を揃えて、管轄の法務局で所有権移転登記(相続登記)※を申請します。
手続きは、財産の種類ごとに管轄や必要書類が異なるため、一つひとつ丁寧に進めましょう。
※2024年4月1日以降は、相続人は不動産の相続取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となっています(正当理由なき不履行は10万円以下の過料)。
やむを得ず3年以内に分割確定が難しい場合は、相続人申告登記で義務を暫定履行できます。
ステップ5:相続税の申告と納税を行う
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。この手続きは、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内に行わなければなりません。
たとえ、小規模宅地等の特例などの適用によって最終的な納税額がゼロになる場合でも、その特例の適用を受けるためには申告自体は必要となるケースがほとんどです。
期限内に申告・納税を怠ると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されるため、注意が必要です。



相続税の計算は非常に複雑であるため、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
現物分割でよくあるトラブル
現物分割は、そのシンプルさゆえに、相続人間の感情的な対立や法的な知識不足が直接的なトラブルに結びつきやすいという側面を持っています。
公平な分割が難しいという構造的な問題に加え、予期せぬ法規制や将来の価値変動が、円満だったはずの家族関係に亀裂を入れることも少なくありません。
現物分割の過程で実際に起こりがちな3つの典型的なトラブルは、以下のとおりです。
ここからは、それぞれの原因と背景を詳しく解説します。
分割割合や評価額で揉めてしまう
現物分割では、多くの場合「評価」を巡るトラブルが発生します。
特に不動産は、一つの資産に対して複数の評価基準(相続税評価額、固定資産税評価額、時価など)が存在するため、どの基準を用いるかで評価額が大きく変動します。この評価額の曖昧さにより、相続人間の利害対立を生みやすいのが特徴です。
たとえば、不動産を現物で取得したい相続人は、代償金を少なくするために評価額を低く主張しがちです。一方で、代償金を受け取る側の相続人は、より多くの金銭を得るために評価額を高く主張するでしょう。
このように、それぞれの立場によって都合の良い評価基準を主張し合うため、話し合いが平行線をたどり、感情的な対立に発展してしまいます。
法律上の制限で土地の分筆ができない
土地の分筆は、所有者が自由にできるわけではなく、さまざまな法律や条例による厳しい制限を受けています。
たとえば、都市計画法によって市街化を抑制すべき区域と定められている「市街化調整区域」では、原則として開発行為が制限されており、安易な分筆は認められません。
また、多くの自治体では、良好な市街地環境を維持するために「最低敷地面積」を条例で定めており、これを下回るような小さな土地を生み出す分筆は不可能です。
これらの法規制を知らずに分割計画を進めてしまうと、手続きの最終段階で計画が白紙に戻り、相続人間の対立を再燃させる原因となります。
分割後に財産の価値に大きな差が生じる
遺産分割協議が円満に成立し、全員が納得して現物分割を行ったとしても、分割したそれぞれの財産の価値が、時間の経過とともに大きく変動してしまうケースも存在します。
たとえば、兄が相続した郊外の土地が、数年後に大規模なインフラ整備計画の対象となり、地価が急騰したとします。一方で、弟が相続した都心の中古マンションの資産価値が大きく下落した場合、分割時点では同程度の価値だったはずの財産に、数年で何倍もの格差が生まれます。
このような事態は、弟の中に「不公平だ」という強い感情を生み出し、一度は解決したはずの遺産分割に対して不満を抱かせ、家族関係に長期的な影を落とす原因となり得るでしょう。
複雑な現物分割は弁護士への相談も効果的!弁護士に依頼するメリット
現物分割は、一見シンプルに見える手続きの中に、法律、税務、不動産評価、そして家族間の感情といった複雑な要素が絡み合っています。
特に、相続財産に不動産が含まれる場合や、相続人間で意見の対立が見られる場合には、当事者だけの話し合いでは解決が困難になることが少なくありません。
このような状況では、相続問題の専門家である弁護士に相談することが大切です。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得られます。
以下、それぞれ具体的に解説します。
他の相続人との交渉を代理してくれ、精神的負担を軽減できる
相続人間の話し合いは、金銭的な利害だけでなく、長年の家族関係や感情的なしがらみが絡むため、冷静な議論が難しくなりがちです。
言いたいことがあっても、関係の悪化を恐れて口に出せなかったり、逆に些細な一言が感情的な対立を招いてしまったりすることも少なくありません。
弁護士に依頼することで、弁護士が代理人として他の相続人との交渉窓口となります。弁護士は、依頼者の意向を法的な観点から整理し、客観的かつ論理的に相手方に伝えることが可能です。
感情的なぶつかり合いを避け、冷静な交渉のテーブルを設けることで、問題の解決に集中できる環境を整えられます。
公平な分割を実現してくれ、将来のトラブルを防げる
弁護士は、単に交渉を代行するだけではありません。
不動産の評価方法や税務上のリスク、法的な規制など、一般の方が見落としがちな専門的な論点をすべて洗い出し、潜在的な不利益の可能性を教えてくれます。
さらに、将来起こりうるあらゆるリスクを想定して、法的に万全な内容の遺産分割協議書を作成してくれる点もメリットです。
協議後に新たな遺産が発見された場合の取り決めや、債務が見つかった場合の負担割合など、細部にわたって明確な条項を盛り込んでくれることで、後々の紛争の蒸し返しを防げます。
交渉が不調に終わった場合、調停や訴訟にスムーズに移行できる
相続人間の協議がどうしてもまとまらず、家庭裁判所での調停や審判といった法的手続きに移行せざるを得なくなるケースもあります。
交渉段階から関与している弁護士であれば、すでに事件の経緯や争点、各相続人の主張内容などを把握しています。
そのため、改めて一から事情を説明する必要がなく、速やかに調停申立書などの裁判所に提出する書類を作成し、法的手続きを開始することが可能です。
交渉から裁判まで一貫してサポートを受けることで、時間的・精神的なロスを最小限に抑えられるでしょう。
遺産分割調停の流れや注意点については、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:遺産分割調停を起こす際の流れや注意点、弁護士費用を解説



無料相談を実施している法律事務所も多いため、気軽に相談してみてください。
現物分割に関するよくある質問
現物分割について検討を始めると、具体的な財産の取り扱いや、万が一の事態への対処法など、様々な疑問が浮かんでくることでしょう。ここでは、多くの方が抱く代表的な質問に回答します。
預貯金や株式も現物分割の対象になる?
預貯金や株式も現物分割の対象です。
金融資産の現物分割は、資産を現金化することなく、口座や株式そのものの所有権を相続人が引き継ぎます。
株式は株数で、預貯金は金額で明確に分割できるため、不動産に比べて公平な分割がしやすい点が特徴です。
現物分割で不公平が出た場合の対処法は?
現物分割によって相続人間に取得する財産の価値に差が生じ、不公平感が出てしまう場合の対処法は、主に2つあります。
- 代償分割
- 換価分割
1つ目は、「代償分割」という方法を用いることです。価値の高い財産を取得した相続人が、自己の財産から他の相続人に対して代償金を支払います。
代償分割の場合、遺産分割協議書に「代償として金銭を支払う」旨を明確に記載することが重要です。この記載がないのに金銭を支払うと、単なる個人間の贈与とみなされ、贈与税が課されるリスクがあるため注意しましょう。
2つ目は、「換価分割」という方法も使用することです。これは、相続した不動産などの資産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分配する方法です。
物理的に分けられない資産でも、売却代金という形で分けるため、公平な分割が実現しやすいのが大きな特徴です。また、代償分割のように特定の相続人が自己資金を用意する必要がない点もメリットといえるでしょう。
土地を分筆せずに現物分割することは可能?
土地を分筆せずに現物分割することはできません。一つの土地(一筆の土地)を複数の独立した土地に分け、それぞれを別々の所有者の名義にするためには、「分筆登記」が必要です。
「分筆をしない」で土地を複数の相続人で相続すると「共有分割」となり、一つの土地を全員で共有名義で所有する状態となります。
土地を物理的に利用する上で区画を分けることはできても、権利としては全員が土地全体に対して持分を持つ状態のため、売却などの処分行為には共有者全員の同意が必要です。
以下の記事では、共有名義の不動産を解消する方法について解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
まとめ|現物分割は慎重な判断が求められるため、専門家に相談することが大切
この記事では、遺産分割の基本である「現物分割」について、メリットや注意点、具体的な手続きからトラブル事例までを解説してきました。
現物分割は、手続きが比較的シンプルで、思い出の財産をそのまま残せるという大きな利点を持つ一方で、土地の分割においては法的な制約や資産価値の変動といった深刻なリスクを伴います。
後悔のない選択をするためには、まず自身の状況を正確に把握することが大切です。遺産の内容をリストアップし、家族間で「財産を維持すること」と「金銭的な公平性を保つこと」のどちらを優先するのか、率直に話し合いましょう。
また、少しでも不安や疑問を感じたり、財産に不動産が含まれていたりする場合には、迷わず専門家へ相談することが大切です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応