【無料相談受付中】24時間365日対応
共有名義ローンは夫・頭金は妻の離婚における財産分与の問題点を解説
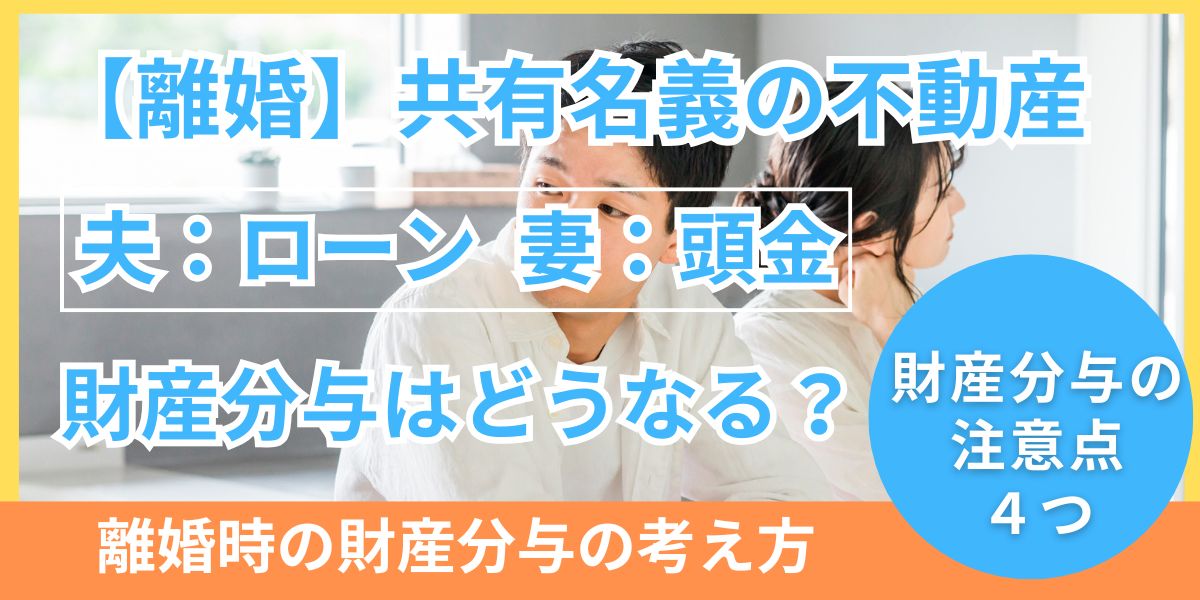
離婚の財産分与では、2分の1ずつの価値で財産を分けるのが原則です。
しかし、共有名義の不動産を財産分与する場合、妻が負担した頭金はどのように扱われるのでしょうか。
この記事では、ローンは夫・頭金は妻が負担した共有名義の不動産の財産分与を検討している方に向けて、次の内容について詳しく解説します。
共有不動産の財産分与をスムーズに進めるには、財産分与の基本ルールやローンや頭金がどのように扱われるかなどを理解しておけば、トラブルを防ぐことができます。
財産分与をめぐる問題を回避したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士法人アクロピースは、7000件以上の豊富な相談経験を活かしてサポートいたします。
\初回60分間の相談は無料/
受付時間:24時間365日対応
共有名義の不動産でローンは夫・頭金は妻の離婚では財産分与が問題となる
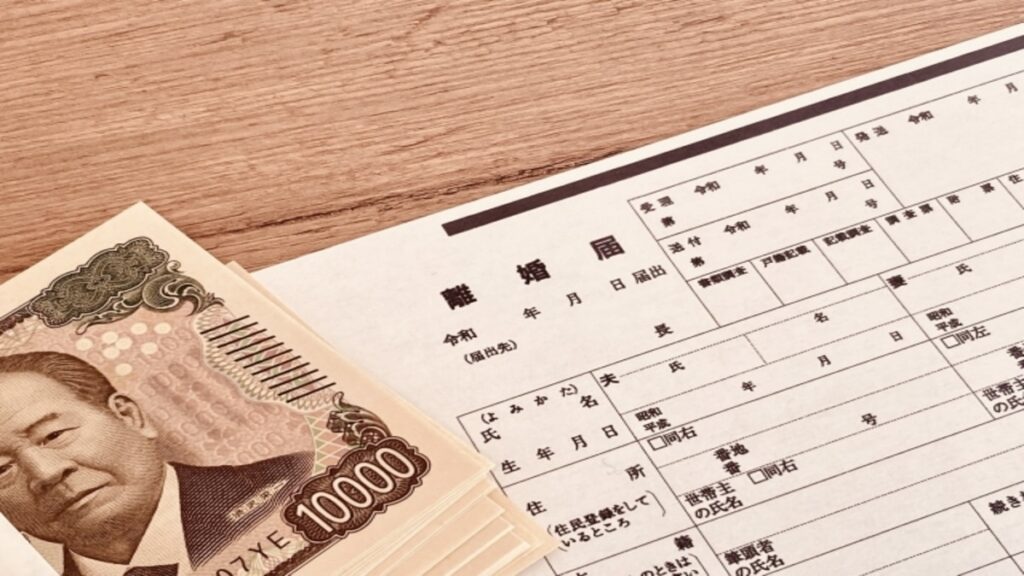
離婚の際に決めるべき条件としては、次のものが挙げられます。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割 など
このうち、自宅との関係で問題となる条件は財産分与です。
つまり、頭金は妻が負担し、ローンは夫が負担している共有名義の不動産を離婚の際にどのように扱うかは、財産分与の条件で決めるべき事項となります。
この記事では、他の離婚条件には影響がないものとして、ローンは夫・頭金は妻の共有不動産が財産分与においてどのように扱われるのかを解説していきます。
離婚の財産分与における基本的な考え方

離婚の際の財産分与は、夫婦の共同生活で築いた財産を公平に分配する制度です。
分配の割合は、夫婦の一方のみが収入を得ていたような場合でも特別な事情がない限り、2分の1ずつが原則となります。
夫婦が婚姻中に購入した共有名義の不動産は、夫婦の共同生活で築いた財産として財産分与の対象となります。
もっとも、特有財産については、財産分与の対象とはなりません。
婚姻前の預貯金や、婚姻後に夫婦生活とは関係のない贈与や相続によって取得した財産のこと
婚姻生活中の夫の給与は、夫婦の共同生活で築いた共有財産となります。
一方、妻が準備した頭金については、妻の特有財産に該当するケースもあるでしょう。
たとえば、妻が婚姻前の貯蓄から頭金を準備したケースでは、頭金は妻の特有財産に該当します。
共有名義の不動産におけるローンと頭金の財産分与における扱い

ここでは、共有名義の不動産におけるローンと頭金が離婚の財産分与における扱いについて、ローンと頭金に分けて詳しく解説します。
ローン負担分は共有財産と扱われるのが原則
ローン負担分は、夫婦の一方の給与から支出したものであっても、夫婦の共有財産として扱われるのが原則です。
婚姻生活中の給与は、どちらが稼いだものであっても夫婦の共有財産となります。
たとえば、夫がサラリーマン、妻が専業主婦の家庭であっても、夫の給与は夫婦が協力して築き上げた共有財産として扱われるのが原則です。
ただし、婚姻生活中に築いた財産であっても、夫が医師や弁護士などの資格を活かして高額の資産を築いたケースや、会社の代表取締役としての才覚で資産を形成したケースでは、2分の1ルールが修正される可能性もあります。
住宅ローンを夫の給与で負担していた場合でも、共有名義の不動産におけるローン負担分の価値は、特別な事情がない限り夫婦の共有財産となり、財産分与では2分の1ずつ分けられます。
頭金は特有財産として扱われるケースがある
共有名義の不動産を購入した際の頭金は、特有財産として扱われて財産分与の対象外となるケースがあります。
たとえば、頭金の500万円を妻の婚姻前からの貯蓄から支払ったケースや、妻が相続によって取得した財産から支払ったケースでは、頭金は妻の特有財産として扱われる可能性があります。
頭金が特有財産として扱われるのは、夫婦の一方が頭金全額を負担したケースだけではありません。
先ほどのケースで、頭金500万円のうち300万円を妻が婚姻前の貯蓄から支払い、残額の200万円を婚姻後の貯蓄で支払った場合であっても、妻が負担した頭金300万円は特有財産として扱われ、残りは共有財産となります。
頭金が特有財産の場合における財産分与

頭金が妻の特有財産と評価される場合であっても、購入時の頭金の価格がそのまま財産分与における評価額となるわけではありません。
財産分与時点の頭金の価値は、次の流れで算出できます。
計算の流れについて詳しく解説します。
家の購入価格に対する頭金の割合を計算する
まずは、不動産の購入価格に対する頭金の割合を計算します。
この段階では時間の経過による価値の変動は考慮せず、購入時点での価格そのままで計算します。
たとえば、不動産の購入価格が5000万円で頭金が1000万円の場合、頭金の割合は2割です。
頭金全額が妻の特有財産と扱われるケースでは、不動産の価値に対する妻の特有財産の割合が2割となります。
なお、頭金を一部のみ負担した場合については、一部のみ特有財産として扱い、その他は共有財産として財産分与を行います。
この場合でも、基本的な計算の流れは変わりません。
たとえば、先ほどのケースで妻が頭金のうち500万円を支出した場合、妻の特有財産の割合を1割として財産分与の計算を行います。
家の現在の価値に対する頭金の価値を計算する
次に、不動産の現在の価値に対する頭金の価値を計算します。
購入時から不動産の価値が上昇していれば頭金の価値も上昇しますが、下落していればその分だけ頭金の価値も下落します。
たとえば、購入価格5000万円の不動産が離婚時に4000万円に下落していたケースにおける、購入時1000万円の頭金の価値は次のとおりです。
4000万円×2割=800万円
つまり、不動産の購入時に妻が1000万円の頭金を支出していた場合でも、財産分与では1000万円全額ではなく800万円分が妻の特有財産として扱われます。
特有財産の価値を差し引いた価値で財産分与を行う
最後に不動産全体の価格から特有財産の価値を差し引いた価値で財産分与を行います。
先ほどのケースでは、離婚時における不動産の価格4000万円から、特有財産の価値800万円を差し引いた3200万円分が財産分与の対象となります。
不動産を原則どおり2分の1ずつで分けるのなら、財産分与としては夫婦それぞれが取得するのは1600万円分です。
結果的に、4000万円の不動産について、夫が1600万円分、妻が2400万円分(1600万円+800万円)を取得することになります。
なお、多くの場合、財産分与では不動産の共有状態を解消することになるでしょう。
つまり、先ほどのケースでは、夫が1600万円分、妻が2400万円分の割合で不動産を所有し続けるのではなく、不動産を売却したうえで代金を分けるか、他の財産で調整してどちらか一方の単独所有とするのが通常です。
共有名義の不動産における具体的な財産分与の方法

先ほども触れましたが、ローンと頭金との関係で財産分与における夫婦それぞれの取り分が決まったとしても、財産分与の具体的な内容は決まりません。
ここでは、不動産の名義を共有名義のままにしておくケースと、どちらか一方の単独名義にするケースに分けて、具体的な財産分与の方法を解説します。
共有名義のままにしておく
財産分与後に共有名義のまま所有し続けることも可能です。
たとえば、財産分与で妻が不動産の3分の2を取得し、夫が不動産の3分の1を取得するとした場合、財産分与で決まった割合に基づく共有名義で不動産を所有し続けることもできます。
しかし、離婚後も不動産を共有名義のままにしておくと、後に利用方法や処分方法をめぐるトラブルに発展する可能性があります。
なぜなら、共有名義の不動産については、双方の合意なしに処分行為ができなくなるためです。
どちらか一方の単独名義にする
離婚後も不動産を共有名義のままにしておくのはトラブルの原因となるため、基本的にはどちらか一方の単独名義とする方向で話を進めるのが良いでしょう。
どちらか一方の単独名義にする場合、相手方の取り分に相当するものを他の財産で調整する必要があります。
たとえば、4000万円の不動産について夫が1600万円、妻が2400万円の取り分があるケースで不動産を夫の単独名義とする場合、妻に分与すべき2400万円分について預貯金や株式などで調整することになるでしょう。
不動産の他に財産がなく財産分与の調整ができないときは、不動産の売却を検討することになります。
不動産を売却する場合は、双方の取り分に従って売却代金を分配すれば足りるため、簡単に財産分与を進められます。
共有名義の不動産を財産分与する際の注意点
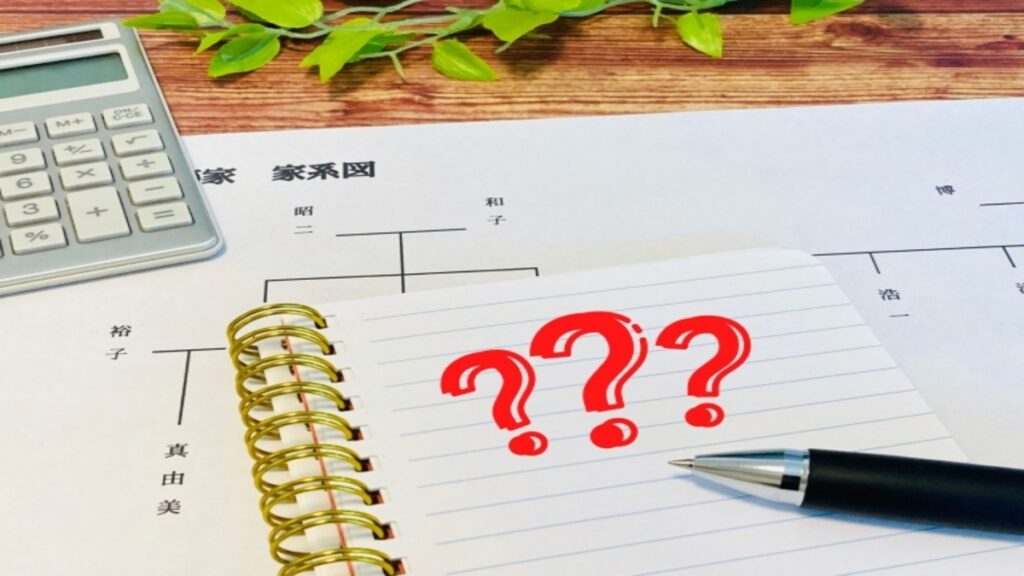
共有名義の不動産を財産分与する際は、次の4つの点に注意すべきです。
それぞれの注意点について詳しく解説します。
不動産の時価をめぐる争いが起こる可能性がある
不動産を売却する場合は、財産分与の割合に従って売却代金を分ければ足ります。
しかし、不動産を売却せずに所有し続ける場合、不動産の価値をめぐる争いが起こる可能性があります。
先ほどまでの説明は、不動産の時価が決まっていることを前提としていました。
ですが、実際の財産分与では、不動産の時価が決まらず、それぞれの取り分が明確にならないケースも少なくありません。
たとえば、財産分与で不動産を夫の単独名義とする場合、他の財産を妻に渡して財産分与の金額を調整する夫としては不動産の価値をできる限り低く見積りたいところです。
一方、妻としては、不動産の価値を高く見積り、調成分として取得する財産を多くしたいと考えるでしょう。
このとおり、不動産の財産分与では、それぞれの取り分を決める前提として不動産の価値そのものが争いの対象となる可能性がある点には注意が必要です。
特有財産に該当するか否かの争いが起こる可能性がある
ひと言に「頭金は妻が出した」と言っても、実際には特有財産に該当するか否かの判断が難しいケースもあります。
そのため、財産分与の取り分を決めるに際しては、そもそも頭金が特有財産に該当するか否かの争いが起こる可能性もあります。
たとえば、妻が自分名義の預金口座で家計を管理していた場合、頭金を婚姻後の収入から捻出したものなのか、婚姻前から持っていた貯金から捻出したものなのかを簡単に判断することはできません。
婚姻前の貯金や相続によって取得した財産、株式投資で得た収入などをまとめて管理していた場合、夫婦の共有財産と特有財産を明確に区別するのは難しいでしょう。
また、頭金が特有財産に該当すると主張する場合、通帳や契約書などの明確な証拠の準備が必要です。
ローンとの関係で名義変更できない可能性がある
財産分与の内容について夫婦間の合意ができたとしても、ローンとの関係で財産分与の内容に従った名義変更ができないケースもあります。
たとえば、夫がローンを負担している場合、財産分与で不動産を妻の単独名義にすると決めても、簡単に名義変更はできません。
夫がローンを負担した状態で妻のみが家に住み続けるとローン規約に違反するケースもあります。
ローン残高がある不動産の財産分与は、夫婦のみの意思では決められず、銀行との協議が必要となる可能性があります。
名義変更ができずに不動産を売却する場合については、こちらの記事も併せてご覧ください。
関連記事:共有不動産はどうしたら売却できるの?同意が必要なケースと持分の処分方法を解説
早い段階で弁護士に相談する
共有名義の不動産の財産分与では、さまざまな問題が起こるリスクがあります。
そのため、財産分与を進める際には、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すると、不動産の査定や特有財産についての証拠が必要となった際に、的確なアドバイスを受けられます。
銀行との交渉が必要な場面では、交渉を依頼することも可能です。
まとめ
今回は、ローンは夫・頭金は妻が負担した共有名義の不動産の財産分与を理解するために、次の内容について解説しました。
- ローン負担分は共有財産として扱われるが、頭金は妻の特有財産として扱われる可能性がある
- 財産分与の金額を算出する際は、頭金の価値も現在の価値に換算し直す必要がある
- 共有名義の不動産の財産分与は早めに弁護士に相談するとよい
共有名義の不動産の財産分与を進めたい方は、弁護士への相談をおすすめします。
無料相談ではトラブルを防ぐための方法についても詳しく説明させていただきます。
電話にて相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
\7000件以上の相談実績/
受付時間:24時間365日対応









