【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産の持分放棄とは?やり方や早い物勝ちの真偽、注意点・登記に必要な書類や費用を解説
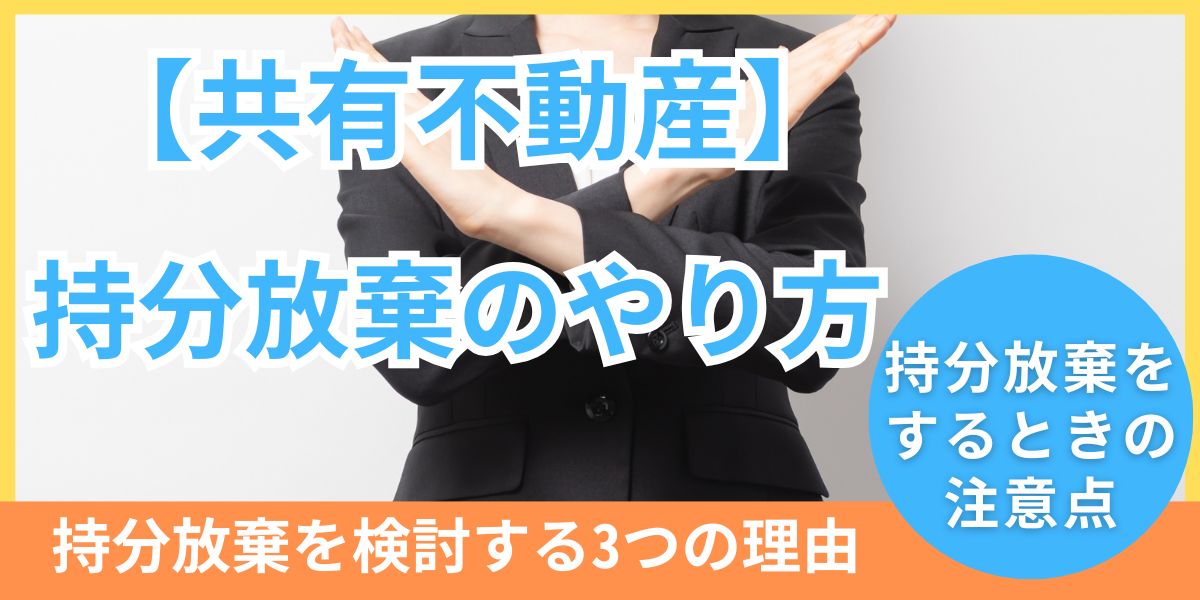
「相続した不動産の共有持分をどう扱えばいいのか悩んでいる」
「持分を放棄したいけれど、手続きや影響がわからず不安……」
共有不動産の持分を放棄したい方のなかには、このような不安を抱えている方がいるのではないでしょうか。
共有不動産の売却や活用は他の共有者の同意が必要ですが、持分の放棄は個人の判断で行えるものであり、他の共有者の同意は必要ありません。
本記事では、持分放棄で共有状態を解消するメリットやデメリット、弁護士に相談する利点を詳しく解説します。
持分放棄は「共有持分だけを一方的に手放す制度」:他の共有者の同意は不要で、放棄した持分は自動的に残りの共有者へ帰属するため、共有状態から単独で離脱できる。
「早い者勝ち」は半分本当:順次放棄は可能だが、最後の1人になると単独所有となり放棄できないため、タイミング次第で負担を一身に背負うリスクがある。
メリットは迅速性、デメリットは不可逆性:訴訟より早く負担を断てる一方、一度放棄すると将来価値が上がっても権利は一切取り戻せない。
税金・費用トラブルが起きやすい:登録免許税が発生し、取得側に贈与税が課税される場合もあるため、事前の税務整理が不可欠。
登記非協力=紛争化の分岐点:共有者が登記に応じない場合は訴訟対応が必要になるため、実務は不動産に強い弁護士法人アクロピースへの早期相談が安全。
持分放棄にかかる費用や必要書類も解説しているため、持分放棄のやり方に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
不動産の持分放棄とは?

不動産の共有持分は、他の共有者と協議を重ねることなく、単独で権利を手放せます。
持分を手放すメリット・デメリットを見る前に、まずは持分放棄の基礎知識を見ていきましょう。
持分放棄とは「所有している共有持分を放棄すること」
持分の放棄とは、文字通り自身の共有持分を放棄することです。
共有持分とは、不動産を複数の人で共有している場合に、共有している人それぞれが持つ所有権の割合です。
民法は、共有持分を放棄すると「その持分は、他の共有者に帰属する(民法255条)」と規定しています。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
引用:民法|第255条
たとえば、ABCが1/3ずつ持分を持つときに、Cだけが持分放棄すると、Cの持分がA・Bのものになり、A・Bが各1/2ずつ持分を有することになります。
共有持分の放棄と似た言葉に「相続放棄」がありますが、相続放棄とは遺産に関する権利をすべて放棄することです。具体的には、以下のような違いがあります。
| 違い | 持分放棄 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 必要な手続き | 共有者の意思表示だけでできる | 家庭裁判所に相続放棄の申述が必要 |
| 放棄の期限 | 期限はない | 相続開始を知ったときから3か月以内(民法915条1項) |
| 放棄の対象 | 放棄対象とした不動産の共有持分のみ | 相続に関する一切の権利 |
持分放棄については、次の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:「共有持分放棄は早い者勝ち」は本当なのか?相続放棄との違い・検討すべき5つのケース
共有持分は他の共有者の同意なしで放棄できる
共有物分割を進めるには通常、他の共有者との合意や裁判所の関与が必要です。
しかし、共有不動産の持分は、他の共有者の同意を得ずに自分の意思だけで可能です。つまり、共有者の理解を取りつけるまでに時間を費やす必要がありません。
「関係が悪化していて交渉が進まない」「遠方に住んでいて連絡が取れない」といった状況でも、放棄の意思表示をするだけで権利から解放されます。
持分を放棄すると、その権利は自動的に他の共有者に帰属し、結果的に残りの共有者の持分割合が増えます。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫自分はその不動産に関わる義務や権利から解放され、共有状態から退ける仕組みです。
持分放棄で共有状態を解消する3つのメリット
持分放棄で共有状態を解消するメリットは、以下の3つです。
共有状態から抜け出したい方は、まずそれぞれのメリットを具体的に確認してみましょう。
共有持分以外の財産は相続対象になる
持分放棄をしても、他の財産への相続権は失われません。放棄の対象となるのは、あくまで共有不動産など特定の財産に限られるため、預貯金や別の不動産は通常どおり相続できます。
相続を放棄した場合、預貯金や不動産、車など、すべての財産から身を退かなけばなりません。負債が多い場合はプラスに働きますが、受け取りたい財産はある場合、不利に働くケースがあります。
共有持分の放棄は、全財産を手放す相続放棄とは異なり、不要なものだけを切り離せる柔軟さが大きな特徴です。財産の一部だけを処分し、他の資産を確保したい方にとって合理的な選択肢といえます。
他の共有者の同意を待たずに持分を手放せる
他の共有者の同意を待たずに持分を手放せる点も、大きなメリットです。
不動産を売却する場合、他の共有者の承諾を得なければなりません。
しかし、持分の放棄なら、自分の判断だけで手続きを進められます。「管理に関与したくない」「固定資産税を負担したくない」と考えたときに、速やかに共有状態から抜け出せます。
ただし、登記変更の段階では他の共有者の協力が必要です。意思表示そのものは自由でも、最終的な手続きでは連携が欠かせないことを理解しておきましょう。
訴訟による解消よりも手続きがスムーズに進む
訴訟で共有関係を解消する場合、調停や裁判を経るため長期化や費用負担が避けられません。
共有者同士でトラブルが起こった場合、収拾がつかなくなって話し合いが長引く可能性があります。
裁判が長期化すれば、固定資産税や維持管理費の負担も続き、生活面への影響が避けられません。共有者同士で意見が対立すれば、精神的な負担も大きくなるでしょう。
一方、持分放棄は、登記手続きを行うだけで共有状態を解消できます。不要な不動産から早く離れたい場合や、裁判に時間も費用もかけたくない場合に適した手段です。



短期間で負担を軽減できるため、共有問題を迅速に解決したい方にとって有力な選択肢といえるでしょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有物分割訴訟については、以下の記事でも解説しています。気になる方は、こちらも併せて参考にしてみてください。
関連記事:共有物分割訴訟とは?共有状態解消が必要なケースと手続き・費用を解説
関連記事:共有物分割訴訟の期間はどれくらいかかるのか?事前協議や調停・競売期間も解説
持分放棄で共有状態を解消する2つのデメリット
持分を放棄すれば、不動産の共有状態から抜け出せますが、以下のデメリットも考慮しなければなりません。
安易に手放すと後から後悔する可能性があるため、これらのデメリットを理解した上で判断しましょう。
一度放棄すると取り戻せない
持分放棄のリスクは、一度権利を手放すと取り戻せない点です。
持分を放棄した時点で、その不動産の所有権や利用権は消滅し、将来どれだけ価値が上がっても一切の利益を受け取れません。
「不動産を利用したい」「将来価値が上がりそうだから持っておきたい」と思っても、権利を回復できないため本当に手放すべきなのか慎重に判断する必要があります。
とくに不動産は将来的な利用や売却益の可能性も失われるため、安易に決断すると後悔するリスクが高いです。将来的な資産価値や相続人への影響も考慮した上で、本当に放棄が妥当かどうかを冷静に判断しましょう。
判断に迷ったら、弁護士に相談してどのような選択が良いかアドバイスをもらうことをおすすめします。
他の共有者との関係が悪化する恐れがある
他の共有者との関係悪化も、持分放棄で懸念すべきデメリットです。
持分を放棄すれば、その権利は自動的に他の共有者へ帰属します。しかし、登記変更や名義調整といった手続きが必要になり、残された共有者に負担が生じるのが実情です。
このため「面倒な手続きを押し付けられた」と不満を抱かれることが少なくありません。
たとえば、兄弟姉妹の一人が持分を放棄した結果、残りの相続人が固定資産税や修繕費を全額負担することになります。結果として、不公平感から感情的な対立が起こる可能性があるのです。
また、持分買取業者などの第三者が新たに共有者になった場合、従来の人間関係が崩れ、予想外のトラブルに発展するケースがあります。営利目的の業者が共有者となれば、強引に売却を迫られたり、分割請求を起こされたりするリスクも否定できません。



持分放棄によって共有者との関係が悪化する恐れがある場合は、事前に他の共有者に説明しておくなど、円滑に進めるための準備をしておきましょう。
持分放棄を検討した方が良い3つのケース


財産的価値がある持分を放棄してまで手放したいと考える主な理由は、次の通りです。
共有者同士のトラブルを避けたいとき
持分放棄をする大きな理由の1つは、共有関係のトラブルを避けたいためです。共有の場合、管理や処分をめぐって、以下のようなトラブルが起こり得ます。
- 共有不動産を売る場合は共有者全員の同意が必要で、1人でも反対すれば売却できない
- 共有者は持分割合に応じ固定資産税や管理費を負担する必要があるが、共有者の連帯債務のため、経費を負担しない共有者がいる場合は、立替をめぐって揉めることがある
- 共有者同士が疎遠で顔を合わせることもなかったため、話し合いができない場合がある
面倒なトラブルに巻き込まれることは避けたいと、放棄を決断する場合も多いでしょう。
子どもや孫に面倒な共有問題を背負わせたくないとき
共有不動産の持分を放棄する理由には、子や孫に負担を残したくないという思いもあります。
共有不動産を有効に活用できる見込みがあれば、多少のトラブルがあっても他の共有者と協議し、利用方法や処分方法を模索する価値があるでしょう。
一方で、物件の所在地が遠方にある場合や、地目が山林など活用が難しい土地の場合、所有し続ける意味が見いだせない方も少なくありません。
また、持分を持ち続けることで相続時に争いが生じ、親族間のトラブルを深める可能性もあります。
そのような場合には、子や孫に複雑な問題を引き継がせるよりも、自分の判断で生前に持分を放棄した方が良いと考えるケースも多いのです。
共有不動産の管理や費用負担が重荷になっているとき
共有不動産を持っていれば、共有者全員に管理義務がありますが、管理の手間や費用負担が重荷になる場合もあるでしょう。
たとえば、土地や建物を使わずに長期間放置していると、雑草の繁茂や建物老朽化などのため近隣の方に迷惑をかけることや、放火などのリスクもあります。
使っていない物件でも定期的な維持管理が必要で、手間も時間もかかります。
しかも、維持管理の費用や固定資産税などの税金が重荷になることもあるのです。



このような場合、活用が見込めない共有物の持分放棄を検討することになるでしょう。
持分放棄のやり方【2ステップ】


共有持分の放棄には、次の2つのステップで行います。
どのような手続きを得て放棄が確定するのか、具体的なステップを見ていきましょう。
関連記事:共有持分を譲渡する4つの方法とは?手続きや税金・注意点をプロが解説
持分放棄の意思表示をする
まず他の共有者に対して、口頭で持分放棄の意思表示をします。その後、配達証明付き内容証明郵便を送付し、持分放棄の意思を示した記録を残しておきましょう。
ただし、内容証明郵便を突然送ると不審に思われるかもしれません。その後の共有者との話し合いがスムーズに進まなくなるおそれもあるため、まずは口頭で放棄の意思を伝えるようにしてください。
配達証明付き内容証明郵便は、話し合いがうまくいかず訴訟になる場合に証拠として活用できます。
事実を伝える上で重要なものになるため、間違いがないよう弁護士に作成・送付を依頼する方が良いでしょう。
持分放棄の登記手続きをする
持分放棄は、意思表示だけでは対外的な効果はなく、持分の権利移転登記が必要になります。
持分放棄そのものは他の共有者の同意を得る必要はありませんが、権利移転登記を進める際に、共有者の住民票などの書類が必要です。そのため、共有者の協力は欠かせません。
共有者が持分放棄の登記手続に協力しなければ、手続きが面倒になります。



具体的には、裁判所に「登記引取請求訴訟(後述)」を提起し、共有者単独での共有持分移転登記申請を認めてもらう必要があります。
共有持分移転登記の申請先と必要書類


共有持分移転登記の申請先と必要書類を紹介します。
手続きをスムーズに進めるためにも、どのような手順を踏めば良いか確認しましょう。
共有持分移転登記の申請先|共有不動産がある所在地を管轄している法務局
持分放棄の権利移転登記申請は、共有不動産がある所在地を管轄している法務局に行いましょう。
法務局の窓口に持参するか、郵送もできます。電子文書の交付に対応している書類は、オンライン提出も可能です。
ただし、持分移転登記は、他の共有者とともに行う必要があります。他の共有者に協力を呼びかけ、円滑に手続きが進むようにしましょう。
持分放棄の登記手続きに必要な書類
持分放棄のための登記(権利移転登記)に必要な書類は、次の通りです。他の共有者の本人確認書や認印などが必要なため、注意しましょう。
| 準備する人 | 必要な書類 |
|---|---|
| 持分を放棄する人(登記義務者) | 登記申請書(法務局公式サイトで入手可能) 登記原因証明情報登記識別情報)不動産を管轄する登記所が発行) 固定資産評価証明書)市区町村の担当窓口で取得) 印鑑証明(市区町村の担当窓口で取得) 実印委任状(代理人が申請する場合) |
| 他の共有者(登記権利者) | 住民票本人確認資料認印 |
他の共有者が登記に協力してくれない場合の対処法
共有者が登記に協力してくれない場合は、登記引取請求訴訟を起こす必要があります。
登記引取請求訴訟とは、登記申請権があることを、持分放棄した人が裁判所に訴える訴訟です。
本来、持分放棄による登記変更は、権利を引き継ぐ共有者と放棄する人が共同で行うのが原則です。しかし、相手が協力しないと手続きが進まず、放棄の効力が事実上宙に浮いた状態になってしまいます。
そこで、裁判所に訴訟を申し立てて「登記引取請求認容判決」を得ることで、放棄する人が単独で移転登記を申請できるようになる仕組みです。(参照:不動産登記法|第63条1項)
登記引取請求訴訟の手順と必要書類は、以下のとおりです。
| 手順 | (1)配達証明付き内容証明郵便で持分放棄の意思表示をする (2)共有者の住所地を管轄する裁判所(共有者が複数いる場合は、すべての管轄裁判所)に訴状を提出する |
|---|---|
| 訴状添付書類 | ・不動産登記事項証明書 ・固定資産評価証明書証拠書類の写し ・放棄の意思表示をした内容証明郵便の写し など |



訴状発行には法律の知識が必要のため、早めに弁護士に対応方法を相談しましょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
持分放棄にかかる費用と税金


持分放棄をする場合にかかる費用・税金は、以下の表のとおりです。
| 費用・税金(負担する人) | 費用相場・税額 |
|---|---|
| 登録免許税(原則放棄する人が支払うが、共有者の話し合いで決めることも可) | 【登録免許税】 登録免許税固定資産税評価額×2%×持分割合 ※建物と土地に別々にかかる例 建物(評価額2,000万円)と土地(評価額3,000万円)の持分1/2を放棄する場合 建物の登録免許税:10万円 土地の登録免許税:20万円 登録免許税合計:30万円 |
| 登記費用(原則放棄する人が支払うが、共有者の話し合いで決めることも可) | 3万円〜5万円程度 ※司法書士等に依頼する場合に必要 |
| 贈与税(放棄持分の取得者が負担する) | 放棄持分が贈与税の控除額(基礎控除110万円)を超える場合に課税 |
| 不動産取得税(放棄持分の取得者が負担する) | 不動産取得税:固定資産税評価額×3%×持分割合 ※令和9年3月31日まで税率3%(本則4%) |
| 固定資産税・都市計画税(1月1日時点の所有者が負担する) | 不動産を所有している場合に、毎年かかる税金 持分を放棄しても納税義務者は変わらないが、日割りで精算するのが一般的 |
持分放棄により、放棄を望んだわけでもない共有者が「持分を押し付けられ、贈与税などの税負担が生じた」と感じる場合もあります。



トラブルに発展しないよう、可能であれば他の共有者にも事前に持分放棄の旨を相談しておくと良いでしょう。
持分放棄をする際の注意点3つ


共有持分を放棄する場合の注意点を紹介します。
後から「手放さなければよかった」と後悔しないためにも、以下で具体的な注意点を確認しましょう。
放棄した年の固定資産税等の納付義務がある
持分を放棄しても、放棄した年の固定資産税・都市計画税は、原則として放棄した人が納付する必要があります。
固定資産税・都市計画税は、割賦期日(1月1日)に固定資産課税台帳に登録された者に課税されるためです。
持分放棄の意思表示をしただけで移転登記をしていない場合、固定資産税の支払い義務が移転登記が完了するまで続くため注意が必要です。
関連記事:共有者が固定資産税を払わないときは?立て替えた際の請求方法や解決策を解説
持分の取得者に贈与税が課される場合がある
持分の取得者に贈与税が課税されることがあります。
持分放棄は民法上の贈与ではありませんが、自分の財産を無償で譲ることから、税法上は「贈与」とみなされているためです。
ただし、放棄した持分の評価額が、控除額(基礎控除額110万円)よりも低い場合は、贈与税は発生しません。
関連記事:共有不動産の放棄と譲渡による贈与税の課税
最後の一人は持分放棄できない
複数いる共有者が持分放棄を順次行っていった場合、最後の一人は持分放棄できません。
最後の一人になると、単独所有となるため、放棄はできないのです。
このような事態を避けるには、事前に共有者全員で話し合い、誰が放棄するのか、最終的に誰が所有するのかを明確にしておくことが大切です。



持分放棄は一人の判断だけで進めると後々の不公平感を生むため、協議を重ねて合意形成を図ることが望ましいでしょう。
共有持分は放棄する前に弁護士に相談|依頼する3つのメリット
共有持分の放棄は、将来の資産価値や人間関係に大きく影響する重要な決断です。
思わぬ不利益やトラブルを避けるためには、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが欠かせません。
弁護士に持分放棄に関する悩みを相談するメリットは、以下のとおりです。
弁護士に相談すべきか悩んでいる方は、ぜひ依頼を検討する際の参考にしてください。
煩雑な登記手続きや書類作成をすべて任せられる
弁護士に相談すれば、持分放棄に必要な登記手続きや書類作成を一任できます。
持分の放棄といっても、実際の手続きは登記変更、内容証明郵便の送付、必要書類の整備など多岐にわたります。不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書の取得、放棄の意思表示を記録する証拠の確保なども欠かせません。
書類に不備があると登記申請が却下されたり、放棄自体が無効とされるリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、法律上の要件を満たす書類を正確にそろえられるだけでなく、手続きにかかる手間や時間を削減できます。
共有者間のトラブルを未然に防ぎ、円滑な交渉が期待できる
複雑な手続きを一任できるだけでなく、共有者間のトラブルを避けやすくなる点もメリットです。
共有不動産は権利関係が複雑で、放棄の意思を一方的に伝えると「手続きを押し付けられた」と不満を招く可能性があります。
とくに相続で共有になった不動産では、親族間の感情的な対立が背景にあり、放棄がきっかけで人間関係が悪化するケースも珍しくありません。
弁護士が間に入れば、第三者の立場から法的根拠に基づいた説明を行い、共有者に納得感を与えやすくなります。公平性を保った交渉ができるため、相手の協力を得やすく、スムーズに手続きを進められるのです。
相続不動産で「後々揉めたくない」と考える方にとって、弁護士のサポートは大きな心の支えとなるでしょう。
訴訟に発展した場合でもスムーズに対応しやすい
持分放棄が訴訟に発展した場合でも、弁護士に依頼していれば迅速に対応できます。
前述のとおり、他の共有者が登記手続きに協力してくれない場合、登記引取請求訴訟を起こす必要があります。訴訟は法的知識と経験がなければ訴状作成や証拠提出が難しく、不備があれば調停で不利な立場に追い込まれる可能性があるのです。
弁護士は訴訟の見通しを立てた上で、主張の整理や証拠の収集を行い、依頼者に代わって法廷での対応を担います。結果として、手続きの遅延や失敗を防ぎ、解決までの道筋を短縮できます。



さらに、訴訟に至る前段階から弁護士が関与していれば、紛争を回避するための交渉や和解案の提示も可能です。
持分放棄に関するよくある質問
持分放棄と贈与の違いは何ですか?
持分放棄と贈与には、以下の違いがあります。
| 内容 | 税務面 | |
|---|---|---|
| 持分放棄 | 自分の権利を一方的に手放す | 課税対象にはならない ※特定の共有者だけが利益を受ける場合は「贈与」とみなされ課税対象となるケースもある |
| 贈与 | 特定の相手に財産を与える | 課税対象(贈与税) |
持分放棄は、自分の権利を一方的に手放す行為であり、放棄された持分は自動的に他の共有者へ帰属します。これに対して贈与は、特定の相手に財産を与える契約行為であり、当事者間の合意が必要です。
また、両者は税務面でも取り扱いが異なるのも特徴です。
持分放棄の場合は原則課税対象にはなりませんが、特定の共有者だけ利益を受ける場合は贈与税の対象になるケースもあります。一方、贈与の場合は贈与税の対象です。
持分放棄を検討する際は、単なる権利放棄にとどまるのか、それとも贈与と判断され得るのかを事前に整理しましょう。
相続で持分を放棄するにはどうすればいいですか?
相続によって共有持分を取得した場合でも、不要と判断すれば放棄は可能です。ただし「相続放棄」と混同しないことが重要です。
相続放棄は家庭裁判所に申述し、被相続人の財産すべてを対象に権利を放棄する制度です。そのため、特定の財産である「持分だけ」を相続放棄することはできません。
もし他の財産は相続したいが、不動産の持分は不要という場合には、相続放棄ではなく持分放棄の手続きを選択する必要があります。
どちらを選ぶかは、負債の有無や残したい財産の種類によって異なるため、状況を慎重に見極めることが大切です。
共有物を勝手に処分してもいいですか?
結論として、共有不動産を勝手に処分することはできません。
民法第251条1項に定められているとおり、共有物を処分するには原則として共有者全員の同意が必要です。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用:民法251条1項
円滑に処分を進めるためには、あらかじめ共有者全員で話し合い、同意を得た上で売却や活用方法を検討する必要があります。
持分放棄の期限はいつですか?
持分放棄には、相続放棄のように明確な期限はありません。
相続によって取得した持分であっても、自分の意思で不要だと判断した時点で放棄することが可能です。
ただし、相続税の申告期限や固定資産税の課税時期との関係で、放棄を先延ばしにすると余計な負担が生じる場合があります。
持分放棄を検討する際には、法的にはいつでもできるとはいえ、できるだけ早めに対応するのが望ましいといえます。
共有持分の放棄が早いもの勝ちと言われる理由は?
共有持分の放棄は、複数の共有者がいる場合には一方的に可能ですが、最後の一人になってしまうと放棄は認められません。
最後の一人は不動産の単独所有者となり、放棄という制度自体を利用できなくなるためです。
たとえば3人で土地を共有している場合、1人が持分を放棄すると残りの2人が自動的に持分を引き継ぎます。さらにもう1人が放棄すれば、最終的に1人だけが全体を所有する状態になります。
このように放棄は途中までは有効でも、最終段階では適用できなくなるため「早い者勝ち」と言われているのです。
不要な持分を抱え込みたくない場合には、タイミングを逃さないことが重要といえます。
詳細は、こちらの記事でも解説しています。併せて参考にしてみてください。
まとめ|持分を放棄すべきか悩んだらまず弁護士に相談!最善の道を探ろう
持分放棄は共有関係を解消する他の方法を含めた慎重な判断が必要です。他の共有者が協力してくれない場合は訴訟が必要になることもあります。
複雑な法的知識や不動産市場の知識・経験も必要なため、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。



持分放棄のやり方で悩むときや不安があるときは、共有不動産の問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









