【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産を現金化する5つの方法とは?売却の手順や費用・注意点を徹底解説
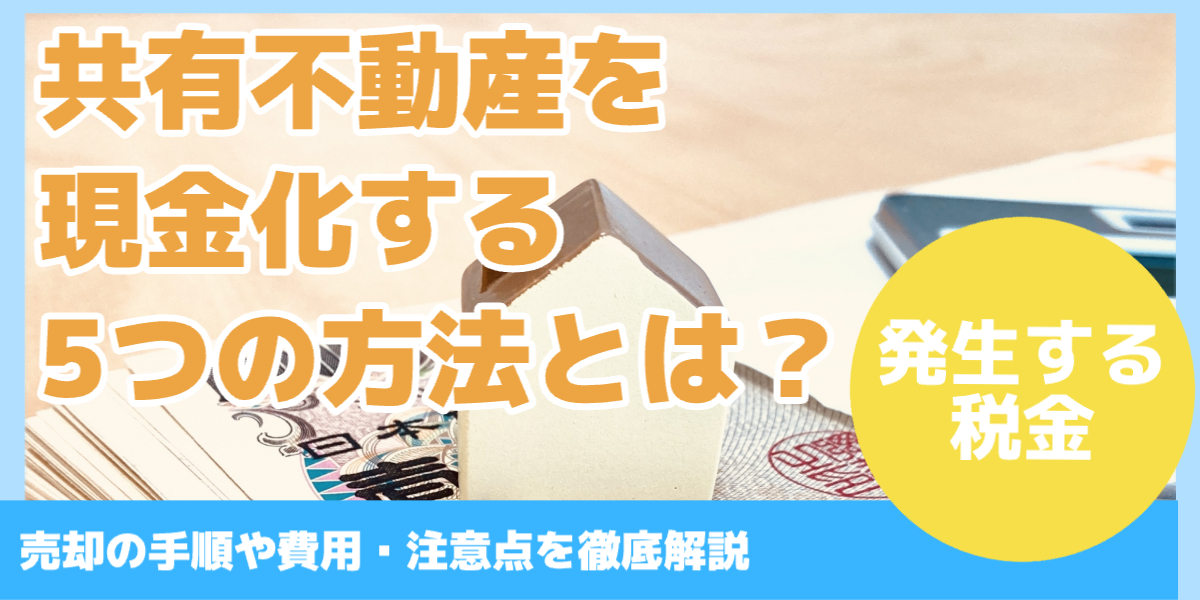
「お金が必要なのに相続した共有不動産しかない」
「共有名義の不動産で現金化する方法はない?」
共有不動産を現金化したいと考える際、上記のような悩みを抱える人も多いのではないでしょうか。共有不動産は権利関係が複雑なため、売却したくてもスムーズに進まないケースが少なくありません。
この記事では、共有不動産を現金化するための5つの具体的な方法を解説します。
 弁護士 佐々木一夫
弁護士 佐々木一夫売却の手順や必要な費用や税金、相談先まで網羅的に紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産を現金化する5つの方法
共有不動産を現金化するには、主に5つの方法が存在します。
共有者全員の状況や不動産の状態によって、適切な選択肢は異なります。それぞれの方法のメリット・デメリットを理解し、慎重に検討することが重要です。
共有者全員の合意で不動産全体を売却する
一般的で、高値での売却が期待できる方法が、共有者全員の合意のもとで不動産全体を売却することです。
共有者全員が売却に同意すれば、単独名義の不動産と同じように市場で売却活動ができます。市場価格で売れるため、現金化できる金額が大きくなる可能性が高い点がメリットです。
ただし、以下の点には注意しましょう。
- 全員の同意が必須
- 手続きの煩雑さ
- 利益配分の問題
共有者が一人でも反対すれば、この方法は選択できません(民法第251条)。また、売買契約や決済など、すべての手続きに共有者全員の署名・捺印が必要です。売却で得た利益は、それぞれの共有持分割合に応じて分配します。
そのため、この方法は共有者間の関係が良好で、全員が売却の意思を持っている場合に適しています。まずは、他の共有者と話し合いの場を設け、売却の意思を確認することから始めましょう。
出典:e-Gov法令検索|民法
関連記事:共有名義のマンションを売却するには?売却方法や費用・注意点を弁護士が解説
自分の共有持分のみを専門の買取業者に売却する
他の共有者の同意が得られない場合でも、自分の共有持分のみを売却することは可能です(民法第206条)。
共有持分は、不動産全体を利用する権利の一部であり、それ自体を財産として売買できます。主な売却先は、共有持分を専門に扱う不動産買取業者です。
この方法には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | ・他の共有者の同意が不要 ・最短で1〜2週間ほどで現金化できるケースがある(※業者によって異なる) ・共有関係のトラブルから解放される |
|---|---|
| デメリット | ・売却価格が市場価格より大幅に安くなる ・一般の個人への売却は困難 |
買取業者は、購入後に他の共有者と交渉したり、共有物分割請求訴訟を起こしたりして利益を得ることを目的にしています。そのため、買取時点での価格は市場価格の5〜7割程度になる傾向があります。
売却価格は低くなりますが、他の共有者との面倒な交渉を避け、迅速に現金化したい場合に有効な選択肢といえるでしょう。
出典:e-Gov法令検索|民法
以下の記事では、共有名義の不動産の売却について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
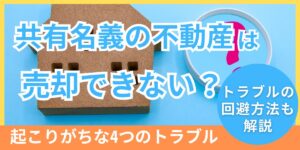
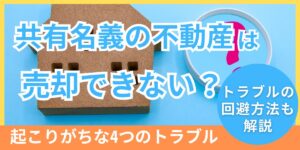
他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう
自分の共有持分を、他の共有者に買い取ってもらう方法もあります。不動産を手放したくない共有者がいる場合に有効な選択肢です。
たとえば、兄弟の一人が実家に住み続けたいと希望しているケースなどが考えられます。売却先が身内であるため、専門業者に売るよりも高い価格で交渉できる可能性が高いでしょう。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 価格交渉:適正な価格で合意に至るためには、客観的な不動産査定が不可欠
- 資金力:買い取る側の共有者に、持分を買い取るだけの資金力が必要
- 関係性:価格交渉が原因で、親族間の関係が悪化するリスクもある
お互いが納得できる価格でスムーズに話を進めるためにも、不動産会社などの第三者に査定を依頼し、その価格を基に交渉することが大切です。
共有持分の買取については、以下の記事でも詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。


共有物分割請求訴訟で裁判所に判断を委ねる
共有者間での話し合いがまとまらない場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起して解決を図る方法があります。
共有物分割請求訴訟とは、共有状態の解消を裁判所に求める法的な手続です。訴訟と聞くと大事に聞こえるかもしれませんが、共有者の権利として法律で認められています。
裁判所は、当事者の主張や不動産の状況を考慮し、以下のいずれかの方法で分割を命じます。
- 現物分割:土地などを物理的に分筆する方法
- 代償分割:特定の共有者が不動産を取得し、他の共有者に金銭を支払う方法
- 換価分割:不動産を競売にかけ、売却代金を共有持分に応じて分配する方法
訴訟は最終手段ですが、当事者同士での解決が困難な場合には、公平な解決を期待できる有効な手段といえるでしょう。
出典:e-Gov法令検索|民法
共有物分割訴訟については、以下の記事でも詳しく解説しています。
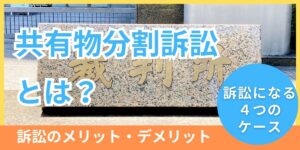
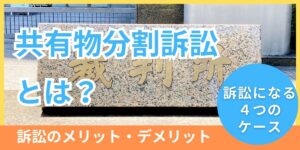
共有持分を担保にしてお金を借りる
共有持分を売るのではなく共有持分を担保にしてお金を借りる方法も現金化の一つの手です。
通常は不動産全体を担保にしてお金を借りる不動産担保ローンですが、ケースによっては共有持分のみであっても担保にしてお金を借りられます。
不動産全体を担保にする場合は共有者全員の同意が必要ですが、共有持分のみを担保にお金を借入する際は、他の共有者の同意を得る必要はありません。
他の共有者に知られることなく現金を調達することが可能です。ただ、返済できなければ共有持分は担保権の実行によって競売されることになる点に注意が必要です。
【ステップで解説】共有不動産を現金化する手順
共有不動産の現金化は、適切な手順を踏むことが成功のカギです。やみくもに行動すると、共有者とのトラブルに発展しかねません。
ここでは、現金化を実現するための基本的な6つのステップを解説します。
ステップ1:現状の権利関係・不動産価値を把握する
まず行うべきことは、現状の正確な把握です。以下の情報を確認し、整理しましょう。
| 1.権利関係の確認 | ・法務局で不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得 ・共有者全員の名前と、それぞれの持分割合を確認 |
|---|---|
| 2.不動産価値の把握 | ・複数の不動産会社に査定を依頼し、おおよその市場価格を把握 |
上記の情報は後の手続きで重要な要素となります。とくに査定額は、後の共有者との交渉や現金化の方法を決定する上で重要な基準です。
共有持分の不動産の売却相場については、以下の記事も参考にしてみてください。
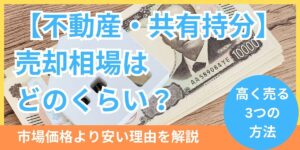
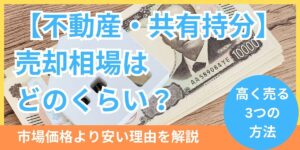
ステップ2:専門家に相談・依頼する
共有不動産の問題は、法律や税金など専門的な知識が不可欠です。早い段階で専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな解決につながります。
相談すべき専門家は、以下のように状況によって異なります。
- 売却の実務や査定:不動産会社
- 登記手続き:司法書士
- 共有者との交渉や訴訟:弁護士
- 税金の計算:税理士
- 共有不動産が農地の場合:行政書士
まずは信頼できる弁護士に相談し、必要に応じて他の専門家を紹介してもらうのがよいでしょう。無料相談を活用し、複数の専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。
ステップ3:現金化の方法を決定する
ステップ1と2で得た情報を基に、どの現金化の方法を選択するかを決定します。
以下を参考に前の章で解説した方法の中から自分の状況に適したものを検討しましょう。
- 共有者全員と連絡が取れ、関係も良好→全員での売却や、持分の買取交渉を検討
- 共有者と揉めている、または連絡が取れない→持分のみの売却や、共有物分割請求訴訟を検討
- とにかく早く現金化したい→専門業者への持分売却を検討
- できるだけ高く売りたい→全員での売却を目指して交渉
それぞれの方法のメリット・デメリットを再確認し、専門家のアドバイスも参考にしながら、適切な方針を固めましょう。
ステップ4:他の共有者と交渉する
現金化の方法が決まったら、他の共有者と具体的な交渉を開始します。感情的にならず、冷静に話し合いを進めることが重要です。
交渉を円滑に進めるためのポイントは以下のとおりです。
- 客観的な資料を提示する
- 相手の意見を尊重する
- 交渉の窓口を一本化する
不動産の査定書など第三者による客観的な資料を基に話を進めましょう。また、自分の希望だけを主張するのではなく、相手の状況や意見にも耳を傾ける姿勢が大切です。
共有者が多い場合は、代表者を決めて交渉すると話がまとまりやすくなるでしょう。当事者間での交渉が難しい場合は、弁護士に代理人として交渉を依頼することも有効な手段です。
ステップ5:売買契約を締結・決済をする
交渉がまとまって売却先が決まったら、次に売買契約を締結します。不動産全体を売却する場合は、共有者全員が売り主として契約書に署名・捺印しましょう。
契約から決済(残代金の受領と物件の引き渡し)までの一般的な流れは以下のとおりです。
- 売買契約の締結
- 決済・引き渡しに必要な書類の準備
- 決済・引き渡し
まず、買い主と売り主(共有者全員)が契約内容を確認し、署名・捺印します。次に、所有権移転登記に必要な書類(登記済権利証、印鑑証明書など)を準備しましょう。
金融機関などで司法書士立ち会いのもと残代金を受領し、同時に所有権移転登記を申請します。決済が完了すると、売却代金が持分割合に応じて各共有者に支払われ、現金化が実現します。
ステップ6:確定申告をする
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、売却した翌年に確定申告を行い、所得税・住民税を納める必要があります。確定申告の期間は、原則として売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
なお、譲渡所得は以下の計算式で算出します。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
共有不動産の場合、共有者それぞれが自身の持分に応じた譲渡所得を計算し、各自で確定申告を行う必要があります。
後述する特別控除などの特例を利用する場合も、確定申告が必須です。税金の計算は複雑なため、不安な場合は弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有不動産の現金化に必要な諸費用
共有不動産を現金化する際には、さまざまな費用が発生します。適切に資金を準備するためにも、どのような費用がどのくらいかかるのかを事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、代表的な諸費用について解説します。これらの費用は、売却代金から差し引かれることを念頭に置いておきましょう。
仲介手数料|不動産会社を通して売却する場合に発生する費用
不動産会社に仲介を依頼して買い主を見つけてもらった場合に支払う成功報酬です。
法律で上限額が定められており、以下の計算式で計算されます。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 価格の5%+消費税 |
| 200万円超400万円以下の部分 | 価格の4%+消費税 |
| 400万円超の部分 | 価格の3%+消費税 |
しかし、この計算式を使うと計算に時間がかかるため、売却価格が800万円を超える場合は以下の速算式が利用されます。
売却価格×3%+6万円
たとえば、不動産が3,000万円で売れた場合の仲介手数料の上限は、「3,000万円×3%+6万円+消費税」で計算できます。
売買契約が成立した際に半金、決済時に残りの半金と分けて支払うのが一般的です。
登記費用|所有権移転登記や抵当権抹消登記の手続きにかかる費用
不動産を売却すると、所有権を買い主に移すための「所有権移転登記」が必要です。また、住宅ローンが残っている場合は、ローンを完済して「抵当権抹消登記」を行う必要があります。
これらの登記には、登録免許税が必要です。登記を司法書士に依頼した場合は、司法書士に支払う費用もかかってきます。
| 登録免許税 | 登記手続きの際に国に納める税金です。 税額は不動産の固定資産税評価額に基づいて決まります。 |
|---|---|
| 司法書士への報酬 | 手続きを代行してもらう司法書士に支払う手数料です。 |
測量費|土地の境界確認の際に発生する費用
土地を含む不動産を売却する場合、隣地との境界を明確にするための測量が必要になることがあります。
とくに、古い土地で境界が曖昧な場合や、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合には、買い主から境界確定測量を求められるケースが多いです。
境界確定測量の費用は、土地の広さや形状、隣接地の所有者の数などによって大きく変動します。
- 一般的な住宅地:30万円〜80万円程度
- 土地が広かったり、地形が複雑であったり、隣接地の所有者が多数いたりするなどの事情がある場合:100万円超になる可能性あり
費用は高額になる可能性がありますが、境界トラブルを防ぎ、不動産の価値を正しく評価するためには重要な手続きです。



自分のケースでどれだけ費用が必要か不安な方は、一度弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
共有持分の売却費用やトラブルについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。


共有不動産の現金化で発生する可能性がある税金
共有不動産を現金化(売却)して利益が出た場合、以下の税金が課されます。
税金の知識がないと、手元に残る金額が想定より少なくなってしまう可能性があるため注意が必要です。
ここでは、現金化の際に発生する可能性のある主な税金について解説します。
譲渡所得税・住民税|売却益が出た場合に発生する税金
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。
譲渡所得は「売却価格」から「取得費(不動産の購入代金など)」と「譲渡費用(仲介手数料など)」を差し引いて計算します。
なお、税率は不動産の所有期間によって、以下のように異なります。また、2037年12月31日まで、復興特別所得税も課税されます。
| 所有期間 | 税率の内訳 | 合計税率 |
|---|---|---|
| 5年以下(短期譲渡所得) | ・所得税:30% ・住民税:9% ・復興特別所得税:0.63% | 39.63% |
| 5年超(長期譲渡所得) | ・所得税:15% ・住民税:5% ・復興特別所得税:0.315% | 20.315% |
所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わるため、売却のタイミングを検討する上で重要なポイントです。
印紙税|売買契約書を作成する際に発生する税金
不動産の売買契約書は、法律で定められた課税文書であり、契約金額に応じた収入印紙を貼り付けて納税する必要があります。これを印紙税といいます。
印紙税は、売り主と買い主がそれぞれ契約書を保有する場合、各自が負担するのが一般的です。
印紙税額は、契約書に記載された金額が高くなるほど高くなります。個別のケースで詳しい印紙税額が気になる場合は、国税庁のページを参考にしてみてください。
出典:国税庁|印紙税額
登録免許税|所有権移転登記時にかかる税金
前述の登記費用の一部で、登記手続きの際に法務局に納める国税です。所有権移転登記の登録免許税は、原則として買い主が負担します。
ただし、売り主側も住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記については、登録免許税(不動産1個につき1,000円)を負担しなければなりません。
また、相続登記が未了のまま不動産を売却する場合は、その前提として相続登記が必要となり、その際の登録免許税は売り主(相続人)の負担となります。
登録免許税の税率は、土地と建物で異なります。詳しくは、国税庁の公式ページを参考にしてみてください。



共有不動産の税金関係で悩みがある場合は、適切に対応するためにも、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談しましょう。
共有不動産の現金化で知っておきたい特例・控除
不動産を売却した際の税金は高額になりがちですが、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる特例や控除制度があります。
これらの制度をうまく活用することで、手元に残る現金を増やすことが可能です。
ここでは、代表的な5つの特例・控除を紹介します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却して利益が出た場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。この特例を適用できれば、譲渡所得税・住民税を大幅に軽減できます。
共有不動産の場合、共有者それぞれが要件を満たせば、各自がこの控除を利用できます。主な適用要件は以下のとおりです。
- 自分が住んでいる家屋(およびその敷地)を売ること、または、住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売ること
- 売った年の前年、前々年にこの特例や他の特例を受けていないこと
- 親子や夫婦など、特別な関係にある人への売却ではないこと
この特例は節税効果が大きいため、自宅として利用していた共有不動産を売却する際は、必ず適用要件を確認しましょう。
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した家が空き家になっており、その家と土地を令和9年12月31日までに売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。増え続ける空き家問題への対策として設けられました。
適用を受けるためには、たとえば以下のような要件を満たす必要があります。
- 相続開始の直前まで被相続人が一人で住んでいたこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 売却代金が1億円以下であること
- 一定の耐震基準を満たすようにリフォームするか、家屋を取り壊して更地で売却すること
相続した実家を売却する際には、この特例が使えないかを確認することも重要です。
※令和6年1月1日以後に行う譲渡で、被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地などを相続・遺贈により取得した相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円までとなります。
出典:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
関連記事:共有名義のリフォームで注意すべき点は?同意の範囲や贈与税について弁護士が徹底解説
10年以上の長期所有による軽減税率
売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えているマイホームを売却する場合、長期譲渡所得よりもさらに低い税率が適用される特例です。
前述の「居住用財産の3,000万円特別控除」との併用もできます。
軽減税率の内容は以下のとおりです。
| 課税譲渡所得6,000万円以下の部分 | 課税長期譲渡所得金額×10% |
|---|---|
| 課税譲渡所得6,000万円超の部分 | (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×15%+600万円 |
なお、課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額のことを指します。
課税長期譲渡所得金額=(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除
長年住んだマイホームを売却する際には、有利な制度といえるでしょう。
出典:国税庁|No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
相続税取得費加算の特例
相続によって取得した財産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、納めた相続税の一部を不動産の取得費に加算できる特例です。
取得費が増えることで、課税対象となる譲渡所得が減り、結果的に譲渡所得税・住民税が軽減されます。
この特例の要件は以下のとおりです。
- 相続や遺贈で財産を取得していること
- 相続税を納税していること
- 相続開始の翌日から相続税の申告期限(10か月)の翌日以後3年以内に売却すること(つまり、相続開始の翌日から3年10か月以内に売却すること)
相続税を支払って不動産を相続し、その後すぐに売却を考えている場合には、この特例の適用を忘れないようにしましょう。
出典:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
マイホームの買い換え特例
マイホームを売却し、新たにマイホームを購入(買い換え)する場合、一定の要件を満たせば、売却した年の譲渡所得への課税を将来に繰り延べられる制度です。
この特例は、譲渡所得が非課税になるわけではなく、あくまで課税を先送りにするものである点に注意が必要です。
また、3,000万円の特別控除など、他の特例とは選択制であり、併用はできません。適用要件は、たとえば以下のようなものがありますが、数多くの要件が定められており複雑です。
- 所有期間が10年を超えていること
- 売却代金が1億円以下であること
- 売却した年の前後1年以内に新たなマイホームを取得すること
住み替えを検討している場合には、どの特例を使うのが適切かをシミュレーションすることが重要です。どの特例を使うべきかわからない場合は、一度弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
出典:国税庁|No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有不動産を現金化できない・共有者と合意できないときの対処法
共有不動産を売却して現金化したくても、他の共有者が反対していたり、連絡が取れなかったりする場合、手続きが思うように進まないことも珍しくありません。
しかし、こうした状況でも以下のように適切な手順を踏めば、法的に現金化を進める方法があります。
以下、それぞれ具体的に解説します。
共有者が売却に反対している場合は「話し合いによる合意形成」が基本
共有者の中に売却に反対する人がいる場合、まずは「話し合いによる合意形成」が基本です。感情的な対立を避け、客観的な判断材料を提示しましょう。
その際、共有者に不動産の市場価格や維持費(固定資産税・修繕費など)を数値で示すことが大切です。弁護士や不動産コンサルタントを交えることで、公平な判断材料を提示しやすくなります。
連絡が取れない共有者がいる場合は「内容証明郵便」を送付する
共有者の中に音信不通・所在不明の人がいると、売却や処分が進まないことがあります。このような場合には、法律上の手続きを踏んで進めることが可能です。
まずは、内容証明郵便などで連絡を試みましょう。住民票や戸籍附票で現住所を調べて送付することで、連絡努力をした証拠を残せます。
また、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者の代わりに意思決定できる管理人を選任してもらうことも一つです。選任後は管理人が代理権を持ち、他の共有者と協議・売却手続きを進められます。
訴訟に発展しそうな場合は家庭裁判所の「調停」制度を活用する
訴訟に発展する前に、家庭裁判所の「調停」制度を活用しましょう。時間・費用を抑えながら、第三者を交えて冷静に話し合うことが可能です。
また、調停の申し立てや書類作成、共有者間の交渉には法律知識が求められるため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいた助言が受けられるだけでなく、代理人として調停や交渉を進めてもらえるため、無用なトラブルを防ぎながらスムーズに現金化を目指せるでしょう。
共有不動産を現金化する際の注意点
共有不動産の現金化は、単独名義の不動産とは異なる注意点があります。これらの注意点を理解しておかないと、思わぬトラブルに発展したり、経済的な損失を被ったりする可能性があります。
ここでは、とくに重要な3つの注意点について解説します。
事前にリスクを把握し、対策を講じておくことが大切です。
共有不動産全体を売却する場合は共有者全員の同意が必要
不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が絶対条件である点に注意が必要です。民法上、共有物の変更行為(売却など)には全員の合意が必要と定められています。
また、以下の点にも注意しましょう。
- 持分割合に関わらず、一人でも反対すれば売却はできない
- 売買契約書や登記に必要な書類には、共有者全員の署名と実印での押印が必要
- 遠方に住んでいる共有者がいる場合、書類のやり取りなどで手続きが煩雑になる
まずは、すべての共有者と連絡を取り、売却に向けた意思統一を図ることが大切です。
もし連絡が取れない共有者がいる場合は、弁護士に相談して住民票や戸籍の附票を調査してもらう必要があります。
出典:e-Gov法令検索|民法
自身の持分のみを売却すると相場より安くなる可能性がある
他の共有者の同意が得られない場合、自分の共有持分のみを売却するという選択肢があります。この方法は、単独の判断で迅速に現金化できる点がメリットです。
しかし、その代償として売却価格が市場価格よりも大幅に安くなる可能性が高いというデメリットを理解しておく必要があります。
買取価格の相場は、一般的に不動ブロック市場価格に自身の持分割合を掛けた金額の、さらに5割〜7割程度になることが多いです。また、一般の個人が買い手になることは稀で、共有持分を購入するのは専門の不動産買取業者がほとんどです。
購入した業者が後に他共有者へ訴訟を提起するケースもあるため、売却前に弁護士へリスク確認を行うのが安心です。



「早く共有関係から抜け出したい」というニーズには応えられますが、経済的な損失は覚悟する必要があるでしょう。
共有名義の売却には民法・税務・登記の知識が必要
共有不動産の売却は、単独名義の不動産売却に比べて、法律や税務、登記の知識がより一層求められます。
- 民法:共有者間の権利関係や、分割請求の方法など
- 税務:譲渡所得税の計算や各種特例の適用要件など
- 登記:所有権移転登記や、相続登記が未了の場合の手続きなど
これらの専門知識を個人ですべてカバーするのは困難です。手続きのどこかでミスがあると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
共有不動産の現金化に関するよくある質問
ここでは、共有不動産の現金化に関して、多くの方が抱く疑問について回答します。事前に疑問点を解消し、安心して手続きに臨みましょう。
共有名義の不動産を勝手に売却することは可能?
共有名義の不動産を勝手に売却することはできません。不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が法律で義務付けられています。
自分の共有持分のみであれば、他の共有者の同意なく売却することは可能です。しかし、不動産そのものを一人の判断で売却することは絶対にできません。
もし、他の共有者が偽造した書類を使って勝手に売却した場合、その売買契約は無効となり、登記を抹消できます。
売却に反対する共有者から妨害された場合の対処法は?
まずは、なぜ反対するのか理由を丁寧にヒアリングし、話し合いでの解決を試みることが大切です。
それでも解決が難しい場合や、嫌がらせなどの妨害行為がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士を通じて交渉することで、相手も冷静に対応する可能性が高まるでしょう。
最終的な手段としては、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起し、法的な強制力をもって共有関係を解消する方法があります。
共有持分の不動産売却時のトラブル防止策について気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。
住宅ローンが残っていても現金化は可能?
住宅ローンが残っていても、共有不動産の現金化は可能です。
ただし、売却するためには、決済時に住宅ローンを全額返済し、金融機関が設定している抵当権を抹消する必要があります。不動産の売却代金をローンの返済に充てるのが一般的です。
売却価格がローン残高を上回るアンダーローンの場合は、売却代金でローンを完済し、残ったお金が手元に入ります。
一方、売却価格がローン残高を下回るオーバーローンの場合は、売却代金だけではローンを完済できないため、不足分を自己資金で補填する必要があります。



まずは金融機関に連絡し、ローン残高を正確に把握することから始めましょう。
まとめ|共有不動産の現金化は専門家に相談し、焦らず適切に実施することが大切
共有不動産の現金化は、権利関係が複雑で、共有者間の合意形成が必要なため、多くの課題を伴います。しかし、正しい知識を持ち、適切な手順を踏むことで、円満な解決は十分に可能です。
まずは、自身の状況を整理し、どの方法が最適かを検討することから始めましょう。そして、手続きを進める上での不安やトラブルは一人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談することが重要です。
不動産会社、司法書士、弁護士など、それぞれの専門家の力を借りながら、焦らず、着実に手続きを進めていきましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









