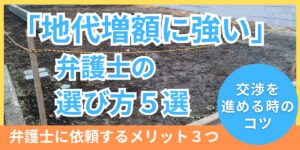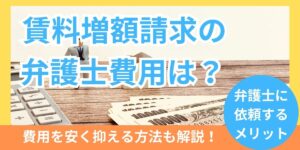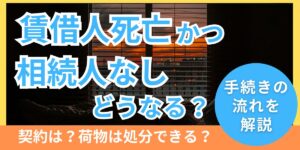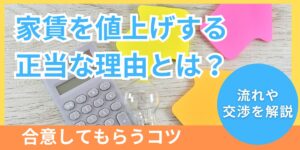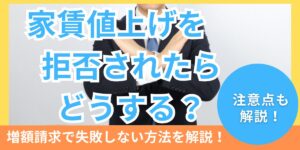【無料相談受付中】24時間365日対応
地代の値上げを拒否されたときの対処法!交渉の進め方と地代相場の計算方法
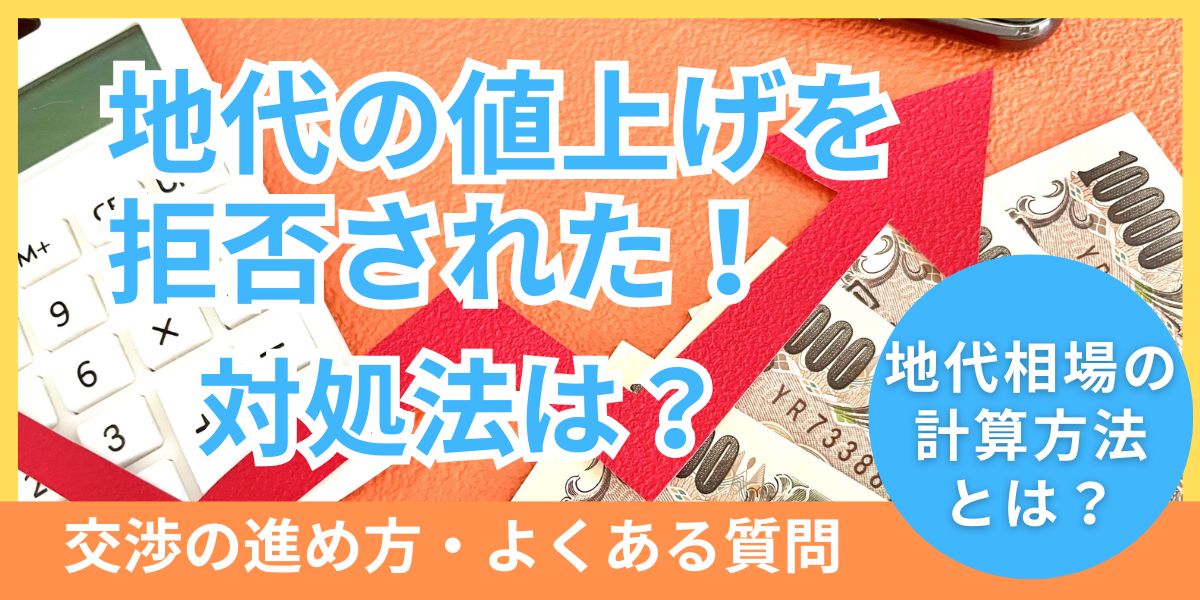
地代の値上げを借主に拒否された場合、どのように対応すればよいか悩んでいるかもしれません。
地代の値上げを拒否されてしまうという問題は、地主なら誰もが直面する可能性があります。
この記事では、交渉をスムーズに進める方法や法的手続きを含め、具体的な対処法を解説します。
トラブルを最小限に抑え、適正な地代での契約を実現できるよう、記事の内容をお役立てください。

地主から多く寄せられる地代の増額に関する質問にもお答えしていますので、最後までお読みください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
地主には地代の値上げを請求する権利がある


長期間にわたり地代が据え置かれており、周辺地域の地価や賃料相場が上昇している場合、地主は借主に地代の増額請求ができる権利を有しています。
地代の値上げは借地借家法によって認められた地主の正当な権利で「賃料増額請求権」として法律に明記されているのです。
以下では、地主が地代の値上げを請求できる法的根拠と、その権利を行使するための条件について解説します。
賃料増額請求権とは
賃料増額請求権とは、借地契約で定めた地代が現状に合わなくなったときに賃料の増額を目的として行使できる法律上の権利です。
なお、賃料減額請求権も存在しており、賃料増額請求権とあわせて賃料増減額請求権と呼ばれます。
地主は、固定資産税の上昇や物価の変動などにより、現行の地代が相場と比べて著しく乖離しているときは、賃料増額請求権を根拠に値上げ交渉が可能です。
地代の値上げについて、地主と借主の間で話し合いによる合意が得られないときは、民事調停や訴訟によって解決が図られるケースもあります。
賃料増額請求権を行使できる条件
地代の値上げを借主に拒否された場合でも、借地借家法第11条により、一定の条件を満たせば地代の増額を請求できます。
出典:e-Govポータル|借地借家法
賃料が不相当かどうかは、以下の事情をもとに判断します。
- 土地にかかる固定資産税などの租税公課が増えた場合
- 土地価格の上昇があった場合
- 経済情勢に大きな変動があった場合
- 近隣の類似条件の土地と比べて地代が著しく安い場合
契約で「一定期間は地代を増額しない」と定められているときは、原則その特約が優先されます。
ただし、特約の期間が極端に長い場合などは、例外的に増額請求が認められるケースもあります。



賃料増額請求に関する弁護士費用は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:賃料増額請求の弁護士費用はどのくらい?その他の費用や安く抑える方法を解説
地主が地代の増額(値上げ)請求を行う手順


地主が地代の値上げを求める場合、まずは借主に事情を説明し、相手の理解を得るための話し合いから始めます。
地主が借主に地代の増額請求を行うには、以下の手順を踏む必要があります。
1.任意の交渉
地代の値上げを進めるには、まず地主と借主による「任意交渉」から始めます。
任意交渉で双方が合意すれば、調停や訴訟といった法的手続きを経ずに、地代の増額が決定します。
賃料の増額請求の形式に定めはなく「来月から地代を○○円に増額します」といった一方的な通知でも意思表示として有効です。
法律上は、地代の増額を伝えた時点から効力が生じ、後に合意や裁判で増額が認められれば、通知日以降にさかのぼって適用されます。
賃料の増額請求では、交渉がこじれて地代の値上げを拒否される事態に備えて、文書でのやり取りを前提に話し合いに臨む必要があります。
2.民事調停
地代の値上げを借主に拒否され、任意交渉で合意に至らなかった場合は、裁判所に民事調停を申立てます。



地代の増額請求では、訴訟に進む前に調停を経る「調停前置」が原則です。
民事調停では、裁判官1名と、不動産鑑定士や弁護士などから選ばれた調停委員2名以上で構成される調停委員会が、双方の主張と提出された資料をもとに解決案を提示します。
調停では、当事者の事情や希望を考慮した対話が重視されるため「段階的な地代引上げ」といった柔軟な合意が実現しやすいのが特徴です。
調停が成立した場合は「調停調書」が作成され、裁判所の判決と同等の効力を持ち、和解内容に従わないときは強制執行も可能です。
出典:民事調停法 第24条の2・別表第二(e-Gov 法令検索)
3.訴訟
民事調停で合意に至らなかった場合は、訴訟を提起します。
訴訟では、裁判所が指定した不動産鑑定士による鑑定評価をもとに、地代の妥当性を判断します。
鑑定人は中立の立場で市場価格や周辺事例を踏まえて評価を行い、裁判所は鑑定結果を尊重して地代の増額を認めるか決定するのです。
任意交渉や民事調停で解決できない場合でも、訴訟では客観的かつ法的に正当な地代であると認めてもらえる可能性があり、地主にとって権利を主張する有効な手段といえます。
地代の値上げを拒否されないための対処法


地代の値上げを拒否されないためには、借主との信頼関係を壊さないように配慮しながら交渉を進める必要があります。
地主が借主と地代の増額交渉をスムーズに行うポイントは、以下の通りです。
値上げする根拠の丁寧な説明
地代の値上げ交渉で借主の納得を得るには、増額請求の妥当性を客観的に説明することが重要です。
借主にとって地代の負担増は生活や経営に直結するため、地主の一方的な値上げの申し入れだけでは、受け入れられない可能性があります。
交渉で借主の納得を得るには、地価の上昇や周辺賃料相場の高騰といった具体的な事情を、数値データや資料などを用いて示すことが重要です。
たとえば、近隣エリアの賃料水準や固定資産税の増加状況などを客観的に提示すれば、借主の納得を得られやすいでしょう。



地代の値上げを拒否されないためにも、客観的データに基づく交渉を心がけてください。
段階的な値上げの提案
大幅な賃料の値上げは借主にとって受け入れ難いため、段階的な地代の値上げを提案する方が合意を得やすい場合があります。
借主にとって地代の値上げは、家計や経営の見直しを迫られるケースがあるため、急激な負担増には応じにくいのが現実です。
そのため、地代の段階的な引上げの提示は、借主側にとって準備期間の確保につながり、負担感を和らげる効果があります。
たとえば、いきなり地代を20%引き上げるのではなく、2年かけて年10%ずつ引き上げる案を提示すれば、借主は資金繰りを調整する余裕ができるため、請求を受け入れやすくなるでしょう。



こうした柔軟な提案は、値上げ交渉の成功率を高める効果が期待できます。
交渉がまとまらない場合の対応(調停や訴訟手続き)も事前に説明する
地代の値上げ交渉において、あらかじめ、調停や訴訟などの法的手続きに進む可能性について説明しておくことは、有効な対応策の一つです。
借主側に訴訟を提起される可能性があると認識させることによって、値上げに応じるケースもあります。
ただし、単に強硬な態度を示すだけでは、逆効果になりかねません。



地主が借主の気持ちをないがしろにして交渉を進めると、抵抗姿勢を強めてしまうリスクもあります。
そのため、法的手続きに言及する際は、地価上昇などの客観的な値上げの根拠を提示するだけではなく、借主の立場にも配慮しながら適切なタイミングで伝える必要があります。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
地代相場の計算方法
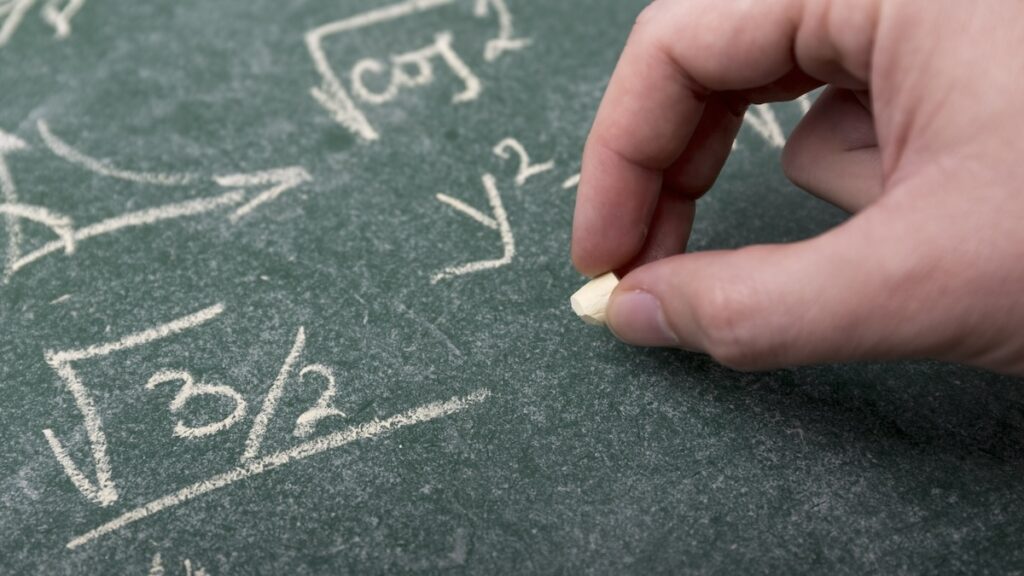
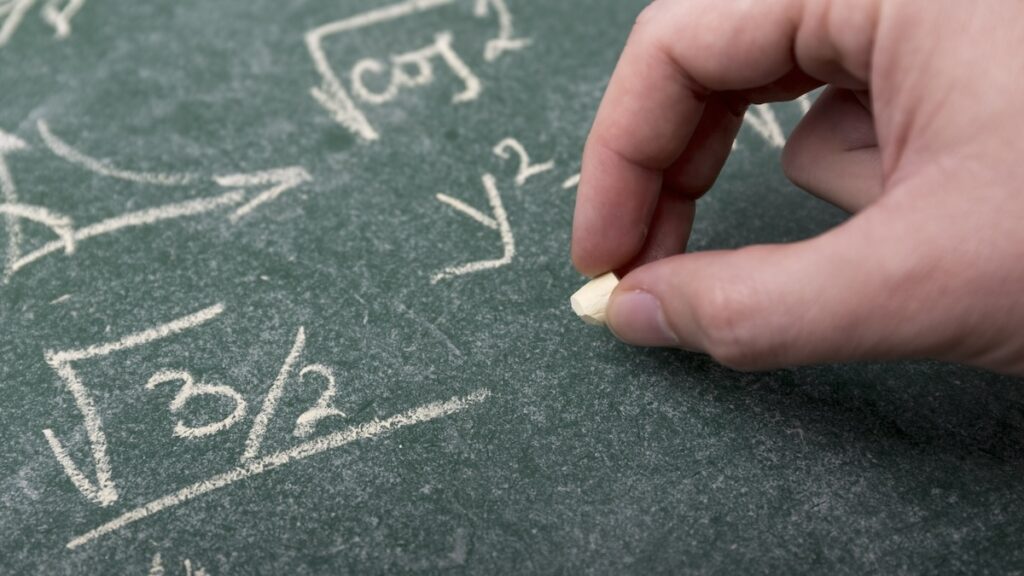
地代の値上げ交渉をスムーズに進めるためには、適正な地代相場の把握が重要です。
地代相場を算出する主な方法は、次の通りです。
固定資産税・都市計画税による計算
地代相場の算出には、固定資産税と都市計画税を基準とする方法があります。
固定資産税とは、土地や建物などの不動産に課される地方税で、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
都市計画税は都市計画区域内に所在する土地・家屋に対して課され、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税です。



固定資産税とあわせて市町村が課税し、通常は固定資産税と同時に徴収します。
固定資産税と都市計画税の額を基準として地代相場を算出するには、固定資産税と都市計画税を合算し、用途に応じた倍率をかけて地代を計算します。
倍率は、住宅地が3〜5倍、商業地が5〜8倍です。
(固定資産税+都市計画税)× 3〜5
(固定資産税+都市計画税)× 5〜8
たとえば、住宅地で年間の固定資産税と都市計画税の合計が30万円の場合、借地料の相場は90万〜150万円程度になるイメージです。
シンプルな計算で地代相場を把握できるため、交渉材料として有効な手法といえます。
相続税路線価による計算
地代相場の計算には、相続税路線価を基準とする方法があります。
相続税路線価とは、国税庁が毎年公表する、主要な道路に面した宅地の1㎡あたりの評価額で、相続税や贈与税の算定基準です。
ただし、相続税路線価は公示価格(標準地における正常な価格)の約8割を目安に設定されているため、地代相場を算出する際は相続税路線価を0.8で割って、公示価格に近づける調整を行います。
さらに、土地価格に、年1.5%〜3%程度をかけて、年間の借地料を算出します。
計算式は次の通りです。
借地料 =(相続税路線価 ÷ 0.8 × 1.5〜3%)× 土地面積
たとえば、相続税路線価が20万円/㎡、土地面積が300㎡の場合、借地料は概算で(20万円 ÷ 0.8 × 2%)× 300㎡=約150万円です。
相続税路線価は公的に定められているため、地代の値上げ交渉においても、借主に対して客観的かつ説得力のある根拠として活用できます。
積算法による計算
地代相場を算出する方法に、積算法があります。
積算法とは、土地の価格に利回りをかけた金額に、固定資産税や都市計画税などの必要経費を加算して借地料を求める方法です。
計算式は以下の通りです。
借地料 =(土地価格 × 利回り)+(固定資産税+都市計画税などの必要経費)
たとえば、土地価格が3,000万円、利回りを5%、年間の固定資産税と都市計画税の合計が30万円とすると年間の借地料は(3,000万円×5%)+ 30万円=190万円です。
積算法は土地価格や利回りという市場に即した指標をもとに算出するため、地代の値上げ交渉においても客観的な裏付けとして有効な手法です。



借主に対して、合理的な値上げ理由を説明したい場合に役立ちます。
近隣の類似物件の地代による計算
地代相場を算出する方法に、賃貸事例比較法があります。
賃貸事例比較法は、周辺地域にある同様の条件を持つ土地の借地料(地代)を比較して、適正な賃料水準を判断する方法です。
土地の立地、面積、形状、接道状況などが類似する土地の地代データを集め、それらを参考にして地代の増額幅を検討します。
賃貸事例比較法は、市場に流通している情報を重視するため、地域ごとの需給バランスや地価動向を反映しやすい特徴があります。
地代の値上げ交渉では、借主に対して「周辺でも同様の値上げ傾向がある」と客観的に説明できるため、拒否されにくい交渉材料となるでしょう。



底地権の価格の評価方法は、次の記事をお読みください。
関連記事:底地権とは?価格の評価や売買する3つの方法などを解説
地代の値上げ請求に関するQ&A
- 地代の増額請求の効力を過去にさかのぼらせることはできますか?
-
地代の増額請求の効力を過去にさかのぼらせることはできません。
地代の増額請求権は「形成権」と呼ばれ、地主が増額の意思表示を行い、通知が借主に到達した時点で法律上の効果が発生します。
このため、地代の増額請求の効力は、通知が到達した日以降の将来に向かってのみ効力を持ち、それ以前の期間には影響が及びません。
- 借地の地代について、法律上の制限や金額の上限はありますか?
-
地代に法律上の制限や金額の上限は設けられていません。
かつては「地代家賃統制令」により、地代・賃料に上限が定められた土地や建物がありました。
しかし、この規制は1986年12月31日をもって廃止されました。
そのため、現代において地代は、原則として当事者間の合意によって自由に決められます。
ただし、地代が社会通念に照らして著しく不合理な場合には、公序良俗に反するとして無効と判断される可能性があります。
地代の値上げ交渉で、借主から拒否されないためには、客観的な合理性を備えた金額の提示が重要です。
- 借地権にはどんな種類があり、それぞれどんな違いがありますか?
-
借地権には「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類があり、それぞれ更新の有無や、建物の扱いが異なります。
具体的に3つの違いは以下のとおりです。
旧借地権(旧法借地権):1992年7月31日以前の契約で、存続期間は建物の構造により契約期間が異なり、木造であれば20年、鉄筋コンクリートや鉄骨であれば30年です。



地主は正当事由がないと、契約更新を拒否できません。
普通借地権:1992年8月1日以降の契約に適用され、初回契約は30年以上、更新後は1回目20年以上、2回目以降は10年以上の契約期間を定めることとなります。
普通借地権も借主が保護され、地主が更新を拒否するには正当事由が必要です。
一方、定期借地権は更新がなく、契約期間満了で終了します。
定期借地権:種類により、一般定期借地権(50年以上)事業用定期借地権(10〜50年)建物譲渡特約付借地権(30年以上)に分かれます。
借主との値上げ交渉や調停・訴訟の手続きは弁護士に相談しよう


地代の値上げを借主に拒否された場合、対応や手続きを誤ると問題がこじれトラブルが長期化する恐れがあります。
地主と借主が直接交渉すると、感情的な対立が生じやすく、話し合いがまとまらないケースも珍しくありません。
もし、借主に地代の値上げを拒否され交渉の見通しが立たず、請求が調停や訴訟へ進む可能性があるなら、弁護士への依頼が賢明です。
不動産問題に精通した弁護士なら、客観的な視点で状況を分析し、冷静で効果的な交渉を行ってくれます。
調停や裁判に進んだ場合でも、的確なアドバイスを行い、依頼者にとってベストな解決策を提案します。
地代の値上げ交渉に不安を感じているなら、トラブルを最小限に抑えるためにも、できるだけ早く弁護士に相談してください。
関連記事:地代増額に強い弁護士の選び方とは?
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応