【無料相談受付中】24時間365日対応
共有物分割訴訟とは?判決のパターンや流れ、提起するリスクを解説
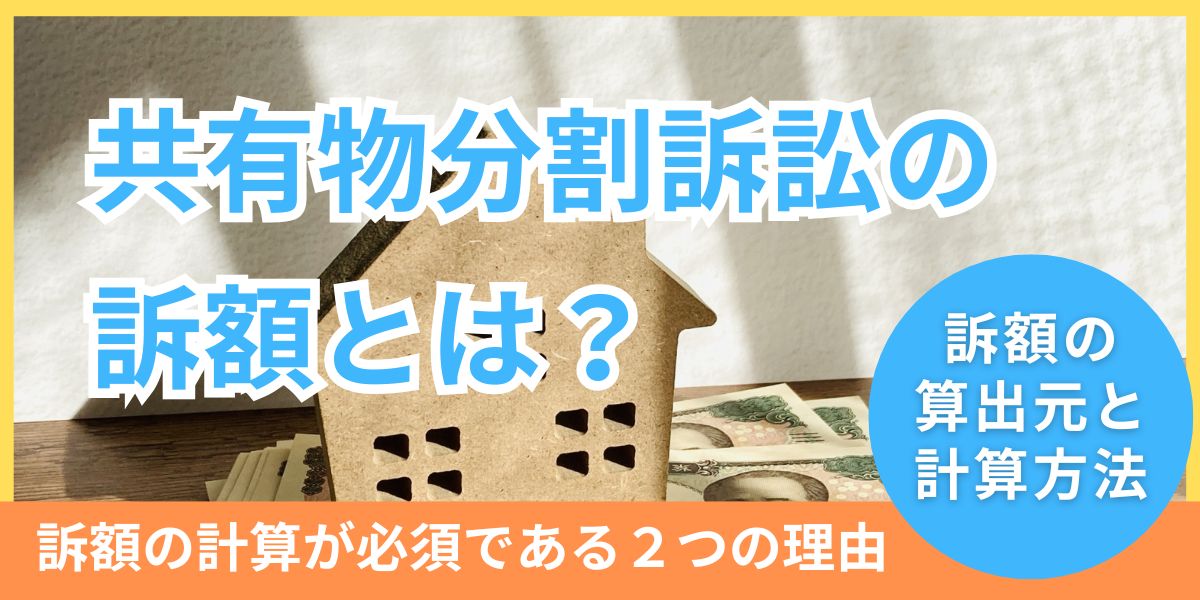
「不動産の共有状態を解消したいけれど、他の共有者と分配割合をめぐって揉めている」
「離婚後に共有名義の家を処分したいが、元配偶者と話し合いが進まない」
共有状態から抜け出そうとしても、共有者が納得してくれなかったり、分割方法に同意を得られなかったりする場合があります。共有者が多いほどトラブルに発展しやすく、それぞれの立場や利害が異なることから、話し合いだけでは解決が難しいケースも多いです。
本記事では、不動産の共有をめぐるトラブルに終止符を打つ手段である「共有物分割訴訟」の判決パターンや流れを詳しく解説します。
共有物分割訴訟とは:共有不動産について話し合いがまとまらない場合に、裁判所の判断で共有状態を強制的に解消する手続き。
主な判決パターン:不動産を分ける「現物分割」、一人が取得して金銭を払う「代償分割」、売却して分ける「換価分割」の3つ。
訴訟を検討すべき場面:共有者が協議に応じない、売却に反対されている、特定の共有者が不動産を占拠している場合など。
メリット・デメリット:公平な解決が期待できる一方、費用や時間がかかり、人間関係が悪化する可能性もある。
実務上の注意点:共有者全員を当事者にする必要があり、専門性が高いため早めに不動産に強い弁護士へ相談するのが望ましい。

共有物分割訴訟の仕組みや訴訟を提起するメリット・デメリットまで体系的に解説しているため、不動産の共有状態から抜け出したい方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
共有物分割訴訟とは?不動産の共有状態解消のために申し立てる訴訟
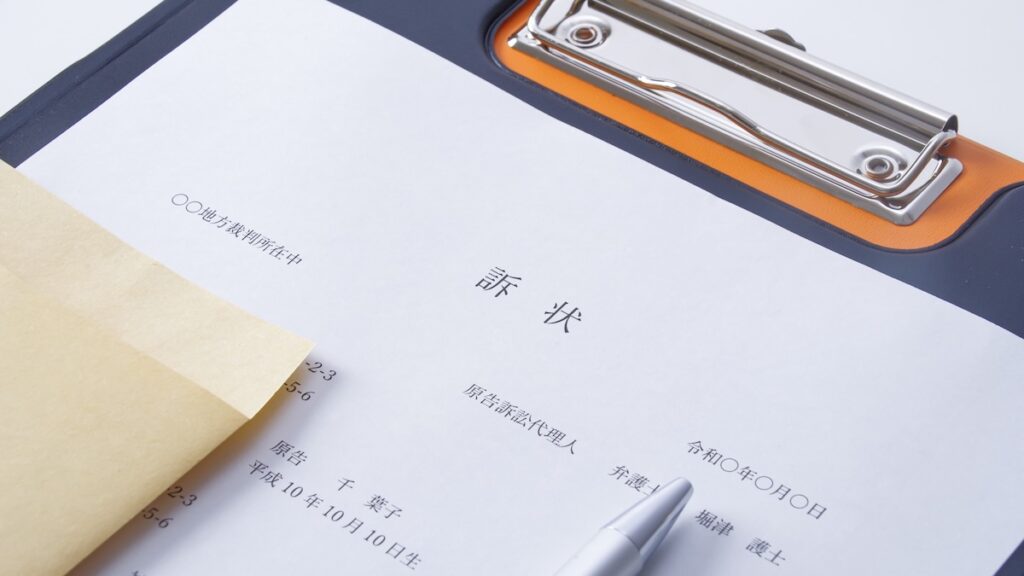
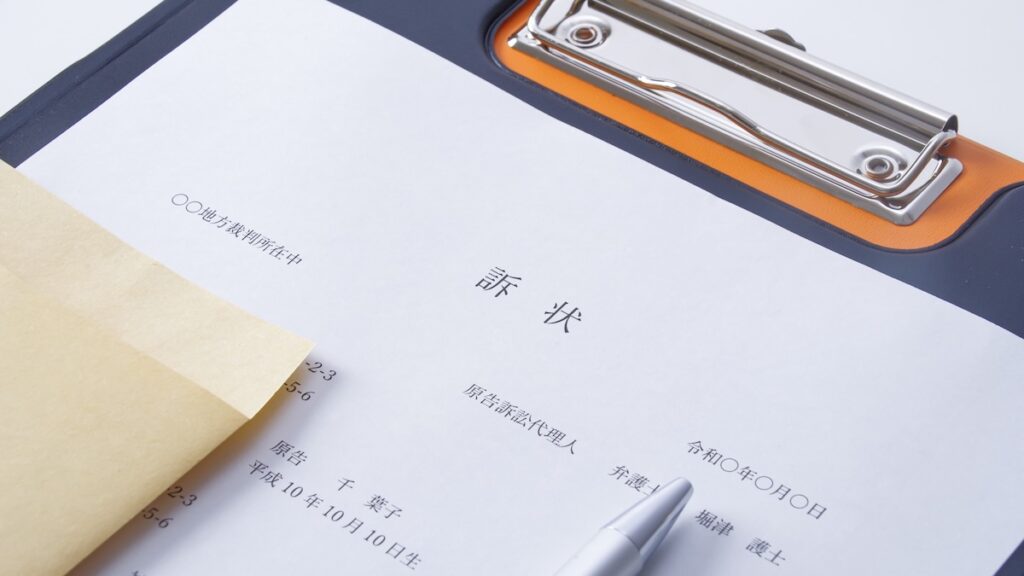
共有物分割訴訟とは、複数人で所有している不動産の共有状態を解消するために家庭裁判所へ申し立てる訴訟です。
相続や離婚により共有名義になった不動産は、利用や処分の自由が制限されます。共有者に無断で売却したり、活用したりするのは、民法251条に違反するとして認められていません。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用:民法|第251条1条
共有者から合意を得られれば売却・活用できますが、誰か一人でも反対している場合、深刻な問題を引き起こす可能性があります。
こうした状況において、裁判所が介入し「現物分割」「代償分割」「換価分割」といった方法で公平に解決を図るのが共有物分割訴訟です。
主に、相続によって発生した不動産の共有状態や、婚姻中に取得した不動産が離婚後も共有名義として残っている場合に活用されます。
本訴訟の本質は、話し合いでの解決が不可能な場合に、裁判所の判断によって強制的に共有を解消する点にあります。



協議では解決が難しい問題も、裁判所の判断を通じて法的に整理できるのが大きな特徴です。
共有物分割訴訟を検討すべき4つのケース
共有物分割訴訟を検討すべきなのは、主に以下のようなケースに該当するときです。
現在の状況に当てはめ、訴訟を提起すべきなのか検討しましょう。
共有物分割協議が難航しているとき
協議が長引いて合意できない場合は、共有物分割訴訟を検討しましょう。
不動産を共有している場合、まずは共有者同士で協議し、どのように分けるかを話し合うのが基本です。しかし、利害関係が複雑に絡み合うと協議は容易に進みません。
とくに共有者が多い場合、利用方法や処分の仕方を巡って対立し、結論が出ないまま時間だけが過ぎてしまうケースもあります。
共有物分割訴訟を活用すれば、裁判所が公平な基準に基づいて分割方法を決定します。協議では解決できない状況でも、法的に確定した判断を得られるため、問題が長期化するのを防ぐことが可能です。
協議が難航し、出口が見えないときは訴訟による解決を検討しましょう。
他の共有者が話し合いに応じないとき
他の共有者が共有状態を解消するための話し合いに応じないときも、訴訟を検討しましょう。
不動産の共有状態を解消するには共有者全員の合意が必要です。先述のとおり、共有物の変更・処分には、共有者全員の同意を得なければなりません。(民法251条)
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
引用:民法|第251条1条
したがって、一部の共有者が協議に参加しない、または明確に拒否する場合、売却や活用を進められません。放置すれば資産価値の低下や維持管理費用の負担が積み重なり、不利益が拡大する可能性があります。
共有物分割訴訟を申し立てれば、相手の意思に関わらず裁判所が手続きを進めるため、行き詰った状況を打開できます。
話し合いができない相手に協議を足止めされている場合、訴訟が実効性のある解決策となるでしょう。
共有不動産の売却を他の共有者から反対されているとき
共有不動産の売却を他の共有者から反対されている場合、訴訟で解決できる可能性があります。
不動産を売却して現金化したいと希望しても、他の共有者が反対すれば勝手に手続きを進められません。共有状態のままでは市場価値を十分に引き出せない場合もあり、資産を有効に活用できないまま時間だけが過ぎるリスクがあります。
共有物分割訴訟を提起すれば、裁判所が競売分割や代償分割を命じることで、共有関係を強制的に解消できます。現金での分配を望む共有者にとっては、有効な解決手段となるでしょう。
市場価格より低く売却されるリスクはあるものの、共有状態から抜け出し、資産を流動化できる点に大きな意義があります。
他の共有者が不動産を占拠しているとき
他の共有者が不動産を占拠しているときは、共有分割訴訟で法的に解決できる場合があります。
不動産の共有者には、各自が持分に応じて利用する権利があります。
しかし、特定の共有者が独占的に使用し、他の共有者が利用できない状況が続けば、不公平が生じて大きなトラブルになりかねません。このような状況で共有関係を放置すると、不利益を拡大してしまう恐れがあります。
共有物分割訴訟を通じて共有関係を整理すれば、公平な資産配分を実現できます。



不動産を利用する権利があるのにも関わらず、特定の共有者の占拠されている場合は、訴訟の提起を選択肢に入れてみましょう。
共有物分割訴訟の3つの判決パターン
共有物分割訴訟では、主に以下の3つの判決パターンで共有状態を解消します。
それぞれどのような分割方法なのかを確認し、何が現在の状況に最適なのか見極めましょう。
現物分割|不動産を物理的に区分して分ける方法
現物分割は、不動産をそのまま物理的に分けて共有者に割り当てる方法です。分割後は各共有者が単独所有者となり、自由に処分や利用ができます。
共有状態を直接的に解消できる手段といえますが、建物は構造上区切るのが困難です。そのため、住宅やマンションなどの建物の共有状態の解消では、そもそも採用できません。
主に土地の分割に採用されますが、形状や立地条件によっては均等な分割が難しく、公平性を保てない場合があります。現物分割が可能な条件を満たしているなら有効ですが、現実的には限られた場面でしか用いられない方法です。
代償分割|特定の共有者が不動産を取得し、他の共有者に代償金を支払う方法
代償分割は、共有不動産を特定の共有者が単独で取得し、その代わりに他の共有者へ持分に応じた金銭(代償金)を支払う方法です。現物を分けられない場合でも、公平に価値を分配できる点が大きな特徴です。
典型的なのは、相続で実家を共有した際に一人が住み続けたいと希望するケースです。この場合、その人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を渡すことで共有関係を解消します。
現物をそのまま活用できる利点がある一方で、代償金を準備する資金力が必要となり、実現できるかどうかは共有者の経済状況に左右されます。
条件が整えば合理的な手段ですが、資金調達のハードルが高い点を理解しておく必要があります。
関連記事:代償分割について解説
換価分割|不動産の売却利益を持分割合に応じて分ける方法
換価分割は、不動産を売却して得た代金を共有者の持分割合に応じて分配する方法です。物理的に分けられない不動産や、代償金を準備できる共有者がいない場合に採用される手段です。
たとえば、兄弟姉妹で相続した土地に古い家屋が建っており、誰も住む予定がない場合、換価分割が選ばれるケースが多いです。売却によって現金に換えれば、共有者それぞれが持分割合に応じた金額を受け取ることができ、共有関係を確実に解消できます。
一方で、競売にかけられると市場価格より低く売却されるリスクがあり、資産価値を十分に反映できない可能性があります。



とにかく現金化して公平に分けたいときには、有効で実効性の高い方法です。
共有物分割訴訟を提起するメリット3つ
共有物分割訴訟を提起するメリットは、以下の3つです。
最適な判断ができるよう、以下でどのような利点があるのか確認しましょう。
裁判所の関与により共有状態を法的に解決できる
裁判所が関与することで、共有状態を法的に強制的に解消できます。
共有不動産の分割は共有者全員の同意が原則ですが、合意に至らないままでは前に進めません。
共有物分割訴訟を申し立てれば、裁判所が「現物分割」「代償分割」「換価分割」といった手段を選び、法的効力を持つ解決策を示します。協議や調停が不成立でも、最終的に裁判所が判決を下すため、共有関係を確実に整理できる点が大きな利点です。
話し合いで解決できない場合でも、裁判所の判断で共有関係を終わらせられます。
公平な共有物分割が期待できる
裁判所の判断により、公平性を重視した分割が実現します。
共有者同士で話し合うと、立場の違いや力関係によって、一方が不利な条件を受け入れざるを得ない場合もあります。公平性が欠けた分割方法になれば、さらに大きなトラブルに発展するリスクも考えられるでしょう。
しかし、裁判所は不動産の性質や各共有者の利益を考慮して、客観的に分割方法を決定します。そのため、持分割合に基づいた公正な配分が期待でき、将来的なトラブルを防ぎやすくなります。
偏った合意に縛られず、正当な権利を守れる点が大きなメリットです。
協議がまとまらない状況を打開できる
協議が長期化し、出口が見えない場合でも訴訟に進めば解決の道が開く可能性があります。
共有不動産をめぐる協議が長期化すると、固定資産税や修繕費などの維持費が積み重なり、経済的な負担が増していきます。管理が行き届かなくなれば建物や土地の劣化が進み、資産価値が下がるリスクも考えられるでしょう。
また、話し合いが続くことで共有者間の関係が悪化し、親族や元配偶者との対立が深刻化するリスクも否めません。
訴訟を起こせば裁判所が分割方法を決定するため、合意できない状況を打破できます。



協議が難航し、時間ばかり浪費していると感じるなら、訴訟で法的に解決する方向に持っていく方が良い場合があります。
共有物分割訴訟を提起するデメリット3つ
共有分割訴訟は、法的に共有状態を解消できる手段です。
しかし、その一方で以下のデメリットが生じる可能性があります。
訴訟を起こす際は、メリットだけでなくデメリットにも目を向ける必要があります。リスクを負ってまで本当に実行すべきなのか、慎重に判断しましょう。
望んでいた判決が下されない場合がある
共有物分割訴訟では、必ずしも自分が望む判決が得られるとは限りません。
裁判所は公平性を重視するため、共有者全員の利益を考慮した上で分割方法を決定します。自分は不動産を単独で取得したいと希望していても、資金力が不足している場合は代償分割が認められず、競売による換価分割となる場合があるのです。
また、土地をそのまま分けたいと考えていても、形状や立地条件によっては現物分割が難しいと判断されるケースもあります。
希望に沿わない結論になる可能性を理解した上で、訴訟を選択する必要があります。
訴訟費用や弁護士費用がかかる
共有物分割訴訟を提起する際は、訴訟費用や弁護士費用を念頭に置いた上で手続きを進めましょう。
家庭裁判所への申し立てには収入印紙代や郵便切手代が必要で、さらに専門家に依頼する場合は弁護士費用も発生します。弁護士費用には着手金や報酬金が含まれるケースが多く、解決までの長期化に応じて費用が増える場合もあります。
また、不動産を公平に分配するための評価額を査定する場合、不動産鑑定士費用を支払わなければなりません。費用負担はケースごとに異なるものの、解決までには経済的コストがかかると理解する必要があります。
訴訟をきっかけに他の共有者との関係が悪化する可能性がある
訴訟を起こすことで、共有者同士の関係が悪化するリスクがあります。法廷で争う形になるため、感情的な対立が深まりやすく、相続や親族間の共有不動産では人間関係の修復が難しくなるケースもあります。
たとえば、親族間で訴訟を行った結果、判決後もわだかまりが残り、その後の交流が途絶えてしまう例は少なくありません。法律的には問題が解決しても、感情的な溝が残れば新たなトラブルに発展する可能性があります。



訴訟を通じた解消のメリットを期待する一方で、人間関係への影響も十分に考慮しましょう。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
共有物分割訴訟の提起から判決までの流れ【5ステップ】
共有分割訴訟の提訴から判決までの流れは、大きく分けて以下の5ステップで進んでいきます。
具体的な流れをつかみ、計画的に訴訟の準備を進めましょう。
共有物分割協議がまとまらない場合は、まず弁護士に相談することが解決への第一歩です。専門家の視点から、今後どのように対応していくのか、どのような分割方法で進めるのかなど、具体的なアドバイスを受けられます。
さらに、弁護士に依頼すれば訴訟提起の準備や必要書類の収集、主張や証拠の整理まで一貫してサポートしてもらえるため、複雑な手続きを効率的に進められます。
弁護士を選ぶ際は、相続や不動産問題の解決実績が豊富かどうかを確認しましょう。共有不動産や分割訴訟の問題に強い弁護士であれば、訴訟戦略や交渉を有利な立場で進められる可能性が高まります。
弁護士と方針を固めたら、地方裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てます。
申し立て先は、相手方共有者の住所地を管轄する地方裁判所です。受理されると、正式に裁判所が関与する段階に入ります。
申し立てには、複数の書類や費用が伴います。
以下は、共有物分割訴訟に必要な書類と費用をまとめたものです。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 訴状原本 | 訴訟を開始するための基本書類弁護士が作成・対応 |
| 訴状副本 | |
| 共有不動産の固定資産評価証明書 | 不動産の評価額を証明する書類訴額算定に使用する共有不動産がある所在地の市町村役場で取得できる |
| 共有不動産の全部事項証明書 | 不動産の所有者・共有関係を証明する資料法務局で取得できる |
| 戸籍謄本(※裁判の原告・被告の一方又は双方が未成年者である場合) | 本籍地の市町村役場で取得できる |
| 裁判手数料(収入印紙代) | 訴額(訴訟で請求する対象物の金銭的な価値)によって変動する法務局・コンビニ・郵便局などで購入できる |
| 郵便切手代 | 申し立てる家庭裁判所によって異なる法務局・コンビニ・郵便局などで購入できる |
訴状原本と副本は弁護士が作成し、共有不動産の固定資産評価証明書は共有不動産がある所在地の市町村役場で取得します。
共有不動産の全部事項証明書は、法務局で取得可能です。(参照:法務局|各種証明書請求手続)
また、裁判手数料として収入印紙代、郵便切手代が必要で、金額は訴額や裁判所によって異なります。訴額については、記事の後半で解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
家庭裁判所に必要書類を提出し、申し立てが受理されれば、共有物分割訴訟が本格的にスタートします。
訴訟の申し立てが受理されると、裁判所から他の共有者に訴状と呼出状が送付されます。これにより、相手方は訴訟に正式に関与する立場となり、争いは法定の場に移ります。
呼出状とは、裁判所が当事者に対して「いつ・どこで審理が行われるのか」を通知する文書です。通常は申し立てから1カ月程度で送付され、記載された期日に出頭しなければなりません。
当日に出頭できない場合は、期日の1週間前までに答弁書を提出し、自らの主張を文書で伝える必要があります。
裁判が始まると、当事者双方が自らの主張を展開し、不動産の価値や利用状況を裏付ける証拠を提出します。裁判官は、提出された書類や証拠を基に事実関係を整理し、どの分割方法が妥当かを判断していきます。
審理は一度では終わらず、複数回にわたって期日が設けられるのが通常です。1回目の口頭弁論期日が終了したら、その後は1カ月に1回のペースで再度口頭弁論期日が設けられます。
弁護士や依頼人は次回に備えて弁論準備を進め、主張の補強や追加証拠の収集を行います。
共有分割訴訟の期間は、以下の記事でも解説しています。後ほど詳しく紹介しますが、気になる方はこちらも併せて参考にしてください。
双方の主張・証拠提出・審判が一定期間繰り返された後は、裁判所が判決を下します。これにより、共有関係は強制的に解消され、当事者は判決に従って不動産の処理を進めることになります。
なお、判決前に裁判所から和解を勧められるケースもあります。
和解が成立すれば、判決より柔軟な条件で解決できる可能性があり、相手方との対立を和らげる効果も期待できるためです。もっとも、和解に至らなかった場合は判決により最終的な解決が図られます。
ただし、判決内容が必ずしも当事者の希望どおりになるとは限りません。資産の売却や代償金の支払いなど、自分にとって不利な方法が選ばれる場合があります。



判決後も不服があれば控訴できるため、手続きがさらに長期化する可能性もあります。
共有物分割請求訴訟の手続きの流れをさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
共有物分割訴訟の目安期間
共有物分割訴訟は、一般的に6か月から1年程度で進むのが目安です。比較的単純な事案であれば、この範囲で判決に至るケースも少なくありません。
しかし、共有不意動を分割するケースでは、不動産鑑定や売却方法の検討が必要となるため、調査や証拠収集の段階で時間を要します。共有者が多数に及ぶ場合は、訴訟の期間がさらに長期化する可能性があります。
また、共有者間の意見が対立していると、裁判所の判断を仰ぐ場面が増え、結果的に1年半以上かかる可能性があります。
裁判期間を少しでも短縮するためには、事前準備が欠かせません。財産の全体像を把握し、必要な資料をそろえた上で訴訟に臨めば、手続きを円滑に進めやすくなります。



効率的に進める工夫をするかどうかで、訴訟にかかる負担と手間は大きく変わるでしょう。
共有物分割訴訟の期間は、以下の記事でも解説しています。併せて参考にしてみてください。
関連記事:共有物分割訴訟の期間はどれくらいかかるのか?事前協議や調停・競売期間も解説
共有物分割訴訟にかかる費用【4項目】
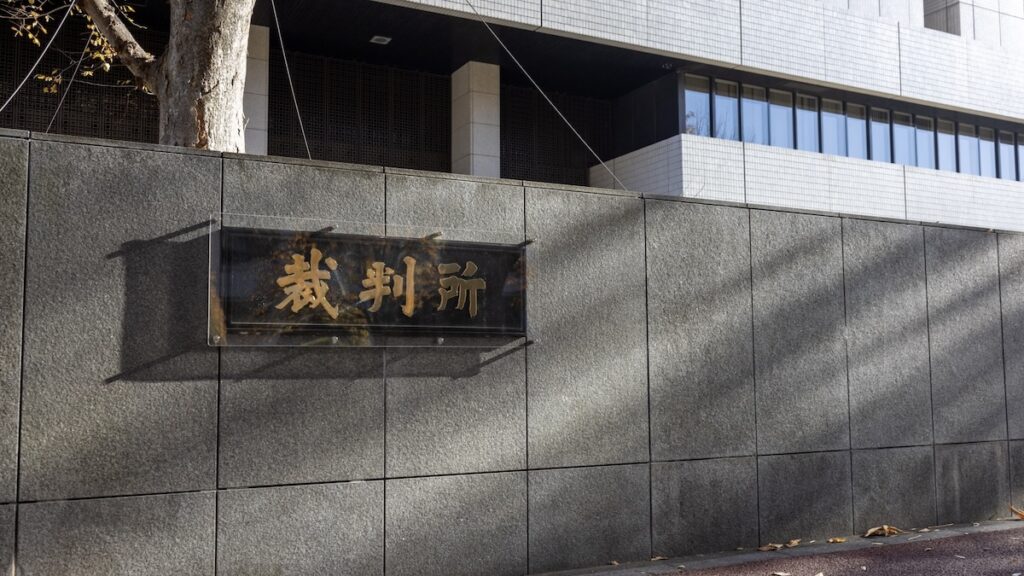
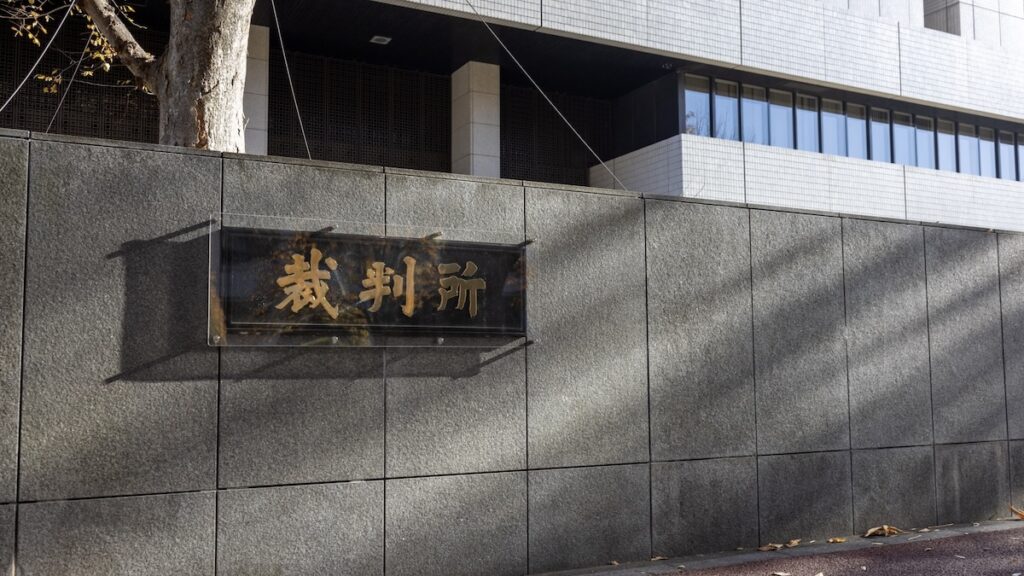
共有分割訴訟を提起する際は、訴訟費用や専門家へ支払う費用も考慮しなければなりません。
主な費用項目は、以下のとおりです。
費用相場を確認し、今後のお金の見通しを立てましょう。
裁判手数料(収入印紙代)|訴額によって変動する
共有物分割請求訴訟を提起するには、訴額に応じた裁判手数料の納付が必要です。訴額とは、訴訟で請求する対象物の金銭的な価値のことです。
民事訴訟では、裁判官や事務官の人件費、書類送達にかかる郵便料などの費用は公費で賄われます。しかし、応益負担の原則により、当事者にも一定の負担が求められるのです。
手数料は訴額ごとに段階的に区分され、以下の基準で計算します。
| 訴額 | 裁判手数料 |
|---|---|
| 100万円以下の部分 | 10万円までごとに1,000円 |
| 100万円超500万円以下の部分 | 20万円までごとに1,000円 |
| 500万円超1000万円以下の部分 | 50万円までごとに2,000円 |
| 1000万円超10億円以下の部分 | 100万円までごとに3,000円 |
| 10億円超50億円以下の部分 | 500万円までごとに1万円 |
| 50億円超の部分 | 1000万円までごとに1万円 |
なお、判決に不服があり控訴する際の手数料は上記の1.5倍、上告する場合は2倍です。控訴・上告にも訴額に応じた裁判手数料が発生します。



訴額が高いほど裁判手数料も増えるため、正確な計算は訴訟費用を見積もる上での重要なプロセスです。
訴額は固定資産税評価額をもとに算出する
有物分割請求訴訟における訴額は、固定資産税評価額を基準に算出します。
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額です。
土地・家屋の固定資産税評価額については3年に1度「評価替え」が実施されており、この評価替えの年度を「基準年度」といいます。固定資産税評価額は、基準年度の評価額が次年度と次々年度にそのまま引き継がれるのが原則です。
固定資産税評価額を確認するには、不動産の所在地を管轄する市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得する方法と、毎年送付される固定資産税の納税通知書を確認する方法があります。
訴額の計算方法は、共有不動産が土地なのか、建物なのかによって異なります。
それぞれの計算方法は、以下のとおりです。
| 共有不動産の種別 | 計算方法 |
|---|---|
| 土地 | 固定資産税評価額×持分割合×1/6 |
| 建物 | 固定資産税評価額×持分割合×1/3 |
建物の分割に関する訴訟では、通常の金銭請求とは異なり、訴訟の目的が占有権の分割にあたるため、評価額の3分の1という基準が適用されます。
たとえば、建物の固定資産税評価額が3,000万円で、持分が1/2の場合の訴額の計算式は、以下のとおりです。
500万円(訴額)=3,000万円(固定資産税評価額)×1/2(持分割合)×1/3
土地を目的とする訴訟では、1994年4月1日以降手数料が高騰するのを防ぐため、当分の間、評価額の1/2を基準に訴額を定める措置が導入されました。
たとえば、固定資産税評価額が9,000万円で持分が1/2の場合の訴額の計算式は、以下の通りです。
750万円(訴額)=9,000万円(固定資産税評価額) × 1/2(持分割合)× 1/3× 1/2
土地の訴額は、建物と異なる算定ルールが適用されます。
書類郵送に必要な郵便切手代|裁判所ごとに異なる
訴訟に必要な書類を裁判所から共有者全員に送付するための郵便切手代もかかります。
裁判所に納付する郵便切手は予納郵券と呼ばれ、裁判所が指定する種類の切手をあらかじめ納付しなければいけません。
東京地方裁判所を例に挙げると民事訴訟の予納郵券の内訳は、次のとおりです。
| 切手の種類 | 枚数 |
|---|---|
| 500円 | 8枚 |
| 110円 | 10枚 |
| 100円 | 5枚 |
| 50円 | 5枚 |
| 20円 | 5枚 |
| 10円 | 5枚 |
※共有者が1人増えるごとに2,440円(内訳500円4枚、110円4枚)加えて予納する
郵便切手代は裁判所ごとに異なる場合があり、共有者が一人なら5,000円から6,000円程度必要で、被告が1人増えるごとに2,000〜2,500円程度増加します。
また、裁判が長引いて送達の回数が増えると、追加予納が命じられる可能性があります。
不動産鑑定費用|20万円~30万円程度
共有物分割請求訴訟では、20万円~30万円程度の不動産鑑定費用が発生する場合があります。
訴訟や調停の場面では、現物分割や代償分割が選択されるにあたり不動産の適正な評価額を明確にするため、鑑定士に依頼して鑑定書を訴訟資料とするケースがあるためです。
不動産鑑定には私的鑑定と裁判所選任鑑定があり、いずれも不動産の規模や種類、評価額に応じて費用が変動します。
不動産鑑定費用は、審理の経過や裁判所の判断によって発生する可能性があるため、共有物分割請求訴訟を提起する際は、事前に概算を把握しておきましょう。
弁護士費用|案件によって変動する
共有物分割請求訴訟の弁護士費用は、手続きの段階に応じて発生します。
弁護士費用は、訴訟全体の経済的負担において大きな割合を占めるため、安心して訴訟を進めるために各費用の相場を把握しておく必要があります。
弁護士費用の内訳は、以下の通りです。
| 費用項目 | 相場・内容 |
|---|---|
| 法律相談料 | 無料~30分5,000円程度(初回無料の事務所もあり) |
| 着手金 | 22万円〜33万円程度 または日弁連旧基準にもとづいて計算 |
| 成功報酬 | 対象となる持分の5.5%~11%程度 または日弁連旧基準にもとづいて計算 |
| 実費 | 1万円〜3万円ほど ※終了後に精算 |
| 日当 | 1日あたり3万円~5万円程度 |
弁護士費用は、案件の進行状況や内容によって変わるため、正式に依頼する前に見積もりを取り、費用の全体像を把握しておくことが大切です。



相続問題の解決実績や担当者との相性なども確認し、パートナーとして長期的に連携できそうな弁護士事務所を選びましょう。
共有物分割請求の弁護士費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:共有物分割請求にかかる弁護士費用は?相場や具体例、安く抑える方法を解説
共有物分割請求訴訟を提起する際の注意点
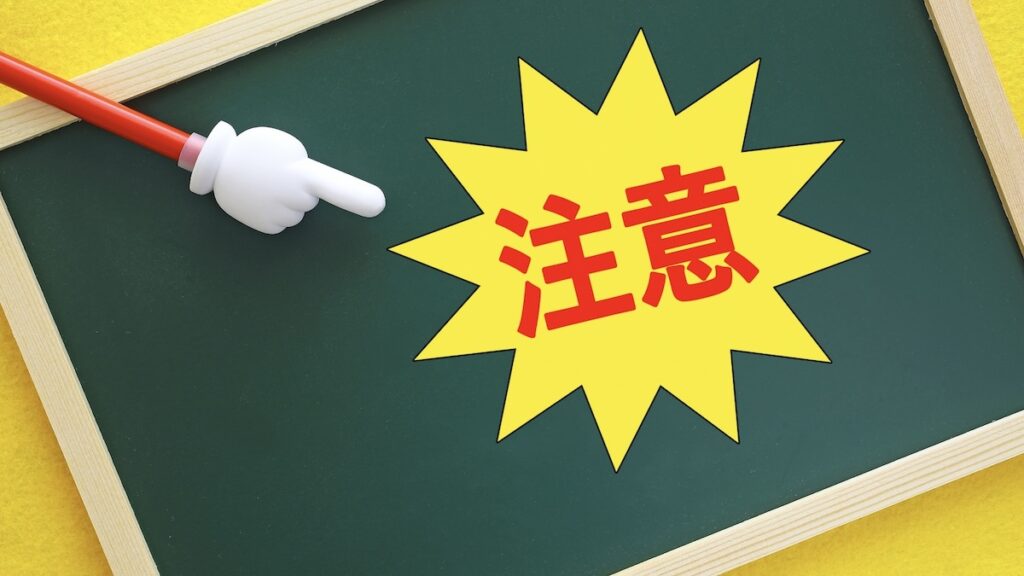
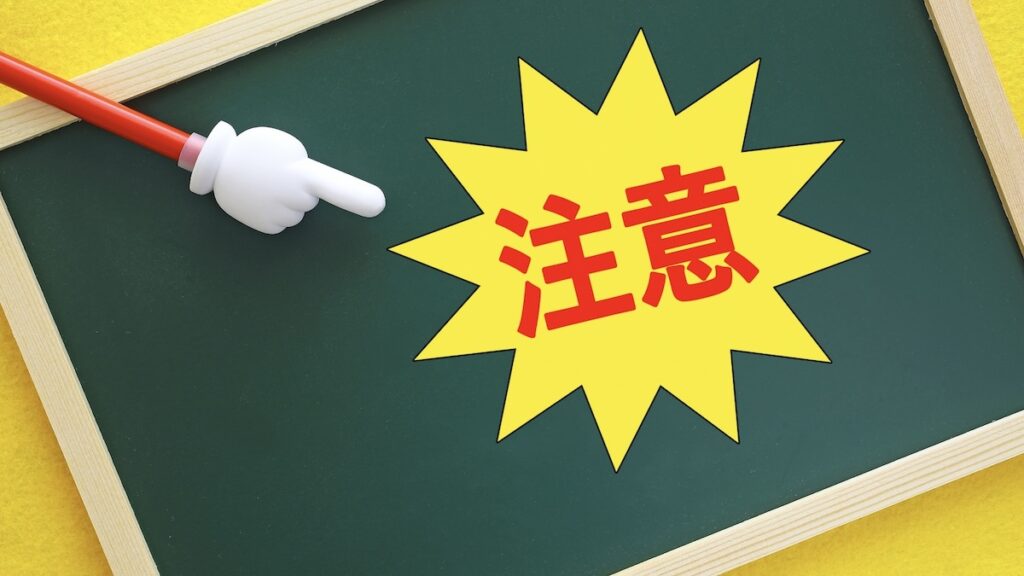
共有物分割請求訴訟には、事前に押さえておくべき注意点があります。
訴訟手続を進める際に理解が必要な主なルールは、以下の通りです。
共有者全員が当事者になる必要がある(固有必要的共同訴訟)
共有物分割請求訴訟を提起する際は、共有者全員を当事者に加える必要があります。
共有物の処分に関する権利義務は共有者全員に生じており、対立の有無にかかわらず、共有関係全体に影響が及ぶためです。
仮に一部の共有者だけで訴訟を提起しても、その訴えは不適法となり、裁判所に却下されます。
たとえば、3人で土地を共有している場合、特定の2人だけで共有物分割請求訴訟を起こすことはできず、残りの1人も必ず当事者として加える必要があります。
このように、共有物分割請求訴訟では「固有必要的共同訴訟」というルールにもとづいて手続きを進めなければなりません。
原則弁護士は当事者双方の代理人になれない(利益相反)
共有物分割請求訴訟では、弁護士が当事者双方の代理人を兼ねることは原則できません。
弁護士が当事者双方の代理人になると、利益相反のおそれがあり、公平性が損なわれる可能性があるからです。
民法第108条では、同一の法律行為について相手方の代理人や当事者双方の代理人となることを禁止しています。
ただし、例外として、債務の履行や当事者双方が同意した場合には、弁護士の双方代理が認められるケースもあります。
共有物分割請求訴訟では当事者が複数いるケースがあるため、利益相反に関するルールを理解して弁護士を選任しましょう。
共有物分割請求訴訟は地方裁判所に提起する(事物管轄)
共有物分割請求訴訟は、地方裁判所に提起する必要があります。
「事物管轄」と呼ばれるルールにもとづき、訴訟の種類ごとに担当する裁判所が決まっています。
不動産を目的とする共有物分割訴訟は、事件の性質上、地方裁判所が管轄です。
裁判所には家庭裁判所、簡易裁判所、高等裁判所、最高裁判所などがありますが、共有物分割請求は簡易裁判所の利用はできず、一審は地方裁判所に提起します。
共有物分割訴訟は弁護士のサポートなしでは進めにくい


共有物分割訴訟は、弁護士のサポートなしで進めるのが困難な手続きです。
訴訟を成立させるには、民法や不動産登記に関する専門知識に加え、訴状作成や証拠の収集など高度な対応が求められます。個人で取り組もうとすると、法的要件を満たせず不利な結果につながるリスクが高まります。
弁護士に依頼すれば、最適な分割方法の提案から裁判所とのやり取りまで一貫して任せられます。どの分割方法が適しているかを客観的に判断してもらえるため、戦略を誤る心配がありません。
さらに、書類準備や裁判期日への対応といった煩雑な作業を任せられるため、時間的・労力的な負担を軽減できます。



精神的な負担を抑えながら適切な解決を目指すためにも、弁護士の専門的サポートを受けましょう。
共有物分割訴訟に関するよくある質問
共有物分割請求は権利濫用になりますか?
共有物分割請求は民法で認められた正当な権利であり、原則として誰でも行使できます。
しかし、権利行使が常に適法とされるわけではなく、濫用と判断される場合もあります。
たとえば、他の共有者に過度な損害を与えることを目的として訴訟を提起した場合や、嫌がらせのために繰り返し請求を行うような場合です。
裁判所は「請求の目的」「共有者間の状況」を踏まえて適法かどうかを判断するため、安易に訴訟を利用すると不利になる可能性があります。
したがって、請求を行う際は、実際に共有状態を解消する合理的な理由があるかどうかを冷静に確認することが重要です。
共有物分割訴訟で相手が欠席したら裁判はどうなりますか?
共有物分割訴訟では、相手方が裁判に欠席しても手続きは停止しません。
欠席した共有者が答弁書や証拠を提出しなければ、裁判所は出席した側の主張や提出資料を基に判断を下します。
民事訴訟法では「欠席判決」が可能とされており、期日に出頭しない当事者は自らの主張を述べる機会を失うことになります。
ただし、欠席しても判決が自動的に請求者の言い分どおりになるわけではありません。
裁判所は、提出された証拠の妥当性を確認した上で適切な分割方法を決定します。
共有物分割訴訟に関する判例はありますか?
共有物分割訴訟に関する重要な判例として、平成25年11月29日の最高裁判決(平成22年(受)第2355号)が挙げられます。
この判例では、相続によって発生した「遺産共有」と通常の共有が混在する不動産についても、裁判所が代償分割を命じられると判断されました。(参照:裁判所|平成22年(受)第2355号 共有物分割等請求事件)
さらに、支払われる代償金は各相続人が直ちに確定取得するものではなく「遺産」として扱われ、遺産分割が完了するまで共同で保管すべきと示されました。
具体的には、相続人の一部が不動産を単独で取得し、他の相続人へ代償金を支払う形が認められたのです。
この判断により、相続財産が関係する場合でも、共有物分割訴訟を通じて実質的に公平な解決を図れることが明確になったといえます。
まとめ|共有物分割訴訟は弁護士の力を借りて解決を目指そう
共有物分割訴訟は、共有不動産をめぐる対立を最終的に解消できる強力な手段です。
裁判所が関与することで公平な分割が実現し、協議や調停では解決できなかった問題にも出口が見えるようになります。
ただし、手続きには専門的な法律知識や膨大な書類準備が必要で、時間的・経済的な負担も大きくなります。
効率的かつ適切に進めるためには、弁護士のサポートが欠かせません。弁護士に依頼すれば、最適な分割方法の検討から裁判所とのやり取り、主張や証拠の整理まで一貫して任せられます。



精神的な負担を軽減しつつ、有利な解決につなげるためにも、共有不動産に関する問題に強い弁護士事務所に依頼しましょう。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応









